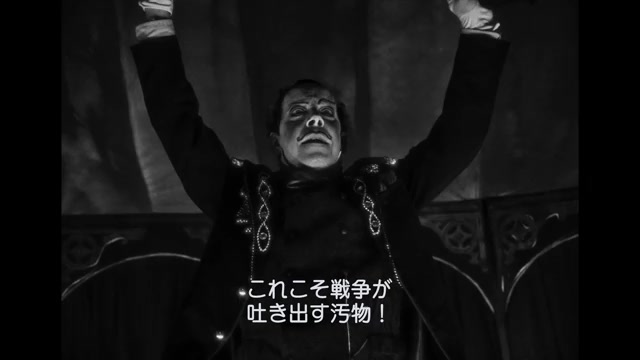ガール・ウィズ・ニードルのレビュー・感想・評価
全109件中、61~80件目を表示
美しいモノクロ映像の美
個人的な趣味から言えば物語や脚本は苦手な部類な筈でしたが、それを超えたいい映画でした。
監督・脚本のマグヌス・フォン・ホーンはかなりのシネフィルであり、写真好きと見えて、ドイツ表現主義的なモノクロ映像と、ダゲレオタイプに通じるフィックスショットの美しさで、暗く陰惨な物語を飽きさせることなく牽引していた。
特に、凶行を行うダウマ(トリーネ・デュアホルム)営む、砂糖菓子店(実は秘密の養子縁組所)の毎回同じアングルからのショットの古典的な美しさと、主人公カロリーネ(ヴィク・カーメン・ソネ)が働いていた工場から、仕事を終えた人々が大勢出てくるシーンの、まさにリュミエール「工場の出口」のアプロプリエーション足る撮影手法などは本映画全体に渡る写真・映画的様式美の象徴的な表れと言えよう。
里親斡旋に見えて、実は乳児連続殺人犯だったダウマ。しかしその犯罪は、当時の時代性と社会の暗部をあぶり出すようで、誰しもが必ずしも糾弾できない二面性を持つ。終始一貫してカロリーネの視点で描かれる物語は、その他者視点とモノクロの映像美に支えられて、現代にも通ずる社会的弱者へのいたわりの心すら感じさせる。
ホラー映画ジャンルらしい本作だが、印象としてはアンゲロプロス的な叙事的な物語と思えた。見世物小屋のシーンや、冒頭とラストにある、二重露光のようなある種PV的な衝撃的なシーンには、初期デビッド・リンチ作品が思い出された。
監督はインタビューで、ホラージャンルへの関心として、黒沢清や三池崇史の名前を挙げていたが、溝口健二等の邦画からもインスパイアされてるのかもしれない。
最近なかなか観ることのない、美しく構築性の高い映画でした✨
主人公カロリーネは折れやすい針から折れにくい針になった? ラストで見せた人生初の能動的な選択
第一次世界大戦直後のデンマークを舞台にしたモノクロ作品。モノクロームか、まあたまたまだけど、今年はよく見てるような気がするなと感じたので、私が2025年に映画館で鑑賞したモノクロ作品を挙げてみます。
『敵』1月に鑑賞 吉田大八監督
『TATAMI』3月に鑑賞 ガイ•ナッティブとザーラ•アミール•エブラヒミの共同監督
そして、今回の
『ガール•ウィズ•ニードル』5月に鑑賞 マグヌス•フォン•ホーン監督
と半年間で3本、2ヶ月に1本のペースで観ておりました。あくまでも私ひとりの個人比になりますが、2024年に映画館で観たモノクロが『WALK UP』(ホン•サンス監督)、2023年が『せかいのおきく』(阪本順治監督)の1本ずつだったことを考えると明らかに多いです。まあだからどうしたといったレベルのお話なんですが、私個人の印象ではこれらの作品群(それぞれモノクロにした意図も感じられますし、なかなかの名作揃いといった感じ)の中でも特にモノクロにした必然性、モノクロにした効果、ともにいちばん強く、大きく感じられるのがこの作品『ガール•ウィズ•ニードル』です。撮影における技術的な面が素晴らしいことはもちろんのこと、モノクロームにしたことによってこの作品の物語性、寓話性がかなり高められたと思います。
本作の監督、マグヌス•フォン•ホーンはスウェーデン生まれだそうですが、本作がデンマークで実際にあった事件を基にしてデンマーク語で語られた物語であること、名前に”フォン”が入っていることから、あのデンマーク生まれの鬼才ラース•フォン•トリアー監督が想起されます。実際にフォン•トリアー監督から少なからず影響を受けているそうです。そう言えば、本作のヒロイン カロリーネは過酷な運命に翻弄され続ける点においてフォン•トリアー監督の代表作である『ダンサー•イン•ザ•ダーク』のヒロイン セルマによく似ています。以下、両作品のネタバレを防ぐために少し曖昧な書き方をします。どちらかというと鑑賞者に同情されやすいタイプのセルマのほうがずっと受け身で過酷な運命の波に飲み込まれていったの対し、鑑賞者に同情されにくいタイプのカロリーネはずっと受動的で仕方ないからそうするみたいな行動を繰り返していたのですが、ラストで人生初と言ってもいいほどの能動的な選択をして前を向きます。ただし、それがその後の彼女の幸福に繋がるかどうかは定かではありません。このあたりのところから、単純にハッピー•エンド、バッド•エンドの二分法では割り切れない映画的な興趣が煙のように立ち昇り、それがたなびいて余韻を残す、そんな感じがしました。
いずれにせよ、マグヌス•フォン•ホーン監督はこの作品の完成度からいって近い将来、カンヌのパルムドールを獲るような作品を生み出すかも知れないと思いましたのでチェックを入れておきました。
ニードルの意味
史実を知って観ると退屈に思えるが、何も知らずに観ると仰天してしまうと思う
2025.5.22 字幕 MOVIX京都
2024年のデンマーク&ポーランド&スウェーデン合作の映画(123分、PG12)
実際に起きた事件をベースに紡がれるクライムミステリー
監督はマグヌス・フォン・ホーン
脚本はマグヌス・フォン・ホーン&リーネ・ランゲベク
原題は『Pigen med nalen』、英題は『The Girl with the Needle』で、「針を持った女」という意味
物語の舞台は、1920代のデンマーク・コペンハーゲン
縫製工場で働いている裁縫師のカロリーネ(ビク・カルメン・ソネ)は、戦争から帰らぬ夫を待ちながらも、行方しれずのために寡婦年金を受け取ることもできなかった
工場の社長ヤアアン(ヨアキム・フィェルストルプ)の伝手を頼るものの、その状況は変わらなかった
カロリーネは夫が死んだものと思い込むようになり、想いを寄せているヤアアンに心を許していく
そして、大人の関係になり、さらには妊娠まで発覚してしまった
カロリーネは結婚を考えていたが、ヤアアンの母(Benedikte Hansen)はそれを認めず、妊娠したのかも疑っていく
結果として、それは証明されたものの、「結婚するなら私のお金は一銭も出さない」と言われてしまう
母親に依存していたヤアアンはカロリーネを捨てることになり、工場もクビになって路頭に迷うことになった
物語は、そんな彼女の元に夫ピーダ(ベーシア・セシリ)が戻ってくるところから動き出す
ヤアアンの母親に反対されるまでは「新しい人ができた」と突き放すものの、生活が困窮し、誰かを頼らざるを得なくなる
ピーダは戦争で傷ついた顔を見せ物としてサーカスの一員になっていて、彼女はそのパフォーマンスに参加することになった
二人は寄りを戻すことになり、一度は堕胎を考えるものの、子どもは無事に生まれた
ピーダは育てたいと考えるものの、カロリーネは耐え難くなり、街で噂されているあることに委ねることを決める
それが菓子屋を営んでいるダウマ(トリーヌ・ディホルム)で、彼女は非摘出子の里親探しを行なっていた
カロリーネは彼女にお金を払い、ヤアアンとの子を里親に出すことに同意する
だが、ダウマは里親には出さず、あることをずっと行なっていたのである
映画は、実話ベースの物語で、ダウマという女性はデンマークで唯一と言って良いほどの連続殺人犯だとされている
合計25人(有罪判決は9人)を殺害し、新聞は「天使製造者(エンジェルマスター)」と書き立てた
当初は金銭目的だったものが徐々に変質し、正義感を持つようになっていく
それは、当時のデンマークでは非摘出子は空気のような存在で、公的な援助の対象外だったことも要因であるとされている
映画は、ダウマが何をしたかというのがミステリーとなっていて、実際の事件を知っていると「なかなか事件が起きない」と感じられると思う
不幸な女性カロリーナの不遇の人生と、戦後に行き場をなくした負傷兵の人生の方がクローズアップされていて、ダウマという存在はあまり認知されないまま進んでいく
そうして後半になって、カロリーヌがダウマのところで働き出してから「異変」を感じるというようになっていて、これは当時の無関心さというものを表していたのだと思う
後半は畳み掛けるような鬱展開だったのだが、ダウマ自身がカロリーネを引き入れたことが発覚に繋がっているので、彼女はどこかで着地点を探していたのかもしれない
ラストでは、イレーネをカロリーネが引き取るというシーンで結ばれるが、カロリーネがピーダの言葉に従ってスーシーを育てていれば、この事件には無縁だったかもしれない
それと同時に事件の発覚も遅れていたと思うので、妙な因果が社会を変えることになったのだなと思った
いずれにせよ、小さい子どもを持つ女性は閲覧注意の作品で、精神的にもキツイ作品であると思う
社会の犠牲になったと言えばそれまでだが、役割を自認する正義感ほど恐ろしいものはない
現在の閉塞的な空気も近いところがあって、国家の将来を危ぶむゆえに子どもを作らないという考えの人もいると思う
そう言った部分も含めれば、弱肉強食の世界で、成果主義と自己責任論で塗れていくと、いずれは落ちこぼれていく人が出て、それが商売になっていくという時代性は、今も変わらないのかな、と感じた
暗い
主人公の女の顔が暗いし怖い。工場の若社長もよく手を出したものだ。新しく借りた部屋が暗いし汚くて、当時をリアルに再現しているのか、トイレがバケツだ。貧困のつらさをひしひしと感じさせる。その上、帰還した旦那さんの顔が凄まじいことになっていて、生きづらいことこの上ない。
里親映画的な展開を見せたと思ったら超絶に違ってまさかの間引き映画で、暗澹たる気持ちになる。しかし最終的に主人公もサーカスで成功したのだろうか、女の子を引き取る里親展開だ。引き取られた彼女にしても、赤ん坊を殺そうとするなど闇が深い。
見ていてしんどいけど、すごかった。フルスイングしている。
砂糖菓子屋のウラ稼業/渡る世間は鬼ばかり
第一次世界大戦終盤から終戦直後のコペンハーゲンで実際に起きた事件にインスパイアされた映画とのこと。予告編からの印象はお針子さんが梅安先生になって復讐するサスペンス映画かな?程度で観初めてましたが、グイグイ引き込まれました。モノトーンなのにカラーで観ているような錯覚におちいるシーンやカット。不気味な効果音。
戦争から帰って来ない夫を待ちながら、縫製工場で働くカロリーネ。カロリーネ役の女優さんは満島ひかり似の美人なんだけど、個性的で、眉毛のうごかし方とかがちあきなおみのマネをするコロッケのよう。
家賃を滞納し、突然乱暴にアパートを追い出される。工場長に寡婦手当申請を出したら、あらあら。そして、妊娠。そこへひょっこり、死んだものと思っていた旦那が帰ってくる。右顔面をふっとばされて、義眼に仮面。
とてもハンサムでモテ男の工場長はなんと、いい歳して独身のマザコン。あの工場は男爵夫人の母親の所有物件なんですね。
縫製工場の親友役の女優さんはとてもタイプでした。
公衆浴場でのシーン。あれは本来何に使うための道具なんでしょうか?
カンヌでパルムドール取った映画「あのこと」を思い出しました。
ダグマ役の女優さんは貫禄があって、あの親切なおばさんがぁ?😨ってなります。面倒見がいいのにはウラがあった。
エーテルは飲みのものなのか?
ナフサも。
死んだと思っていた旦那が傷痍軍人となって帰ってくるとか、サーカスの見世物小屋っていうのも、映画ではよくあるのですが、カロリーネが舞台にみずから上がってゆくのは結構な衝撃でした。焼跡闇市世代ではないのに悲惨な戦争映画の秀作が多い塚本晋也も思わずウナったかもしれません。
裁判でのダグマの言い分もなかなか。
最後。イレーヌはカロリーネに引き取られると、ずっとあの日々を思い出して、かえってツラいのでは???と思いました。
モノクロの良さが際立つ映画
モノクロ、スタンダードサイズの画面に見入った
残されたイレーネに幸多かれと祈る
期待度◎鑑賞後の満足度◎ 北欧では有名な話でも日本では殆ど知られていない。だから余計前知識無しで観た方が良い。モノクロ-ムの映像もさることなから語り口のユニークさに唸らされる。
①形は変わってもこの問題は現代社会の裏側で生き続けている。そこにこの映画の現代性がある。
②映画の3/4までは色んな事が起こるのだが何も起こっていないに等しい。話が何処に向かっているのかよくわからないからだ。しかし、残りの1/4にさしかかったところで一気に全体像が露になる。
ずっとカロリーネがヒロインで彼女中心の映画だと思っていたら終盤で彼女はこの物語の内側を外から覗くための装置であった事がわかる。
実に面白い語り口の映画だ。
③「殺す」のと「捨てる」のとどちらが良いか。“良識”で考えれば勿論「殺す」ことは罪であるが、現代でも望まれなくて生まれた子供をやむを得ず殺す母親(というか妊娠した/させられた女性)は後を経たない。
○○○の中では「捨てる・手離す」ことと「殺す」ことは言い方は違っても同じことだったのかも知れない。
結局○○○の反抗動機はハッキリさせないまま観客の想像に任せることで終わっているが、○○○が死産ばかりで結局自分の子供を持てなかったこと、○○○○が赤ん坊を殺そうとしたエピソード等、そこここに推察する手掛かりは寘かれているようだ。
ラストの
罪の重さ
着想、からのアプローチ
第97回アカデミー賞において、国際長編映画賞(デンマーク代表)にノミネートされた本作。会員サービスデイのヒューマントラストシネマ有楽町、9時30分からの回はあまり客入り多くはありませんが、層の厚い今週公開作品を考慮すれば健闘している方かと思います。
終戦(第1次世界大戦)直前のデンマーク・コペンハーゲン。改めてWikipediaを確認してみると国としてのデンマークは「中立」という立場のようですが、経済状況は戦争の影響で大変に厳しく、劇中に見て取れる世間の雰囲気、そして主人公であるカロリーネ(ビク・カルメン・ソンネ)の状況もそのことを物語っています。真面目に働いてはいても、女手一つでは充分な収入を得ることはできずに家賃を滞納、遂にアパートを明け渡すように言われるカロリーネ。大家の伝手で何とか移住先は決まったものの、そのかなり荒んだ状態の部屋ですら家賃を払える余裕はありません。そのため、そんな状況を打破しようと勤め先である縫製会社の社長ヤアアン(ヨアキム・フィェルストロプ)に「寡婦手当」を出してくれるよう訴え出るカロリーネ。ところが、このことがきっかけとなりカロリーネの人生は大きく、そして意外な方向へ動き始めます。
本作を観ていて気付くのは、戦後の貧しさに喘ぎながらも皆、他人を見捨てることはせずにギリギリの中で手を差し伸べあって生きていることが見て取れます。登場人物たちがとる言動や選択は、当然に現代の倫理観のままではみられないこととは言え、大変に人間味を感じて理解も出来るし、寄り添えなくもありません。そしてまた、戦争という背景に何かしらのトラウマを抱える者は、モルヒネやエーテルなどに頼り、苦しみを遣り過ごしながら生きる日々がやるせなく、観ていてただただ悲しくなります。
そんな中において、若干「楽観的」に過ぎるとは言え、好転することに期待を持てそうになると決まって裏切られるカロリーネ。ようやく「こうなることが運命だったのか」と思い始める後半、カロリーネの希望を完全に打ち砕くほどの「衝撃の真実」が判明し、観ているこちらも思わず唖然。そして、作品が終わった直後に一文、フィクション映画におなじみの「実際あったことを基に着想を得て作られたストーリー」。観終わって、こちらもWikipediaで追いかけてみると解る「基」の部分に対し、なるほどこれがあってこそ作品のインパクトなのは間違いないものの、このアプローチでストーリーに仕上げたことこそが「作品の評価」に繋がっていることが判って改めて驚き、そして納得。マグヌス・フォン・ホーン監督(脚本)の手練れっぷりを知れ、今後も出来るだけ注目したいお一人。日本でも作品が観やすくなるといいな、と期待して微力ながらチェックインしておこっと。想像以上の良作、見事な一本でした。
人間の業
高度なリアリズムの技巧で、
「100年前の当時の光景」を見事に再現している、
そこには一切の欺瞞がない。
だが、その徹底した客観性ゆえに、
観る者の感情の奥底に触れるような、
「匂い立つ」情動や、
人間存在の普遍的な問いかけが、
やや希薄に感じられる側面がある。
それは、技術的な完璧さと引き換えに、
物語が持つべき詩情や、
時代や場所を超えて観客の琴線に触れるような情感が、
わずかに後退しているのかもしれない。
もう少し具体的に書いてみよう。
モノクロのコントラストが際立つシャープな映像は、
ベルイマンの作品群を強く彷彿とさせる。
窓から差し込む太陽の光の筋、
簡素ながらも計算された家の佇まい、
そして部屋の在り方は、
ベルイマン作品が持つ象徴的な美学と共鳴し、
スクリーンに緊張感と奥行きをもたらしているのは確かだ。
しかし、そのアプローチには決定的な違いがある。
ベルイマンが、ある種のリアリズムを基盤としつつも、
スクリーン内の情報量を可能な限り効果的に捨象して、
抽象度を上げる、
そこから哲学的な問いかけや、
人間の業、神の存在といった深遠なテーマを物語的にフォーカスし、
観客を誘導したのに対し、
本作はひたすらに現実に肉薄する。
ストーリーは、時に複雑な人間関係を孕みながら、
あくまで日常の延長線上にあるリアリズムに徹し、
淡々と、当時の「ファクト(らしいこと)」を提示し続ける。
私はこの作品のビジュアルには圧倒されたが、ストーリーや演出には完全に没入しきることができなかった。
それは、
かつてポーランドのウッチの国立映画大学の校長と話したときの、
学長の言葉を思い出す。
「学生の多くは撮影や照明の技術は高い。
人間の業のようなものをシナリオに書いてくる学生も多い。
ただ、キェシロフスキやズラウスキーのような、
匂い立つような描写の表現を書いてくる学生は少ない」
女が命の責任を負わされる、今も変わらない世界。
今年の胸糞オブTheイヤーになりそう!yearってか嫌〜!しんどいしんどい!50歳子持ちのオバチャンにはしんどいが過ぎるよ!母乳育児大変だったなぁ⋯。
サブスタンスを観る前に観ておけば良かった。女性性の消費に対する問題提起の部分は同じだけど真逆の描き方だった。
デンマークで実際に起きた事件に着想を得た物語。ラース・フォン・トリアーに最も影響を受けたと語る監督が描いた世界と知って、かなりわかりみが深まる。
街並みや部屋の美術、音楽が白黒の世界を哀しく美しく見せてくれて、モノクロ映画どうなの?と思ったけど、実際観るととても良かった。ただ、前半ちょっと眠かった。北欧の鬱々とした雰囲気とセリフで眠くなりがちです。
母乳って、あげれないと岩みたいにカチカチになってとにかく痛いんだよね。搾っても痛いんだ。あの辛さ思い出すだけでも憂鬱。
身体の痛みと心の痛み、全身全霊で痛みを感じるのですよ。後半は観ててずっと胸が痛い。
「あなたは善いことをした」と言う彼女のセリフは自分に向けての言葉でもあったのかな。弱者が身を寄せ合うあの世界に、果たして救いはあったのか。どこにも無いのかも知れない。
現代日本も、女が命の責任を負わされるという意味ではこの映画の世界とそう大差ない、同じ糸で繋がれてるんじゃなかろうかと思う。
タイトルの針の意味をあとから知って余計に落ち込むところまでセットで味わっていただきたい!
【パンフレット B5 表紙込み28P 1000円】
縫い針がデザインされた表紙と裏表紙、全体のデザインもページ端を縫ったようにデザインされてて全体的にレトロかわいい感じ。ヒグチユウコさんのイラスト良かったぁ。内容は、受賞歴や各賞のノミネート紹介、インフルエンサーコメント、ストーリーを思い出せるような劇中写真、公式解説&あらすじ、試写会後の監督アフタートーク、専門分野の人や作家、記者のレビュー4本、美術監督&映画プロデューサー磯見俊裕氏の美術レビュー、キャストスタッフ紹介、監督コメント、少しオフショットなんかもあって、少し高いかなと思いつつ満足。
『エグい描写あるってよ』
正しい選択
針のように突き刺さる、子供を産む事、子供を育む社会への問い
【イントロダクション】
第一次世界大戦後のデンマークにおいて実際に起きた事件を基にしたミステリー。主演に、若手女優のヴィクトーリア・カーメン・ソネ。監督・脚本はマグヌス・フォン・ホーン。
【ストーリー】
第一次世界大戦中のデンマーク、コペンハーゲン。カロリーネ(ヴィクトーリア・カーメン・ソネ)は家賃を滞納しており、退居を命じられてしまう。夫のペーター(ベーシア・セシーリ)は派兵されてから連絡がつかず、生死不明により戦没者名簿にも記載されていない事から、カロリーネは寡婦補償を受ける事も出来ないでいた。カロリーネが勤務する裁縫工場の社長ヤアアン(ヨアキム・フェルストロプ)は、不憫な境遇の彼女の事を気に入り、2人は肉体関係を持つようになる。
しかし、終戦後のある日、行方不明だったペーターがカロリーネの前に現れる。彼は戦場で負傷し、歪になった顔の右半分を隠すため鉄製の仮面を被っていた。連絡も寄越さず、醜く変わり果ててしまった夫を前に、カロリーネはヤアアンの子を妊娠していると打ち明け、彼との未来を選択してペーターを追い出す。
後日、出勤したカロリーネはヤアアンのオフィスに押し掛け、強引に結婚を迫る。無事結婚を取り付けたかに見えたカロリーネだったが、ヤアアンの母親が結婚に反対し、ヤアアンは婚約関係を破棄する。
失意のカロリーネは、公衆浴場に持ち込んだ裁縫針で堕胎を試みるが、偶然居合わせたダウマ(トリーネ・デュアホルム)という中年女性と7歳の娘イレーナによって助けられる。ダウマは飴菓子店を営む傍ら、カロリーネのように望まぬ出産をしてしまった女性達から赤子を引き取り、養父母を斡旋しているという。
帰り道、カロリーネはサーカスの見せ物小屋を訪れる。そこでは、ペーターが戦争負傷者として醜く変わり果ててしまった素顔を晒していた。互いの絶望と苦しみに共鳴し合った2人は、再び一緒に暮らし始める。
カロリーネのお腹は次第に大きくなっていき、出産の日が近付いていた。ペーターは産まれてくる子を自分達の子として育てる事を望むが、カロリーネはヤアアンとの子を産む事に拒否反応を示し、堕胎してペーターとの子供を望む。しかし、ペーターは生殖機能不全に陥っており、自分達の子供は望めないと告げる。
出産後、カロリーネは産まれた女の子をどうすべきか苦悩し、ペーターの隙を見て赤子と共に家を飛び出し、ダウマの元を尋ねた。仲介料を払えず、住む家も失ったカロリーネは、ベビーシッターとして赤子に母乳を与え、店を手伝う事を条件にダウマの家で共同生活をする事になる。
新生活が始まり、カロリーネは時折母乳を与えているイレーナと親しく、孤独感と罪悪感を抱えるダウマと薬物(エーテル)を乱用するようになっていく。
ある日、ダウマは男の子の赤子を引き取り、カロリーネに世話をさせる。世話をする中で次第に赤子に対して愛着が湧いていくカロリーネだったが、ダウマは彼女から赤子を取り上げ、何処かへ連れて行ってしまう。ダウマを尾行したカロリーネが目にしたのは、路地裏で赤子を絞殺し、下水道に棄てる姿だった…。
【感想】
モノクロで描かれる「幸福の国」デンマークの歴史の闇。事態が悪化していく瞬間に陰鬱で不穏なメロディーを大音量で流す演出含め、とにかくラストに辿り着くまでは陰鬱な雰囲気と絶望的な出来事の連続で、全く救いが無い。
事実を基に、暗黒の時代を淡々と描いており、全体的に大人しめの作品なのだが、妙な魅力があり嫌いにはなれない。
ヴィクトーリア・カーメン・ソネの役作りが凄まじく、ダウマとの生活の中で次第にやつれ、老け込んでいく姿は圧巻。ダウマが逮捕され、彼女の裁判の傍聴席に佇む姿、孤児院に引き取られたイレーナを養子に迎えるラストの笑顔には、暗い時代、凄惨な事件の果てに僅かな光が差し込んだような気がした。
ダウマ役のトリーネ・デュアホルムも良い。一見すると人当たりの良い中年女性だが、その内に抱える狂気は邪悪そのもの。度々口にする「(あなたは)正しいことをした」という台詞は、実際には自身の行いを正当化する為に言い聞かせていたかのように感じられた。
警察が押し入る直前、ダウマが暖炉の中に残っていた遺灰と遺骨を一瞬見つめ、カーペットの下に隠して処理する姿も印象的だった。
しかし、彼女が法廷で傍聴者達に投げ掛けた「じゃあどうすれば良かった?他に何か出来たか?お前達は私に感謝すべきだ。私が代わりにやってやったんだ。表彰されたっていいくらいだ」という主張は、望まれない不幸な赤子達を溢れさせた世間に対する痛烈な批判だ。終戦後、夫の戦死によるシングルマザーが増えた。しかし、婚外子に世間や政府は無関心であり、貧困や世間体から、女性達は赤子の扱いに困っていた。ダウマのした事は許されない事だが、一体あの時代、あの場所でダウマを攻めるに値する人がどのくらい居たのだろうか?彼女の主張に一度静まり返る法廷の様子が忘れられない。
では、ここ現代日本ではどうだろう?現代においても、様々な理不尽な要因による望まない妊娠はあるだろう。だが、少なくともこの日本においては、多くの妊娠と出産は親である男女の自由意志と自己責任であるはずだ。しかし、それでも望まれない不幸な子供は産まれてくる。父母が赤子を殺めてしまうニュースはいつの時代も耳に入ってくる。ダウマは他人の子を幾人も手に掛けていたが、実の親が子供を手に掛ける事もまた許されざる悪である。
恐らく、現代で本作が製作され、それを目にした我々観客に考えてほしい事の一つのは、「親になるのに“資格”は要らないが、“責任”は要る」という事だろう。
そして、子供を産んで育てていくには、社会保障や周囲の理解と協力、そうした環境の充実が必要不可欠だ。世間や政府が無関心を貫けば、現代においても再び凄惨な事件がいつ起きても不思議ではないのだから。
ラスト、カロリーネは孤児院に送られたイレーナを引き取り、養子として迎え入れる。ダウマの下で奇妙な友情を育んだ2人が再会の瞬間に零した笑みと、あの抱擁に見た僅かな光が、希望の光であってくれる事を願うばかりだ。
【総評】
デンマークの暗黒時代にメスを入れ、救いと答えのない、しかし忘れてはならない問題を問い掛けてくる。日本では出生率が減少し続ける一方だが、そんな現代日本においてすら、本作で提示される問題は針のように観客の心に突き刺さる。
全109件中、61~80件目を表示