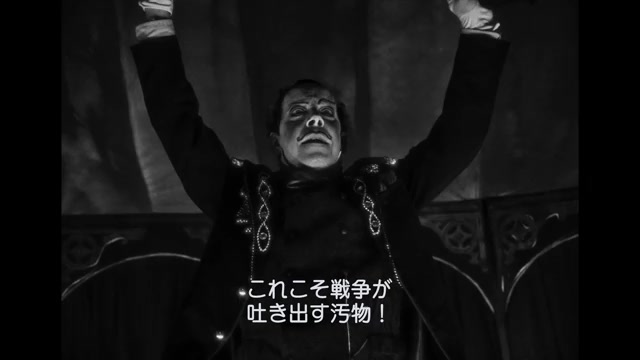ガール・ウィズ・ニードルのレビュー・感想・評価
全109件中、1~20件目を表示
闇を照らす、モノクロの凄み
本作がカラーであれば、流れる血は赤く、乳は白く滲んだかもしれない。けれども、モノクロームの世界ではどちらもどす黒く、不穏だ。冒頭から、これは最後まで正視し通せないかもとたじろいだが、いつの間にか、まばたきが惜しいくらいに惹きつけられていた。
住まいも仕事もままならないとはいえ、なりふり構わぬカロリーネの言動は、ちょっと共感しづらい。猛然と周りに牙をむき、感情をほとばしらせる。彼女の転機の可能性は、幾つかあった。しかし、彼女は、誰かと生きる道を踏み出さない。その人を幸せにできない、その人とは幸せになれないと割り切り、自分の幸せを貪欲に追い求める。そんな彼女の孤独、崖っぷちゆえの力強さを目の当たりにするうちに、少しずつ、彼女への見方が変わっていった。
あれよあれよと境地に陥った彼女に差し伸べられた手は、救いどころか、更なる地獄巡りに彼女を引きずり込む。カロリーネが流れ着いた、いわくつきの砂糖菓子店。ゆるいゆえに抜け出せない、絡みつく共同体のさまは、川上未映子の「黄色い家」に、どこか重なる気がした。
カロリーネをすくい上げるかに思えた、女主人・ダウマのキャラクターが、とにかく不可解で目が離せない。てきぱきと指示を出し、迷える女たちに「あなたは正しい」とささやき君臨する。その一方で、意外な脆さ、人間臭さを併せ持つ。ラストの不遜な立ち姿と、懸命な抵抗が印象に残った。
ダウマの寵愛を争うかのように、密かに火花を散らすカロリーネとダウマの娘。裏稼業を続けるため、「あること」を毎日欠かさぬよう命じられる。主人に認められるための、互いに望まぬ共同作業だ。それは画的もグロテスクで、本来の意味合いとは程遠い。ダウマが一手に引き受けてきた汚れ仕事の恐ろしさを、彼女たちは日々の作業で少しずつ体得したのではないか。愛情を求めるほどにすれ違う、ねじれた関係の行く末に、思わず息を呑んだ。
周りを蹴落とし続けたカロリーネの新た選択は、到底罪滅ぼしにはなり得ない。けれども、誰かに引き上げられ、救われることから訣別し、彼女はようやく一歩を踏み出した。くすんだモロクロームの世界に、わずかな光と温かみが宿ったと、心から信じたい結末だった。
実際の事件に基づくが、創作された主人公により衝撃と余韻が増した
第1次世界大戦直後のデンマークで実際に起きた犯罪に基づき、時代と地域はそのままに、モノクロの映像で当時の雰囲気を再現している。スウェーデン出身のマグヌス・フォン・ホーン監督はこの事件がデンマーク以外ではあまり知られていないことから、事件を起こした人物ではなく、意図せず大変な状況に巻き込まれていく創作された女性カロリーネを主人公に据えた。その工夫により、観客もカロリーネの目を通じておそるべき事実を知り衝撃を受けることになる。また彼女に感情移入することで、自分や身近な人が似たような状況に置かれたらどうするだろうかと、答えの出ない問いを鑑賞後も抱え続けるのではないか。
本作はあまり予備知識を仕入れずに鑑賞したほうがいいだろう。とはいえ、貧困、望まぬ妊娠や出産、第1次大戦後(1919年頃)の社会状況などがテーマに関わっていることくらいは、観るかどうかを判断する基準として知っていても問題ない。影響がよく指摘されているミヒャエル・ハネケ監督の映画の中では、題材はやや異なるが「愛、アムール」に近いものを感じた。
映画の内容には直接関係しないが、プレス向け資料に早稲田大学名誉教授の村井誠人氏が寄せた解説の中で、望まれない新生児の誕生後、頭頂の頭蓋骨が閉じる前の柔らかい部分「(大)泉門」に針を刺す間引き(口減らし)の方法があったと書かれていて、これも衝撃だった。気になってネット検索したところ、英文の学術論文がいくつか見つかった。「Sewing needles in the brain: infanticide attempts or accidental insertion?」と題された論文によると、大泉門を通して脳に縫い針を刺す行為は、科学文献では40例が報告され、トルコとイランで多く、北欧や東欧などでも確認されたという。また、脳内に針が残ったまま成人することもまれにあり、同論文では82歳のイタリア人女性、また1970年に掲載された別の論文(Attempted infanticide by insertion of sewing needles through fontanels)では、32歳男性と31歳女性からそれぞれ脳内の針が見つかったという。
余談を長々と申し訳ない。もし本作の鑑賞後に興味を持った方が調べる手がかりになればと思い、書き残しておく。
静謐さと恐ろしさの狭間で
静謐なモノクローム映像の中、人間のグロテスクな側面が剥き出しにされていく。1910年代にデンマークで実際に起こった事件に着想を得たストーリーだが、すべての発端はやはり第一次大戦なのだろう。戦争さえなければ、誰もがこんなに追い詰められ、社会が蜂の巣をつつくように混沌化することもなかったはず。前半ではギリギリの状況を生きる主人公がさらなる苦難へと突き落とされ、中盤以降は、彼女に唯一救いの手を差し伸べた中年女性とのミステリアスな交流劇が描かれる。眼前に広がる町並みはまるで複雑な心理を象徴する迷宮だ。工場門が定刻通りに女性従業員を吐き出す様はリュミエールの代表作のよう。その上、そびえ立つ建物が不気味な影を落とし、道が曲がりくねる光景には、ドイツ表現主義の影響すら感じさせる。直視するのも恐ろしい歪み、傷跡、所業。なのにまるで催眠術でも掛けられたかのように、スクリーンへ引きつけられ続ける2時間である。
Gothic Film Noir
Girl with the Needle is more audiovisual eye candy than an engaging story. Think a techno music video shot as David Lynch's Elephant Man with the fine black and white compositions of Poland's Ida. Obviously there is some Von Trier influence in there. The pieces don't add to a whole but I may have only thought so because I am not a parent. Who would want to deliver kids into this dark world?
バッドエンドのようなハッピーエンドなのか?
第一次大戦直後デンマーク・コペンハーゲンで実際起こった幼児連続殺人事件を元に製作されたとかでかなり期待して見に行った(猟奇殺人モノが好き)
戦場から戻って来ない夫を待つ女性の極貧生活を事細かく描いて行く
針子として働く会社の社長と不倫妊娠、変わり果てた夫の帰還と別れ、会社をクビととてもミステリィとは思えない展開
正直私は何を見せられているのだろうかと完全に引いてしまったほど衝撃的過ぎた
私はミステリィを見に来たはずだがと
しかし、本作は更に畳み掛けてくる
大衆浴場で堕胎しようとした時に出会った女性(親子)に助けられてからが本番だった
砂糖菓子店の裏稼業として養子縁組の仲介業者してる所へ転がり込み安住の地かと
この頃には連続殺人事件の映画である事はすっかり忘れていた
それくらいガッツリ当時の女性による歴史的背景を描き続ける
上映2時間の内1時間半かけてやっと殺人らしき描写が出てきた
結構最悪な感じで
最悪な流れだがハッピーエンドなのか?と訳が分からなくなった
主役の女優と砂糖菓子店の女優がとてつもなく上手い
久しぶりに観たリアルで暗くて重さを感じてしまうが、観終わってから意外と悪くなかったと思ってしまった(感覚が麻痺してる)
麻痺した脳があの「サブスタンス」が明るい作品と感じるくらいに
私は胸糞悪い主人公だとおもた。
第一次大戦後の貧困に喘ぐ1922年のデンマーク🇩🇰で起きた実際の事件に着想を得た物語。
そう云う時代だった…と云われればそうなんだろうけども、
なぁぁんか、好きになれんのよ、主人公が。
いつも眠たそうな眼に幸薄そうな暗い表情で、
私は世界一の悲劇のヒロインでござい!って感じが鼻に付く。
戦争で夫を亡くし、家賃滞納でアパートから追い出されるくらい困窮してて、針子の薄給じゃぁ生活もままならないのは、まぁ、分かる。
そんな彼女の弱みに付け込んで、お遊び感覚で近付いてきた工場長に弄ばれた挙句…孕まされてポイだし、其処迄は同情出来るけど、
必死の想いで子供を産んだ後だよ…問題は!
ヒョンなキッカケとは云え、戦場で受けた顔の深手をサーカス🎪で見世物として晒しながらも、懸命に生きる元傷痍軍人さんと知り合えて…
全く血の繋がらない彼女の子供を、本当の我が子の様に受け入れてくれて、剰え一緒に生きていこう!って寄り添ってくれたのにぃ😭
そりゃぁさ、子供の父親であり元カレに、怨みつらみが有りすぎて、子供を見るとソイツを思い出して辛いってのも分かるけど…
そのクセ、自分の意志で我が子を捨てたのに、、
母性に目醒めてツライですムーヴはヤメロや!😡
ラストも…なんか一筋の希望が!エンドで、主人公をムリクリ良い人っぽく映そうとすんのがもう厭🤔
報われない母性、母体
妊娠や授乳という女性ならではの役割、さらにいえば子宮や乳房といった器官を、なりふり構わず「武器」にして生き抜く女性たち。同時に、それが本来の目的に向けられない痛ましさを見せつけられる映画だった。
裁縫工場で働くカロリーネは、戦争に行った夫を待ちながら困窮している。形勢逆転のため工場長の男性と関係を持ち、妊娠を理由に結婚にこぎつけようとするが、所詮は身分違いで破談。望まない妊娠に加えて工場もクビになり、完全に空回りだ。
入浴施設で自ら堕胎(!)しようとしているところ、養子縁組を斡旋する中年女性ダウマに出会い、産んだ子どもを託す。
子どもとの別れが皮肉にもカロリーネの母性を目覚めさせた。養子に出された赤ちゃんの引き取り手が決まるまで授乳する役目を引き受ける。それだけでなくダウマの7歳の娘イレーネにも母乳を与え始めるのだ。
前半までの悲痛な物語とは違い、曲がりなりにも母性の暖かさを感じる展開だが、ここで明らかになる恐ろしい事実。ダウマは赤ちゃんを養父母に斡旋などしておらず、自ら手をかけて殺害していたのだ。もちろん、カトリーネの子どもも。
多くの子を殺めながら、実子ではないイレーネを大事そうに育て、その子にカトリーネの母乳を飲ませる間、別の若い男と情事にふける。ダウマは女性として多くの矛盾を抱えており、謎の深さは陰の主人公と呼ぶのがふさわしい。
そもそも赤ちゃんを養子に出さないなら、乳母役としてカトリーネを雇う必要もなかったはず。ダウマは無意識に共犯者としてカトリーネを求めていたのではないだろうか。秘密を知ったカトリーネと一緒に赤ちゃんを圧殺するシーンは、まるで2人の情事のようだった。
終盤、ついに罪に問われたダウマに代わってカトリーネはイレーネを孤児院から引き取る。救いのあるラストではあるけれど、果たしてこれをカトリーネの成長と言ってよいのか。
容姿に恵まれ、戦争から戻った夫も(負傷によりサーカスの見世物になってしまったが)カトリーネを見捨てない。カトリーネを通じて、縫製工場で働く女性たち(ガール・ウィズ・ニードル)の不幸を描き切れたのかというと少し疑問なのだ。
思えば、産婆や乳母というように他者の生殖に介在する役割を女性は担ってきた。それが支え合いになることもあれば、命の否定に加担してしまうこともある。ダウマだけが加害者ではないだろう、本当の悪はどこにあるのだろうか。
少し装いを変えれば、そのまま
超ヘビー級作品
なんだかんだ言っても、結局ハッピーエンドで終わる映画的な体裁を取りつつ、「“ハッピーエンドでよかった”なんて言わせねぇよ」という圧が、全編を通してグイグイと迫ってくる作品だった。
「戦後」と言っても、第一次世界大戦の後なので、今から100年以上前の話だが、出産や子育てに関わる点においては、日本でも今なお解決できていないテーマが描かれているし、裁判の傍聴人は、まさにネット民の姿で、裁かれるダウマは、山ゆり園の事件の植松死刑囚に重なって見えた。
産業革命期を経て大規模に稼働する縫製工場や、見世物小屋としてのサーカス、日雇い労働に群がる人々や、食事や洗面・入浴などに垣間見える彼らの生活の様子が、匂いと共に感じられるような映像だった。超ヘビー級作品。
ひたすら息苦しくなる映画
アカデミー国際長編映画賞候補作で第一時世界大戦の頃のデンマークが舞台のモノクロ映画。暗そうな話は覚悟してたが、ひたすら息苦しい映画だった。救いはラストシーンだけかも、。
「正しいことをしたのよ」と、もぐりの養子縁組仲介(嘘だが)を営むダウマはそう言って泣く泣く自分の産んだ赤ちゃんを手放す母親を慰めるが、自らの犯罪を正当化する為に自分に言い聞かせていたに過ぎない。どんなに国が衰退してても庶民の生活が苦しかろうが、望まない子を宿し産んだ人々を手助けしたと主張しても、彼女の行為は全て許されない鬼畜の所業である。
カロリーネも同情するところはあるが基本的に身勝手であり、彼女の気持ちには寄り添えない。実話であり、表沙汰になった事件なのだが、世界には暗い闇の現実が今でも沢山ある。100年位前のこのような悲劇だけでも激減していることを祈るのみである、。
ホラータッチな演出に引き込まれる
20世紀前半にデンマークで実際に起こった事件に着想を得て創り上げた作品ということである。かつて日本でも”間引き”という風習があったが、それを連想させる話だと思った。こういう話はきっとどこの国にでもあるのだろう。
観終わって何ともビターな鑑賞感が残ったが、事件を伝えようという製作サイドの意気込みは強く感じられた。
ダウマのやっていることは明らかに違法行為である。そればかりか、後半で明らかにされるが、その行為は人道に反するものである。まるで鬼か悪魔か。終盤で見せる開き直りとも言える彼女の態度に戦慄を覚えた。
ただ一方で、当時の社会状況を鑑みれば”汚れ仕事”をやらされている…という見方も出来る。先述した”間引き”にしても、当時の人々は生きるためにやむを得ずしていたわけで、自分はダウマを一方的に糾弾するという気にはなれなかった。
実際、彼女は本作の主人公カロリーナに救いの手を差し伸べたわけで、人間らしい心を失くしたわけではないように思う。
二人の出会いは公衆浴場。絶望に打ちひしがれ傷ついたカロリーナを見て、ダウマは理由も聞かずに介抱してやる。そして、住むところを失った彼女を家に招き入れて面倒を見てやる。後になって、ダウマ自身、悲劇の過去を持っていたことが分かるが、それを知ると彼女はカロリーナとの共同生活に安らぎを求めていたのかもしれない。あるいは、男尊女卑的な社会に対する女性の連帯という見方もできる。
一方のカロリーナは出征した夫と再会を果たすが、時すでに遅し。別の男の赤ん坊を身ごもっており、元の幸せな暮らしには戻れない。そして、我が子を委ねたという複雑な感情はあるものの、孤独な者同士、ダウマと親密な関係を築いていく。年齢差を考えれば、あるいは疑似母子のような関係にも見えた。
こうして二人の共同生活は始まるが、しかしこの安然の時間はそう長く続かない。当然のことながら、ダウマのやっていることは法律的には違法であり、その罪からは決して逃れることはできないからである。それはカロリーナも同じことで、我が子を捨てた罪は一生ついて回るものであり決して消せるものではない。
鑑賞後に知ったが、主人公カロリーナは映画独自のキャラクターということである。彼女は事件の被害者であると同時に共犯者でもある。ダウマの犯罪を間近で目撃するキャラであり、観客は自ずと彼女の目を通して一連の経緯を知ることとなる。この構成が中々秀逸で、事件の裏側を覗き見するような、そんな感覚で物語を追いかけることが出来た。
映像はダークなモノクロで統一されており、画面全体が不穏なトーンに覆われている。複数の顔がモンタージュされる奇怪なオープニングシーンに始まり、瞳の強烈なクローズアップ、シャープな照明効果等が不気味さを煽り、ほとんどホラー映画のような禍々しさが作品全体に蔓延している。
加えて、映像に合わさる音楽も不快感、不穏さを募り、観てて非常に神経が逆なでされる。
本作は決してホラー映画ではないのだが、ある意味で極めてホラー映画然とした演出が徹底されており、それが一種独特な作風に繋がっているように思った。
ちなみに、ドラマ的には名匠マイク・リー監督の「ヴェラ・ドレイク」を連想したりもした。これは秘密裏に堕胎手術を引き受ける主婦の数奇な運命を描いた作品であるが、本作のダウマに通じるような所がある。
ただ、社会背景、宗教観、信条という点ではかなり異なる部分もある。また、どちらもシビアなラストを迎えるが、本作は少しだけ光明を見出せるようなエピローグが追加されており、そこは救いであった。
ガール ウィズ ニードル
「今作一番の発見」
なかなかの良作
正しいことを
第一次世界大戦下のデンマーク、コペンハーゲン。
カロリーネは戦場へ行った夫の帰りを待ちながらお針子として必死に働いていたが、アパートの支払いもできないほど生活に困窮していた。
やがて勤め先の工場長と恋に落ちたカロリーネは妊娠し、彼との結婚を約束する。
しかし、そんな時に死んだと思っていた夫が帰ってきて……
うーん……期待してただけに……
良くも悪くも言いたいことありすぎる。
まず、期待してるような胸糞人怖ホラーではなかった。
実話ベースだとどうしても真面目になってしまうし、真面目になるってことはホラーじゃなくなる。
もちろんそれが悪いことではないんだけど、あれだけトガってますよ感を出しておきながら、思った以上にガッチガチで、しまいにはあんなヌルい結末なので、ちょっと、それはね…
全体的にとっ散らかっちゃった印象。
当然ホラーでなければミステリーでもないし、社会派作品かと思えばドラマ展開。
やりたいこと全部ぶち込んで結局何がやりたいのか分からなくなっちゃった感じ。
何かしら1つ方向軸を定めて、それに向かって映画を作って欲しかった。
結局何がやりたかったのかが見えてこない。
なんとなくは分かるけど、他の要素も主題に限りなく近いせいでメッセージ性弱いよ。
あまりにも主人公がアホすぎる。
はじめは時代や環境のせいで、彼女たち女性の権利といった面で共感できる物語になると思ったのだが、結局彼女の問題では。
まあそういうカロリーネを作り上げたのも親や周りの環境、そして時代なんだと思うけど。
本当に申し訳ないんだけど、勝手に恋に落ちて、待ち受ける将来を予想もせずに飛び込み苦しんで、覗かなくても良い深淵を覗いたのはお前だろうがと。
お産を手伝ってくれたおばちゃんや旦那さんなど、彼女に手を差し伸べる優しさは身近にたくさんあったのに、それに気付けない、助けの求め方を知らない。
そんな彼女が哀れに思えると同時に、そういった生き抜く術を教えてもらえなかったんだと思うととても悲しい気持ちにもなった。
そして救いを求めた相手はよりによって…
そういう運の無さというか、人を見る目というか。
現代社会、身近でもこういう不幸続きの人って、何故かこういうものを持ってないよなと思う。
一体なんなんだろう。
能力なのか、学習できるものなのか、はたまた運なのか。
だから頭ごなしに否定はできないんだけどね。
正しさとは。
ダウマのことは責められないし、私は彼女の意見を大いに肯定したいけど、殺人を犯している時点で全くの肯定はできない。
鑑賞者側もあのシーンだけは正しさと悪さの境界がぐちゃぐちゃになって頭を抱えたと思う。
法廷シーンだけ見たらかなり好き。
途中で「はいはい分かった分かった、子殺しの話ですね」ってなってからは普通に飽きてしまって、あんまり乗れなかった。
途中は本当に退屈って声に出したいくらい退屈だった。
さらに、せっかくおばさんのところで強烈なパンチラインを残したくせに、再会からの引き取りとかいう激ヌルラストが本当に嫌すぎて、上がりかけた点数戻した。
陰影の使い方とかは良かったけど、映像もそんなに印象に残るほどではなかったし、音楽も雰囲気に合ってるようで微妙にあってない気がしてそこも残念。
かと言って、全体をボロクソにいうほど悪くもない。
ただ、やっぱり冒頭で合わないかもと思った作品はだいたい合わないな。
ラストが好きじゃないとさらにダメ。
予告編の煽り方が1番怖かった。
抉るような絶望
スケキヨが一番正常なのか
ホラーらしいと言う予備知識だけで鑑賞
怪物の様に奇妙に歪んだ恐ろしい顔が不協和音と共に延々と流れ続けるオープニング
なるほど、これは確実にホラーがはじまるオープニング
ドイツの撤退で戦争が終わって乾杯!
と言う場面から察するに時代は世界大戦直後
戦争未亡人が家賃を払えず無情にも追い出される
新しい家に幽霊がいるのか?
などとホラーを期待しながら物語が進んでいく
白黒で描かれる独特の画角の美しい映像
不協和音の入り混じる音楽
しかし最後まで幽霊は出てこないまま終わった
だけど確かにこれはまごうことなき100%のホラー
モンスターは人間
戦争が引き起こす貧困
貧困極まりない社会が人間を狂気の行動に追い詰める
金持ちの貴族が自社の社員の平民の未亡人をはらませたのに、冷酷に首にする場面などレミゼが始まるかと思いましたよ
人間の中に潜む怪物性があらわにされる本作
まさかの実話ベースの物語だとは驚愕です
戦争帰りのスケキヨ3倍増しの見た目怪物な旦那さんが一番正常な精神を保って日々を生きている皮肉
名作で怪作
SING SINGに続く2025年のベスト10に入れたいの洋画でした
全109件中、1~20件目を表示