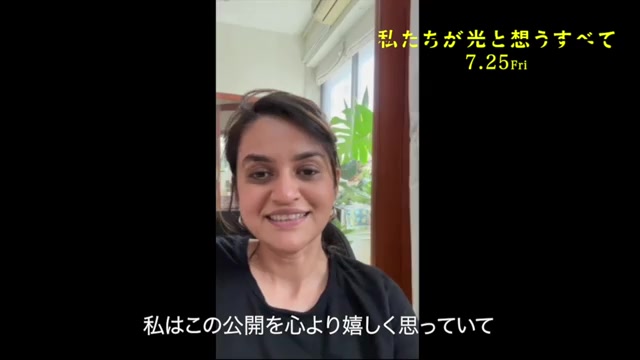「孤独な人を映し出す鏡のような輝き」私たちが光と想うすべて KaMiさんの映画レビュー(感想・評価)
孤独な人を映し出す鏡のような輝き
夕闇の中、インドの都市ムンバイの地下鉄で運ばれていく人たちに、無名の人たちのモノローグが重なる。「都会の暮らしは決して安住できるものではないが、人が集まる場所に私たちは希望を見続けてしまう」(大意)。この冒頭だけで引き込まれた。
高架を走る電車(上に架線が走っていないから地下鉄仕様なのだと思う)の「むき出し感」や、夏なので窓が開いた団地の家々を覗き込む感じが、見知らぬ人の人生を垣間見る映画のテーマを予告している。
看護師である主人公プラバは、良くも悪くもまじめで「堅物」といえる働きぶり。後輩の看護師が胎盤の処置に弱腰なのを叱り、中年女性のパルヴァディが地上げ屋に追い出されそうなので一緒に弁護士に相談して抵抗する。ただ、他人のために動けても自分のためには動けない。連絡が取れない夫との関係にしがみついているが、よりを取り戻したいのか、きっとプラバ自身もよくわからない。
ルームシェア相手の若い看護師のアヌは対照的な性格。宗教の違う恋人と、半ば公然とデートを繰り返している。プラバはそれをとがめるでもなく、新しい恋のチャンスをつかもうとするわけでもない。ただ、見ている側は「プラバの幸せとは何なんだろうか」をじわじわと意識させられる。
後半はパルヴァディが海辺の田舎に帰ることになり、プラバとアヌの2人も見送るため同行する。アヌはちゃっかり恋人と逢引きするのに対し、プラバも海で年上の男性を人命救助するという事件が起こる。
この男性に寄り添うなかで、プラバの脳内でドイツにいる夫が重なってくるのだ。許しを請う夫に、プラバはきっぱり別れを告げる。
重苦しい展開の中でようやく「光」が差すようなシーンだったが、これは果たして希望だったのか、それとも断念か。
思うに、アヌのような人が都会に「光」(たとえ幻想であっても)を見つけようとするのに対し、プラバは本来そういうタイプではない。アヌの言葉で言えば、洞窟の中で「何かが起こるのを待っている」女神のような存在。ちょうど鏡のように、孤独な人の思いを映し出すことで輝く。
プラバが都会の光を浴びるとき、また誰かの横に寄り添うとき。プラバ自身の中に何か大きなことが起こるわけではない。しかし人どうしが照らし合うような、希望と闇が交錯する時間が流れる。それをそのまま映し取ったような映画だった。
付け加えるならば、冒頭の魅力的なモノローグにつながるような、またプラバの未来を暗示するようなラストがあってもよかったと思うのだが。