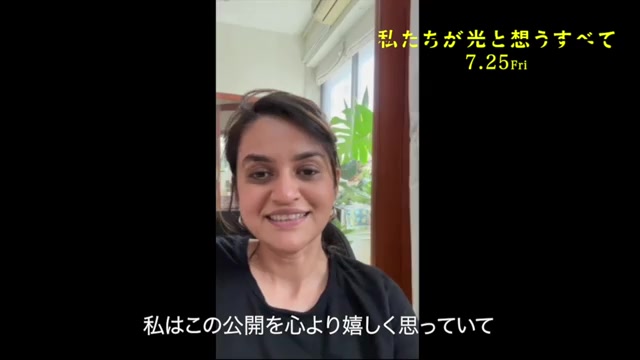「自分がしっくりくる場所を探して」私たちが光と想うすべて つとみさんの映画レビュー(感想・評価)
自分がしっくりくる場所を探して
気になる映画を観に行く機会に恵まれ、「私たちが光と想うすべて」を鑑賞。設定を聞く限りではもっとドラマチックな展開があるのかな?と思っていたが、どちらかというと日常に根ざした落ち着きのある映画だった。
いい映画だったなぁと思うが、娯楽度は低め。一応製作国にインドも名を連ねているものの、テイストはヨーロッパ映画である。というか、インドでは無理めなシーンがチラホラあって、観てる最中に「これインド映画じゃないな」と気づく。
そこは大した問題じゃないけど。
主人公のプラバの変化が作品の一本の道筋となっていることは明白だ。
見合いで結婚した夫がいるが、関係を深める間もなくドイツへ出稼ぎ中。長らく不在の夫は音信不通気味で夫婦関係などほとんど存在していない。だが、離婚したわけでもない、宙ぶらりんの状態なのに、根が真面目で規範に忠実なプラバはほとんど表情を変えることもなく、職場と家との往復だけの毎日を淡々と送っている。
そんな彼女とルームメイトのマヌが同じ病院で働くパルヴァティの帰郷に同行したことで、ほんの少し変化するのだ。
規範とされていることに疑問を抱く暇すらない都会の忙しない日常と、その対極として田舎のゆったりとした空気感。
その雰囲気の違いが彼女の心のケリをつけられない部分に変化を促したのだろうと思う。
また、もう一人の主役はムンバイという都市そのものなのだろうとも思う。都市を離れることでプラバが変化する物語ではあるが、監督はムンバイを悪役にしようとは考えていないように思うからだ。
プラバを人生の鎖から解き放ったのはムンバイから離れたことがきっかけではあるが、プラバの同僚であるアヌは「今さら田舎で生きていける?私は無理だな」と口にしているし、ムンバイという都市の持つ圧倒的なパワーが伝わってくるようなシーンも多かった。
大事なのは「自分にとってしっくりくる」生き方や場所、それを選ぶのは自分自身なのだということなんじゃないかと思う。
私自身はバリバリの都会っ子なんだなということも痛感した。前半のムンバイ・後半の海辺の村ともに、映画は色んな音にあふれている。工事の音、雨の音、電車の音、風の音、波の音、虫の音。
これは意図して大きめに入れているそうなのだが、映画前半ではほとんど気にならない、むしろ音として認識していなかったものが、後半ではやけに大きく聞こえたからだ。
普段聞き慣れている音はあまり意識に残らない。私にとっては工事の音や電車の音は無音に近い感覚で、波の音や風の音ははっきりと聞こえてくるものなのだ。
うるさい、とは思わないが「音デカいな」とすぐに気づくほどには顕著な差があったのである。
気になる映画を気軽に観に行けるのも都会っ子ならではの幸せだ。
私が私らしくあるために一番大事なことでもある。