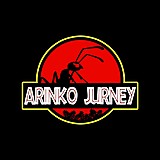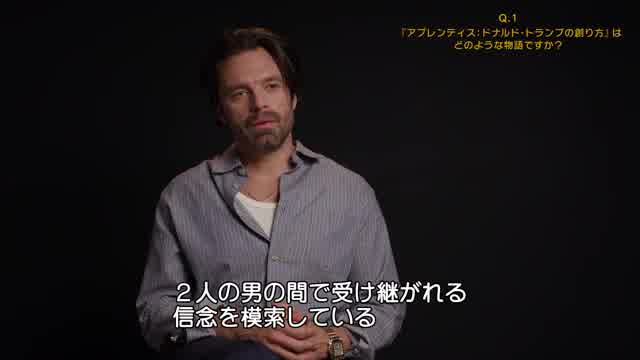アプレンティス ドナルド・トランプの創り方のレビュー・感想・評価
全220件中、1~20件目を表示
続編求ム!
映画で言われる3つのルールよりも、ドナルド・トランプのいう成功の秘訣「好きなことをやれ。決して諦めるな。勢い(momentum)を保ち続けるんだ」は普遍的なものだが、彼が言うととても響く。
大統領としての彼の政治的立場や発言にはここでは全く触れるつもりはない。前述の秘訣を押さえておくと、とても素晴らしい娯楽作品だった。
「アプレンティス ドナルド・トランプの創り方」
・
・
・
The Apprentice とは「師弟」「見習い」といった意味を持つが、自身がホストで参加した、参加者に様々な課題を課し、個人やグループ単位で課題に取り組むTV番組のタイトルであり、本作の主軸となる悪名高き弁護士ロイ・コーンとの関係を示した2つの意味を持つ。
副題の「創り方」がマイケル・ムーアの作品や「マネーショート 華麗なる大逆転」などの観る側に勝手に観方を操作しており、これにはがっかりだが、そこにとらわれなければ、普通に成り上がりものとして、ピカレスクものと呼んだりするのは、観る側の受け取り方で、「サクセスストーリー」とみてもよい。
70年代から80年代後半へ渡る映像と音楽にすごいこだわりがあり、ちゃんとタイムスリップさせてくれる。オレはそうした映像と全編にわたるディスコミュージックと、シンセの不穏な劇伴、「f**k」が飛び交うセリフ、「ゴージャス」な豪邸と、「スカーフェイス」(’83)を思い出した。そういえばアル・パチーノはHBOのミニシリーズ「エンジェルス・イン・アメリカ」でロイ・コーンを演じていたな。
アニキからの子供へのプレゼントを受け取るや放り投げたり、そのあと奥さんがスルーしたり、笑いも随所にあって楽しいし、物語の後半のハゲと出っ腹の脂肪除去手術のシーンは、アリ・アッバシ監督が言うようにフランケンシュタインのモンスターの誕生がイメージされる。オレはそのあとのカットの、天井に映った彼の頭頂部のほうが気にはなったが。
そしてやはりアメリカの政治史やビジネス界で重要となるコーンとトランプの関係の物語がとても興味深い。
コーンの攻撃的な法律戦術や、勝つためにはどんな手段も辞さない姿勢は、若きトランプを見事に変えた。そして物語の後半、コーンがエイズを発症し、1986年に死ぬに至るまで、彼の健康状態が悪化してトランプは彼との関係が逆転する。
トランプがコーンの教えを守り「強さや成功」に固執し、「弱さや失敗」を嫌う教えを忠実に学んだ結果に至るまでの、セバスチャン・スタン、ジェレミー・ストロングの両者の変貌ぶりがスゴイ!(特にストロングの、冷たくも強い目力、つやっつやな肢体からのエイズに侵されてからのギャップの激しさ!)
トランプどうのこうの、副題で客寄せの効果はあるが、それを差っ引いて、もともと映画的に強いキャラクターな主人公とその師の壮絶な生きざまを「娯楽」としてみるのが一番いい。
そして観る側もThe Apprenticeのごとく「学ぶ」ことも多い。
追記
現在に沿って、どんどん続編をつくってほしいと切に願う。
トニー・モンタナのような最期となるか、それとも。
追記2
オープニングのニクソン元大統領の声明の引用がちょっと誘導的だったのが残念。
映画で似せるとはどういうことか
セバスチャン・スタンをドナルド・トランプに似ていると思ったことはなかったが、役者だからそれなりにやるのでしょうと期待していて、フタを開けてみたらとんでもなかった。自分を含めて多くの人は若い頃のトランプをさして知らず、しかしスクリーンの中にいたのはちゃんと後のトランプに繋がるクセやビジュアルを兼ね備えた、トランプ一歩手前の若者の姿だったから。
若い頃には随分ナイーブだった(劇中の)ヤングトランプは、ロイ・コーンという手本にしちゃいけないけれど力を求め、力にひれ伏したい欲望を持った男を手本にして、どんどん自我が肥大したろくでなしになっていく。つまりはわれわれが知っているトランプのイメージに近づいていくわけだが、セバスチャン・スタンはモノマネのように似せるでなく、しかし要所要所でしっかりとトランプ味をだだ漏れにさせて、ひとつの寓話としての半生記を形にしていく。
物語上の時代を反映させた映像処理も、ちょっとやり過ぎなくらいクッキリとしていて監督の腕力を感じさせる出来栄えだが、とにかくセバスチャン・スタンが良かった。いや、ロイ・コーンを演じたジェレミー・ストロングも良かった。もう肩幅の狭さだけでキャラに説得力が宿っている。ストロングも、似ているといえば似ているし、似てないといえばそんなには似てないのだが、人としてのインパクトがある。キャスティングの勝利!
闇から這い出てきたアッバシ的な怪人たち
まるでアリ・アッバシ監督はヒーローの全く登場しない怪人映画の語り手のようだ。世間的にはトランプの秘話映画として注目を浴びるだろうが、私としては、アッバシが描くキャラ列伝に現役大統領が顔を並べることになった事実に沸々とした高揚と震撼を覚える。それも今作は最も社会の明るみに立ち、邪悪で、不遜で、巨大で、危険。本作で明かされるルール3ヶ条に基けば実際のトランプは映画の内容を「でっち上げだ」と完全否定し続けるだろうから、そこも含めて現実と地続きのストーリーとして楽しめる。とはいえ、驚異的な俳優二人が織りなす本作が伝統的な「メフィストとの取引契約」として描かれるのが面白いところ。ファウストは最後に魂を奪われるべきだが、その既定路線に陥らないところがトランプらしさであり、実は彼こそがメフィストだったとも言える。ならば彼と契約を交わした米国は、いやこの世界は一体どうなっていくのか。それこそが最大の謎だ。
トランプについてというより、ロイ・コーンについての映画
トランプが大統領に返り咲いたことで、俄然注目を浴びている本作だが、これはトランプについての映画というより、ロイ・コーンについての映画と思った方がいい。ちなみにタイトルの「アプレンティス」は、英語で「見習い」みたいな意味で、この映画の中のトランプがまさにコーンの見習い的ポジションの人物として描かれる。後年、トランプを有名にした同名のリアリティショーの話ではない。
トランプが駆け出しのころに、彼をビジネスの成功に導くメンターのような役割を果たしたロイ・コーンの教えが今日のトランプの行動原理となっていると本作は解釈している。これは劇映画なので、作り手の解釈によって提示されている物語なので、これを見てトランプの全てをわかった気になるのは危険だが、コーンの教えが彼の行動に影響を与えたのは確か。マイノリティとして成りあがるための戦略が、ある種の帝王学となり、それがトランプへと受け継がれてゆくという筋書きは興味深くはある。
観ていて楽しいレアネタ満載の人物伝
ドナルド・トランプが2期目のアメリカ大統領に就任する直前(日本では)、彼の知られざる成功物語の裏側を描いた映画が公開された。不動産王として名を馳せた父親の陰にまだ隠れていた若きトランプが、ニューヨークの高級レストランで何かと黒い噂が絶えない弁護士のロイ・コーンと出会い、コーンに言われるがまま、常に攻撃し、非を認めず、勝利を主張せよ、という、今に繋がる3原則を守って不動産業界で一気にのし上がっていく。
成功者にはいつもアドバイザーがいるというのはよく聞く話だ。しかし、この映画が面白いのは、日本やアラブマネーにニューヨークが買い占められようとしていた1980年代、当時のアメリカ大統領、ドナルド・レーガンがぶち上げた"アメリカをもう一度偉大に"というキャッチフレーズを借用したトランプが、時代のうねりに乗って成功への階段を上り詰めていくところ。ドナルド・トランプとはアメリカ的民主主義と資本主義が生み出した怪物なのだと、改めて確信した。
詳細は控えるがトランプのプライバシーに関するあれこれも随所に散りばめて、すべてを鵜呑みにするのは危険だが、観ていて楽しいレアネタ満載の実録物語。トランプ自身は映画の内容に抗議しているらしいが、決してネガティブキャンペーンにはなっていないと思う。
“怪物”を生み出す米政財界の構造的欠陥を示唆する点で、チェイニーを扱った「バイス」に通じる
メンターとしてドナルド・トランプを成功に導いた弁護士ロイ・コーンの存在は不勉強で知らなかったが、演じたジェレミー・ストロングの冷徹な眼力と抑制された凄味が身震いするほど素晴らしい。ロイの指導がトランプの人格形成に影響し、彼が実業(と後の政治)の世界でkiller=勝者になるのを後押ししたことは本作でわかりやすく語られている。
とはいえ、ロイの個人的な資質がトランプを創ったという単純な話ではない。米国の財界と政界で一部の役職やリーダー的存在に強大な権力が集中し、そうした強すぎる権力の行使が正義や道義や公平さを損ねても抑えたり罰したりすることが困難であるという構造的な脆弱さと欠陥が、ロイ・コーンやトランプのような“怪物”が生まれる背景にあることも、本作は丁寧に描いている。
アダム・マッケイ監督作「バイス」でも、クリスチャン・ベール演じるディック・チェイニーが酒癖の悪いただの若者から、大物政治家ラムズフェルドのもとで権謀術数を学び副大統領まで成り上がる過程が描かれた。勝者がどこまでも強大になることがアメリカ的な民主主義と資本主義の強みであると同時に、脆弱さでもあることを両作品が示唆している。
An Unpack of the Guy Everybody is Tired Of
Released just before the election, Apprentice is a savvy-eyed look at the young president-to-be. Sebastian Stan's performance of Trump is by far the best of the myriad of impersonations over the years. One would think the man himself could appreciate it. Demoralizing events onscreen will make even detractors wish the film really is a so-called "hatchet job." Roy Cohn's AIDS story was news to me.
Donaldにも、ゴメンナサイが言えた頃があった。
セバスチャン・スタンのファンなので、トランプを演じると聞いた時は「見るのもイヤなあの男を、推しが演じるなんて〜!」とガックリ、劇場公開時かなり迷ったものの(近場での上映が無かったのもあり)結局見ませんでした。
気にしつつ、高い評判は聞きつつも今回やっと配信で視聴。
いやなんとも…よく作ったなぁこんな映画。
もう、ソコソコいい年になってるのはわかってるんだけど、セバスタの魅力の1つである「子犬っぽさ」が序盤、まだ頼りない若トランプに滲み出ていて自分が何を見てんだかよくわからなくなりました(苦笑)
「負けても負けるな」はスポーツだったらいいアドバイスと思う。
ただ、スポーツなら真に競って勝つべきは自分自身のみ、というところに落ち着くだろうが、悪のメンター(メフィストフェレスのような)ロイ・コーンの言う「負けるな」はひたすら他者を貶めて貪欲に自身を拡大していくための処世術。
年をとり、してきた事の毒が総身に回ったロイ・コーンは心身ともに弱ったことで逆に人間性を取り戻していく(ように見える)が、もう取り返しがつかないことばかり。この展開はかなり胸苦しい。
「勝って威張りたい」の一念でひたすら登りつめていく、その結果は残念ながら現行の現実で実際に見ることが出来る。いまだに信じたくないが。
ただ、この映画を観たことで現アメリカ大統領を「見る」ことがほんの少し、楽になったかも。見てるだけじゃなくて、現世のためになんかしないといかんな、とも思えた。
ハイリスクな仕事を見事こなしたセバスタに感謝。
成り上がり
「アプレンティス」とは「見習い」という意味で、トランプが00年代に司会を務めていたテレビのリアリティ番組のタイトルとのこと。1970~80年代というトランプが不動産業を始めた頃から不動産王として成り上がっていく時代を描いた映画で、ニクソン政権末期からレーガン政権の頃にあたる。
最初にこの映画のあらすじを知った時に、トランプってあのロイ・コーンの薫陶を受けてたのか!と驚いた。コーンが赤狩りでマッカーシーの右腕として活躍?し、検事としてスパイ容疑を受けたローゼンバーグ夫妻を電気椅子送りにしたのは知ってたが、マッカーシー失脚後のコーンのことは全然知らなかった。他にもコーンの顧客としてマフィアのトニー・サレルノ、コーン邸のパーティーにメディア王ルパート・マードックやヤンキースのオーナーのスタインブレナー、名前こそ出てこないものの明らかにアンディ・ウォーホルなどが登場し、80年代のトランプのパーティーではトランプが画角の外にいる人物に向かって「アキオサン!」と呼びかける(たぶん盛田昭夫のことだろう)など、あの頃の時代の有名人がちょこちょこ出てくる。また良くも悪くも、というより悪くも悪くもやり手だったコーンがトランプに出し抜かれ、80年代にはエイズに罹患。“エイズ”というのもやはりあの頃の時代のものだ。ゲイでありながらそれを隠して同性愛者を苛烈に批判してきたコーンが、みるみる弱っていきエイズで死去する姿も描かれるが、たとえ悪党であってもやはりそこには哀れを誘うものがある。まさに70~80年代という“あの時代”のある側面が描かれた映画だ。面白かった。
それにしても映画を観て思ったんだけど、トランプは結局この頃のコーンの手法を今でも実践してるんだな。トランプが最初の奥さん(後に離婚)と付き合ってる時に、「世の中には2種類の人間がいる。“殺す側”と“負ける側”だ」「私のことも殺すの?」「“勝つ側”ってことさ」と言うシーンがあった。そして大統領になった今でも、彼にとって全ては“ディール”、つまり取り引きなんだろう。困ったもんだが。
トランプいっちょあがり!
ロイ・コーンのキャラがあまりに強烈で、序盤はトランプが食われ気味。
若かりし頃のトランプは少々頼りないが、
ロイから人を貶めてマウントを取る術を学び、
ラストでは、しっかりと尊大な今のトランプになっていて、ある意味安心した。
イヴァンカへのDV描写が怖い。現夫人は大丈夫なのだろうかと心配になる。
植毛手術をあえてグロテスクに、生々しく描いていたのは、
あの場面で“人間の心を失った”という演出だったのだろうか。
もしトランプ本人がこれを観たら、激怒するに違いない。
こうした映画を作る自由が守られているアメリカであってほしいと、改めて思う。
ウォールストリートの亡霊
こんなトランプに誰がした?
まさか当選するとは思わなかった…。
またしても初の女性大統領誕生ならず。
アメリカはよほど“アメリカ・ファースト”を掲げる傲慢男が好きなのか、それともただのバカなのか。
今年の一月から始まった第二次トランプ政権。
世界中の問題に世直しマンの如く乱入したり、世界中大混乱のトランプ関税…。早速、やりたい放題。
イランの核施設を爆撃した際、それを広島・長崎の原爆投下になぞらえて正当化しようとした発言にドン引き…。
少なくとも後3年半はコイツの独裁が続くのか…。
こんなトランプを誰が選んだ?
こんなトランプに誰がした?
それは若き頃、ある弁護士との出会い…。
1970年代。20代のドナルド・トランプは不動産王の父フレッドの下、実業家のキャリアをスタート。
が、父が政府に訴えられ、破産寸前。仕事も行き詰まり、父からも無能者扱いされ、崖っぷちにいた。
そんな時、財政界の大物が集う高級クラブで出会ったのが、弁護士ロイ・コーンだった…。
ロイ・コーン。本作を見るまで知らなかったが、超有名らしい。
たくさんの顧客を抱えるやり手。時のニクソン大統領とも親しく、財政界やマフィアのボスとも繋がりが。
裁判では負け知らず。勝つ為にはどんな手段も厭わない。
性格は鋭く、冷徹。無能、役立たず、価値ナシは容赦なく切り捨て。…
そう。有名なのはその悪名高さ。白を黒、黒を白にもする悪徳弁護士であった…!
初めて会った時もロイはトランプにシビアな態度。
圧倒的オーラに萎縮する若きトランプ。あのトランプが…!
トランプとて最初から“トランプ”ではなかった。最初はまあ一応、実業家としての成功を夢見る“普通”の青年だった。我々一般人から見れば、傲慢さや俺様はちらつくが…。
ロイのお眼鏡に適う人はそういない。
が、何故かトランプは気に入られ、その時抱えていた父の問題を強引な手腕であっさり解決。
ロイに心酔するトランプ。顧問弁護士になって貰う。
この若造が気に入ったロイ。たくさんの顧客の中でも特別な顧客に。
もしこれが成長株の若者とクリーンな弁護士だったらその出会いに感謝だが、悪徳弁護士と後の…。
ここから誕生してしまったのだ…。
とは言え、アンチ・サクセスストーリーとしては面白い。
ロイはトランプに、身の振る舞い、トーク、着る服まで指南。
さらに、“勝つ為の3つのルール”を伝授。
一つ、攻撃。
一つ、非を認めるな。
一つ、勝利を主張し続けろ。
若造を仕立て上げていく。
トランプを。プロデュース!
サバイバルな世界をタフに生き抜く為、言ってる事は分からなくもないが…、いずれも強引・横暴な事ばかり。時には違法も。
ある時、ロイは盗聴を。それを目撃し、違法じゃないのかと危惧するトランプにロイは、それがどうした?
ロイは堂々と、取るに足らん多少の法律など守る必要ない。
真実はいつも一つなんて妄想。真実はいつだってねじ曲げられる。某名探偵の信念を一蹴。
差別主義者。黒人嫌い。その他の人種も。
ロイの第一は、アメリカ。アメリカを愛している。アメリカこそ私の一番の顧客だ。アメリカの為なら何でもする。
移民への強固な姿勢。アメリカ・ファースト…。
トランプの思想にも影響を及ぼしていたとは…。
若き実業家とやり手の悪徳弁護士。鬼に金棒。ビジネス上のパートナー関係を超えた信頼と友情を育むが、その終わりは呆気なく早かった…。
すっかり時代の寵児となったトランプ。
豪華ホテル、トランプタワー、カジノ…。その飛ぶ鳥を落とす勢いは常に注目の的。
トランプも強気な言動。異を唱える者は皆敵。
あの平凡だった若者がNYの王に。まだまだ目指す。
政治家? 大統領? 興味無いね。
この頃からロイの助言を聞かなくなる。それほどの自信家になったという事でもあるが、理由はそれだけじゃない気がする。
薄々察しは付くが、ロイは同性愛者。男性パートナーがいる。
ある時、トランプは“その場”を目撃してしまう…。
80年代になり、エイズが流行。当時のエイズへの認識や理解の無さは言うまでもなく。
ロイのパートナーがエイズに。つまりはロイも…。
ロイが次第に衰弱。自身はガンだと言い張るが…。
これまでの違法行為により弁護士資格も剥奪。ロイは自分の事よりパートナーの為にトランプに助けを求めるが…。
トランプは恩を仇で返す仕打ち。
激昂するロイ。一蹴するトランプ。激しく言い合う二人。
信頼と友情の終わりはいとも簡単に…。
あんなにロイに教えを乞うていたトランプ。もう自分に必要無くなったら切り捨て。
そのやり口はまるで…。
そういう意味では、トランプはしっかりとロイの教えを身に付けたと言えよう。
ロイにとっては誤算。あのやり手ですら先を読めなかった。
可能性に満ち溢れた可愛かった若者が、想像を超えた大物…いや、“怪物”になるのを…。
トランプが失ったのはロイとの友情だけじゃない。
結婚なんて財産を損するだけだ…とロイに反対されながらも結婚したイヴァナ。
当初は愛に溢れていたが、トランプの身の振り方が尊大になると比例して愛は薄れ、妻に魅力も感じなくなり…。ある時などレイプ紛いの行為を。
家族。父、母、兄の存在。
かつては帝王のような父に従うだけだった。いつしか父を上回る実業家に。
父が認知症に。そんな父を利用しようとするが、気付いた母に止められる。
父に厳しくされた時も味方になってくれた母だが、この時ばかりは息子に怒り。
家族を襲った悲劇。一族の劣等者の兄。精神を病んだ果てに…。
ロイとの友情を失い、妻との愛を失い、家族との絆を失い…。
普通だったら孤独と破滅へ転落なのだが、その野心は留まる事を知らない。
何を失おうとも、どんなに憎まれようとも。
俺は、ドナルド・トランプだ。
鬼才アリ・アッバシの演出は妙なカタルシスを呼ぶ。
小難しい政治ドラマになったりせず、異様な高揚感。
テンポも良く見易く、お陰で全く飽きずに見れた。と言うか、思ってた以上に面白かった。
オスカーノミネートはサプライズと言われたセバスチャン・スタンとジェレミー・ストロングの熱演。いや、怪演。
あのウィンター・ソルジャーがトランプに…? セバスチャンはトランプに全く似てない。だってセバスチャン、イケメンだもん。ヘアメイクの力もあるが、それだけじゃない。平凡だった青年が凄みのある怪物=トランプに。その変貌ぶりはセバスチャンの演技力の賜物。
圧巻はジェレミー・ストロング。登場時から只者じゃない雰囲気。悪党と言われ続け、決してクリーンじゃなかったかもしれないが、いつだって自分に真っ直ぐだった。その姿は何処かカッコ良くもあった。それだけに、終盤の悲哀さは…。
良作で実力を発揮してきたストロングだが、本作で飛躍。遅咲きながらこれからクリストフ・ヴァルツやマーク・ライランスのように重宝されていくだろう。
長らく疎遠だったトランプとロイだが、久し振りに再会。あるパーティーに招く。
プレゼントを贈ったり、ロイを讃えたりして、まだ敬愛は失っていなかったと思うが…、
結局それはトランプの引き立て役でしかなかった。
私は負けたのだ。この男に。
程なくして、ロイはエイズで死去。トランプは葬儀に出席したりせず、ハゲ隠しや脂肪吸引の手術を。
ラストシーン。ある作家に勝利する為の3つのルールを説く。
恩を仇で返すどころではない。欲するもの、必要なものは全て自分のものに。俺様ファースト!
やがてトランプは本当にアメリカの頂点に。
崖っぷちにいた青年がアメリカ大統領になろうとは、ある意味アメリカン・ドリームである。
トランプ万歳!
いや、見れば分かる。本作はアンチ・トランプ映画である。
あからさまに批判はせず、そのサクセスや人間性も描いているが、こうしてトランプはトランプになった…と、警鐘と戦慄を感じる。
言うまでもなく、トランプ本人は本作に対して…。
こんなトランプに誰がした?
ロイと思うが、あくまで影響やきっかけ。
悪徳教えに自分でブレーキを踏む事だって出来た。
そうしなかったのは…。自分がそれを望んだから。
自分の中の野心と傲慢。なるべくしてなったのだ。
元々本人に備わっていた“天賦の才”なのかもしれない…。
困った事に。
勝つ事への執念と野心が凄い
テーマは明確「リーダーは人物で選べ」
長所をもっと見つけたかった
国を超え電波を通しても、トランプが嫌われやすい印象を与える人物像なことは感じ取れるが、作内でも存分に周囲の人物がトランプに感じるであろう不快感を味わえる。
不動産の家に産まれ裕福だが家賃滞納のような底辺生活層も目にして育った生い立ちが、クイーンズ出身から42丁目を制し5番街の人間かのように人生をのし上がるまでには、ロイコーンというトランプ父が抱えていた訴訟を引き受けてくれた敏腕弁護士がいた。
ロイコーンとその側近フレディが実はゲイでお互いにエイズにかかったと示唆されるが、肺炎だと話していたうちから、隔離しようとするトランプの性格はいささか礼節に欠くし、散々泣きついてのし上がるまで世話になったロイコーンに真鍮にジルコニアの安物カフスをトランプロゴ入りで渡せてしまう神経は理解し難い。
だが、製作者がトランプに中身の薄い紛い者という印象を持っているか、観る者にそう思わせたいのかなとも思った、
真偽のほどはわからないが、徐々に聞かん気傲慢になっていく作中のトランプは妙な薬のせいだと良いのだが、残念ながら違うだろう。
アメリカの国益を貪り食うジャップと作中で言われてしまった日本人感覚としては、トランプがアメリカの国益のために奮闘しているのはよくわかる。
でも、関税を叩きつけてきたトランプは私の中ではマリオパーティーのクッパそのものである。
妻に豊胸させた上プラスチックと罵ったり、
センスの悪い天然巨乳と不倫したり、
本当は育ちの良さを学んで育っていないのに、
本物への憧れが一際あるように思えた。
父の暴言から自信を持てず病んでいく兄への対応、
いつも要望を叶え忠告してくれたロイコーンへの態度、
トロフィーワイフではなく意思を持った綺麗な妻や子供をぞんざいに扱う点。
一流に相応しいとは思えなかったが、
自己資金で当選できる議員は日本では皆無に等しいので、野心ゆえのすごい部分は沢山あるのだろう。
青年期の素直に話す部分はまだ残っているのだろうか?
ロイ・コーンの"ラブ"ストーリ
『The Apprentice』(=「弟子、見習い」の意)というタイトルの通り、ドナルド・トランプと弁護士ロイ・コーンとの「師弟関係」が映画の主軸になる。ドナルド・トランプがホストも務めたアメリカ制作のリアリティ番組名と同じ名前なのも興味深い。
やはり他の方も書かれているようにキャスト陣がすごい。トランプを演じるセバスチャン・スタンは、毎朝トランプになるのに2時間かけたというメイクは似ているが、コメディ感がない。ロイ・コーンを演じるジェレミー・ストロングも本人同様一回見ると忘れられないような、あの目つきをよく掴んでいる。さすがゴールデングローブ賞に二人でノミネートされているだけある。
実際にロイ・コーンは、トランプのことを「親友」と呼んでいたそう。トランプに目が行きがちな今作だが、この複雑なロイ・コーンの立ち位置と苦悩を歪んだ愛情を通してうまく表現した、期待以上の良作だと思う。
バースデーのシーンのロイの「目」が忘れられない。
意外と奥行きのある人物描写でした
不動産業を営む父の会社で働く、何者でもなかったドナルド青年がドナルド・トランプとなるまでの十数年を描いた映画です。
本作で面白いなと思ったのが、野心的ではあるけれど所謂普通の青年であったドナルドが怪物的な性格を表していく迄を一直線で描いていないところです。
成功が人を慢心させるのは想像通りですが、望みのものを手に入れる度に傲慢になるモンスターの影に若き日の初々しさをを垣間見せるような感情の揺らぎが何度も指し挟まれることにより、ドナルド・トランプという人物に深い奥行きを与えています。
決して俺様だけな人物ではない、弱さもあり、葛藤を抱えた人間であると。
ドナルド・トランプを称賛しているのか、ディスっているのか、著名な人物を通して人間の複雑さを描こうとしているのか。
観る人により様々な受け取り方があると感じさせる作品でした。
全220件中、1~20件目を表示