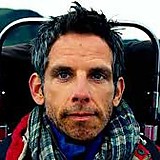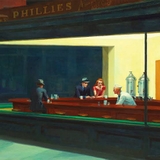国宝のレビュー・感想・評価
全1848件中、961~980件目を表示
感動はした
頑張ってたー
壮絶
男の色気
吉沢亮の宣材写真が色気あるのと、高畑充希が好きなので、どんな恋愛コンビになるかたのしみに観た。それと、評判よいので、3時間近い上映時間に躊躇したものの、後押しになった。
さて、吉沢亮はきれいなお顔で女役の歌舞伎には適役ですね。中性的な顔立ちだから、男のゴツゴツ感がないので、ピッタリ。横浜流星はNHK大河ドラマ並みの人の良さが滲みてていたものの、いいとこのお坊ちゃんという世間知らずなにありがちな無邪気な鈍感さが感じられないだけに、ちょっと物足りない感じもした(よく世間知ってる感じが出てしまっていた)。
それにしても、この二人の男優の掛け合いは色気あり、男気あり、恋愛あり(少しだけ吉沢亮と恋人とのベッドシーンもあり)で、見応えはあったかな。特に観客女性多いのは納得の内容でした。
但し、歌舞伎の映像シーンが長いので、冗長さがあったのは否めない。歌舞伎のシーンは圧倒されるとはいえど、それを観にきたわけではないので・・・。それよりも、もっとドロドロした主人公の生い立ち、男同士の葛藤、それをもっと深堀したシーンが欲しかった。任侠上がりの吉沢にもっとキレたら怖い感じのナイフのような危なさをもった感じたかった(ちょっと求めすぎですが・・・)。高畑充希は安定だったけど、森七菜はかわいらしくてちょっとしたベッドシーンもよかったです。
歌舞伎を包括的に描こうとし過ぎか、中途半端に感じた
この作品は、歌舞伎という芸そのものの奥深さや美しさ、習得の困難さだけではなく、その世界特有の慣例や習わしも描くなど包括的に描かれているが、それには歌舞伎の世界が深すぎるのか、どこか全体的に中途半端になってしまった印象である。
歌舞伎を鑑賞したことがない自分にとって、本作は歌舞伎の世界を垣間見るだけでなく、実際の生の歌舞伎を観ているような体験で、面白いと感じた。またその稽古シーンも、その道を極めしものだからこそ分かる所作の違いや感覚について描かれ、いかに奥深い世界かを分からせてくれる。
一方で、物語が展開するにつれて次第に飽きてきた部分もあり、それは歌舞伎の演目自体に飽きたのではなく、物語展開に飽きてしまったのかもしれない。例えば、喜久雄は任侠の一門として描く意味はなんだったのだろうか。この物語の一つの大きな要素として「歌舞伎の血筋ではない」ことからの排除があるが、であれば別に任侠の一門である必要はなく、前半に任侠シーンを挟んだ割にはそれが後半活かしてくるのは一瞬スキャンダルがあったくらいであまり意味があるように感じなかった。また、俊介が失踪したり復帰するあたりもなんか雑に感じてしまった。それでか、集中を保てず後半は時間が長く感じてしまった。個人的には歌舞伎の中でもテーマをもう少し絞って、芸の習得に絞るか、あるいその慣例慣わしに絞るか、したほうがより深い作品となったように感じる。
高評価すぎることがよくわからない‥
「血」か「芸」か。
魂が震える大傑作
圧巻の演舞
全てが見事
歌舞伎素人の
最後の光景
歌舞伎の悪魔と契約し歌舞伎の神が微笑む映画。簡単に言うと芸のためなら女房も泣かす🎵の歌の通りに生きたらこうなりますよって事かなぁ。最後の光景が見たくて歌舞伎の悪魔と契約したんでしょうが、一般ピープルの私がそんな事怖くてできるはずもなく、だからこそ最後の風景を見る主人公に共感するんでしょう。普通の人は見た事ないんですからね。
完全なる勝者や完遂者だけが見る世界。どうなんでしょうかねぇ。私はクーラーの効いた6畳の部屋でエヤコン温度を24度の微妙な温度に保ちながら、自分で作った麦茶をすすりながら安心安全に暮らしたいですね。
PS:少し考えを整理しているときに思った事。あの光の先、それはかつて父親の宴で演技を披露した時に戻るって事かも。最高点に達してみた風景は初心って事でしょう。
評判通り良い作品
一人の少年が才能を見出されて歌舞伎の世界に入り、頂点を極めるまでの人生を描いた作品。ちょっと長かったけど、途中でダレることはない。評判通り良い作品でした。
歌舞伎をしっかり観たことはないが面白そうだなと感じた。
吉沢亮、横浜流星、田中泯の演技が素晴らしかった。特に曾根崎心中のシーンは圧巻の演技でした。
世襲と聞くとネガティブな印象を受けるが、先祖代々受け継がれた芸が血筋に沁み込んでいるというのは、大一番に臨むときは大きな助けになる。その世界の中で生まれ育ち、物心ついた時から両親を含めて周りから自然に知識が入る環境というのは大切なことなのかも。
自由であるべきと思うが、特殊な世界の存在も肯定されるべきかな。
精進する、その美しさ。すべてを蹴散らして。
映画「国宝」を観てきました。ネットでの評判も、メディアの取り上げ方もすごくて、ちょっとそれに引っ張られたかな。もうネタバレで書いてもいいと思うけど、心理描写という意味ではちょっと物足りなかった。歌舞伎界という特殊な技能集団、世襲制が色濃く残る世界での主人公たちの葛藤と、取り巻く女性たちのそれぞれの生き様。難しく、切なかった。歌舞伎という芸の美しさがそれを増幅させる。
喜久雄は結局誰も信じていないし、誰も愛していないよね?その分、芸に愛されたかというとそうでもない。誰かを傷つけながら名声を勝ち取った、などといわれても彼に実感はないだろう。ただ次の高みを観たかったんだ。最後の彼が見た風景、それはゴールなんかじゃない。奇しくも人間国宝たるお手本、万菊がいるじゃないか。もっともっと先がある。それが無でも地獄でも、なんだっていいんです。それに魅入られたものだけが手にできる風景。精進するしかないんだよ。すべてを蹴散らして。
全1848件中、961~980件目を表示
映画チケットがいつでも1,500円!
詳細は遷移先をご確認ください。