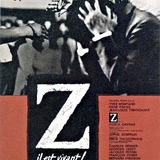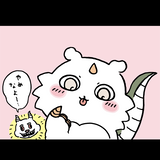国宝のレビュー・感想・評価
全2354件中、1101~1120件目を表示
歌舞伎という世界をしらなくても
鳥肌が立つシーンがたくさんありました。
およそ3時間。おそらく私が映画館で見た作品の中でいちばんの長時間だったとおもいますが、本当に魅せられる映画って時間感覚を狂わせますね。
閑古鳥が鳴くような食堂や宴会場で、余興の1部になり得るかも危ういほどに関心を持たれずにいる中で気丈に踊る姿、観客に揶揄混じりに性の的にされながら暴力を振るわれる姿、屋上での錯乱、そして泥に沈むようにして床に伏す姿……東一郎の転落の過程があまりにも痛々しくて、-0.5させていただきましたが、それも物語の大切な1部であることはわかります。
最後のステージの鷺娘で彼が見た景色と、冒頭で父が殺された時の景色。被るものがあったと思った時に、彼が歌舞伎に人生を捧げ、悪魔に魂を売ることは決まっていたのかもしれないと思いました。
私は歌舞伎に関しては全く知識がなく、多くを語るに足りない身ですが、ただただ人間が描く世界のうつくしさに圧巻しました。
良い映画に出会えて良かったです。
圧倒される3時間
冒頭のシーンから、ラストまで息つく暇を与えられず壮絶な人生を体験させられるような作品!
それは主役の人生だけではない。
ヤクザの親分としての死様を見せようとする父親。
高齢になり皺多き顔に化粧をして舞う人間国宝。
自分の息子よりも、芸によって内子に自分の代役、そして名前を継がせる男。
長崎からついてきたのに心折れた男を放っておけない女。
名前欲しさに抱かれ、最も辛い時を支えても報われない女。
芸者だからと日陰の人生を選んで耐えて生きた女と、最後にインタビュー時のカメラマンとして対峙する娘。
原作を読んでいないが、多分もっと様々な事が語られていたのであろう事は容易に分かる。
しかし、それをダイジェストのように感じさせず、多くを語らずともそこにそれぞれの人生があったのだと感じられる俳優達の演技の凄まじさ、脚本の素晴らしさ、それを撮り切った監督の手腕。
それら全てが静かに、だが圧倒的な力でスクリーンからほとばしっている。
そして、あまり語られないと思うが、特殊メイクが恐ろしくハイレベルだった。映画後半、3人が墓参りするシーン。それまでの人生が刻まれた顔が完璧に作られていた。
原作小説も読みたくなった。
美しく、グロテスク
冒頭から、どう話が展開していくんだろうと引き込まれました。まさか極道者が歌舞伎役者になる話とは露知らず。
歌舞伎のシーンはとても美しく、緊張感があり、それでいて夢心地で、役者さんたちの研鑽の賜物だと感激しました。舞台袖に捌けた瞬間に素に戻る描写で一緒に現実に帰ってきた心地がしました。
喜久雄と俊介。どちらも歌舞伎に、役者という人生に魅入られた二人ですが、他のすべてと引き換えにしても日本一の歌舞伎役者になりたいという喜久雄の狂気がこの作品の核であり、人間国宝にまでなる所以なのかと得心がいきました。それを象徴していたのが、喜久雄の周りの女性たちでしょうか。幸子や春江、藤駒や彰子のリアリティが、時にグロテスクに感じるほどで、なによりも歌舞伎を第一にしてしまう、その才能と実力のある喜久雄の狂気を引き立てていたように思います。
また、俊介との関係が最終的にはあの形で落ち着いたことがとても印象深く思います。互いに衝突しかけては茶化し、というシーンがありますが、隠しきれない本音と、感情的にはなりきれない大人らしい振る舞いが、子供の時分から大人に囲まれ大舞台に立つ歌舞伎の世界の特殊な環境で生きてきたことの証左に思えます。
決定的な衝突の後、ほぼ絶縁状態になりますが、その後時を経て曽根崎心中を二人で演じきる姿がとても心に残りました。
悪魔と契る
糖尿病怖い。
レビュー1000越え、すごいね。
上映から1ヶ月で50億、(鬼滅は3日で80億)平日でもなかなか良い席取れない。リピーター居ないとこうはならないね。朝日新聞に連載してた小説だそうだが未読です。
話もテンポも良い、わたしは歌舞伎に全く詳しくないけどぐいぐい引き摺り込まれました。歌舞伎関係者が見てどうなんだろう、一年位の特訓ではまあこんなところかなって感じなんだろうか?でも出演者かなり頑張ったことは間違いないだろう。
私は吉沢氏の映画は何本か見ていていつも
「少し美し過ぎるなぁ」という感想を持っていたのでこれは完全ハマり役だと思った。相方の横浜氏も頑張ってるし、子供時代の黒川、越山も美しくて眼福でありました。
田中泯エグい!指先だけで魅せる。
で寺島しのぶ来たー、わかる人だけわかれば良いキャスティング。
2人の友情を軸に血統と芸の世界の浮き沈みをがっつり3時間、全くうとうとせずに見れました。
こうやって頭整理して行くと歌舞伎や興行の暗黒部分はあまり深掘りしてないんだなと気づきますが、そこ行くと3時間時じゃ済まないんでしょうね。
最後瀧内さんのよいシーンで空腹でお腹が鳴ってしまった事が悔やまれます。
見応えがある難解な作品
おそらく上映時間内に収めるために心理描写などを原作から削ったためだと思われるが、登場人物がなぜそのような行動を取ったのかを理解しづらい場面がいくつかあった。
他の方が書いた解説やレビューなどを読むとある程度理解できるため自分の読解力が低いだけかもしれないが、3時間近い上映時間も相まって観終わった後に疲れを感じる作品だった。
俳優の演技や演出などは非常に優れているため、歌舞伎の知識を予習し、原作も読んだ後に再挑戦したい。
ドラマよりパフォーマンス
総じて高い評価を得ているようで、期待して見に行ったが、思ったほどではなかったというのが正直なところ。任侠の世界から歌舞伎の世界に飛び込み、女形として芸道を極めた男の一代記で、主人公喜久雄を演じている吉沢亮、ライバルとなる俊介役の横浜流星ともに、歌舞伎の所作・演技や舞踊に修練を積んでいることがうかがわれた。
ドラマとしては、血筋と才能のせめぎ合いが軸となるが、喜久雄が俊介を押しのけて『曽根崎心中』のお初役に、養父の花井半二郎(渡辺謙)に指名された時も、両者の能力の違いがそれほど分からず、単に半二郎にひいきされただけのようにしか見えない。その采配に落胆した俊介が、喜久雄の恋人であった春江(高畑充希)と十年間失踪してしてしまうが、春江の心が喜久雄から俊介に移った経緯がよく描かれず、失踪していた十年間を俊介たちがどう過ごしていたのかも分からない。
総じて「血筋(家)と才能」という構図を浮き立たせようとすると、両者の能力を差別化しなくてはならず、そうすると舞台上で二人が見せる芸が不調和なものになってしまうため、それができないというジレンマが全体を貫いているように思われた。主役級二人が見せる演技、舞踊は魅力的だが、ドラマよりもパフォーマンスを取るという選択がされているのは残念だった。
良作ではある。
他の人が論ってるネガティブな批評にいくつかは同じ感想を持った。万菊が鷺娘を舞ってる時の味付けの濃い演出や、ドサ回りの時のやっつけ感や酔っぱらいに絡まれるシーン、必然性の薄いカット割が多々見られるところなど、、
ただ、人間関係や心理描写が甘い、伝えたいことがわからないと言った意見が散見されるのだが、それは要所で演じられる演目自体のテーマが補ってるのではないだろうか。言うなれば勉強不足、表層しか見られない他人にとっては振り回されるような映画に映るだろう。
3時間と長い映画だが、2回目を見る機会があるのなら、出てきた演目のプロットを頭に入れて視聴するともっと立体的な見え方になるかもしれない。3時間の長編だが、気がつくと終わっててのめり込める映画体験だった。
冒頭で惹き込まれます…
新聞連載時に読んだだけだったので、細かい部分はスッカリ抜け落ちていたのですが、冒頭の新年会のシーンは強烈に印象に残っていました。そこがその時のイメージのまま映像になっていたことで、まずは引き込まれ、あとは3時間が夢のように過ぎてしまった…。恍惚とした思いとともに、映画館をでてきました。
代役を喜久雄にしたときの半二郎の判断は、俊介に失敗させたくない、という親心でもあったのではないか、と今になって思います。
また喜久雄と俊介の曽根崎心中の口上も、ただのライバルや義兄弟といった関係性をはるかに超えた2人が、芝居のために、この人とであれば共に命を懸けられる、という意味にもとれて、切なかったなぁ…。
エンタメ性だけを求めるなら、ブラックスワンみたいな描き方や終わらせ方だってあり得ただろうに、原作と歌舞伎文化への敬意を忘れず、ストーリーはリアルに、でも映像は様式美に満ちた作品に仕立てたことが、深みと充実した見応えの要因かと思います。
ありがとうございました!
国宝(映画の記憶2025/7/12)
人気の高い作品を観てきたわけですが、見ごたえは十分。映画なんだけど歌舞伎の舞台を観ているような感覚に襲われた。
吉沢亮がやばいね。長期間役作りしたってテレビで言ってたが、それだけのことはある。引き込まれる芝居ができているってことは役としては十分成立している。
当然本業からすればまだまだなんだろうけど。
越山さんは「ぼくのお日さま」以来やっぱいい役者になるなあの子。
映画の時間は3時間と結構な大作だが、何かドラマの一気見した感覚くらいな程度だった。割と重厚な作りだから、人によっては耐えられない人もいそう。
まぁヒットするわっていうストーリーと作りなんでこういうのが嫌いじゃない人にはおすすめできる作品。
(個人的評価7点/10点中)
血か才能か…相克の大河ドラマ
通常スクリーンで鑑賞。
原作は未読。
私の主義としてだが、原作有りの映画で、原作を読むならばきちんと読了してから映画を観に行くことにしている。
先に映画を観て、結末を知ってしまったら、原作を読む気が失せてしまうと、自身の性格的に分かっているからだ。
本を読むスピードは遅い方だし、映像化されていれば当然そちらの方が早い。わざわざ文字で読むのが億劫になる。
だが今回は例外。原作を読んでいる途中だが、話題になっているので居ても立っても居られず映画館へ足を運んだ。
すっかり前置きが長くなってしまった。
芸を極めることの美しさ、醜さ、そして儚さを、血か才能かの50年に及ぶ相克を軸に描き出す、圧巻の大河ドラマ。
只管に夢を追い、人生を駆け抜けた喜久雄と俊介を演じた吉沢亮と横浜流星の名演に魅せられ続ける174分だった。
鑑賞後の興奮がなかなか冷めない。役者たちの渾身の演技に心を鷲掴みにされた。まるで名演の博覧会状態である。
吉沢亮と横浜流星の、女形の所作の素晴らしさと言ったらない。肉体の動きの靭やかさ、艶めいた仕草に魅せられた。
上下巻800ページ近くの原作を約3時間に落とし込もうとすれば、かなりの換骨奪胎を要しただろうと想像する。
観に行った時点で上巻を100ページほど読んでいたが、そこまででも様々な要素が削られていることに気づいた。
早速、原作を読むことを再開しようと思う。映画の内容を補完しながらの読書体験になりそうでワクワクしている。
国宝
評判通り
覇王別姫っぽい?
原作を読んでないけど、なんか、全体に早送りみたいな印象でした。
ただ、3時間あるなんて知らずにふらっと観てしまい、
最後の1時間トイレに行きたいのを我慢していたせいで、
終盤の間を味わえなかったのが残念。
なんか、覇王別姫っぽいなぁと思ったのですが、
京劇と歌舞伎が脳内でリンクしただけかも。
あと、原作では細かく書いてあるのでしょうが
主役二人の関係性が謎のままで、モヤってます。
そんな心理状態になる???って違和感しかわかなかった。
役者に関しては、吉沢亮と横浜流星の顔の区別がつかなくて、
かなり集中してないとどっちがどっちかわからなくなり混乱。
渡辺謙が異常にうまそうに茶漬け食ってたせいで
帰宅後に茶漬け食いました。
寺島しのぶの本物感(いや本物なんだけど)が圧倒的すぎて、
もはや笑いそうになりました。
総評: 175分ってわかってたらきっと観なかった。知らなくてよかった。
才能と血筋との葛藤
仲良しの間柄でも、実の親からは、血筋よりも才能を選ばれ、疎まれた息子はしばらく離れるが、世間は血筋を重視した。実話であったとしても、おかしくない内容である。お互いに辛酸を嘗める時期を経て、共演に到る。血筋のある息子は、不摂生が祟って、義足をつけることになるが、そこでも圧巻の演技をする。複数の監修つきでもある。全体の演技指導も、中村鴈治郎氏の賜である。
吉沢亮さんの大粒の涙の綺麗なことよ
核となるエピソードが私にはわかりやすく、サクサク進み、登場人物は少なく悪い人もいないため、観やすい大作だと思いました。
主人公が、初めて花井の家に来た時の緊張感の無い様子と、裏腹な挨拶のしっかりした様で、彼が目の前で見た父の死以上に感じ入れるものは無いと分かります。その後の彼の全ての行動の原因が「親」です。
そして主人公は、花井親子の連獅子を見て、芸に寄って親子というものが存在できると知るわけです。一生懸命やった先に、「親」がいるかもしれない。
親子のような関係にやっとなれたと感じる瞬間がやってきたと思ったら、それが、突然粉々に崩れ、彼は本当の孤児になります。自分が受け取ったものに縋り付き、その全てを見透かす万菊により救われ、花井親子の血としか思えない行動の連鎖を受け止め、血を分けた様な馴染みの子供に稽古をつけ、傷つけてきた本当の娘から、悪魔との契約である芸を認められてやっと、主人公は父親の死の瞬間以上の景色を見ることができたわけです。
結局、彼らを揺り動かしてきたものは、親子という血と、努力できる才能という血だ。という物語だと私は受け取りました。
なによりも、これを完成させるために、俳優たちがしたであろう想像も及ばぬ努力、あっぱれです!!!吉沢亮の大粒の涙と、横浜流星のまつ毛と、田中泯さんのあの瞳、素晴らしかったです!!
海老様の暴行事件
全2354件中、1101~1120件目を表示
映画チケットがいつでも1,500円!
詳細は遷移先をご確認ください。