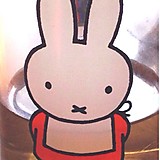国宝のレビュー・感想・評価
全2354件中、961~980件目を表示
国宝級の面白さ。
完成された芸は観るものを圧倒し感動を生むが、軽率な笑いは生まない。だからTVでは沢山笑いを作るために素人芸が溢れている。今こそ舞台で歌舞伎を観て完成された本物の芸を知りたいと思った。
この「国宝」という映画はもちろん日本の誇れる映画だが、それで終わらず、もっと深く芸能に触れる良いきっかけにもなる映画であると思う。
「日本一の歌舞伎役者になりたい」と喜久雄は願うが、その承認欲求さえなければ狂気の苦しみから逃れ、観客の側になれるのに、観客になれれば楽になれるのに。僕なんかそう思ってしまう。
人間国宝になるような人はこんな辛い景色やクライマックスの美しい景色、僕が見たことのない景色を見ているのだと感慨深かった。
約3時間という長編映画であったが時間を気にすることは1度もなかった。引き込まれ続けて、気がつくと映画は終わっていた。
とにかく素晴らしい作品だった。絶対DVD買います。10回観ます。11回は観ません。
人生うまくいかない
後半が駆け足すぎてもったいない
映像の美しさ、音楽の調和、俳優さんの素晴らしいお芝居と、どれもすばらしく、レイトショーで睡魔との闘いに負けないかとの懸念は全く不要だった3時間でした。
ただ2点だけ、どうしても気になったこと。
破門同然で一門を去った喜久雄は、どうしてあんなにあっさりと、表舞台に復帰出来たのか?
血筋と才能をめぐる喜久雄と俊介の確執や、芸に対する執念がこの映画の主題だと感じていたので、そこをもっと丁寧に描いて欲しかったなーと思いました。
そもそも175分の長尺映画ですし、もう少し長くなったとしても、その辺りの描写で説得力を持たせてくれても構わないのに…と感じました。
そしてもう1点。喜久雄にかかわる女性たちの描き方が雑に感じました。
春江と藤駒に関しては、身の処し方にまだ納得できるところがあったものの、彰子に関しては、愛のない駆け落ちであることをわかった上での隠遁生活を支える辛さや、忍耐が限界を迎える様の描き方に納得感が得られず…。
喜久雄が表舞台に戻るためには、彰子が父親に頭を下げたり、関係者に根回しをしたり、それこそ「血」を活かした働きがあったんじゃないかしら?と、勝手に想像したので、余計にかわいそうに思いました。
ともあれ、役者さんの細かな表情の動きや息遣いなどが感じられ、映画だからこそできる歌舞伎の描き方は、新しい世界を開いた感がありました。
文句なしに「凄い映画」だが…
俳優陣の鬼気迫る熱演や、計算し尽くされたカメラワークや画づくりなど、見応えは十分な作品。
特に主演の吉沢亮は、その整った顔貌と、どこか感情が読みにくい瞳の印象も相まって、キャリア最大の当たり役と言えるであろう主人公の喜久雄を見事に演じ切っていた。
一方で、物語としては非常に類型的な成功譚の形をとっているためか新鮮味に欠け、終盤の挫折から再起への流れにはかなり唐突感がある(人智を超えた力が働いた、という表現なのかもしれないが)など、正直あまり面白みを感じられないものだった。
また、話の軸の一つとなっている血筋にまつわる葛藤と軋轢についても、人物と舞台設定が整った時点で想像できる範疇のもので、特に意外性はなかった。
3時間ほどの作品を飽きずに最後まで見せきるだけの熱量と力をもった「凄い映画」ではあるのだが、個人的には傑作には一歩及ばない良作に留まってしまったというのが正直な印象。
国宝とは
横顔がとくに綺麗
前半少しだったのに永瀬正敏さん印象的でした。
芸姑さんの色気も心に残りました。
しゅんぼうは喜久雄をいじめちゃうの?とおもい、排他的なところを見る辛さを覚悟してしまってたのですが、そんなことなくてその点良かったです。
春江は彼女なりの理由があるんでしょうけど、したたかで黒く見えてしまいましたが…入れ墨ほるとき一緒にいるって言ってたのに…
テレビに3人家族で映ったとき奥さん然でドヤって語っておられて…いや、奥さんなんだけど…寺島しのぶさんの横にも普通に座ってるし…いや奥さんなんですけど…でも何その切り替え…わたしには無理で解せなかったです。
渡辺謙さんの晩年のやつれ具合は違和感なく、対して喜久雄は近年になったときの見た目の違和感を大きく感じました。体型もなにか入れてどうにかできなかったのかな(してたのかな?)。綺麗な顔は邪魔も邪魔、て、こういうことなのかな、とそのとき少し思いましたが
綺麗なしゅんぼうと喜久雄の、歌舞伎の演技を充分な時間堪能できて良かったです。
映画の魅力が詰まった素晴らしいエンターテイメント作品
この景色を見せたかったのか…
『国宝』すごかった。
歌舞伎に人生を捧げた二人の青年、喜久雄と俊介の青春と対立、そして美の本質を描き出す壮大な芸道ドラマ。
冒頭、雪景色の中で父を失う少年・喜久雄。その父はヤクザの親分で、少年の人生はこのときからすでに“常識の外側“にあった。
血のつながりはないが、兄弟のように育った俊介とともに、二人は舞台の世界へと身を投じていく。
他の同級生たちが部活や恋愛に明け暮れる中、喜久雄と俊介だけはただひたすらに歌舞伎の世界に生きる。その姿はまさに青春であり、舞台稽古や川辺での語らい、橋の上でのやりとりが胸を打つ。
二人が語る、伝説の役者・万菊の「鷺娘」を見たときのセリフが印象的。
「こんなんもん、ただの化物やで」
「たしかに化物や。せやけど美しい化物やで」
この“美しい化物“という言葉は、物語全体を象徴している。芸の力は、常人には届かぬ狂気すらはらむ。その果てに、舞台の神が降りる。
師である花井半次郎は、俊介に「お前には血がある」、喜久雄に「お前には芸がある」と語る。
そして自らが舞台に立てなくなったとき、代役に選んだのは、血を分けた息子ではなく、芸を選んだ喜久雄。その瞬間から、二人の運命は狂い始めていく。
俊介は「すべて奪い去る気か」と叫びながらも冗談だと言う。喜久雄の才能と人柄を知っているがゆえに、恨みきれない。
喜久雄も苦悩する。上演前に震えながら言います。
「幕上がると思ったら、震えが止まらんねん……お前の“血”がほしい」
その後の舞台で、喜久雄は圧巻の演技を見せるが、俊介はその場を去る。
終盤、俊介は再び舞台に戻り、『曽根崎心中』で共演します。
俊介の脚は壊死し、二人の時間はもう戻らない。喜久雄は心中してもいいと言う――それは“芸”と“血”、二つの道を極めようとした者たちの、痛ましくも美しい結末。
喜久雄は人間国宝に。
「鷺娘」に挑みます。
舞台で雪が舞い散るなか、それは父が亡くなった瞬間、万菊の神々しい演技とも重なる。
この景色を見せるためにこの映画はあった…。圧倒されました…。
日本文化と人生
自分には響かなかった...
俳優陣の演技や、ここまでトレーニングしてきたことは本当にすごいと思いました。この点に関しては文句なしで星5つ。相当な努力があったんだろうな、と感じます。
ただ、ストーリーや全体の構成は正直星1つ…。観終わった直後、どうして自分には全然ハマらなかったんだろう?といろいろ考えてしまいました。。。
まず、歌舞伎のシーンがとにかく長い。最近だとティモシー・シャラメがボブ・ディランを演じた映画でも、ストーリーより歌ってる時間が長すぎて気になったけど、それと似た感覚。ミュージカル映画だったら、歌やダンスでストーリーが進んでいくけど、今回はそういう流れも感じられず、歌舞伎が物語と直接つながっていないこともある
監督の作風として、抽象的で役者の表現を活かすタイプだとは思うんですが、歌舞伎が多くちょっと集中力が切れてしまいました
少ない中でセリフは過激な発言が多いのに、肝心のストーリー自体はかなり薄い気がします。国宝?というところが最後までピンと来ませんでした。作中での、主人公の圧倒的な才能をどう感じ取るのか難しかったです
終盤で年をとるが、特殊メイクがあまり自然じゃなくて、ちょっと気になりました
スクリーンで観るべし
吉沢亮の顔がキレイ
期待ほどじゃない
間違いなく生涯の中で心に残る作品
あっという間の3時間でした。
まずは吉沢亮さんと横浜流星さんの素晴らしさ。
それぞれの立場の違いと背景が舞踊に表れている。
そしてこれを軸に出演していらっしゃるすべての方々がまた凄いの一言だった。
中でも特に、田中泯さんと高畑充希さんと三浦貴大さん。
田中泯さんの手と足と目線の演技とそれを捉えるカメラワーク。
高畑充希さんの一見流されてしまいそうに見えるのに芯の強さを感じさせる演技。
要所要所で効く三浦貴大さんの存在感。
どれも物語の語られない部分の多くを理解させてくれました。
映像の美しさと主題歌の歌詞もとても良かった。
この世はあまねく二律背反。
それが最期に溶け合うのか、そうか。
原作未読で1回目を観て、原作を読んで2回目を観ましたが、あの原作をここに昇華した監督と脚本家の素晴らしさに震えました。
好き嫌いはあれど映画館で見る価値はあり。
私にとっては原作、映画、どちらも納得の作品で間違いなく生涯の殿堂入りです。
和製、覇王別姫。歌舞伎が観たくなる!
公開が落ち着いて空いてきたら観ようと思ってたら、まさかの尻上がりで人気上昇中の本作。
上映時間の長さもあり、連休中に観なくてはと一念発起し、レイトショーなら空いてるだろうと思ってたら、これまたまさかの満席御礼。なるほど、終電で来て始発で帰る気か(笑)
高評価の作品ほど事前情報はなるべく排除して観るようにしてるのですが、なるほど、さすが李相日監督。長尺を感じさせない見事な演出。歌舞伎は若者にとっては退屈と思われかねないものをアップや、汗や、静寂、荘厳な音楽で全く飽きさせない。
伝統芸能、ブラザーフッド、、、観ながら、覇王別姫を思い出した。なるほど、やはり意識されてたのですね。特に屋上のシーン。
こんな素晴らしい映画を作ってくれたのが、在日3世の李相日監督。日本人より日本を上手く描いてくれている。こじつけかもしれないが、奇しくも参院選の日でもあり、色々と思うところがあった。
全2354件中、961~980件目を表示
映画チケットがいつでも1,500円!
詳細は遷移先をご確認ください。