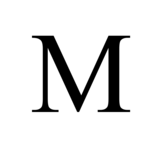国宝のレビュー・感想・評価
全2339件中、41~60件目を表示
嫁が…
『邦画の興業収入歴代1位だって。 観た方が良いのかな?』
と言うので、個人的に興味はそれほど無かったが鑑賞。
結論的に言えば、まぁ良かった。
が、それほどヒットする作品なのか?
万人受けする踊る大捜査線が1位だったのは納得出来る。
しかし、この作品は観る人を選ぶ映画だと思う。
マスコミが持ち上げまくりで、伸びてるのかなぁ。
別にダメな作品では無いんですよ。
むしろ良い映画だとは思う。
おそらく稽古もそうとうな時間をかけてやったのでしょう。
この映画に出演している人達は評価されるべきだと思うし。
でも人にはオススメはしないかな。
ちょっと重めの話でスッキリするワケでは無いしね。
高畑充希はなぜ裏切った?
そこが意味ワカラン。
エンドロールがスゲー短いのが良かった。
洋画もこのくらい短いと良いんだけどね。
新記録になるのは間違いない映画でした
会社の上司から、日本人なら絶対に観ておくべき映画でしょ❗️と言われ…アクション映画、SF映画好きの俺としては、間違いなく眠くなる邦画だろうと…睡魔覚悟で邦画興行収入新記録映画🎬
【国宝】
鑑賞しました
「血」と「才」
「陰」と「陽」
「表」と「裏」
相対する二人の演者の鬼気迫る歌舞伎の熱演に度肝を抜かれました
眠たくなる事も、トイレに行きたくなる事も…全くなく、あっという間に3時間が過ぎてしまった…
これなら、確かに新記録になるのは間違いない
主役を演じた、吉沢亮さん、横浜流星さん…マジで凄いです
糖尿病って怖えーー!
すっごいよかった!
面白かった!
感情を揺さぶられて泣いたもん!
この映画、非常に評判良いでしょ?
大体そう言う映画って往々にして面白くないのよねー
でもね、この映画は違ったわ!めっちゃ良かった!
感情も揺さぶってきたし半端じゃない面白さだった!
大衆に迎合することを是としない私が良いと思ったから間違いなく良い!!
糖尿病で2人ほど死ぬけど、病って怖いね
目見えなくなって血吐いたり、四肢を切断したり演者としては致命傷だね
結局芸事の世界は血なんかね?先代が亡くなったら外様は、すぐに冷遇されるわ
世襲の嫌なところ大衆の嫌なところコミュニティの嫌なところ欲張りセットで楽しめたわ!
ほんとな、そりゃ1番欲しいのは血だわな
芸なんか身を助けんのんやな、狭きコミュニティは血であり伝統なんよな
あー老害どもめ!
上映3時間なので飽きたりするかなって思ったけどそんなことはなかったぜ!
頭からケツまで面白かった!飽きなかった!3時間退屈しなかった!
歌舞伎の演目は、はっきり言って退屈だったけど面白った!シュン坊が片足失ってからの「曽根崎心中」は本当に気持ちが乗ってて良かった!
物語前半で気持ちが乗ってないとか演技指導が入っていたが、物語後半でそれらを踏襲した気持ちのノリが入っていて良かったし!
足首にしがみつくキクちゃんの感情が分かりにわかって涙した!
シュン坊の足は汚い!糖尿病に侵され腐った足は見苦しい!しかし美しい!演目上のコノ一点においては堪らなく美しい!演技上この足にしがみつく!!
なんと烏滸がましいことかッ!
病を推して演じるシュン坊!
残り、変色し、いくばくもないことを悟らせるには十分な片足を見、それに演技とはいえ縋らなければまならぬキクちゃん!
キクちゃんの気持ち、シュン坊の気持ち、考えれば考えるほど泣いてしまった
「曽根崎心中」のセリフ、一挙手一投足が全て積み重ねてきた年月を思い望郷に至る
当たり前だ!こちらは上映時間の半分以上は見ているのだ、思いもひとしおである
「死ぬる覚悟が聞きたい」人としての死、演者としての死、差し迫ったシュン坊の情念が乗った良い芝居だった!
国宝!ただの伝統芸能アゲ映画じゃなかった!
本当に良い映画だった
------------
若干、キクちゃんの復帰からの展開が急すぎて冷めた、人間国宝の推挙からの復帰早すぎて若干の置いてけぼりだった。喜ばしくはあるが!
最終的に凄く泣いて、面白かったけど、この世界血だよね
芸とか関係ない!後ろ盾、血筋で決まってんだよね。
歌舞伎界、伝統芸能のクソさを感じたけど国宝という作品は素晴らしいものだった!
是非とも逆張りの諸君にも広く掲示してもらいたい!!!
俳優陣は素晴らしい
自分には刺さらないけど
ずっと楽しみにしてたので公開初日に行きました今さらレビューです
見た時の感想は、そりゃ役者や美術が良すぎるので
よかった!とは思いましたが、ここまで流行ると思いませんでした
だってこの話めちゃくちゃわかりにくいし…話ガンガン飛ぶし…
でもこんな分かりにくい映画をたくさんの人が面白いと言っている、この社会は好きです
海外でディズニー映画の実写化が叩かれる時に
「ほぼCGじゃねーかどこが実写なんだよ!」
という意見があるらしいんですね
そういう意味では、これから実写映画というのは
いかにCGを使わず生身の映像・パフォーマンスを作り上げられるか、というのが大事になるのかなと思います
その文脈で、国宝は海外でもウケるのかなーなんて
とは言え倫理的にどうかと思うところもありますし、世界でどう評価されるのかこれから楽しみです
文化を越えた先に彼が見た景色とは…。
伝統や芸能と聞くと皆さんはどういった事を思い浮かべるだろうか?比較的若年層であれば、「堅苦しいもの」や「難解なもの」という捉え方が多いのではないか。
「歌舞伎」とは4世紀ほどの歴史を経て、庶民演劇としては最古の歴史をもつ日本文化の宝である。かく言う私も歌舞伎にはあまり馴染みのない部分も多いが、純粋に面白いと感じ、3時間弱という最近の映画の中ではそこそこ長い上映時間でも飽きることなく、非常に満足度の高い作品であった。
寧ろ、上下巻の原作をよく3時間ほどであそこまで上手にまとめられたものだなと感心さえした程である。
物語の基本はもちろん、歌舞伎を追い求めた男の行く末とは…的な部分が主軸だが、その中にも役者がその歌舞伎という夢に対してがむしゃらに喰らい付いていく部分の中に、愛憎の縺れ、人間関係の汚さなど、歌舞伎以外の面での面白さもあり、単なるエンターテインメントを超えたドキュメンタリーチックな部分もある。なので、歌舞伎にあまり触れたことのない人にも観て頂きたいのである。
とある場面で三友の社員の「竹野」が「歌舞伎はどうせ世襲だ」と言う場面があるのだが、素人の私も歌舞伎を世襲であり、どうせ血がものを言うものなのだ、と思っていた節があるので、そんな中でも一人必死に喰らい付く、「喜久雄」の様には感涙した。
もう一つ面白い?不思議?と感じたのは、人間は「美」というものに対して、自分が感じられる以上の「美」を目にしたとき、なぜか「怖い」という感情が芽生え、人が出せる限度を越えた「美」というものの恐ろしさを体感し、不思議な感覚に陥った。正に「喜久雄」、「俊介」が言っていた通り、「美しい化け物」であると私も思った。
私は原作→映画と入ったので、もし原作、映画どちらも目にしたいのであれば、順序は映画→原作の方がおすすめだなと個人的には思った。もちろんどちらの順序でもこの作品の面白さは感じられるが、原作の方は「喜久雄」と「俊介」の闇の中での模索を詳細に書かれているので、映画を観賞した後に原作を見ることで更に二人の歌舞伎に対する思いの丈を感じ取れるだろう。
映像綺麗だった。 歌舞伎には誠実でありながら、 歌舞伎以外には不誠...
やっと観た、たしかに凄いといえば凄い映画だけどあまり好きな作品ではない、そして尿意問題と途中休憩について
混んだ映画館は大の苦手なので鑑賞を見合わせていたのだけれど、やっと観ることができた。それでもいまだに混んでいた。この「ブーム」いつまで続くのか?
というわけで、おそるべき大ヒット作『国宝』。
結論からいうと、僕はこのお話があまり好きではないです。
「たしかに凄いな、10年に一本の映画かもしれないな」――序盤から中盤までは、そう思って観ていた。ストーリーの設定も面白い。流れるような展開でテンポもよい。緊張感もある。そして、何といっても作品に力がある、凄みがある。あれよあれよという間にスクリーンの中に引き込まれていった。「これだけ評判になる理由もわかるなぁ」。そう思った。
けれども、喜久雄が三代目を襲名するあたりから、なんだかちょっとしんどくなってきた。中だるみした。そしてその後も前半に感じたような高揚感の持続を味わうことはできなかった。その理由は、僕が単純にこのお話が好きではないとわかったからだった。全体を通して最後まで観ると、物語の筋立てがいささか俗っぽく安易であるような気もした。さらにいうと、ストーリーだけでなく、本作のトーンというかムードというか、そういったものも僕はあまり好きになれなかった。それは気持ちが作品に引き込まれていた前半から「違和感」という形でうっすらと感じていたが、後半に至って明確に自覚できた。そして、前半に感じた「なるほど、これだけ評判になる理由もわかるなぁ」という思いは、観終わってみると「果たして、これだけ評判になるほどの作品なのだろうか?」という感想に変わっていた。そんなわけで、強く感動を覚えることはなかったし、もう一度観たいとも思わなかった。たしかに凄いといえば凄い作品だけど、どうなのかなぁ? みんな本当に感動してるのかなぁ? まあ自分とは相性が合わない作品だったのでしょう。
それにしても、このごろ、こういう3時間、あるいはそれ以上の上映時間を要する映画(以下、「長時間作品」とする)が多くなってきて困ります。僕も中年になって、おしっこの心配をすることが増えてきたからです。じつは今回も途中から尿意を催してきて集中力が低下しました。歳とるとロクなことないですね。
ボンタンアメや大福餅が有効かどうかは知らないけど、僕は尿意対策として体が冷えない格好をして映画館に出かけるようにしています。水分を控えていっても、体が冷えると、交感神経が刺激されて尿意を催しやすくなるので。それでも今回のように尿意とのたたかいをしないといけないときがあるから難儀します。
そんなわけで、僕はいいたい、訴えたい! できるだけ長時間作品には10分くらいの途中休憩をつくってほしい、と。制作者サイドからすると、はじめから終わりまでいっぺんに見せたいという思いもあるだろうけど、この高齢化社会、やっぱり長時間作品には休憩があったほうがいいのではないでしょうか(『ベン・ハー』『マイ・フェア・レディ』『ゴッドファーザーPARTⅡ』……この数年のあいだに観た映画だけど、全部インターミッションがあって有り難かった)。
今回の『国宝』鑑賞でも中高年の観客が多かった、というか、観客のほとんどが中高年だったのではないか。おしっこの心配をしながら鑑賞した人も少なくないはずです。
映画のつくり手は、途中休憩によって作品への没入感が途切れるのではないかなどと危惧するかもしれないけれど、長時間、尿意とたたかいながら観ているほうがよほど集中力がそがれて没入できない。そもそも人間の集中力が3時間も続くわけはないのだ。ちょっと気分転換を入れたほうが絶対にいいと思う。リフレッシュして再びスクリーンに臨んだほうがより集中できると思います。是非、映画関係者の皆さんにご検討いただきたい問題です。
――とはいうものの、本作のような超人気作、大勢の観客が入る映画では、インターミッションをつくったとしてもトイレが混んで(とくに女性トイレは混むでしょうね)10分や15分の休憩では済まないかもしれないなぁ。なかなか悩ましい問題だなぁ。
なんか『国宝』の感想より、おしっこ問題についての記述のほうが長くなっちゃいました。ごめんなさい。
追記
途中から尿意のために集中力が低下した状態、つまり作品をじゅうぶんに玩味できていなかったかもしれない状態で鑑賞してネガティブな感想を書くのは何だか良くないような気がしましたが、あまり好きな映画ではないということははっきりしているので、このままレビューを投稿します。
なにを描きたかったのだろう
中盤辺りまでは物語として追えていたが、終盤にさしかかるにつれブツ切りエピソードが並び、非常に退屈。
途中で帰りたくなる映画を観たのは久しぶり。
映像と役者の演技は良いのだけど、それ以外はもう、、、。
この作品がここまで話題になってる理由は、プロモーションによるものだと強く感じる。
まさに国宝
俳優陣みんな素晴らしかったが特に印象に残ったのが、万菊(田中泯さん)と彰子(森七菜さん)の2人。
万菊さんは、とにかく恐ろしい。全てを見透かしているかのような、まさに人間国宝の貫禄。「憎くて仕方ないんでしょう、でもそれでいいの、それでもやるの」は映画史に残る名ゼリフだと思う。
そして、鑑賞後もずっと心に残ったのは彰子。喜久雄が落ちぶれた時のあのやさぐれた若女将感。森七菜さんこんな演技もできる方なのかと感動。
彰子が報われるシーンがあればよかったのにとも思ったが、ないからこそ、描かれなかった部分にも思いを馳せ、国宝という作品がずっと心に残るに至ったのかもしれない。
『国宝』を観て、「綺麗」という言葉での表現よりは「美」を強く感じま...
『国宝』を観て、「綺麗」という言葉での表現よりは「美」を強く感じました。
歌舞伎の世界に受け継がれてきた血筋や世襲の重み、
その宿命を抱えながら舞台に立つ姿は、芸能という枠を超えた生き様を感じました。
伝統に縛られる苦しさと、それでも芸を守り続ける誇りに感銘を受けました。
3時間という時間があっという間にすぎる作品でした。
日本人は流される人が多い印象
テレビでもこういうところでも高評価が多いですが、見た感想としては本当に?と思いました。多分世間での評価が高いから流されている人が多いんじゃないかなという印象です。
作った話の割には共感できるところがなかなかなかったです。
これは主役二人のファンが高評価にしてるとか、歌舞伎界が持ち上げたいとか、マスコミが持ち上げたいか…
何かわかりませんがそういうものしか感じませんでした。
確かに長期間に渡っていろんな下準備をして出した作品なのでしょうけど、いくら昔の話とはいえ今の時代に作ったものとしてはストーリーがよくないし、イケメンだからといって女形がきれいな訳ではないし、いろんなところにお金がかかってはいるんでしょうけど、お金がかかっている=作品として素晴らしい訳ではないと思います。
一番は私にはストーリーが合わなかったです。
いいもの見させてもらったな
全2339件中、41~60件目を表示
映画チケットがいつでも1,500円!
詳細は遷移先をご確認ください。