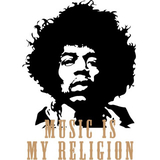国宝のレビュー・感想・評価
全2341件中、221~240件目を表示
なんの予備知識もなく、 とりあえずそんなに流行ってるなら どんだけ...
なんの予備知識もなく、
とりあえずそんなに流行ってるなら
どんだけすごいのか?
と、鑑賞。
そんなわたしでも、長さを感じないで最後まで
楽しめたのでよかったです。
ちゃんと作ってるなー
役者ってすごいなー
とか思いました。
好みのジャンルではなくても、
ちゃんと作られた映画は、やっぱいいですね!
吉沢亮さんの本気で神作になった
国宝級イケメン投票1位の吉沢亮さんが本気で歌舞伎の世界に飛び込んだら、梨園の御曹司も真っ青の看板役者になるかもね、女形なんかさせたら綺麗だろうなあ……と思った人がいたかどうかは知りませんが、すばらしい作品でした。
米国アカデミー賞にも日本から出品することが決まったそうで、日本国内の映画の賞は総ナメにするだろうと言われています。
この作品は製作陣の映画作りの基本姿勢がまず違っていました。この作品はちゃんと「映画」として、大画面で見てもらう前提で画面が設計されていて、背景の細かいところまで丁寧にこだわりをもって作られていました。撮影もすばらしかったし、役者さんもすばらしかったです。ストーリー展開もすばらしかったし、編集もすばらしかったです。そこに、日本が誇る伝統の歌舞伎が培ってきた舞台芸術の耽美的な世界が加わって、これは米国アカデミー賞に出品されるのは納得です。
曽根崎心中は歌舞伎の舞台で観たことありますが、本作に出てくる曽根崎心中は感動してしまって、ひたすらに「すごい!」としびれてしまいました。二人の気持ちが入っていて、すごかった。
歌舞伎見たいなあ。吉沢亮さんと横浜流星さんで「滝沢歌舞伎」みたいなイベント興行をやってくれないかなあ…。ブルーレイ買って、リピートしてみたい作品でした。
シンプルに観ないと損
特別な理由やこだわりが無いのなら、是非映画館で観てほしい作品。大満足。
歌舞伎に馴染みがないとか演目や用語がわからないとか、三時間長いとかその程度の理由なら、じゃあとにかく観た方が良い。
血がある血がないという重要テーマがあるが、主人公に流れている血とは冒頭の亡き父のものであり、主人公が生涯通して見たかった景色とは雪の中で散った父の姿(もしくは父が見たであろう最期の景色)かと思う。彼は命をかけて「見得を切り」その生き様を息子に残してくれた。
からっぽの喜久雄が、芸をどんどん吸収して成長していく一方で実は周りの人の幸福をどんどん食べて最強のモンスターになっていく様子が恐ろしくて美しい。格が違う、吸い取られる、とでも直感したのか早々に離れていく春江の本能が素晴らしいし、そこに空いた穴にタイミング良くはまるような弱った俊介の演技が良かった。
ストーリーに口を出すのは論外だけど俊介を女方にしたのはお父ちゃん正しかったのかな?と思ったりもする。役者さんの骨格が男性ぽいから余計に、最初から立役/女方だったら運命は違っていたのかなとifを妄想したくもなった。(化粧した顔が、吉沢亮のつるっとしたフェイスラインが完璧すぎるものの対照的に笑顔を見せて愛嬌で勝負する横浜流星も可愛かったけども)
人間国宝万菊さんは出てくるだけで空気が冷えるような、でも主人公達に温かい重要な役。他ジャンルの方らしいですが、目線、手招き、何と言っても台詞まわしというか語尾の調子?が素晴らしかった。骨の髄まで女方が染み付いたみたいな演技が凄い。
ストーリー的には竹野という男がなんだかんだ見届け人という感じで良いキャラだった。
ところで落語心中という別作品が好きで、構図がよく似た話だなと思ったので、国宝の原作と共にそちらも再履修したくなった。
長いが良い
そういうことか
テレビ協賛なしだから作れたのかも
全てが美しい
3時間の長尺の映画でしたがあっという間でした。むしろ尺が足らないぐらい。
吉沢亮さんと横浜流星さんの演技が素晴らしく、歌舞伎に詳しくない人間でも食い入るように魅入りました。
嫉妬、才覚、大切な人達との離別や死、一人の人間の人生を描ききった本作に胸を打たれ涙しました。忘れられない映画がまた一つ増えました。
惜しいのが話が急に飛ぶのでこの間の話もっと見たかったんだけど??ということが度々あったのと吉沢亮さんの老けメイクがあまりにも拙かったのでもう少し上手く出来なかったのかとツッコミを入れてしまいたくなった部分ですね(笑)あと出てくる女性陣みんな同じような顔なので見分けがつかない!!!そういう所も御愛嬌という事で。
円盤化したらディレクターズカットのような形で補完してくださると嬉しいなと思います。
公開して5日後に観に行きましたが、その時点ですでに評価が高かったの...
なんかすごい感じだった
原作読んでないので誰のせいかわからないですけど、ストーリーはちょっとぐだぐだかな・・・
でも見ててなんかすごい・・・と思えた。だてに130億を超えないよな、みたいな。自分的には何度も見たいタイプの映画ではないけどリピートする人がいるのもわかる。朝9時半の回だったけど、客層が若もんから老人までめちゃ広かった!
自分的には導入部の15分くらい?が一番刺さったな。吉沢亮の少年時代の子が出てくる場面がほんと衝撃的に・・・なんだろ。かっこいいとゆーかきれいとゆうか。これからどんな話が展開するんだろ?みたいなわくわく感。渡辺謙と一緒に、え?何これ?いったい誰?みたいなリアクションしちゃうよなー。
本物の歌舞伎を見てみたくなる
役者の皆様の素晴らしさ
いやー、3時間長いよなぁと思いながら見始めましたが結論から言うともちろん飽きる事なく、最後まで熱狂して観させて頂きました!
原作は未読なので、所々解釈が難しいところもありますが、役者の皆様の演技が素晴らしいこと、この上ないです
主演の吉沢亮さんの演技がもうほんとに素晴らしいです
吉沢亮さんが、代役として選ばれたときの渡辺謙さんとの稽古からの舞台の演技はもうほんとに必見です
そして、大御所の渡辺謙さんも言わずもがなの素晴らしさだし、しょっぱなに出演されている映画「怪物」にも出演されていた黒川想矢さんも素晴らしい!
田中泯さんも迫力があるし、こういう良い映画にはやはり役者さんの素晴らしさがあってこそですね
ご自宅で観られるのも良いですが、ぜひ映画館で観られる事をお勧めします!
芸術!!
1ヶ月前以上に観に行ったこの作品。
見応えという言葉では足りないくらいの重厚感のある作品でした。
3時間はあっという間!ではなく、しっかりズシンとくる3時間に感じました。
まず、歌舞伎役者が本業ではない主演のお二人が、映画として世に出せるまでの努力をされたことが目で伝わってくるようでした。
言葉が見つかりませんが、汗と血と涙が本当に感じられる作品に思いました。
歌舞伎を今まで見たことがありませんでしたが、この映画をきっかけに興味が湧きました。作品名がテロップでも写し出されていて、きっと知識があればもっと楽しめたんだろうなと思います。
映画によって日本の文化を広くひろめる、興味を持ってもらうことに、文化継承のための価値を感じました。
渡辺謙さんの食事中のシーン、ご飯をかき込むところやため息をつく間合いなど、本当に何気ない仕草が日常そのままで、それを当たり前に表現するのってすごいなあと思いました。
画面は本当に美しく、作品全体が一つの芸術作品に思いました。
映画館で見ることができてよかったです。
やっぱりすごかった
自分の趣味には合わないかなー、と思って見ずにいましたが、あまりに評判がいいので見てみることにしました。結果、やっぱりこれだけ評価が高いのも納得の素晴らしい作品でした。
最初からぐいぐい引き込まれ、緊張が途切れることなくラストまで見られました。
原作、脚本、キャスト、演出、どれをとっても一級品だと思います。邦画にもまだこれだけいい作品が生まれる土壌があるんだと希望が持てるような作品でした。
以下、雑多な感想を。
・あれだけ名声を築いてからあんなに浮き沈みするものか?
・喜久雄がキレて俊介を殴るシーンの緊迫感はすごかった。
・少女時代と大人になってからの春江を別の人物だと誤解したまま見終えてしまった。
・見上愛がかわいかった。
・原作読んでみたい!
・歌舞伎見てみたい! できれば京都の南座で!
飽きることなく面白い 音響に迫力
3時間飽きる間が全くなかった。少し始まったところでアメリカ映画のセッションようなテーマかなと思ったらやはりそうだと思った。芸術を極める人は魂を売る。
映画館で観たが故に歌舞伎の伴奏に迫力り。物語は同じ母として寺島しのぶに感情移入。とにかく役者も衣装も何もかも豪華で贅沢な3時間でした。ストーリーは映画だけでは説明不足的な箇所が多い。さらっとしてる。故に凄い映画なのは感じるが物語的な余韻が殆どない不思議さ。他の映画だと暫く考えたりするけぢこれは特に考えない。 一番知りたいのはお爺さん国宝が最後ドヤガイの宿屋のようなところにいたこと。それは小説で補えばよいかと。小説まで読んで完成かな。長い小説を上手く3時間でまとめた脚本家もすごい。 小説だと音も衣装も分からないのでまずは映画館で観るべき一品。
演技力が凄すぎて3時間があっという間でした…‼︎
何度見ても同じように新鮮で、もう一度見たくなる
何度見ても同じように新鮮で、もう一度見たくなる。
初めて見たときは喜久雄の絶望的なまでの孤独を感じて怖くなった。
2回目に見た時は、ここまで歌舞伎という芸能が今に残っていることに深く感慨を覚えた。
そして今回、我ながら不思議なことに「舞台の上では男ばっかりだな」と思ってしまった。
これは長い歴史がそうさせたもの。
舞台の表だけではないシーンを見て、芸だけに邁進できる環境はこれしかないのか、と思わずにいられなかった。
曽根崎心中の舞台で喜久雄と俊介が舞台で支えあうのも、男女ではあり得ない光景のように思えた。
友情というよりはとにかく芸、芸、芸、それだけが伝わって空恐ろしい気持ちになった。
また、舞台の外では軽やかながらも生きている人間らしいずっしりとした重量感をもつ喜久雄や俊介が、舞では人外のような存在になっていることもまたこの世界の恐ろしさと凄みを体感した。
歌舞伎の演技は良いが、どれだけ年を取っても大学生臭
年老いた母がどうしても見たいというので、一緒に連れて行った。親孝行になったなと思いながら。
皆さんがおっしゃってるように、いち役者がここまで歌舞伎の演技に情熱を持って取り組んでいる、この演技は圧巻だった。
ただ、それ以外の通常のシーンで、どれだけ年を取っても若すぎて、リアリティがなくなる。特に主人公のライバルが、チャラチャラした大学生みたいな雰囲気をずっと引きずっていて、歌舞伎以外のシーンで冷める。そういうキャラクターだから、と言えなくもないが、どれだけ軽めの性格でも、さすがに年齢を重ねて、あの年代まで行けば、それなりの重厚感が出てくるはず。そこまでを求めるのは酷なんだろうか。邦画によくあることだと思うが。
年齢を重ねた人たちの演技をよりリアリティを持って演じれるようになれば、最高点にまで行くのかなと思った。
まあ、でもこれだけの人たちを映画館に連れてきて、映画文化がすごく栄えている邦画として、とても魅力的だとは思います。
全2341件中、221~240件目を表示
映画チケットがいつでも1,500円!
詳細は遷移先をご確認ください。