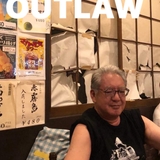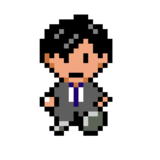国宝のレビュー・感想・評価
全2343件中、201~220件目を表示
歌舞伎を観たいと思わされる作品
とにかく出てくる俳優さんの圧倒的な存在感、演技が素晴らしかったと思う。特にメインのお2人の歌舞伎の部分、素人目に観てもどれだけ努力されたのかと思わされる。壊死した足を撫でる場面が心中へと向かうところも胸に刺さった。舞台には魔物が住んでいるのだろう。様々なものを捨てても掴んだラストも悲しみと共に救いもあった。内容的にも、このラストは現実にはありえないと思うと、これが歌舞伎界ではどう受け取られるのだろう?と興味深い内容だった。ただ、あくまでも好みの話をするならば、青年時代の2人の役者さんもとても良かったので、もっと青年時代の2人の歌舞伎での成長や2人の取り組み方の違いが分かりやすく表現されてほしかったし、歌舞伎に取り憑かれる様がもっとドラマチックに表現されてほしかった。2人の栄光と挫折の繰り返しも、ちょっと長く感じた。でもこれは私の好みの話で、この作品を観るならばテレビやスマホの画面ではなく映画館で観るべき映画だと思う。
間違いなくアカデミー賞級
3時間
良かった点
①人間国宝の爺の「芸に身を捧げてきた人間らしい異質さ」
②歌舞伎の演出の華麗さ、見たことない人間にも伝わる魅力
悪かった点
①ともかく冗長な暴力シーン、色気シーン(男性の裸含む)
②前半あれほど語られてた努力の要素がどこかへ消えた、呆気ない主人公の復活
③周囲の人物が舞台装置と化すご都合主義、特に隠し子に最後あれを言わすのは尊厳の否定に等しい
④「芸に身を捧げた」割には凄みを感じない主人公
作りがTVドラマの拡張版に過ぎず、作り手のこだわりや思い入れが微塵も感じられない無味乾燥な出来上がり。
取捨選択をできなかった結果が3時間という長さに過ぎず、これで絶賛してる人はマトモな「お話」を観てこなかったのだろなと。
観客が、
・若い男の裸を見たい女性
・分かりやすい劇を摂取したい高齢者
に偏ってたのも、当然の帰結かと。
是非映画館で観よう!
優れた映画の原点は尺に無駄がない事に尽きる。無駄がなくしてこの長さ。圧巻である。
この映画の醍醐味はカメラにある。構成は3つ。舞台、日常、そして映画である。私たちはこの監督にまず映画として切り取られた画面を見せられることになる。即ち非日常である。さらにその先にはそこで描かれた日常と、さらにその奥にはそれを超えた天上の舞台が描かれる。その天上の舞台の景色が恐ろしい迄にエロティックである。この画面の切り取りに胸がときめかぬ者がいたら教えて欲しい位である。ほとんど何も見せない切り取りの連続、時にインサートされるズームアウトのショットに一瞬気を取られるもすぐさま演者の目の前に引き戻される。汗が飛び息遣いが目の前で聞こえる・・・さながら猫じゃらしで弄ばれる猫よろしく、李監督のカメラワークに興奮のるつぼの中その視線は引きずり回される。この監督の凄さは日常がキチンと日常として描ける点にある。それが故に今回の作品のように天上の世界へいざなわれた時のトリップ感が半端ない。俳優陣の凄みのある演技は勿論であるが、それだけではどんな俳優を使おうともあの天上感は生まれない。何しろ描かれているものは国宝への道である。「国宝」とは何か?彼岸と此岸の架け橋である。神々が御住まう世界との身体の接点である。登場人物の二人は高校一年の時に醜くバケモノの住むこの世のものとは思えぬ美しい世界に触れるのである。触れたが最後血筋と芸に彩られた国宝への箱舟は歌舞伎と大衆演芸のふたつの道程を、魂を悪魔に売り渡してでも歩むものと、血筋の圧力と才の欠落に追い込まれながらも、病に果てる死に際に見た鬼畜の演技で袋小路を抜けるもの・・・この二つの対立軸に前者にゲーテの📖ファウストを、後者にダンテの📖神曲を見る思いがしたのは私だけであろうか?血筋に保証さえされていたならば見る事が出来たであろう神の恩寵の世界・・それを持たぬ者は全てをなげうちありとあらゆる醜悪な世界を渡り切ったその先に初めて目にする事の出来る世界、またそれを共に見るものをいざないスクリーンと言う世界で追体験する天上世界・・・これこそが「国宝」であると言わんばかりの演技と映像美・・・これはもはや病み付きの世界、この世のものとは思えぬ世界、これこそが多くのリピーターを生み出す原動力なのであろう。
映像の美しさを表現する為の切り取られ捨て去られたカメラアングルの他にもう一つの仕掛けの躍動に身も心も持って行かれるのもこの作品の魅力のひとつである。普段歌舞伎の舞台では見る事の出来ぬ二人演者のお題目の数々、そこで繰り広げられるユニゾンの妙。本作品ではこの若い二人のユニゾン演技を芸道の『共鳴・対立・融合の象徴』として使われている。そう、いわゆる芸事の成長プロセスの原理「序・破・離」である。そしてユニゾンとジョハリ(もしくはジョハキュウ)と来たら思い出されるものこそ🎦エヴァンゲリオンである。庵野は🎦シン・ゴジラにも狂言の立ち回りを取り入れるなど、数々の日本的精神要素をその作品に盛り込み、やもすると海外のファンからは難解すぎるとの評も多くあるが、フィヒテの「正・反・合」の概念もその作品には多く盛り込まれており、あらかじめ用意された真実への道しるべとまだ見ぬ世界の新たなる創造への道、この二つが見事に盛り込まれた庵野作品にも通じる所があるのではないだろうか?いずれも見たい世界、見ようとする世界、まだ見ぬ真実と歓喜の世界へ少年と少女、人間とクローンなどの対立の浄化をテーマとして誘う物語。それぞれの到達点こそ違うとはいえ、その最後の描写に人間の持つ身体性への到達・・それこそが究極の答えとして提示された点で高い共通性を見出す事が出来るのである。天上の世界に到達した人間の持つ身体性、現実を突き抜けた先にある天上界での象徴性。本作品の「国宝」というタイトルに込められた真の解釈こそがこの作品を唯一無二物へと押し上げている。
光と闇
ほんの少しだけ不満
期待しすぎた
前評判がすごかった。友達からみたほうがいいよと言われて、遅ればせながら見に行ってみた。
期待しすぎて評価が下がってたらごめんなさい。
前半、子役のときはドキドキした。演技もストーリーも、ああきっと素晴らしい3時間になると思った。いや、大人になっても演技はうまかった。映像も美しかった。
それはそう。それはそうなんだけど…
なにやろ、すごく長いところと、突然話が切れてよくわからない所、歌舞伎の演技シーンはとても大切にしてるけど、恋愛系とか、3つともどこでどうなったかさっぱりわからないとか。
その割には、ドサ回りのところとか、そこそんなに時間割く?と感じたりとか。
他の人の評価にもあったけど、歌舞伎シーンがやたら長くて、頑張ってるけど本物でもないのになと少し冷めた気分になることも。
私だけ感性がバグってるの?て思ったけど、一緒に行った友達も同じ評価で。
実話ならちょっとのタラタラは仕方ないなと調べたら、実話でもなかったし。
いや、演技も映像も良かったんだけど
私にはこのあまりにもすごい評判が、ちょっと謎です。
美と狂気の狭間で、芝居の本質を問う
歌舞伎の美しさに魅了されながらも、その裏側に潜む「芝居というものの本質」に触れたとき、観客はただ美に酔うだけではいられなくなる。『映画国宝』は、伝統芸能の荘厳さと、その背後にある人間の業をあぶり出す、極めて挑戦的な作品だ。
本作は、国宝という称号を持つ芸術の価値を、ただ讃えるのではなく、「それは本当に価値あるものなのか?」という根源的な問いを突きつけてくる。観客は、舞台の華やかさに目を奪われながらも、次第にその奥に潜むおどろおどろしい世界に引き込まれていく。
芝居とは何か。演じるとは何か。美とは、狂気と紙一重なのか。
この映画は、そうした問いを観る者に突きつける。そして、答えを提示するのではなく、「あなたはどう思うか?」と静かに問いかけてくる。
歌舞伎の美しさは確かにある。だが、その裏側にある人間の欲望、執念、そして孤独に触れたとき、私はただ怖かった。
この「怖さ」は、単なるホラー的な恐怖ではない。人間の深層に触れてしまったときの、言葉にならない震えである。芝居の世界に生きる者たちの、演技と現実の境界が曖昧になる瞬間。そこにこそ、芸術の本質があるのかもしれない。
『映画国宝』は、芸術を讃える映画ではなく、芸術を問い直す映画だ。美しさに酔いしれるだけではなく、その裏にある「人間の闇」に向き合う覚悟が、観客に求められる。
血筋と才能に翻弄される歌舞伎役者の生き様
鑑賞中、思わず腕組みをしてしまった。高評価とは異なる印象に違和感を覚え、“どんな作品にも良いところがある”という視点に戻って鑑賞を続けた。
本作は、歌舞伎役者の波乱万丈の半生を描いた話題作である。淡々として静かな大人味の作風を貫いている。歌舞伎のシーンが絢爛豪華であり監督の歌舞伎に対する畏敬の念が伝わってくる。
本作の主人公は裏社会に関わる父を持つ立花喜久雄(吉沢亮)。父が亡くなって、喜久雄の歌舞伎役者としての才能を見抜いた上方歌舞伎役者・花井半次郎(渡辺謙)に引き取られ、息子の俊介(横浜流星)と親友、ライバルとして厳しい歌舞伎修行に励んでいく。ある日、けがをした半次郎が代役に喜久雄を抜擢したことで、彼の人生は大きく動き出す。
喜久雄と俊介は半次郎の後継者争いで険悪な関係になりそうだがそうはならない。俊介は血筋重視、喜久雄は才能重視。二人の価値観の違いが対立ではなく相互補完関係を生み、互いの修行の糧になったと推察できる。喜久雄の抜擢に俊介の母親も反対するが、迫力不足だったのは彼女も舞台で喜久雄の才能を見抜いていたからだろう。喜久雄の抜擢で、既に後継者は決まった。半次郎は血筋ではなく才能の継承を取った。半次郎という名跡、更には歌舞伎界の今後の発展のために。
歌舞伎シーンのカメラアングルが出色。舞台裏、役者の背後から撮ることで、観客がその場にいるかのような臨場感に圧倒される。喜久雄と俊介の出番は、最初は踊りだけだが、次第に台詞が多いシーンが増え二人の表情が美しくなっていく。歌舞伎役者の世界には演技美という言葉が相応しい。型のなかに情熱を宿し観客の心を揺さぶる美しさがある。
映画俳優の世界も同様。吉沢亮、横浜流星は完璧に歌舞伎役者に成り切っていた。二人には映画俳優の天賦の才があると感じた。二人が更に精進し唯一無二の存在になった時、映画界は新たな“国宝”を創り出すだろう。
一回観てスッキリ分かる作品も良いが本作の様に何回か観て新しい発見がある作品には観客との対話がある。
修羅の道は、人を捨ててようやくスタートライン。
■まだ見てない君へ
感想以降はネタバレなので見ないよう。
気になるよな。分かる。
この映画の人気レビューは結構当てになるよ。
それ見て行く気になったら見に行くと良い。
あと病んでる君。
見に行くな。そういう時に見ていい映画じゃない。
もし病んでる状態で見に行きたいなら、一つだけ。
この映画から何かを得ようとするんじゃない。
いってらっしゃい。
■前置き
前から噂だけは聞いていた国宝。
ついに見た。
正直、女形の役に取り憑かれて、自分の人生も女形に引っ張られるとかいう安直な物語を想像していたのだが、安直なのは私の方だったらしい。
■感想
見る前から長そうだなという印象はあったが、実際はそれ程長く感じられなかった、なんて感想が多く見受けられる。
個人的には、後半はもう少し畳み掛けても良かった様な気がする。
飽きたとかではなく、
「半二郎が自身の代役に俊介ではなく喜久雄を指名し、演目が始まるまで」
がピークに見え、その後は落ちて上がるの繰り返しの「一般人の日常」を見せられている気分にさせられたのだ。
何か一つの人生の終わり、死後の世界を見せられているような感覚。その感覚が何とも遣る瀬無かった。
また、後半の「喜久雄のサイコ感」が、役者特有の異質な物ではなく、そこら中に転がっている無気力な若者達が持つ様な、「浅はかなサイコ感」であったのも、後半に魅力を感じなかった要因の一つである。
これに関しては、同じ人間なんだから、そらそうやろ、と言われればそれまでなのだが、「プロの役者」に、得も言われぬ様なカリスマ性を求めてしまう感覚は、皆にも理解出来るのではないだろうか。
次に肝心の歌舞伎。
歌舞伎に関しては何も知らない。知識で言えば本当に一般人以下だ。
その上で、感じ取れるだけの物を得ようとして、2シーンだけ響いたものがあった。
一つ目は、化け物爺さんの演目。
そこかよ、と、浅はかに思われるだろうか。安心して欲しい。恐怖を感じさせようと音楽が流れ始めてからの演技ではない。むしろそこらは全然顔が映らなかったのでガッカリした。
注目したのは、演目の始まりの部分。
何の調味料も無い状態の爺さんに、鳥肌が立った。
人生で始めて、ちょっとだけ思わされた。
「妖か?」と。
あのお爺さんは誰なのだろう。歌舞伎を全く知らないが凄い人なのだろうか。無名の役者だったとしても、あの演技にはとても引き込まれた。この際、名声の有無はどうでもいい。
ただ素晴らしい、と思った。
二つ目は分かりやすい。
半二郎の病室での一幕。
自身をビンタした後の喜久雄の演技だ。
分かりやすくこちらに響かせようと演出してきて腹が立って、「響かんぞ」と構えていたが、あれは見事だった。
何と言っても目だ、鼻だ、口先だ、顎先だ。
そして、声だ。
あれは素晴らしい。
.....ただ他の演目は響かなかった。
客の中には喜久雄の演目中にすすり泣く方もいたが、私にはその感覚がイマイチ分からなかった。
「我が子が沢山努力や苦労を上で、形にしようと頑張る姿に泣けた」とかそういう感覚なんだろうか。
ならまだ理解は出来る。
「演目中の役者の姿に自分を投影して」とかだったら、すまないが普通に腹が立つ。おこがましい。
彼の歩んだ人生は誰にも歩めないし、それ故に誰も彼の人生を参考にする事は出来ない。
強いて言うなら、覚悟を決め過ぎると、人生どうなるのか、
覚悟という言葉を、我々がどれ程浅はかに浪費してきたのか、
それらは何となく学び取れるだろう。
修羅の道は、人を捨ててようやくスタートライン。
そんな事を感じさせられる作品だった。
■総評
国宝がいて、歌舞伎があった。
ただ、そこに人はいなかった。
あくまで、彼は国宝なのだ。
人ではなく国宝なのだ。
あくま、で。
■自由欄
外行きの感想はこれ位にして、後は浅はかに行くとしよう。
まず、雰囲気だ。
いいじゃないか。とても好きだ。やはり昭和中期あたりのセットは大好きだ。
そして歌舞伎。
こんなにも感情が読めるものなのか。正直舐めていた。
映画の内容抜きにして、歌舞伎がとても好きになった。
必ず見に行こう。あわよくばレビューしよう。
良い映画だった。
良い三時間だった。
邦画で過去一の作品
目標を達成するには何らかの犠牲を払う必要があるという話
原作、監督ともにドロドロした人間ドラマをきっちり見せてくれる作風で期待して観に行きました。
ドラマパートはさすがの出来ですし、歌舞伎パートも二人歌舞伎のシンクロが特に素晴らしかった。今年の日本アカデミー賞の大本命ですね。
普段、歌舞伎になじみがない方でも多くの方が感じられたように、歌舞伎の素晴らしさを伝える力作でした。
特に高校生の喜久雄が初めて本物の歌舞伎に触れた時のキラキラした眼。歌舞伎のここが凄い!ってシーンと交互にみせるシーン切り替えの所が最高でした。
この時、国宝を演じる田中泯さんの鬼神のような舞い。この方、クラシックバレエからモダンダンサーの出自の方なので歌舞伎はおそらく80才で初挑戦じゃないですか?一芸を極めた方だけが到達できる山の頂きをみせていただいたようで本当に震えました。
ストーリーラインが夢を現実にするには代償を払う必要があるという全世界共通の流れですし、日本独自の歌舞伎を扱ったコンテンツということで、海外にも響きやすいとは思いましたが、独特の家父長制や、女性に対する扱いは国内だと理解は得られそうですが、海外だと違和感あるのか気になるところです。
あと、この映画の内容ならエンディングロールは無音の方がキマッたんじゃないですかね。静かに余韻を味わいたかったです。高齢の方も多く、集中力が途切れたのか暗い中退席する方が多く危なかったですよ。
3時間上映の長丁場だけど映画館で見たほうがいい!
原作は同名の小説を下にしたもの。
ちなみに読んではいない。
あと歌舞伎にも詳しくはない!(笑)
ロングラン上映を聞きつけてやっと足を運んだ!
大作だね!正直、上映時間としては長いのだろうが、
見てみるとそんな長さを感じることを忘れるくらい、
心に残る・心に刺さる作品だった。
出来ることなら、映画館で観ることをオススメする。
まぁ、どんなにつまらない作品でも映画館で観ないと、
正当な評価はできないと思ってるのであるが!
衝撃的シーンはいくつがあるが、あえて1つだけに絞るなら、
田中泯さん演じる小野川万菊が鷺娘を演じてるシーンだ!
主人公たち(吉沢亮・横浜流星)が高校生の頃に観劇して、
主人公が歌舞伎にのめり込むことになったところだ。
既に人間国宝となっていてお爺さんに近い役どころなのに、
妖艶に踊り切る姿が印象的だった。
もちろん、吉沢亮・横浜流星・師匠の渡辺謙も
相当訓練したのであろう。
素人目には、歌舞伎役者ってこんなんだろうなと
思わせる程度には演じていたのだと思う。
もちろん、詳しい人の厳しい視点で見れば、
ツッコミどころはあるのかもしれないが、
大抵の人にとっては十分なのではないだろうか?
波乱アリのサクセスストーリーは、
最近多い波乱なしのサクセスストーリーに比べて、
見応えがあるな!と思った。
森七菜演じる彰子はどうなった?とか、
気になる点もあるけど!(笑)
ここのコメントにPROが6人も投稿してるのも
注目度が高い作品なのだろう。
森七菜・高畑充希・見上愛など、今を彩る女優が
出演しているのも個人的には👍️な感覚だ。
血筋についての考察
公開4ヶ月、遅ればせながら鑑賞。
興行収入はついに150億円を突破し、邦画実写映画では「踊る大捜査線THE MOVIE2レインボーブリッジを閉鎖せよ!」に迫る勢い。とはいえ邦画のベスト10はすべてアニメーション映画で、アニメの幅広い世代のマーケットには敵わない。
これだけヒットしているということは誰が観ても面白い=大衆的な映画で、観るものによって評価が異なるエッジが効いた作品が好みなのが、遅ればせながらの理由。
また、上下巻の長編小説をいかに3時間にまとめたのかを確認したかったのも鑑賞理由の一つだ。
李相日監督は原作の登場人物をバッサリ省略し、喜久雄(吉沢亮)と俊介(横浜流星)を中心とした歌舞伎の世界と舞台シーンをじっくり観せることで大成功していた。
小説の欠点は歌舞伎の世界を描きながら実際の舞台の歌舞伎は見せられないこと。逆に映画の利点は映像として歌舞伎を見せられる事だ。この最大の利点を活かし映画化したことがこの映画が幅広い世代に受けた理由であろう。
任侠出身でありながらその才能を見出され歌舞伎スターに駆け上がる喜久雄と歌舞伎の血筋でスターになるのが当然であった俊介の一世代にわたる葛藤を3時間で描き切るのは相当難しかったはずだ。
実際、喜久雄の恋人であった春江が俊介と逃亡し戻ってきてからの後半は駆け足で、俊介がなぜ歌舞伎の世界に戻れたのか、春江がなぜ俊介と一緒になったのかは唐突で、疑問に感じるのではないか。
任侠出身の喜久雄が保守的な伝統芸能の世界でもがき苦しみながら国宝にまで上り詰める人生が物語のテーマであるはずだが、エンタメ作品としてそこが薄くなったのが、分かってはいるが残念。
雪
全2343件中、201~220件目を表示
映画チケットがいつでも1,500円!
詳細は遷移先をご確認ください。