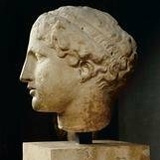ぼくのお日さまのレビュー・感想・評価
全272件中、21~40件目を表示
ほろ苦くてすっぱい
いろんな雪景色と、
日光の差し込むリンクで
音無く滑る2人のスケートが
印象的だった
きっと、この監督は
雪景色とスケートの美しさを知っていて
それを撮りたいのだなと思った
性的マイノリティに対する偏見が
あんな若い女の子の心の中にも
入り込んでいて
人間には
自分の知っている多数派が当たり前で
そこから外れている少数派を
おかしいと感じる性質が
きっとあるのだろう
最後にタクヤがさくらに
言おうとした言葉は
何だったんだろう
「あ・あ・あ・・・・・」
あから始まる言葉
会いたかった
会えてうれしい
見終わると
レモンを皮ごと
かじったような後味がした
お日さまの光
話題性だけのコミックやTVドラマの映画化、アニメーションばかりヒットする昨今の日本映画だが、まだまだこんなにもピュアな作品が生まれる。
これが長編2作目、デビュー作『僕はイエス様が嫌い』でいきなり注目された俊英・奥山大史の確かな才。主演二人の初々しさ。それらの賜物。美しい白銀の世界が拍車をかける。
しかし、ただピュアなだけじゃない。
優しさ、温もり、愛おしさの中にも、ピュア故の切なさ、残酷さ…。
それがまた胸に染み入る。
北国の雪深い田舎町。
吃音症のアイスホッケー少年・タクヤはフィギュアスケートをする少女・さくらに心を奪われる。
一人で不器用に滑っていた所をさくらのコーチ・荒川が気に掛け、個人レッスンを受けるように。
少しずつ上達し、やがてペアを組むまでにもなり、さくらとの距離も縮まるが…。
フィギュアスケートを通して描かれる少年少女の淡い恋。氷上版『小さな恋のメロディ』。
そこにコーチも加わり、三者の交流が紡がれていく。
情報や説明過多の作品が氾濫する昨今、話の方も至ってシンプル。
それが本作の作風にぴったり。
シンプルな物語に身を委ね、見る者は心行くまで三人の感情に寄り添える。
野球も下手、ホッケーもあまり上手くない。吃音で上手く喋れない。
自身に対し劣等感を抱きつつも、その眼差しや佇まいは素朴。
越山敬達くんのナチュラルさ。奥山監督は彼に台本を渡さず、現場で即興演出。これに見事応えた。子役からのキャリアと自然体がマッチ。
彼が自然体なら、彼女は輝かんばかりのフレッシュさ。
ドビュッシーの『月の光』に乗せてスケートをしながらのさくらの初登場シーン。まさに氷上の天使。神々しいほど。タクヤでなくとも見惚れる。
本作で映画デビューどころか、演技も初という中西希亜良。子供の頃から習っていたフィギュアスケートが見る者を魅了する。顔立ちも小松菜奈を彷彿させる美少女っぷり。
二人共、順調なキャリアを築いていって欲しい。荒川でなくとも見守りたくなる。
池松壮亮も好演。『ベイビーわるきゅーれ ナイスデイズ』ではアクションのプロに見え、本作では本物のコーチに見えるさすがの芸達者ぶり。
新人賞や助演男優賞も納得の、三人が織り成すケミストリー。
映像の美しさは特筆。
開幕からの雪国白銀の世界の美しさ、氷上を滑るさくら、ペアでアイスダンスをするタクヤとさくら…。ため息が漏れるほど。
絆や交流が深まり、三人で練習やドライブ。氷の湖のシーン…。その一つ一つが、美しく楽しい思い出として見る者の心にも残る。
このまま温かさに包まれていたかった…。
本作、ピュアなだけのジュブナイル・ラブストーリーではないのは見ていて分かってくる。
各々が抱える悩みや陰…。
吃音症のタクヤ。父親も吃音症。母親はまたアイスホッケーをやらせたいが、父親は息子のやりたい事の背中を押す。
元プロの選手だった荒川。が、夢諦め…。完全に諦めた訳ではない。まだ未練が…。
同性愛者でもある荒川。プロを辞め地元に戻り、コーチをしながら恋人の青年と慎ましく…。
一見幸せそうだが、関係は秘密。田舎町、噂はすぐ広がる。
おおっぴらに出来ず、内に秘めた想い。
それがさくらに片想いしたタクヤにシンパシーを感じたのであろう。
さくらは感情表現が苦手。密かに荒川に憧れている。
ある時、荒川が恋人と一緒にいる所を見てしまい…。
愛の形は様々。が、無垢な少女にそれはショックな事…。
荒川がタクヤにスケートを教えた訳、荒川自身にも酷い言葉を…。
悪気はない。悪気はないのだ。無垢でピュア故、つい出てしまった事。
しかし、それがまた残酷でもあるのだ。悲しい事に。
三人の交流もそれっきりに。
荒川は自身の将来を、さくらは練習に来なくなり、タクヤはまたアイスホッケーを…。
“ぼくのお日さま”というタイトルから終始温かい作風だと思っていた。
が、雪が解け、春の温かさがやって来る。奥山監督の彼らへの眼差しも温かい。
春の陽光がまた美しい。
タクヤは荒川と再会。
そして、さくらとも。
再びスケートを滑り始めたさくら。
三人がまた集うかどうかは分からない。
しかしそこに、三人の間に紡がれたものは確かにあった。
ラストシーン。タクヤはさくらに何と声を掛けたのだろう。
言葉に詰まりながらも、きっとそれは温かく包み込んでくれるだろう。
お日さまの光のように。
作られた感がないのがいいですね。
余白というか余韻というものを大切にして、ストーリーや解釈を
鑑賞者にゆだねているような作品。いろんなテーマを盛り込みながらも、
ストーリーは、静かにゆっくりと展開していく。
ラストがいいですね、そして、その後の楽曲がいい。
ハンバートの昔の曲だそうで、この曲を元に、作られた作品なのかな?
いずれにしろ、いい作品だと感じました。
観終わってシートから直ぐに立ち上がることが出来なかった
ジェンダー平等
私の感じ方は長々と解説している方とは違い、同性愛について異論を唱えた
それもソフトに と言う感想です。小さな恋のメロディみたいとか言う意見
も有りますがそれ違うでしょうと思う。主人公二人の純粋な初恋を見て、俺
何やってるんだと気が付いた先生と言うのが含まれているのでは?
ジェンダーに反対ではないが、持ち上げられるのも嫌だと同性愛者言っている
エンドロールの歌イイね。それと「本末転倒虫」最高❤
ドビュッシーの「月光」いやいや、「月の光」が流れる。
「ダニエルがメロディーに出会う場面」❤
この映画の主題は言うまでもない。
まぁ、すれ違いの純愛タネ。第二成長期にはいる少女と少年の姿を見事に表していると思う。
でも、ファンタジーだけどね。だって、周りのク●ガキどもが黙って見ているわけがない。
「月の光」をバックに少し露出過多の「日の光の中」を踊る少女の姿を少年は見て迷わず「美しい❤」って言えたんだろうね。
もっと若い内に出会いたかった作品である。
追記
この演出家には毒されないように育って貰いたいと思った。
あえて苦言を呈するなら。。。
具体的には言えないが、映画を制作する動機づけになった歌をテーマだと思ってしまう鑑賞者がいると思うから。そこに触れなくとも充分な脚本で、演出も申し分ないと思う。若い頃の岩井俊二さんみたいだと感じた。
追記
最後のカットも含めて、小津安二郎監督に対するオマージュもあるかなぁ。
月とお日様も月が満月の時、お日様は反対にある。間には地球。このコーチは地球って事だ❤
監督は女性が嫌いなのか?
映像は綺麗で、前半の内容もあり、終始ウットリするような優しい気分で見ることが出来ました。
しかし、同性愛者と知ってからの女の子とその親御さんの対応に、嫌な人たちだなーとしか感じませんでした。90年代(?)当時は同性愛者に無理解があったにしても、もう少し配慮があっても良かったのではないかと。テストに参加しないにしても、電話ひとつ入れるとか。感情的になったとしても、参加しなかった事をあとで一言くらい謝るとか。
なので最後のシーンも、「嫌な女が来た」と思ってしまい、そこから良い展開を想像できませんでした。
小さな恋の物語
北海道、海辺(?)のどこかの街。カセットテープで音楽を聴く&ガラケーって1990年代から2000年前後の設定なのかな。
吃音で不器用な男の子・タクヤ。子どもって無慈悲だから上下関係感じとって弱い者を叩くこと(物理的にでないにせよ)、平気でするんだよね。自分に自信が持てないまま、皆と同じように野球をやって、アイスホッケーをやって、時が無為に過ぎていく。そんな最中、同じスケートリンクでフィギュアスケートで舞う女の子・さくらに心奪われる。自身も同じ土俵に立って、アイスダンスのパートナーとして滑走するようになって。子どもの成長を見つめ見守る元フィギュアスケーターのコーチ荒川(池松壮亮)、決して言葉は多くないけど、表情や立ち居振る舞いの柔らかさから、人としての温かみを感じる。
タクヤ、さくら、二人の技術が向上し息も合ってきて。チームとしてバッジテストを受けるその日を迎えるのだが。
荒川の恋人・五十嵐との関係を目の当たりにしたさくら、まだ幼いかったし、時代的にも多様性を受け入れることができないのは仕方ないのかな。ここまで頑張って自信もつけてきたタクヤの心情を考えると胸が締め付けられる。ほろ苦い思い、自分ではどうしようもないこと。そうだよな、これからの人生で何度となくぶつかる心の痛みを積み重ねて、人は大人になっていくのだよな。
ラスト、「あ…」のそのあとは?観客に投げられて終わる、このモンモンとしてしまう感じ。余白があってとても良かった。
映像は綺麗、少女も美しい。しかし
予備知識無しで観よう🌟
ラストシーンのその後は・・・
1スケートを通して知り合った少年と少女、そしてコーチ。3人の一冬の出来事を描く。
2 運動ベタな少年がスケートで舞っている少女に惹かれ、自分も始める。氷上でバタつく彼の姿に気付き、コーチが靴を貸し基本を教授。そして二人にペアを組むことを促し指導する。そんなある日、少女が街中で見かけたコーチの振る舞いに嫌悪感を覚え、そして・・・。
3 三人の練習風景がとても良い。そして温かい。少年のスケートが次第に様になっていく姿、完成された少女の優雅な演技、まとを得たコーチの指導、それに応じてペアの課題に取り組む二人、三人の屋外での戯れ。それらが愛おしい。
4 少女の嫌悪感はコーチに同性愛の疑いを感じたためであった。確かにコーチは友人以上の関係性で同性と同居しており、ゲイかもしれない。少女の拒絶感は、地域性やカセットテープが主流であった恐らく20~30年前であろう時代背景、そしてコーチをとられたという妬みの感情から三倍増しに強くなった。彼女に対しては、「それほどたいしたことではないよ」と言ってあげたい。
5コーチは(映画では描かれていないし、それで良かったが、噂が燎原の火のように広がり)、スケートシーズン終了後に失意の中で町を出ていく。その時、少年と偶然再会し、三人で訪れた場所でキャッチボールをする。コーチの沈んでいた気持ちが落ち着き、少年のスケートに対する思いが再度持ち上がっていく。余韻の残る別れのシーンとなった。
6ラストシーンは春爛漫の一本の道。スケート靴を抱えた少年と少女が次第に近づき、相対する。何か言いたげな少女、何かを言いかけた少年のカットで暗転。想像を掻き立てられる終わり方で、ハッピーなストーリーを想像したい。
7 少年と少女の素材の良さ。それを活かし全編においてさらりとした柔かなタッチで見ていて優しい気持ちになる奥山の演出、なんでもできてしまう池松壮亮、劇中の洋楽が良かった。
素晴らしいライティング
本作は、奥山大史監督(弱冠27歳!)の商業映画デビュー作であり、彼の卓越した才能が余すところなく発揮されています。物語は、雪深い田舎町を舞台に、吃音に悩む少年タクヤが、フィギュアスケートに情熱を注ぐ少女さくらに心惹かれる姿を描いています。彼らの関係を優しく見守るコーチの荒川の存在も、物語に深みを与えています。
奥山監督は幼少期にフィギュアスケートを学んだ経験を持ち、その知識と感性が作品全体に息づいています。特に、ドビュッシーの「月の光」に合わせて滑るシーンは、視覚と聴覚の美しい融合を体験させてくれます。さらに、主題歌としてハンバート ハンバートの「ぼくのお日さま」が使用され、物語のテーマと深く共鳴しています。
キャスト陣の演技も見事です。越山敬達は、吃音に悩みながらも純粋な心を持つタクヤを繊細に演じ、その内面の葛藤と成長を見事に表現しています。中西希亜良は、フィギュアスケートに情熱を注ぐさくらの強さと脆さを巧みに演じ、観客の共感を呼び起こします。池松壮亮は、二人の若者を優しく見守る荒川役を自然体で演じ、その存在感が物語に深みを加えています。
物語は、タクヤの初恋を中心に展開しますが、その背後には多様性や自己受容といった深いテーマが織り込まれています。タクヤの吃音、荒川の性的指向など、現代社会が抱える課題を繊細に描き出し、観客に深い感慨を与えます。しかし、これらのテーマは決して押し付けがましくなく、物語の中で自然に表現されています。
映像美も特筆すべき点です。雪景色の中でのスケートシーンや(三人が凍った湖で触れ合うシーンは素敵でした「小さな恋のメロディ」を思い出しました劇伴もジャストマッチ)
光と影のコントラストを巧みに利用した撮影は、観る者の目を楽しませるだけでなく、物語の感情的な深みを増しています。奥山監督自身が撮影と編集を手掛けたことで、彼のビジョンが隅々まで行き渡った作品となっています。
「気持ち悪い」というたったひと言の破壊力
無料の客と有料の客の待遇の違い
無意識の傷
知らない世界に夢中になっていくタクヤを応援しつつ寂しさを抱く親友
そんな気持ちにまったく気がつかないタクヤ
さくらに足されていくある感情が
理解しがたい気持ちの悪さに触れたときにとった行動
言葉の選択と
荒川が突きつけられた 他人からみた〝自分〟
眠れぬ部屋の空気を沈ませる大切なひと
私たちは生傷をつけあいながら生きている
ポストや白樺につもった雪が
時間をかけとかされるように
今ある不安も
いつかは過去になって
ほしいと祈りながら
離れていく船や
再会の坂道は知っている
陽を求め
未来に向かう
道の途中にいること
修正済み
瑞々しい
“ある視点部門”でなく“ある界隈部門”
最後のエンディングロールに流れる曲を真剣に見た(聴いた?)のはもしかして初めてかも、、、。この映画のために書かれた曲だと思ったらずっと前の曲なのね、お恐れ入りました、映画の終わりがまだ続いているかの名エンディングロール👏
心象描写もへったくれもない喋り過ぎな映画しかないんか!トホホと日本映画を観るのを止めてたけど、ちゃんとした普通の脚本の映画を観れて嬉しい^^。あのおバカ監督の題名だけはイカしてた「−1.0」はぜひこの作品に使ってもらいたいほどだ。
主演の男の子って「天狗の台所」のあの少年なのねぇ。スカしたふてくされガキがこの子とは、演技力バリバリやんwww
日本人受けする男の子と女の子をキャスティングした監督の眼力は、きっとふたつの“ある界隈”では万雷の拍手で迎えられたに違いないwただあまりそこの世界の人を刺激し過ぎる脚本となるとちょいとヤバ系なので、まあ綺麗に作っとこ、ということなのか。
小さな恋のメロディ、からのベニスに死す、からの第三の男、で終わるのかと思ったら最後は僕のようなチンケな想像より美的感覚に優れた方のナイスなカットでした。
今回の評価は、30人余りの小さな映画館で観たんで、いい意味でのバイアスは掛かってるっぽい気がしますw、あしからず。
監督の次回作を見逃さんようにせんと^^/
美しい雪の世界にうっとり。
あの二人はあの後何を話したんだろうか。
途中まで、それこそ胸の前で手を組み合わせて目をキラキラさせてスクリーンを見つめてしまうような、幸せすぎる場面が続いてたから、絶対どっかで何かあるんだろうなあ、と思って半ばびくびくしてたんだけど、、あんな風になるとはなあ・・・TT
最後ほんとは、コーチとあの子が再び邂逅するところまでたどり着いて欲しかったんだけど。。
しかしもちろん、この映画の終わりはあれで良いのだと思う。
もう少しこうなって欲しいかな、と思うところを敢えて足さない、絶妙なストーリー運び。
セリフもそうだったんだけど、もう一つ二つ、何か付け足してしまいそうなところを、そこで止めるが故の余韻がすごくいい味わいになっていたように思います。
あの少年の吃音も、こういう言い方はおかしいかもしれないけど、その少ない言葉なりの余韻にプラスに働いていたと思う。
終わり良ければ全て良し、というけれど、じゃあ終わりが良くなければ、それまでの全ては色褪せて、ダメになってしまうのか。
決してそうではなくて、そのひとつひとつのきらめきは、確かにそこにあって、人の心を、時間を、価値あるものにするのだということ。
その大切な事実に、光を当てる映画だったと思います。
ラスト、あの二人は、あの後どんな会話を交わしたのだろうか・・・すごく知りたい!!
全272件中、21~40件目を表示