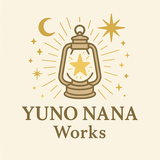ぼくのお日さまのレビュー・感想・評価
全271件中、1~20件目を表示
リンクの凛とした空気と差し込む光の中で舞う眩しい二人
タクヤはさくらに憧れに近いほのかな恋心を抱く。つい目で追ってしまう。それは観ているこちらも微笑ましくなるほどのピュアな恋。荒川の「羨ましかったのかも。」という気持ちがわかる。
荒川コーチがアシストして二人はアイスダンスのペアに。スラっとして美しい2人。とても画になる。そんな2人がリンクに差し込む光の中、「月の光」の美しい旋律に合わせ、照れながらも手を取り合って氷の上を舞う。2人のドキドキがこちらにまで伝わる。この年代だからこそのドキドキ。キャンプファイアーのフォークダンスで好きな女の子と真っ赤になりながら手をつないで踊ったあの頃の空気感が蘇る。(ここに男女の肉体的な欲望が入り込む余地はない。)
荒川コーチ演じる池松もいい。池松が出演するとその映画は、雰囲気がゆったりで、静かで、優しくて、美しくなる。口調がゆったりなのがいい。(ぜひ真似したい。。)タクヤとサクラと荒川コーチ。この3人のキャスティングがあってこそ。絶妙。
タクヤの笑顔のように、純粋で、無垢で、月の光のように輝く3人の関係。
これを壊したのは、、、ある一言。ドロっとしたものが垣間見えた瞬間。一気に現実に引き戻された。子供&おとなしくみえて芯は強い。女性はすごい。。。タクヤが能天気なだけに、余計に男と女の差を強く感じた。荒川コーチも観ている我々もバケツで冷や水をかけられた気分。
最後のシーンは「そこで終わるかー」という感じ。でも確かにそれが一番綺麗かも。
高評価だから足を運んだこともあり、期待値が高すぎて、映画としては物足りなく感じてしまった。
ただ、幼いころの淡い想いと澄んだ光景を想い出させるあの奇跡の映像描写に関しては、確かに高評価をつけられる方が多いのも納得である。
※美しい風景をバックに滑る屋外の天然リンクのシーンもまた同様に格別だった。
※店員がガソリンを入れてくれていた頃のお話なんだな。車でカセットテープを聞く、古いボルボ、ガラケー、防具もステイックもひょっとして古かったかな。ザンボも?
※ザンボかけてる時に滑ったらあかんよ!
※タクヤがいい。そしてタクヤの友達がいいヤツでいい!
誰かを好きになってしまう、ぼくの原罪
「ぼくのお日さま」というタイトルは二重の意味で罪深いと思う。他人を神格化させて、救いを与えてくれる「お日さま」にする罪。さらにそのお日さまを格助詞「の」で「ぼく」とつなげて、「ぼく」の所有物にする罪。
だからこのタイトルからして、本作には不穏な空気が漂っていたのだが、その予感は的中した。ポスタービジュアルや光のやわらかさに反して、とても残酷な物語である。でもよかったとも思う。吃音の少年・タクヤが、「男の子がやらない」フィギュアスケートを習ううちに、さらにゲイのコーチ・荒川との交流を通して、自分らしさを見つける物語だったら、綺麗すぎると思ったからだ。その綺麗さこそ、障害や性的マイノリティーのウォッシングでしかない。
そしてこのような物語化は、普遍的なテーマを浮かび上がらせる。すなわち〈私〉の好意の問題である。「誰かを好きになること」を素朴に良いことだと信じられたら、人生はとても生きやすいと思うが、そのことに罪の意識を持ってしまう人は深刻だ。でも好意を持つことは、他人に危害を加えることと切り離せない。好意には、他人に対する選択と排除が伴っている。さらに上述のように、好意は〈私〉のエゴイズムによって他人の人格を剥奪する。一方的に救いを与えてくれる神にさせることも、操作可能でないがしろにできる物にもさせる。
でも私たちは好意なしに他人と関わることはできない。そして自分の理性や損得勘定でどうにかできるわけでもない。荒川だってゲイであることを選択してはいない。それなら、この誰かを好きになってしまうことは、私たちが背負わなければならない原罪ではないだろうか。
さらに他人の好意を〈私〉が目撃してしまったら?
他人は〈私〉を好きではない。さらにその他人が好意を向ける対象は、〈私〉の規範を逸脱する他者である。その時、生じる感情はどのようなものか。それを現前させたのが本作である。
以下、ネタバレを含みます。
まず、本作の好意は性愛に必ずしも結びつかない。
本作では、タクヤ→さくら、さくら→荒川、荒川→タクヤと好意が向けられているのだが、それぞれ好意のありようは全く違う。
タクヤがさくらに向ける好意は憧憬に近い。光の中をフィギュアスケートする美しさに見惚れ、まさに神が現れた感覚だ。
さくらが荒川に向ける好意は、恋愛未然だけれど、同級生に荒川の魅力を伝えられて、気づいてしまった感覚である。
荒川がタクヤに向ける好意も、自身の幼少期を投影した愛おしい感覚だろう。彼はガソリンスタンドで働く五十嵐と恋愛し、同棲関係でもあるのだが、劇中にセックスは存在しない。これらからも、本作の好意は性愛と結びついておらず、恋愛未然の感覚といってよいだろう。そんな印象は、本作に特徴的なぽわぽわな光とも共振する。だが彼らの好意は対象が一致しないズレが生じている。そんな様も、カットによる視線の不一致で巧みに描かれている。
タクヤが野球ーアイスホッケーでは停止しているのだが、フィギュアスケートでは氷上を滑り出すことからも、彼らの好意の滑り出しを感じれてとてもいい。そして彼らは、荒川が強引に二人をアイスダンスの試験にトライさせることで近づき合うのだ。
だが、トライの最中にさくらは、荒川がスーパーの駐車場で五十嵐といちゃいちゃするのを目撃してしまう。そして彼女は、荒川が五十嵐に向ける好意を、タクヤへの好意と同様と錯覚し、気持ち悪いと言い放つ。さらに、彼女はトライ当日も来ず、3人の親密さは冬の一時で終わってしまうのだ。
さて、さくらが、荒川が五十嵐やタクヤに向ける好意を気持ち悪いと思ったことは罪なのだろうか。
私は気持ち悪いと思うこと自体は仕方ないこととは思う。直感に近い感情は拭い去ることはできない。彼女の生きる街は都会以上に、マイノリティーは不可視化されているし、異性愛が当然だと思っているのなら許容できる余地はない。思うこと自体は罪ではない。しかしそれが加害に転じたら罪だ。荒川に直接言い放つことが、即時的な加害になったとは言えないかもしれない。だが、さくらには「お日さま」の資格を失った荒川を物のようにないがしろにしてもいいという明確な悪意がある。そして結果的に彼は職を失い、五十嵐も失い、街を出て行かなければならなくなったのだから、彼女の行為は重大な加害と言わざるを得ない。
荒川は好意をわきまえていた。駐車場に止めてある車内を、公共ともプライベートとも区分しがたいところが悩ましいところではあるが、それでも配慮していたことは言えるだろう。だから物語として、彼が原罪のために街を追放されたことは、時代性を言い訳にしても世俗感覚に追従したただの現状肯定という名の不正としか言いようがない。
もちろんさくらが自力で気持ち悪さを解消する必要もない。そのために、コーチングという行為があるのではないだろうか。さくらの偏見を正すコーチングがないことも、時代性や土地柄と言っていいのだろうか。もちろん荒川がそのコーチングを担う必要はない。だから荒川とさくらを仲介する母がその役目を担ってもいいはずなのに、なんだか露悪的な姿に留まってしまう。
タクヤがその役目を担ってもいい。というか、タクヤはいつまでも受け身過ぎる。本作の登場人物は言いっ放し、やりっ放しでリアクションが欠如していることは指摘できると思うが、そのドラマの果てに雪解けの和解が起こりうるのではないかと思ってしまう。
だからタクヤは何も言わず/言えず、荒川の謝罪もなかったことにして街から追放する、そしてさくらがフィギュアスケートに回帰し、綺麗に滑ることで物語を終わらせてはいけないはずなのだ。
このような不十分さから、本作を手放しに傑作とは言えないのだが、タクヤとさくらの次のドラマは準備されている。春になって、タクヤは中学生となり制服を来て登校する。そして大地でさくらと再会する。きっとタクヤがさくらと再会する場所が、スケートリンクではなく大地であるのは、さくらからお日さま性を取り除き、さくらその人に眼差しを向けるためだ。タクヤとさくらは、同じ中学生となって人と人との対等な関係になりだしている。さくらが「ぼくのお日さま」でなくなったとしたら、タクヤはさくらとどう向き合うのだろう。そして二人にはどんなドラマが起こるのだろうか。さらにさくらの気持ち悪さは解消されるのだろうか。もしかしたらさらなる葛藤を呼び起こし、罪を重ねてしまうかもしれない。どこまでもいっても赦しは存在しないかもしれない。だが荒川を歓待できる未来を私は期待したい。
成る程納得!カンヌも認めた「その視点」!!「目は口ほどに物を言う」その視線の先にあるものは?
今注目の新進気鋭の若手映画監督、奥山大史監督が、監督・脚本・撮影・編集まで手がけた商業映画デビュー作品です。
是枝裕和監督からも一目おかれ、主演の池松壮亮さんが「凄まじい才能」と絶賛する奥山大史監督は、第77回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門に、日本人監督としては史上最年少で選出されました。日本映画の未来を担う監督とあらば、
これはもう、
観るしかないっしょ!!!
勇んで仕事終わりに映画館へ。
連日の疲れが溜まってか、
まさかの開始5分からの爆睡…。
目覚めた時には、エンドロールという大失態を…😭😭😭久々の全寝でした…。映画を観に行って寝るとか信じられん!!と、よく人からお叱りを受けますが、映画館って本当に心地いい場所なのよ、私にとって。一番リラックスできる場所。どんなに寝不足でも、寝室に行くと逆に目が覚めちゃうのに、なんて映画館って心地よいんだろう?
私だけかなぁ…🙄
で、体調整えて
「リベンジお日さま」して参りましたよ!!
感想は、
「やっぱり観ておいてよかった〜」というのが、まず率直な感想です。終始派手さはなく、物語は淡々と静かに進んでいきます。(寝不足の人は要注意よ!)でも退屈なんかじゃ、決してないのよ!!(一回寝た人が説得力ないね😅)全部必要な静けさ。不必要な音楽やセリフは一切必要ない。余白すら演出。大好きな池松壮亮さんと、恋人役にこれまた大好きな若葉竜也さん。ふたりの掛け合いのシーンを見てるだけで幸せになれます。子役のお2人もとってもナチュラルでよかったです。
その視線から、表情から
全て理解できます。
言葉などなくても。
ある人が、
ある人に向けたその熱い視線
またある人が、
ある人に向けた軽蔑の視線
そしてまたある人が
ある人に向けた失望の眼差し
などなど
「目は口ほどに物を言う」
まさにそれを存分に感じる映画でございました。主題歌は、ハンバート ハンバートの代表曲「ぼくのお日さま」で、この映画のタイトルにもなっています。監督がこの曲からイメージを膨らませたとコメントしているように、本作品の大事なキーとなっています。エンドロールまで見逃せません。
こんなにも優しく、
こんなにも痛い映画を
私は今年初めて観た気がします。
いやぁ、いい映画を観させていただきました。合掌🙏
*ご鑑賞は十分に体調を整えて🙄
痛みも含めての人生
ひと冬のあたたかさと痛みでツーンとなる物語。
光と雪の白さ、スケートリンクを滑る音、まだ純真無垢な中学生のふたり、全てが美しくて、全てが眩しくて、そして痛い。
中学生ふたりの恋と言うにはまだ早い、淡くて朧げな感情は、綺麗だけど綺麗すぎる故に潔癖で、でも思春期ってそうだったかもなと思う。
吃音で言葉がうまく出てこないタクヤが、必死に想いを伝えようとする姿は、吃音気味の甥っ子が浮かび応援せずにはいられなかった。
徐々にフィギュアスケートを楽しむ姿は見ているこっちがニコニコしてしまったし、やっぱり楽しいや好きな感情が上達の近道だよなと思い知る。
見た後、痛いけどこの痛みも含めて人生だって思える映画だった。
それにしても、荒川役の池松さんは、本当に撮影前までスケート出来なかったんですか?
コーチ役だから相当努力されたんだろうなと思うけど、全然違和感なかった。本当にすごい役者さんだよ。
若葉竜也と池松壮亮が共演してる幸せを噛み締められる作品でもあった。
今年の邦画で私的暫定1位。予備知識は少なめ推奨
映画「ぼくのお日さま」に惚れ込んだ。脚本・撮影・編集も手がけた奥山大史監督、長編第1作「僕はイエス様が嫌い」は自主制作だったからこの長編第2作で商業映画デビューとなるが、弱冠28歳にしてこの完成度に驚かされる。冬の始まりを告げるひとひらの雪の結晶のように、完璧で無駄のない美しさ。映画は光を操る芸術形式だということを改めて思い出させる、光と影の見事なコントロールに、スモークも活用した空間と空気感の演出の巧みさ。
可能であれば予備知識なしで登場人物たちに出会い、彼らを知り、寄り添うような気持ちでひと冬の出来事と感情を一緒に体験してもらえたらと願う。とはいえ人によって映画の好き嫌いは異なるし、時間もお金も有限なので、事前に自分の好みに合うかどうかを知っておきたいというのもよくわかる。最初に、これらの過去の映画が好きだったら本作もきっと気に入るはず、というのをいくつか挙げてみると、まず奥山監督が影響を受けたと明言しているイギリス映画「リトル・ダンサー」。ほかに共通要素があるのは、岩井俊二監督作「花とアリス」、橋口亮輔監督作「恋人たち」、押見修造原作・湯浅弘章監督作「志乃ちゃんは自分の名前が言えない」あたりか。
本作はミステリ仕立てでもないしどんでん返しなどももちろんないのだが、以降は当レビューを読む方の意向や状況に合わせて【1】ネタバレなしのトリビアなど【2】予告編や解説文でも分かる程度のストーリーの鍵になる要素【3】軽いネタバレを含むレビュー、の3段階で構成するので、鑑賞前・鑑賞後などそれぞれの事情で読み進めていただければありがたい。(あと、だいぶ長いので、できればお時間のあるときに)
【1】ネタバレなしのトリビアなど
・主要な登場人物は、小学6年生のタクヤ(越山敬達)、中学1年生のさくら(中西希亜良)、スケートリンクでさくらをコーチする元フィギュアスケート選手の荒川(池松壮亮)の3人。彼らが氷上を滑る姿を並走しながらスムーズに流れるようにとらえるカメラワーク(そのおかげで一緒に滑っているような気分になれる)が本作の見所のひとつでもあるが、奥山監督がスケート靴で滑りながら撮影している(映画公式サイトにメイキング動画あり)。監督自身が幼少期にフィギュアスケートを習っていたそうで、その頃の経験が脚本に反映されている。
・越山敬達は2009年生まれ、中西希亜良は2011年生まれ。それぞれ13歳と11歳だった撮影当時は中西の方が背が高かったので、さくらが1学年上という役の設定に違和感がなかったが、2年ほどの間に越山の背が伸びて中西を抜いてしまったとか。元々キャスティングには運や縁がつきものだが、2人のキャスティングと撮影時期のタイミングの良さには奇跡的な巡りあわせも感じてしまう。
・舞台は雪国の架空の町という設定だが、本編中に実在の施設の名称が映るので、北海道のどこかだろうとたいていの観客は思うはず。たとえば荒川が同居人と買い出しに行く南樽市場(なんたるいちば)はJR南小樽駅の近く、アイスダンスのテスト会場になるセキスイハイムアイスアリーナは札幌市中心部から少し南の真駒内にある(さらに詳しいロケ地の情報については、小樽フィルムコミッションのサイトでロケ地マップが公開されている)。
・時代設定について。フィギュア選手時代の荒川の写真が掲載された1993年のカレンダーが映るので、その数年後だろうとまず推測できるが、その後スケートリンクの事務室内に映る2月のカレンダーの曜日から、うるう年の1996年だと特定できる。ちなみに奥山監督の誕生日は1996年2月27日で、時代を決める1つの材料にはなったかもしれない。とはいえ、この時代を選んだのにはより重要な理由があると考えられるが、それについては後述。
【2】予告編や解説文でも分かる程度のストーリーの鍵になる要素
・タクヤに軽い吃音があるのは、当サイトの解説文などでも触れられている通り。吃音があると他者とのコミュニケーションが難しくなることもあるだろうが、だからこそ誰かに出会い心と心が通うときの喜びも特別になる。その点で、「志乃ちゃんは自分の名前が言えない」に通じる魅力がある。
・奥山監督はハンバート ハンバート(佐藤良成と佐野遊穂の夫婦デュオ)が2014年に発表した「ぼくのお日さま」を聴き、自身がフィギュアを習った体験を反映した主人公の少年に吃音持ちという設定を加えた。その後奥山監督は佐藤良成に手紙を書き、主題歌としての同曲の使用と映画のタイトルとしての使用を快諾してもらえたという。「ぼくはことばが うまく言えない/はじめの音で つっかえてしまう」という歌い出しの同曲が流れるエンドロールでは、歌詞の文字がアイスダンスを踊っているかのようにくるくる、すいすいと流れて表示される。歌の内容と優しい歌声に相まって、この遊び心もまた映画の余韻に貢献している。
・ハンバート ハンバートの佐藤良成は劇中音楽でも参加。オリジナル曲2曲を提供したほか、3人が天然のスケートリンク(ロケ地は苫小牧市の丹治沼で、地元の建設会社が除雪し水を張って氷面を平らにした)で滑るシーンで流れるThe Zombiesの「Going Out of My Head」も提案したという。同曲のオリジナルはLittle Anthony&The Imperialsという米国のR&Bボーカルグループが1964年に発表したものだが、これを英国バンドのThe Zombiesが1967年にカバー。結果、60年代ブリティッシュロックとモータウンサウンドが混じったような明るいポップナンバーとなり、「君のことばかり考えて頭がおかしくなる」と繰り返される歌詞も相まって、陽光が降り注ぐ氷上で3人がはしゃぐ多幸感に満ちたシーンにぴたりとはまっている。
【3】軽いネタバレを含む解説など
ここから先で触れる内容は、事前に知っていると本編中で観客が自ら気づいたり驚いたりする楽しみを損ねてしまうので、できれば鑑賞後に読んでもらえたらと願う。
・90年代に設定された理由・その1:先述のように1996年2月を含む冬の数か月間(より正確には95年の冬の始まりからタクヤが中学に進学する96年4月まで)に時代が設定されているが、この年に生まれた奥山監督が実際にフィギュアスケートを習ったのは2000年代のはず。実体験の時代よりも前にしたのには、主に2つの理由が考えられる。第1は、荒川の台詞にもあったように、日本でのフィギュアの競技人口における男女比にまつわる事情。2000年代に入ると髙橋大輔選手や織田信成選手などの活躍で徐々に男子の競技としても広く認知されていくが、90年代にはまだ「女子がやる競技」という世間一般の偏った認識があった。そうした時代背景が、フィギュアを始めたタクヤに対する周囲の反応に描き込まれている。
・90年代に設定された理由・その2:これについては序盤から少しずつ繊細に伏線が張られているので、本当なら観客それぞれに鑑賞中のどこかで気づいてほしい要素。たとえ見過ごしていたとしても、やがてはさくらと同じタイミング、南樽市場の前の橋で知ることになるだろう。その要素とは、荒川が同性愛者であり、同居人の五十嵐(若葉竜也)とパートナーの関係であること。映画後半は、同性愛者への偏見から発せられる心ない言葉(言葉の暴力と言ってもいい)が3人の物語を大きく変えていく。そうした性的マイノリティーに対する偏見と差別は90年代から2000年代にかけて徐々に減っていったと思われるが、たとえば2006年にはアカデミー賞で監督賞を含む3部門を受賞した「ブロークバック・マウンテン」が日本でも公開され話題になるといった画期的な出来事もあった。地方の町での同性愛者に対する偏見という意味でも、2000年代より90年代のほうがより説得力を持つという判断があっただろうと推測する。
・荒川が自身の性的傾向にいつ気づいたかは語られないが、自認してからはおそらく一人で悩み苦しみ、周囲に好きな男性ができてもたいていは打ち明けられないまま終わり、勇気を出して告白したのに拒絶されたこともきっとあったはず。若い頃にそうした思いをしたからこそ、タクヤについて「うらやましかったんだよ。ちゃんと恋してるっていうかさ」と五十嵐に吐露したのだろう。
・ローティーンの2人を支える役割も担った池松壮亮の演技は安定感と繊細さを兼ね備えていて実に見応えがある。特にラスト近くのキャッチボールの場面で、タクヤが捕れない球を投げてしまった後、「タクヤ、ごめん」と微妙に声を震わせた台詞が絶品。もちろん暴投のことだけではなく、タクヤの恋を応援するつもりで始めたアイスダンスが結果的にタクヤとさくらを傷つけてしまったことを詫びる気持ち、不意に沸き上がった感情の表れなのだろう。
・本作の“光”と“輝き”を担ったのは間違いなく、中西希亜良のフィギュアスケートのパフォーマンスと愛らしい表情だ。父親がフランス人で、フランス語、英語も話すマルチリンガルだそう。映画初出演作でカンヌデビューを果たしただけに、ぜひ国際派スターを目指して精進してほしい。フィギュアができること自体が大きな武器だし、高い身体能力はきっと活劇でのアクション演技にも応用がきくはず。今後の活躍に大いに期待する。
言葉を超えた忘れがたい瞬間の数々が胸いっぱいに広がる
ひと目見た瞬間に引き込まれる作品というものがある。まさに本作も同じ。決して強烈なインパクトを放つ類ではないが、この全てを照らすお日様のような大らかさ、透き通った柔らかな光、交わされる心と心、未来へと続く道筋に、こちら側から胸を開き溶け合いたくなってしまう逸品だ。思いがけずフィギュアスケートに魅せられる少年の物語という意味では『リトル・ダンサー』を彷彿とさせる部分もあるが、一方で私が惹かれたのは本作が「眼差しの映画」でもあるという点だ。日々、フィギュアの虜になっていく少年の様子をきちんと見ている人がいる。また少年と少女、コーチが一体となって練習に打ち込む時、窓からは穏やかな陽光が微笑むように射し込んでいる。踊ることへの喜びを体現する若き二人もさることながら、池松壮亮のナチュラルな存在感には息を呑んだ。慈愛に満ちた表情で指導する一挙手一投足は、今年観た中で最も忘れがたい名演の一つと言えそうだ。
人生思い道理な帰結は難しいものだけど、取り敢えず足掻いて挑戦してみ...
できる限り予備知識無しでの鑑賞をお勧めします
2025年のアンコール上映での鑑賞。
ネタバレしてしまったら楽しめないという作品ではありませんでしたが、未鑑賞の方にはできる限り予備知識を入れずに見ることをお勧めします。
とても美しく切ない映像と話運びで、主演3名がこの役者さんたちであったからこそ、ここまで素晴らしい作品になったと思います。(もちろん、監督さんはじめ、素晴らしい製作陣あっての作品です。)
自分で★5をつけた他の作品よりもある面では上回っている作品とも感じたのでかなり迷いましたが、荒川コーチの結末だけはどうしても雑に見えてしまったので、満点にまではあと少し届いていなかったかということで★4.5にします。
タクヤにも会わず、会わないことを選択した理由や心情も描かれていないというのが、この作品のそれ以外の部分はすべて緻密に描かれていたのに対して、不釣り合いというか、違和感を覚えました。
カーステレオでカセットの音楽が流れてくる、というと思い出すのは…
二人の少年・少女の真っ直ぐなまなざしが眩しい。
その二人を描写する映像とともに流れる
音楽の美しさに心惹かれる映画でした。
さくらが一人リンクで滑る場面の
ドビュッシー「月の光」。
タクヤとさくらの二人が
アイスダンスのダッチ・ワルツに取り組む場面の挿入曲。
コーチの荒川と3人で一緒に
湖の氷上で踊る場面の
ゾンビーズ「Going out of My Head」。
そして、エンディングロールで流れる
味わい深い歌詞とメロディーの
ハンバート・ハンバートの「ぼくのお日さま」。
どの曲も各シーンを深く印象付ける効果的な選曲でした。
特に、
車の中でカセットを取り出して
カーステレオをかけるとオールディーズが流れてくる…。
ビム・ベンダース監督の「パーフェクトデイズ」を思い出しました。
ピュアなタクヤが良い
撮影技術に驚嘆
恋心を描いたシンプルで分かりやすいストーリーと美しい映像。そうした映画は過去にいくらでもある。その中でこの映画で特筆すべきは、監督自身が撮影を担当し、この映像を撮っていること。
スケート場のシーンは窓外にたくさんの照明を仕込み、光を流し込むライティングで叙情性を高めていたし、屋外のスケートシーンも逆光を多用し、同じ雰囲気を作り出し、淡い恋心を見事に描いていた。また、時折みせた不安定な構図が、この映画が描く思春期の不安定な気持ちとマッチしていた。あと、セリフでは、好きであるがゆえに「気持ち悪い」と言ってしまう幼さが切なかった。
非常にパーソナルでシンプルな物語で、一部同性愛を描いているとはいえ、全体としては社会性に乏しかった。そのため、この監督が将来、どういった方向に進むのかは未知数。次の作品は若者の恋愛物だろうか?それともストーリーの面白さを押し出した映画だろうか?いずれにしても、作家性を保ちながらもう少し商業映画寄りの作品が期待されるのではないか?
美しい映像を作る手腕は一流。期待を込めて星半分を加点した。
氷上の美しく透明な時間
少年と少女と男性コーチ、3人の孤独な魂の束の間の美しい触れ合い。それが淡い光の中で優しく穏やかに紡がれていくのが良い。そしてそれがほんの少しのボタンの掛け違いで儚くも脆く壊れていく思春期特有の繊細な難しさまでもが愛おしい。コーチ役の池松壮亮のどこか影のある佇まいも良いが、少年役の越山敬達、そして何より少女役の中西希亜良が素晴らしい。子役出身で映画初主演の越山くんのピュアな少年ぶりも上手いが、演技初経験の中西さんの繊細で複雑な内面の少女像を演じる姿が秀逸。もちろん役との親和性の要素によるビギナーズラック的な部分もあったかもしれないけど。
それにしてもこれほどフィギュアスケートを美しく映像に捉えた劇映画は初なのではないか。これまで米国映画『冬の恋人たち』『アイ、トーニャ』などを観たが、この映画は頭抜けている。越山くんと中西さんが共にフィギュア経験者というのが大きかったんだろう。共に4歳からフィギュアを初め、中西さんに至っては現役フィギュアスケーターでコーチの勧めでオーディションを受けたんだとか。撮影時は14歳と12歳ながら中西さんのほうが背が高いが、それから1年過ぎた舞台挨拶では越山くんの背がすっかり伸びて池松壮亮も抜きそうなくらいになってた。成長期すげえ。流れる音楽のドビュッシー「月の光」もフィギュアお馴染みの名曲でこれまた良かった。
20代の奥山大史監督はこれが長編2作目で、初監督の2019年『僕はイエス様が嫌い』で66回サンセバスチャン国際映画祭最優秀新人監督賞を受賞したとのことで、史上最年少受賞だったそうだ。これからも楽しみな監督かも。
不完全な世界
思春期の美しさと、残酷さ
全271件中、1~20件目を表示