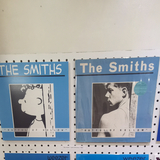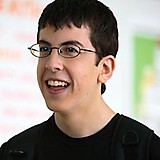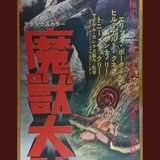ザ・ウォッチャーズのレビュー・感想・評価
全71件中、41~60件目を表示
前半ホラー風、後半は…
ホラーを堪能できるかと思い鑑賞。
前半は暗い森が舞台なので、全体的に見えにくく分かりにくい。
後半になり、森に潜むウォッチャーズの謎が解かれ始めるにつれ、ホラー要素は薄くなる。というか、なくなる。
最後、ウォッチャーがヒロインの言葉をすんなり信じるあたり、妖精でもあり、人間でもあるんだなぁと感じる。人間を信じる心を捨てられないのかなぁと。
ラストがあっけないと言えばそれまでだけど、ほっこり終わるホラーもいいと思った。
森の奥にある秘密の部屋で・・・
「シックス・センス」で一世を風靡したM・ナイト・シャマラン監督、今度はどんなどんでん返しを見せてくれるのかと思ったら、娘さんのイシャナ・ナイト・シャマラン監督のデビュー作だそうで・・・
このレビューを書くまで知らなくて、ずっとM・ナイト・シャマラン監督の作品だと思ってました。
どうしても、どんでん返しに期待がいくので、そういう見方をしちゃってました。
迷い込んだら脱け出すことができない森の中に、見つめられるための部屋があるという、なんとも不思議なシチュエーションの話です。
この奇妙な設定の割には、それほど入り込めなかった自分がいます。
妖精?ナイトウォーカー?得たいの知れないモノが出てくる映画は、好きなジャンルでそれなりに楽しませてもらえましたが、あくまでそれなりです。
最後も、それほどの衝撃はなかったかな。
期待が大きすぎたってところもあるのでしょうが・・・
なんかこう違和感が残る
良いところ
話が二転三転して予想を違えてくる
?なところ
結構長い時間居たはずなのに確かめるべきところを放置してる違和感
超常的な存在なのだろうけど、なぜか物理的範囲の動きしかしないから、所詮淘汰される存在でしかないな。詰まる所知られてないからこその価値。まあ、知られたら碌でもない実験に使われて終わり。んなもんで見終わった後の絶望感はあんまりないな、続編があるとすればそこら辺かな。
そもそもの話だけど、なんであんだけ長く居たのにお互いの状況確認してないんだよ、というのが違和感ある。真っ先に色々試してそうなのに地下室見つけるのはギリギリだし不自然さがあちこち。気になると気になる。
なんか作中年月が曖昧なんだけど、仲良くなって擬態させて交尾して子供もうけて射殺したのか?それで三百日は無理じゃないけど、なんか日数が合わん気がする。それとも十月十日ではないのかな?
Gene
シャマランの娘さんの長編映画デビュー作ということで、父親のDNAが全開なのか、はたまた違うアプローチで攻めてくるのか…そういう期待と不安も込めつつ鑑賞。
割としっかりしたミステリアスな作品で、父と似通っている部分もあれば、自分の色を出しているところあってクセはあれど楽しめました。
森の中の一軒家に迷い込んだミナが、その家にいる3人と共にウォッチャーズに監視される日々を送る中での脱出を目論む…といった感じで、序盤の男性が襲われるシーン然り、情報が開示されない序盤の不気味さは中々に秀逸でした。
劇中で流れている恋愛リアリティショー、普段全然目にしないジャンルですし、付き合ったのに別れました〜みたいなノリ(出演者たちが気の毒でもある)をよく目にするので興味のないものですが、今作では良い味を出していました。
恋愛リアリティショーを観る視聴者はやんややんや言い放題ですし、それこそ今作のウォッチャーズと一緒だよなとなって面白いメタファーだなぁと感心しながら観ていました。
今作のウォッチャーズの正体は教授が蘇らせた妖精で、その妖精は色々な人物に変化できますし、家来的なやつは謎にスレンダーマン風味があって造形は良かったです。
ただスレンダーマンはむっちゃ獰猛な事以外は、こちらを見ている状態でそこまででしたし、もっと襲ってくれたら見せ場もあったのになと思いました。
ルールを破ったもの(というか破らせようとした)は殺されて、ルールを守ったもの(もしくは巻き込まれそうになった)は無事生還できるといった感じで、森の中全力疾走からの、湖に出てからの、スレンダーマンもとい妖精たちに1人ぶっ殺されーの、オンボロボートでの脱出で街まで生還とサラッとしていましたが、無事帰れて良かったけどこれで終わったら消化不良すぎるよなー、あらあっさり脱出できちゃった…と思ったらそこからもう一捻りあるので、父の遺伝子が突然変異してくれていて、ちょっとだけお得感がありました。
教授の真の目的は妻を甦らせる事。
それで妖精を呼び出してしまったがために殺されて体を乗っ取られて、妖精は太陽を浴びれないという弱点をハーフリング(妖精と人間ががーっちゃんこ)で補って、人間の世界で生きていくという一気にファンタジーに飛躍した瞬間は驚きましたが、それ相応の理由がしっかり提示されたタイミングでなぞに納得できるものがありました。
羽でバッサバッサ飛んでいくところだけは違和感満載でしたが笑
ツッコミどころはたっぷりありまして、なぜ森に一直線で向かってしまったのか、床下の扉になぜ気づかなかったのか、ルール破りまくりだけど大丈夫なのか、
ホラーとして観るとインパクト不足ですが、怪しげなファンタジーとして観たら結構楽しめました。
粗っぽい部分やホラーテイストがどう改善されていくのかも見ものですし、ここから父親と一緒に映画を作るか、それとも1人で新たな道を切り開くのか、イシャナ監督の次回作に期待しています。
鑑賞日 6/23
鑑賞時間 18:40〜20:35
座席 H-15
親の七光り~長編監督本格デビュ-じゃったが 蛍の光に終わる!
とーちゃんを超えるんだぁ~イシャナ。
シックスセンスをも遙かに凌ぐ、(´-ω-`)
「ザ・ウォッチャーズ」を今日は見ましたよん。
監督は、あの”シックスセンス”を手掛けたM・ナイト・シャマランさんの娘である
イシャナ・ナイト・シャマランさんだぁ。
きゃ、きゃ、脚本も手掛けて居られるのだぞぅ。
皆の者 頭が高-い。m(_ _)m
折角の長編デビュ-作ですが、すみませんが 回れ右で元へ戻って下さい。
余りの詰まらなさ過ぎて ★2個程度ですよ。(´・ω・`)
なんやてぇ~・・・声が本人から聞こえて来そうやけども、
詰まらんモノはツマらんのよ。
森の中で遭難は良いけど、急に現れるシェルタ-施設。
昼間 御日様に当たる所の森に居るのは良いが、
夜はこの家の中に居ないとダメ。
その条件はいい。まだ理解できる。
外になんか居るのも分かった。古くからいるソレ(妖精ね)。
それも 一応理解できる。
分らん疑問羅列すると。
・なぜ大きい1枚板のミラ-ガラスが有るのか。
・夜に姿を森の連中に見える様にしなきゃならんのか。
・何年もココに居たの?日頃何喰ってるのか。
・トイレ・バスルームは何処に。
・ベットは基本無いのか。
・えっTV? ラジオ? 電波あるの?携帯電話は無理?
・ビデオ見てた訳ね。繰り返しね。まさかレンタルじゃ無いよね。
・家電に、照明機器あるなら電気は来てるんだ。電線何処から来てるの?
・えっ高性能ソーラ-パネルの設定? でも映って無かったけど。
・そもそも 太陽光が森に強く差し込まないけど、発電は無理では?
・最初にココにやって来た白髪の老女。 実は人と妖精との間の子。
ココから連れ出される計画。人が多い街へ行って人喰う?狙い。
聞いてて だっせぇ計画だなぁ と真摯に思う。
・森から色んな方向に看板と番号が。なんかウケる。
そこを超えると元には戻れないらしい。調べた奴、超暇人。
・夜に家の外に老婆と居て、妖精らしき正体を見る。
背がやたらと高い黒い影の存在。何で襲われないのか。
それは 逃されるため?だったのか。
・妖精は池?川? 水は苦手なの?
・妖精が次々と人に変化。都合のいい変化。
・防犯カメラへの映り場面、中々面白かったけども。
・地下穴に居たのは誰?関係性なし?
・博士遺言、博士の大学で何かを壊せと。
・最後展開は、人間とのハーフ妖精に目覚めで、森に帰るのかな?
親の七光り 不思議ちゃん光線でまくりの
展開映画でしたわ。
イシャナさん、ドンマイドンマイですよ。
次回作は、今より輝いた作品を期待しております。
変わりモノホラ-好きな方は
劇場へ。
監禁、監視する者たちの正体とは? ただのサプライズネタもの映画ではなかった
広大な森林の奥深く、ガラス張りの小屋に捕らわれた4人。
彼らを監禁し、監視する者たちの正体は…。
この手の映画では、謎の正体が解明され、脱出できたところで終わることが多いが、本作はそこからが結構長い。
「シックス・センス」のM・ナイト・シャマラン製作ということで、どうしてもラストのどんでん返しやタネ明かしを売りに宣伝されがちですが、本作は、伝承・神話が背景にあることと、彼らの存在と人々とのかかわりあいの方に重点があって、面白い。
監視は、人になりすます擬態のため、と思っていたが、実はそれはすでに完成していたのだ。
オウムの鳥かごが、ガラス張りの小屋を思わせる。
かごの中のオウムが脱出で大きな役目を担っていた。
ミナには双子の姉妹がいて、ガラス張りの小屋の壁が夜は鏡のようになり、自分が映る合わせ鏡になることにも通じている。
ダコダ・ファニングがいい。
湖のシーンの彼らのCGが、のっぺりしていかにもCGで、安っぽいカットがあったのは残念でした。
私が 私を 見つめてました
とりあえず、街から街へ移動する中で迷い込むような森なら、普通に地図に載せよう。
そして行方不明者多数なら封鎖しよう。
定番ではあるけど、近道しようとした主人公が出来心で入っちゃった、でいいじゃん。
それはさておき、人物描写が薄すぎる。
4人の関係性もまともに描けてないのに、モノローグで「揉め事が増えた」みたいに言われても…
ダニエルは取ってつけたように唐突に自分語りしだし、これまた急に未亡人キアラとロマンスを匂わせ。
この手の作品でそれは当然フラグなわけで、あっさり回収という情緒のなさ。
“鳥籠”での生活描写も足りておらず、何となく出来事だけ並べて数ヶ月経ったが、恐怖も疲弊も感じない。
一度も水場が映らなかったのもどうかと思う。
あの建物は鬼畜教授が建てたのだろうが、だったら何故あんなにウォッチャーズに都合のいい構造なのか。
教授はビデオを回しっぱなしで殺されたのに、300日目の動画は誰が保存したのか。
マデリンが教授の捕らえてたハーフリングなら、地下の存在知ってるハズでは。
主人公の特技(?)が脱出の鍵になるわけだが、絵を描くのとマッピングはまったく別物だよ。
結局あの真相だと車が消えた説明はつかないし、ウォッチャーズが森から出られない理由も不明。
などなどモヤモヤしながら鑑賞。
そこから太古の種族だの過去との対峙だの特殊な存在だの共存の未来だのと広げられても…
途中から、鳥籠の中身が鴉夜さまで持っているのが津軽だったら…なんて関係ないこと考えてた。
ジョン以外のウォッチャーズも服を着てください。
★2024年劇場鑑賞52★
やはりこういうのは何も情報を入れないに限る。
おもしろかった。ん?って思うところはあれど面白い
途中のミナが外側から見るシーンは進撃の巨人に見えてしまった
あと最後がああいう終わりならばダニエルを殺さなくても良かったのになぁ。
ダニエル殺すなら皆殺しエンドの方が面白かったかも。
まあ直近で胸騒ぎを見たからそんなことを思うのかもですけど笑
もののけ姫
面白かった。ホラーとファンタジーの融合みたいな。
設定やストーリーに多くの暗喩が込められているように思う。
森、闇、異類婚姻譚、鏡、双子、自然の征服・環境問題、地下、インコ、鳥籠…。
この辺がキーワードだろうか。
主人公は自分のせいで母親を殺してしまい、自分の双子の姉妹の顔に一生消えない傷をつけてしまったトラウマを抱えており、そのことに正面から向き合えないでいる。
このことと、人類が自然の象徴である森を破壊してしまい、人類と自然が調和していない状態であることが重ね合わされている。
①主人公(人類)と母親(森・自然)はかつて幸せな関係を築いていた
②主人公(人類)の愚かな行為により、母親(森・自然)を殺してしまい、そのトラウマが主人公を苦しめている
したがってこの物語は、森の人格的表現である妖精との和解を通して、主人公が母親のトラウマを克服する話だということになる。
<妖精が象徴するもの>
妖精というと小人に透明な羽をはやした無害な存在のイメージがあるが、アイルランドの民話などに出てくる妖精は日本でいう妖怪や鬼のような恐ろしい存在。妖精と結婚するという民話や神話(異類婚姻譚)が存在するところも、日本の妖怪と似ている。異類婚姻譚というのは、人間が自然を畏怖し、またその恵みに感謝していた時代の自然信仰的感覚が反映されている。人間が自然とコミュニケーションをとる方法として、動物や妖怪・妖精が人語を話す、という話が日本にもアイルランドにもある。たとえば日本には「おいてけ堀」のような、人外の者が魚や動物の捕りすぎを戒める話がたくさん残っている。
<3つのルールが象徴するもの>
主人公の思い込みや恐怖を象徴しているのではないか。
ルールを守っていれば安全、ルールを破れば危険、というのは、この映画の前半部が「安全な世界と危険な世界」という2つの世界を前提としており、ルールを破ることは2つの世界の境界をおかすことを意味する。
・都市(人間の世界)と森(自然の世界)
・人間と妖精
・光と闇
・昼と夜
・地上と地下
・「鳥籠」の中と外
ルールを守っている限りは安全だが、問題に対する根本的な解決はできない。物語はこの二分法的世界観の緊張をどう解消するか、ということがテーマになる。
そしてこの2つの世界は主人公の「顕在意識」と「無意識」でもあり、「無意識」にひそんでいるトラウマに主人公が向き合えない状況を表している。
2つの世界は相対的なものではなく、後者「観る側」が前者「観られる側」を支配し、主導権をにぎっている。
<鏡・人間に擬態する妖精・双子が象徴するもの>
灯りをつけたガラス張りの部屋が、外からは中が丸見えになり、中からは外が鏡になる、というのはうまい仕掛けだと思った。
主人公がガラスに映った自分自身の姿を見つめるシーンがとても印象的だが、つまり主人公が怖れているのは自分自身だ、ということだ。
そしてそれは環境破壊を重ねる人類全体についてもいえる。自然の姿は人間のありかたを反映する。自然を守ろうと思えば恵みを、ないがしろにすれば牙をむく。
<地下に脱出のヒントがある>
この物語の世界では、単にルールを守るだけでは状況を変えることができない。この世界に変化をもたらした主人公の行動は2つあり、どちらも「地下に行く」ことだったのが興味深い。はじめに地下に行ったときの結果は失敗に終わった。二番目に行ったときは成功した。何が違っていたのだろう?
<なぜ主人公のトラウマは克服されたか>
主人公の再生のプロセスが丁寧に描写されている。まずは、他人のトラウマ(罪、自分が悪人であると認めること)を聞くことにより、苦しんでいるのが自分だけではないことに気づくとともに、自分自身の状況を客観視する。次に、避けていた自分の過去(罪)を直視する。次に、他人に自分の罪を告白し、自己開示する。そして最後に、主人公の双子の姉妹に会うこと。顔に傷をつけてしまった姉妹は、今は子供をもち幸せに暮らしている。過去の罪にばかりとらわれていたが、現在の幸せに目を向けることができた。
このプロセスがうまく人間と妖精(自然)との和解と対応している。
①何を考えているか分からない、恐ろしいだけの存在
②かつては人間と幸せな関係を築いていた神のような存在だったが、人間によりその力を奪われた被害者
③人間と混血し、生き延びて人間社会で暮らしている子孫もいる
②を主人公が知ることは、妖精の正体を知り、人類の罪を認めることを意味する。
③は、主人公が妖精は一方的な被害者というだけではないことに気づき、和解の可能性を見出すことを意味する。
ここで、妖精が「自由」の象徴である「翼」を回復したことに重要な意味があると思う。
この辺の展開に何か既視感があるな、と思ったが、これはまさに「もののけ姫」とテーマと同じだ、と気づいた。人間がシシ神を殺してしまったことで、自然が神としてあがめられていた時代は終わり(原生林は破壊され)、そのあと、人はシシ神の首を返すことで森は復活したが、かつての森は永久に失われ、人工林となってしまった。しかし自然と人間は対立しつつも一緒に歩むしかない(「だが共に生きることはできる」)。
<インコが意味するもの>
二つの世界をつなぐアイコンではないか。
インコを追って異世界から脱出するというのは、非常に神話的だ。
人間が「鳥籠」から出ることと、インコが鳥籠から出ることが同時に起こっている。
「鳥籠から出る」のは、二分法の世界の解消を象徴している。
ペットは人間に飼われている動物なので、人間と動物を仲介する存在である。
また、インコは人間の言葉を話す動物でもある。
さらに、「ダーウィン」という名前。
「ダーウィンの進化論」は、人間と動物は分けられた存在ではなく、連続したものであることを示した説である。
「死んじゃダメ」というセリフも、「死にたい」と思っている人間には不吉な皮肉に聞こえ、「生きたい」と思っている人間にははげましに聞こえるという意味で面白い。
タイトルなし(ネタバレ)
マデリンの正体が妖精と人間のハーフでそれは教授が捕まえたウォッチャーズがもともとハーフだったと理解しましたが、捕まえたのがオリジナルのウォッチャーズで教授との間に子が生まれ、それがマデリンになったという解釈も可能でしょうか?
Year! めっちゃシャマラン
もはやジャンルの一つとして認めたい、シャマラン作品をカテゴリー化したいのだが何と呼べばいいのかをずっと考えていた。
黒澤映画と聞けば、あの脈々たる名作の風景が浮かんでくるし、ジブリ映画と聞くとトトロやらもののけやらがサッと脳裏に浮かぶ。ヒッチコックはサスペンスの巨匠。スピルバーグは既にスピルバーグという名前そのものが形容詞か。
まてよ、そうか。映画監督の名前を形容詞として扱ってみて、腹落ち感というか、人々がそれをイメージできるようになったら殿堂入りということか。
だとするなら、「~的」なんていう言い方、形容動詞化してみたとき、問題なく使用できればその監督の作品ジャンルは殿堂入りできるという、フィルタリング方法はどうだろう。
クロサワ的な映画。
ハヤオ的な映画。ふむふむ。
ヒッチコック的な映画。
スピルバーグ的な映画。
シャマラン的な映画。おー!
別に無理やりカテゴリ名を作らずとも、シャマラン映画はその名で既に形容できる文化へと昇華しているようだ。
パパシャマランでも、ママシャマランでも、ムスメシャマランでも、シャマラン作と聞いただけで、あの何か「謎」仕掛けがありそうで鑑賞後の帰り道でガッカリしたり仲間とツッコミどころを言い合ったりできるスリラー・ホラー映画。それをみんな想像しちゃう感じだ。
本作「ザ・ウォッチャーズ」の鑑賞前の期待感と、鑑賞後のモヤ残り感は、ムスメシャマランでもシャマラン100%の味わい。そこまで食べたい気はしないのだけど、口に入れたら結構美味しいから手が進んでしまうものの、次の日にそれを食べたことや味を忘れていそうな感じ。まるで居酒屋の突き出し料理のように。突き出しにはこんなにツッコミどころはありませんけどね。
沢山ありすぎて疲れるので、ツッコミどころを書くのはやめておこう。それに、ツッコミどころにいちいちツッコんでいくのは正しいシャマランの食べ方とは言えないのだ。激辛ラーメン店で激辛ラーメンを食べて出てくる汗に文句を言うようなものである。そのツッコミどころを全無視して、作品の美味しさだけを味わい切るのが正しいシャマランの食べ方なのだ。
今回のシャマランはメインのストーリーに加えて、デザートとしてエピローグまで付いてくるというお得感あふれる内容。やっぱりデザートは別腹というか、そのあたりはムスメシャマランの「やっぱりデザートつけようよー」的なこだわりが有ったのではなかろうか。そしてデザートは確かに有ったほうが良かったように思えた。
・・・。
ツッコミどころを書かないと言ったが、そしたら書くことが無くなっちゃた。
美味しかったなあ。
シャマランの次回作、パパシャマランによるコンサート会場スリラーも、今から楽しみなのである。
イニシェリン島の、、
シャマラン親子ということでホラーの構えで見ましたが、自然の美しいアイルランドのゴールウェイとアイルランドのどこかの森が舞台ということで、私はイニシェリン島の精霊をやや思い出しました。
調べてみると、イニシェリン島の精霊の舞台であるアラン諸島とゴールウェイは近い場所で、妖精の神話というのはこの地方では割と根付いている話なのかもしれない。
民俗学という観点から見ればファンタジーとしてまあまあおもろいかなというくらいでした。
ダコタ・ファニング目当て
で映画館いきました。
相変わらずかわいいですね。歳をかさねても、スクリーンの中で汚れていても素敵でした。
アイルランドと妖精って日本人でもなんとなくノルウェーとならんで密接な感じすると
思っているもんですから、まったく違和感なくストーリーに没入していきました。
舞台自体が深~い森ですし、湖とか川にかかる橋とかの雰囲気、そして知っている土地の
名前がでてきたりしたので最後まで
ぶれないというか、これで宇宙人だったら怒るよ~とか思いつつ楽しみました。
原作マンガとアニメの印象がごっちゃですけど、デビルマンを想起させてくれました。
古文書(?)みたいな絵の中では、白くて羽の翼があって、人間と共生しているときは
天使みたいにみえました。でも人間にだまされて地下に閉じ込められて、黒くて異形にかわった後は
悪魔ぽく見えます。マデリンが正体を現すとき、台所に虫がうごめいたりしているシーンは
ほかの映画だと悪魔や死霊がでてくるときの前触れな気がしますし。
デビルマンは悪魔(デーモン族でしたっけ)の力を身につけた人間の
葛藤の物語です。人間を守ろうともするんですが、人間も悪魔より業が深いので、、、
ダニエルやキアラやミナを守ろうとした時、ひび割れた鏡の壁の前のマデリンはデビルマンだったなーと
真相がわかった後にはさみこまれた回想シーンから想い起こしてしまいました。
デビルマンもハーフでしたから。氷河期に氷に閉じ込められたデーモン族も悪役にしては征服のモチベが
しっかりしてますしね。
鑑賞後ですけど、
氷河といえば、太古のばい菌やらウイルスやら生物が温暖化でどんどん溶けて復活するなんて記事を
観てたので、森林も伐採をつづけると変な穴ぼこを発見したり、パンドラのハコの蓋をあけちゃうんだろうな、
と想像しました。
この監督・脚本さん、原作の方の映画はまた観たいです!
シャマランブランド無くて良かったのかも
だいぶ覚悟して、ハードル下げて見ましたが意外と良かったです。
なんで?なんで?は沢山ありますが、この程度ならトークトウミーとかと同じようなレベルだと思いました。シャマランブランド無くても、無い方が正当に評価されたかも。
妖精の成れの果てというのも、そう来たか!と。これが宇宙人や、モンスターだったら寝てました。個人的な感想です。
あの小屋どうやって作った?あの説明じゃなぁ。なんで実在の人に化けたがる?化けなかったらバレないのに。化けるために毎晩見てた?やっばシャマランブランドでしたね。
鳥の飛び去る方へ。
地図には載ってない森に迷い込んだミナの話。
職場のペットショップから動物園に鳥を届けてくれと頼まれたミナ、鳥籠に鳥を入れ車である森へ入っていったがスマホにノイズと車の故障で足止めに…、助けを求め車外に出ると森の中を走り去る白髪女性の姿が、その女性を追うと鉄の扉を開けた白髪女性が「助かりたければ入れ」と始まる。
鳥籠と呼ぶ建物に住むマデリン、キアラ、ダニエルとその森での三つの掟、「監視者に背を向けない」「常に光のあたるところ」「ドアを開けてはいけない」…、建物の一部の壁がマジックミラーの様になってて、夜はその森に住むウォッチャーズと呼ばれる者に自分の姿を見せると…、もとネタはMM号?何ておふざけをいれながらも、その森に住む何かが中々姿を見せず、最初は恐怖からの被害妄想か何かなんて思ったけど…。
結局この細長い人ってハーフだったんですね、見た目は怖くなかったけど音で少し驚かされた感、怖さとしては個人的にはもの足らなかった。ミナ演じたダコタ・ファニングさんは最近またよく作品で見掛けますね~素敵!
人間の完コピは難しい
Mナイト・シャマランの娘さんが監督という事でどんでん返しを期待したが、なるほどという感じで悪くはなかった。
長い間虐げられ?表に出て来れなかったモノ達が虎視眈々と人間との入れ替わりを狙う、という大きな筋としてはなんとなくジョーダン・ピールの「アス」を思わせる。
監視される側のルールも面白く、毎日全身を見せ、時にはダンスを踊るなどはコピーを完全なものにするためのものだったという発想は面白かったし、混血の存在など興味をそそる設定も秀逸だった。
教授の研究室にある資料や写真を見て状況が明らかになって行くのだが、それまでとは明らかにテンポが早くなるのでまだ何かあるのかなと思ってしまった。
森を出てからたたみかける様なバタバタした感じがもうちょっとだった。(バスでも何か怖いことがあると思ったしw)
妖精?を閉じ込めてる蓋みたいなのはご当地マンホールみたいで可愛かった。
主演のダコタ・ファニングは子供の頃の印象が強く、成人してからもそれなりに活躍してはいるがかつて美少女だった面影が無くなっているのが残念だった。
(妹のエルの方がビジュアル的評価は高いですね)
世界観は最高だが、、、
オープニングからの不穏さは、この先の展開が
楽しみになる良い引き込みでした。
中盤少し超えるあたりまで、
ウォッチャーズが謎の存在でありながらも、
姿形が少しずつハッキリしてきたり、と
少しずつ解明されていくあたりは、
スリラーのみならず、ミステリー要素も強く
大変面白かったです。
ただ、籠の地下で全貌が明るみに出て、
そこからの妖精🧚と人間の太古の時代からの
共生的な流れは、現代の多様性重視にもつながると
思いましたし、俄然雰囲気が変わったなと感じました。
私としては一貫して不条理スリラーだと
より楽しめましたかなと思います。
私は、ウォッチャーズ=宇宙人との仮説を
予告を見て立てていたのですが、
全然違いました(笑)
主演のダコタ・ファニングは良かったです!
エルのお姉さんですが、姉妹ともファンです。
次回作にも期待しています。
妖精怪奇譚
シャマラン娘の作品なら観てみようかと…
まあ、おおよその想像通り得体の知れない妖精か何かの怪異を描いた、文字通りやたら薄暗いダークホラーですかね。
映像や音楽など父親譲り?の仕上がりに感じましたし、思ったより観れたのですが…
個人的にはモンスター?の容姿や描写などがもう無理…既視感しかありません。
どうして海外モノは同じ様なもんなんでしょう?
バカの一つ覚えみたくすぐに「キシャーッ!」と大口開けて叫ぶし…ホンマ好きですねぇこんなの。
この辺りがマイナス。
父よりは話をきちんとまとめているが、突っ込みどころ満載は伝統芸のような気がする
2024.6.22 字幕 イオンシネマ久御山
2024年のアメリカ映画(102分、G)
原作はA・M・シャインの『The Watchers』
森の中の奇妙な小屋に迷い込んだ女性を描いたスリラー映画
監督&脚本はイシャナ・ナイト・シャマラン
原題の「The Watchers」は「観察者たち」という意味
物語の舞台は、アイルランド西方に位置するとある田舎町
そこでペットショップの店員として働いているミナ(ダコタ・ファニング、幼少期:Hannah Dargan)は、店主バーク(アンソニー・モリス)に頼まれて、インコをベルファストの顧客のところに届けるように言われた
彼女は幼少期に母親(Siobhan Hewlett)を事故で亡くしていて、双子の姉のルーシー(ダコタ・ファニング、幼少期:Emily Dargan)とは疎遠になっていた
翌日、ベルファストに向けて出発したミナは、奥深い森を突っ切ることになったが、その途中で車の故障に見舞われてしまう
助けを探しに付近を捜索すると、今度は車が消えてしまった
森には「回帰不能点」と書かれた奇妙な看板があるものの、それ以外には何もない
しばらくして、人影をみつけたミナはその人物を追う
その人物は、ある小屋に彼女を誘導し、中へと招き入れた
その人物はマデリン(オルウェン・フエレ)という老女で、小屋にはキアラ(ジョージナ・キャンベル)という若い女と、ダニエル(オリバー・フィネガン)という若い男がいた
そしてその小屋は、一面が鏡のようになっていたが、外からは中が見えるようになっていて、夜になると「ウォッチャーズ」という謎の存在が、自分たちを観察しているというのである
映画は、この小屋の存在やウォッチャーズと呼ばれる謎の存在を紐解く流れになっている
あっさりと、ウォッチャーズは人外の何かであることがわかり、小屋に関しても設立した教授(ジョン・リンチ)の存在が暴露される
そして、教授はウォッチャーズ(=妖精)の存在を研究していて、多大な犠牲のもとに、この小屋を作ったということがわかる
これ以上は完全ネタバレになるので避けるが、この「妖精」と人間の関係と歴史、そして「もうひとつの存在の意味」について暴露されるのが後半になっている
数々の疑問が浮かぶが、一応はまとまっているようには思える
とは言え、それじゃあマデリン自由やんという突っ込みが入ってしまうので、その事実自体もマデリンは知らされていなかったと解釈するしかないのかは微妙なところになっている
マデリンは自分を外に出してくれる存在を探していたことになるのだが、ぶっちゃけると自分で勝手に出られたのではないか、と思ってしまうので、このあたりを突っ込んではいけないのかな、と感じた
いずれにせよ、プロデューサーに父親が入っているためか、作風も似ている感じがした
謎の物体の正体もそっち系ですかという感じになっていて、おそらくはアイルランドの伝承などががベースになっているようも思えた
このあたりは調べこんでいけばわかると思うが、ざっくりとそんな話がありそうだよね、で終わらせても問題ないのだろう
全71件中、41~60件目を表示