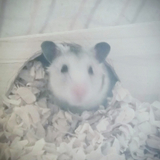35年目のラブレターのレビュー・感想・評価
全244件中、161~180件目を表示
作品内容は良かったです
夫婦の思いやりや気ずかいなど物語は良かったです。
ただ観客には老人が多くうるさい
あれは遺書やでとか意味不明の考察を後ろの2人の老人がうるさかったです
また持ち込みのお菓子が臭い
ビニールバリバリうるさい
また変なお菓子で臭いが強烈
本編以外で不快なのはワイスピ以来です
あと気になったのが若い時代の夫婦と現代夫婦の身長差かな
余りにも違いすぎる
それは製作時に課題にならなかったのかと
あきらかに変、最後のシーンで写真並ぶけどおかしいやん
ただ原田知世さんは娘かと思うくらい見た目が美しいです
外野が良ければ楽しめると思います
35年間、変わらぬ愛を貫いた夫婦の姿を描いた作品。 本年度ベスト!
予告編から泣ける映画と予想されるも案の定、泣いてしまった。
隣の若い女性は終始泣きっぱなしでちょっと映画に集中出来無かったのが悔やまれる(笑)
寿司職人の西畑保。
タイプライターで原稿を打つ皎子(キョウコ)。
この夫婦の愛に溢れたストーリー。
若い保と皎子を重岡大毅&上白石萌音さん。
老けた保と皎子を鶴瓶&原田知世さんが担当。
世代の異なるストーリーを4人で演じ、2つのラブストーリーが観られた感じのお得感(笑)
ある理由で読み書きが出来ない保。
職を探すも断られ続け、やっとお寿司屋で働く事が出来、職人として成長して行く感じ。
そんな中、お見合いで上白石萌音さん演じる皎子と結婚する展開。
保が読み書きが出来ない事を皎子に隠し結婚したけど、それを知った皎子が心の優しさが素敵だった。
保が読み書きが出来るよう一念発起して夜間学校に通う事に。
安田顕さん演じる谷山がバツイチだけど、とても優しい素敵な先生。
学校での人と顔を合わせない生徒の素敵なエピソードも良かった。
保と皎子の2人の娘も優しく成長した感じも印象に残る。
関西系のギャグも多め。
クスッと笑えるシーンが気が利いてて好印象。
本作のタイトルでもあるラブレター。
思ってたのと違って騙された感じがしたけど、一番泣かされたシーン。
ラストで4人の保と皎子がベンチに座っているシーンもとても良かったです( ´∀`)
凄く心があたたまる映画です!!
年に1度はこういう映画と出会いたい
キャスティングが最高にいい感じです。実話ベースで、変にストーリーが作り込まれていないのがいい。とにかく主人公夫婦の人物像を描くことに集中されたんだと思いました。
若い時(重岡大毅さん、上白石萌音さん)と晩年(笑福亭鶴瓶さん、原田知世さん)が似ても似つかない、みたいな指摘が散見されますが、物語を感じる上で見た目は問題じゃなくて、人物がちゃんと描かれていて共通性があることが大事だと思うので、今回はぜんぜん違和感なかったです
というか、一見違っていそうな俳優たちの組み合わせがピッタリ来る、というのが逆にプロデュースの妙ってことですよね
「読み書きなんて長いこと生きてれば自然にちょっとずつ覚えられるんでは?」なんて安易に思いがちですが、多分そうではないことを映画を見ていて実感しました
一般的には小学生低学年頃までにひらがな、カタカナ、簡単な漢字...と覚えていくわけですが、これは脳の発達の過程と同時進行なんだと思います。つまりこの過程で「文字の覚え方を覚えている」訳で、これを経て育った人は大人になってから外国語の読み書きを学ぶこともできるでしょう。しかしそうじゃない場合、この"回路"を作るのにとても時間がかかるんだろうな、と。でも、時間はかかるが不可能じゃない。この映画は実話なので、実際にそうなんだろうな、と実感を伴って理解できるんです
しかし、そういう科学的な仕組みを描くのではなくて、登場人物たちはその苦労や辛さを直感的に理解して寄り添い、助け合う。そういうことが、実際のエピソードをベースに丁寧に描かれているので、観る者の心を動かせるのだと思います
世に実話ベースの映画は沢山あります。しかし全てのシーンが実話のままではない訳で、当然フィクション部分が加えられます。ここで、実話の本質を捉えないシーンやプロットを追加してしまい、ちぐはぐなストーリーになっている映画は非常に多いと思います。
というか、現実は、私が物語の"本質"だと思っているモノが、その作り手にとってはどうでもいい枝葉だ、ということしょうけど。しかし、それが映画の好き、嫌いに直結するのです。
そういう意味で、この作品はとても好きな映画だし、出演者をはじめ作り手の皆さんが描きたかったことがちゃんと私に伝わった気がします
温かい気持ちになれる良い映画を見た
昨年から試写会で観ていて、笑いを挟みつつも涙が止まらない作品で、公開を楽しみにしていました。
幼少期の環境から文字の読み書きができない西畑保さんの実話を元にしたお話。
ストーリーとしては定年後から夜間学級で文字を学び奥さんへラブレターを贈るというシンプルなもので、特に派手な演出もないのでさらっと物語に入り込めました。
・長年支え合ってきた夫婦の愛
・何歳からでも学びを始められるんだという勇気
・文字を使って言葉を伝えられる尊さ
どなたかの映画評でも書かれていましたが、見終わった後にこれらの温かい感情を無理やり押しつけられることなく自然に感じることができます。
秦基博さんの主題歌もこの物語にぴったりの優しいメロディに歌詞で、エンディングで更に作品の余韻に浸ることができました。
インタビュー記事や舞台挨拶を見て、夫婦役を演じた2組が実際に皎子さん役が保さん役に寄り添って信頼して役を作り上げていったと聞き、まさに演技にもその信頼関係が見え、本当にこの作品に出会えて良かったなと思えます。
色々な世代の方に観てもらい、家族愛や何かを頑張ることの尊さを感じるきっかけになって欲しいです。
献身的な奥様にほっこり
三つの「さん」の夫婦愛
実在の主人公は「2.26事件」の年、
戦前の生まれのようだが、
その頃は貧しさゆえに
読み書きができない人は多くいたのではないか。
長じて一念発起し、彼のように努力する人、
識字の力がないまま亡くなる人と、様々だったろう。
とは言え、これは必ずしも過去のことではない。
日本の識字率はほぼ100%と言われてきたようだが、
自分は実際に字が読めない若者を十年以上前に見たことがある。
彼は脇に居る人に文章を読み上げて貰い、
回答していた。
勿論、全ての文字を読めないのではないだろうが。
そしてスマホが発達した今では猶更、
字が読めなくても機械が代行してくれる。
目で見るものと音が一致さえすれば
なんとか暮らせるほどにテクノロジーは発達している。
『西畑保(笑福亭鶴瓶)』が定年後に一念発起して
夜間中学校に通うようになったのは、
三十年以上寄り添ってくれた妻『皎子(原田知世)』にラブレターを書くため。
読み書きができない『保』の目になり
手になり支えてくれていた彼女への恩返しが
一つのモチベーションになる。
物語りは、彼の努力を一つの柱とするのだが、
もう一つの柱は夫婦間の愛情の描写の麗しさ。
「おはようさん」
「おつかれさん」
「ありがとうさん」
の三つの言葉が夫婦間で頻繁に交わされる。
なんという心地好い響きだろうか。
読みかけができないことを隠しての結婚。
真実を告白するまでの葛藤。
全てを受け入れ、二人で生きて行くことの決意。
山谷を乗り越え、
裕福ではなくとも、幸せが溢れる世帯は、
見ていて羨ましい。
しかしそうした二人を不幸が襲う。
これは演出の上手さと思うが、
画面に映されていたのは
『保』が字を書く練習をするシーンが主。
学校に通うようになった目的もそこにあったはず。
が、本作の一番の見せ所は、
彼がある手紙を読むところにある。
ここで観客ははっと気づかされる。
「書く」と「読む」は同じ比重であり、
共に人を生かすためのものであることを。
読めることで、主人公が再生できたことを。
『笑福亭鶴瓶』は、一見良い人も、
実は裏や影のあるキャラクターを演らせると
抜群の味を出す。
〔ディア・ドクター(2009年)〕
〔閉鎖病棟-それぞれの朝-(2019年)〕
あたりが好例か。
本作も合わせて、また一つ良い役柄が加わった。
言葉に尽くせない
何となく、観てきたら。。
時をかける少女
キャスティングが素晴らしい
キャスティング◎
事実を元にされているのですね
予告からだいたいストーリーが予想できます。鑑賞しながら、展開もたぶんこうなのだろうと予想できます。
その予想の範囲内ではありますが、結局泣けました。
字が読み書きできるベースで見てしまいますが、そう言われればそうなのかと気が付かされました。
若い時の重岡大毅さんと上白石萌音さんも良かったし、鶴瓶さんと原田知世さんも良かった。
冒頭、原田さんが「お父さん」と呼ぶので、鶴瓶さんは旦那さんではなくてお父さんなのだと思ってしまった。
それぞれ、適役だと思いますがさすがに歳が離れすぎですかね。
最後の方は、感動演出がちょっとやりすぎ感を感じてしまいました。創作にしてはやりすぎと想ってしまいましたが、事実を元にしているとの事なので、本当なのかもしれませんが。
観終わると自分の心がキレイになった気がする
あかんこんなん泣くしかないわ
勇気と愛で心を満たしてくれる最高な作品に出会えた👍
定期的に泣ける映画を観るようにしているが、
定期的に泣ける映画を観るようにしている。号泣すると脳がデトックスされ、アクション映画を観る3倍(※当社比)はスッキリするから。
「この題名で泣けないなんてことないだろ」と事前情報なく観劇…泣き所はなかなかやって来ない。それは最終盤に固め打たれ「そうきたか」展開もあり、仕立てとして泣ける構造ではある。ただ要所での演出意図がわかりにくく・鶴瓶さんの訥々とした演技・更には原田知世さんの抑制された演技で号泣までは至らず、私はやや泣きであった。もちろん気持ちよく号泣された方もおられることと思う。ストーリーはすごく良かったが演出にやや難ありで粗が目立ってしまった気がする。
例えば。主人公は夜間中学に20年間通学するのだが、月日の経過を示す演出が希薄でかつ定年退職後の夫婦の風体がぼぼ(というか全く)変わらないため時間を圧縮して見せられたような感じがした。教師(安田顕)が主人公に無駄な努力などないと言い聞かせるシーンがあるが、やや取ってつけたように感ずる。演劇の台本ならそれでもいいが、映画なのだからそこはセリフに頼るのではなく演出で時間経過とそれに伴う喜怒哀楽を表すべきではなかったか。
さて、本作品は実話を元に制作されている。ネットで西畑さん御本人のインタビュー記事を読むことができるが、驚くことに殆どの設定・エピソードが実話の通りなのだ。もちろんそのままだと尺が足りないので膨らませた部分はあるだろうが。塚本監督(脚本)の、西畑さんと皎子さんの生き様をまんま切り抜きたいという想いが伝わってきた。そのうえで、その志と映画作品としての出来栄えの両立で悩まれた点は多かったのだろうと推察。
全244件中、161~180件目を表示