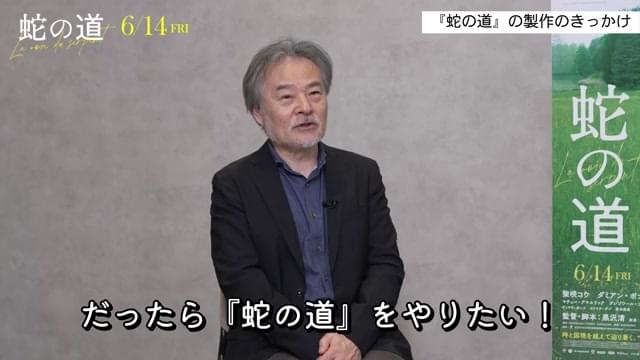「ルンバすら不穏なムードを掻き散らす」蛇の道 ドミトリー・グーロフさんの映画レビュー(感想・評価)
ルンバすら不穏なムードを掻き散らす
セルフリメイクの元となったVシネマでは、幼い娘の復讐にとり憑かれた男(香川照之)と彼を手助けする謎の塾講師(哀川翔)の、男ふたりがW主人公だった。リメイク作では、この哀川翔の役どころがフランス在住の心療内科医(柴咲コウ)へと置き換えられ、彼女が実質的な主人公役を担う。
その点で本作は、蓮實重彦氏が黒沢監督の前作『スパイの妻』評で「…『贖罪』(12年)シリーズ以降、監督の描くものは、予測不能な女たちの変貌ぶりの描写へと推移している。」と書いた、まさにその系譜に連なる一作となっている。今作のキモも、柴咲コウによる「予測不能な女」の「変貌ぶりの描写」にあるといえよう。
野ジカのような柴咲コウの身のこなしと比べて、ガタイの大きな共演者たちは総じて緩んでみえる。柴咲は、そんな彼らの肉体を生死にかかわらずモノ扱いする。ずらりと日仏の実力派俳優を並べてみせながら、彼女の「身体性」その一点突破に賭けた本作の「思い切りよう」に正直、驚いた。
復讐に手を染める女でも『マッドマックス:フュリオサ』のアニャ・テイラー=ジョイのようなストレートさや涙はここにはない。虚無の淵から時おり憎悪を覗かせる柴咲コウにとにかく目を見張らされる。
他方、オリジナル版で香川照之が演じた役のダミアン・ボナールは、どこか自らの体躯を持て余し気味にみえる。夜道で少女を凝視し続けていた香川照之の“闇の顔”はここでは影を潜める。ボナールが路駐現場から小走りで逃げ去ろうとする姿など、まるでMr.ビーンみたいだ。
元警備員役のスリマヌ・タジは007シリーズのリチャード・キールのようにいかつく、あの小柄なマチュー・アマルリックでさえ肉厚感が漂う(余談だが、マチューやグレゴワール・コランらが嬉々として演じていた「横並びの死体」には思わず吹き出してしまった)。
そのほか、ヴィマラ・ポンス、青木崇高、西島秀俊らは、ぜいたくな配役というか無駄遣い感がハンパない。
大まかなストーリーはオリジナル版に準じており、Vシネマにあった数々の印象的なシーン——例えば、人質が詰まった寝袋を引きずりながら野原を駆けてゆく遠景、壁に寄りかけられた3つの死体、不意に再生が始まる複数のビデオモニター、殺害映像を凝視する男の顔のアップなども本作で“再現”されている。
しかし、両作の「空気感」はまるで違う。
Vシネマの方は、一見いかにもチープな人物・場所設定のなかで時系列の再構成や反復を巧みに織り交ぜた脚本の妙(初期のクリストファー・ノーランみたい)が見事で、加えて哀川翔が乗り回すママチャリ、路上に書かれた謎の数式、仄暗い室内や夜道、ザラザラした質感のビデオ画面…などのディテールが、白昼夢のようないかがわしさとホラー・テイストを強めている。
一方、リメイク版を支配するのは、漠とした虚無感が支配する不穏なムードだ。そこへパリの石畳とアンゲロプロス監督作のような曇天が、本作に硬質な品格をもたらしている。
自分にとって、素直にB級映画的な愉しみに浸れたのが1998年公開の前作だとしたら、逃げ場のない虚しさが覆いつくす世界を垣間見てしまったのが本作だった、といえるかもしれない。