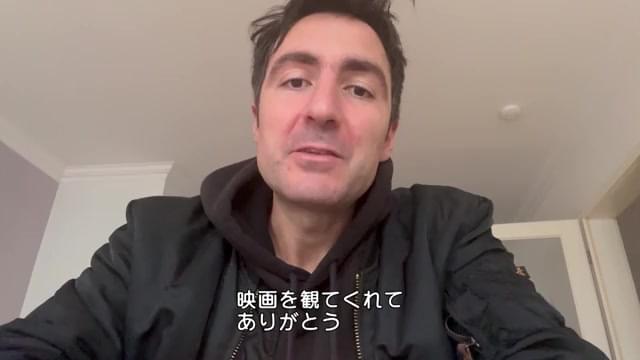ありふれた教室のレビュー・感想・評価
全125件中、41~60件目を表示
教員希望者は絶対に観ないで下さい
古典的不条理劇風。
むか〜し、若かった頃、渋谷のジャンジャンで中村伸郎の「授業」を観たのを思い出しました。
移民の子どもたちが多いドイツの中学の新任先生の担当は数学でした。
おいしい給食の甘利田先生も数学教師ですが、授業シーンは皆無😋
0.999999999は1ではないことの証明なんて、難しくてどうしていいかわかりません。
トラブル処理担当のトラブルメーカー先輩教師に引っ掻き回され、こまっしゃくれた生徒たちに翻弄され、幻覚を見るほどにヤラれてしまう美人先生。体育授業中にノートパソコンの画面スリープ中に動画撮影を起動させ、おとり捜査したことがアダになってしまう。
おいしい給食では給食費がなくなったと訴えた女子生徒に対し、全員に下を向いて目を閉じさせたままで、手を挙げさせる。みんな甘利田先生に従います。信じているからです。
学校全体のルールが不寛容主義の徹底ってなによ?
校長先生の威厳もスゴいですが、殺伐とし過ぎ。
監督はトルコ系移民のドイツ人の男性。
登校停止処分を破ると警察介入なんですね。なんですか、あの最後のシーン。
ライオンキングか!
エヌエッチケーの解説員のひとが取り上げて紹介していたので観ました。「怪物」よりはおすすめですが、教員希望者にはお勧めしません。人手不足で辞めさせてももらえないんだから。
サービスデーでもない新宿武蔵野館にラッパー風の若い男や外国からの留学生らしいひとが結構多く観に来ていて、終わったあとも不条理劇の続きなのかなとちょっとアセりました😱
怖い効果音は関心領域とほぼ一緒。
ドイツ映画だから?
スリリングな「社会の縮図」としての学校。ラストは「投げっぱなしジャーマン」な印象も。
端的に言って、面白い映画だったけど、
みんなは、あのエンディングで良かったのかな?
なんか、あまりに話の途中でぷつっと終わっちゃったような……。
個人的には、「最後にクラシック(メンデルスゾーンの『真夏の夜の夢』)かけたら、それだけできれいに終われると思ってるんじゃないだろうな?」と、ちょっと思いました(笑)。
とはいえ、先が読めない楽しさがあって、
本当によくできた脚本だというのは確かで。
ヒリヒリ系の学園ドラマとしては、いくつかの新機軸があって、
①もめ事の発端が子供ではなく、大人の置き引き
②その大人の息子が在学中でキーパーソンになる
③クラスが多人種であることが徹底的に強調される
④中1は「ほぼ大人並みの存在」として扱われる
といったあたりは、僕にとって大変新鮮だった。
この物語のキモは、「置き引き犯」と目されるおばちゃんの存在だ。
どのキャラクターも自らの正義を信じて「正しく」動こうとしているのに、だんだんと食い違って、いつしか大変なことになっていくというのが本作の大筋だが、その「変異点」として機能しているのがこのおばちゃんだ。
ここには制作者の仕掛けた「罠」が存在する。
客観的に見れば、99%置き引き犯として「有罪」。
それなのに、演出上は「無罪」としか思えない言動で、
自分はやっていないと言い張り続ける。
この矛盾した二つの属性を付与することで、
作り手は作品に「歪み」を生じさせているのだ。
しかも、犯人を見つけるためにヒロインが採った「手法」自体が疑問視されるために、「なぜ映っていたのか」「服を揺らして何をやっていたと主張するのか」「他に同じ服を着た人間はいなかったのか」といった、肝心の捜査・追及がまったく成されない。
これももう一つの、物語を支える「理不尽」だ。
われわれ視聴者は、「証拠上はどう見ても犯人にしか思えない」のに「どう見ても犯人とは思えない挙動をとる」女性にとまどわされながら、その「変異点」の異常性ゆえに周りの人々がきちんと機能できなくなっていく様子を、ただ外から見守るしかない。
要するに、監督&脚本は、「ほぼ絶対的なクロの証拠」と「通常のドラマならシロの演技」を掛け合わせたうえで、その矛盾・対立する要素を敢えてそれ以上「アウフヘーベン」しないで、宙ぶらりんのまま解決しないという「ギミック」を用いて、本作の混沌を生み出しているわけだ。実に映画的で、頭の良い仕掛けだと思う。
― ― ―
ただ、若干乗り切れなかったのもそこにひとつ理由があって、要するに、なんでみんなガッツリとコソ泥ババアを追い詰めないで、相手に反撃なんかさせてるんだ?ってのは、最後まで違和感として残ったんだよね。
個人的には、学園内部で盗難事件があったとして、隠しカメラを仕掛けることが悪手のように言われる筋合いは1ミクロンもないと思うし、それを責められる筋合いもないと思う(これは児童の万引きではなく、大人の起こした明快な窃盗事案であり、僕なら大っぴらに同僚全員に何があったか話したうえで、速攻で総務から警察に連絡させますが)。
それに、録画にだれかが映っていたのなら、それこそ徹底的に追い込むことにも、なんら抵抗を感じない。証拠としても、もちろん有用だし、有効でしょう(僕なら、やり口がまずいと言われたくないので、職員全員にやはり起きたことを共有したうえで監視下に置き、現行犯逮捕を目指しますが)。
おばさんの犯罪の内的調査結果を確定させずに善後策を講じつづけても、得るものなど何もないし、犯罪者に対して隙を与えることになってしまう。それなのに、なんで先生方はみんな「本当は何が起きたか」を詰めようとしないのか。
不寛容主義が、きいてあきれる。
たぶん、背景にあるのは「お国柄」だ。
ドイツならではの「後悔」と「反省」と「トラウマ」。
そう、ドイツ人は皆、ナチスや秘密警察シュタージによる「相互監視」と「密告」の制度運営によって、自分たちが私的に監視し合い、密告しまくっていたことに対する、強烈な罪悪感と恐怖感から未だ抜け出せていないのだ。
だから、善良な主人公の女性教師は、自分のやった「盗撮」という行為をアンフェアだと考え、周りの教師たちも不快感を隠さない。彼らのなかでは容易に、相互監視と密告によって個人情報が国家に搾取されていた過去のおぞましい経緯が想起されるからだ。
戦後のドイツ映画を観るときに、ユダヤ人虐殺に対する深い悔恨や、二度の戦争における敗北に起因するある種の劣等感に加えて、「自分たちはかつて、国家のために隣人を平然と犠牲にしてきた民族だ」という恥の感覚に彼らが今も囚われているという部分は、決して忘れてはならないポイントだと思う。
― ― ―
なんにせよ、最初に言った通り、本作の終わり方については僕個人は否定的。
本当に何も解決していないし、何も明らかになっていないし、これからどう転ぶかもわからない。
もちろん意図的にそうしたということなんだろうけど、こういう「起・承・転」だけで映画を放置するのが本当に誠実なやり方なのか。
結末をつけないことで、楽をしたり逃げたりしている部分は本当にないのか。
「実際には教師と子供のあいだには、しっかりとした心の絆が生まれていた。彼女がやってきたことは間違いではなかった。真摯な思いはしっかり伝わっていた。一方で大人とちゃんと対峙して戦った少年も立派なヒーローだった」からといって、この大騒動にまでなってしまった件に結局のところ、どう落とし前をつけるつもりなのか。
そこの道筋すらつけずに、「やりたい部分はじゅうぶんにやり切りました。あとはすべて蛇足みたいなもんです」と、音楽と演出の力を借りて映画を終わらせてしまうのは、いささか手前勝手な振る舞いであるように僕は思うわけだ。
たぶん監督たちにとって、本作の「教室」は、文字通り「社会の縮図」なのだ。
ちょっとした問題が、世論の「分断」を生み、対立と抗争が発生する。
そこには人種問題や、民族間での思考の違い、ジェネレーションギャップ、支配者(教師)と被支配者(生徒)の関係性など、さまざまなフェイズの問題がからんでくる。
誰もが自分の「正義」を信じながら、お互いの認識には「齟齬」が生まれ、しだいに対立と分断は無視し難いものになっていく。
さらにはSNS世論やジャーナリズム(ここでは学生新聞)が分断を加速させ、深刻化させる。そのなかでも、当事者たちは、「議論」と「寛容」の精神をもって誠実に物事に対処していくしか手がない……。
そういった「社会の縮図」として教室内を規定しているからこそ、「この問題には終わりがつかない」。すなわち、ここでは「盗難事件」が「宗教対立」や「領土問題」の「小さなひな型」として扱われているが故に、本家本元が永遠に解決しない事案である以上は、こちらもおいそれと解決篇をつけるわけにはいかないということになる。
「真相の探求」についても、各勢力によるバイアスがかかって「本当に正しい解答など最初から見いだせない」というのが社会の常であるから、本作でもきちんとした調査・追及は行われない。
だから、この映画は「尻切れトンボで終わる」しかない。
それはわかっている。
わかってはいるが、一本の映画としてはやはり、こういうのは「投げっぱなしジャーマン映画」に思えてしまうわけだ(ドイツだしね)。
以下、雑感。
●カメラワークとしては、少しダーレン・アロノフスキーの『レスラー』や『ブラック・スワン』を思わせるような、後ろから常に尾行している感じのバックショットが印象的。
ヒロインは、常に小気味よいテンポとリズムで学校内をてくてく移動するので、その後ろ姿を追い続けるカメラワークもまた、いきおいテキパキとしたものになる。
それから、極端なアップ。これもアロノフスキーっぽい。
総じて、テンポと切れのよいカット割りと、不安を煽るアングルのアップの組み立てで、緊張感と疾走感のある演出が貫かれており、そのぶん、終幕まぎわに挿入される「静謐な瞬間」や「無人の教室」といったシーンも非常に効果的だ。
アロノフスキー風の窃視感覚でヒロインを追い続けるカメラは、次第に追い詰められ、精神の均衡を喪っていく彼女の心理状態をつぶさに描き出してゆく。まさに『ブラック・スワン』でも採られていた手法だ。最近では『TAR/ター』でも似たようなカメラワークが散見された。『TAR』は「女王の失墜と混乱」というテーマにおいても本作と通底する部分が大いにあり、その撮り方を参考にしている可能性は十分にある。
●教室内の様子は、日本人の僕にとってなじみのある雰囲気とはだいぶ異なっていて、異文化体験として新鮮。でも僕が知らないだけで、今の日本の学校でも「多人種」化はずいぶんと進んでいるのだろうし、授業の進め方も今は日本でもこんな感じでやってるということもあるかもしれない。
ただ、学校新聞に関しては、ここまで生徒の自治が認められて、教師がかかわることなく取材と記事づくりが行われているのかと、結構びっくりした。
総じて、子供を子供として扱わずにきちんと相対しているのが伝わって来るし、子供たちも結構な知性で団結し、動こうとしていて、まあまあ普通に感心する。すくなくとも自分が中学生の頃は、学内自治なんてしょせんは絵空事で、大半の物事は最終的に担当教師の理念と誘導のもと決めていたからなあ(笑)。
このへん、ドイツらしいといえばドイツらしいともいえるし(ドイツには「ディスカッション文化」という言葉があるらしい)、さきほどの「社会の縮図」論でいえば、もしかすると「労働組合」のメタファーみたいな部分もあるのかもしれないなあ。
●終盤で、追い詰められた女性教師がトイレでゴミをぶちまけて袋に顔を突っ込んですうはあすうはあ呼吸するシーン。あれ、知らないで観たら単に頭がおかしくなってるだけのように見えるかもしれないが、一応あれは「過呼吸」を起こした際に採られるオーソドックスな対処法のひとつであり、むしろ主人公が自身のパニック発作にも、ぎりぎりのところで冷静に対処できていることを占めすエピソードと考えるべきだろう。
●たった一人の叛乱を起こし、子供ながらに母を守るため教師と対峙してみせるオスカー少年は名演技。こういう「ひとりぼっちの反抗」を賞賛する機運が、欧米ではたしかに高いよね。
個人的には、組織に外から「抵抗」するよりは、組織の中枢に上り詰めて(もしくは中枢から信頼を受けるご意見番や黒幕の立場を立脚することで)内から「支配」することのほうが有効だと考え、実際にそうやって人生を送ってきた人間なので、こういう「自暴自棄」を評価する気にはあまりなれないんだよね(笑)。
●先生が子供と一緒に「あああああああ!!!」と大声を出し合うシーン。
まったく同じものを、ついこのあいだ『胸騒ぎ』(善良なデンマーク人夫婦がろくでなしのオランダ人夫婦のもとでコワい目に遇う映画)で観たばっかりだが、ヨーロッパ北部地域では、ストレス発散法として比較的よくやることなのだろうか?? もしかしてはやってるの??
あまりに似たシーンだったので、ちょっとびっくりした。
●あと、教室内がうるさくなってきたら、先生が拍子をとって、生徒が手拍子で合いの手を入れて丸く収めるやつ。たしか作中で生徒に「あれは小さい子のクラスでやるものだ」とか言って歯向かわれていた気がするが、あれ初めて観たけど、ドイツでは一般的なんだろうか? 結構面白そうだし、楽しそう(笑)。
●なんでラストの音楽は『真夏の夜の夢』なんだろうね? なんか理由がありそうだけど。
●私事で恐縮だが、母親も昔、小学校の教師をしていて、まあまあのカリスマ教師だったときく(退職したあとも、大人になった教え子たちが四六時中家に遊びに来ていた)。昔、母からきいた様々な児童の問題行動やモンペの暴走や左翼教師の謀略やロリコン教師の犯罪の話を思い出しながら、本当に教師ってのは大変なお仕事だよなあ、と、ちょっと懐かしい想いに駆られながらの映画鑑賞でした。
善という名の不寛容
銀座の某老舗映画館で珍事が起きた。館内照明の不具合によって、映画冒頭2度にわたって上映が中断されたのである。観客数も少なかったせいか特に文句をたれる輩も現れず、無事最後まで鑑賞することができたのだが、(自己の寛容性を問われるという意味で)この現実に起きた事件がまさか映画の内容にリンクしていたとはねえ、不思議なことも起こるものである。
トルコ系ドイツ人のイルケル・チャタク監督が少年時代移民の子供として経験した出来事が本作には反映されているという。84年生まれのチャタク監督が中学生だった頃は、まだクラスのなかで移民は監督一人だけだったという。この映画同様、クラスの中で盗難事件が起きたりすると真っ先に疑われるのは、肌の色が違うチャタク監督だったらしい。そんな子供時代に感じた人種差別に対するなんともいえない不快感を反映させた映画だそうな。
ハネケの『白いリボン』(2010)や『ペルシャン・レッスン』(2022)で、チクリ系女子役がはまっていたレオニー・ベネシュが演じるのは、ポーランド移民2世であるノヴァク先生だ。チャタク少年の中学生時代とは違って、ノヴァク先生が担任を勤めるクラスは、今やゲルマン純血の生徒を探す方が難しいほど移民の子供が大半を占めている。あのパルムドール作品『パリ20区、僕たちのクラス』(2010)と同じ設定だ。
その教室ならびに職員室でおきた盗難事件を巡って、移民の子供やその親の職員が疑われたからさぁ大変。密告、監視カメラ、検閲、監禁...EUの寛容を旨とするグローバリズム精神はどこへやら、ここドイツのみならず右翼が政権を奪取しそうな勢いのフランスでもノヴァク先生のクラス同様の疑念と不寛容が渦巻き、EU内の雰囲気はきわめて悪くなっていると、ジャック・アタリが諦め顔でつぶやいていた。
要するにこの映画に描かれているのは、ドイツいなEU全体における社会の縮図なのである。
0.999…=0.111...×9
0.111…=1/9
1/9×9=1
∴0.999...=1
この無限級数命題をすらすらと解いてみせるオスカー少年は、おそらくドイツ系女性と移民の父親との間に生まれたハーフ(0.999…)。これを無限に繰り返すとその内自然と、ドイツ人(1)に限りなく近づいていくということを、多分いいたかったのではあるまいか。
しかし、ポーランド移民の子供であるノヴァク先生の場合は違っていたのである。話す言葉はすべてドイツ語、生徒たちに全体主義的グーテンタークを半ば強制、パソコンを利用した監視カメラ、証拠ありの密告、そして監禁という、まるで第三帝国を彷彿とさせる“アルゴリズム”に則った不寛容な態度をとれば、私のような移民の子供でもドイツ人としてちゃんと認めてもらえるのではないか。生真面目なノヴァク先生はおそらくそう考えていたと思うのである。
そんなこといったって俺たちゃ肌の色も考え方も全然違うんだぜ、ときっちり(肌の)色分けされたルービック・キューブをノヴァク先生の前に放りなげるオスカー。つまり本作は、生徒や教職員のみならずPTAまでまきこんだ窃盗事件をめぐる大騒動を、欧米最大の問題と見なされている移民問題の寓話として描いた映画なのだ。犯人は結局誰だったのかって?私は“善という名の不寛容”が真犯人だと思うのだが、はたしてどうだろう。
こんな嫌な雰囲気が終始続く作品も珍しいのでは?
学校の先生の大変さが痛いほど伝わる作品でした。
学校での盗難事件から端を発し、
主人公が自分のPCの動画録画機能を職員室内でONにしていたところ
犯人らしき人物がうつっており、そこからのコンフリクトがこの映画の始まりです。
主人公も生徒を守りたい一心で、この愚挙に出ているのですが(気持ちはわかる!)
これが裏目に出続け、負の連鎖を生んでいくんですね。
特に中盤に生徒から反発される展開は
本当に胸が痛くなりました。
「先生にあわせてあげてたんだよ」って言われた日にゃ、もう立ち直れないレベルで
傷つきますよ、先生は。
予告編で主人公がシャウトするシーンがあるのですが、
本編では私の予想とは異なっていて、
つらい場面ではなく、むしろ良い場面だったので、ちょっぴり安心しました。
ミステリー要素がありながらも、
結局はグレーなまま完結するのですが、
ラストもちょっとだけ光が見える終わり方だったので、鑑賞後観はさほど悪くありませんでした。
なにはともあれ、学校の先生にはリスペクトしかないです。
先生、教員と教師はどう違うのですか!?
サスペンススリラーというふれ込み、教員と思しき女性が絶叫しているキービジュアルにどこかヒッチコック「サイコ」のようなスリラー映画の印象を持って見始めた本作は、普通に真面目、ややシニカルな社会派ドラマだった。捉えようだけど。
原題が表す通り、話の主体はあくまでも教員側で、各々が教育実務に忙殺される職員室は、いかんせん上手くいってそうもないコミュニティのような空気感。
根が真面目な主人公は、教師として一見ダメな箇所も見当たらないようなタイプ。ただ、常に適切な受け答えを遵守する性格が裏目となり適切と言い難い事象に出会した際に弱目がたつ皮肉が正味90分続く物語だ。
このような場面はドイツの教育現場に限らず、どの国の職場、家庭でも見かける風景で本作邦題のそれは言い得て妙だった。
***
結局あの事務員はクロということでOKなのだろうか。盗人猛々しいのはよく分かったが、、。ラスト玉座のように強制排除される子供のカットは何を表現したかったのか、今ひとつ分からない。
テンポよく目を離せない進行なのはとても良いのに、所々キーポイントが未回収のため居心地が悪くなっているのが勿体ない気がした。
***
ところで、小6か中1あたりの子供は精神が特に勢いよく成長しており正に日進月歩とはこの事と日々感じる。大人が思うよりもずっと「わかってる」ものと考えた方がいい。
私は恩師から「子供を子供扱いするから失敗する」と習ってきたのだが、先生と呼ばれる方は相手が子供であっても人格を慮ることを肝要とするらしい。本作の主人公はその点いかにも、子供扱いをベースとしていて尚「ダメなものはダメ」というぶち込み精神論もできないわけだから、前述のとおり極端な出来事に対処しきれない。で、叫ぶし。やるなら海辺で一人でやれよである。
日本でも、教員を教育する制度もこれ、必要なのではないかな。
日本の80年代には校内暴力という異常な社会現象があった。本作品のチャタク監督には名作ドラマ「金八先生」そして「スクール・ウォーズ」をぜひ見ていただきたいと思う。お門違いながら、そういう時代を見てきた世代からすると共感しきれない、本作の今っぽい教員に、見ているこちらも叫びたくなる作品であった。
彼女は終始
信頼に足る人物だった。
というか、スーパーマン。あんなにメンタルが強い人はそういないだろう。最後まで強靭な彼女の言動には感心せずにはいられない。一般の人であれば、どこかでメンタルが崩壊してしまうことだろう。
ずっと、胸くそ悪い映画だった。しかし、予想された最後ではあったが、逆に予想通りであることで、悪くない終り方だったと感じた。
ひとつだけ、とても好きなシーンがあった。ラストの音楽もよい。
観た直後はうーんという感じ
いつもの映画館で
チラシを見て楽しみにしていた
観た直後はうーんという感じ
雰囲気的には怪物に似た感じなのだが
ストーリーはあちらほど練られてなくて
整理されていない雑多なものを出されたような
しかし一晩置いてみると
不思議と味わい深かったように思われる
いやぁ教師は大変だ
日本はほぼ単一民族国家だから
めんどくささの要素は若干少ないかもしれないが
オラが北海道に行った感覚で
修学旅行でイギリスに行くのか とか平和な感想もありつつ
ポルトガル語で話すことをためらうシーンとか
移民とのつきあいとかEU傘下のヨーロッパの
複雑な事情が垣間見える
・ポリティカルコレクトネス
・人権
・プライバシー
・報道の自由
・モンスターペアレンツ
とか結構な難題を学校というひとつの空間に入れ込んでいる
ファストファッション全盛の今の世の中シャツ被りなんてザラでは
なんてことも
何でもかんでもヨーロッパは高尚で
つい正しいように思ってしまうが そうでもないよなと思う
植民地を是としていたりするし
一方で単一民族国家がいいなんて意見をいったら
たちまち何らかのレッテルを貼られる
オラだってそんなことを表立って言う人物とは距離を置くだろう
なんかごちゃごちや考えてしまう一作だ
最後の方で追い詰められた主人公がそれまでどちらかといえば
ソリが合わなかった同僚に助けを求めるシーンが気に入った
結局いろんな人の協力を得て折り合いをつけて前に進むのだ
ラストのオスカーの行動
主人公と通わせたとみるべきなのだろうが
揺れ動く子どもの感情の一端という気もする
人間として素晴らしいが高学年の教師としてはどうだったか
主人公が教えてるのが何年生か分かんないんだよね。
でもけっこう子供だましみたいなことやってるから、低学年なのかなと思うの。
そうかと思うと 1 = 0.99…… を証明させたりしてるしね。
この「高学年の教師として、力不足では」っていうのが、物語全体に効いてる気がするの。
高学年の教師としてクラス運営できる力量があったらね、ビハインド局面でもなんとかまとめきれたんじゃないかな。父母を味方につけることもできたんじゃないかとか。
校長も弱いね。事態に対処できないの。
学校新聞が振りかざすヘンテコジャーナリズムも風刺が効いてる。
偉そうなことを言いながら、結局、売れて金が儲かればいいんだろっていう。
同僚教師も学校新聞に名指しで批判されると、突然冷静さを失って怒っちゃうしね。
物語中でうまいと思ったのはカンニングする生徒を登場させるところ。
生徒は「カンニングしてました」って認めないんだよね。でもこれはハッキリやってる。
だから、仮に悪いことしていても、悪びれずに「やってない」と言う人が当たり前の世界になってるの。
なので、本当にお金を盗んだ人は誰なのか、余計に観てる方はグラグラしちゃうの。
ラストは「先生の方を信頼します」ってことなのかなって思ったな。
人間としての素晴らしさが伝わった感じ。
全体に「誰が悪いともいえない」っていう状況を描く事情設定のバランスがすごくうまいと思ったの。その中で最後までブレない主人公がすごかったよ。
ドイツの教育って良いな、って思った。
正義感の強い教師のカーラは、赴任した中学校で1年生のクラスを受け持っていた。しばらくした頃に、校内で盗難事件が続き、カーラのクラスの生徒が疑われた。校長らの任意の事情聴取で仲間を売るようなやり方に違和感を持ったカーラは、独自に犯人捜しを開始し、自分のPCで職員室を撮影した映像に、中学の職員でオスカーの母と同じ服を着た人物がカーラの上着からお金を盗む瞬間の動画が映っていた。しかし、この盗難事件でのカーラや学校側の対応は、保護者の批判や生徒の反発、といった事態へ進んでしまった。そして、カーラは次第に窮地に追い込まれていき・・・さてどうなる、という話。
ドイツの教育って詰め込みじゃないみたいで、生徒の自主性や自由な発想を引き出そうとしてる事に素晴しさを感じた。
せっかく動画撮影するなら、もっと広角で設定してたら良かったのに、確かに服だけじゃ弱いかも、とは思った。
ラスト警官が椅子から離れようとしないオスカーを連れて教室から出ていったのだろうけど、で、どうなったんだろう?
学校は社会の縮図。移民が増えているドイツならではの複雑なコミュニケーション
まさに、現代のドイツの日常を生々しく描いた作品。脚本がとても上手い。意図していない方向に物事が転がっていく様を見事に描いていて、しかもとてもリアリティを感じる。とにかく生徒の気持ちを一番に考えているとても良い先生なのに…。でも悲しいかな、こういうことって、有りがち。学校新聞がゴシップ記事を書き、報道の自由を口にするいっぱしのジャーナリスト気取りの生徒達に、現代のSNSを見た。怖っ。
ありふれているのか…
中学校にてお金が無くなる事件が頻発し、こっそり動画を撮ったらそこには驚きの真実(?)が…
対応に迫られる教員と不信感を抱く生徒保護者達の姿を描いた作品。
先生という難しい仕事の残酷さをこれでもかと表していますね。皆の言ってることもわかるが、こうでもしないと解決はできんよな…。
生徒のことをどこまで疑ってよいものか。
信じてあげるのも大切だが、それを愛と感じるほど子どもって純粋ではないと思ってしまうが…。
んで、何か行動を起こせばすぐに吊し上げ。保護者同士のグループSNSとか怖いよ。
そんなこんなで窮地に立たされるカーラ。先生達も一枚岩じゃないし、それぞれに問題があるようにも見えるし。
やり方が正しいかどうかは置いておいて、カーラは立派ですね。あそこまでされてそれでも守ろうとするんですから。
本来は盗った奴が100%悪いに決まってるのに、この仕打ちはあんまりですよね。
終わり方がかなり好みではなかったのが残念だけど、決して長くない尺の中で生徒それぞれの存在感や先生達の出番もバランスよく、終始ヒリヒリさせられる良作だった。
嫌な映画だけど惹きつけられてしまう
良かれと思ってしたことが仇となって帰って来るとは、何ともやりきれない思いにさせられるが、カーラのような正義が”ひっくり返る”ということは実際にままあるように思う。結局、その正義が本当に正しい物なのかどうかという判断は、当事者ではなく周囲の人々や社会が下すものなのだろう。
そういう意味では、今回の容疑者が頑なに罪を認めようとせず、その状態のまま学校側が一方的に断罪してしまったことは大いに問題があると思った。本来であれば冷静になって話し合いの場を設けるのが筋なのだが、余りにも感情的になってしまった結果、カーラと容疑者の間には深い溝が生まれてしまった。
また、この一件が学校中に知れ渡ってしまったのも問題だろう。生徒たちの間に不信感が生まれ、そこから保護者へ、更には教員同士の疑心暗鬼を生み、もはや盗難事件どころではなくなってしまった。
こういうのは初手をミスると、どんどんドツボにハマってしまうから恐ろしい。
正直、観てて終始嫌な気分にさせられる映画なので、万人には決してお勧めできない。しかし、この物語の根底には人間の愚かさや弱さが流れており、そこに惹きつけられてしまうのも事実だ。自分は終始画面から目が離せなかった。
監督、脚本は本作が長編4作目という作家である。長編以前には短編をたくさん撮っており、キャリア自体は結構長いようで、演出はかなり手練れていると感じた。
リアリズムを重視したストイックな語り口と軽快なテンポ、全編学校内で展開される物語が閉塞感や緊張感を上手く醸造していた。
また、中盤でカーラの心象を表すシュールなシーンが登場するが、ここは本作で唯一幻想的なタッチで表現されている。とは言っても、全体のリアリズムから変に浮くようなこともなく、このバランス感覚も絶妙だと思った。
更に、キーアイテムとしてルービックキューブを持ってきたのも面白いと思った。最初は突然出てくるので少し不自然に感じたのだが、要は”答えを出すことの難しさ”ということを暗喩しているのだろう。そのメッセージはカーラからオスカーに宿題のように託され、最後に思わぬ形で返答される。
印象に残ると言えば、エンドクレジットへの導入も見事で、思わず声が出てしまった。オスカーのカーラに対する、あるいはカーラを含めた大人たちに対する”宣戦布告”のように思えた。
もう一つ、本作で特筆すべきは音楽ではないかと思う。もはや、音楽と言うより効果音と言ってしまった方がシックリとくるのだが、これが全体に不穏なトーンを持ち込んでいることは間違いない。
まるで現代社会の縮図。
決してカーラは間違ってたのか?とか、どうすべきだったのか?ということを問うている映画ではない。
それは、最後まで犯人が明らかにならない事からも明らかだ。いや、あえて犯人を明らかにしてないと言ったほうが良い。犯人探しのミステリー映画ではないのだ。
鑑賞前は、最後に犯人や驚きの事実が明らかになるミステリー映画だと思ってたから、いやオドロイタ ( ゚д゚)
最初の、 「0.999··· は 1 と同じか」 の授業で、それは「主張」なのか「証明」なのかを問う場面がある。カーラが数学教師であることの単なる紹介の場面だと思っていたが、作品が問いかけてくるテーマに絡んでくる。
この映画は僕たちに、真実(事実)とは何かを問うてくる。果たして僕たちが正しいと信じる真実は正しいものなのか? 真実と思ってたものが、思い込み、勘違い、推測、間違った情報を元にしたものかもしれない。それは単なる「主張」であって、「証明」された真実とは限らない。その「主張」がたまたま真実である事もあるが、「証明」されて初めて真実であると言える。
しかし、ここで最近の生成A Iの凄まじい進歩が頭に浮かぶ。写真どころか本人、家族、側近でさえ見分けがつかない音声付き動画が簡単に作れてしまうらしい。いや、それ以前からネットのフェイクニュースは、プロのジャーナリストでさえ見分けるのが難しかったり、騙されたりするという感じだった。
この映画を見てて1番恐ろしかったのが、生徒達が正義の名の下に自分達の作った真実を突きつけてきた場面だ。 生徒は、親と生徒どうしの話を信じ、カーラと教師たちには不信感がある。
ここでも生徒たちは、自分達が正しいと思う正義と真実を主張する。それが正しいと証明されたワケでもないのにだ。
で、このレビューは特に結論も出さずに、突然ここで中途半端なまま終わる。
もう日付も替わって1時だし、よく分からないし上手くまとまらずに結局レビューしなかったという僕のよくあるパターンになりそうなので、このままレビューをUPする。
ナイスアイデア。
ああ、あと映画の最後にオスカー少年がルービックキューブを6面揃えた事と、玉座で運ばれる王様のようにPOLICEにイスのまま担がれて運ばれる場面も何か意味あるはずだから、他のレビューを見ることにしようと思いました○(マル)。
「女王の教室」の天海祐希なら、、、
ほとんど予備知識無しで鑑賞しました。ふれこみのサスペンススリラーと言うのとは、自分はちょっと違う印象。不寛容方式とやらを導入していると言う教育現場の問題点を鋭くついた社会派映画だと思いました。スリラーと言うならちゃんと真相を明らかにして欲しいが、明確な結末ではない。観るものにその解釈を任せると言う場合によってはズルいなあとよくあるラストでしたが、自分はおそらくラストであの少年が自分の母親が盗難事件の犯人だったことに気がついたのではと、少年の涙を見て思いました。また、それを見た女性教師もそれを察して校長たちを追い出して教室を施錠したのだと思います。少年がルービックキューブを完成させて、彼女に見せることでお互いの間にある種の信頼関係が生まれたのだと思います。自分の人生の味方は、必ずしも血の繋がった血縁の人間ではないと言う辛いが厳然たる真実がここにはあります。この映画で一番最悪なのは校長ですね。上に立つ者の資質が欠けてます。問題が劣勢に傾くと下の者に責任転嫁するあの光景は、よく見かけます。遊川和彦の「女王の教室」の天海祐希なら、もっと観る者にフラストレーションを与えないリアクションをしてくれるんだろうなあと思いながら観てました。
ドツボサスペンス?
まさに淡々とドツボにハマっていく。
些細な原因から始まり、主人公カーラは彼女の信念で対応していく。
しかし状況はどんどんとドツボに・・・
どうなるのか?真相は?
もはやそんなことは関係なく事態は想像を超えて悪化して、
そしてどんどん周りに感染し、巨大化していく・・・
確かにラストはある意味衝撃。
最近の伏線回収映画に見慣れた人にはどうかな?
個人的には映画らしい映画なので、好きです
全125件中、41~60件目を表示