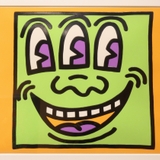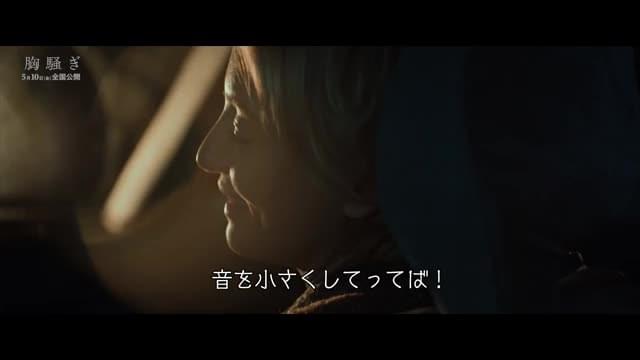胸騒ぎのレビュー・感想・評価
全117件中、81~100件目を表示
タイトルなし(ネタバレ)
イタリア旅行で知り合ったオランダ人の家に遊びに行く。
親切で陽気そうだったが、飲み方、子供への教育など 違和感が続く。
遂にその家族が、連続幼児誘拐殺人犯と分かり
逃げるが捕まり、子供はさらわれ、親は殺された。
最初から BGMが 不穏で、嫌な感じ
最後は 救いようの無いバッドエンド。
客は2時間 嫌な気分で、何を得れば良い?
世の中 ままにならない、人生は不条理、
私にはキツすぎる。
違和感
ホラーって事だけ情報を入れて観ました。
原題は『SPEAK NO EVIL』
オープニングで、このタイトルが表示された時ギョッとした。
見覚えある言葉、同じタイトルの曲を知っている。
観たあと意味を調べたら“悪口を言わない”とか“言わざる”って意味があるらしい…
なるほど、このタイトルは合ってる。
『胸騒ぎ』って邦題は、合わないな…と思って観てたんだけど、最後まで観たら、コレはコレで…。
天才的に人を不安でイヤな気持ちにさせる映画で、何かが起こりそうな不穏な空気に心をかき乱され、不安と焦燥感に支配されます。
どうなる?どうなる?と引き込まれ観てました。
『サイコ』を連想する天才的に不安を煽る不穏な音楽、素晴らしい役者による迫真の演技…
胸クソわるく観賞後の気持ちは最悪だけど、完成度が高くホントよく出来てます。
胸クソ映画はキライだけど、あまりの完成度の高さに2回観ました。
好みじゃないので、個人的には75点ぐらい
こういうのが好きな方には、オススメです。
後味悪いし救いがなくて怖かった
・旅先で知り合った人と仲良くなったとしても、連絡を取るのがとても怖くなった。
・日常にある些細な暴力的、威圧的な態度、行動がいかに怖いかっていうのを改めて感じた。
・旅先で出会った家族を家に招待して両親は殺して子供は舌を切って言葉の自由を奪って拘束しつづけた後、次の獲物の子供が見つかったらあっさり殺して入れ替えるといったことを繰り返す犯人の動機が全くわからないのがとても怖かった。
・犯人夫婦が差し出したんだぞ的なことをいったセリフがあった。何と自己都合なセリフだと思ったけど、最後の一日の時に家に向かった際、ぬいぐるみがないからと駄々をこねる娘のために戻った際、罪悪感と危機感とを天秤にかけられて残る決断をしたけど、ああいうときは危機感を優先すべきだと思った。
・度々、セックスしてたから娘の声を無視したのが原因の罪悪感や金を少し出そうかといった気遣いからの行為を逆手に取られて気が重くなった。嫌な感じって思ったら逃げろという教訓を次々教えてくれる映画だった。
・ラストに子供の舌を普通に切り落とすし両親を全裸にして岩石の破片を投げて殺すした後も、また次の家族を探すサイコパス的な夫婦の日常がはじまる感じが救いがなくて怖かった。
・幽霊とか怪物とかが出てこないだけに恐怖が日常に潜んでる感がすごかった。
本能に従順で、対外関係を壊さない嘘こそが、生き残る唯一の術だったのかもしれません
2024.5.14 字幕 アップリンク京都
2022年のデンマーク&オランダ合作の映画(95分、PG12)
旅行先で出会ったオランダ人家族の元を訪ねるデンマーク人家族を描いた不条理スリラー映画
監督はクリスチャン・タフドルップ
脚本はクリスチャン・タフドルップ&マッズ・タフドルップ
原題は『Gaesterene』で「ゲスト」、英題は『Speak No Evil』で「悪口を言うな」という意味
物語は、デンマーク人一家の主人・ビャヤン(モルテン・ブリアン)、その妻・ルイーセ(スィセル・スィーム・コク)、娘のアウネス(リーバ・フォシュベリ)が、オランダのある村に休暇に訪れるところから紡がれる
彼らは、地元のオランダ人一家の主人・パトリック(フェジャ・ファン・フェスト)、その妻・カリン(カリーナ・スムルダース)、息子のアーベル(マリウス・ダムスレフ)と仲良くなり、社交辞令の如く、「今度ウチにいらしてください」と言う会話を交わすほどになっていた
帰国して間もなく、パトリックたちから絵葉書が送られてきたが、遠方ゆえに行くことは躊躇われた
だが、友人のヨーナス(イェスパ・デュポン)から「車で8時間の距離だ」と聞かされ、夜に出れば朝には着ける距離であることがわかった
そこでビャヤンたちは、パトリックたちの申し出を受けて、彼らの自宅へと訪れることになったのである
物語は、パトリックの家で過ごすうちに違和感を覚えたルイーセが「帰りたい」と言い出すところから動き出す
彼らが寝静まった頃に逃げるように家を出たものの、アウネスが大事にしていたウサギのぬいぐるみを忘れてきたことに気づく
やむを得ずに戻り、こっそりとそれを探しに行くものの、パトリックたちに見つかってしまい、黙って去ったことを咎められてしまうのである
物語性はさほどなく、パトリックたちの何かを生理的に嫌うルイーセが警鐘を鳴らすものの、黙って帰ろうとしたことを取り繕ううちに、逃げられずに終わる様子が描かれていく
その後もパトリックたちは「最高の1日にしたい」ともてなしを続けていき、ルイーセの違和感も拭えていく
だが、そこで再び違和感が生じ、逃げ出そうとするものの、時すでに遅しという感じに綴られていた
映画は、終始不穏な雰囲気が漂っていて、人としての礼節を怠ったビャヤンたちの居心地の悪さが描かれていく
だが、パトリックたちの本性はルイーセの予感通りで、実のところ、これまでに何度も「子どもが一人いる家族」と関係を持ち、子どもを入れ替えてきたことがわかる
アーベルの先天性の失語症は嘘で、実際にはパトリックたちによって舌を切られていて、アウネスもその仕打ちに苛まれることになった
そして、絶望したビャヤンとルイーセは彼らに言われるがままに行動し、最終的には石を投げつけられて殺されてしまうのである
どうして徹底的に抵抗しないのかは謎に思うものの、これまでの経緯から「抵抗できない家族」と言うものを選んでいるように思えた
あくまでも相手の行動を自主的に促し、それによって行動制限をしているのだが、ラストに至る「言いなり」には違和感を覚えてしまう
おそらくは、娘の喪失によって未来に絶望を感じ、生きる気力を失ってしまったのだろう
いずれにせよ、前半はそこまで奇異な体験でもなく、どこにでもありそうな人間関係の不和と言うものを描いていた
後半になって、実は相手が異常者だったとわかるのだが、前半の段階でここまでの落差というものは想像し得ないだろう
そう言った意味において、人間の本能の鋭さというものを磨いておく必要があるのかな、とも思う
とは言え、自分に接近するすべてを疑うのは難しいので、違和感を感じた時には、相手の機嫌を損ねないように距離を取るのがベターだったと言えるのではないだろうか
「悪意」があるかどうかで話は違ってくる
相手の何気ない振る舞いに、不快感や不信感を抱くことは、日常生活の中でもあることだ。
自分自身も、決して悪気はないのに、不用意な言動で相手を怒らせたり、憤らせたりしていることがあるかもしれない。
そんなことを思いながら、2組の夫婦が溝を深めていく様子を興味深く観ていたが、終盤になって、ホスト側の夫婦に始めから「悪意」があったことが明らかになると、何だか興醒めしてしまった。
それにしても、ホスト側の夫婦にあのような目的があったのならば、ゲスト側の夫婦にはできる限り快適に過ごしてもらい、油断をさせるべきだったのではないだろうか?
実際、ホストの言動に「違和感」を覚えたゲストは、2度に渡って逃走を企てているし、しかも、1回目の逃走は、ゲスト側の不手際がなければ成功していた可能性が高いのである。
2回目の逃走にしても、ホスト側がわざと逃がしたように見えないでもないが、家で犯行に及んでいれば、何の苦労もなかったはずで、ゲストに不信感を抱かせ、恐怖を感じさせたのは、明らかに失敗であったと思えるのである。
そもそも、ゲストが、訪問先を誰かに教えていたら、行方不明になった時点ですぐに警察の捜査が入るはずで、犯行の計画そのものが極めて杜撰であると考えざるを得ず、壁に飾ってあった写真のように、いくつもの家族が犠牲になったとはとても思えない。
ゲスト側の家族にしても、大事なぬいぐるみを何度も失くす娘には、もっと物の管理をしっかりしろと怒りたくなるし、ホスト側の不審な動向に関して、夫婦間での情報共有ができていないばかりか、「帰ってもいい」と言われているのに滞在し続けるという判断能力の無さには、見ていてイライラさせられた。
極めつけは、娘や妻が酷い目に合っているのに、ただ泣いて「助けてくれ」と懇願するばかりの夫で、もっと、戦うなり、抵抗するなりできないものかと、情けなく思ってしまった。しかも、相手は、「石」以外に、武器らしい武器を持っていないのにである。
まあ、犯罪者としては、そういう夫であることを見極めて、この家族に狙いを定めたのかもしれないし、実際に犯罪の現場に居合わせたら、誰もが恐怖でああなってしまうのかもしれないが・・・
いずれにしても、変に意図的な「犯罪」の話に落とし込まないで、最後まで、無意識の「ボタンの掛け違い」が対人関係を悪化させていく話にしていれば、もっと面白い映画になったのではないかと、残念に思えてならなかった。
叫ばない魂
イタリア旅行で知り合ったオランダ人家族に招待されて訪れた彼らの自宅で、彼らとの関係にズレを感じ始めるデンマーク人家族の話。
ベジタリアンと知っているのに、そう言っているのにいきなり猪肉を食べさせようしたり、突然の子どもは留守番だったり、道徳観の違いからなのかちょいちょいストレスが…。
不快さが積み重なっていく様はなかなかお見事だったけど、ティータイムの行から、これこそが帰るところじゃ?
いよいよパパが動いたけれど、何で急にママが呑気になってんの?に始まって、なんだか都合が良すぎるし、パパのポンコツとママの呑気さが加速して、足掻くの期待したけど言いなりで…。
終盤前までかなり面白かったし、不快さや不条理さは最後まで良かったけれど、展開的にちょっと尻すぼみだったかな。
Don't think, feel
ホラーなのは最後の10分間の、無意味に全裸にされて、残忍に殺されるシーンだけ!おそらく、主演のお二人もこのシーンを了解したからキャスティングされた感じ。そこまでの85分間の前振りは、一切回収されず、観なくても良かった。
ハリウッド版リメイクで、素晴らしい脚本と演出に生まれ変わる事に期待します!
後味が悪いタイプの映画
イタリア旅行中に親しくなったデンマーク人家族とオランダ人家族。都会暮らしのデンマーク人夫妻は、オランダ人夫婦に、「ウチは田舎暮らし。週末を自然の中でのんびり過ごすのはどう?」と招待される。ところが、訪れた場所は、寂れた、陰気臭い所。あれ?
夫妻は礼儀正しく、「素敵な所ですね」と褒めるが……
些細な判断ミスが重なった末に、悲劇に見舞われるデンマーク人家族。もう、飛んで火に入る夏の虫、アリ地獄に落ちた蟻、蜘蛛の巣にからめとられた蝶…あのオランダ人夫婦は、相手が裕福で、意識高い系で、なおかつ親切——つまり心に余裕があるほど、それをぶっ壊したくなるのかもしれません。彼らから見ると、のほほんと生きている人間なんでしょう。
確かに怖かったんですが、それよりもイヤーな気持ちの方が強いです。少なくともオランダ人とスウェーデン人は嫌な気分になると思います。「胸騒ぎ」というタイトルは合っていますが、私はもっと得体のしれない恐怖のようなものを想像していたので、ちょっと予想と違いました。こういうジャンルは苦手です。
<追記>
以下はネタバレです。
英語は得意ではないので、原題のSPEAK NO EVILをどう訳せばいいんだろうと思いました。
主人公のビャアンは、人を非難する言葉や、嫌な気持ちにさせる事を言いません。
カンツォーネに感動して涙を流したり、娘の為に外国の街でぬいぐるみを探し回ったりするのは彼の美徳です。でもその善性が、オランダ人夫婦には憎悪の対象となって、次の獲物に選ばれたのかもしれません。娘がいた事も大きいですが、それだけでは無いと思いました。
「なぜこんな目に?」と訴えると、「おまえが差し出した」と言われました。
招かれた場所は、美しいイタリアに比べると、殺風景で全く魅力が無い土地です。葉書をもらった時に調べて、断っても良かったのに、厚意だからと断らなかった。
今夜は猪料理だと言われても、妻はベジタリアンだと言わなかった(以前に言ってるが)
子供を残す事に抗議しないし、支払いは自分が持ったことを妻に言ってないかも。
お土産のカップを割られても怒らなかった。
娘の機嫌を損ねたくなくて戻ってしまった。夫婦の機嫌も損ねたくなかった。
そして、夫婦の正体を知ったのに、妻を怖がらせたくなくて伝えなかった。
おまえのその勇気の無さのせいで、家族を守れなかったのだという事でしょうか。
正当防衛さえさせてもらえない。
北欧イヤミス。動機が理解できないまま、クライマックスは宗教的な暗喩。エンドクレジットのベースや原題にも『善と悪』のテーマを強調されている。ある意味…九条は「純粋な悪意(侵略)」を防御できない、と思い知らされる。だって完全無防備にされて抹殺されてしまうのだから。となると、政治的な映画なのかな、こいつは。
ハネケ…風な。
胸糞 イヤミス
⦅#胸騒ぎ⦆
あの夏に出会わなければ...
この招待を断っていれば...
あの時引き返さなければ...
北欧産のイヤミス映画
閉塞感と不穏な煽り
決して本当の正体を隠して
蝕んでいく
そして気づいた時には
【もう、戻れない】⚠️⚠️⚠️
私たち観客の良心を根刮ぎ奪い取られる
鑑賞後は焼肉食べれなくなる映画👅
都内では満席🈵覚悟
郊外がお勧め
既にアメリカリメイク版も今年米公開
#SpeakNoEvil
エンドロールの絵画の意味も知りたい
救われない映画と言うよりも救いようのない映画
内容は、何となく感じていた展開で進んでいきます。確かに「ミッドサマー」以来の衝撃作に間違いはなく、重い溜息が残るラストです。しかし終始主人公に同情できないのはなぜか?
他の方のレビューにも書いてありますが、逃げるチャンスはありました。と言うか、2度逃げています。1度目は、娘のぬいぐるみを取りに戻り(車に持ってきていたのが後でわかる
が)、2度目はわき道に入り車がスタックしてしまう。とにかく、身の危険を感じ逃げ出したのにぬいぐるみの為に戻るとか、土地勘のない夜道であえて危険なわき道に入るとか(気の動転?)。なぜ逃げる際に武器となるもの(包丁や鈍器など)を持っていかないのか?度胸もない人間なのに、なぜ皆の命よりもぬいぐるみを選ぶのか?ちょっと情けなくなるくらいアホ過ぎます。
捕まってからも、言われるまま、されるままで、どうせ殺されるなら抵抗ぐらいしても良いのに殴られたら何も出来ず。これじゃ死んでからも、妻や娘から恨まれても仕方ないです。何もしない何もできない、ただただ弱い人間の末路が描かれただけでした。
他の映画では、最後反撃に出るのがよくあるパターンですが、この映画はリアルさを追求し、生身の人間の最悪なケースを描きたかったのでしょうか。ただ、結果的には主人公の不甲斐なさが際立ち、相手夫婦(本当に夫婦なのかどうかはわからない)の非道凶悪さが薄れてしまった。
ちなみのここからは想像によるものですが、例え逃げたとしても、必ず子供(娘)を奪いにデンマークまで追いかけてくるだろう。でもその場合は、警察の援護が受けられるかも知れません。また、ラストで主人公夫婦が殺される場所ですが、誰も来ない河川敷のような干潮・満潮で海水が流れ込みそうな場所なので、死体は満潮時に海に流れ魚の餌となるのではと受け止めました。
タイトルなし(ネタバレ)
タイトル通り。
映画館で鑑賞。日曜の昼の時間帯だったからか、席はほぼ満席。
客層は30代男女が多めでした。
イタリアの旅行先で知り合った気さくなオランダ人夫婦からの自宅への招待状から、週末を夫婦の家で過ごすことになった家族の話。
映画冒頭に映し出される運転のシーン、最後のビャアンが必死に家から逃げるシーンだったのか。
物語の展開的には、かなり遅めに感じた。
違和感には薄らと気付いているものの、確信めいたものがなく、中々「家から逃げ出そう」という展開には至らない。
洋画ホラー映画特有の途中のベッドシーンは、狭い劇場だとよく響いてかなり気まずい。
だが、不穏な音楽との対比で更に不気味さを増長しているとも感じる。
キャラクターについて、オランダ人夫婦の息子、アーベルと、主人公娘のアウネスがかなり不憫なので見ていられない部分がある。
特に、ダンスのシーンは精神的に追い詰められる感じがして息が詰まった。
誰しもが感じたことのある、「自分では無いが誰かが怒鳴られている時の辛さ、気まずさ」が強く描写されている。
その後の展開もかなり不憫で、観る人によっては「絶対にもう見ない」と言う人も居るだろう。
個人的に1番キツかったのは、最後、ビャアン、ルイーセ夫妻がオランダ人夫婦に石を投げつけられるシーン。
衣服を脱がされ裸の状態であることもあり、夫婦の投げつけた石が背中に赤黒い跡を残す。
直接石を持って殴り殺すのかと思いきや、上から石を落とす感じだったので、「本気を出せば全然逃げられるのでは?」と考えてしまったが、
妻のルイーセの方が、娘を失い生気を失ってしまっていたので呆気なく終わったのが残念。
個人的には、「絶対に復讐する」と言ったような展開が好みだったので、やられっぱなしの2人を上映中応援していたが、「憂鬱度NO.1」の理由はここにあった。
礼儀の正しさがあるが故にどんどん悪い方向へといくので、物語が明るくなる瞬間が見えない。
大学で映画好きの友人が居るが、中々見て欲しい!と紹介しずらい映画だった。
ノーと言える日本人になろう!
ホラーは苦手なんですが、紹介文にある“ヒューマンホラー”という言葉を見て、これはきっとだいじょうぶと自分に言い聞かせて鑑賞してきました。
ストーリーは、休暇でイタリア旅行に出かけたデンマーク人夫妻のビャアンとルイーセと娘のアウネスは、そこで出会ったオランダ人夫妻のパトリックとカリンと息子のアベールと仲よくなり、帰国後しばらくしてパトリック夫妻から招待状が届いたため、ビャアン一家はパトリック家を訪問し、再会を喜ぶものの、ちょっとした違和感からしだいに居心地が悪くなっていくというもの。
些細なことと思いながらも感じる微妙な違和感が、少しずつ積み重なることで居心地の悪さにつながり、それが決定的な嫌悪となり、やがて恐怖へと変化していきます。人のよさげなビャアンの出方を見ながら、パトリックがグイグイと詰め寄っていく感じが、とてもうまく描かれていると感じます。パトリックがビャアンに大声を出させる場面も、ビャアンの内に秘めた心情と人柄を描くとともに、そこにつけ込むパトリックの巧妙さを描いていると感じます。
終盤は、しゃべれない息子、自宅への誘い、錆びたハサミ、庭先の小屋など、用意した伏線を回収しながら見せるオチが、なかなかおもしろかったです。その上で、畳みかけてくるようなエグさと胸クソの悪さが、本作の見どころの一つになっていると思います。まあ、好きな人にはたまらないかもしれませんが、自分には好みの終わり方ではなかったです。最後はもう少し救いがあってもよかったのではないかと思います。
ただ、冷静に考えると気になることがいくつもあります。そういう目的で一家を招いたのなら、何日も滞在させる必要はないように思います。ビャアンたちをあのまま放置したのも解せません。そもそも招待のハガキが自宅にあり、パトリック宅に行くことも話しているので、戻らなければすぐに捜査の手が伸びるのではないでしょうか。…などといろいろ考えると楽しめないので、この週末の出来事だけを切り取って鑑賞するのがいいのでしょうね。
誰かのお世話になる時、その人のやり方に関して覚える違和感はなかなか口に出しにくいものです。相手に不快な思いをさせまいとする配慮、きっとこういう理由があるのだろうと考える善意の解釈、加えて正常性バイアスが働いて、ことを荒立てず、心の平穏を保とうとするからでしょう。本作では、そんなビャアンの言動に対して、ラストでパトリックが突きつけた「君が差し出した」という言葉が印象的です。だからといってパトリックの行動が許されるはずもないのですが、ビャアンのような言動をとりがちな日本人は、上手にノーと言えるスキルと強い気持ちを身につけなければいけないと感じました。
キャストは、モルテン・ブリアン、スィセル・スィーム・コク、フェジャ・ファン・フェット、カリーナ・スムルダースら。知らない俳優さんばかりですが、それぞれに好演していたように思います。
最悪な気持ちになれます⭐️
鬱映画とよばれるジャンルのものは数多くみてきたが、これは今まで観てきた中でもトップクラスで最悪の結末かも。なぜ北欧の映画やドラマは絶望的な内容が多いんやろう…?
旅行先で出会った家族同士が意気投合して、相手のお家に招待されるがだんだんと違和感を感じて…っていう内容。
最初のシーンからして、まあいい結末にはならんやろうなあと思いながらみていたけれど、主人公たちがいい人だからこそ余計にやめて〜!!もうええって!!と祈るような気持ちで見てしまった。
あの子どもは、訴えようとしてたんやね…あえて英語がわからない子がいる家庭を狙ってやっているんやろうなあ。寄生虫というのかなんというのか。ちょっと違うけど、九州のマインドコントロールした事件を思い出した。奥さんも子どもはもう自分の元に帰ってこないと察して絶望したんやろうなあ。こういうサイコパスって平気で嘘つくんやな。こんなん絶対騙されてしまいそう。
あまり強く言えない夫が普段のストレスを絶叫して発散するシーンも…これさ、こんな広大なところもう伏線やん…絶望しかないんやけどって感じやった。これでもかという鬱映画を観たい方にはおすすめ!苦笑
最後に、うさぎはとりにかえらんでええねん!!あのままやったら逃げ切れてたのに…。
全117件中、81~100件目を表示