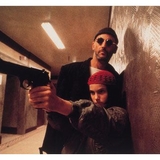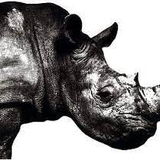侍タイムスリッパーのレビュー・感想・評価
全265件中、1~20件目を表示
純真無垢な昔堅気の映画野郎
タイトルと主題だけでなく、この映画丸ごと、タイムスリップしてきたかのような気がしました。弟子入りを志願して「落ちる滑るって言っちゃいけない」などというベタベタのシーンがそれを表していたかのような。水戸黄門、銭形平次など昔の人の如何にもというやり取り、困っている人を放っておけない優子さんのような古風な頑張り屋が活躍する、庶民的な舞台劇を観たかのような、そんな印象。
タイムスリップといってもSF要素は余りなく、古き良き時代劇や映画バカの撮影風景、そういうのがテーマだったのではないでしょうか。撮影所の楽屋?でポスターは時代劇なのに、テレビの横に並んでいたDVDは、何故か伊丹十三監督作品。これも、この映画の主張の一つだったのかな。話の流れも無理などんでん返しもないトントン拍子。最後に武士の身の上に立ち返っての一騎打ちも、まあ、予測通りではあるけれど。
でも、最後の殺陣(たて)は痺れました。いつ動き出すんだという凄まじいタメ。刃が打ち合う鋼の音は、これまでのチャンバラシーンで録に擬音を付けなかったのが効果を上げているのでしょう。本当に真剣でやっているんじゃないかという緊迫感。劇中劇の顛末も踏まえて、歯を食いしばってしまうほど凄まじかった。
そして出来上がった劇中劇の映画は、なんというか、本当に無骨な作品のようですね。この映画とまったく同じ、最後の一騎打ちが売りでしかないような骨太い時代劇のようですけど、果たして、売れるんでしょうか。恐らく、例え売れなくとも「これぞ本物の映画だ」という評価さえあれば、劇中の監督も満足したのではないでしょうか。この映画そのもののように。
この前に観た「ルックバック」という漫画家のアニメ映画を思い出した。自分達の仕事をもモデルにしているからこそ、カタルシスが凄まじい。ましてや、私たちも武士の国。美味しいおにぎり、美味しいケーキがいつでも食べられる時代になって本当に良かった。先人達に感謝、感謝。
昔の人が生きた時代の延長線上に私たちの現在はあるのだ
どこにでもあるショートケーキをはじめて口にし「これが普通の人でも食べれるとは。。本当に良い世の中になった。」とボロボロ泣く。会津藩の悲惨な最後を知り、むせび泣く。感極まるこの2つのシーン。昔の人たちの努力や犠牲の上に、私たちの平和で豊かな世界があることを改めて実感し、感謝した。
竹光で本身を振っているようにみせるため、振り方を試行錯誤した結果、本当に重さが加わったように見えてきた演技に驚き。 いやいや待て待て。この映画の中にいくつかある真剣のシーンも、実際は竹光使って演じているはず。(クライマックスの風見との対決シーンなど)凄い演技力だ。
クライマックスの戦いのシーン。最初のながーい無音の時間の演出が真剣による緊張感を最大限高めることに成功している。
時代劇を辞めて東京に行っていた大物俳優の風見恭一郎が、時代劇&京都に凱旋。このシーン、風見が真田広之とオーバーラップした。真田広之は別に時代劇やめてないけど。(笑
2021年に上映された『サマーフィルムにのって』を思い出した。共通項多し。
・タイムスリップもの
・時代劇
・映画を撮る映画
・低予算ムービー
・拡大上映!
そしてなんといっても「空気感」が同じなのよ!
朴訥なこの侍のように、背筋を伸ばし、周りに感謝して生きようと、気持ち新たに映画館を出た。
※失礼ながら知らない役者さんばかり。
※高坂と風見と女将さんがいい!
※風見は誰かに似てるなあ~と思ってあとで調べたらそうそう「別所哲也」「 西岡德馬」「嶋大輔」だ。冨家ノリマサさんという方なんですね。これからチェックさせていただきます!
※真面目で無骨で、少し汚い高坂が侍っぽくてとてもいい!
※ロケ地は随心院、亀岡の大正池まではわかった。京都がほとんどだと思う。聖地巡りしたい。
→ 10.15追記 このレビューで教えていただいた「油日神社」に行ってきました。最後の真剣でのシーンの舞台です。京都でなく滋賀県(三重県との県境)でした。飾り気のないとても良い気が流れる神社でした!ぜひ。
※風見が怒って池に石を投げ込むシーン(笑 見逃さないよ。
※どうしても受けてしまったり、師匠を斬ってしまったりするシーンも笑けた!
※パンフレットはまだ届いていなかった。あらためて買いにいかねば。
※殺陣の指導シーンで「当たるから切っ先は上へ」と。なるほど。
山口馬木也に主演男優賞をあげたい
インディペンデント監督が書いた脚本のために京都の撮影所が協力して実現した娯楽活劇コメディ、という作品の成り立ちは美しいし、主演の山口馬木也があまりにもみごとで、立ち姿や所作、殺陣の決まり具合に惚れ惚れする。
しかも演技がべらぼうに上手い。上手いを超えている。正直、和尚が檀家の前で電話をするシーンとかは観終わってあれ必要だっけ?と思ってしまったし、ベタすぎて鼻白む部分も多いのだけれど、どんな場面でも、どんなセリフでも、山口馬木也という人が驚くほど誠実に、自然に演じてしまうので、山口馬木也を見ているだけで十分お釣りがくる!という気がしてくる。
ただ、別の時代からやってきた異分子という設定に即していて成立してないわけではないのだが、山口馬木也の佇まいがあまりにもナチュラルなせいで、他の出演者の芝居がクサく誇張されたものに見えてしまうのも事実。それくらいの圧倒的な本物感が山口馬木也にあったということでもある。
しかし、最後の真剣のくだりは、正直ザザッと音を立てるように気持ちが離れた。理由はいくつかあり、あの二人の対決自体は当人たちの決断としてお好きになさってくださいなんだが、撮影現場が容認してしまう流れは、全員が完全に狂気に取り込まれた!くらいの描写でない限り絶対にナシだろうと思ってしまう。ビンタで許されることじゃないよ、マジで。気がつけばあの二人が真剣でやりあっていて、誰も止められなかったとかならまだわかるんだけど。
あと、あの真剣勝負に、どこから撮ったの?という寄りの短いカットがモンタージュされるのも気になった。さらにいえば、これは単に自分の好みですけど、最後の対決だけは、撮影用に刀を上に掲げるように修正された上段の構えを、もともとの構えに戻して戦っていいんじゃないかなと思ったりしました。
廃れゆく時代劇と日本人スピリッツへの思いが溢れる
8月に都内1館のみの公開から全国100館以上での公開が決まったタイミングで、大急ぎで鑑賞。口コミで広がった映画にハズレはないとは思っていたが、出来栄えは想像以上だった。
幕末の京都から雷と共にタイムスリップする会津藩士の着地した場所が、一瞬、江戸時代の京都かと思わせて、実は時代劇を撮影中のセットだったと言う幕開けから、すでに捻りが効いている。そこからの展開は、映画スタッフや関わる人々が主人公を役者だと勘違いし続ける様子を上手に描いて、なんら不自然さを感じさせない。それは、タイムスリップの先輩がいたことが分かる後半でも同じだ。
ベースには廃れゆく時代劇とそれを支える人々、そして、日本人のスピリッツに対する熱い思いがある。こちらは自主映画で、越えるべき壁の高さに違いがあるだろうが、監督と脚本を兼任する安田淳一と『SHOGUN 将軍』で遂に天下を獲った真田広之とは根っこで繋がっているのだと思う。
今日がその日ではない
山口馬木也さん地味だけど名優ですよね
すっとんきょうな出だしから前半はコメディが続くが、因縁の(宿命の!)相手と再会してから一転して重厚な人間ドラマに様変わりする流れに無理はなく、ぐいぐい引き込まれてしまう
ゆうこのビンタは愛があふれてましたね
爽やかな名作でした!
侍、現代に溶け込みすぎwww
過去から現代にタイムスリップしてくる人を描いた作品は数多ありますが、この作品は、それらと基本同じですが、どこかしら一味違う感じもします。
“何が違うんだろ?”と思ったんですが、まずは、その制作。大手の作品ではなくて、インデペンデント作品だったんですね。最初1館で上映が始まり、徐々に上映館が増えて行って、大手の映画館でも上映されるようになったという。そのあたりは『カメラを止めるな』に似ていますね。
前半は、江戸時代から現代にタイムスリップしてきた侍が、徐々に現代社会に慣れていく様を描いていますが、この作品の本当の面白いところは後半部分。
この手の作品に有りがちですが、雷を契機にタイムスリップしてしまっているのですが、同じ時に雷でタイムスリップした人物と邂逅します。そして、そのもう一人のタイムスリップした人物と映画に出るという流れに。最後の最後のシーン、劇中で映画を撮っている(という設定の)人たちは知らないわけですが、この作品と見ている観客はこの二人の遺恨を知っているわけで、それがシーンに緊張感を与えます。
それと、侍の優子に対する思いが、優子以外にはバレバレなのも面白かったですねwww
中々に面白い作品でした。
話題作なので
WOWOWで鑑賞しました。
前半から中後半にかけてはコメディパート、後半は元の時代をベースに繰り広げられる人間ドラマ、アクションでバランス良く組立てられている。何となくテルマエロマエの時代劇版という気がした
ラストの真剣での死合いは彼らの背負ったモノ、生き様を見事に反映した臨場感たっぷりの立ち会いになってます。シンプルで分かりやすいストーリーになってますが、フックの効いた作品になってると思います。それと顔見たことあるかなくらいの印象ですが、いい俳優さんとの出会いもありました。おすすめ◎
元の時代に戻れるのか?戻れないのか?
幕末から現代日本へタイムスリップした会津藩士の男。
頼る者も無く、行き場を失って彷徨っていたら映画関係者である女性に助けられて寺に住み込みで居候に。
自分にあるのは剣の腕だけ。その剣の腕を活かして現代で生きていくには・・・「芝居の斬られ役を演じること」。
150年後の現代にカルチャーショックを受けつつ、幕府が滅んでしまって武士の自身など何処にも居場所が無いと絶望していたものが、自分自身で新しい時代に順応していくための努力をし、やがて周囲の人たちからも認められていく。
そんな時、彼の演技を見た大物俳優が彼を自分の出演する作品で起用したいとオファーが入る。
だが、そのオファーをしてきた男とは・・・・・。
武士の世の中が終わるなどとは、当時の人々の大多数は全く想定していなかっただろう。
しかし「武士という括り」が無ければ存在することさえできないと思っていた男は、武士である前に一人の人間であることに気付いていく。
侍という誇りを胸に持ちつつも、それをどうすれば良いのか持て余す。
江戸の世とはまた違った苦しみ。
それを分かち合える同士を得て、男は大きく成長するのだ。
最期に江戸時代に戻るのか?それとも戻らないのか?予想しながら観ると良いよ!
とっつきやすい
映画特有の暗さや、ボソボソ喋る聞き取りにくい話し方もない。
映画というよりは2時間のスペシャルドラマを見ている感じだった。
ただ、ラストの死合の緊迫感は映画そのもの。
時間をたっぷりと使い、緊迫した空気感を醸し出し、2人の切り合いを見守る制作陣と心を通わせられた。
かなりストーリーがポップで展開感もよく、正直「戸籍は?」「時代に順応するの早くない?」など、ツッコミどころが何度も登場するが、そんな揚げ足取りを置き去りする展開感で、見ていて気持ち良かった。
また、ラストにかかる小気味の良いBGM、そこから高坂の仲間が転生する、というラストは80~90年代のオシャレな洋画のような終わり方だったのも見事。
全体的に、コメディ要素に若干の古臭さを覚えるが、平成レトロ的な感じがして、むしろ良い味を出していた。
やっぱり映画は予算じゃないよねぇー
この作品は本当に観た方がいい!!
監督、スタッフ、協力者、俳優さんと、本作品に関わる全員の本気度が映像から伝播してしまう作品でした。
劇中にはいろいろ『んん?』が頭にが出てきちゃう場面もあるんだけれど、それがぜんぜん気にならないくらいに劇中に引き込まれます。
待てよ、、もしかすると端から期待せずに観たからか?と思い、2回観ました。ですが、2度目も劇中にいるような感覚に、フッと我に返る場面がいくつもありました。 特に終盤、寺での決闘シーンでは、あたかもその場にいるような錯覚にさえなりました。 俳優さんの緊迫感、終わりを迎える寂しさのような、堪らない感情がスクリーンからあふれ出て来ていました。
映画ファン必見の作品です。
日ごろの煩わしい事を忘れたい方は是非ご覧ください。
幕末の侍が現代にタイムスリップ!?
日本アカデミー賞で作品賞を受賞したのがきっかけでどんな映画なのか金曜ロードショーで初めて観ました。
幕末の侍がある夜の雷で目が覚めたら現代の日本にタイムスリップする所から始まります。そっから右も左も分からず彷徨ってしまい寺で居候という形になり、他の人からは時代劇の役者だと勘違いしますが、ある撮影で主人公の侍が斬られ役が凄っと感じ斬られ役で生きてきます。
中でもラストの殺陣シーンで真剣を使ってやるのが凄かったです。
※前述の通り日本アカデミー賞で有力候補(キングダム、正体)のどっちかと思ったらまさかのこの作品で僕は驚きました!
やっぱり低予算で製作した映画は凄いなと改めて感じました。
レビューが書けないほど、何度も見たくなる作品
公開当初は知らなかったが、東映撮影で撮影した時代劇とのことで公開から3か月経って見に行った。見た当初、今レビューを書こうとするが、なかなか筆が進まない作品だ。
ストーリーは単純明快でタイムスリップした侍が斬られ役になる話。山口馬木也氏演じる会津藩士・高坂新左衛門が侍で侍役を演じているのだ。所作、身なり、セリフがあって役を演じているのが時代劇の侍役だが、高坂の生きてる侍が現代で斬られ役になるのだ。
当初から高坂の侍の心情、小ネタ、最後の2人の侍同士の殺陣は素晴らしいが、今改めて見ると切ないのだ。
おそらく、時代劇が衰退と言われ、良くも悪くも変化していき、無くなってしまうものと重なってしまう。
時代劇について考えるにもいい作品だ。
武士の想いに心打たれつつ、しっかり笑いもある
タイムスリップした先が京都の映画村のおかげで、戸惑いながらも比較的あっさりと現代に溶け込めた幕末武士、高坂新左衛門。
斬られ役の練習で、ついお師匠を斬ってしまう場面は声を出して笑ってしまった。周りの人達がみんないい人たちで、ほんわかとした気持で見ていられる。
終盤、自分の藩(会津藩)の最後を台本で知ることになるが、幕末の会津藩といえば、白虎隊に鶴ヶ城の戦い、一番悲惨な結末を迎えた藩ともいえる。そんな会津藩の結末を知った高坂新左衛門が台本に向かって手を合わせるシーン、辛さ、無念さが、その表情から汲み取られ、こちらも胸が締め付けられる思いがする。
今の私達には及びもつかない覚悟を持って戦っていた武士の思いを、ほんの少し垣間見た気がする。
低予算とか無名の役者とか言われているようだが、どうしてどうして、近頃こんなに人の心をうつ邦画はなかなかないのではないか。映画館で観たかった。
関本さんの演技が良かった
たくさんの賞を受賞していたので、ぜひ観たいと思いつつも映画館で見逃したが、早速テレビで放映されたので観ることができた。
殺陣師の役の方が自然で良い演技をされていて、調べたところ関本さんという方でした。
元々は「どこかで誰かが見ていてくれる」の福本清三さんがこの役をされる予定だったそうですが亡くなられたんですね。
誰もが知ってるお顔でも、それほど有名でなかった福本さん、探偵ナイトスクープで「徹子の部屋」に出演してほしいという一ファンの依頼から実際に出演され、後に有名になりましたね、あれは感動もんでした。
タイムトラベルするときは、雷が鳴るのが定番なんですね、バック・トゥ・ザ・フューチャーもそうだったし。
しかしながら、一緒にいた人間が時間差で先に同じ場所にタイムスリップしてる…というのが面白かったです。
しかも、徳川幕府派と倒幕派…2人がバーでお酒を飲む…とか笑えました。
お金はそんなにかかってなさそうだけど、それでもいい映画が撮れるんですね、監督さん、スタッフさんの努力ですね。
時代劇って、お金も手間もかかるんでしょうけど、なくならないでほしい。
殺陣って、最高にカッコいいから。
そして……侍たちは元の世界に帰れたのだろうか??
気になるぅー!
時代劇場大好き爺さんにはたまらない!
いやいや脚本が素晴らしくたまらない。
時代劇場の良さが沢山です。
お寺の夫婦の爺さんの演技が上手い。
最後のシーンも、椿三十郎を感じるところもあり、あっぱれな剣術シーンです。
上がったハードルはちゃんと超えてくる作品
評判が良すぎてハードルが上がりすぎてた気がするので間をおこうという事で、今さら鑑賞。
ものすごくベタな展開ではあるものの、主演の熱演のおかげでとても面白かった。
時代劇を古臭いものとして自虐するネタに走らず、真摯に向き合ってる点に好感が持てる。
ただ、最後の真剣のくだりだけは好みではなかった。
二人の真剣勝負が避けられないものなのはわかるが、周りがそれを容認するのは違う。
プロデューサー?がベタなノリでお気楽なボケをかますシーンが物凄く余計に感じる。
ベタはベタでも、二人以外は真剣とは知らない設定で良いではないか。
師匠の「段取りのある立ち回りを本物に見せてこそ切られ役や」ってセリフは本当にその通りで、やはりそれこそ時代劇だと思いました。
って偉そうに言えるほど最近は時代劇観てないけれど、小さい頃、テレビで時代劇観てた人には十分刺さるものがありますね。
時代劇っていいものですよね
確かに本作で触れられている通り、時代劇は廃れてしまいましたね。
私が小さい頃は「水戸黄門」「大岡越前」「暴れん坊将軍」「銭形平次」「必殺シリーズ」等々、たくさんの時代劇がテレビで放映されていたものですが。
なんでそんなに廃れたんでしょうね。今でも面白いコンテンツだとは思うのですが。
海外で「SHOGUN」が受賞してましたが、まだポテンシャルはありそうです。
その時代劇への愛がふんだんに感じられる作品だと思いました。
最後の真剣による殺陣も緊張感があって良かったと思います。
しかし高坂さん、演技上手すぎですよ。殺陣だけならともかくセリフまで。すっかり俳優さんじゃないですか。失礼ながら幕末の田舎侍でしかないはずなのにスゴすぎます。(もちろん主演の山口馬木也さんの演技は素晴らしいのですが)
あと、どうでもいい突っ込みですが、高坂が街のポスターを見て幕府が滅んだことを知るシーン。左から右へ流れる横書き文字をスラスラ読むのはちょっと無理がないですかね?
あと、「幕府が滅んで140年」とありましたが、アラビア数字を読める日本人は、あの時代にほとんどいなかったはずですけどね・・・まあどうでもいいですけどね(笑)
傑作でした。面白かったです。
幕末の志士が現在の時代劇撮影所にタイムスリップするというアイデアがなんとも秀逸
安田淳一 監督・脚本・撮影・編集の2024年製作(131分/G)の日本映画。
配給:ギャガ、未来映画社、劇場公開日:2024年8月17日。
維新の武士が現代に迷い込むというアイデアが秀逸でもあり、チャンバラ殺陣映画のリバイバルという側面も有り、大変に面白かった。
全く知らなかったが、これだけの映画をほぼ独力で創った安田淳一という才能に大きな拍手を送りたい。今時珍しい(タイムスリップしたから当然という設定)硬骨漢を体現した主演の山口馬木也もとても良かった。
助監督兼任のヒロイン沙倉ゆうのも、主人公が恋する眼鏡が似合うみじかな存在として好感を覚えた。また、実在モデルがあるらしいが時代劇における殺人師(峰蘭太郎)の存在に陽をあてたのもGood。
時代劇出身のスター(冨家ノリマサ)も実は、タイムスリッパーであって主人公の闘いの相手であった。更に最後にまた一人やって来るというオチも含めて、実に面白いアイデア。
監督安田淳一、脚本安田淳一、撮影安田淳一、照明土居欣也 、はのひろし、音声岩瀬航、 江原三郎 、松野泉、床山川田政史、特効前田智広、 佃光、時代衣装古賀博隆 、片山郁江、美術協力辻野大、 田宮美咲 、岡崎眞理、編集安田淳一、殺陣清家一斗、助監督高垣博也、 沙倉ゆうの、制作清水正子。
出演
高坂新左衛門山口馬木也、風見恭一郎冨家ノリマサ、山本優子沙倉ゆうの、殺陣師・関本峰蘭太郎、山形彦九郎庄野﨑謙、住職の妻・節子紅萬子、西経寺住職福田善晴、撮影所所長・井上井上肇、斬られ役俳優・安藤安藤彰則、錦京太郎田村ツトム、多賀勝一、吹上タツヒロ、佐渡山順久、Rene、柴田善行、きらく尚賢、ムラサトシ、神原弘之、五馬さとし、田井克幸、徳丸新作、泉原豊、岸原柊、戸田都康、矢口恭平、吉永真也、楠瀬アキ、佐波太郎、高寺裕司、江村修平、山本拓平、西村裕慶、谷垣宏尚、篠崎雅美、夏守陽平、橋本裕也、
大野洋史、山内良、宮崎恵美子、岩澤俊治、雨音テン、水瀬望、石川典佳、結月舞、鈴木ただし、皷美佳、吉村栄義。
殺陣に息を飲む
ミーハー風情の私、3月に舞台挨拶付き上映のチケットが取れたのでお邪魔しました。当たり前ですが全体的に音楽や演出、編集は自主映画だねいう出来具合で、どうしてもチープに見えてしまうがそれは仕方のないこと。でもそんな映画が単館上映から広がってヒット作となったことに、謎の感慨深さを覚えた(多分、カメラを止めるな以来の感情)
裏方さんが出役もやっていたりと手作り感があり、キャストも主題歌もプロモーションも華やかな商業映画ばかり見ていることを少し考えさせられた。監督が愛車を売り払ってまで資金にあて制作したというエピソードを知り妙に納得。
設定は突飛だが、とにかく殺陣が素晴らしい。時代劇など全く縁のない生活をしてきた私、いかにも時代劇~ではない作りなので余計に殺陣のシーンが新鮮で際立って見えました。
今も上映しているとのこと。キャストのファンというよりこの映画のファンがたくさん増えたのだなと、舞台挨拶やSNSの熱量からも感じました。
本編で女性助監役をやられている方が実際に裏方をいくつか兼任されていることをエンドロールで知り、撮影所やインディーズ界隈の実情も、舞台挨拶のトークや彼女のインタビューから何となく伺い知ることができ、応援したくなりました。
此度、金曜ロードショーの放映が決まり、見に行ったことを思い出して、レビューさせていただきました。最後の方、(ややネタバレになりますが)
真剣でやり合うシーンの殺陣は圧巻で呼吸を忘れていました。もちろん、実際は真剣じゃないけれど、どうなるのかというハラハラドキドキ。
映画自体は、笑いあり、涙あり、現代の生活を考えさせられたりもしました。
悪い人がだれも出てこない。役者さんは知らない方が大半ですが切られ役から主演まで全て良かった。
今さらですが、山口馬木也さんに日本アカデミー賞最優秀男優賞をあげたかった(笑)
チャンバラ時代劇
子供のころは時代劇は身近にあったなぁ。
朝、夕方、ゴールデンタイム、いろんな時代劇やってたけどあまり観ない子供だった。優子ちゃんとは違って。
幕末、会津藩の高坂新左衛門は長州藩士を討ちにいく。
そこでの立ち会いがなんだかショボくてそんな大袈裟な目逸らしに引っかかる?って思いながら雷に打たれる。
雨の降る地面に反射するオープニング。
気がつくと太秦映画村!おぉ!
戸惑いながらもうっかり時代劇撮影に混ざったり、頭をぶつけて病院に来たり、外を見たら街並みが変わってて衝撃を受けて脱走して、ポスターで140年経っている事がわかる…元の時代に戻れず、自死もできず、西経寺の住職さんに拾われる。
ツッコミポイント多いんだよ、ベッタベタなんだよ。そもそも私は生まれてこのかた髷を結った御仁にすれ違った事はござらん。
私、この映画最後まで観れるか少し心配になる。
しかし!
ショートケーキを初めて食べた時、彼は涙を流す。
単純に美味しい!ではなく命を賭しても日の本の平和を願い刀を握り仲間と戦い続けた自分の人生のその先にこんなに美味しいものを庶民が気軽に食べれる世の中になった事が嬉しいのだ。自分達がこの未来に貢献できたと。
もし、私が140年先の未来にタイムスリップして今まで見た事がない未来の極上の物を食べてもそんな感想は出ない。何故なら平和ボケだから。
もう、そんなの見たら高坂さん大好きになるじゃん。
そこから私の高坂ポイント爆上がりで何をしてても素敵。
優子ちゃんが気になってソワソワしたり、切られ役を表情までちゃんと死んでたり、龍馬に拳銃に撃たれて血糊でマジ死んだ…って走馬灯見たり。それはそうだ。銃で撃たれた経験もないし、血糊なんて知らないし死んだ事もない。「ナンジャコリャー!」てなる。素直で真面目で天然ボケ。
そんな息子にしたいNo.1な彼は住職夫婦に親しまれ、切られ役として生きる事にする。
人を斬る世の中ではない。食うに困らず平和な世の中。自分に出来る事は唯一褒められた「斬られ役」
その時の優子ちゃんの作品に救われた高坂、そんな言葉に毎日忙しく働き愛情を持ち作品を作る優子ちゃんも救われていた。
お師さんとの稽古で毎回切っちゃう所、お師さんのきちんと決めてくる死に顔に斬られ役マスター感を感じて笑いが止まらなかった。ずっとやって欲しい。
そんな斬られ役のスターダムに登っていくのだが、何がいいって周囲の人々がとにかく良い人ばかり。
新人斬られ役にいじめをするわけでない先輩、主演の俳優も奢りだ〜って一緒に声をかける。
彼は時代劇が失われつつある世の中に時代劇という自分の生きてきた過去を残し「斬られたモブ」として大切に作り続ける。
いいぞいいぞ、高坂くん。
そしたらまさかあの!長州藩士の山形がいるじゃないの!
しかも大スター。彼は時代劇の大作作りに高坂を抜擢し、自分が高坂より30年前にタイムスリップをして同じ様な経緯でハリウッド進出までしていた。
うわ〜すごい胸熱展開きたよ〜思いもしない舵取りにワクワクが止まらない。
過去は敵同士だった2人、今では高坂が大事にしている時代劇を風見は捨ててしまった。唯一彼らが生きてきた時代を模した作品を捨てた事を高坂は許せない。
馴れ合うつもりはない…なスタンスで接する高坂だが風見は好意的。30年の重みは違うのだろうね。
2人だけで話す時お江戸言葉になるのいいなぁ。
140年前でもやはり人を斬るのは辛く今でも思い出す風見も敵対はしてても悪人ではないのだね。
恨み顔が忘れられない。成仏してくれ…腰を落とし声をかける事。時代劇だからこそ風見はその気持ちを吐き出す事ができた。
会津藩がどんな目に遭って途絶えたのかを知り激しく動揺する。自分の守ったニッポンは平和になったが仲間や家族達がどんな目にあったか。それは複雑で吐き出し口が分からない。そうね。過去の事だしもう済んだ事。しかし自分はここで何不自由なく暮らしている。思いがループする。
風見と真剣で勝負に挑みその心を汲み取った風見も了承し、真剣で撮影が始まる。
長い睨み合い、両者動かない…この辺で私は泣けてくる。鯉口を切った瞬間激しい打ち合いが始まる。キンッと金属音と空を切り裂く音。殺陣ではない。しかし2人の勝負は明らかに140年前より剣筋が出来上がっている様に見える。まさか未来の時代劇、むしろ「ごっこ遊び」の様な時代劇の斬られ役として剣王に近づいていた彼ら。
もうやめようよ〜平和なんだからいいじゃん〜仲良く撮影して〜とグスグス泣いていたので他の観客には迷惑をかけてしまった…
成仏してくれ。
倒れる風見と舞う血飛沫。
を、観る住職夫婦。
よ、良かった…
優子ちゃんにはビンタ一発かまされ、無事に撮影終了。
決して主役を演じる側にまわるではなく、その後も斬られ役として生きていく彼がとても好き。
剣心会でお師から学び続け、住職夫婦と仲良くコンビニのショートケーキを食べ、優子ちゃんへなかなか想いを伝えられない甘酸っぱい平和なこの世を生きて欲しい。
きっと風見もこれからの時代劇を支えていくからたまにはウィスキーを呑みに行ってお江戸言葉で語れば良いよ。
優子ちゃんの服装がダサいのが良かった。
決してボーダーのポロシャツがダサいのではなく、全体的に野暮ったくオシャレよりも時代劇を作る事に邁進しているというキャラが好き。
高坂さんとの恋愛フラグはなかなか立たない予定。
設定がガラケーだったりパラボラアンテナが乱立してたりするからやや昔なのかな。
それなら高坂はまだ時代劇を続けているのかな?テレビをつけたら斬られ役としてまだいるかもな〜なんて思いながら庶民の幸せコンビニのショートを買って帰った。
こんな風に登場人物達の幸せを願える作品は良作。
全265件中、1~20件目を表示