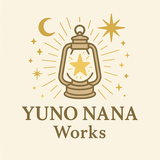侍タイムスリッパーのレビュー・感想・評価
全1302件中、1~20件目を表示
インディーズ映画が日本アカデミー賞をとってしまう驚き
池袋駅西口にあるシネマ・ロサでインディーズ作品として単館上映された作品が、口コミで広がり、ギャガが配給に協力して、まさかの第48回日本アカデミー賞最優秀作品賞…。こんな夢みたいなことがあるんですね。
本作がこの1年で最も素晴らしい邦画と言われたら困るのが正直なところですが、直球の優しさや一生懸命さ、責任の引き受け方を観ることができたのは純粋に嬉しいし、楽しい。斬られ役に徹せられず、咄嗟に師匠を斬り込んでしまうシーンも笑ってしまいました。
カメラワークやポジションがやっぱり上手い。ファーストショットの横移動のカメラワークで平凡なインディーズ作品ではないことが一発で分かるし、カメラポジションによってタイムスリップを実現させている。
それはタイムスリップ先の東映京都の地の利もあると思うが、高坂新左衛門を真正面から捉えるカメラと時代劇の撮影をするカメラは直角の関係になっており、高坂が移動し時代劇のカメラに合流することで、時もまた合流するのである。
つまるところ本作は本当の侍になりたい「未熟な男児」の成長物語であり、そんな主人公と本当は侍になりたかった観客が合流したことによって、熱狂を生み出したのだろう。私はファンダムとか応援上映とか大嫌いだし、独りで勝手にみろとは思ってしまうのだが、本作がそれでも気持ち悪さをかいくぐっているのはヒロインの山本優子の佇まいのおかげだろう。
優子は最後まで眼鏡を外さなかった。それは斬られ役の所作と同等にもっと重要視されていいと思う。
不滅の風情
「いかにも低予算」
「無名の役者ばかり」
「ベタな設定云々」
もし仮に、もしも仮に、この映画が巷でそんな風に評されていたとしたら、私はそれらの言葉をかき集めて火薬いっぱいの三尺玉に詰め込み導火線に火をつけてやりたい。
あ、別に危険思想ではありません。
その三尺玉は大空に放たれて大爆発。大輪の花火となり多くの人々足を止めてい見上げるだろうと思う。と、言うか既にそうなっている。もちろん立ち止まらない人もいるだろうけど。てもやっぱり私は足を止めて見上げたい。
「殺陣」と言う何やら物騒な漢字が時代劇のアクションを指す言葉だと知った時、ひとつ物知りになったような気がして嬉しかった。そしてその殺陣はそれこそ血の滲むような稽古に時間を費やし時代劇を観る全ての人が喜べるようにと綿密に練られた技だと知って憧れた。だから冒頭の3行に対して私はついつい熱くなりカッカしてしまうのだ。
花火のように日本人の心の中にある風情、時代劇。時代の波にのまれて消えて欲しくない。ふと忙しい足を止めて立ち止まった時いつでもそこに在るものであって欲しい。
夢ある受賞!自主制作作品から第48回日本アカデミー賞最優秀作品賞受賞の快挙!!
自称映画好きなワタシ。
2024年の映画業界を静かに時に熱い視線で見守ってきたつもりだった。今年もいい映画をたくさん観て心から満足していた。楽しみにしていた日本アカデミー賞授賞式。横浜流星くんの主演男優賞、大沢たかおさんの助演男優賞、河合優実ちゃんの主演女優賞、吉岡里帆ちゃんの助演女優賞とここまでは予想通り🧐
しかし、最後にそれはおこったのです。唯一私がノーマークで未鑑賞であった「侍タイムスリッパー」がなんと最優秀作品賞を受賞したのだ。てっきり「正体」か「夜明けのすべて」の2択だと決め込んでいた。
ええっ?!ええっ?やらかした…。
どうして見逃したんだろう???
しかも調べれば京都発の自主制作映画だという。ノーマークで未鑑賞であった自分を今更ながら猛烈に反省した。無意識ながら、時代ものはスルーするクセが祟ってしまった😭
気を取り直して本日遅ればせながら
いざ、禊の鑑賞でござる⚔️
感想は
はい、優勝🏅
いいものはいい。理屈じゃなくとりあえず一度ご鑑賞あれ🫡
映画の原点みたいなものをこの作品に観た気がしましたよ。脚本があって、演じる人がいて、それを撮る人がいて。シンプルにいえば、それだけで十分なのです。話はありがちな設定ではあったものの、笑いや涙を交えて終始飽きさせない130分でした。シリアスではなく、コメディに主体を置いたのが良かったと思う。
監督・脚本・撮影・照明・編集もろもろを担当し、自身の全てを賭けてこの作品に向き合い結果を手に入れた安田淳一監督本当におめでとうござます🎉まだまだ日本映画業界も捨てたもんじゃありませんね!こういったインディペンデント映画が最優秀作品賞を受賞できるという事実に夢が広がります。
笑いと涙とメッセージ性がしっかりとある作品
見る前は、侍が現代にタイムスリップしてきて、現代とのギャップにドタバタとなるコメディかなと思ったら、予想通りのコメディ要素はあるものの、しっかりとしたメッセージ性も高い作品だった。
時代劇が廃れていく寂しさは、朝ドラの「カムカムエブリデイ」も描かれていて、世の中栄枯盛衰だから致し方ないよなーと思ったけれど、現代の人たちの視点ではなく、あの時代を生きた侍に時代劇を演じさせることで、より一層の寂しさが募ると同時に、申し訳なさみたいな感情が芽生えた。
また、当事者の彼らの視点だからこそ、現代にあの時代の皆の想いを残したいという気持ちの強さがより伝わってきて、涙腺が刺激された。
幕末の志士たちは、新政府軍と幕府軍に分かれて各々の信念のもと戦ったけれど、どちらが正しいというわけではなく、ただその時貫いた信念が今に続いている。会津藩の高坂にとっては辛い事実でも、今日本は争いのない平和な世になっているし、良い国にしたいという彼らの願いは叶えられているんだよなと思った。
インディーズ映画あるあるで、俳優さんは皆さん初めて見る方々でしたが、主演の山口さんの演技がとてつもなく良かった!わざとらしくなく、本当に侍がタイムスリップしてきたような動作や話し方で驚いた。周りの方々の演技がわざとくさく見えてしまうほど。
また、劇伴や効果音がちょい古典的でダサいのは笑ってしまうw
カメとめの再来言われていて、ずっと気になっていた作品だったので、見れて良かった!
純真無垢な昔堅気の映画野郎
タイトルと主題だけでなく、この映画丸ごと、タイムスリップしてきたかのような気がしました。弟子入りを志願して「落ちる滑るって言っちゃいけない」などというベタベタのシーンがそれを表していたかのような。水戸黄門、銭形平次など昔の人の如何にもというやり取り、困っている人を放っておけない優子さんのような古風な頑張り屋が活躍する、庶民的な舞台劇を観たかのような、そんな印象。
タイムスリップといってもSF要素は余りなく、古き良き時代劇や映画バカの撮影風景、そういうのがテーマだったのではないでしょうか。撮影所の楽屋?でポスターは時代劇なのに、テレビの横に並んでいたDVDは、何故か伊丹十三監督作品。これも、この映画の主張の一つだったのかな。話の流れも無理などんでん返しもないトントン拍子。最後に武士の身の上に立ち返っての一騎打ちも、まあ、予測通りではあるけれど。
でも、最後の殺陣(たて)は痺れました。いつ動き出すんだという凄まじいタメ。刃が打ち合う鋼の音は、これまでのチャンバラシーンで録に擬音を付けなかったのが効果を上げているのでしょう。本当に真剣でやっているんじゃないかという緊迫感。劇中劇の顛末も踏まえて、歯を食いしばってしまうほど凄まじかった。
そして出来上がった劇中劇の映画は、なんというか、本当に無骨な作品のようですね。この映画とまったく同じ、最後の一騎打ちが売りでしかないような骨太い時代劇のようですけど、果たして、売れるんでしょうか。恐らく、例え売れなくとも「これぞ本物の映画だ」という評価さえあれば、劇中の監督も満足したのではないでしょうか。この映画そのもののように。
この前に観た「ルックバック」という漫画家のアニメ映画を思い出した。自分達の仕事をもモデルにしているからこそ、カタルシスが凄まじい。ましてや、私たちも武士の国。美味しいおにぎり、美味しいケーキがいつでも食べられる時代になって本当に良かった。先人達に感謝、感謝。
昔の人が生きた時代の延長線上に私たちの現在はあるのだ
どこにでもあるショートケーキをはじめて口にし「これが普通の人でも食べれるとは。。本当に良い世の中になった。」とボロボロ泣く。会津藩の悲惨な最後を知り、むせび泣く。感極まるこの2つのシーン。昔の人たちの努力や犠牲の上に、私たちの平和で豊かな世界があることを改めて実感し、感謝した。
竹光で本身を振っているようにみせるため、振り方を試行錯誤した結果、本当に重さが加わったように見えてきた演技に驚き。 いやいや待て待て。この映画の中にいくつかある真剣のシーンも、実際は竹光使って演じているはず。(クライマックスの風見との対決シーンなど)凄い演技力だ。
クライマックスの戦いのシーン。最初のながーい無音の時間の演出が真剣による緊張感を最大限高めることに成功している。
時代劇を辞めて東京に行っていた大物俳優の風見恭一郎が、時代劇&京都に凱旋。このシーン、風見が真田広之とオーバーラップした。真田広之は別に時代劇やめてないけど。(笑
2021年に上映された『サマーフィルムにのって』を思い出した。共通項多し。
・タイムスリップもの
・時代劇
・映画を撮る映画
・低予算ムービー
・拡大上映!
そしてなんといっても「空気感」が同じなのよ!
朴訥なこの侍のように、背筋を伸ばし、周りに感謝して生きようと、気持ち新たに映画館を出た。
※失礼ながら知らない役者さんばかり。
※高坂と風見と女将さんがいい!
※風見は誰かに似てるなあ~と思ってあとで調べたらそうそう「別所哲也」「 西岡德馬」「嶋大輔」だ。冨家ノリマサさんという方なんですね。これからチェックさせていただきます!
※真面目で無骨で、少し汚い高坂が侍っぽくてとてもいい!
※ロケ地は随心院、亀岡の大正池まではわかった。京都がほとんどだと思う。聖地巡りしたい。
→ 10.15追記 このレビューで教えていただいた「油日神社」に行ってきました。最後の真剣でのシーンの舞台です。京都でなく滋賀県(三重県との県境)でした。飾り気のないとても良い気が流れる神社でした!ぜひ。
※風見が怒って池に石を投げ込むシーン(笑 見逃さないよ。
※どうしても受けてしまったり、師匠を斬ってしまったりするシーンも笑けた!
※パンフレットはまだ届いていなかった。あらためて買いにいかねば。
※殺陣の指導シーンで「当たるから切っ先は上へ」と。なるほど。
山口馬木也に主演男優賞をあげたい
インディペンデント監督が書いた脚本のために京都の撮影所が協力して実現した娯楽活劇コメディ、という作品の成り立ちは美しいし、主演の山口馬木也があまりにもみごとで、立ち姿や所作、殺陣の決まり具合に惚れ惚れする。
しかも演技がべらぼうに上手い。上手いを超えている。正直、和尚が檀家の前で電話をするシーンとかは観終わってあれ必要だっけ?と思ってしまったし、ベタすぎて鼻白む部分も多いのだけれど、どんな場面でも、どんなセリフでも、山口馬木也という人が驚くほど誠実に、自然に演じてしまうので、山口馬木也を見ているだけで十分お釣りがくる!という気がしてくる。
ただ、別の時代からやってきた異分子という設定に即していて成立してないわけではないのだが、山口馬木也の佇まいがあまりにもナチュラルなせいで、他の出演者の芝居がクサく誇張されたものに見えてしまうのも事実。それくらいの圧倒的な本物感が山口馬木也にあったということでもある。
しかし、最後の真剣のくだりは、正直ザザッと音を立てるように気持ちが離れた。理由はいくつかあり、あの二人の対決自体は当人たちの決断としてお好きになさってくださいなんだが、撮影現場が容認してしまう流れは、全員が完全に狂気に取り込まれた!くらいの描写でない限り絶対にナシだろうと思ってしまう。ビンタで許されることじゃないよ、マジで。気がつけばあの二人が真剣でやりあっていて、誰も止められなかったとかならまだわかるんだけど。
あと、あの真剣勝負に、どこから撮ったの?という寄りの短いカットがモンタージュされるのも気になった。さらにいえば、これは単に自分の好みですけど、最後の対決だけは、撮影用に刀を上に掲げるように修正された上段の構えを、もともとの構えに戻して戦っていいんじゃないかなと思ったりしました。
廃れゆく時代劇と日本人スピリッツへの思いが溢れる
8月に都内1館のみの公開から全国100館以上での公開が決まったタイミングで、大急ぎで鑑賞。口コミで広がった映画にハズレはないとは思っていたが、出来栄えは想像以上だった。
幕末の京都から雷と共にタイムスリップする会津藩士の着地した場所が、一瞬、江戸時代の京都かと思わせて、実は時代劇を撮影中のセットだったと言う幕開けから、すでに捻りが効いている。そこからの展開は、映画スタッフや関わる人々が主人公を役者だと勘違いし続ける様子を上手に描いて、なんら不自然さを感じさせない。それは、タイムスリップの先輩がいたことが分かる後半でも同じだ。
ベースには廃れゆく時代劇とそれを支える人々、そして、日本人のスピリッツに対する熱い思いがある。こちらは自主映画で、越えるべき壁の高さに違いがあるだろうが、監督と脚本を兼任する安田淳一と『SHOGUN 将軍』で遂に天下を獲った真田広之とは根っこで繋がっているのだと思う。
低予算だからこその面白さ
面白っ!
お金もかかってませんし、有名な俳優さんも出てない。でも、面白いです。
マジで、人気俳優メインのつまらん映画とかやめて、こんな映画がたくさんできるといいなと思います。
ストーリーは、昔の人が現代にタイムスリップするという、ありきたり(?)なものですが、グイグイ引き込まれてしまいました。
感想
多分、かの時代のお侍たちは、
いろいろ性格があるにしても
高坂さんや風見さんのように
真剣を腰に刺し、
その重みや怖さを充分に知るが故、
名のごとく真剣に生き
いつなくなるかもしれない自分の命を守り
その時が来れば差し出す覚悟で毎日を
暮らしていたのだろうなぁ。
故に明治維新に繋がる様々な事に
自身も参加していた責任上、
風見さんからのオファーがあっても
受け入れられないのだろう。
しかし、風見さんの
この時代で生きていくのだ、
サムライとしての勤めを果たせ、
という言葉で考えを改める。
よく怒らなかったものだ。
現代の日本人に対して。
ダラけているとは思わなかったのか。
皆真剣な表情で仕事する撮影現場にいたからか?
住むのもお寺で住職夫婦だし。
一度不良たちにやっつけられたが、
江戸の時代でも不届きな輩がいたから
別段違うとまでは思わなかったのか。
高坂さんの人柄のせいだろうか。
コレしかできないと時代劇での斬られ役、
所長も言っていたように
日々精進していれば日の目を見れる、と。
本作の人気が高いのは、
希少な時代劇モドキというだけでなく、
山口馬木也さん演じる高坂の人物像に魅力があるから
ではないだろうか。
無骨なまでに信念を貫く姿に共感共鳴するのだろう。
しかし、時代劇ファンなら
真剣勝負なる殺陣のシーンが感動モノで、
他の殺陣シーンもドキドキワクワクだったように思える。
インディーズ映画!?面白い
こき下ろすつもりで観たが素晴らしかった
よくあるタイムスリップでドタバタコメディなのかと思ったが、それだけではなかった
ちゃんと侍としてストーリーに活きていたし、侍でなければ物語が成り立たないものになっていた
起承はよくあるものだなーと観ていたのもつかの間
転の部分ではそうくるかと唸らせてくる
クライマックスでは令和の時代に作られたと思えない神がかった間
じっくりと、かつ、緊張感を持たせる間で評価が一気に上がった
思わず息を呑むような演技、殺陣、カメラワーク、そして間
それまでフッと鼻で笑うようなコメディしていたとは思えないクライマックス
鬼気迫る怒涛の迫力だった
邦画はクソみたいなものばかりだが極稀に素晴らしい作品が出てくる
それがこの映画だった
忌避感がある人も騙されたと思ってじっくりと腰を据えて観て欲しい作品だった
監督、俳優さんに感謝しています。
「アカデミー的時代劇である現代劇」こそタイムスリップ
しばらく日本を離れていたせいか、この映画をめぐる評価に、完全にタイムスリップした気分になった。
インディペンデント映画として大ヒット、日本アカデミー賞・最優秀作品賞と聞いて観たが、「どこがそこまで?」というのが正直な感想。
低予算、大部屋俳優総動員、内輪的な熱量。
作りとしては時代劇版『カメラを止めるな!』で、嫌いではない。
ただ、これを年度代表作として祭り上げるのは、さすがに評価を盛りすぎではないかと思う。
話題性と無難さを取り違えるあたり、日本アカデミー賞らしいといえばらしい。
この映画のいちばんの問題は、
一見すると歴史の重さや矛盾を描く顔をしていながら、
最終的には「安心して消費できる時代劇」にきれいに着地してしまうところだろう。
挑発的な構えを見せておいて、誰も不快にしない。
そこが、この作品の自己矛盾のいちばん分かりやすい点だと思う。
会津の重さを真正面から引き受けるわけでもなく、
薩長史観を問い直すほど踏み込むわけでもない。
歴史は角を取られ、ほどよく軽く、ほどよく無難な物語へ。
「考えさせるふり」をしながら、ちゃんと安心して見終われる設計だ。
個人的には、
山口馬木也さん(大河出演おめでとう?)、
沙倉ゆうのさん(知り合いの劇団員感がすごい。そこにおるで!)、
冨家ノリマサさん(めちゃ久々やん?)、
紅萬子さん(お久しぶりで好きやけど、面と向かって名前呼べないやん!)
を確認する映画で終わってしまった。
悪くはない。
でも、この作品が「その年の顔」になる日本映画界の感覚には、やはりついていけなかった。
2024年に生まれた奇跡の作品として、長く語り継がれるべき映画だと感じた。
2024年の映画界を語るうえで、『侍タイムスリッパー』は欠かすことのできない一本である。
自主映画であり、出演者もポスターも地味。誰もが「小規模な話題作」で終わると思っていた作品が、まさか“2024年を代表する奇跡の大ヒット作”になるとは、誰も予想していなかっただろう。
その奇跡を生み出した中心にいるのが、監督・安田淳一だ。
米農家として働きながら、1500万円の貯金をすべて投じ、愛車のスポーツカーを500万円で売却し、さらに国の補助金600万円を加えて、総額2600万円を製作費に全投入。
撮影後の預金残高はわずか7000円。
ここまでして作品を完成させようとした“覚悟”と“行動力”が、映画そのものに宿り、観客の心を動かしたのだと思う。
脚本は、現実には起こりえない設定であり、もし起きたとしても映画のように物事が進むはずはない。しかし、この作品は単なるコメディに留まらない。
笑いの中に、武士の誠実さ、人情、そして“人が人を思う温かさ”が深く流れている。
出演者たちの素朴で誠実な演技が、脚本の矛盾を自然に補完し、物語を違和感なく前へ進めていく。これは、“役者の身体性が脚本を救う”典型的な成功例と言える。
特筆すべきは、東映の殺陣専門家が役者として出演している点だ。
現実の殺陣師が虚構の中に入り込むことで、作品は“現実と虚構の交差”という独特の構造を獲得している。
東映が長年培ってきた時代劇のノウハウが、エンターテインメントとしてわかりやすく、かつ愛情深く表現されているのも魅力だ。
『侍タイムスリッパー』は、幅広い層が楽しめる娯楽性を持ちながら、同時に“時代劇の面白さ”を再発見させてくれる作品でもある。
そこには、時代劇を支えてきた人々の努力、誇り、愛情が確かに息づいている。
自主映画という枠を超え、
「時代劇とは何か」
「人が誠実に生きるとはどういうことか」
を、笑いと温かさの中で静かに伝えてくれる一本だった。
2024年に生まれた奇跡の作品として、長く語り継がれるべき映画だと感じた。
今日がその日ではない
山口馬木也さん地味だけど名優ですよね
すっとんきょうな出だしから前半はコメディが続くが、因縁の(宿命の!)相手と再会してから一転して重厚な人間ドラマに様変わりする流れに無理はなく、ぐいぐい引き込まれてしまう
ゆうこのビンタは愛があふれてましたね
爽やかな名作でした!
侍、現代に溶け込みすぎwww
過去から現代にタイムスリップしてくる人を描いた作品は数多ありますが、この作品は、それらと基本同じですが、どこかしら一味違う感じもします。
“何が違うんだろ?”と思ったんですが、まずは、その制作。大手の作品ではなくて、インデペンデント作品だったんですね。最初1館で上映が始まり、徐々に上映館が増えて行って、大手の映画館でも上映されるようになったという。そのあたりは『カメラを止めるな』に似ていますね。
前半は、江戸時代から現代にタイムスリップしてきた侍が、徐々に現代社会に慣れていく様を描いていますが、この作品の本当の面白いところは後半部分。
この手の作品に有りがちですが、雷を契機にタイムスリップしてしまっているのですが、同じ時に雷でタイムスリップした人物と邂逅します。そして、そのもう一人のタイムスリップした人物と映画に出るという流れに。最後の最後のシーン、劇中で映画を撮っている(という設定の)人たちは知らないわけですが、この作品と見ている観客はこの二人の遺恨を知っているわけで、それがシーンに緊張感を与えます。
それと、侍の優子に対する思いが、優子以外にはバレバレなのも面白かったですねwww
中々に面白い作品でした。
全1302件中、1~20件目を表示