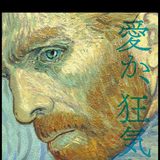ぼくが生きてる、ふたつの世界のレビュー・感想・評価
全266件中、161~180件目を表示
日本版コーダ?音が少ないのが絶妙に良い
両親が聾者から生まれた、健常者の一人息子 小さいときから心ない田舎者からの差別的行為を受けながらも、強く生きてきた家族 堪らなく涙がこぼれた… 健常者じゃないと生きることすら儘ならないのか 田舎のあの独特な雰囲気とでも言うか村八分傾向が、この家族を日常から遠ざける… 一概に田舎が悪いとは思えないけど、健常者じゃない立場に立って観るべきことも有るんだよ✨お山の大将ではなく、共存して欲しい
24時間テレビのドラマみたいなクオリティ
良い関係性を持った家族だなぁ
ぼくが生きてる、ふたつのせかい
静かな映画
聾者の両親のもとに生まれた主人公を中心に、
聾者とその家族の葛藤、愛情を描く映画
「聞こえない」親のもとに生まれた「聞こえる」こどもを、
『コーダ(Children of Deaf Adults)』と称するんですね。
初めて知りました。
主人公の出生から始まり、幼少期・小学校・中学校と進みます。
いろいろと嫌な思いをしたり、同情されたり…
自分の失敗を親のせいにしてみたりと、様々な葛藤がある。
しかも、同居の祖父は刺青しょった博打うちだし、祖母は宗教に傾倒しているし…
なかなかの家庭環境ですね。
私はエンパスの気があるので、ちょっと観ていて辛かった。
そんな中でも、聾者の両親は穏やかで誠実なタイプで、自己肯定感の強い、明るい人たち。
これが救いでしたね。
主人公も、いろいろと葛藤はありつつも愛情深くて、良い人。
静かな明るさが好印象でした。
映画としては、派手なことは何も起きなくて、
静かに静かにエピソードが紡がれていくもの。
エンタメとしてのおもしろさは無いかも知れないけど、
エピソードの向こうに透けて見えるものに感じ入りました。
母と子の暖かい関係
2022年の米国アカデミー賞作品賞を受賞した「コーダ あいのうた」に続く”コーダもの”(そんなジャンルがあるのか知らんけど)でした。 コーダ=CODAは、Child of Deaf Adultsの頭文字を取った言葉で、直訳すれば”聾唖者の親を持つ子供”という意味であり、本作でもこの言葉そのものもが出て来てました。「コーダ あいのうた」も本作も、聾啞の親と耳が聞こえる子供の親子関係にスポットを当てた良作でしたが、創作の物語でどちらかと言えばコメディ要素が強かった「コーダ あいのうた」に比べると、本作は原作者にして主人公でもあった五十嵐大(吉沢亮)のエッセイを元に映画化されていることや、舞台が日本であることもあって、非常に身近なお話に感じられました。
そして主役の大が生まれたところから始まり、大人になるまでを描くことで、特に母親である明子(忍足亜希子)に対する大の感情や二人の関係性の変遷が、非常に分かりやすく表現されていて、コーダの偽らざる想いが十二分に伝わってきました。
さらに大が故郷の宮城から東京に出て来て働き始めた以降の展開も面白く、第三者との関係性の中で両親、特に一度は反発した母親に対する想いが再び優しい方向に向いた時、こちらも自分の母親を思い出して涙腺が緩んでしまいました🥲
俳優陣は、主人公・大を演じた吉沢亮が、表情だけでなく後ろ姿を含めて実に繊細な感情表現をしていて素晴らしかったです。また、母親役の忍足亜希子はじめ、「コーダ あいのうた」同様に聾の役は聾の俳優が務めており、本作の見所とも言うべきものでした。
大が勤めることになった雑誌編集長のユースケ・サンタマリアも、怪しげでいながら魅力的な雰囲気で良かったです。
一点予想と違ったのが、東日本大震災の話が出てこなかったこと。原作者の五十嵐大は1983年生まれとのこと。主人公の大の生年は作中明示されていなかったものの、子供時代にファミコンでスーパーマリオに夢中になっていることからも、年代にブレはないのでしょう。従って、宮城県の海辺の街を舞台にした作品だったので、確実に震災の話が盛り込まれるだろうと思っていたのですが、実際はそうではありませんでした。
震災の話を入れるとそちらがメインになってしまいがちなので、それを避けたかったのか、全く当初から念頭にすらなかったのかは分かりませんが、そういう物語になっていたらどうだったのだろうと夢想しながら劇場を後にしました。
そんな訳で、本作の評価は★4とします。
Coda日本版と、言ってはいけない。
邦画を字幕付で観ると、字幕なしで観た時と違う印象を持つ場合がある。
聞き取れなかった言葉や台詞が文字で表された事により視覚と聴覚に二重に訴えるからかも知れない。最近は字幕付上映もあるので、邦画でも可能な限り字幕付で鑑賞している。今回は内容からも、あえて字幕付版の回で鑑賞。五十嵐大の自伝的エッセイの原作は未読。
9月24日(火)
新宿ピカデリーで「ぼくが生きてる、ふたつの世界」日本語字幕版を。
「Coda あいのうた」に触発された作品かと思ったがアプローチが違った。
この映画は大が生まれたところから始まる(背景音は無音)。宮城の港町、誕生祝いに集まる人々。両親は耳が聞こえない。赤ん坊の大が泣いても泣き声が聞こえない。小学生になった大は親と手話で会話するので同級生から奇異な目を向けられる。そんな状況に母親を疎ましく思い始める。授業参観日を母に教えない。奇異な目で見られたくないからだ。
高校受験のための三者面談でも耳の聞こえない母親は上手く相談に乗れない。塾にも通うが第一志望の高校には入れない。
20歳の大はやりたい事を探すため東京へ旅立つ。しかし、パチンコ店で働くなどしている。壁には上京する時に母が買ってくれたスーツが掛かっている。母から送られてくる荷物、食料品と封筒に入った五千円札。大は東京でも手話サークルに入り、聾者と交流する。
スーツを着て出版社の面接を重ねる大。やっと調子の良い編集長(ユースケ・サンタマリア)に採用され、編集の仕事を始める。しかし、その編集長も逃げ出し、大はライターとなる。父が病に倒れて見舞いに宮城に戻る。東京に戻る大を母は駅まで見送りに来る。その後ろ姿に上京する際の母の後ろ姿を重ね、過去の様々な母の姿を思い出し泣き崩れる。
無音世界から東京へ向かう電車は暗闇のトンネルを抜ける。それは別の世界に出て行く大の姿を現しているように見えた。
大は、母を疎ましく思いつつ、東京でも手話サークルに入り聾者との繋がりを続けて行く。サークルの飲み会で注文を耳が聞こえる大が行い、聾者でも出来るから余計な事をするなと諫められる(聾者の気持ちが理解出来ていない事を現している)。
少年時代を演じた子供たちが吉沢亮に似ているのは良かったが、さすがに中3を本人が演じたのはきつかった(似ている中学生はいなかったか)。両親を演じたのも、その他の聾者の役にも聾者の俳優を使ったのも良かった。祖母が烏丸せつこだったのがビックリだった。
本作にはユーモアはあってもエンタメ性はない。劇映画なのでその点が不満。(Codaにはあった)
Codaでは、大学に旅立つ娘を家族全員で見送り、娘は愛していると表現する。
上京する息子は、母親に愛する事を表現出来ない。
今日観た2本は、上京する息子を見送る母親(本作)と上京する娘を見送る父親(ごはん)が描かれていた。子供は親を疎ましく思っても、子を思う親の気持ちは変わらない。
そして、その思いを知った時に、子は親を思い涙を流すのである。
ドラマ『デフ・ヴォイス』と共通したところ
人気俳優が主人公のコーダを演じ、ろう当事者が親や友人として多数出演するとともに、手話表現の監修や演出まで関わって丁寧に制作され、母親役として忍足亜希子氏が抜擢されている点では、NHKドラマ『デフ・ヴォイス』と共通している。実話でもそうなのかもしれないけれど、主人公の生き方がはっきりせず、祖父母の人物設定が冗長で、また母親に比べて父親の出番が少なく感じられた。子役が赤ん坊から細かく区切られ、小学生時代は、『君の手がささやいている』のエピソードも採り入れ、演技場面も多かったから、中学生・高校生時代も、相応の年代の子役の演技をみたかった気がする。ろう当事者との絡みの場面は、ドラマ『サイレント』よりも薄いけれども、自己主張の強いろう者像も随所にみられたことは収穫であった。阿武隈急行にも乗りに行きたい。
小さな物語の大きな感動
予告編の吉沢亮君が無性に気になり、鑑賞する事に。
物語としては普遍的な親子の愛情物語なのだが、構成に一切無駄がなく過剰な演出もせず、でも描く所はしっかり描くという呉美保監督の手腕がはっきり見て取れる作品だったように思う。息子の誕生から始まり、前半部分では息子の成長と共にろうあ者の日常生活で生じる不便や困難、危険などが描かれ、さらに息子(吉沢亮)のコーダとしての葛藤や苛立ちもリアルに伝わってくる。この辺のさりげない自然な見せ方が実に上手く、しかも本当に無駄がない。最小限の表現で最大限の効果を発揮している。呉美保作品を観るのは初めてなのだが、前半だけで「この監督すごいかも」と思わずにはいられなかった。ろうあ者の日常生活において起こる様々な出来事はあらゆる困難や不安に満ちており、それらの多くが彼らにとってはあるある話なのだろうが、僕にとっては驚きの連続だった。
三浦友和に似てる似てないのバカ話、カレーの隠し味に味噌を使ってボロクソ言われる、パチンコ屋でどの台が出るか聞いてみたりする。まさにどうでもいいような「会話」を、彼らだって僕らと同じように日常的にしている事にすら僕は気付かずに今まで生きてきた。そんな自分を恥ずかしく思うが、それと同時に僕は基本的に「聞こえる世界」の住民であり、だから「聞こえない世界」というものを実は何ひとつ分かってない、という現実を思い知らされるのだ。最初は「ふたつの世界」って何だろう?と思っていたのだが、上映が始まってすぐに「なるほど、そういう事か」となる。
登場人物はみな素晴らしい。母は息子の全てを受け止め、信じ、寄り添い続ける。補聴器を20万で買い、ろくに会話出来てないにも関わらず「これで大ちゃんの声が聞ける」と嬉しそうに言う。それを聞いて泣かずにいられるかっつーの。父は地元で働くと言う息子に「東京へ行け」と背中を押す。たったひと言だが、父の思いがしっかり込められている。またフルーツパーラーのエピソードだけでも両親がどう生きて来たかをしっかり想像させてくれる。
じいちゃんとばあちゃんも素晴らしい。荒くれ者のじいちゃんなりに孫に何かを伝えているし、ばあちゃんは大にとって家庭内で貴重な「話し相手」だったわけだ。彼らの果たした役割(家庭としても映画的にも)は実に大きいと思う。また大の成長する姿だけでなく、彼らが年老いて行く姿を通じて、家族の「時間の流れ」というものをはっきり感じさせてくれた。2時間に満たない尺でこれだけ深みのある物語を作り上げた呉美保監督には本当に驚かされる。
また上京してから知り合う河合(ユースケ・サンタマリア)も非常に印象深かった。大(吉沢亮)の採用を決めるくだりも面白かったし、大がライターと喧嘩した後に河合が「大はどこでも生きていけそうだな」と笑いかける。それまで「何者」でもなかった大が東京に来てしっかり成長している様(さま)を河合の何気ない言葉が的確に表現しているように感じ、非常に深く刺さる言葉だと思った。そして偉そうな事言ってると思ったらタモリの言葉を丸パクリだったり、しまいには結局飛んでしまうという掴みどころのないこの男は、実は大の成長において(この作品においても)かなり重要な立ち位置だったのではないかと個人的には感じた。
そして最後。
これはもう完全にやられた。駅のホームで母からの「手話で話してくれてありがとう」という言葉に、不意を突かれた大は思わず泣き崩れる。ここでまさかの「無音」という演出かいっ!これは見事としか言いようがない。この静寂の瞬間、僕にはふたつの世界が「ひとつ」になったような、たまらなく愛おしい時間に思えた。もう本当にマジでやられた。母にとってはたわいもないひと言でも、この言葉がその後の彼を支え続けたんじゃないかと思うし、こういう小さな出来事ってきっと誰の人生にもあるはずなのだ。だから大のくしゃくしゃの泣き顔に、誰もがどこかで自分の人生と重ね合わせたのではないだろうか。そして大の心を表現してるかのように、真っ暗闇の奥に見える微かな光が大きくなりながら眩いトンネルの出口へと向かっていくラスト。もうただただ号泣です。最後に流れる歌(手紙の歌詞)も良かった。
やはり予告編で感じた直感は間違っていなかった。吉沢亮君の表情がとにかく素晴らしい。かつて「青くて痛くて脆い」で闇深い青年を演じて非常に良かったのだが、今回はさらに更新してくれた。ちょっと大げさに言えば、これで主演男優賞とか獲れないかなと本気で思ってしまう。この作品はシンプルなのに奥行きがある。基本はろうあ者のお話なのに、最後はそんなの関係ないと思えるほどの親子の物語であり、一人の青年の物語なのだ。
この作品は多くの人に強くお勧めしたい。
※追記
終盤スーツを買いに親子で洋服の青山へ行っていたが、さりげなく三浦友和ネタを回収していた事にあとで気付いた。なぜ三浦友和?と思っていたのだがそういう事かと感心した。
盛り上がる部分が欲しかった
誰もがいくつかの世界を生きている。
五十嵐大さんによって出版された自叙伝の実写化で耳の聞こえない両親の元に生まれた息子の成長を描く物語。両親を実際に聾者である俳優が演じている。
ごく当然だったことが、成長と共に違和感に変わってゆく。お母さんの通訳を誉められて誇らしかったはずなのに、いつの間にか手話を恥ずかしいと感じてしまう。そんな少年が成長しやがて東京へ旅立つ。そして都会の中にも両親と同じように耳の聞こえない人達がいて、それぞれが地に足をつけて生活していることを知る。
各世代の子役がしっかり吉沢亮に似ていて感心した。欲を言えば中学生までは子役でやってほしかったかな。さすがに吉沢亮の中学生はちょっと無理があった。
両親との確執ばかり描いたりせず、あくまで大の成長の過程の中での両親との関わり方を描いていて、そこがとても良かった。この世界の全ての家族と同じように。出版社のシーンも面白かった。
可もなく不可もなく🙏
健常者と障がい者との間に「壁」はない。
そんなきれい事はいくらでも言えるのです。
手話出来ないし、なんなら口話ですら
(唇の動きで会話読み取る)
めちゃくちゃ難しい。
壁とまでは言わないけど、やはりどうしても
隔たりがあるのが現実ではないかと思う。
喫茶店でパフェを食べている時
カウンターに座ったカップル。
あんな感じの無神経さ。往々にあるのです。
なんでも口に出す、それを正義と思っているし
なんなら何が悪い?と開き直る。
障がい者じゃなくても生きづらいいまの世の中。
大が「こんな家に生まれたくなかった!」の言葉は
確かに、両親がろうあ者であった事の苦労から
来るものでもあるけれど、
個人的には「ふたつの世界」ではなく
「ひとつの世界」での子供の成長日記と
親の深い愛情を思い出させる、とてもセンチメンタルな気持ちになる作品だったと思うのです。
点数5点は、作品云々ではなく
自分の素直な気持ち、可もなく不可もなく🙏
ぼくらが生きてる、ひとつの人生
前半の浮き沈みが激しく、それだけで、もう…
大の誕生による幸せムードから、聾者による子育ての難しさで一気に胸が苦しくなる。
差別的な意味ではなく、祖父母のサポート無しでは実際問題立ち行かなかったかっただろう。
(手話を憶えず明子を育てきったのもある意味凄い)
それでも愛情に溢れた家庭で幸せに育っていたところ、友人の「変」の一言で世界との隔たりを意識する。
手話で人気者になれそうなときにも、茶化す阿呆が…
しかし、花壇荒らしの濡れ衣を着せてきた女性含めて、悪意なき悪意が非常にリアル。
中学時代(サスガの吉沢亮でもムリがある)からの反抗期は、みんな身に覚えがあるのでは。
正直、観てて居た堪れなくなった。
だがそれに対し悩み、相談し合う両親の姿は、これも一般的なそれと何ら変わりない。
プータローからの上京暮らしは、両親の出番が減ったこともあり、うだつの上がらない平凡な日常。
大は、成りたいモノはないけど成りたくないモノはある。
だから面接で口では嘘をついても表情で自らバラすし、理不尽なライターには決して謝らない。
この辺は自分に似てて複雑な感情になった。
そんな半生を描く中で、言葉以上に物語る吉沢亮の表情や佇まいの奥行きが凄い。
両親はじめ脇もみな素晴らしいし、複数の子役が悉く吉沢亮っぽい上に演技もちゃんと出来るという。
サークルの酔って記憶なくした一人っ子女性が好き。
聾者同士の会話にユーモアがあって楽しかった。
誰にとっても人生は自分のもの一つきりだし、父も母も一人きりで、その中で生きていくしかない。
世界をいくつに区切ろうが、それは等しく変わらない。
素晴らしかった
出演者みんな良かった。
コーダの悩みや、障害者との関わり方もリアルなんだろうなと感じられた。
大ちゃんとご両親役のお二人が実は年齢が近いだなんて、観ているときはまったく感じず、祖父母や叔父叔母含め、本当の家族のようで自然だった。
お父さんが倒れて実家に戻った大ちゃんに、おばさんが「大ちゃんが生まれるとき祖父母が反対したけどお母さんは産んだ」と伝えるときの感じとか、私に語彙力がないから上手く表現できないのだけど、本当に関係ができてる家族の感じで、聞こえない両親の元に子が産まれることへの祖父母の不安と、子を産み愛したかった両親の愛、それを見守ってきた叔母、みんなが素敵で…
近所で鉢植えが倒されなぜか犯人扱いされる理不尽、
きちんとお母さんは怒ってくれたのに、お母さんが聞こえないから自分がこんな目に遭うと思ってしまう苦しさ、リアルだった。
面接で落ちる経験はしつつも、大ちゃんが東京で居場所を見つけられたのは、親や家族に愛されて慈しまれて育ったからなんだなと感じた。
ユースケサンタマリアの「大ちゃんはどこでもやっていけそう」「しがみつく場所ができたらいいね」の台詞が沁みた。
自分が「こんな思いをする」苦しさ・怒りを、本当は大好きな両親に向けてしまうことでの二重の苦しみが、上京するとき、駅のホームでの涙と表情に表現されていて、こちらも一緒に感情が高ぶり、たまらなかった。
手話をからかうような、小学校のときの同級生は問題外としても、飲食店で注文の際に良かれと思って“手伝ってしまう”のとか自分もやっているけど、当事者がそこまでいいのにと思っても言い出しづらい関係性だったら、良かれと思ってても相手にはありがた迷惑通り越して不快かもしれない…
自分も含め、障害者に障害を背負わせてる側の者として、どうするのが良いことなのか、考えて行動していきたいと思った。
お母さんが、外で手話を使う自分について、必要なものだ、ごめんと素直に伝えたこと。
率直に逃げずに向き合える親って素敵だなと思った。
大ちゃんは心の底では、外で手話を使うお母さんを嫌いとか恥ずかしいとか思ってないんだよね。
だから、東京で知り合えた手話サークルの人の知り合いとの誕生会に参加するし、上京前にカフェや電車でお母さんと自然に盛り上がる。
パチンコ屋さんで意思疎通が取れずに困っている人を、見て見ぬふりせずに助ける。
とにかく、とにかく、素敵な映画でした。
素敵な家族の、あたたかな物語なので、障害がテーマだとか思わず構えずに観てほしい。
主演の俳優さんは今旬の若手俳優さんだと思うが、そういう方が出たことで間口が広がって、たくさんの方に届くといいなと思う。
思い出した順に取りとめなくダーッと書いてしまったが、本当に良い映画です!
全266件中、161~180件目を表示