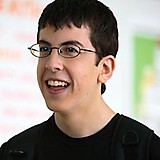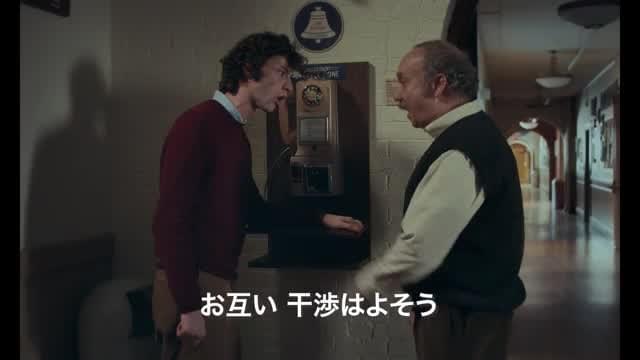ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディのレビュー・感想・評価
全50件中、21~40件目を表示
ハングオーバーみたいなタイトル
堅物教師とやさぐれ生徒がクリスマスシーズンを共に過ごすことによって互いの良さを見出し、それぞれに変化が訪れるという非常にクラシカルでトラディショナルな物語。
決して自分の信念を曲げない先生が彼の為に自己犠牲を選んだ瞬間に、涙したよね…。
彼の生き甲斐である職を手放す覚悟で生徒の未来を選んだ。考えを押し付けるだけではなく、自己犠牲の精神も経験した彼はより良い教師になっただろうに…。
展開は誰にでも読めるものだけれど、やっぱり感動しちゃう。
でもちょっと物足りなかったかな。
予想外のことが起こらないし、少し長い。
あと、序盤に出てきた他の生徒たちの物語も見たかったかな。
まあでもクリスマスシーズンに観るにはピッタリの佳作。「ハングオーバー」と対をなす作品としてどうぞ。
忘れ得ぬクリスマス休暇
1970年の暮れ、マサチューセッツ州の寄宿学校で共にクリスマス休暇を過ごすことになった教師と生徒、給食係の心の触れ合いを描いた作品。おりしもこの年の夏、韓国クンチョンでは金塊を巡って海女さんとヤクザ、国税局が入り乱れての争奪戦が行われた(「密輸1970」現在絶賛公開中)。
学園は年末のクリスマス休暇を控え生徒たちは浮足立っていた。しかし家庭の事情から休暇を寄宿舎で過ごす生徒もいて、その管理を歴史教師のポールが任される。堅物で融通の利かない彼は他の教師からも生徒からも嫌われていたが人情には厚い部分があった。
最終的に母親と連絡が取れなかった問題児のアンガスだけが残り、アンガス、ポール、給食係のメアリーの三人で過ごすこととなる。休暇を奪われ再婚した母に不満を抱くアンガス、ただ彼にはそれだけではないもう一つ大きな悩みがあった。
メアリーはあえて休暇を取らず今回の仕事を引き受けた。ベトナムで戦死した息子の遺影が飾られてるこの学園で過ごすために。
成績優秀ながらも貧困ゆえに従軍を余儀なくされ戦死した一人息子。富裕層の能天気な落ちこぼれ生徒たちがいかに憎らしかったことか。食事の味が悪いのは彼女なりの富裕層への抵抗だったのかもしれない。
事務員の女性のクリスマスパーティーで羽目を外したメアリーは息子を失った悲しみに耐えられなくなって号泣する。そんな彼女を見て気の毒に思うポール。
アンガスは生真面目でルールにうるさいポールとはことあるごとにぶつかるが、うまく彼を丸め込みボストンへの外出を勝ち取る。
そこで二人はある人物と再会を果たす、ポールは大学時代の同級生と、そしてアンガスは父親と。アンガスのボストン行きの目的は最初から精神病院に入院する父との対面だった。
誇りにしていた父の変わり果てた姿、もはや話も通じない。さみしさと不安を口にするそんなアンガスを慰めるポール。
そしてポールも学生時代のつらい体験を告白する。彼も出自は裕福ではなく富裕層の同級生にあらぬ疑いをかけられ退学となっていた。彼も天涯孤独であり、いままで心を閉ざして生きてきたのだ、まじめな堅物教師という仮面をかぶって。
立場の違う教師と生徒、普通に学園生活を送っていては到底過ごせない濃密な時間を共に過ごした二人。この時間が二人を少しだけ変えてゆく。
ポールから勇気を与えられたアンガスはもう問題児じゃあない。信頼できるポールとの出会いが彼を大きく成長させた。そして毛嫌いしていた問題児の生徒との心のふれあいを通して自分をさらけ出したポールもアンガスをかばい学校を辞職することとなる。あの堅物で融通の利かない男が一人の生徒のために自分の身をささげたのだ。彼はアンガスを救ったが、彼もまたアンガスから救われたのだ。もう今までの嫌われ者のポールではない。
けしてここまで深くかかわりあうことのなかった立場の違う人間たちが偶然のきっかけで人生を変えるほどの出会いを果たした。
アメリカ社会の貧困問題や格差問題も余すことなく描いた心温まるヒューマンドラマの傑作。
ちなみに宿舎に残されるのはヘイトしていた一番の問題児の彼だと思ってた。彼に比べればアンガスはむちゃくちゃ好青年に見えるけど。
誰しも、気軽に人に話せない葛藤がある
舞台は1970年代のアメリカマサチューセッツ州だけれども、フランス映画にも感じてしまう。それほど軽くなくしっかりと胸に残る映画。
全寮制の寄宿学校でクリスマス休暇に家へ帰れず残る生徒たちの監督役をすることになった教師のハナム。
皆と同じように家に帰るはずだったが、母親が再婚し新婚旅行に行くため帰れなくなり、突然寄宿学校に残ることになった生徒のアンガス。
ベトナム戦争で、まだ10代の息子を亡くした寄宿舎の料理長のメアリーもまた残って一緒にクリスマスを過ごすことに。
それぞれに葛藤を抱えてて、それぞれが望まない2週間を過ごすこととなる。
だけれどもそうすることでだんだんとお互いの本質が見えてきて、家族のように思いやることができるようになる。
アンガスは思ったことがそのまま口に出て、人を傷つけることもしばしばで、生意気で憎たらしいが、見た目は大きくても子供なのだ。嬉しかった時の表情が何とも可愛らしい。
そのアンガスを見事にハナムが教育するように思ったが、2人の関係はそうではなくて、お互いを知り尊重し合う事でお互いを家族のように大切に思うというものだったのだと思う。
最後アンガスは退学せずに済んだが、ハナムはクビに。
アンガスの将来を思ってのハナムの選択だったのだと思う。きっと多分、アンガスはそれを忘れることなく、クリスマス休暇にハナムに教えられたことを糧に立派な大人になれるだろう。
最後の終わりもフランス映画っぼかった
劇中の音楽がとても良くて、たくさんのクリスマスソングが流れ、とても綺麗なコーラスが流れたり、ブルースっぽい曲も流れたり。クリスマスにもう一度観たくなるかもね。
タイトルなし(ネタバレ)
1970年、米国北東部の寄宿制の名門バートン高校。
クリスマス休暇でほとんどの生徒たちは親元へ帰るのだが、事情があって帰れない生徒たちが何人かいる。
今年も4人、寄宿舎に残ることになった。
監督役を命じられたのは古代史を教える非常勤教師ポール・ハナム(ポール・ジアマッティ)。
頑固で偏屈、その上、体臭がキツイと、生徒はもちろん教師仲間からも疎まれている。
4人の居残り生徒と思ったが、急遽ひとり追加。
問題行動で高校を転々としているアンガス(ドミニク・セッサ)だ。
それに、黒人女性料理長メアリー(ダヴァイン・ジョイ・ランドルフ)。
彼女は、去年同校を卒業した息子をベトナム戦争で息子を亡くしたばかりだった・・・
といったところからはじまる物語。
予告編などから、居残る生徒はひとりだと思っていたので、あれれと思ったけれど、他の4人は序盤でホリデイを迎えることができて、いなくなってしまう。
本題はどこからなのだけれど、この生徒5人のときの描写が丹念。
で、ここが意外といい。
急いては事を仕損じると言わんばかりの映画の語り口。
冒頭のユニバーサル映画マーク、鑑賞年齢の制限を示す「R」マーク、主要キャスト・スタッフのオープニングクレジットなど、画面のフィルム感も含めて、これぞ70年代の映画という雰囲気から続くのだから、急いではいけないわけである。
(なお、画質はデジタル撮影の上に効果処理を施したらしい)
で、ハナム、アンガス、メアリーの3人になってからの物語に通底するのは、嘘と後ろめたさ。
ベトナムで戦死したメアリーの息子は、白人の後ろめたさの象徴のようだ。
3人が徐々に心を通わせていく、というのはお馴染みの展開だが、アンガスがハナムの体臭に言及するあたりから、ふたりは似た者同士、同じ人物像の若きと老いとわかってくる。
このあたりから、じんわりと胸が熱くなってきます。
どうしてもボストンに行きたかったアンガスの理由、ハナムが母校で非常勤教師を務めている理由・・・
それらの真実には、幾分かの嘘が覆いかぶさっている。
物事を滞りなく進めるために。
けれど、嘘と真実のどちらを見ればいいのか。
嘘だけみていても世の中生きていけるじゃないか、とも思う。
それは、ハナムの斜視、左右で異なる方向をみているように見える目のようなものだろうか。
「どっちの眼をみて話をすればいいの」とアンガスがそれとなく言う。
最終盤、右の眼を指さしてハナムが言う。
「こちらの眼をみて、話せばいいんだよ」と。
観終わってすぐの感想は「久しぶりに、いい映画を観たなぁ」だった。
「いい」は「良い」「好い」とも書けるが、「善い」が適切でしょう。
3人の心が通い合う様は、とってもハートフル
問題児タリー君が、ひょんな事から、ハナム先生とラム(料理を作る人)と、3人で冬休みを過ごす事に。。。
タリー君は、言わゆるイタズラっ子、クソガキなんですが。。。3人で暮らして行く過程で、ハナム先生が、イタズラっ子なタリーを良く面倒を見ます。そのシーンが微笑ましいです。
タリー君は、終盤に生い立ちが解って行き、恵まれ無い、苦労せざる得ない子なんです。。。それでも、病気のお父さんの事を思いやる心優しい子なんです。ジーンとします🥹
ラムも、子供を戦争で亡くしており、ハナム先生も、大学を中退して、波乱万丈な人生!
その3者3様が、毎日一緒に暮らす中で、心が自然と通い合う姿に感動します🥹涙😭
ハートフルな映画🎞です。みなさんも、是非、観てみたらどうですか❓感動しますよ😃✨
何度でも観たい
爆笑コメディというよりは
ホロリ要素強め、時々クスっと笑えるビタースウィートヒューマンストーリー。
先生のポール、生徒のアンガス、共に嫌われ者らしいが
優しく常識的な一面を冒頭から醸し出しており、共感が沸いた。
生徒役のドミニク・セッサ、これが映画初出演だとは思えない程
屈折した部分と素直さを併せ持つ少年の演技が素晴らしかった。
ポール、アンガス、メアリー、3人とも深い悲しみを抱えており
それぞれの人生に身につまされるものがあった。
1970年から71年にかけての冬が舞台ということだが
その時代らしい演出が、音楽も含めてとてもはまっている。
斜視や臭いは今のご時世だともう話題にもできないかもしれないが
ポールが辿っていた人生を描く上で避けては通れず、
関連したセリフが何度も出る。そういう時代である。
印象的な場面の多い映画だが、
アンガスとポールの学校での追いかけっこ、
台所での爆竹、
アンガスとポールの最後の場面が特に心に残った。
何回も観たい映画であり出会えて良かった。
ジジイには懐かしいオープニング!
1970年代後半~80年代前半、親や親戚と一緒に「タワーリングインフェルノ」や「ミッドウェイ」などの洋画ロードショーを見た身にとって、冒頭の「ユニバーサル」「ミラマックス」のロゴや、鑑賞対象世代を表す画面や、光学式サウンドトラック特有のパチパチノイズ(わざと入れたんだろうな)は涙モノ。あそこまでやるんだったら、いっそのこと、映写機切替合図の黒丸(2回出てきましたね)と「ブチッ」という切替ノイズも欲しかったかも。
先生も生徒も給食のおばちゃんも、根は皆良い人で、ただ星のめぐりが悪くて貧乏くじを引いてしまっただけの人。ハーバード時代の旧友や校長(実は元教え子)は、要領よく(この場合は狡猾に)世間を渡り歩いて、お金持ちにはなったが心が貧しい。主人公たちのような不器用で純粋な人間は貧乏のままだが、こころは豊か。日本人的には後者が良いかなあ。ただ、四六時中空腹は辛いから、そこそこのお金は必要だけどね。
丁寧に作られた物語で、衝突が融和して変化していく過程が緻密に描かれていた
2024.7.2 字幕 イオンシネマ京都桂川
2023年のアメリカ映画(133分、PG12)
クリスマス休暇で帰れなくなった生徒を世話する偏屈な教師を描いたヒューマンドラマ
監督はアレクサンダー・ベイン
脚本はデビッド・ヘミングストン
原題の『Holdovers』は「残留者たち」「囚われている人たち」という意味
物語の舞台は、1970年の12月のアメリカ・ニューイングランドの寄宿学校
その高校の出身者である教師のポール・ハナム(ポール・ジアマティ)は、数十年を母校に捧げ、今では教え子ハーディ(アンドリュー・ガーマン)が校長を務めるほどになっていた
彼は生徒に厳しく、富裕層で寄付者の子どもだろうと容赦はしない
その対応は校長にしわ寄せが来ていて、教師間でも距離を置く人間が多くなっていた
そんな中でも、校長の助手ミス・クレイン(キャリー・プレストン)は分け隔てなく接し、彼は密かな思いを抱いていた
その年の冬、クリスマス休暇であるにも関わらず家に帰れない子どもたちがいて、その管理者を誰にするかを押し付け合うことになった
当初はエンディコット先生(ビル・モートス)が受け持つはずだったが、彼は母の病気を理由にして、最終的にはポールに押し付けることになってしまう
残ることになったのは、素行が悪いクンツ(ブレイディ・ヘプナー)、遠くて帰れない韓国人留学生のイェジュン(ジム・カプラン)、両親の宗教が原因のオラーマン(イアン・ドリー)で、両親が旅行中のジェイソン(マイケル・プロヴォスト)は都合がつき次第帰ることになっていた
そんな中に、生徒の中でも嫌われ者のアンガス・タリー(ドミニク・セッサ)が加わることになる
彼は父トーマス(ステファン・トーン)が精神病院に入院していて、母ジュディ(ジリアン・カプラン)は離婚し、スタンリー(テイト・ドノヴァン)と再婚していた
スタンリーが多忙のために新婚旅行に行けておらず、この機会を使おうと考えていたのである
映画は、ポールが5人の生徒と、寮のコック長メアリー(ダバイン・ジョン・ランドルフ)、用務員のダニー(ナヒム・ガルシア)たちとクリスマス休暇を過ごす様子が描かれる
その後、ジェイソンの父(グレッグ・チョーポリアン)が迎えに来たことで、タリー以外の生徒が一緒にスキーへといってしまう
タリーは両親と連絡が取れずに許可が取れず、彼一人が取り残されることになってしまうのである
映画は、偏屈なポールと頑固で制御不能なタリーの交流を描いていて、メアリーとダニーは場を和ませる役割を担っている
ポールは課外学習との名目でタリーが行きたがっているボストンへといくのだが、そこでタリーの父の精神病院へ行ったことがバレて、事態はややこしくなってしまう
さらにボストンでは、ハーバート大学時代の同級生ヒュー(ケリー・オコイン)とその妻カレン(コレーン・クリントン)と再会することになる
ヒューはハーバードを中退した元凶でポールは自身が成功していると嘯きその場を取り繕うのだが、タリーはそれに加担する格好になってしまう
ポールはタリーに自分の過去を語り、それがタリー考え方を変えていくことにも繋がっていくのである
映画は、少し長めの上映時間だが、そこまで長さを感じさせない印象
青春期の危うさが全開になっているが、騒動の顛末をポールの決断で締めるのは良かったと思う
精神的な父親代わりになりそうなポールは、彼をこの時点で転校させることは人生に悪影響だと考えていた
過去を清算する意味合いも含めて退職を決意したと思うのだが、縛りがなくなったとは言え高齢なので、これから彼がどのように生活をしていくのかは気になってしまう
メアリーからもらったノートに執筆を始めるかもしれないが、隠居するにはまだ早いので、どこかで教師を続けてほしいなあと思ってしまった
いずれにせよ、問題を抱えた教師と、大人の問題に晒されている生徒の交流を描いているのだが、この擬似的な関係がうまく融和していく過程は綿密だったと思う
この二人だけだと空気が最悪なまま進んでしまうのだが、メアリーとダニーがいることが緩衝材になっていた
二人は自分が抱える問題に内向していく中で、メアリーの問題が浮上して物語が転換するし、ミス・クレインのパーティでの顛末もなかなか見応えがあった
最終的に校長室での一件が物語を締めるのだが、四面楚歌の状況で男を貫いたのは良かったと思うし、それをタリーが知ることがないというのも良いと思う
卒業して再会するときには、タリーは彼自身が臨む大人になっていると思うので、生理的な父、環境的な父、そして精神的な父がいることは彼の人生にとって幸運なことだったのではないだろうか
たった2週間の出来事なのに。
孤独を抱えて生きてきた先生の、皮肉だけど的を得ている言葉が、キラキラ散りばめられてて、なんとも心地の良い時間でした。
バートンが、彼のすべてだったのに、それを犠牲にしてもタリーを守ったなんて。
バートンマンを貫いた先生が、ホントに素敵。
頑なだったタリーが、2週間で得た擬似家族体験は、それまでの彼の人生になかったものなんだろうな。
そのことを素直に言えるまでになったのも、身近な大人たちのお陰。
アメリカ東部のトラディショナルな雰囲気も素敵。
う〜ん、ジンビームが飲みたくなる!
貧しいものは浮かばれないアメリカの現実
教師・ハナムは有り体に言って嫌な奴。堅真面目はそうだが、正論にかこつけて生徒たちをいたぶってもいる。大体世の中をナナメに見ている。皮肉屋で、自分でも気づいていないかもだが裕福なお坊ちゃまな教え子全般に憎しみに近いものを抱いているよう。特殊な病気の影響で強い体臭があったり斜視だったり、オトコとして女性に好かれることを諦めている。それでも、教師としての責任感は持ち合わせているし、勤め先である学校を愛している、矛盾だらけのニンゲン。
クリスマス休暇にたったひとり寮に残される羽目になった悪童・アンガスは悪質さはまだマシなほうで、かわいそうが先に立つ。わがままだが寂しがりで健気なところがあり、年少の少年のおねしょを一緒に対処してあげる優しいところがあったりもする。学校の食堂の料理長メアリーは、使用人として蔑まれることに慣れているよう。無愛想だが温かみがあり、最愛の一人息子を失った悲しみ、喪失感でいっぱいいっぱい。ポーカーフェイスでいるが、なにかの拍子に大爆発したりする。
3人共良い面悪い面持ち合わせて、矛盾だらけだが、これが「普通の人間」だ。
雪で閉ざされがちな学校で3人で過ごすうちに、なんとなく心が通い合うようになる。
彼ら3人に共通して言えるのは、寂しさを抱えていることだ。
ハナムは嫌われ者であることを自覚しているものの、開き直りながらも誰かの愛を求めているよう。アンガスはストレートに母の愛に飢えている。メアリーはいわずもがな。
多分、「寂しさ」に共感したことが、3人の心の交流の取っ掛かりだったんだと思う。
ポールが嫌なやつになっていったそもそもの原因、メアリーの息子が亡くなった原因。
それは彼らが貧しかったから。
貧乏人が努力してなんとか学歴社会に食い込んでも、貧しいがゆえに内部で蹴落とされるのが現実。
この点は日本の社会のほうがまだマシな気がする。
ハナムはクソッタレのはずの教え子アンガスに肩入れして庇った結局、自身が職を追われることになった。
解雇が本人の本意か不本意かわからないが、ハナム先生にとっては遅まきながら「巣立ちの時」になった。それまでのしがらみと、自分自身を過去のものにして、新しい自分として生きていくことになったのだ。
すでに良いお年だし狭い世界しか知らず、しかも性格も歪んでいるし、病気のこともある。これからどうするんだろう。
本人にあまり悲壮感がない様に見えるのは、強がりなのか本当に気分がいいのかわからない。
独身だし滅多に外出もしない、自費出版で本を出した以外大した趣味もなさそうなので実はたんまり貯め込んでいて、当面生活に困らないんだといいなと思った。
または、上流階級の子弟のための名門校で、超がつくほど長く勤務した実績を引っ提げて求職したら引く手あまたで仕事の心配はないのかも。バートン校の校長だって、推薦状を書くくらいはしてくれるのではないか。それなら先が明るい、ハッピーな巣立ちになる。
ハナム先生が幸せになれると良いと思った。
良い話のようだが、良いことをした人が必ずしも報われるわけではない。
良いことをしたがゆえに、窮地に立たされる。
現実はそんなもので。
ハナム先生の将来は誰にもわからない。
やりきれなさ苦さも妙な余韻として残る、アメリカン・ニューシネマみたいなテイストの映画と思いました。
鑑賞動機:予告:4割、あらすじ3割、アカデミー賞3割
アプリで鑑賞劇場が最近選択したとこしか指定できなくなったのはバグかな。
舞台が70年代だからというだけでなく、映像自体がむかしの映像のような質感がするの気のせいだろうか。エンドクレジットの出し方とかも意図的にちょっと古い感じにしているでしょ。
マリアはともかく二人の拗らせ具合にウンザリする序盤。
片や未熟さゆえの浅慮と、その裏返しで背伸びして虚勢を張りたがる若者というかガキ(いやわかるけどそれ絶対10年後黒歴史よ)。片や研究への情熱の残滓は持ちながらも諦念と開き直りが悪い方に出てるオッサン。
クリスマスの奇跡…ではないのだけれど、そんな彼らが数日間でどう変わっていくか。
時に下品なユーモアが辛い人生にささやかな暖かみを与えてるのが不思議。
アレクサンダー•ペインはやっぱりいい!
ネブラスカ好きの私からすると、相変わらず地味で家で見たら寝そうな作品ですが、最高の作品でした。
相手に対して映画演出的にはちょっと物足りないくらいのリアクションが、また心に残る見事な演出でした。もちろん脚本も見事で、丁寧な作りの作品でした。ラストはいくらなんでも、そこまでやるか?と思いましたが、脚本が巧みで、時代背景も上手く生かされており、ハナムの決断も納得できました。アンガスの母の考え方も理解できました。
ただハナムが新しい生き方をするにはちょっと歳をとり過ぎてるとは思いました。しかし、彼も一皮向け逞しくなったと思うので、楽しく余生を送ってほしいと思いました。
ラストに至るまで色々感じるところがあり、ちょっと書ききれないのですが、本当に珠玉の作品だと思いました。
名作という程でもないが・・・
ライムスター宇多丸さんがラジオで話してるのを聞いて興味を持ったので鑑賞。心に穴を持った三人の最初はぎこちなく反発しても徐々に打ち解け分かりあっていく。最後に二人が話すシーン、「頑張るんだぞ、君なら大丈夫」という台詞でこれまでの全てが報われた気持ちになってとても清々しかった!名作という程でもないけど凄くイイ映画でした!
Bon voyage
ダヴァイン・ジョイ・ランドルフさんがアカデミー賞で最優秀助演女優賞を受賞した事だけを頭に入れての鑑賞。
どんな作品かはあらすじでフワッと触れたレベルで、そういえば予告とか全く観なかったなーと思っていたり。
これはダークホースだ…!想像以上に面白く、自然に感動できる作品になっており、観終わったあとにとってもほっこりできる理想的なクリスマス&年末映画でした。
斜視の症状を持つ教師のハナム先生と、ママが新しい夫とバカンスに行くがために学校に残れと言われたアンガスと、息子を亡くしている学校の料理担当のメアリーの3人で繰り広げられるなんて事ない休暇に色を付けていく物語で、最初はソリの合わない感じだったのに、互いの心情や行動について理解を含めていくと、どんどん相手を大切に思うようになっていく構成が本当素晴らしくずーっとトキメキながら観ていました。
最初こそ5人の居残り生徒がいたものの、途中でヘリで迎えにきてくれて4人は戻れるのに、アンガスのママは連絡がつかないというなんたる奔放っぷりに憤りを感じましたが、結果的に3人の距離を近づけるきっかけになっていく展開はエモかったです。
アンガスが年相応にハナムを振り回す中で、体育館のジャンプ台から思いっきり飛んでからの脱臼で大慌てのハナムが病院へと連れていく過程でグッと関係性が近くなって、痛々しいところですがフフッと笑える構図になっていたのも良かったです。
メアリーとお酒を飲んだり、恋愛ショーを見てキャッキャッウフフしていたのも微笑ましく、その中で体臭について指摘されて、ウッとなっていたのも良かったです。
ボストンに行ってからはガラッと流れが動き出して、親子のようにキャッキャッするハナムとアンガスがとても良いですし、メアリーが妹宅でまったりしてるのも良いですし、旧友と出会った時に嘘をついたハナムをアンガスがフォローしてくれたり、ジムビームを買う時に武勇伝をワッハッハと語っていたら店主に殺人犯と蔑まれたりと、笑いどころも多く含まれていて最高でした。
アンガスの真の目的は父親に会いにいく事で、最初こそ事情を説明しないアンガスを引き留めたハナムだったけれど、事情が分かってからは二つ返事で介護施設にいる父親への元へ向かい、再会を見届けるというのもわだかまりの解消ができていてとても沁みました。
この災害により、父親が元の家へと戻れる希望を持ってしまったがために不安定になってしまい、元嫁に違う施設に送られるという事情は分からんでもないけれど…もう少し責任持とうぜ…と元嫁に憤りを感じるくらいには感情移入していました。
クリスマスのレストランでは、お酒の入ってるスイーツは提供できない、いやしてくれの押し問答が面白く、ならばアイスとチェリーを持ち帰って、ジムビールをかけてなんちゃってスイーツに火をつけて燃えまくって友達のように笑い合っていて微笑ましかったです(はよ消化しないとヤバいことにはなりますが笑)。
ラストシーンもこれまた良くて、結果的には学校を追い出されてしまうハナム先生の元に全力疾走でやってくるアンガスが軽口を叩いて、熱い握手をしての別れが物悲しいはずなのに、どこか前向きになれる感じで良く、THE・恩人なハナム先生と自分も握手したくなりました。
空気を重くしないためにこっちの目を見て話してくれよと呟いたりしてほぐしてくれるのも良かったです。
役者陣もこれまた素晴らしく、特にアンガス役のドミニク・サッセ君は学校で行われたオーディションで選ばれたとのことなので、ほんまに良い子連れてきたわ〜と拍手したくなりました。
音楽も70年代の緩やかな感じが素敵で、背景のインテリアも部屋に飾りたくなるくらいオシャレでとても好みでしたし、街並みもこれまた美しいもんですから、どのシーンを切り取っても良いな〜という感動がありました。
夏場だけどクリスマス映画ってのも良いな〜となりました。
きっと今年のクリスマスのお供になる作品だと思います。上半期滑り込みで傑作キター!
鑑賞日 6/26
鑑賞時間 16:05〜18:25
座席 E-10
結局
最初は全然タイプの違う2人な感じですが、結局、よく似てるのかあ?って言う感じでしたね。気持ち的に互いをかばいあう関係にまでなったのは、やはり置いてけぼりになった短くも濃厚な期間があり、互いを理解できたからですね。
アントルヌー《我々だけの話》
楽しみにしていた作品だったのですが、そのぶん拍子抜けしてしまったかも。
まず、居残り組を二段階に分けた意味が分からない。
もちろん、それによりアンガスの孤独感がより強まる側面はある。
でも、300人が一気にいなくなる方が画面的な印象は強いし、テンポもよかったと思う。
残りの4人が後半に効いてるとも思えないし。
また、派手なイベントが必要とも思わないが、地味すぎる上に繋がりを感じなかった。
リディアの姪とのキスとか、一体なんだったのか。
ってか、ボーリング場とかでもアンガス、やたらとモテてないですか?(クソゥ
それより何より、アンガスが父に会いに行く場面ではちゃんとポールに相談してほしかった。
あの段階に到ってもまだ信頼築けてないのか、と。
事前情報では3人の話っぽいが、メアリー成分は薄め。
言ってみればひたすらルート弾きしてるベースのような立ち位置で、それはそれでいいのだけど…
パーティでやさぐれたり、妹の家に行ったり、変なとこで強めに主張してくるのでバランスが悪い。
最初からポールとアンガスに絞った方がよかった。
最後にアンガスを庇ってクビになるのは定番だが、イマイチ響かなかった。
途中で無駄打ちせずに、ここで初めてポールがウソを吐く流れにするべきだったのでは。
クソ親は何も変わらないし、なんだかスッキリせず。
アンガスが脱臼するシーンなんかは面白かったし、チェリージュビリーの一連の流れは好き。
熱中症になりそうな夜に観たけど
自分を除き、この映画を観る人は本物の映画通だと、数々のレビューを読んで思う。重なってしまうが、私が好きなのはアルコールの入ったデザートを出さない融通の利かない店員に悪態をつくポールの姿。自分も生徒たちにそうだったくせに。嘘をつかないはずなのに嘘をついたり、数々の悪態にクスクス笑えるシーンがたくさん。それでいて、少ししんみりさせる場面もある。父親のようになってしまうのではないかと不安を抱えるアンガスに、君は大丈夫と励ますところが、ベタではあるが名優の演技で、すんなりと心に沁みる。笑わせたい、泣かせたいが強過ぎなくて脚本が絶妙。熱中症になりそうな夜ではなく、一人寂しいクリスマスにもう一度観たい映画。
素晴らしかった
映像の質感が、アメリカンニューシネマの時代そのもので、当時作られた幻の名作が発掘されました、と言われたら信じてしまう。『スケアクロウ』と同時上映されていても違和感がない。
はぐれ者の教師と生徒と給食のおばちゃんの3人が寄り添って年末年始を学校で過ごす。お互い仲がいいわけではなく、生徒と先生は決定的に仲が悪い。特にクリスマスは日本とは意味が違って、何がなんでも家族と過ごす重要な日だ。僕が若いころは彼女と過ごすのが当たり前だとされていて、一人で過ごすことがとても惨めに感じたものだけど、その何倍も彼らは心を苛まれていることだろう。
生徒の男の子が本当に世間知らずの甘ったれで、イライラする。彼が同級生と言い合いになるのだけど罵倒がすごい。イギリス映画かと思うほど口が悪い。
そうして過ごすうちにトラブルがあったりしてお互いに気心が知れていく。それがとても丁寧に描かれている。気心が知れすぎて、さらなるトラブルに発展して最終的に先生は職を失う。そんなにクビになるほどの失点ではないと思うが元々校長先生に嫌われていたので、これ幸いとクビにする口実にされたのかもしれない。
その先生がスケートリンクで大学の同級生と会って、つい見栄を張ってしまう場面が見ていて本当に心が苦しくなる。極力等身大であろうと心がけているのだけど、自分ももしあんなふうについ背伸びをしてしまったら、その後何日もベッドで眠れずに叫ぶことになる。
古本市で話しかける売春婦が絶妙で、ぱっと見ないわ~と思うのだけど話しているうちにもしかしてありかな、あれれ?みたいな感じだ。
一体なぜこんな映画を今の時代に作ろうとしたのか意図が分からない。他にも全体像として把握しきれていない感じがする。ただ、誰とも友達になりたいと思えなかったので、また見たい気持ちは今はあまりない。
あったけぇよお。
近頃は切なかったり辛辣だったりする物語に入り浸っていたので、久かたぶりのハートウォーミングストーリー。
よかったよ~。
久しぶりに周りにお勧めできる作品だぁ~。
そうなんだあ〜こういう映画、好きなんだよなァ。
古いけど「アバウト・ア・ボーイ」を思い出しました。
短期間ながら、欧米ホリデーシーズンにまさかの学校居残りというシチュエーションはある種の密室劇のようであり、だからこそ所々の「外出」は観ているこちらもお出かけ気分というか主人公達と共にウキウキした気持ちになる。
そして当然のように起こる”何か”を経て、寮生活に戻るたび、何だかホッとしてしまう感覚は正に「我が家=ホーム」のそれ。起こるべく何かを恐れずに共有して、結果的な喜びも痛みも分かち合う。本作はそういった、まるで家族の正しい、あるべき姿をそれぞれの登場人物に分け与えていくのだ。聖なる季節であるからゆえの最高のプレゼント。
そりゃこの映画の観客だって嬉しくもなるさ。
家庭環境からヤサグレ盛りだったアンガスくん。序盤の校内追いかけっこは、?
はい…それ、私です…(^^;;
お恥ずかし過ぎて多くは語りませんが、個人的に物凄く彼の気持ちが理解できてしまって。年甲斐も無く追いかけてくるポール先生を見る彼の眼差しはすごく楽しそうでしたでしょう?本気で向き合ってくれる存在を渇望していたんだよね。そういう心の機微も上手に描いていたと思う。
劇場内では結構きちんと(?)笑い声が起きていたなあ。観客がこの物語にほぐされているようで嬉しかった。
「いやあ!映画って本当にいいもんですね」
って言いたいー!!(言ってるけど)
全50件中、21~40件目を表示