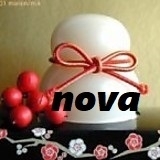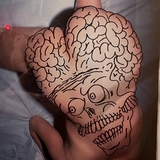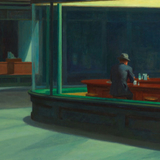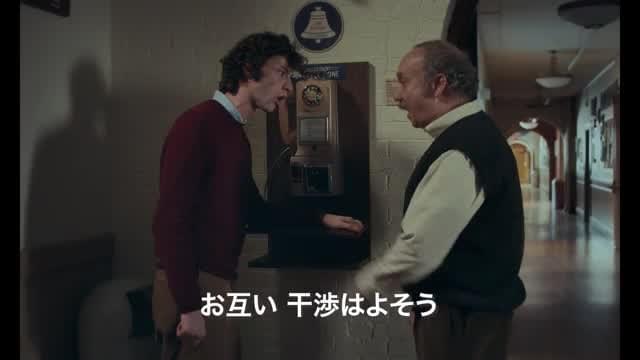ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディのレビュー・感想・評価
全253件中、101~120件目を表示
2024年一番の映画
手堅いストーリーだけどそれを退屈に感じさせないしっかりした脚本が見事だと思う。今年の新作映画で一番好きな作品。
妥協しないし皮肉屋で生徒に嫌われている教師ハナム。ボストン近郊の全寮制の名門寄宿学校でハナムはホリデイに家に帰れない生徒の面倒をみる仕事を押し付けられ…。
アンガス役のドミニク・セッサは進学校で声をかけられオーディション参加した新星ということだけど癖ツヨのアンガスはまってて良かった。アンガスとハナムと寮の料理長メアリーという居残り達が学校を飛び出す展開もロードムービー的で好きな展開。
前にSNSで見かけた、「冬の朝、祖母が靴を温めていてくれたって記憶。その記憶、あのときの愛でなんとか生きてる」っていう内容の投稿をなんだか思い出した。誰かが自分を守ろうとしてくれたって記憶は、人を守ってくれる力になると思う。英雄も偉業もでてこないけど、こういうささやかな人間ドラマに心揺り動かされることも、わたしの力になってくれてる気がする。
心温かく…なりそなところで突き放す
クリスマスシーズンの映画をこんな時期に出してくるのは、
クリスマスシーズンに配信するための箔付けなんでしょうかね。
でもその時期にコレ見たら凹みそうな気もする、そんな最後の突き放し方。
絶対ハッピーエンドに見えない、容赦のない感じ。
人に対してやってきたことは、ちゃんと全部、漏れなく自分に返ってくるという
因果応報を、ハートウォーミングな展開の末に見せつけられる絶望感。。。
大学辞めることになった理由も、本人から聞いただけで真偽のほどは定かではないし、
この年で庇ってくれる人もいない中で何の再出発が出来るのか。
誰も支えてくれない、終焉への道行にしか見えなかったのは、自分の問題でしょうか〜…。
宿舎だけで終わるのかと思ったらロードムービーになり、心が温かくなってきたところで、思いっきり突き落とされた気分で終わったので、年末年始には見たくないなと思いました。
アメリカンヒューマニズムの良作
1 年末休暇を寄宿学校で過ごす生徒と教師たちの人間関係の機微を描く。
2 1970年の年末。名門の私立高校が舞台。家庭の事情などで帰省せず学校にとどまる生徒たちがいた。そのお守りに一人の偏屈な教師ハナムと同校OBの息子がベトナムで戦死したばかりの調理場責任者メアリーが残った。面白みのない日々に嫌気がさしていた生徒たちはスキー旅行に出かけることになったが、一人の生徒アンガスは親と連絡が取れず残った。クリスマスを校内で過ごした三人は社会見学と称して、校外に出た。そこで、アンガスはある場所に行きたいとに伝えた、そして・・・。
3 本作では、個人的な悲しみや怒りを抱え、自分ファーストであったハナムとアンガスが、行動を共にするにつれて、心の内を吐露しあい、そしてハナムが自己を捨ててアンガスの才能を活かそうとした姿にアメリカ固有の隣人愛や家父長的な愛に基づくヒューマニズムを感じた。ハナムはさっぱりした顔つきで、校舎を後にし、アンガスは和らいだ表情で校舎に戻って行ったラストショットは印象的であった。
4 一方、メアリーには、心中の大きな悲しみと天使のような慈愛を感じた。息子が死んで独り身となった辛さだけではなく、除隊後の優遇措置を使って大学進学を目指すため入隊させてしまった親としての力のなさや後悔が滲んでいた。そして、恐らく孫用のベビー肌着や靴を生まれ来る甥か姪のために譲ることで思いを託そうとしていた。その中で校内に残ったメアリーは、ハナムに寄り添い、アンガスのために家庭的なクリスマスディナーを用意するとともに二人の仲介役となった。
5 本筋とは関係ないが、現場となった木造校舎の佇まいが荘厳かつ凛として素敵だった。また、当時の時代感を上手く再現していた。
アメリカ的
季節外れが
しみじみとくる良作
オープニングのクラシカルなユニバーサルのロゴに驚かされたが、物語の時代設定が1970年ということなので、敢えて狙ってやっているのだろう。映像の質感を含めたトータルデザインが70年代風な作りになっていて、どこか懐かしさを覚える作品だった。
劇中ではベトナム戦争の影もちらつき、メインキャラの一人、料理長メアリーは息子を戦争で亡くしている。ただ、映画を観る限り、これ以外に当時の時代背景を大きくクローズアップするような箇所はなく、基本的に登場人物は皆ノンポリで、どこか浮世離れしているような印象も持った。
監督はアレクサンダー・ペイン。少し癖を持った悲喜劇を撮らせると大変上手い監督で、心に染みるような良作をたくさん輩出している名匠である。今回は彼の自伝的な内容なのかと思いきや、年齢を考えると、どうもそういうわけではないらしい。
また、ペイン監督は基本的に自分で脚本を書くことが多いが、今回は別に脚本家がいる。彼も年齢から逆算すると、1970年に青春時代を送ったというわけはないようだ。
では、何故1970年なのか?これが自分には今一つピンとこなかった。劇中にアメリカン・ニューシネマの佳作「小さな巨人」が流れるので、もしかしたらアメリカン・ニューシネマのオマージュといった狙いがあったのかもしれない。尚、ここに「いちご白書」を持ってこなかったのも意図してのことだろう。政治色を払拭したかったのだと思う。
更に、物語は中盤からハナムとアンガスのロードムービーになっていくのだが、このあたりにはニューシネマの代表格「さらば冬のかもめ」や「スケアクロウ」も連想された。
そんなハナムとアンガスのやり取りは、時に微笑ましく、時にしみじみと観ることが出来た。二人とも人付き合いが下手で友達がいない孤独な者同士。教師と生徒という立場的な隔たりもあって、最初は全くそりが合わない。しかし、旅を通してお互いの過去や葛藤を知ることで徐々に絆が深まっていくようになる。
また、ここに孤独な黒人女性メアリーが関わることで、物語は単調にならずに済んでいると思った。
例えば、クリスマスイブのパーティーで酒に酔った彼女が取り乱すシーン、3人でチェリーケーキを燃やすシーンなどは抜群の存在感を見せている。彼女がいることでハナムとアンガスの友情がより一層深まった感じがした。
ちなみに、映画前半はアンガス以外に4人の学生が登場してくる。夫々に個性的で面白くなりそうだったのだが、早々に彼らを退場させ、以降はハナムとアンガス、メアリーという3人だけのドラマに転換していく。このあたりの大胆な切り替えにも良い意味で驚かされた。
クライマックスの展開は容易に先が読めてしまうのだが、こういう人情めいた話に自分は弱いということもあり自然と涙腺が緩んでしまった。
また、結末も良かったように思う。このくらいのビター&ウェット感が伴うと気持ちよく受け入れられる。
キャスト陣も夫々に魅力的な演技を披露している。
ハナムを演じたポール・ジアマッティの妙演は相変わらずの見事さである。同じペイン作品で言えば「アバウト・シュミット」のジャック・ニコルソン、「ネブラスカ ふたつの心をつなぐ旅」のブルース・ダーンに通じるような役所と言えるが、そこに少し毒気をまぶしたような造形に面白みを感じた。
アンガスを演じたドミニク・セッサの独特なビジュアルも印象に残った。本作が映画初出演ということで、今後の活躍が楽しみな新人である。
寄り添う人たち
確かに、いい映画だとは思うけど…。
とても良い映画だと思います。
観て損はありません。
けど、何かが足りないような気がした。
「ハロルド・フライのうまくいきそうもない巡礼の旅」の感動が
尾を引いているのは間違いないにしても、
今一つ映画に入って行けず、若干冷めている自分を感じながら観ていた。
言ってみれば「連れて行ってくれなかった」ということかな。
しかし、テンポの良い(良すぎる?)会話と、意味の分からない言い回しについて行けなかっただけかも知れない。いや、多分そうだ。
それが、映画に入って行けなかった理由、じゃないかな…。
ということで、きっと素晴らしい映画です。
若者に何が残せるかを考える。
月に8回ほど映画館で映画を観る中途半端な映画好き。
専門的過ぎないライトな紹介を心掛けています。
====================
若さ故、大人の苦労など何も見えない17歳の若者アンガスと
長年、金持ちのバカ息子ばかり相手にしているうちに
すっかり彼らを見下すクセが身に付いてしまった中年男性ハナム先生。
表面的にはどちらもちょっと問題ありの2人に
シングルマザーで、一人息子が戦死したばかりの黒人女性メアリーと言う
社会的にも境遇的にも彼ら2人とは違う第三者が加わって過ごすことで
少しづつわかり合い、ちょっと凝り固まっていた大人も
実は問題を抱えている若者も共に成長して行く。
派手な出来事が起こる訳ではないけれど
若者にも大人にもぜひ観て欲しい映画です。
ぜひ劇場で〜〜
教師と学生の成長の映画では
「グット・ウイル・ハンティング」
「今を生きる」とか
教師では無いけれど大人が学生に
影響を与える作品として
「センス・オブ・ウーマン」とか
その手の映画を思い出しました。
ただ、この映画は、それらの以前の名作と違って
明らかに効いているのは
見事に米アカデミー賞で助演女優賞を受賞した
ダバイン・ジョイ・ランドルフさんが演じる
メアリーの存在。
映画の時代の設定が1970年代。
裕福では無い階層の黒人女性のメアリーが1人で子供を育て、
その子は優秀だったのに、大学へ進学する資金が足りず、
徴兵に応じれば帰還兵には奨学金が与えられる制度を
利用するために戦争に行き、呆気なく戦死。
名門私学の学生寮で働くメアリーの目の前で、
ロクデモ無い金持ちのバカ息子たちが
親の金やコネでホイホイ進学してゆく。
友人のホームパーティーに招かれた夜、
息子を思い号泣するメアリー。
流石にその姿は反抗的な若者のアンガスにも
学生達を斜めにしてきたハナム先生にも
世の中の理不尽さや人それぞれの苦しみ悲しみを
思いやる心が生まれてくる姿を大袈裟でなく、伝えてくる。
一見、変わり者だったり、堅物だったりしても
人は何かしらの事情を抱えており、
それ故に、そんな言動になっていることを
思いやる心の余裕がいかに大事な事か〜〜
映画の後半、ボストンの博物館で、ある展示物を前に
盛り上がるアンガスとハナム先生。
アンガスは事情があって今は会えない父親との良い思い出に
ハナム先生との楽しい会話が重なって多幸感あふれるシーン。
後の展開を思うと、このシーンの欠け替えの無さに
改めて泣けて来てしまいます。
人生の後半、私も若者に何が残せるのか、
少しづつでも考えて行きたいと思った一作でした。
ジアマッティの斜視って演技?
「多くの人にとって人生は鶏小屋のはしごだ、クソまみれで短い」とか、「セックスは99%の摩擦と1%の好意だ」とか、「人間の形をした陰茎癌」とか、名言(笑)の詰まった作品。それぞれに孤独を抱えた嫌われ者、厄介者、社会の低位にある者。人には触れられたくない秘密や言いたくない過去が明かされる展開を通じて、世間から取り残された空間で反発と融和を重ねながら、信頼に足る関係性を築いていくさまがじんわり沁みる。
1970年目前のクリスマス期間の物語を70年代テイストで描いていて、ベトナム戦争や当時の人種差別を背景とした時代の空気感はある程度の知識を前提に想像できるけれど、アレクサンダー・ペイン監督の作品は米国の土地勘もけっこう必要とされる。ニューイングランドとかボストンとかの位置もちゃんとわかってない自分自身がやや残念…。
弱者たちの連帯
2023年。アレクサンダー・ペイン監督。1970年冬。アメリカの有名私立校のクリスマス休みに実家に帰らないことになった生徒と、その監督教師との数日間。決して分かり合えないお互いの事情や過去を少しずつ知り、自分の考え方を相対化し、大切なことに気づく奇跡のような時間。
内容的には、時代設定からしてノスタルジー満載。世界に希望を持たなくなった教師が、職をなげうってまでも生徒を助けるラストシーンに、人生を賭けられるものを見失っている大多数の大人たちは感動するだろう。「私に人生を賭けられるものを教えてほしい」。まっとうなことを考える人ほどうまくいかない世界(教師も生徒も鬱の薬を飲んでいる)に対して、涙ぐましく抵抗するという側面もある。弱者たちの連帯。主要登場人物たちの会話の場面での嫌味や皮肉や嘘(特に教師)は、典型的な負け犬の遠吠えであり、それが知的な要素を含んでいるのが楽しい。知性とは弱者による抵抗の手段だったのだということを思い出す。
映像的には、70年代の街や建物や車や服装をなにげなく映像で表現しているが、実はこれは大変なのではないか。特にボストンの街の描写があるが、CGだとしたらすごい。
尊敬できる大人と出会うこと
上映時間2時間以上、たまらなく幸福でした。
映像、音楽、脚本、役者、全てが見事に重なってそこに生きる人々の悲哀、喜びを丁寧に紡いでいた。スクリーンから慈しみの粒子が溢れ出ていた。優しさ、浴びまくりました。
子供のうちに、自分を叱り、認め、守り、時に共にふざけてくれる、そんな大人と出会い心通わせることの尊さ。
師を見つけることが、そして誰かの師になれることが、どれほど人生を豊かにするか。人生における喪失や孤独とその救済を、奇をてらうことなく、静かに、優しく、真摯に描き出した良作でした。きっとまた観たくなる。
あと、蒸し暑い夏にクリスマス映画をスクリーンで観れるという喜びもありました。上映館減ってますが、ぜひ映画館で観てください!
全253件中、101~120件目を表示