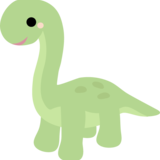型破りな教室のレビュー・感想・評価
全160件中、121~140件目を表示
好奇心は誰にでも
フアレス先生の授業を受けた生徒たちは、どんどん目がキラキラしてきて好奇心に溢れてきましたよね。そしてフアレス先生も彼らの未知なる才能を発見しやる気がみなぎってきます。数学の天才パロマ、ものづくりが得意なニコ、哲学者になりたい女子などなど。
本来教育者とはフアレス先生みたいに生徒の好奇心を引き出しアシストする人だと思います。でも昨今では、先生は生徒のテストの点数などで数字管理されているから、テストで良い点数を取らすことを優先する刹那的な教育になってしまうんでしょうね。学校の現場を知らない教育委員会が教育要項を勝手に決めてしまうのだろうし、日本では受験勉強に勝ち抜いた文科省の役人が決めてますもんね。そりゃあ不登校にもなるわけだ。だってつまらないから!
あと、パロマの父親も子供の時は好奇心に溢れていたと思います。だから、ラストでパロマの気持ちに気がついたんです。そう、本来好奇心は誰にでもあるのです。そして人だけではなく、映画や本からも自然からも学ぶことができるのです。そんな老若男女の好奇心を社会がアシストすることで人類は幸せになれると思いました。
可能性は無限
型破りな先生
自分の頭で考えてる?
ベタな教師モノと思っていたら、やはりベタなんだけど、国家が行う教育とは何かと改めて考えさせてくれる作品でした。メキシコでも治安が悪い地区にあり全国統一テストでは最下位の小学校にやって来た教師が、文字通り型破りな授業で生徒達を惹きつけるお話しです。わかってはいても、教師の一言で今まで考えもしなかった未来に子供達が眼を輝かせるのは、ジーンときます。この一言や教室で出される問題が頭にインプットされた子供達が、自主的にその事を考え続け結論を見出す過程が、微笑ましくも楽しいです。子供の個性を大事にと言う甘い教育論でなく、ネットに頼らず自分の頭で何が正しいのかを考え続け発見し答えを出すことの楽しさと大切さを強調しているのに好感が持てます。もちろん、子供達が全員ハッピーになれるわけでなく、厳しい現実もしっかり描いているのもいい所ですね。一方で、教育委員会のお偉方の目指す教育や試験は、国や社会の一員としてコントロールしやすい国民を育てることであり、映画のジャンルは違うけどキューブリックの『フルメタルジャケット』で新兵を同じ基準の兵器に訓練していたのを思い出しました。役者では、まさにエウヘニオ・デルベスの独壇場で、この人『コーダ』でも音楽教師役がハマってました。校長役のダニエル・ハダットもいい味でした。
自分と同じ絶望を子供に押し付ける親たち。メキシコにも真面目に前向きに考える人がいるんだと初めて知る。
子供の未来を信じることができない大人たちが腹立たしい。
少しの可能性も、寄ってたかって台無しにする。
どうせこの現実から逃れられないのだから、少しでも傷つけないようにと教え込む大人たち。
親から子に引き継がれるあきらめの気持ちが、その状況から抜け出せない連鎖を作る。
いかにも容姿端麗なパロマとニコのカップルより、弟たちを風呂に入れながら、疑問の答えを見つけたときの喜びを知ったルペの表情が素晴らしい。
貧しい家庭で、子供が子供の面倒を見るために学校にいけなくなるのに、なぜ子供を作るのか。
本当に疑問。
教育が無くて大人になると、そんなことも考えられないのか。
アメリカのアクション映画やドラマのせいで、メキシコは単なる犯罪国家で無法地帯としか思ってなかった。
(あと、コロンビアは麻薬犯罪密輸出国、のイメージしかない。)
真面目に前向きに考える人なんていないと思っていたので、こういう真面目な映画をどんどん作ってほしい。
教育に携わる人間として、実話ベースであることも含めて希望になるよう...
教育を根本から考え直す
【可能性を信じれば、希望を持って生きていける】
教師と生徒の関係を描いた映画は数多くある。それでもこの映画は異彩を放つ。舞台となるのは、教育環境が厳しい地域にある国内最低レベルの小学校。ここで型破りな教師が子どもたちと出会い、彼らの人生に小さな光を灯す物語だ。教育を取り巻く困難や現実に直面しながらも、子どもたちが未来へ向かう姿を描いている。
【邦題からは伝わりにくい映画のテーマ】
「型破りな教室」という邦題は興味を引きやすい。しかし、原題の”radical”には「根本から覆す、根源に立ち返る」というニュアンスが込められている。主人公である教師の視点は、教育の根本的な問い——「どうすれば子どもたちは学びたくなるのか?」——に立ち返り、その答えを模索する挑戦そのものだ。この映画は、そうした問いに対するアプローチを観客に問いかけている。
【学習の根源は「人間の好奇心」】
どんな人間も本来好奇心を持っているが、子どもたちがそれを失う原因はしばしば大人にある。この物語では、意外性のある方法で生徒たちの好奇心を呼び起こし、学ぶ喜びを再発見させる教師の姿が印象的だ。
【教育者の役割を問い直す】
限られた資源や困難な環境の中でも、教師は子どもたちの可能性を信じ、その力を引き出そうとする。学びの場において、教育者は知識を与えるだけではなく、子どもたちの中に眠る好奇心という灯火を守り、燃料となる題材を提供し続ける存在であるべきだと、この映画は教えてくれる。
【境界を超えて学ぶ】
この映画は、知識に境界線を引くのは誰なのかという根本的な問いを投げかける。学ぶ意欲に年齢や環境の制限は必要ない。子どもたちの中に火がついた好奇心は、どこまでも進んでいく力となる。
【深く考えさせられるもう一つのメッセージ】
映画は、教育をめぐる現実の問題にも目を向ける。教育の機会が与えられない子どもたちがどれほど多く存在するのか。学校や教師だけでは解決できない社会全体の課題であることを、この映画は静かに訴えている。未来を担う子どもたちのために、大人として私たちは何ができるのか。この映画は、教育を社会全体で考える必要性を改めて問いかけてくれる。
Radical
革命的な授業、こういう授業を小学生の時に受けてたらどうなってたんだろうなーって観ながら思いました。
序盤からメキシコの現在の状況を少ないセリフとシーンで見せるのがお見事でした。
車椅子を押す少年はヤングケアラーだと思いますし、麻薬組織が蔓延っていたり、奴隷のように扱われてる人たちと一気に不穏な状況が映され、これがリアルなんだとも突きつけられるのも強烈でした。
ダメダメな教え子たちをエリート教師が立ち直らせていくという感じの構図だと思っていたのですが、子供たちの知識を伸ばす方向にシフトしていくというのが珍しく面白かったです。
学校のお堅い考えを全て変えていくとかではなく、ちょっとおかしいんじゃない?というところを楽しく開拓していくスタイルがとても好みでした。
ボートの推進力や密度などを小難しく説明するのではなく、生徒同士で考えて、人でも実践してみようというフアレス先生の考えが展開されるんですが嫌味なくストレートにこちらにも伝わってくるもんですから小学生の頃を思い出すようなワクワクした授業風景が繰り広げられて楽しかったです。
最初は嫌がっていた校長先生がめっちゃ協力してくれるのもとても良かったです。
パソコンがあったら子供たちは自分たちで学んでいくから導入してほしいという切り口はとても新鮮でした。
現代的に捉えればパソコンやスマホは中毒性のあるものだからむしろ離すべきという考えになってしまうんですが、そういう文化が根付いていない国や国民にとっては便利なもの一つがあれば価値観も変わるんだなとなって感心しっぱなしでした。
子供たちの状況も中々にヘビーなものが多く、貧困もあってゴミ捨て場に住む子もいれば、麻薬組織に勧誘されている子、母親が妊娠しており母親代わりに弟妹たちを育てるといった過酷な状況が提示されるのでグッときましたし、しっかりと育ててもらったんだなと改めて両親に感謝しなきゃだなと思いました。
麻薬組織がいるからこそ日常の身近に潜む"死"がショックを引き起こすというのも中々に辛く、フアレス先生が塞ぎ込んでしまうのも仕方ないと思うのですが、最初にこの学校に来た時の最初の信念を思い出して一念発起する流れ、テストをカンニングに頼らず真っ向勝負で挑む姿勢がもう素晴らしすぎて拍手喝采でした。
希望が微かに見えたラスト、それでも変わらない状況がいる子供たちがい続けているリアルもあるという考えさせられる作品にもなっていたので本当に凄かったです。
その後のキャリアで大成する子もいたりと、フアレス先生の努力と子供たちの努力が実っていったんだなと観ているこちらも嬉しくなりました。
鑑賞日 12/26
鑑賞時間 13:50〜16:00
座席 G-1
人生の舵は自分で取れ
スラムの広がるメキシコ北東部の街マタモロスに在る小学校に、セルヒオ・フアレス・コレア( エウヘニオ・デルベス )が後任教師として着任し、貧困等様々な家庭の事情を抱えた生徒達に学ぶ喜びを伝えるべく尽力する。
厳しい環境下で生きる彼らが、学びに目覚め瞳をキラキラと輝かせる姿が眩しい。
貧しい家庭で育ちながらも、数学が得意で宇宙に興味を持つパロマ( ジェニファー・トレホ )が実在の女性だとエンドロールで紹介され、驚きました。
『 学ぶ喜び 』の大切さを、改めて考えさせれられる作品。
映画館での鑑賞
本作が実話からどれだけ脚色されているかは不明だが…
【”生徒自身に自らの可能性を想像させる授業。”今作は、既成のカリキュラムに捉われず、子供の好奇心を刺激する授業により飛躍的に学力向上を実現させたメキシコ人教師の実話の実写化作品である。】
■2011年。米国国境に近いメキシコのマタモロスにあるホセ・ウルビナ・ロペス小学校が舞台。麻薬と暴力が蔓延る中、小学生たちは家の手伝いなどで、勉強に身が入らずに6年生の半数は卒業が難しい状態。
そこに、地元出身の元中学教師フアレス先生(ヘウエニオ・デルベス)が赴任して来る。
◆感想<Caution!内容に触れています。>
・フアレス先生は、赴任初日からラディカルな授業を繰り広げる。部屋の生徒の机は逆さまにおいてあり、自分の机は廊下に押し出す。
生徒は自由な場所に腰掛けて、この不思議な先生が何を言うのか興味深げに見ている。
ー 所謂、掴みはOKと言う奴である。
先生は”井戸に落ちたロバの話”をして、ロバのように土に埋もれずに這い上がれ!”とはっぱをかけ、更に生徒達に質問するのである。”君たち、23人が6つの救命ボートに同人数乗るには、どうしたら良い?”
生徒達は皆で話し合いながら、その問いを考えるうちに、物理や哲学などにまで思考を広げて行くのである。ー
■この映画では、当時のメキシコの教育を阻む社会問題が描かれている。
1.数学に秀でながら、父の廃品回収の手伝いをしなければいけないパロマ。それにしても彼女が、フアレス先生の”1から100まで足すと幾つになる?”という問いに、”5050”と答えるシーンは彼女の数学の強さを一発で示すシーンであり、フアレス先生が彼女の数学に秀でたる生徒である事を知ったシーンでもある。
2.兄と同じ犯罪組織に入るようにプレッシャーを掛けられ、ナップザックに勝手に銃を入れられ戸惑うニコ。だが、彼は密かにパロマが好きなんだよね。
それを、あと押しするフアレス先生も素敵である。
3.幼い姉弟の面倒を見ながら学校に通う、哲学に興味を持ったルペ。彼女は哲学書を読むために大学の図書館から本を沢山借りて来るのである。だが、子が生まれる母から学校を休学するように言われてしまう。
・フアレス先生は、生徒達に対し上から目線では接しない。故に生徒達は、フアレス先生の問いを自分達でドンドン”思考”して行き、比重に気付いて行くのである。
フアレス先生をサポートする太っちょ校長と、フアレス先生を水槽に沈め、生徒達が大喜びするシーンは、良かったなあ。
■要領の良いズルイ先生は、メキシコの全国共通テスト”ENLACE"の答案を何故か持っていて、生徒に事前に教えたり、教育委員会のお偉いさんは”パソコンを配布する・”と新聞記事にさせておいて、実際は配布しないというメキシコ教育界の不正も今作では描いているのである。
それに対し、敢然と抗議するフアレス先生。彼はズルイ先生から”ENLACE"の答案を渡されても、ごみ箱に捨ててしまう。
・だが、ある日パロマと下校途中だったニコの所にギャング達がやって来て、悲劇は起きてしまう。それ以来フアレス先生もカリキュラム通りに授業をしなかった事を咎められ、2週間の停職。それを知った生徒達も学校に来なくなる。
・校長が、フアレス先生を説得し何とか外に連れ出すシーン。彼らは浜辺に有った”パロマと書かれた小舟”を浜辺を引きずって、海に浮かべるのである。
ー 今作の中身を暗喩した象徴シーンだと思う。ー
<今作は、メキシコの貧困、犯罪、家族環境など学びには障害が山積みの中、生徒達に”自らの可能性を想像させる授業”を行う気概ある先生と、先生により学びの楽しさ、素晴らしさに目覚めていく生徒の姿を描いた作品なのである。>
知的好奇心こそが、私たちの最も偉大な業績を推進する燃料である。
ニコ!君の選択を私は否定できないよ。
そして君はもう、自由だ!
ほのかな初恋の情を小舟「パロマ号」に乗せて旅立つニコ君。
ああ、いま思い出しても泣けてくる・・・(T_T)
なんだよ~もう~。
いい映画じゃんかよー(ToT)グスッ
オッサンが明るいうちから目を充血させちゃったよ。
個人的に引っかかる上映作がここ1~2ヶ月ほど無く、そして仕事の合間も無く「あぁこのまま今年の映画鑑賞は終わりかな」なんて考えていたところの、本作の鑑賞だった。
ええ、締った締った!これは良作でした。映画COMの評点、RTの評点いずれも高く、事前に抱いた期待感は裏切られなかった!
*****
掲題にリチャード・ブランソンの名言を戴いてみた。
『型破りな教室』は邦題だが、フアレス先生の考える理念や教育の本質からすれば、現代的な教育流れの方が目的ズレの、それこそ型破りだということになるだろう。
その点、原題の"Radical"は、うまい。
気になったので僕の優秀な相方・チャットGPTさんに聞いてみた。
----------------------------
「radical」には、さまざまな意味がありますが、文脈によって異なります。主な意味は以下の通りです:
1. 基本的な・根本的な
物事の根本や基本に関わるものを指します。
例: "a radical change"(根本的な変化)
2. 急進的な・過激な
社会や政治的な考え方、行動が従来の枠を超えるほど革新的・急進的なことを意味します。
例: "radical politics"(急進的な政治)
3. 素晴らしい・かっこいい(俗語的な意味)
主に英語圏(特にアメリカ)で使われるスラングとして、「とても良い」「すごい」という意味があります。
例: "That skateboarding trick was radical!"(そのスケボーの技、すごい!)
4. (数学・科学)根号・基底
数学では「√」(ルート、根号)や、化学では分子のラジカル(基)を指します。
例: "radical expression"(根号を含む式)
5. 漢字の部首(英語学習時の意味)
日本語の漢字学習では、「部首」を英語で「radical」と表現します。
例: "The radical of this kanji is '木'."(この漢字の部首は「木」です。)
----------------------------
おお~。まるでこの映画の内容そのもの。
⑤なんてとてもイイ感じではないか。
ジャパニーズ解釈でこじつければ、本作内容を現す部首はニンベンに違いない。
ニッポンの現代教育にもグサグサ刺さるであろう今作。そのメッセージ、その心の一文字はきっと「仁」ではなかろうか。
人口減少に向かい、更に複雑化するイデオロギー社会のなかでの教育。
常日頃より私は「仁力」が鍵になると信じている。
2024みんなに見てもらいたい映画で賞・ベスト1をあげたいのだ。
導くことの素晴らしさ
子供が家で勉強していると親が止めさせようとする世界の話
2011年、当時のメキシコにおける治安の悪さを象徴するかのように、本編のドラマとは関係なくずっと銃声や悲鳴が聞こえている作りで、今年公開の『関心領域』みたいと思ったが、『関心領域』と違うのは、この構造が物語後半の展開に直接関わってくるところ。
先生や生徒の台詞の中に、人生の教訓になりそうな哲学的な内容が多かった印象。
納得できることもあれば、それはどうかなと思うこともあった。
個人的に一番同意した部分は、学校の教師が「生徒に舐められたらダメ」というのに対し、主人公の教師・セルヒアが「僕とは正反対の意見ですね」みたいなことを言う場面。
昔あったCMの台詞で「教師は嫌われるのが仕事」というのがあったが、個人的にこの意見には反対で、まず教師は生徒から好かれて尊敬されることを目指すべきだと思う。
その方が教師の伝えたいメッセージが生徒に浸透しやすいと思うのだが。
やる気のない生徒が、セルヒア先生の型破りなやり方で授業に夢中になっていく場面は、2021年公開のデンマーク映画『アナザーラウンド』の授業シーンと比べると、説得力が弱かったように感じた。
というか、『アナザーラウンド』の授業シーンは、映画史に残る名授業だと個人的には思ってる。
両作共通のメッセージは「教師は生徒が興味を持つような授業をしろ」ということで、そこを否定する教師はいないと思うが、それって実はものすごく難しいことなのでは?
たぶん、そこそこ儲かっているお笑い芸人ぐらいの人を惹きつける能力が必要で、日本全国数万人の教師全員にそれを求めるのは厳しいものがあると思う。
努力すべきだとは思うけど。
本作のような映画でありがちなのは「通常の授業のやり方を全否定して、こっちのやり方が正しい」という見せ方。
子供は多様で、勉強のやり方の合う・合わないは人それぞれだ思う。
「セルヒア先生の型破りな授業」より「定番の授業」の方がやりやすい子供もいると思うので、今までのやり方を全否定するのではなく、こういうやり方もあるよ、ぐらいの描き方の方が良かったように思う。
この映画で不幸だと思ったのは、親が子供の勉強を否定してしまうこと。
子供が家で勉強していたら、日本だったら泣いて喜ぶ親ばかりだと思う。
親が子供を自分の所有物と思っているから、こういうことが起きるのかなと思った。
でも、自分の将来を楽にするために子供を作る親は、日本にも多い印象。
興味ある分野を伸ばすことと、基礎学習を均一化することの境界線はどこにある?
2024.12.24 字幕 アップリンク京都
2023年のメキシコ映画(125分、PG12)
原作はジョシュア・デイヴィスの記事『A Radical Way od Unleashing a Generation of Geniuses(2013年)』
2011年に実際に起こった小学校における革新的な授業を追った社会派ヒューマンドラマ
監督&脚本はクリストファー・ザラ
原題の『Radical』は、「革新的な」「基礎的な」という意味
物語の舞台は、2011年のスペイン北部の国境地帯にあるマタモロス
そこには「罰の学校」と呼ばれるホセ・ウルビナ・ロペス小学校があった
麻薬戦争の紛争地帯で治安は最悪な地域、そこに通う子どもたちは卒業できずに中途退学になるものが多かった
そんな小学校にセルヒオ・フアレス(エウヘニオ・デルベス)が赴任してきた
彼は職員会議をガン無視して授業の準備に取り掛かっていて、それは全ての机椅子を端に寄せて、大きめの机を救命ボートに見立てるというものだった
生徒たちは困惑するものの、セルヒオは構わずに「ボートは6台、君たちは23人だ。どうする?」と問いかけた
そこに校長のチュチョ(ダニエル・ハダット)がやってきて、セルヒオは「彼も助けなければ」という
すると、生徒の一人が「ボートが沈む」と言い出した
そこでセルヒオは、「なぜボートが沈むと思ったのか?」問いかけた
映画は、身近に接しているものや経験則からわかる感覚を学問に落とし込むという方法で、救命ボートの件は「物理学」の範疇になる
ボートがどうやって浮くのかとか、物質の質量や密度の求め方を学んでいく中で、考察から方式を紐解いていく流れになっていた
主要な生徒として、宇宙物理学を習いたいパロマ(ジェニファー・トレホ)、弟妹の世話に明け暮れる哲学好きのルペ(ミア・フェルナンダ・ソリス)、兄チェぺ(Victor Estrada)からアウトローの誘いを受けているニコ(ダニーロ・グアルディオラ)たちが描かれていく
パロマにはモデルの女性がいて、「次世代のスティーブ・ジョブス」と言われるほどの秀才で、そんな彼女も家庭環境から勉学の道を諦めざるを得なかった
映画では、子どもが持つ重要な武器は「可能性」と言い、それを阻むのは「自分自身」だとも言う
家庭に理解を得られない子どもがいて、パロマは父(Gilberto Barraza)が理解を示したが、ルペの方は退学を余儀なくされている
だが、末っ子を背負ってどこかに行こうとする彼女を見ると、そのまま図書館で独学で勉強を始めるのではないかと思わせる
環境が確かに阻害するとは思うものの、その気になればどこでも学べると言う意味を含んでいるのだろう
だが、本作はそれだけでは終わらず、冒頭から登場する「車椅子を押す少年(Kaarlo Isaac)」がクローズアップされている
彼は幾度となく小学校の金網のところで中の様子を伺っているのだが、セルヒオの力が学外には及ばないことを示唆していた
この街には「通いたくても通えない」と言う子どもたちが一定数いて、全ての子どもたちに「機会」を与えられてはいない
小学校が無償なのに通えないのはなぜか
これがマタモロスの隠れた問題になっていて、次の課題になっているのだろうと感じた
いずれにせよ、このような教育法はあることにはあるが実践できる場所は限られていると思う
教育委員長(Enoc Leañno)がいう「基礎的なものが欠けている」と言うことも一理あり、基礎学習の理解度を測る上でのテストには意味があると思う
だが、その教育方法をどの時点まで続けるべきかには諸説あり、大学入試まで行う必要があるのかはわからない
勉強に対して「課せられた労働」と思う子どももいれば、「探究心を満たす知的活動」と捉える子どももいるわけで、そのあたりの線引きは難しいのだと思う
セルヒオの学習方法は「勉強を好きになる」と言うファーストステップだと思うので、彼の言うとおり「パソコンがあれば子どもは勝手に学び出す」と思うので、きっかけを与える授業としては有効なのかな、と感じた
全160件中、121~140件目を表示