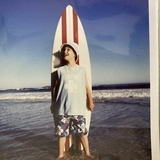ニューヨーク・オールド・アパートメントのレビュー・感想・評価
全37件中、1~20件目を表示
外国で生きる若者への理解と共感をはぐくむために
評者自身も仕事の都合で一定期間アメリカで過ごした体験があり、市民カレッジと言うのだろうか、わずかな授業料でESL(第二言語としての英語)を教わるクラスに通ったこともあるので、懐かしさを覚えるシーンが多々あった。もちろん似たような経験がなくても、進学や就職、転勤などを機に地元を離れて不慣れな場所で暮らし始める時の心細さは大勢が知っているだろう。またコンビニやファストフードの店員など、接客業に従事する外国人に接することも年々増えているし、職場や学校でも移民やその二世・三世、あるいは留学生や技能実習生と一緒になる機会も増えているのではないか。本作のような題材を扱う映画を鑑賞することで、外国で生きる若者、あるいは不慣れな環境で疎外感を味わっている人たちへの理解と共感がはぐくまれ広がるといいなと願う。
不法移民という境遇に関しては、技能実習生として来日するもブラックな職場から逃げ出したベトナム人女性たちを描く「海辺の彼女たち」を思い出したが、比較すると本作のほうが明るく希望もたくさん感じられる。"boys meet a girl"の要素がそうしたポジティブな印象に大きく貢献しているのだろう。大人への通過儀礼とでも言うべき“体験”が描かれているが、2人目の際に「おいおい、初めてでそれはチャレンジャーすぎる……」と余計な心配をしてしまった。
良かった
ニューヨークの片隅で
母は息子二人とニューヨークに暮らすペルーからの不法移民。
息子二人は英会話教室で謎めいた美女と知り合う。
母は小説家の男と愛し合うようになる。
強烈な人生が待ち受けているのだが、最後に出てくるペルーの風景に圧倒される。
月曜ドラマランド
タイトルからスパニッシュアパートメントを想起しておしゃれな映画なのかと思ってたけど真逆でした。反トランプなのかな?私もトランプが言ってることがすべて正しいとは思わないけど、不法滞在して(この人たちは越境も不法)強制送還されてまたもう戻ってこようとしてる、しかもそれが良いことのように描かれてる、単純にルールに照らし合わせると違和感なんだよなー。それ以前に映画としていろいろ稚拙で、兄弟はいかにも素人オーディションだろうなという感じでそれが全然いい方にいきてない。昭和の頃のジャニーズアイドルの演技見せられてるみたい。あとハイティーンの息子たちがお母さんが美人だの他人だったら結婚したいのって、ちょっと気持ち悪いんだよなー。兄弟で初体験を同じ部屋で同じ相手でってのもとっても違和感。この映画ちょっと日本には合わなかったんじゃないでしょうか?スイス人官能小説化の演技もとってもわざとらしくて、やっぱり昭和の月曜ドラマランドを見せられているようでした。そんなもの知ってる人も少なくなっているかしらね。
24-027
透明人間だけど…
NYに暮らす不法移民の家族のストーリー
時にある題材ではあるが何故かこの家族に悲壮感を感じられないのは肝っ玉かぁちゃんの明るさとクロアチア人の美女に恋をし
しっかり青春(性春…😁)を謳歌している兄弟の日常が自然に見えてしまっていたからかもしれない…
しかしその日常も徐々に崩れて行く…
透明人間でなくなる時が
彼らが恋するクリスティンも含め現実は底辺に位置する自分達であれど前を向き誇りを持って進んで行く姿とエンディング曲にかすかながら希望や微光が見えた気がしました
心留めしておきたい作品になりました
…クリスティンの受刑中の恋人や母親の恋人のポルノ作家…家族の親戚の親父などなど登場する男ども揃いも揃ってクズばかり!!
腹が立って仕方なかったよ!
そんな中でも母親の同僚
コインランドリーでの多人種達の協力に感動しました
帰りにタコスをテイクアウトしてしまいました😁
75点ぐらい。庶民の目線で描かれたニューヨーク。
多様性とは?人種差別が蔓延る現代における感じる矛盾
ペルーからアメリカの移民兄弟&母親を軸に
様々な出来事・事件を通して、社会問題を抉りだすように描いている作品だと思いました。
移民の生きにくさ、透明人間と自分で揶揄されるほどの無視っぷり、
冒頭のシーンなんて人間扱いすらされていない、
でも、それが当たり前の世界でも、
主人公兄弟ふたりが恋したクリスティンは、ふたりを差別なんてしていない。
まさにそういう世代なのかもしれないし、生きてきた境遇・教育にも影響があるのだろうと思います。
こういうテーマを扱った映画を観るたびに、世界で叫ばれている多様性という言葉が
実に陳腐に聞こえます。
本音で本当に多様な人種(LGBTQ含め)を受けとめることができる人が
一体どれほどいるのだろうと考えてしまいます。
またしてもそういう課題を突きつけられたと感じた作品でした。
この現実に唾を吐く
安定した暮らしを求めペルーから不法移民としてアメリカに来た家族だが、現実は厳しく…そんな中で母、息子がそれぞれ恋に落ちて巻き起こる物語。
アメリカにとって不法移民というのは勿論良くないことなんだろうけど、自らが透明人間に思える程、居場所の無い日々は辛いだろうなぁ…。
そんな燻った3人の生活がよく描かれており、双子のピュアさとたくましさが重々しいハズの雰囲気も和らげてくれ、とても見易い作品に仕上がっている印象。
一見ワルに見えるクリスティも(実際に悪い事してるんだけれど)、クロアチアからの移民。双子からは高貴に見えてたかもだけど、彼女は彼女で居場所探しに必死だったんでしょうね。
比較的、淡々とした展開ながらも終盤に向けて畳み掛けるような負の連鎖には焦燥感を覚えたし、そこからの一本の電話で胸にジ〜ンと熱が広がる。
その他にも、少なからず差別を受けているであろう人達のコインランドリーでの協力にはグッときた。
家族愛はまたきっと国境を超えてくれるでしょう。大きなインパクトは無くとも、リアリティがありつつ、わざとらしすぎない作風でとても良作だった。
【人種の坩堝、ニューヨークで暮らす不法移民のペルーやクロアチアの人々の自分達の居場所を必死に探しつつ生きる姿を描いた作品。】
■ペルーから不法に国境を越え、ニューヨークに辿り着いた双子のポールとティト。二人は語学学校で知り合ったクロアチアから来た超絶白人美女のクリスティンと出会い、恋をするが写真を貰っただけで、友達止まり。
二人を育てるシングルマザーのラファエルは愚かしき白人の恋人と、デリバリーの食品店を開く。
◆感想<Caution!内容に触れています。>
・クリスティンは実は恋人が、刑務所の中にいる。コールガールとして生計を立てているが、その恋人の出所日にこっそり見に行くと、恋人には妻子がいて・・。
ー 列車の中で彼女がネイルをこそげ落とすシーンの彼女の鬼気迫る表情と、ポールとティトを呼び出し”あたしのことを聞かれたら、良い人だったよと言ってね。”と言って場末のモーテルで二人を次々に優しく抱いてから、恋人を・・。
ウワワ。けれども、気持ちは分からないでもない。必死に支えて来たんだし、刑務所の中の、彼との電話が彼女の生き甲斐でもあったのだろう。彼女の人間としての矜持であろう。-
・自分達を”透明人間”と卑下しながらも、毎日を必死に送るポールとティトは、街中の人だかりの中で、クリスティンの写真を見て彼女に言われた通りの言葉を発するが、警官に事情聴取を受け、更に移民局の職員から国外追放を言い渡される。
ー 部屋の中に掲げてある、愚かしきトランプの写真が、絶妙に効いている。-
・シングルマザーのラファエルは、デリバリーの食品店が配達人のポールとティトが居ないせいもあり、あっと言う間に行き詰まる。
そして、息子達と交流があったクリスティンが起こした出来事を知り、友人から許可証を借り、彼女に会いに刑務所へ行く。
- そこで、やつれた彼女が言った言葉。”あの子たち、充分に愛されてるじゃない・・。”可なり沁みる。
<ラストシーンは、ペルーに強制送還されたポールとティトが立ちはだかる山に向かい、再びアメリカを目指す姿で終わる。
微かな希望と、勇気を感じさせる良いラストシーンだったなあ。>
<2024年1月28日 刈谷日劇にて鑑賞>
移民と飲食店の厳しさ
アメリカは移民が多い国ではあるが、不法滞在も厳しく取り締まる国でもある。それでも入国しようとする人が後を絶たないのは、そこに夢と希望がある(ように見える)から。
本作に登場する移民たちが置かれている状況と彼らの周りで起こる出来事は、移民の厳しさと彼らが感じる夢と希望を説明するものだった。男も女もカラダを使ってしか金を稼ぐができない。生活をやりくりするだけでなく、商売を始めたり進学したり、何かしらのステップアップするのはとてつもなく高いハードルが待ち受けている。
そうした弱みに付け込む人もいれば、助けてくれる人もいる。なんてツラいのだろうとも思うが、捨てたもんでもない。あんな感じでブリトー屋を開こうとする神経が信じられない。それに乗っかるママも含めてだけど。飲食店経営ナメんなと言ってやりたい。
後半、結構大きな出来事が起きて大変な状況に陥るのだが、なんか微妙に希望を感じる終わり方だったのがまだ救いか。恋の話とも言えるし家族愛の話とも言えるが、やはり移民と飲食店の厳しさが一番印象に残ってしまう映画だった。
中盤から
青春ラブストーリー?家族愛?
食肉のトラック🚚に紛れてアメリカに不法に越境したペルー人の家族(母親と子供二人 子供は高校?)の話
子供二人は英語学校に通いながら、ウーバー(食事の配達)で日々の生活費を稼いでいる 母親は朝早くから仕事に出かけウェートレス 食事に来た男に口説かれ、アレヨアレヨと…
子供二人は英語学校に入学してきたどこか不幸をしょっているような女性にメロメロに…
しかしその女性は収監されている男(妻子持ち)を出所させる為に身体を売りながら…最後には
悲しくなるが、現実を見せつけられる内容でした
邦題が意味不明だが、移民と不法滞在者のリアルが描かれていた
2024.1.22 字幕 アップリンク京都
2020年のスイス映画(97分、PG12)
原作はアーノン・グランバーグの小説『De bellige Antonio(1998年)』
クロアチア移民に恋をしたペルーからの不法滞在兄弟を描いた社会派ラブロマンス映画
監督はマーク・ウィルキンス
脚本はラニ=レイン・フェルタム
原題は『The Saint of the Impossible』で「不可能の聖人=劇中で登場する聖リタ」を表す言葉
物語の舞台はアメリカ・ニューヨーク
そこで暮らすペルーからの不法滞在者ポール(アドリアーノ・デュラン・カストロ)とティト(マルチェロ・ディラン・カストロ)の兄弟は、ある女性との思い出に耽っていた
その女性の名はクリスティン(タラ・サラー)と言い、彼女はクロアチアからの移民だった
二人が通う英語教室に突如現れたクリスティンに恋をした二人は、あの手この手で距離を近づけようと行動していた
二人には近くのダイナーで働いている母ラファエラ(マガリ・ソリエル)がいて、ある日突然姿を消した息子のことを案じていた
友人のルーチャ(Elizabeth Covarrubias)とともに仮住まいを訪れたラファエラは「移民局」の捜査が入ったことに気を病んでいた
映画は、ラファエラの回想を主体にしつつ、彼女が知らない兄弟の一面を再現していく内容になっていた
映画は、クリスティンとの色恋沙汰がメインの童貞ものという感じで、彼女には訳があるという内容になっている
彼女の恋人ジェイク(ブライアン・ドール)が収監されていて、その釈放のための弁護士費用を集めるためにコールガールをしているというもので、その真相が後半で暴かれる感じになっている
兄弟の本音を察したクリスティンが条件を提示して行為に及ぶのだが、その余波を受けた二人が移民局の世話になってしまう
ペルーに強制送還された二人が何とかルーチャに連絡を取り、それによってラファエラに安堵が訪れるというものだが、訳あり底辺なので足元を見られまくっているという流れになっていた
そんな彼女にも一時の清涼が訪れ、それがスイス人の官能小説家エワルド(サイモン・ケザー)なのだが、彼が家に来たことによって、兄弟たちの行動がエスカレートしていくように紡がれていく
要は、母親が兄弟のことを考えているふりをしながら男に傾倒し、彼らの始めるビジネスに巻き込まれるのだが、その反発は水面下で起こっている、という感じになっている
飲食デリバリーの経験があると言っても、無許可で無計画で始めるあたりが無茶苦茶で、そりゃあそうなるよねという結末が訪れる
エワルドはラファエラ捨てられた後にちゃっかりと新しい女を連れ込んでいたが、街角のラバが一撃をお見舞いするのは爽快と言えば爽快なのかもしれません
いずれにせよ、邦題の印象から「ニューヨーカーと移民の恋」みたいなイメージを持っていたが、原題の意味が劇中で登場した唖然としてしまった
久しぶりに全く関係のない邦題がついて呆れてしまったのだが、これ以外に思いつかなかったというのが現実なのかもしれない
原題をそのまま使用しても日本人にはほぼ意味が通じないのだが、せめて「ダウンタウンの聖リタ」ぐらいの宗教色を取り込んでも良かったように思えた
ラマになって唾を吐く
幸せの未来完了形
評判の良さを目にして、予告編も未視聴のまま鑑賞したので、のっけから衝撃を受けた。
自転車が車と衝突しても、車側から「傷がついたじゃない!」と怒られてしまう街なんですね、ニューヨークって。
公然と格差が肯定されていて、弱い立場の者は強い立場の者に何をされても逆らえない。まぁ、あの女性ドライバーからすると「デリバリーをしているのは、どうせ不法滞在者で、表に出られない奴らなんでしょ?」といったことなのかもしれないけど、ポールとティトの2人の「透明人間は嫌だ」と言う気持ちは痛い程伝わってくる。
2人が恋するクリスティンも、ちょっとは身につける物が小綺麗でも、男たちにいいように扱われ続けている様は、やはり「透明人間」。自分のポートレートを相手に渡し、自分が求める時にはすぐに提示できるよう指図するのも、相手が自分を大切に思ってくれていることを目に見えて確かめる、彼女にとっての存在確認の大切な方法だったのだろう。
スプレーとナイフを携帯しつつ、自分の身を投げ出すことと引き換えに対価を得てきた彼女が、そうした生活に耐えられたのは、愛する彼の存在があったから。だからこそ、それが裏切られた出所の場面、美しく着飾った彼女の顔がみるみるうちに歪んでいくあのシーンの切なくて残酷なこと。
2人の母親のラファエラから「愛を与えたつもり?」と尋ねられて、クリスティンの「(2人は)もともと愛でいっぱいだった」との答えが胸を打った。
ビールを飲みながら授業する英会話学校教師や、上から目線のスイス人エロ作家を始め、胸糞な輩は山ほど出てくるが、不思議と爽やかさが途切れないのは、やはりポールとティトが真っ直ぐで清々しいからだと思う。
まだ道のりは長そうだったが、この2人だったら、確実に将来的には幸せをつかむだろうという希望が感じられた。
個人的には、ラマに「いいね!👍」を連打してつけたい。
話は変わるが、今回鑑賞した映画館は、塩尻市の東座という。上映前に、支配人?の合木さんから、毎月2週間自分のおすすめ映画を上映するというこの「FROM EAST上映会」の説明と、今回の映画の見どころや監督に関する話があった。NO原稿で、柔らかな語り口で、しかも決して観る前の余分なネタバレにはならない内容で、その見事さに心から感動した。また是非足を運びたいと思った。
透明人間って、いい得て妙な。
皆懸命に生きている
全37件中、1~20件目を表示