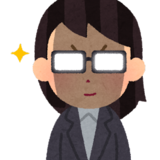雪山の絆のレビュー・感想・評価
全56件中、41~56件目を表示
「自分だったら」を突きつけられる
「極限状態」を標榜する映画は多々あるが、事故の描写、雪山の過酷さと飢餓への恐怖等、圧倒的な救いのなさで打ちのめされた。
あの中に放り込まれていたら、自分はどんな選択をしただろうか…。2時間半を超える長さで、静かなリアリティを持って迫ってくる画面を見ながら、幾度も「自分だったら」を突きつけられた。
このタイミングということもあり、観終わってからも、胸にズシンと重いものが残ったままの状態。
生きてこそ
1972年10月13日、ウルグアイのラグビー選手団を乗せチリに向かっていたチャーター機がアンデス山脈に墜落。72日間に及ぶ想像を絶するサバイバル…。
悲劇の事故であり奇跡の生還劇とも言われるこの実話は、1993年の『生きてこそ』や幾度も映画化やドキュメンタリーになっている。
今回スペインで(アメリカ・ウルグアイ・チリ合作)J・A・バヨナ監督が新たに映画化。
まだゴジラやドラえもんなどの映画しか見ていなかったあの頃、初めて見たと言っていい“実話サバイバル映画”が『生きてこそ』だった。なので、今でも印象に残っている。
それを新たに映画化するのだから、興味惹かれない訳がない。配信を楽しみにしていた。
一部劇場でも公開されているらしいが、劇場大スクリーンで見たかった…。
『生きてこそ』を見ていたので、事故の概要、そこで何があったか、生還まで分かっている。それでも見入ってしまう。
やはり事故~サバイバルが見所。それを製作側は分かっているようで、蛇足や冗長になりがちな導入部のドラマを極力省き(でも簡素に纏めている)、早々と展開。
アンデス上空に差し掛かった機。激しく揺れる。
ただの揺れじゃない。その恐怖と不安は的中した。
機はコントロール不能に。山に衝突し、機体は真っ二つに…。
機内の惨事。頑丈な座席は玩具を壊したかのように前方に押し出され、座っていた乗客のやわな身体などぺしゃんこ。
簡単に書いたが、それがどんな恐ろしい事か…。飛行機や電車の事故で、中でどんな惨状になっているか…。ふと、2005年の痛ましい脱線事故を思い出した。
多くの乗客が死亡。即死。
が、助かった者たちも。生死を分けたのは何なのだろう。座席の位置…? 運…?
墜落という惨事から生き残った彼らを待ち受けていたのは、別の惨事であった…。
極寒の雪山。身体を刺すような寒さが襲う。
墜落時の負傷。手当てもままならない。
サバイバル最大の難題。水と食糧。
水は雪から得られるが、食糧は…。備蓄もあっという間に底を付く。
人は水だけでも暫く生きられるというが、この場合状況が違う。寒さに体力が持たない。何か食べないと、皆…。
そうこうしてる内に、一人、また一人…と命を落としていく。
彼らが下した決断と選択は…。
かつて『生きてこそ』を見た時も衝撃だった。
死んだ人の肉を食べる。
何も極限状況下のサバイバルでの食人はこの事故だけじゃない。日本でも『ひかりこげ』という映画になった海難事故があった。
生きる為には仕方ないかもしれない。が、究極なまでに苦悩する。躊躇する。拒む。
意見が分かれる。
人が人を食べたら、人じゃなくなる。
後もう少し待とう。救助が来るかもしれない。
そんな倫理観や望みの無い期待を待っている余裕はない。
食べなきゃ死ぬんだ。生き残る為なんだ。
彼らは食す。が、徹底して拒む者も…。
私だったらどうだろう…?
食べられるか…? 食べたのがもし友人だったら、それに耐えられるか…?
この事故に於いて特に衝撃の出来事だが、それメインではない。
何としてでも生還する。
彼らの“生”へのヒューマン・ドラマになっている。
やはり若者たち。晴れた日には辺りを散策。自力での生還を試みる。
こんな状況下でも、自分やお互いを勇気元気付けるようにバカ話でもして笑い合う。
ある時、ヘリが。探してくれている。発見される。決してその望みを捨てない。
こういう時、地上からはヘリは見えるが、遥か上空のヘリのコクピットからは地上の豆粒のような人は分からないという。
結局救助のヘリは来ず…。
そして追い討ちを掛ける事が。
ラジオから、捜索打ち切りの報せ…。
これからここアンデスは捜索困難な季節にもなるが、もう彼らは生きてはいまい。死んだ可能性の方が高い。
それを聞いた彼らの絶望感…。
俺たちは、ここにいる。生きている。
それが見えない。聞こえない。
世界から見離されたも同然。
悲劇はまだまだ彼らを奈落の底に突き落とす。
晴れた日は外に出れるほど比較的穏やかだが、一転して吹雪の日は…。
忘れちゃいけない。ここは、極寒の雪山なのだ。
機内で押しくら饅頭のようにして寒さを堪え忍ぶ。
その時、不穏な轟音。
それは、雪崩だった。
機体を飲み込む。皆、雪の中に生き埋め。
何処まで彼らを苦しめるのか…?
この雪崩と生き埋めでまた多くが命を落とす。
すでに1ヶ月近く。何とかここまで生き延びたというのに…。
それでも、それでも、生存者は雪の中から這い出る。
死んでなるものか。
1ヶ月以上も過ぎた。
もう本当に限界。いやもう、限界もとっくに過ぎている。
ここでこのまま死んでいった者たちと同じく死んでいくのか…?
いつ再開されるか分からない救助を待つのか…?
いやそもそも、救助自体再開されるのか…?
現状を変える唯一の方法はやはりこれしかない。
自力での生還。
体力がまだある者がこの雪山を越え、西へ。チリを目指す。
もし、辿り着ける事が出来れば…。
無論、容易い事でも絶対的な望みもある訳ではない。
下手したら…。
でも、誰かが行くしかない。
決断した3人。出発。生存者の命を背負って。
残った者たちは3人に命を託して。
スマトラ沖地震を題材にした実話サバイバル×ヒューマン・ドラマの『インポッシブル』で名を上げたJ・A・バヨナ監督が本領発揮。
墜落時の緊迫感溢れるパニック描写、雪崩時の閉塞感、絶望的状況下のリアリティー…見る者を圧する臨場感と迫力の演出。
アンデスの雪山群。過酷で恐ろしくあるのに、スケールと景観にも魅せられる。
キャストは皆知らないが、アンサンブル熱演。
J・A・バヨナ監督のキャリアベストの一本。あの恐竜映画が代表作じゃない。
実に72日目。
乗員乗客45人の内、生還したのは16人。
半数以上が…。
それでも16人が生きて還ってきた。
夢にまで見た家族や恋人との再会。
果たせなかった死亡者や遺族の無念を忘れてはならない。
映画は生還と再会で一応のハッピーエンドとなるが、実際は食人が議論の的になったという。
何が一番重要か。そんなの誰でも分かる筈だ。
その揚げ足を取る輩がいるのも事実。
素直に喜べ。彼らの尊い命を。
印象的なナレーションは生存者ではなく、命を落とした友。
友たちに語り掛ける。
生き延びた理由は…? 意味は…?
それは当人たちにしか分からない。
生きていく上で見出だしていく。
見る我々も。
『雪山の絆』というタイトルも悪くないが、同題材の別映画のタイトルをレビュータイトルに。
生きてこそ。
本当にそうだと思う。この悲劇に見舞われた彼らにとっても、今を生きる我々にとっても。
生きてこそ。
2024年、早くもベストの一本に推したい。
パンフレットがない点が厳しいが、それでもおすすめ以上
今年13本目(合計1,105本目/今月(2024年1月度)13本目)。
もともとネットフリックス契約者向けの作品のようで、この手の映画は映画館で見てもパンフレットなどないようです。
ただこのサイトを見てもちゃんと元になる事件名までは記述されているので、そこで予習していくかいかないかという点がまず分かれるのかな…という気がします。
かえって日本を見ると、飛行機事故も、いわゆる登山によるトラブルもどちらも見られますが、映画で描かれるような類型はあまり聞かず(ただ、趣旨としては理解できる)、ある程度類推してみることができるタイプの映画です。
映画のレーティングとしてはPG12で、一部に不穏当な描写・発言が出てくることによりますが、もっともこの映画をお子さんが見に行くのかというと微妙で、正直この事件自体も「調べればわかる」程度になっているので、そこをどう評価するかという点に大半つきるというところです。
なお、スペイン語放映ではありますが、実際には南米スペイン語である(スペイン語に関してある程度知識があればわかるし、そもそも「スペイン語」と「南米スペイン語」は別の字幕扱い)ことに注意です。
採点上特に差し引く要素まで見出せないのでフルスコア扱いとしています。
実話に基づく奇跡の物語
原題
La Sociedad de la Nieve
Society of the Snow
感想
構想から10年、アンデス山脈で起きた悲劇の全貌をJ•A•バヨナが映像化
遭難事故から36年後に執筆された著書を基に、生き残った者、そして生き残れなかった者たち、両者の姿を描く。
壮絶、壮大でした。
飛行機墜落はあっという間に機体がバラバラになり、後部座席が吹っ飛び仲間も消える、機内もぐちゃぐちゃになり、人間の骨の折れる音はキツかったです。
墜落後も極寒と飢餓。
次第に食料がなくなって遺体を食べるという…。しょうがないと思います、生きる為に…。
でも死者の肉で飢えを凌いでいたのが物議を醸すんですよね…。
雪崩が起きた時は絶望でした。
生き埋めになり、観てるだけでも息が詰まるような思いでした。
語り手で主人公だと思ってたヌマが死ぬなんて、最後の死亡者になるなんて思ってなかったです。
ナンド、ロベルトの遠征隊がタフでした、アンデスの山々も絶景でした。
72日間のサバイバル生活で生還できた人は本当に助かって良かったと思います!
※友のために命を捧げるほど偉大な愛はない
湯気
生き延びる方法を模索する生存者達に感情移入して、映画である事を忘れて全てがリアルに見えました。
事故の瞬間の映像や
雪崩のシーンの臨場感が凄い。
ネトフリで見ましたが、
映画館のスクリーンで見たかったです。
事故当日の夜、生存者達が機体でうずくまりながら息をしている時に口から出ていた湯気。
「これから死にゆく」湯気。
登山をした2人が救出された後にパンをスープにつけてハフハフしながら食べるシーンの湯気。
「これから生きゆく」湯気。
対照的なシーンで印象的でした。
救出後のエピローグもある程度描かれていて良かった。
痩せ細った体を洗うシーンなど最後までリアル。
【アンデス山脈に墜落し、過酷な状況下最後まで生き残った16名のラガーマンの姿を描く。彼らは生きるために究極の手段を取るが、人間としての理性を保ち生き延びようとする姿とラストは涙を堪えきれない作品。】
ー 学生時代に、雪山登山をしていた事もあり原作は読んだ記憶がある。だが、映像化された今作品を見ると、1972年の雪深き4000Mを超えるアンデス山脈に墜落しながらもよくぞ生還したモノだなと改めて思った作品である。-
◆感想
・微かな記憶だが、原作はウルグアイ空軍機に乗っていた人たちの視点から描かれていたと思うが、今作はラグビー選手のヌマの視点で描かれている点が個人的意見だが奏功していると思う。
・冒頭の、ウルグアイ空軍機をチャーターしたラグビー選手団が乗った小型飛行機が墜落するシーンはトンデモナイ臨場感である。後部座席は吹き飛び外に投げ出される選手たち。
・その後、飢えと寒さが襲う中、選手団一の俊足を誇るロベルトが口にした究極の選択。
ー 最初は拒否する人もいるが、フィト達が意を決して解体し、小さな凍った肉片を無表情で口にする人達。
ヌマはその時の気持ちを”口にして2,3回咀嚼しただけで、呑み込む。”とモノローグで伝える。-
・その後、やや体力を回復した機内に居た彼らを襲う表層雪崩。仲間を必死に雪から掘り出すも、尊き命が失われる。
ー だが、生き残った選手たちは数日後、雪を掘り進め陽光を浴びるのである。表層雪崩であった事と、季節が春に向かっていた事も彼らの命を救ったのだろうと思う。-
・漸く掘り出したラジオから流れる、捜索打ち切りのニュース。彼らは一度は絶望に陥れられるが、36日目、ヌマを含めた4人がアルゼンチンに向けて僅かなる装備を整え出掛けるのである。
ー 物凄い、生きる事を諦めない精神力である。だが、途中足を怪我していたヌマの傷が化膿していた事を知った仲間は引き返すのである。劇中、屡々生き残った彼らの的確な判断が描かれる。だが、ヌマは傷が元で亡くなってしまう・・。-
・生き残った彼らは儀式の様に小さな凍った肉片を口にしつつも、理性を失わず決死の行動に出る。それは吹き飛ばされた機体の後部にある筈のバッテリーを回収する事である。
ー その途中に見た、吹き飛ばされ亡くなった後部座席に座っていた友の凍った遺骸から、免許証などを回収する姿。-
・61日目、ナンドとロベルト達3人はチリへ向け、再び歩み出す。
ー このシーンも良く撮ったなと思う。アイゼンもピッケルもない中、斜度45度以上(観た感じです。)の斜面をラッセルで登り、雪壁をトラバースし、峠に立つのである。
そして、峠に立った時に目の前にある雪を冠った山塊を見たナンドが言った言葉。”ここまでくれば、海まで歩くぞ!”
今作では、生き残ったもしくは自らが死に行く時に”俺の遺体を食べてくれ・・。”と言った仲間の姿と共に、驚異的な精神力を持つナンドとロベルトの姿は驚異的ですらある。涙腺が緩み始めてしまう。-
<ラスト、ナンドとロベルトの二人が麓の地元民に発見され、彼らの帰りを待つ仲間達が、ラジオから流れる自分達の名前が告げられるシーン辺りから、涙腺が崩壊し始める。
救援のヘリコプターが来た際に、亡くなった仲間の遺品が入った荷物を必死に抱え、ヘリに乗る男の姿。それを許容する操縦士。
今作は、実話ベースである事をさしおいても、究極のサバイバル映画でありながら、人間の尊厳を失わずに生還した若者達の姿が深く心に刻まれる作品である。
冒頭で撮られた、彼らの集合写真がラストに再び映し出される瞬間は、思わず嗚咽が出てしまった作品でもある。>
奇跡ってなに
間もなくNetflixで配信されますが
自宅のテレビで観るより、
断然スクリーンで
あの迫力を味わって頂きたい🥶
アンデス山脈の美しい山々や
墜落シーン、機内の衝撃が忠実に
再現されていて最恐トラウマ級です🥶✈️
諦めないこと
信じることの大切さ
「奇跡ってなに」
実話と知らなかったらそんな訳あるかと思ってしまう
2023年劇場鑑賞309本目。ネトフリ配信作なのでパンフレットはもちろんなくマイナス0.5。今年最後の作品になりましたがなんて作品が最後だよ!
雪山に遭難したラグビー部の話とだけ聞いていったのですが、まさかあの事件の映画化だったとは・・・。
どんどん人がなくなっていく中、こちらのトイレの我慢も極限になってどっちが先に限界を迎えるか勝手に体験型ムービーになっていました。サバイバルの描き方は本当に絶望的で良かったです。
トイレの事を考えると1秒でも早く終わって欲しかったのですが、助かった後彼らに待ち受けていたであろう世間の反応とそれに対する彼らの向き合い方は観たかったです。そうなると確実に漏れてましたけど(笑)
面白いけど長い
生命力に驚愕
1972年10月13日、ラグビー選手団を乗せてウルグアイからチリへ向かっていたウルグアイ空軍機571便が、アンデス山脈中心部の氷河に墜落した。乗客・乗員45名のうち生存者は29名。想像を絶する過酷な環境のなかに取り残された彼らは、食料も底をつき、生き延びるために遺体の人肉を食べるしかない状況に追い込まれていった。そして、雪崩などにも襲われ、救助活動も打ち切られ、約2ヶ月経った頃、チリへ向けて救助要請に向かった2人がなんとか地元民に遭遇でき、残り14人の計16人が生還できたという、事実に基づく話。
標高4200mで峰に激突し墜落して、3700mの高地で酸素も薄く、食料もなく、まだ雪解けも始まらない山の中で、嵐にもあい、極限状態に置かれた人々の恐怖と遺体の人肉を食べるという倫理的な葛藤、生きることへの執念、仲間との強い絆なと、凄いものを観せてもらった。
雪山を10日間も歩き、チリの地元民に出会えた時の嬉しさがスクリーンからも伝わってきて感動した。
遺体を処理した3〜4人は辛かったと思う。
これ、生還者の書いた本が原作らしいが、Wiki読んだだけでも凄さがわかり、本当に感動した。
NETFLIX発、「ジュラシック・ワールド 炎の王国」のJ・A・バヨナ監督が贈る、驚愕の実話ドラマ
配信前の先行劇場ロードショーで観てきました
50年前にアンデス山脈で起きたウルグアイの航空機墜落事故と奇跡の生存者たちが送った2ヶ月のサバイバルドラマをじっくり2時間半かけて描き切る骨太の実話ドラマ
絶対に風化させてはいけない出来事だし、目も背けてはいけない
とは思いますが、閉じられた場所での寒さと飢え、そして人の死と向き合わなければならない極限状態を疑似体験するような内容だから、不謹慎な言い回しかもしれませんが、苦手な人はかなり苦手な内容かもしれません
全体的に観ていてキツかったのですが、私の中で一番インパクトがあって観終わっても精神的に尾を引いているのは冒頭の飛行機の墜落シーンです
いろんな映画の中でよく描かれてきた類のシーンですが、本作の映像はリアルで木っ端微塵になる描写がエゲつなく、凄まじくて痛々しい最恐の映像体験になりました
その墜落シーンの圧倒的迫力に加え全編に映し出されるアンデス山中のダイナミックなフルロケーション映像が本当に見事で素晴しい、これはNETFLIXの家庭用モニターだけでは本当にもったいない、是非 劇場の大画面と大音響で体験してもらいたい作品です
ストーリー展開は分かっている、だが目が離せない
全56件中、41~56件目を表示