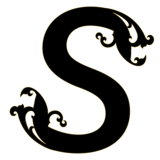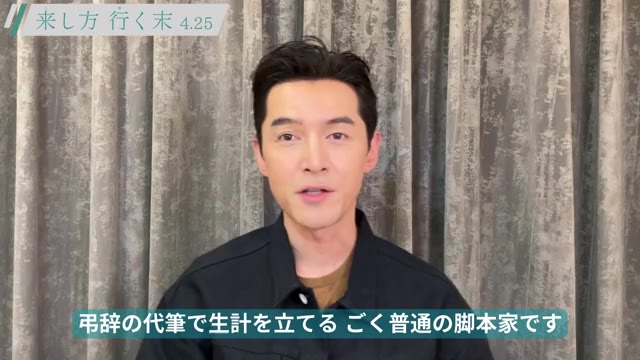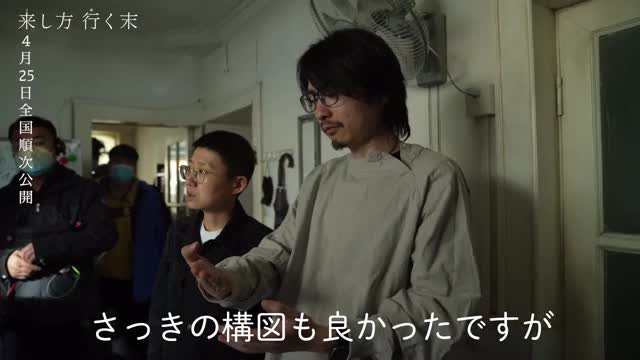来し方 行く末のレビュー・感想・評価
全36件中、1~20件目を表示
透明感と柔らかさに満ちた映像で紡がれる再出発への道
透明感あふれる映像の中で、人の生き様や遺したものを真摯に見つめる物語である。主人公は弔辞の代筆業を担っている。遺族に代わって故人の人となりをまとめる仕事だ。依頼者は北京で日々忙しく暮らす人ばかり。もしかすると10年先にはAIでたやすく代用される職かもしれないが、しかし今依頼が絶えないのは、彼のとても誠実なリサーチ力と、完成原稿のクオリティに定評があるから。案件によっては、遺族から話を色々と聞く中で、故人の知られざる思いを発見することもある。ではなぜ彼はこうして見ず知らずの人について掘り起こすことに長けているのか。ここに本作のもう一つの焦点と、なるほどと腑に落ちる展開がある。終始ゆったりとした語り口で、感情を荒げたり、感動を押し付ける真似はしない。悪人も出てこない。だからこそ、この再出発の物語に安心して身を委ねられる。決して派手さはないが、気がつけば不思議と心にエナジーが溜まっている一作だ。
落ち着いた台詞劇 これが今の北京の空気感? 追記
弔辞の代筆サービスは日本でもあるらしい。
5000〜15000円くらい。
弔辞代筆が北京でどのくらいポピュラーのものかは分からない。
この作品は2023年公開。
マスクがでてくるのでコロナの残滓がある空気感だ。
ウェンが弔辞代筆を請け負うのは映画の中で4件。
①同居していた父親との交流が少なかった男性
②CEOの突然死に戸惑うあとを継ぐ経営者
③余命宣告を受けて自身の弔辞を依頼する婦人
④ネットで知り合った顔も知らない声優仲間を探す女性
途中で北京でおそらく成功している人物として描かれた①の男性はウェンに4000元(82000円くらい)を振り込む。
多分、相場よりずっと高い金額なのだろう。
それでも、あの丁寧さで弔辞を書いていたのであれば生活は苦しかろう。
全体にストーリーは淡々と進み、大きな事件は起こらない。
おそらく人に疲れて動物園で観察をするが、それでも着ぐるみを来てゴリラの世話をする飼育員という人間を相手にすることになる。
同居人は謎であったが、彼はウェンが脚本の中で育てられた架空の小尹(シャオイン)であることが最後に明かされる。
ウェンはおそらく脚本の学校にいる頃からその才能を認められていたのだろう。
多くの脚本を依頼されているのだ。
ただ全てが未完成。
この静かな展開、4件の弔辞案件を重ねる手法、大成功で終わらないラストシーン。
死者は全て残された関係者によって言葉のみで語られ写真さえ登場しない。
癌の老婦人の葬式では姿は映されない。
①〜④の人生は台詞のみで描写され、ラジオドラマでもよかったのではないかと思うくらいだ。
ウェンは、それでも遺族の感謝を糧に一歩踏み出す。
そこで小尹(シャオイン)は消える。
とても静謐で成熟したドラマだ。
こういう機微は中国の古典にあるのだろうか?
あぁ、文化的にも大陸は侮れない存在のようだ。
ただイケイケドンドンでないのは衰退も感じなくはない。
追記
ウェンの漢字は「聞善」
これは漢字文化圏でないと分からないだろう。
ウェンは書けなくて苦しむが「聞く」ことで救われていく。
ウェンのアイスクリームを買ってくるシーンは記憶されるべき。
原題「不虚此行」は日本語で「行ってよかった」「無駄足ではなかった」
行くは、逝くとウェンが前に進むことの意味でしょうか。
英語版の題は、all ears 耳を傾けてください。
あまり中国映画と意識しないで見れたかな
中国映画。
脚本家になれなかった男が、弔辞の代筆業を行う話。
身近な人が死んで弔辞の代筆を頼む人達の話。
いろいろな人間ドラマが描かれる。
あまり期待してなかったけど、良い映画でした。
中国も、こういう感性の映画も作るんですね。
基本、日本と感覚は同じなんだと思った。
でも、実際は、弔辞の代筆は難しいと思うし、いろんな人からの聞き取りが必要になるから時間はかかるし、そうなれば費用も高額になると思う。
結局は一番関係が深い人しか書けないと思うのだけど、中国の文化では違和感は無いのだろうか。。
最後には分かったのだけど、誰だか分からない同居人。
その二つが気になりながら見ていた。
映像やテンポは、とても良い雰囲気でした。
あまり中国を意識しなくても見れた感じでした。
北京が舞台だったからなんでしょうね。
中国映画というと貧しい農村をイメージしてしまう。
パソコンにスマホでフードデリバリーと、出てくる日常生活は日本と同じでした。
いろんな出来事を通して主人公は、、ファーストシーンよりもラストシーンでは確実に成長していた。
出てくるキャラ・役者さん達も良い感じだったし、楽しく見れました。
ラストシーンは、もう一度、夢に挑戦するという事なんでしょうね。
後味の良い映画でした。
中国映画も面白いものがたくさんありそうですね。
合わなかった
読み手は物語が完結していないと次のページをめくれないように、遺族も故人の人生が完結しないと次に進めない
主人公のウェン・シャンは大学院まで進学しながら、脚本家として商業デビューが叶わず、不思議な同居人シャオインと暮らしながら、今は葬儀場での〈弔辞の代筆業〉のアルバイトで生計を立てている。丁寧な取材による弔辞は好評だが、本人はミドルエイジへと差し掛かる年齢で、このままで良いのか、時間を見つけては動物園へ行き、自問自答する。同居していた父親との交流が少なかった男性、仲間の突然死に戸惑う経営者、余命宣告を受けて自身の弔辞を依頼する婦人、ネットで知り合った顔も知らない声優仲間を探す女性など、様々な境遇の依頼主たちとの交流を通して、ウェンの中で止まっていた時間がゆっくりと進みだす(公式サイトより)。
主人公のウェンは脚本家を志しながらも、「多くの仕事を受けたが、全部未完成」である。他方で生業としている弔辞は、故人の人生を完成させる営為である。読み手は物語が完結していないと次のページをめくれないように、遺族も故人の人生が完結しないと次に進めない。弔辞をはじめ、火葬や葬儀といった一連の儀式は、徐々に大切な人の死を形象化し、これからも生きていかなければならないわたしたちを前に進めるためにある、人類が蓄積してきた叡智、あるいは切実な処世術である。
生活のためにだけにやっている弔辞執筆が、常に「テンションの低い」ウェンの完結できない創作に、とても静かに穏やかに反響していく様が、美しい映像で表現されている。内省的で、聡明で、温和なウェンをフー・ゴーが好演。この作品で唯一動的な登場人物であるシャオ・ジンスイ役のチー・シーがよかった。突然、立ち去り、いきなりアイスを買って戻ってくるシーンは素敵。経済発展を続ける中国に現在進行形で起きているであろう、仕事と人間性の狭間の葛藤や、要所に織り込まれるコロナのマスクなどの描写も良かった。あと猫も。エンドロールまでご覧ください。
ゆったりしっとりやわらかい
新宿武蔵野館で観た時は、ゆったりした雰囲気は好きなのに、エピソード量の割に主人公のウェンシャンが物静かすぎてイマイチ入ってこず。
でも好きな映画のはずだから、ちゃんと観たくて2回目。
故人との関係の長さ深さは人それぞれで、想いもそれぞれ。
接した人の視点で良くも見えるし悪くも見えるから、内容に納得いかないのも分からないではない。
一度観ているから、今回はそれぞれのエピソードがすんなり入ってきた。
感情があまり出ないウェンシャンがファンさんのお葬式で想いが溢れてしまうシーンは良かった。
そしてファンさんへの弔辞が沁みた。
原題のとおり、彼のまわり道は決して無駄ではないし、パソコンに向かう表情は晴れやかだった。
だけどやっぱりシャオインとの関係は分からなかった。そもそも生きてる人なのか?はたまたウェンシャンの心が具現化したものなのか?
おそらく彼女には見えてなかったような。
回り道の人生でも
文章で食べる事
「パソコンは逝去者の名前を3回入れるとその名前を学習してくれる」。 「そして時を経ても、なにかのきっかけでふとその名前がモニターに現れるんだ」。
弔辞を読んだ事がある。
親しい、早世した友人のために。
いつも一緒にいた人だから、その彼女の人となりは熟知していたし、ご家族の皆さんのこともよく知っている。
だから、旧知の人間の野辺送りのために言葉を贈ること=弔辞は、(辛いけれど) ある意味で出来ない事ではない。
うちの両親も齢九十を超え、食が細り、元気が失われてきている。先週から僕ら子供たちで「死亡広告」の数行の文案をいろいろと練り始めたところだ。僕が「叩き台」を出したので弟たちもそこに乗って「弔辞の添削作業」で盛り上がっている。
⇒本人を良く表す言葉は何か。
⇒その家族の眼差しを尊ぶ言葉はどこか。
準備するに遅すぎることはない。
けれど本作、
一度も会った事のない誰かの、その葬儀のために送り言葉をしたためるという「弔辞屋」についての話だ。
・・・・・・・・・・・・・
日本では、少子高齢化の波は街角の姿の変わりように如実に現れている。逆台形の「人口年齢分布グラフ」は今にもひっくり返ってコケそうである。
指圧・整骨・マッサージ店の隆盛、
林立する高齢者デイサービスの出張所、
家族葬のための小規模斎場がここにもあそこにも軒並みあるし、
散骨や樹木葬の看板も頻繁に見かける。
・・これら高齢者向け、あるいはお葬式のためのエンディング産業が、潰れたコンビニの建物の居抜きとして、また大きな新築のビルとして、石を投げればどれかに当たるほどの社会な現象として、一大産業となっているのだ。
これはお隣の中国でも同じように、否もっと大変な規模と事態で、今まさに社会を揺るがしているはずだ。
今回のこの映画は、「何十年にも渡って一人っ子政策をやっちまった中国」の
引く手あまたの葬式産業について、
そしてその下請けであるひとりのアルバイト男=「弔辞屋」の物語なのだ。
・・・・・・・・・・・・・
人生は 一章、二章、そして最終章の第三章から成ると主人公は呟く。しかし
【人生の第二章】で頓挫するのが我々の人生。そして死なのだと。
主人公は自分に失望している。
脚本家を目指して文学部の大学院まで行ったものの、躓き、そして頓挫した四十男のウェン・シャン。
満足などなし得なかった人の人生について
たくさんの死と別れに出会うことで彼も手探りの答えを見つけていく
その展開が、斬新で素晴らしかった。
― 生きて惑う人生こそ、つまり、「私の人生 今からだ!」と意気込んでいるさなかでの《第二章で潰えてしまう人生》こそ、嘘がない (そして恥じることのない) 我々の本当の生き方だったのだと、彼が気付いていくからだ。
死ぬことと、生きることの輝き。そこに彼は、己も自分自身として立ち会っている事を知るのだ。
⇒ いつも遺族にインタビューしてきたウェン・シャン。その彼のアパートに転がり込んできた変わり者の女から、今度は逆に根掘り葉掘り彼がインタビューを受け、初めて《取材される立場》を経験する事で、ウェン・シャンは自身の「来し方 行く末」の《自分の座標》を発見する。
これは新時代の、迷える現代人のためのシナリオと言えよう。
同居人(=実は主人公が作り出した幻影)や、バイト先の先輩、そして脚本学校の教師の言葉が光る。
パソコン、フリーター、同人アニメサイト、親や同級生たちへの卑屈感情、モラトリアム・・と、劇中の「キーワード」は今の僕たちに実感をもって寄り添ってくれる。
まったくこれは我々ためのシナリオと言えるのだ。
(死者はやさしく、すでに物言わぬ存在になっている所が、弱いナイーブな現代人への寄り添いと癒しになるのかも・・)。
そして登場人物は多いのだけれど、綿密な脚本の組み立てのお陰で、お見事、混乱は無い。
若い女性監督さんがこれを書き、撮ったらしい。信じがたい才能!
驚くべき重厚な人間ドラマだ。
かの国に蓄積し、数千年積み重ねられてきた文明と文学の、この土台の《厚み》。若き監督に開いたその開花を見せてもらって、まったく圧倒されてしまった。
そして物書きの映画らしく、たくさんの心に残る言葉のフレーズが僕の胸にも刻まれる。そうなのだ、
僕たち人の人生は、小さなエピソードと何気ない言葉の集積なのだ。
九十年生きれば九十年の、後から後から思い出す声とエピソードの、それは積み重ねだったのだ。
・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・
今夜の塩尻 東座 ―
スリムで長身の社長=合木こずえさんは黒の革ジャンの上下に目も覚めるような深紅の丸いイヤリング。
レイトショーだったので他のお客さんが はけるのを待ってから、ロビーで見つめ合って語り合う。
この小さな映画館の主宰者にも、そして今夜の客の僕にも、映画に負けないムービーが、そして
「来し方〜行く末」が息づいているのかと思うと
全てが愛おしかった。
ありがとう、いい映画に出会えました。
やや技巧的に過ぎるという印象
脚本、演出はリュウ・ジャイン。漢字では劉伽茵となる。我々にはちょっと性別が分かりにくいが44歳の女性。2000年代初頭にはインディペンデントの映画製作者としていくつかの海外映画祭で賞を得た。現在は北京電影学院(公立大学です)で脚本を指導する先生らしい。
さてこの映画ではフー・ゴーが演ずる聞善(ウェン・シャン)は大学院まで卒業している脚本家志望の青年?という設定。明らかに北京電影学院出身者を意識していますね。彼は脚本が書けないため弔辞を書いて生計を立てている。日本でもそうだけどこれは葬儀、告別式ではなく、後日催される「偲ぶ会」とか「お別れの会」で読まれるもの。亡くなってからしばらく時間があくのでその間、取材もできるし推敲の時間も取れる。でも一方、発注側(遺族や会社関係など)にすれば当初の悲しみからはやや立ち直っているだけに弔辞の出来には厳しくなるわけだ。
よく言われるように死後の一連の儀式や手続きは故人のためではなく残された人たちのためにある。だから弔辞は、故人の業績、故人との交流を懐かしく、有り難く、思い起こすだけではなく、自分たちがまた前に進むよすがになるような内容が望ましいのである。
この作品では弔辞ライターである聞善自身が、弔辞を依頼した人々(なかには自分で自分の弔辞を依頼する人もいる)と触れ合う中で、自分自身も前に進む力を取り戻していく姿が描かれている。脚本家である聞善にとっては、それは、納得がいくまで再び、脚本を書いてみることに他ならない。
だから、彼の脚本の登場人物である少尹(シャオイン、イン兄ちゃんっていうところか)は明確な実像を持たないまま、ぼんやりと聞善と同居しているが、きちんとした名前や設定を身にまとい、原稿用紙(パソコンですが)に姿を移すこととなる。
ここまで書いてきて、整理してみて、よく分かるのです。確かによく書けた脚本だと思います。演出も抑制が利いている。
でも、なにか、いかにも脚本の先生が書いた優等生らしさがちらついてしまう。そこが、正直、この作品があまり面白くないところにつながっている気がします。
静か 薄味 分かりずらい 眠い…
おみおくりの文法
脚本家への夢破れ、40歳を間近に停滞した人生を送る聞善(ウェン・シャン)。
葬儀業者から弔辞の代筆を請け負い糊口をしのいでいることを故郷の家族には内緒にしているが、同居人の青年から「本当のことを言え」と諭されても、「同じ物書きだから」と自分をごまかす。そんな彼の部屋には今も映画関係の書籍が幾つも並んでいる。
弔辞を仕上げるために近親者から聞き取りを続けると、物故者のあらたな一面が次々と明らかになるのは『市民ケーン』(1941)や『羅生門』(1950)のよう。
一見社交的ではないが、聞善の誠実な態度に依頼者も次第に信頼を寄せ、場合によっては故人との関わりを見つめ直す切っ掛けにもなっていく。
人間観察のために葬儀場に出入りするうち、弔辞の代筆をこなすことになった聞善は文章が評価されて依頼も次々舞い込み、周囲からも信頼を得ている。
故郷の人間から鼠眉(意気地なし)と呼ばれることを気にしているが、依頼主からは軸(頑固者)と言われることも。
聞善がいちばん理解出来ていないのは、自分自身なのかも知れない。
BGMもほとんどなく、セリフもまばらでゆったりと時間が流れる作品。観念的で中だるみする部分もあるのに最後まで弛緩せずに見られた理由は、大ヒット時代劇『榔琊榜』で共演した胡歌(フー・ゴー)と呉磊(ウー・レイ)が本作ではどのように絡み合うかに注目していたから。
本作で聞善を演じる胡歌は天才策士に扮した『榔琊榜』の時と異なり、風雲どころか波風も起こさない。
人生の最終章に辿り着けない社会の落伍者(と自分で決め付けている人間)を淡々と演じている。
悪くない映画なのに物足りなく感じてしまうのは、出演したTVドラマの多くで固定していたみずからの体育会系キャラを破って呉磊が新境地を示した『西湖畔に生きる』(2023)と較べてしまうから。そもそも、彼を本作にキャスティングした必然性をあまり感じない。
あくまで自己流の解釈だが、小尹(シャオイン)は聞善が考案した過去最高のキャラクターなのではという気がする。
溢れ出るアイデアを小尹を中心とした相関図にしてホワイトボード一杯に書き留めたものの、いつものごとく物語を結末まで導けず持て余す聞善の前に現れた小尹は、いつまでもフルネームがないことやセーター姿のままであることに文句をつけ創造主に進歩を促す。
いる筈のない小尹の名を呼びながら、悲しげな表情で聞善が家の中を徘徊する謎めいたなラストシーンが不思議な余韻を残す。
“聞”
ふんわりと心地良い
大学院卒のウェン・シャン、
脚本家を目指すがデビュー叶わず、
葬儀場での弔辞の代筆業で生計を立てているミドルエイジ。
シャオインという不思議な同居人と暮らしている。
丁寧な取材や弔辞の内容へのこだわりは、彼の真面目な性格が判るところ。
そして、時間のある時は、動物園に出かけ、このままで良いのか自問自答。
自身が位置づけるのは普通のつまらない男らしいが、
中盤以降で、その存在の意味が判明するシェイオンとの同居や、
弔辞へのこだわりは、なかなか個性的な男に思うけど。
そんな彼に仕事を依頼する人々、
例えば、
同居していた父親との交流が少なかった男性、
仲間の突然死に戸惑う経営者、
余命宣告を受けて自身の弔辞を依頼する婦人、
ネットで知り合った顔も知らない声優仲間を探す女性などなど、
様々な境遇の依頼主たちとの交流し、いろいろな考え方に触れることにより、
自分を肯定していく様がやんわりと描かれていて、
ふんわりと心に染みて心地よく感じました。
優しい作品でした。
地味ながらじんわりと感動する秀作
全36件中、1~20件目を表示