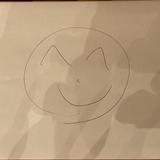小学校 それは小さな社会のレビュー・感想・評価
全17件を表示
子供達の心迄届くように
ー 小学校では色々な決まりがあります ー
初めて学校生活を迎えた子供達の何気ない日々を、まるでその場で見ているかのような映像で綴られた作品。
笑ったり、走り出したり、戸惑ったり、目にいっぱいの涙を浮かべたり、何気ない子供達の姿はずっと見ていたいほど (^^)
六年生の児童達の大人びた会話に驚かされる。
「 日々闘いです。」と語る教員の皆さんの熱い思いと踏ん張りに支えられているからこそ成り立っている、改めてそう感じました。
本当に頭が下がります。
ー 足はぴたっ
ー 皆んな優しい子
ー 子供のままでいたい
Eテレを録画にて鑑賞
タイトルなし(ネタバレ)
小学一年生担任のわたなべ先生は最初は言い方がきついと思っていたけど言っていることはわかる
🙂↕️
手裏剣を教えて作ってあげてる一年生の男の子が「係とか他にやることあるのにこれじゃできないよどうしよう😨」と戸惑っていた男の子に対し「手裏剣教えてあげるけど作るのは自分でやってくれる?って言ってもいいんだよ?」とわたなべ先生が提案しててそれをやるかやらないかは本人次第だけどあーそれも言っていいんだなって教えてくれる先生だったので良い先生だなと思った
6年生修学旅行先を事前調べで女子児童が
「先生部屋にドライヤーがない部屋があるだってどうしよう💦」
先生「自然乾燥で乾かせばいいじゃん!犬みたいにブルブルって笑」
児童「私は犬じゃありません!」が印象的
もし本当にドライヤーがなかったらフロントに借りるのか?本当に自然乾燥だったのかそれはデマだったのかはわからないけど先生冗談で言ってたのかな?
来年2年生になる児童が新1年生に歓喜の歌(第九)を演奏することになり来年度2年生になる女の子がオーディションに受かってシンバル担当になって朝練で楽譜を忘れて先生に怒られて大泣きしてしまった場面で閉じた
これ以上は自分はのりこえられないと思ってしまった
けど気になっていたので音無しで見てわたなべ先生がいいさんの一番の味方になっていたので視聴を再開しました。
私も一緒に怒られてあげるという言葉に救われました.
なんて愛にあふれた先生なんだ!!!と思った。いいさんに叱った先生も体育館での全体練習で失敗せずできたらほめてくれてとホッとした😮💨
昼休み練習しようねの後忙いでわたなべ先生に走って抱きつきに行ったところを見て本当に先生が大好きなんだな〜落ち込んだ時に抱み込んで
くれる存在がいいさんにいてよかったな☺️
タイトルなし(ネタバレ)
東京・世田谷区の公立小学校の1年を撮ったドキュメンタリー。
図らずもコロナ禍の2021年の撮影となり、コロナ禍下での小学校生活の記録となった。
リモート授業の様子が興味深い。
映画は、はじめは探るように様々な生徒を写していくが、そのうち数人の生徒に焦点があてられるようになる。
六年生の放送部員の男子生徒と、この年に入学した女児。
小学校生活を切り取ると、どうしても年中行事にカメラを向けることになる。
放送部員の男子生徒は、運動会・体育祭での集団での縄跳び演技が苦手で何度も失敗、自宅での練習を重ねる。
1年生の女児は、次の4月、新たに新入生を迎えるにあたっての音楽隊でシンバル担当をオーディションで勝ち取る。
が、勝ち取ったはいいもの、なかなか上手く演奏できず、ベソをかいてしまう。
こういうあたりを美談的にまとめていて、日本の小学校教育が集団を第一にしているのがよくわかる。
が、やはり観ていて、息苦しい。
型にはめることが最善、というのは、60歳のわたしが小学生だったころより、強固になっているのかもしれない。
英語タイトルは「The Making of a JAPANESE」。
日本人は、こうやって成型されるんですってね。
「大人になりたくないよ」という言葉の重み
色々と言いたいことは多いけれど、全体として思ったのは、日本の公立の初等教育は、やっぱりダメだな、ということです。
1年生と6年生の個人を中心に撮影されているのだけれど、6年生の男子が、卒業直前に同級生の女子に「大人になりたくないよ」って言っているのが、この映画を(そして日本の初等教育の成果を)象徴している言葉だと思いました。
日本の社会性に過度に順応させることを初等教育全体の目的にしているために、窮屈で理不尽な大人社会に出ていく恐怖を、小学校卒業時点で徹底的に深層心理に植え付けてしまっている。
目的と手段が完全に入れ違いになっているのではないか?
何のために生きるか、どの様に生きていくか、という教育を疎かにして、日本社会から爪弾きにならない手段だけを、徹底的に刷り込んでいるように思えます。
教員が、全力で集団的に善意で信念から、それを実践しているのが、本当に恐ろしいと感じます。
日本社会の歪みの原因の一端は、良くも悪くも、教育にあるのだと思います。
この映画は、私自身が日本の学校教育に感じていた疑問の一部を、反面教師的に解明してくれた映画になりました。
心の底から、自分の子どもを公立に通わせなくて良かったと確信しました。
日本の教育の全てを否定するつもりはないけれど、それがこの映画の率直な感想です。
誇るべきことでも卑下することでもない
「6歳児は世界のどこでも同じようだけれど、12歳になる頃には、日本の子どもは“日本人”になっている」は秀逸なコピーだ。
日本は経済規模の割には公教育にお金を出さない国で、公財政教育支出対GDP比はOECD加盟国の中で下から2番目だ。生徒が教室の掃除をしたり、給食の配膳をしたりするのはひとえに金をかけないからであって、生活指導も学校の機能だからというのは国の言い訳に過ぎない。たびたび批判にさらされる、枠にはめたがる画一的な教育も、そこに思想があるというよりも、枠にはめて一律に扱う方が教員の数を少なく抑えられ金がかからないからである。多様性を受け入れるにはコストがかかるのだ。精神論に偏りがちなのもそうだ。要するに「みんなビンボが悪いんや」ということなのだが、結果として、集団性や協調性が身につくと海外から評価されてるというのはなんともこそばゆい。卑下することはないが、決して誇るべきことでもないような気がする。
ただ、教育システムが画一的でも、限られた予算の中で教員たちは悩みながらも連携してよい教育を提供しようと奮闘しているのが画面から伝わってくる。結果、子供の個性はちゃんと様々に伸びる。同じ教育を受けてきただろう教員たちがそれぞれに個性豊かなのが何よりの証拠だ。シンバルの彼女が力不足だったのは入学後から1年間近く見ていた教師は最初からわかっていただろう。それでも、本人の希望に沿ってあえて役を与え、責任感を自覚させ、最後には自信をつけ、やり遂げさせるというのは教育の力としか言いようがない。
良くも悪くも集団生活を描く貴重な映像。作りもの感が惜しい
勉強以外の行事や学級の活動が盛りだくさんで、それらが子どもの成長の機会として意図されている日本の小学校。この映画は、集団活動の良さや、若干の弊害に焦点を当てた貴重な映像だ。
ただ特に前半は作りもののように見える場面も多く、ありのままの学校生活を見ている感じがしない。
なぜなのかと考えると、一つに「音」の聞こえ方がある。先生が子どもを指導する声が、遠くに移動した場面でも同じ音量ではっきり聞こえる。これはピンマイクをつけて撮影されているということなのだろうか。
実際の学校ではもっと声が反響してしまったり、子どものざわつきにかき消されてしまったりして、それが学校独特の活気や気だるさにつながっていると思う。この映画の場合、先生の指導内容が明確で、子どものほうも理解しやすく行動する場面が多く切り取られている。つまり「見やすいように撮る」ことが優先され、演技みたいな映像になってしまっているのではないか。
それでも放送委員をしている縄跳びが苦手な男の子のエピソード、卒業式の練習で行動がそろわず叱られる子どもの様子などは現実感があり、映画の見どころになっていた。
クライマックスでは2年生になった子たちが1年生のために楽器を披露する。そこでシンバルに立候補した女の子が練習で間違えて音楽の先生に叱られてしまう。厳しさと暖かさのある良い場面ではあるのだが、集団の同調圧力をありありと感じ取れた。
先生が女の子に自分の考えを言う前に、他の子たちに「練習しているから」楽譜がなくても間違えないと言わせている。でも本当は楽譜を必要とするタイミングは個人で違うかもしれないし、練習しても間違えてしまうかもしれない。
このような指導では、自分に合った練習法を選ぶというより、結局集団からはみ出さないことが大事だと学んでしまうのではないか。ほかに提出物に関する指導でも「反省しているかどうか」、つまり教師に与える心証を基準に評価する価値観が見て取れる。
集団のなかで自分の役割を学ぶ教育や、結果よりも成長を重視する指導はよいと思う。しかしその目的が「輪を乱さない人材」に集約されしまっているのではないか。先生たち自身、自分たちの指導のよしあしを職員室での反省会に委ねていて、確たる基準を持っていないように見える。こうした課題をどう見るのか、多くの人と共有してみたくなった。
凄いドキュメンタリーですね
元小学校教員です。ここにある映像は自分が何十年見てきた光景と非常に近く、そのリアリティは驚きしかないです。また、2021年度の撮影という事でコロナ禍の影響が強く残り、いろいろな教育活動に影を落としていたことも実際に体験した者として大変よくわかります。
映画館でお客さんがお金を払って観る映画ということで、単なる断片的な記録映像ではないのがいいです。ストーリーがある主演級人物として踏み込んで撮影された方が5人います。1年生の女の子と男の子、6年生の男の子、1年生の担任のベテラン女性教員、6年生の担任の坊主頭が印象的な若手の男性教員です。それぞれの人物が他の人物と密接に関わりながら、展開していく物語だけでも見応えがあります。涙を流すシーンがいくつかありますが、演技として泣くのではないガチの涙なので観る方としてもウルっと来ました。
追加です。2学期になって1年生は秋の公園てのどんぐりや落ち葉拾い、6年生は5年生のとき行けなかった日光での宿泊学習。多分他の学年でもコロナが落ち着いて行事が少しずつ復活しているだろうし、本当に良かったですね。なんだかんだ言っても学校行事は子どもを育てると思う。教員の犠牲的な奉仕に支えられているのは言うまでもないが。運動会も全校揃って開催できてよかったですね。羨ましいです。ただ、給食が「個食 黙食」で1年生も例外なしなのはちょっと辛いですね。
英語版タイトル『日本人の作られ方(THE MAKING OF A JAPANESE)』の方がしっくりきます
ドキュメンタリー映画としての技術的な面はちゃんとしていると感じました。
一方で、描かれていた内容は、教員が子供をコントロールするために強い口調で威圧する姿で、観ているこっちまで緊張し、何度も心臓がギュッとつぶされました。とても辛い映画でした。
ここに出てくる教員は、自分のやっている「子供のために、よかれと思って」やっているその方法を、私のような元小学生に否定されたくはないでしょう。ですが、威嚇することで相手を操るというのは、犬のしつけと変わらない。この映画に登場した教員の皆様には、このままのやり方で本当にいいのか、振り返って考えてくれていることを望みます。
朝一番に学校に来て、自分のクラスの机をぴったり揃えているあの先生が、一番ケアが必要に感じました。これ以上、強い口調で威圧して思う通りの行動をさせるこの方法を連鎖させて欲しくない。
減り続ける教員、増え続ける不登校、増え続ける若者の自死も同時に考えたい。
子供同士で靴箱の靴のおき方をチェックさせ報告させるという悪趣味な方法で、日本人の礼儀正しさが作られているなんて恥以外の何物でもない。
児童個人に貸与されているはずのタブレット端末を、教員が無言で取り上げる行為は窃盗とどう違うのだろうか?
コメントのお返事:
コメントありがとうございます。嬉しいです。
PISAとかOECD の調査とか?の学力的な面は日本は上位ですが、一方で幸福度や社会を変える力があると思える点は低いですね。この辺りも含めて考えたいですね。
考え直してみましたが、子ども同士で靴の揃え方をチェックさせるのは、自分にはやっぱり悪趣味で恥に思います。そういう部分が映像化され、改めて日本の教育の一部分と向き合うきっかけをいただいたのはいい事だと思います。
生徒も教師も楽しくなさそうだけど大丈夫?~ブラック教育文化
「外国から見た日本の小学校とは」という視点で、私たちが当たり前に思っていた学校の日常から、学校の内情、生徒と教師の喜怒哀楽にまで迫っている本作。
この映画のいくつかのシーンを通して、日本の学校教育が良さと危うさを同時に孕んでいることが見て取れる。
なお、この映画はドキュメンタリーであり、実在する人物が登場するが、教師個人を批判する意図はまったくない。あくまでその教師たちすら巻き込む文化としての日本の学校教育の危うさをここに書いていきたい。
1つ目の危うさは、周りと同じことをやらせすぎる、同調圧力。例えば、靴箱のシーン。廊下をくねくね歩く生徒に「普通に」と注意するシーン。
同調圧力によって、自分はこうしたいという「自分らしさ」(アイデンティティ)が育まれにくくなる。同調圧力のなかで選ぶ自由も多様性もなく、自分らしさは削がれていく。
皮肉にも、映画の中では、先生たちはたびたび「自分らしさ」という言葉を口にして、その大切さを強調していた。その一方、彼らは「普通に(しろ)」という言葉を使って真逆のことを強いており、その矛盾に気づいていない。教師たちの意味する「自分らしさ」とは、生徒が望んだ多様なものではなく、あくまで教師たちが望む限定されたものなのではないか。
2つ目の危うさは言いなりにさせる構造である。
例えば避難訓練のシーン。「遅い!」と言った時の声のトーンと大きさ。卒業式の生徒たちへの言葉。一般の社会で昨今あまり聞かれることのない内容で一般社会でこれらをしたらハラスメントである。しかし、教師たちも苦しそうである。
避難訓練で、逆に生徒が急いで転びそうになったら、今度は「あわてるな!」と怒鳴ることが予測される。つまり、どっちにしても、何をしても、生徒たちは怒鳴られるのでは。心理学では、これをダブルバインド(板挟み)と呼ぶ。
映画内で撮られた言葉かけは、一見生徒たちの注意を引くわけだが、具体的な改善点を教師が指摘しているわけではない(実は指摘できないのでは)。
けっきょくダブルバインドと同じように、生徒たちはどうしていいかは分からないまま教師の顔色をうかがうばかりになる。これは子育てにおける親子関係でも同じことが起こりやすい。
皮肉にも、映画の中では、教師たちはたびたび「自主性を育む」という言葉を口にして、その大切さを強調していた。そのわりに受け身にさせることばかりをしており、その矛盾に気づいていないのである。教師たちの意味する「自主性」とは、生徒が望む自由な行動ではなく、あくまで教師たちが喜ぶ行動を「自主的」にやることに結果的になってしまっている。
それでは、どうすれば良かったのか? 例えば、避難訓練で声かけするとしたら、せめて「急いで」と冷静に言う。卒業式の練習では「ちょっとおかしかったかな? でも、これぐらい元気よく返事をすることをお勧めするよ」と答えることができるであろう。
3つの目の危うさは吊し上げをするスケープゴートである。
音楽会のシーン。私は胸が張り裂けそうな思いになり、映画を見ている時逃げたい気持ちになった。
と同時に、これは俳優たちが演技したフィクションではなく、実在する人物たちが実際にやり取りしたドキュメンタリーだったと我に返ると、やるせなさも感じた。
一般社会の職場で、これをやったら明らかなモラルハラスメントで、一発アウトである。
「練習しないとこうなるぞ」という他の生徒への裏メッセージが忍ばせられたやり取りであった。
しかし教師に悪意はないようである。教師たち自身も自分たちの教育をどうすればいいのか、これでいいのか、葛藤を抱いているシーンが随所にあったのである。
もしも生徒に演奏する能力や2重とびをする能力が足りなくて、練習しても上達しなかったら、どうなっていたのか? 決して美談にはならない。
教師の多くが(というか、あの学校の教師だけでなく、そもそも教育のあり方や子育てをしている親も含む)、「がんばること」と「できること」を分けて考えておらず、がんばればできると思い込んでいる。ここに根本的な問題がある。
走るのが速い人も遅い人もいるのと同じように、人のさまざまな能力には歴然とした遺伝的な差がグラデーションのようにある。
つまり、人によって必要な練習の量は違う。
練習してもできない人もいる(私がそうだった)。練習しなくてもできる人もいる。
何より練習を一律に強要しないことがよいより教育のあり方では、と考えさせられたシーンであった。
練習を全然しなくて、さらに演奏が全然できないなら、その生徒は担当学期から外れてもらえばいいだけの話である。なぜなら、演奏ができなかったとしたら、それは生徒の責任ではなく、選んだ大人の責任だからである。
ここで、再度誤解がないようにしたいのは、これまで取り上げた教師たちの指導方法には改善点が多々あるが、教師個人は批判されるべきとは思わない。
なぜなら、実は生徒たちだけでなく教師たちもまた、この日本の危うい教育文化から抜け出せない学校という職場環境に身を置いているからである。
伝統という名の呪縛に苦しんでいるのは生徒だけではないのである。
ブラックボックスだった学校教育に切り込んだ本作は、非常に示唆に富む内容であった。
教育ホラー映画の感想
某国立大学の教育学部の学生です。
友人から、教育ホラー映画と聞いて,一体どんな内容なのだろうかと疑問に思いましたが,確かにホラー映画だったと 見終わって思いました。
・オーディションで 1 人しか選ばれないということは,選ばれなかった人はダメだと示しているようなものであり,「緊張しないためには?→いっぱい練習して自信を持つことが大切!」という場面があったが,「緊張している人=練習不足」ということを非言語的に暗示していて,頑張って練習しても緊張する子はいるので,子どもたちの自尊心が傷つくと感じた。競争・実力主義を徹底して,その子どもの背景を考えず,学校でその子がどれだけできるかしか見ていないことは残酷だと思う。子どもによって,多様な個性・生活スタイル・家庭環境など様々な事情がある中で,同じ指導・同じ尺度で測って,できないことを責めるのはおかしいと感じる。
・男性の先生がシンバルの女の子を,きつい言葉で刺すように問い詰めている場面は,脅していじめているように感じて,かわいそうすぎて,見ていていたたまれなくなった。みんなの前で見せしめのように,「みんなは何で楽譜がなくてできるの?→練習したから」と言わせる場面は,「先生とリズムを間違えなかったみんな vs リズムを間違えたシンバルの女の子」という構図を作り出しており,みんなに合わせて正しいことをせずに,間違ったことをしたら,周りに迷惑がかかり,締め出されるのだという恐怖感を子どもたちに植え付けてしまう指導だと感じた。このような価値観が学校教育によって,子どもたちに内在化されると,他人のミスを自己責任として責め立てる不寛容な人であふれた社会となり,生きづらさに繋がり,最悪の場合,自死を招きかねないと感じた。また,誰もが個性を持って生まれてきており,みんな違うからこそ,補い合って社会が回っていくのだから,やりたいことをやって,お互いに尊重し合えるのが理想だが,このような指導の下で育った場合,周りの目を気にして自分がやりたいと思ったことに自由に挑戦することが怖くなってしまうのではないかと考えた。主体性を育む教育が必要だと言われているが,主体性とはかけ離れていると感じる。あれもだめ,これもだめ,列を乱さずちゃんとしなさい,問題を起こすなと,自分の個性と意見を出してありのままにふるまうことを否定され,自分らしさを封印して育ってきた子どもたちには,本音と建て前という2面性が育まれるだろうと感じる。自分を守る手段として,「こうやって振舞っておけば怒られない」という方法を習得することはできても,真の心のワクワクや,もっといろんなことを知って,経験して生きていきたいというエネルギーは枯渇していくと考える。学校でも家庭でも,大人に叱られて,否定されてきた子どもは,どこで本当の自分を出せばいいのか?多忙な先生や親の心の余裕のなさは,「子どもを脅して自分の思い通りに管理しようとする」という接し方に繋がり,結果として,子どもたちがどんどん生きづらくなっていくと鳥越千寛思う。そのような環境では,自分が自分でいていい感覚,他者に共感する力,他者を思いやる優しさなど,人間としての豊かな心は育まれず,無気力になってしまうと感じる。
・男性の先生は,演奏を成功させようとしすぎており,「子どもたちが音楽を奏でる過程を楽しむことで,感性を育む」という視点が欠けていると感じた。正直,演奏が下手でも,子どもたちが生き生き演奏する楽しさを学ぶ方が重要なのではないかと考えた。身勝手な「先生は,信じているからね」という言葉は本当に怖いし,「練習に来ない人は心をそろえることを壊しています」「こんな人が代表でいいのですか?」「オーディションに受かったから終わりなのですか?」というような,脅して圧をかける指導方法では,子どもたちは恐怖とプレッシャーで萎縮してしまうと感じた。私は,学校教育は,「躓いた時の立ち直り方」や,「人に頼り頼られ,協力して生きていくこと」を学ぶためにあるのだと考えておいるため,失敗を経験してなんぼだと思う。恐怖で支配するのではなく,頑張って練習する意味を子どもたちに問いかけて考えさせ,合意の上で進める方が,子どもたちの生きる力を育むことに繋がるため大事だと感じる。
・女の子の気持ちを言語化して,安心させるような女性の先生のフォローがあったことがせめてもの救いだと感じた。女性の先生や ,大太鼓の子をはじめとする優しいクラスメイトがいなかったら,女の子は学校自体が怖くなり,不登校になっていた可能性もあると考えた。(先生同士が意図して怖い役割と優しい役割を分担しているのかはわからないが,そこまで追い詰める必要はないと感じた。)
・先生は,人数の多いクラスを 1 人でまとめて管理していくために,「先生からの指示が全部正しい」というように生徒に対して示すが,「それは誰が決めた正しさなのか,正しさなんて 1つじゃないよな~」と顧みる感性を持っていてほしいし,自分の中の常識に当てはまらない子どもがいたとしても,その子どもの考え方や背景に耳を傾け,対話して共に考えるという心の余裕をもてるような労働環境の改善が必要だと思う。自らの信念を疑わす,がむしゃらに頑張っている先生こそ,視野狭窄に陥る危険性があるのかもしれない。先生自身が頑張っているからこそ, 「努力=素晴らしい,みんなも努力するべき」という価値観を,子どもに対して押し付けてしまうのかもしれない。生徒が起こした問題と思われる行動は,問題ではなく,生徒からの SOS かもしれないという視点や,生徒が成長していくきっかけとなるという視点が持てるような,子ども 1 人 1 人と向き合える労働環境の改善が必要不可欠だと考える。
・子どもにとって「学校という世界は全てである」といっても過言ではないほど,学校で先生から教わること,人間関係などは,人格形成に大きな影響を持つと感じる。「学校での常識が,生きる指針となり,社会の常識となっていく」と考えると,やはり教育の持つ鳥越千寛力はとても大きく,教育が変われば社会が変わるのではないかと考える。今のままではやはり何かおかしいと感じるし(たくさん真面目に働く人を育てて,経済を発展させるための教育になっているかも) ,そのおかしさに気づいていない人,自分も含めてだが,気づいていても従っている人が多いのかもしれない。だから何か変えたいと思う。
不登校の現役中3が感じた「本作に仕込まれた二重構造」 ※映画鑑賞後に読むと10倍面白い
※タイトルにもあるとおり、先に一度映画を鑑賞し、ご自身の感想を持ってから読むことを強くお勧めします。鑑賞前に読むと、映画を純粋に楽しめなくなるかもしれません。
-----
他のレビューはおそらく大人の視点から書かれているが、私は今まさに義務教育を受けている年齢、それも不登校の立場からのレビューだ。
結論から言えば、この映画は立場によって全く異なる感想を抱かせる"二重構造"を持つ作品である。
ホームページでは小学校のことがすごくポジティブに書かれていた。
「世界各国で大反響!」「日本の教育も悪くない」とか。
映画を見た外国人が小学校の教育を賞賛しているコメントをアピールしていた。
だから、さぞかし「日本の小学校っていいな」って思える映画なのだろう、と思い、鑑賞を楽しみにしていた。
だが、実際は全く違った。
むしろ、鑑賞後に真っ先に浮かんできた感想は「教育って難しいな」ってこと。
予想通り、鑑賞中は何度も泣いた。泣いた場面と理由は様々で「先生が苦労し試行錯誤している」「1年生なのに責められて可哀想」「この子、成長してるなあ」とか。
泣いたけれども、小学校に対して肯定的な意見は持てなかったし、単なる「感動的な映画」で片づけられるものでもなかった。
私は中学生の初めから不登校になったが、小学校は通いきった。
その上で「1年生ってこんなに厳しかったかな?」って思った。
少なくとも、これが「平均的な現代の小学校」とは思わない方がいいかもしれない。
特に印象に残ったのは、1年生が新1年生を歓迎するために楽器を演奏することになった場面。
楽器が全然できなかった女子児童1人を先生が責め、他の児童に
「なんでみんなはできるの?」→他の児童「きちんと練習してるからです」
「オーディションに受かったらそれで終わり?」
的なことを言ってとにかく泣かされていた。胸が痛くなった。
その後無事に楽器を演奏できて、先生に褒められる、って流れなんだけど、さすがにこれは気持ち悪くなった...。
いじめの原因を作っているような。というか、他の児童を引き合いに出して「きちんと練習してるからです」って言わせるのって、"先生公認のいじめそのもの"な気がする。
繰り返しになるが、この部分はかなり心に残った。
「この子、可哀想だな」と感じ、まるで自分が責められているかのように、ここでめちゃくちゃ泣いた。
ただ、ここまでではなくても、私の小学校でも公開処刑が何度もあったことは事実。
小中学校の悪いところってまさにそれで、なんでも「集団責任」「公開処刑」の傾向が強すぎる。
集団のミスならまだしも、個人のミスなら、あとで呼び出して1対1で叱ればいいだけなのに。
あの女子児童や私たち日本人の多くが経験した"洗脳"はこうだ。
①公の場で自分1人だけ叱られた児童は、精神的ダメージを受ける
②自己肯定感がすっごく下がる
③その後、小さな成功や褒められることで精神的な報酬を得る
④それにより、叱られたこと自体を「自分が悪かったから」と納得するようになる
⑤結果的に、教育システム(または権威者)への従属意識が強まる
これは日本の教育現場で多用されているが、学校に限らず社会でも日常的に行われている手法だと思う。
そう、この場面も、"社会の縮図の一部"として機能していたのだ。
実は私も、小学5・6年でこの手法を多用する先生に当たった。
自己肯定感は下がり続けたが、小さなことで褒められたのでその先生を好きになった。最初は「こんなことで怒るの?」と思っていたが、次第に納得し、自分の心の中でさえ反抗しないようになっていった。ーーそう、これが「洗脳」だ。
なんとか小学校は乗り越えたが、中学校に入りさらに自己肯定感が下がり、耐えられず不登校になった。そのとき、小学校の日々が"洗脳"だったことに気づいた。
もし中学で不登校になっていなければ、洗脳には気づかないままだっただろう。
ただ、今の教師に1対1で向き合って叱る時間なんてないのかもしれない。見せしめ的な意味合いもあるのだろう。その根底には、教師不足もあるのではないだろうか?
だから、各々の教師のやり方だけが悪い、とも言い切れないのがまた複雑である。
もちろん、「叱られるようなことをする自分が悪い」と言えばそうかもしれない。叱られることを最初からしなければいいのかもしれない。環境のせいにしてはいけないのかもしれないし、実際私は自分も悪かったとも思っている。
でも、この女子児童が叱られているところを、当事者ではなく第三者の視点から見て、確信した。
「それでも、こんな叱り方は間違っているのではないか」と。
むしろ、私はこの映画を観て改めて「中学生で不登校になってよかった」とも思ってしまった。小中学校のつらい日々を思い出してしまったからだ。
ーーーーーーーーーーー
映画の意図について考察
ーーーーーーーーーーー
この映画では細かいところで児童が先生に注意される様子が度々見られる。
監督は、あえて"窮屈に感じる日本教育らしい場面"を多く選んだのかもしれない。
他にも印象に残ったシーンはある。
「ふざける1年生の児童に児童同士で注意しあうシーン」
「運動会の縄跳びがうまく跳べない6年生の児童に、ペアの子が指摘するシーン」
これらのシーンも、児童が日本式教育を施され、日本人として仕上がっていることの象徴だ。
このような「児童同士の指導」をするように仕向ける教育は、言い換えれば「同年代の子供同士が集団内の規律を守る役割を担わせる」ということ。
700時間の撮影の中であえてこれらのシーンをカットせず入れたのは、「日本的な集団の在り方」を描こうとしたのだろう。もちろんそこには賛否両論あって当然だ。
この映画は、日本社会や保護者にとっても日本の教育を再考できるいい機会になると思う。
最初に"二重構造"と言ったのはまさにこれだ。
外国人から見れば、自分の国の教育の悪いところを埋めているように見えて「日本の教育は素晴らしいな」と思うのかもしれない。
だが、日本人から見れば、日本の教育について再考し、賛否両論を巻き起こす"起爆剤"となるのだ。私や他のレビューにあるように。
もしかすると、この映画は最初からそのような狙いがあったのかもしれない。
山崎エマ監督は中高ではインターナショナルスクールも経験している立場だ。
ホームページにもこう書かれている。
「いま、小学校を知ることは、未来の日本を考えること」
つまり、日本人の鑑賞者に対する、監督の本当の狙いは「未来の日本社会のために、日本人に教育の在り方を考えさせること」だったのではないだろうか。
もしそうなら、このレビューサイトで私を含めた多くの日本人の間で賛否両論を巻き起こしている時点で、その狙いは一部成功したと言えるだろう。
かくいう私も、「教育は何が正解なのか?」は分からない。
教師不足もあり、教育のリソースには限りがある。また、日本社会で生きていくためには、こうした価値観を均等に植え付けることが必要なのではないか、という考え方もある。
総じて「教育って難しいな」という結論に至ったのだ。
「学校教育の在り方」「日本人とはなにか」について改めて考えさせられる、ある意味での傑作であった。
世田谷区教育員会によるプロパガンダ?
私は1980年代に世田谷区の公立小に通っていました。(この学校ではありません)
それは時代もあったのかもしれませんが、高圧的な教師と伝統を守ることに縛られた学校生活で、決して良い思い出ではありません。
そして、今は都内の別の場所で小学校高学年の子供を育てています。
その目線からのレビューであることを最初にお断りさせてください。
(以下、否定的なレビューになりますので、この映画で感動した方はお読みにならないことをおすすめします)
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
子供の学校生活を見ていて、令和の小学校は私の時代よりだいぶ自由になったと思っていたのですが世田谷区においては未だに時代錯誤な管理教育をしていた!というのが一番の驚きです。
序盤にある、入学したばかりの1年生がランドセルを小さなロッカーに無理矢理押し込み、綺麗に並んだショットを見て嫌な予感。これは、すべての生徒を規格内におさめます、という痛烈な皮肉?
嫌な予感は当たり、生徒による下駄箱チェック、お互いに注意し合う様子、1年生の担任がクネクネ歩いてる男子生徒に向かって「普通に歩いて」(普通に、って今時NGでは?)と声かけするシーンなど、気持ち悪いほどの相互監視、教師が管理するシーンが続きます。
はいっ、と大きな声でまっすぐ手を上げてお返事する規格内の子供が礼賛される世界。
運動会の縄跳びがうまく跳べない生徒に、ペアの子が指摘するシーンを見て胸が痛くなりましたが、さらに胸糞悪いのが、合奏でシンバルがうまく叩けない生徒への教師による指導。
本人はふざけているわけではなく、真剣にやっているのに、あのように吊し上げるのはいかがなものと。詳しくは書きませんが、他の生徒を引き合いに出して叱責する言い方にイラッとしました。
縄跳びの子もシンバルの子も、練習をして苦手を克服し本番は大成功、良かったね、という流れなのですが、それは頑張れる「規格内」の子だから美談になったのであって、そうでない子ならどうなったのだろうと。
どうにも、先生がたの指導が規格内に生徒を納めることをやっきになっていて、しかも自発的に生徒が規格内に沿わせるように仕向けているように感じたのが一番の気持ち悪さです。
朝6時前に自主的に出勤して準備する6年生の教師「いつか報われるかなと思って」…って、働き方改革が浸透しつつある現代において、美談としてあのシーンを入れているなら大問題かと。
まあ、大なり小なり日本の公立小学校は似たような教育をしているとは思いますが、ここまで管理型なのは今時珍しいし、このやり方を礼賛するのはとても危険だと思います。
おそらく世田谷区の閑静な住宅街で、収入に余裕があり教育意識が高いご家庭が多いからあの教育が成り立つんですよね。
(入学前に家庭でお盆に載せた給食を運ぶ練習をしたり、母親が子供のオンライン授業を横ではりついて見守るシーンを見て)
私が今あの地域で子育てしたら子供は不登校になってるだろうし、私は学校にクレームを入れまくってモンペ扱い必至だな、との想像が頭をよぎりました…
ちなみに、劇場では時折感動のすすり泣きが。
自分がおかしいのかしら?と思って、みんなの学校、でこの小学校のレビューをみたら、自分と似たような理由で保護者の評価が低く、安心しました。
完全に蛇足になりますが、昔から世田谷区は教育委員会が強権的な保守的な土地柄で、教師は委員会に絶対服従、親への圧力も強いです。
監督は外国人目線(ハーフとのことですが)で純粋に日本の小学校の素晴らしさを伝えるためにこのドキュメンタリーを撮影したのかもしれませんが、もう少しリベラルな地域の小学校を選べなかったのかな?と思います。
世田谷区教育委員会のプロパガンダに利用されるのだとしたら、非常に残念です。
学校と教育委員会の勇気は称えたい
どんな内容でも、肯定する人がいれば批判する人もいるのに、学校教育の一部ではあるが公開する学校と世田谷区教育委員会の勇気を称えたい。坊主の先生が児童に「殻を破れ」と言って、ダチョウの卵?の殻をおでこで割り、出血したのはさすがにやり過ぎと思ったが、殻を破りたかったのは、その先生自身であることは後で分かる。先生も正解が分からない中、もがいている。最後に我が子と思われる幼児が出てくることから、朝早く出勤して仕事をして、夕方は早く退勤して子供を保育園に迎えに行くのだろう。1日に24時間じゃ足りない、他人の子供のために仕事をして、我が子には十分なことが出来ないと思っている教員は、たくさんいる。そういう教員に、日本の教育は支えられている。
1年生のための合奏の練習で、ミスばかりする児童を叱るシーンで、初めは厳しく指導し、励まして、出来たら誉めるというのは昔の学校で良くあった。いくら子供が喜び、成長したとしても、私はこういう指導は好きではない。はじめから個別指導を丁寧にしてほしい。放送委員会の児童が二人しか出てこないが、この規模の学校なら20人以上の委員がいるはず。他の委員会も活動しているが、あまり紹介されない。挨拶運動ぐらいか。
この映画は、日本の小学校を外国の人や保護者に紹介するのにはよいが、これが全ての小学校で同じように行われているわけではないし、コロナ後はますます多様化しているはずである。また、特別活動を日本の教育の特徴として、映画を製作しているが、もっと特色のある特別活動をしている学校は他にあるし、特別活動より特徴的なのは教科指導の方ではないだろうか。
見た人に勘違いしてほしくないのは、学校も組織で仕事をしているのであり、教員が全て自分の考えでやっているのではなく、校長の学校経営方針のもとで仕事をしているということ。校長が何度か画面に登場するが、本当は見えないところで教員に指導をしているのである。頭で卵を割ることは、さすがに指示も指導もしていないだろうけど。
【”規律と責任を教える小さな社会。”今作は、コロナ禍の中で学ぶ小学生達と、彼らに真摯な姿勢で様々な事を教える教師達の姿から学ぶこと多き、且つ涙腺が緩むドキュメンタリー映画の逸品である。】
ー 今作はコロナ禍の中、ある小学校の一年生と六年生と彼らを教える教師たちの一年間を追った一切ナレーション無き、ドキュメンタリー作品である。-
■今作では、一年生では小さな可愛い男の子と女の子、六年生では放送係の男の子と教師たちに焦点が当てられているが、基本的には小学校の行事を含めた全体が映されている。
そして、個人的には一切ナレーションが入っていない事が、奏功していると思った作品でもある。
◆感想
・4月。初々しい小学一年生が入学して来る。希望と不安をないまぜにした表情で教室で、初めて先生に名前を呼ばれ、”ハイ!”と元気よく返事する男の子や、小さな声で恥ずかしそうに答える子もいる。
だが、彼らを新六年生が、しっかりと面倒を見て上げるのである。
・今作では授業風景よりも”特別活動”に焦点を当てている。
1.教室内の清掃
2.給食の配膳
3.各係を決めるシーン
4.下駄箱への靴の入れ方のチェック
5.校内放送
6.運動会の予行演習
7.新一年生を迎えるための演奏隊のメンバー決めからの演奏シーン etc.
・2.給食の配膳
一年生が配膳をする中で、後ろを男の子が走ったためにおかずの入ったお皿を割ってしまうシーン。ここでも、しょげる生徒達に女の先生は優しく”配膳をしている時は気を付けようね。”と告げるのである。声は、決して荒げない。
・3.各係を決めるシーン
男の子が図書係を希望するも、級友達の投票で成れずにべそをかいている所に、選ばれた優しき女の子が来て係を譲ってあげるシーン。
女の先生は男の子に優しく”しっかりやろうね。”と声を掛けて上げるのである。彼はこの出来事で人の優しさと、”自分に与えられた責任を果たさなければ。”と思ったことだろう。
・4.下駄箱への靴の入れ方のチェック
風紀委員らしい子供達が、靴の入れ方をチェックする。このシーンは個人的には余り好きではない。そして校長先生が先生方に言う言葉。”任せるという事は、両刃の刃です・・。”
・5.校内放送
六年生の放送係の男の子と女の子が二人だけで、朝の放送をするシーン。とてもしっかりしているし、二人とも相手を信頼している。先生は一切映らない。全てを任されている事が分かる。
・6.運動会の予行演習
六年生の放送係の男の子が団体演技の練習中に、何度も縄跳びが引っかかってしまう。すると彼は自宅で縄跳びの練習を頑張って独りでするのである。
そして、本番では彼はミスなく演技を終えるのである。責任感の強い男の子なんだなあ。
■沁みたシーン幾つか
1.新一年生を迎えるための演奏隊のメンバー決めから演奏シーン
一人の女の子が大太鼓を希望するも、先生に指名されずにべそをかくがシンバルに選ばれて大喜び。だが、彼女は練習の時に何度も叩くタイミングを間違えて、男の先生からキビシク注意される。”選ばれて終わりではないよ。練習はしましたか?”彼女は何も答えられずにボロボロと服が濡れる程に涙を流すのである。観ていて”もう、許してあげて”と思うが、男の先生の叱り方は、感情的ではなく言葉遣いも丁寧である。
基本的に、この学校の先生たちは厳しいが、言葉遣いは丁寧であり、決して感情的にはならない。とても大切な事である。子供は先生のそういう部分には、敏感だろうし女の子も先生の指摘が合っているから、黙って大粒の涙を流すのだろう。
だが、そんな女の子には、女の先生が”間違えたら、先生も一緒に叱られてあげるから・・。”と言って、尻込みしていた女の子を練習場に出して上げるのである。
そして、本番。女の子はミスなく演奏を終えると、男の先生はキチンとそれを観ていて、優しい言葉で褒めてあげるのである。女の子の誇らしげで嬉しそうな顔。彼女も又、成長したんだよね。
2.男性教師二人の姿
1)一人の坊主頭の先生は、厳しい。けれども劇中で彼自身も”厳しいのは分かっているけれども、あの子たちの事を考えると、厳しく言ってしまうんですよ。”と言いながら何か悩んでいる様子である。因みにこの先生はいつも朝早く一番に学校に来て、職員室で朝ご飯を食べている。真面目な先生なんだろうなあ。
そして、彼は六年生の卒業式の時の挨拶で”中学校に行ったら、もっと色んな事が有るだろうけれども、ブレないで下さい。”と立派な挨拶をするのである。だが、全てが終わって皆がいる職員室で、皆の前で”悩んでいたんです。もう辞めようかな、と・・。けれども辞めなくて良かったです。”と涙を流すのである。このシーンは沁みたなあ。矢張り良い先生である。そして、この先生は新学期に三年生の担任として紹介されるのだが、その顔は自信に満ちているのである。
ー 先生自身も生徒達と真剣に向き合い、一年間教え切った事で、成長するんだなあ。-
2)もう一人のイケメン先生。卒業式の練習の時に生徒達が喋っていた時に、真剣に怒るのである。だが、この先生は卒業式の生徒への挨拶の時に、涙が込み上げて、最初は声が出ないのである。だが、涙を堪えて言った”先生は、皆が好きだから怒ったんだよ・・。”と言う言葉も沁みたなあ。
当然、生徒達は誰一人無駄口を叩くことなく、先生の顔をしっかりと見ているのである。
■そして、季節は巡って、桜咲く四月。
新一年生だった男の子の表情は、あどけなさを残すも、一年前の幼さはない。しっかりとしたお兄さんの顔をしているのである。
それは、他の新2年生も同じなのである。
<今作はコロナ禍の中で学ぶ小学生達と、彼らに真摯な姿勢で様々な事を教える教師達の姿から学ぶこと多き、且つ数々のシーンで涙腺が緩むドキュメンタリー映画の逸品なのである。>
教師も子どもも平凡な日常を頑張り、成長していく姿
序盤は、6年生が整然と統制の取れた行動を取っていて不気味だったが、外れた子どもや教師の姿も描かれ、少し安心した。1年生になって、楽器演奏指導で泣き出す子がいて、他の教師から慰められ、頑張り、2年生になった本番では、立派に発表していた。子ども同士の支え合いの姿もみられた。6年生の代表教師が最後の挨拶で泣き出した。1年生の最後にクラス解散で子どもたちが泣き、慰めていた教師は新学期には他校に異動していて、惜しまれていた。6年生担任だった異色教師は、別の学年の担任となり、新しいスタートを迎えていた。教師も子どもも、平凡な日常を頑張り、成長していく姿をよく捉えていた。NHKドキュメンタリー作品の傑作の一つであろう。
全17件を表示