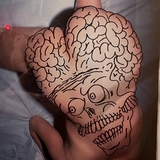小学校 それは小さな社会のレビュー・感想・評価
全89件中、41~60件目を表示
「日本人が作られていく」事を日本人が知る事になるドキュメンタリー
銀座を歩いていたら『小学校〜それは小さな社会〜』が20分後に上映されるのを見つけた。
時間もあったので観てみることに。
「6歳児は世界のどこでも同じようだけれど、12歳になる頃には、日本の子どもは“日本人”になっている。すなわちそれは、小学校が鍵になっているのではないか」との前提の思いがまず面白い。
この作品は世田谷の公立小学校を1年以上かけて撮っている。
1年生の女の子と6年生の男の子を中心に学校生活を丁寧に見せていくドキュメンタリー。この2人がかなりいいキャラクターで2人とも壁にぶつかり乗り越える。この2人を見つけて追えた事がこのドキュメンタリーの成功に繋がっている。
小学校という集団生活の中、給食や掃除などの仕事分担、運動会の全体パフォーマンスや入学式の音楽隊などの集団行動、出来ない事を練習して出来るようになる勤勉さなど「日本人が作られていく」様を当たり前な感じでみせてくれる。
まず日本人が作られていくという感覚が面白い。海外でウケていて、短編にまとめたものは今年度アカデミー賞にノミネートされているらしい。改めて観ていると確かに日本人が作られていく。良くも悪くもだ。
また小学生だけでなくもちろん担任の先生も撮られている。先生の言動も日本人を作ることに寄与している。これも色々と賛否はあるだろう。
未来の日本のためにこの映画を観た多くの大人たちと語り合いたい気分になる映画でした。
#小学校
#それは小さな社会
#映画
子を従順平均に矯正する教員、感動して泣いたって駄目だ。
これが正解と言っているわけではないし、これが全てとも言っていないが、現実の一部であり、映画という形にしたことに意義がある。よく実現できたと思う。
現代の小学校の一面を、ありのままに生に映し出す。
決してこれが正しいと言っているわけでもなく、ある部分は正しく素晴らしいが、その反面問題もある。
現場の教師の皆さんは、本当に真摯に対応されていて尊敬する。
生徒もまた一生懸命。
それを、ナレーションなしで、良くまとめた。
観ながら自然と何度も泣いた。
そして考えさせられる。
良く実現できたと思う。
数知れない許可取り、承認が必要だったかもしれない。
NHKだからできたという面もあると思う。
テレビで十分という声もあるかもしれないが、これを映画と言うパッケージにしたことの意義は大きい。
テレビ・ドキュメンタリー番組では、そうはいかない。
映画として、世界中に流通させることが容易になる。
そのことで、より多くの人々に、伝えられる。
不登校児童が増えるのに納得しました
最近の小学校事情は報道くらいでしか知らない者です。
すごく評判になっているので劇場に向かいました。
これは、世田谷区の小学校だけの雰囲気なのでしょうか。
コロナ下だからでしょうか。まさか全国平均??
自分達の子供の頃とくらべて、あまりに息が詰まるというか、細かくて、
先生も児童も大変だなと思いました。
縄跳びや打楽器が苦手な子が努力して克服するのは感動的ですが、
「できない→くやしい→がんばる→できるようになる」の公式に当てはまらない子にとっては、地獄のような環境ではないでしょうか。
日本で生きる限り、あらゆる組織団体で同調圧力はありますし、
その免疫をつけるのが学校での集団生活なんだなと改めて思いました。
この集団生活になじめず、体調不良を起こす子が、不登校になっていくんだなと、
すとんと納得できました。
高齢化のすすむ日本では、子供達は宝です。
この学校生活についていけない子たちに合った別の道、才能を伸ばして成長させてあげられる道をきちんと用意してこそ「個性」「多様性」を大切にしている国といえるでしょう。
「小学校」を見て、「小学校に行かないで済む方法」の必要性を考えてしまいました。
いずれにせよ、教育についての議論を巻き起こす話題作だという評判どおりの映画でした。
日本人がしっかり見て考えないと!
たくさんの人に観てほしい。
まずは、シネコンでこの地味な作品だと、もしかして貸し切り状態かなと思ってたら、ほぼ満席でびっくり。
観る前からちょっと感動。
新一年生が1年間の成長を経て、次の新入生を迎え入れる様子を丁寧に追った作品だけど。
自分は、縁あって20年以上地元の小学校の入学式・卒業式に出席しているし、ちょいちょい小学校に入るので、ほぼ見慣れた光景だけど、この新1年生の大冒険を知らない(忘れている)大人たちはきっと多いことでしょう。
とにかく「自分はなんでもできる!」という万能感とすべてを父や母に守られていた幼児期をおえて、いきなり『社会』にほうりこまれた6歳の、困惑と挫折が痛いほど伝わってきます。
『競争』なんてもんに直面して、頑張っても一位になれないってことがわかったり、楽器をうまく弾けずに、練習不足だと叱られたり、給食の配膳で失敗してしまったり。
とにかくこの1年は、できるようにならないといけないこと、克服しなければいけないことが次から次にやってくる。
足し算とか漢字とかなんて5%くらいしか占めてないんじゃないかと思うくらい。
逆にいうと、『学校』というものの重要性が浮き彫りになってくる。
さっこん、「通信制高校」なんてもんがもてはやされているけど、人間が集団のなかで形成される能力ってのは、中学生でも高校生でも実は重要なんじゃないか。
その中でしか培われない力ってもんがあるんじゃないか。
なんてことを考えさせてくれる作品でした。
来月も卒業式に呼ばれてるんだけど、6年前に作品中の新1年生と同様、立ったり座ったりで必死だった子たちが、立派な合唱ができるようになり、しっかりとした答辞を言えるようになってるのを見るのはいつも楽しい。
それにしても、「さんぽ」で新一年生が入場し、「旅立ちの日に」で巣立っていくのは全国共通なんですかね?
「日本人の形成」のプロセスがつまびらかにされる
舞台は2021年度の世田谷区立塚戸小学校。新入生の入学前から翌年の入学式までの一年間を追ったドキュメンタリー。主に1年生と6年生に焦点を当てて追いかけていて、6年生は新入生を迎えるところから卒業式まで、1年生は自分たちが入学するところから翌年2年生として新入生を迎えるところまでが描かれている。
ちょうどコロナ禍2年目の年で、マスクやアクリルの仕切り板、そして黙食など、あの時代を象徴するいくつかのアイテムが必然的に含まれることを除けば、おそらく多くの日本人にとっては馴染み深い、誰しもが頭に描くであろう小学校生活が淡々と映し出される。
学習指導と生活指導が並行して行われ、その中で規律や努力、勤勉といった日本社会や日本人を形容するのに頻繁に用いられる資質を6年間で獲得していく様、まさに英語タイトルが示している通り「日本人の形成(The Making of a Japanese)」のプロセスがつまびらかにされている。
まさに日本人の美徳であり、その過程での児童たちや先生方の葛藤や努力の様には胸を打たれ、目頭が熱くなる。おそらく製作者サイドの意図もその日本の良さを世界に知らしめることにあったに違いないと思う。
ただ、一方で、前日に「型を破る」話を観たばかりであるせいか、「子どもたちの主体性を伸ばすために頑張っていきましょう」と職員会議で話していながら、手の挙げ方や靴の揃え方、廊下の歩き方まで、事細かに指導している様を目撃していると、どちらかというと「型にはめる」方向に向かっているのではなかろうかという疑念が自分の中で払拭できなくなっている。社会マナーの指導の意義も理解できるだけに、どの点をどう評価するのか、観客一人ひとりの観点が問われる気がする。
アカデミー賞獲れるでしょう
米アカデミー賞短編ドキュメンタリー部門にノミネートされた山崎エマ監督の舞台挨拶付きの上映をキネマ旬報シアターで観てきました。監督の当日のお顔も撮ることが出来、投稿も許可いただいたのでFacebookにあげました。
映画は都内の普通の小学校の1年生と6年生とその担任の先生をコロナ禍の1年間撮り続けたドキュメンタリー。しかもナレーションは一切なく生徒や先生の名前をテロップにつけるのみ。1年生は入学から挙手の仕方や廊下の歩き方、掃除や給食当番など基本的な集団生活の規律を学び、6年生は1年生の生活教育の手助けをしたりクラスで何らかの役割りを担う様子を追う、又1年生も6年生それぞれフォーカスを当てた生徒が一生懸命に課題に取り組む日々とそれを支える先生たちのありのままの姿も捉えていく。そして1年生は2年生に、6年生は卒業する。
映画を見ながら、当然遥か昔の小学生の頃を思い出し、私は集団行動も苦手だったし、勉強もダメだったし音楽でも楽器も操れなかったし嫌な記憶ばかりだなぁとか考えてたが、99分のこの小学校での映像を見つめ続けた私は結局、最後は目に涙を溜めていた。
「いま、小学校を知ることは未来の日本を考えること」とのメッセージの通り、この映画は我々が忘れていた日本人のアイデンティティを思い起こさせ、今の日本とこれからの日本を考えるきっかけを与えてくれるんだなと感じました。
アカデミー賞獲得をお祈りしています。
素晴らしい映画でした
見て良かったです。子どもたちの優しさに感動しました。小さい社会で自分の思い通りにならないこともありますが、泣いている子には回りにいる子が声をかけたり、手伝ったりする姿がありました。泣いている子の心の葛藤も垣間見れました。先生たちもそれぞれの強みを生かし働かれていて、大変なお仕事だと感じました。大勢の保護者の方やお子さんが出ていたので一人一人の許可を取るのが大変だったのではと思いました。素敵な作品でした。他の人にもおススメしたいです。
日本の教育の長所を抽出した作品、泣けました~。
出演者は、皆さん素人の方なのでしょうか?
カメラを向けられていることが信じられないくらい、先生方も子どもたちもナチュラルです。
先生方は、子どもたちに寄り添い、基本的にやさしく接しています。
子どもたちも、喧嘩などなく、穏やかです。
1年生のクラスも落ち着いていて、一見私立の小学校なのだろうかと思いました。
さすが世田谷です。
印象に残ったのは、6年生の放送委員の男の子。
運動会の団体種目のために、一生懸命2重飛びの練習をして、当日見事に演じ切ります。
胸アツです。
そういえば、息子たちも縄跳びを結構練習していたなーと思い出しました。
この映画でフォーカスされた子どもたちは、いわゆるいい子たち。
1年生のクラスではいなかったけれど、6年生の方では学校がしんどそうな子も見かけました。
先生方があまりにも子どもたちに一生懸命で、もう少し自分の生活を大切にしてはと感じるほどでした。
6年1組の担任の先生が、「言葉が子どもたちの心に届くように」という想いで、6年生に厳しめの言葉で注意するところは、心に沁みました。
なぜなら、中学校は、小学校よりも先生との距離が遠く、ある程度自立した行動を求められるからです。
反面、1年生の合奏の指導している先生が、練習中に間違えた1年生の女の子を厳しく叱責する場面は、ちょっと引きました。
1年生なら、その子なりに一所懸命することが大事で、失敗したらそこから学べばいいのではと思いました。
ラスト、卒業式は、息子たちのそれを思い出して、涙駄々洩れになりました。
息子たちが合唱した「3月9日」を歌われていたら、号泣していたかもしれません。
そして、新1年生の入学式で、新2年生たちの合奏がうまくいって、また涙。
一生懸命の子どもたちに、幸あれと願いました。
個人主義の欧米から見たら、和を大事にする日本の小学校の様子は、よく見えるかもしれません。
ホントは、両方が合わさって、個人が幸せでありながら全体も満たされる、そんな社会が最高。
学校教育のアップデートは、今こそ必要ですね、きっと。
それは小さな日本⁈
やや(海外視点で)わかりにくい点はあろうがおすすめ枠か
今年31本目(合計1,573本目/今月(2025年1月度)31本目)。
この映画それ自体は日本の映画で日本の小学校の、新1年生と6年生の1年の生活、そして新2年生と中学生へ(=小学校の卒業式まで)を1年扱ったドキュメンタリー映画の扱いですが、公式サイト等にあるように海外で見ることが相当考慮されていて、エンディングロールにはその旨のクレジット等や関係者の名前もあがります。
公立小学校ということなので、昔も今も変わっていない部分もあれば、映画で扱われているのが2021年以降という事情もあるのでコロナ事情によるいわゆる自宅学習やタブレット学習といった、やはり公立といっても10年、20年前ではなかったようなことも扱われているので、ここはやはりコロナ事情が(結果的に、一過性のものではありましたが)特殊な部分もあるので、そこを特に強調すると「コロナと小学校の在り方」という別の論点になってしまうのではないかな、といったところです。
気になった点として、ややプライバシー保護が「すぎるかな」といった点があります。明確に名前が出てくる登場人物(児童)以外の児童は名札などにうっすらモザイク(ぼかし)がかかっていますし、登場人物としてあげられる児童数名も全て「ひらがな」の名前での紹介です(もちろん、本名がひらがなの子もいましょうが、全員ということは考えにくい)。
こうした事情から、一部後半からわかりにくい点があり、そこがどうかなといったところです。
採点に関しては以下まで考慮しています。
-----------------------------
(減点0.2/一部の理解がわかりにくい部分がある)
上記のプライバシー保護の観点で名札などにうっすらぼかしがある点を書きましたが、この関係で、映画後半から終わりかけに登場する、当時1年生(映画内では、2年生となる直前で1年生を迎える会の話に登場する)の登場人物の一人、「あやめちゃん」の部分(その新1年生を迎えるための音楽会に参加するという趣旨の部分)で、誰が誰かわかりにくい部分があります。
※ 女児の名前として「あやめ」は時々みますが、海外では当然これら当然追加字幕はつくのだろうと思いますが、 Japanese Iris なのでしょうか?(いわゆる「あやめ」と「アイリス」は実際には同じものだが、それは花屋等では当然のことではあっても、一般には別扱いされるため)
(減点0.2/足し算の交換法則についてやや配慮が足りない)
1年生では1桁までの繰り上がりがある、1桁どうしの加法を学習します。その中で「11が答えになる計算式を色々探す」というカリキュラムの中で「2+9のカードがなくなった」という趣旨の話が登場します。もちろん答えはそれだけではなく(例えば3+8も答えになる)、「答えが11になるカードを全部探そう」という趣旨のものです。
ただ、答えが11になる点においては、2+9も9+2も同じであり、この点の話が出てこないので、この点やや配慮を欠くかなという気がしました(加法の交換法則ほかは3年以降の扱いですが、多少なりとも理系的な知識・教養がある子なら、「足し算について、交換法則(に相当するもの)が成り立つ」ということは推知できるため、それらに対する配慮が足りないわけです。
※ ただ、この「加法について交換法則が成り立つ」のは大学以降も含めて常にそうですが(代数上の環では乗法の交換法則は保証されない(それも成り立つのは可換環)ものの、加法の交換法則は常に保証される)、例えば文章題として「初めに9人の子供がいました。遊び友達に2人加わりました。合計で何人ですか?式と一緒に答えましょう」という問題なら、9+2を認めるのは当然だが、2+9を認めるかどうかは見解が分かれうる(このあたりが乗法(掛け算)で厳密にうるさく論争になっているのが、いわゆる「掛け算の教え方論争」という、実際にツイッター(現、X)等でしばしば問題になることがら)ところです。
希望に溢れていた
採点4.3
何とか観に行くことができました。
まず映像が美しくすごく柔らかいです。何だか陽だまりのよう。
カメラは子どもの目線、随所に差し込まれるアップのカット、何とも懐かしい気持ちになりました。
観ていて思うのが「そういえば子どもの時こんな感じだったなぁ」といった懐かしい気持ち。
そして自分の子らが今こんな生活に触れているんだなという、知らない時間を見たような新鮮な気持ち。
またコロナ禍での子らの学校生活はとても興味深かったです。
保育園も小学校もとても窮屈そうで、やっぱりこんな感じで過ごしていたんですね。
運動会や遠足がなくなったり、あってもすごく制限されていて、胸が痛かったの覚えています。
また、子ども達も大きくなった時観たら「そうだったそうだった!」ってなるんでしょうね。
また大人になってこの景色を見ると、少しずつ感じる違和感が散らばっていたりもします。
それは教育方法。時間通りの行動、机の並び、給食の食べ方、靴箱検査など、皆が一つに纏まるを一番とする先生の言葉、その世界は今見るとやはり少し気になるところがありました。
ピークに持ってきたシンバルの女の子は、演奏が上手くできなかった事を他の生徒の前で叱責されていました。これはちょっとなぁ。
そして校外の教授による講義で「協調性の高さは世界に誇れることであるが、それは諸刃の剣でもある」といった趣旨の言葉。これにはドキッとさせらレました。
このシーンを敢えて入れたのは、それを気づかせる意図があったのでしょうね。
少しネガティブな書き方になりましたが、別に全部が悪いとも思わないのです。
そうした中で磨かれた心や技術は、実際日本が世界に誇れる部分だとも思っています。
圧倒的に世界一の正確さを誇る鉄道など、まさにその表れだと思うんですよね。
それに怒られていたシンバルの女の子。彼女はクラスメイトに励まされ、練習の末無事習得していました。
皆に支えられ壁をこえて、その時の彼女の笑顔は素晴らしかったんですよ。
このドキュメントは学校生徒の一年間がうつされているのですが、メインは入学してから2年生になるまでの子ども達。シンバルの女の子たちですね。
一年を通したその成長には本当驚かされるんです。
まるで自分の子を見ているようで、ラストのカットからエンドロールはずっと涙が出ていました。
原題は「The Making of a Japanese」。
確かに作り上げる教育には考えさせられる部分もあるでしょう。
でもそれよりも、映る子ども達の姿は本当に希望に溢れて見えました。
ありのままの、素晴らしいドキュメンタリー作品でした。
こうして「日本人」になる…?
まこちゃんの2+9のカードがない!
すっかり大人になってしまったわが子らの小学校入学時を思い出して初っ端からじんわり。ピカピカの1年生と6年生を並べて、6年間で日本人として「できあがって」いくのもすごいが、生物としての細胞分裂度合いにも単純に驚く。
教室での黙食や修学旅行で全員前を向いた御膳の配置などコロナ禍で学校は大変だったとは思うのだが、若い先生たちの規律に向けての力の入りっぷりを観ていると、戦前の軍国主義教育への反省を國學院の教授が講演しているほどなので、やはり下駄箱の上履き並べ方チェックとか、なんでそんなことまでやるのか?と思う。J・K・シモンズじゃないんだから、シンバルできないあやねちゃんを泣くまで責めんでも…。
教育水準が高いと言われるフィンランドで本作が拡大公開されるほど日本の教育は(いろんな意味で)興味深いのかもしれないが、「日本人の作り方」という英副題になるほどと思いつつ、小学校の頃はまじめに教師の言うことをよく聞いていた自分がいつから捻くれた人間になったのかと考えると、日本人を作り出す社会の空気が初等教育の現場に滲み出ているという気もする。
とはいえ、ナチュラルな子どもらの姿を99分間眺めるだけで2024年末に微笑ましい気持ちにもなったのはたしか。
とても作為的な作品
ドキュメンタリー「ある小学校の一年間~コロナ禍編~」
世田谷区のとある小学校の1年間を映した作品。
ただ、時期的にコロナ禍という要素が多分に混合している点にはご留意。“コロナ禍の”小学校のドキュメンタリー、という感じ。
意図してこの期間を選んだのかたまたま時期が被ってしまった形なのか分からないが、これはこれでとても貴重な記録映像だと思う。コロナ禍が実際にどう子どもたちに影響しているか、何を犠牲にさせられているかというのを映像として見ることができる。まさに百聞は一見に如かずだなと思う。
余計な演出等はなく、ただ小学校の1年間が順々に、色々と映っていく。99分の中に1年を詰め込んでいるから、余すところは実際沢山あるんだろうけど、観た側の感想としてはそれでも結構余すことなく詰め込まれていた感じがした。一つ一つの尺も丁度よかった。せっかくなのでもう20分くらい長尺で観てみたかった気もするけど、これくらいで丁度よかった感じもする。
「なるほど、そこを叱るのか」とか、「そこまでするか」とか、個人的にも色々感じながら鑑賞した。本作を観て何に驚いたり、感動したり、問題を感じたりするかは千差万別だと思う。
本作のような実態を忠実にとらえて広く提供する存在がなければそもそも俎上に上がる機会もない訳で、記録映像としても、広い議論や関心を喚起する一歩目という意味でも、貴重な作品だと思う。生の学校を撮って映画として公開するというのは相当にハードルの高いことだったんじゃなかろうかと思うので、制作者の方々は勿論、何より作品の成立のために自らが映ることを引き受けてくれた先生や生徒さんには感謝したいし、敬意を表したい。
集団心理
ポスターに書かれている、
THE MAKING OF A JAPANESE
この言葉に強く惹かれ、鑑賞。
『ウィンストン・チャーチル ヒトラーから世界を救った男』や『スキャンダル』で賞を取った特殊メイクのカズ・ヒロさんが言ってたこと…
日本人は日本人ということに拘りすぎて、個人のアイデンティティが確立していない。
大事なのは個人として、どんな存在なのか何をやっているのかということ。
日本人は集団意識が強く、その中で当てはまるように生きている。
周囲の目を気にして、その理由で行動する人が多いことが問題。
日本は威圧されている。どう受け入れられているか、どう見られているか、全部周りの目。
自分の人生であり、周りの人の為に生きているのではない。当てはまろう、じゃなく、どう生きるかが大事。
心が痛いですが、かなり的を射ていると思う。
この作中で少しだけ触れられますが“日本は軍事教育をした国”だと、
そして“世界に誇るべき協調性の高さ”があると、
ただイジメを生む可能性があり“諸刃の剣”だと。
その日本人の集団心理をエグるような尖った内容を期待したけど、普通に小学校に密着したハートフルな内容でした。
でも、面白かった。
鑑賞後、様々なことを考えてしまいました。
ドキュメンタリーとしてとても面白かったです。
一般的な公立小学校の数人の児童・先生をピックアップしながら一年間をカメラを通して見つめてゆくスタイル。
児童も先生もとても自然で、かといってカメラを無いものとするわけでもなく。
カメラも動きを見せるわけでもなく、淡々と撮る、みつめる。
私自身も映画の内容とほぼ変わらない小学生時代を過ごし、自分の子どもを通して小学校とかかわった経験から歩んできた道をもう一度客観的になぞる。
そうすると視えてくるものもあり、小学校教育とは何なのだろうかと、はたしてどこまでが教育でどこからが理想でどこからが抑圧なのだろうかと。
大人の「こういうものだろう」は子どもには通じない。
大人になって振り返ったときに気づけばいいと私も思うこともあります。
しかし今、瞬間、考えることを促されずに指導される子どもたちの協調性とはどこに向かうのか。
日本がとても特殊な小学校スタイルであるがゆえに海外ではとても高評価の作品と伺いました。
掃除、配膳、お当番や委員、運動会に宿泊行事。
いつか社会に出てゆく人間として必要な経験値のファーストステップがここにあるのかもしれない。
1年生の初々しい可愛らしい入学式からの1年間。
びっくりするほど顔つきが変わりしっかり2年生のお顔になっていました。
カメラに映っていないところでも彼らは様々なことを経験し心も頭も体もフル回転だったのだろうと。
先生がたも様々に悩み苦しみ楽しみながら成長されてゆくはずですが、小学校教師の体調不良による離職がとても多い昨今の現状を垣間見せてもらえました。
対しているのが生の人間と言うことだけでも神経を擦り減らすであろうのに、仕事量の多さがまじめで真剣な先生ほど追い詰められてゆくように思えました。
作品に登場している先生方のだれよりも長生きをしている私からすると、その目線から一段おりて様々なものを見渡すと見えないものも見えてくるかもしれないよと感じてしまいました。
冒頭にも書きましたが、ドキュメンタリーとしては良い作品。
ただ、海外の評価と日本の評価では少し違いが出るのではないかとも感じます。
あまりにも日常すぎて。
鑑賞は劇場でなくても十分に良さを味わえると思います。
全89件中、41~60件目を表示