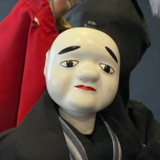小学校 それは小さな社会のレビュー・感想・評価
全106件中、41~60件目を表示
まさにドキュメンタリーという感じ。
NHKの番組をみているかのようなドキュメンタリー。
一年を通して、先生の葛藤や生徒、親の生活を映している。
周囲の観客は先生っぽい人が多い。
隣の人は寝ていたのに、最後は涙ぐんでるという、先生ならではの視点があるらしかった。
こういう教育なんだ
学校教育と子どもの成長
生徒も教師も楽しくなさそうだけど大丈夫?~ブラック教育文化
「外国から見た日本の小学校とは」という視点で、私たちが当たり前に思っていた学校の日常から、学校の内情、生徒と教師の喜怒哀楽にまで迫っている本作。
この映画のいくつかのシーンを通して、日本の学校教育が良さと危うさを同時に孕んでいることが見て取れる。
なお、この映画はドキュメンタリーであり、実在する人物が登場するが、教師個人を批判する意図はまったくない。あくまでその教師たちすら巻き込む文化としての日本の学校教育の危うさをここに書いていきたい。
1つ目の危うさは、周りと同じことをやらせすぎる、同調圧力。例えば、靴箱のシーン。廊下をくねくね歩く生徒に「普通に」と注意するシーン。
同調圧力によって、自分はこうしたいという「自分らしさ」(アイデンティティ)が育まれにくくなる。同調圧力のなかで選ぶ自由も多様性もなく、自分らしさは削がれていく。
皮肉にも、映画の中では、先生たちはたびたび「自分らしさ」という言葉を口にして、その大切さを強調していた。その一方、彼らは「普通に(しろ)」という言葉を使って真逆のことを強いており、その矛盾に気づいていない。教師たちの意味する「自分らしさ」とは、生徒が望んだ多様なものではなく、あくまで教師たちが望む限定されたものなのではないか。
2つ目の危うさは言いなりにさせる構造である。
例えば避難訓練のシーン。「遅い!」と言った時の声のトーンと大きさ。卒業式の生徒たちへの言葉。一般の社会で昨今あまり聞かれることのない内容で一般社会でこれらをしたらハラスメントである。しかし、教師たちも苦しそうである。
避難訓練で、逆に生徒が急いで転びそうになったら、今度は「あわてるな!」と怒鳴ることが予測される。つまり、どっちにしても、何をしても、生徒たちは怒鳴られるのでは。心理学では、これをダブルバインド(板挟み)と呼ぶ。
映画内で撮られた言葉かけは、一見生徒たちの注意を引くわけだが、具体的な改善点を教師が指摘しているわけではない(実は指摘できないのでは)。
けっきょくダブルバインドと同じように、生徒たちはどうしていいかは分からないまま教師の顔色をうかがうばかりになる。これは子育てにおける親子関係でも同じことが起こりやすい。
皮肉にも、映画の中では、教師たちはたびたび「自主性を育む」という言葉を口にして、その大切さを強調していた。そのわりに受け身にさせることばかりをしており、その矛盾に気づいていないのである。教師たちの意味する「自主性」とは、生徒が望む自由な行動ではなく、あくまで教師たちが喜ぶ行動を「自主的」にやることに結果的になってしまっている。
それでは、どうすれば良かったのか? 例えば、避難訓練で声かけするとしたら、せめて「急いで」と冷静に言う。卒業式の練習では「ちょっとおかしかったかな? でも、これぐらい元気よく返事をすることをお勧めするよ」と答えることができるであろう。
3つの目の危うさは吊し上げをするスケープゴートである。
音楽会のシーン。私は胸が張り裂けそうな思いになり、映画を見ている時逃げたい気持ちになった。
と同時に、これは俳優たちが演技したフィクションではなく、実在する人物たちが実際にやり取りしたドキュメンタリーだったと我に返ると、やるせなさも感じた。
一般社会の職場で、これをやったら明らかなモラルハラスメントで、一発アウトである。
「練習しないとこうなるぞ」という他の生徒への裏メッセージが忍ばせられたやり取りであった。
しかし教師に悪意はないようである。教師たち自身も自分たちの教育をどうすればいいのか、これでいいのか、葛藤を抱いているシーンが随所にあったのである。
もしも生徒に演奏する能力や2重とびをする能力が足りなくて、練習しても上達しなかったら、どうなっていたのか? 決して美談にはならない。
教師の多くが(というか、あの学校の教師だけでなく、そもそも教育のあり方や子育てをしている親も含む)、「がんばること」と「できること」を分けて考えておらず、がんばればできると思い込んでいる。ここに根本的な問題がある。
走るのが速い人も遅い人もいるのと同じように、人のさまざまな能力には歴然とした遺伝的な差がグラデーションのようにある。
つまり、人によって必要な練習の量は違う。
練習してもできない人もいる(私がそうだった)。練習しなくてもできる人もいる。
何より練習を一律に強要しないことがよいより教育のあり方では、と考えさせられたシーンであった。
練習を全然しなくて、さらに演奏が全然できないなら、その生徒は担当学期から外れてもらえばいいだけの話である。なぜなら、演奏ができなかったとしたら、それは生徒の責任ではなく、選んだ大人の責任だからである。
ここで、再度誤解がないようにしたいのは、これまで取り上げた教師たちの指導方法には改善点が多々あるが、教師個人は批判されるべきとは思わない。
なぜなら、実は生徒たちだけでなく教師たちもまた、この日本の危うい教育文化から抜け出せない学校という職場環境に身を置いているからである。
伝統という名の呪縛に苦しんでいるのは生徒だけではないのである。
ブラックボックスだった学校教育に切り込んだ本作は、非常に示唆に富む内容であった。
教育ホラー映画の感想
某国立大学の教育学部の学生です。
友人から、教育ホラー映画と聞いて,一体どんな内容なのだろうかと疑問に思いましたが,確かにホラー映画だったと 見終わって思いました。
・オーディションで 1 人しか選ばれないということは,選ばれなかった人はダメだと示しているようなものであり,「緊張しないためには?→いっぱい練習して自信を持つことが大切!」という場面があったが,「緊張している人=練習不足」ということを非言語的に暗示していて,頑張って練習しても緊張する子はいるので,子どもたちの自尊心が傷つくと感じた。競争・実力主義を徹底して,その子どもの背景を考えず,学校でその子がどれだけできるかしか見ていないことは残酷だと思う。子どもによって,多様な個性・生活スタイル・家庭環境など様々な事情がある中で,同じ指導・同じ尺度で測って,できないことを責めるのはおかしいと感じる。
・男性の先生がシンバルの女の子を,きつい言葉で刺すように問い詰めている場面は,脅していじめているように感じて,かわいそうすぎて,見ていていたたまれなくなった。みんなの前で見せしめのように,「みんなは何で楽譜がなくてできるの?→練習したから」と言わせる場面は,「先生とリズムを間違えなかったみんな vs リズムを間違えたシンバルの女の子」という構図を作り出しており,みんなに合わせて正しいことをせずに,間違ったことをしたら,周りに迷惑がかかり,締め出されるのだという恐怖感を子どもたちに植え付けてしまう指導だと感じた。このような価値観が学校教育によって,子どもたちに内在化されると,他人のミスを自己責任として責め立てる不寛容な人であふれた社会となり,生きづらさに繋がり,最悪の場合,自死を招きかねないと感じた。また,誰もが個性を持って生まれてきており,みんな違うからこそ,補い合って社会が回っていくのだから,やりたいことをやって,お互いに尊重し合えるのが理想だが,このような指導の下で育った場合,周りの目を気にして自分がやりたいと思ったことに自由に挑戦することが怖くなってしまうのではないかと考えた。主体性を育む教育が必要だと言われているが,主体性とはかけ離れていると感じる。あれもだめ,これもだめ,列を乱さずちゃんとしなさい,問題を起こすなと,自分の個性と意見を出してありのままにふるまうことを否定され,自分らしさを封印して育ってきた子どもたちには,本音と建て前という2面性が育まれるだろうと感じる。自分を守る手段として,「こうやって振舞っておけば怒られない」という方法を習得することはできても,真の心のワクワクや,もっといろんなことを知って,経験して生きていきたいというエネルギーは枯渇していくと考える。学校でも家庭でも,大人に叱られて,否定されてきた子どもは,どこで本当の自分を出せばいいのか?多忙な先生や親の心の余裕のなさは,「子どもを脅して自分の思い通りに管理しようとする」という接し方に繋がり,結果として,子どもたちがどんどん生きづらくなっていくと鳥越千寛思う。そのような環境では,自分が自分でいていい感覚,他者に共感する力,他者を思いやる優しさなど,人間としての豊かな心は育まれず,無気力になってしまうと感じる。
・男性の先生は,演奏を成功させようとしすぎており,「子どもたちが音楽を奏でる過程を楽しむことで,感性を育む」という視点が欠けていると感じた。正直,演奏が下手でも,子どもたちが生き生き演奏する楽しさを学ぶ方が重要なのではないかと考えた。身勝手な「先生は,信じているからね」という言葉は本当に怖いし,「練習に来ない人は心をそろえることを壊しています」「こんな人が代表でいいのですか?」「オーディションに受かったから終わりなのですか?」というような,脅して圧をかける指導方法では,子どもたちは恐怖とプレッシャーで萎縮してしまうと感じた。私は,学校教育は,「躓いた時の立ち直り方」や,「人に頼り頼られ,協力して生きていくこと」を学ぶためにあるのだと考えておいるため,失敗を経験してなんぼだと思う。恐怖で支配するのではなく,頑張って練習する意味を子どもたちに問いかけて考えさせ,合意の上で進める方が,子どもたちの生きる力を育むことに繋がるため大事だと感じる。
・女の子の気持ちを言語化して,安心させるような女性の先生のフォローがあったことがせめてもの救いだと感じた。女性の先生や ,大太鼓の子をはじめとする優しいクラスメイトがいなかったら,女の子は学校自体が怖くなり,不登校になっていた可能性もあると考えた。(先生同士が意図して怖い役割と優しい役割を分担しているのかはわからないが,そこまで追い詰める必要はないと感じた。)
・先生は,人数の多いクラスを 1 人でまとめて管理していくために,「先生からの指示が全部正しい」というように生徒に対して示すが,「それは誰が決めた正しさなのか,正しさなんて 1つじゃないよな~」と顧みる感性を持っていてほしいし,自分の中の常識に当てはまらない子どもがいたとしても,その子どもの考え方や背景に耳を傾け,対話して共に考えるという心の余裕をもてるような労働環境の改善が必要だと思う。自らの信念を疑わす,がむしゃらに頑張っている先生こそ,視野狭窄に陥る危険性があるのかもしれない。先生自身が頑張っているからこそ, 「努力=素晴らしい,みんなも努力するべき」という価値観を,子どもに対して押し付けてしまうのかもしれない。生徒が起こした問題と思われる行動は,問題ではなく,生徒からの SOS かもしれないという視点や,生徒が成長していくきっかけとなるという視点が持てるような,子ども 1 人 1 人と向き合える労働環境の改善が必要不可欠だと考える。
・子どもにとって「学校という世界は全てである」といっても過言ではないほど,学校で先生から教わること,人間関係などは,人格形成に大きな影響を持つと感じる。「学校での常識が,生きる指針となり,社会の常識となっていく」と考えると,やはり教育の持つ鳥越千寛力はとても大きく,教育が変われば社会が変わるのではないかと考える。今のままではやはり何かおかしいと感じるし(たくさん真面目に働く人を育てて,経済を発展させるための教育になっているかも) ,そのおかしさに気づいていない人,自分も含めてだが,気づいていても従っている人が多いのかもしれない。だから何か変えたいと思う。
原題のほうがあっているかも
小学校に入り成長する子どもたちの姿、コロナ禍での大変な時期の小学校での様子、先生たちの葛藤などドキュメンタリーとして楽しむことができた。日本では多くの人が小学校で体験してきた内容で懐かしくも感じるし、子どもの成長物語もよい。
合奏練習シーンや運動会練習のみんな同じレベルできないといけないプレッシャー、それに耐え良くなろうとして努力する姿は、原題の日本人のつくりかた、のほうがあっている気がした。なぜ日本ではタイトルかえたのかな?先日、メキシコ映画の[型破りな教室]をみて、教育について心震える体験をし感動が強かった分、型にはめる教育をみてしまったという印象。映画の子どもたち、先生たちも素晴らしい。ただ、教育方針が日本ならではの、こうでないといけない、というものなので、観たあと、ややモヤっとした。
日本の小学校をとらえた素晴らしい映画
んー
教師経験があって今は教師を辞めた立場の僕がみた感想。
朝5時過ぎの電車で通勤
職員室での朝ごはん
そして教師としての成長?
頑張る先生
児童たちは1年生は1年生の中での成長
その1年生からの6年生の存在感・・・
ただ
映画の撮影に協力できる学校であるということ
先生のそういうボランティアの中で成り立っている学校
そしてそれが美談として捉えられる日本の状況
児童は努力をして成長していく
当然映画なのでその制作者の意図があってこの作品になることは十分理解できるんですけど。
決して映画の先生の非難ではなく
本来ならばその個人の教師の犠牲がなく
どの先生であっても誰もが
ある程度達成できる学校でなければ・・・
一人の先生ができればいいの範疇はいいのですが
基本的な学校の指導がある先生はできるけど他の先生はできない
そしてできない先生がダメな先生となるのは何か違う気がする
そしてこの映画の中の児童でも同じ事が・・・
映画を見てもらいたいので中身は書きませんが
今の日本の歪みが映画の裏側に見え隠れしてるように
僕は感じました。
確かにだからこそ
タイトルの
小学校 それは小さな社会・・・
良い面はそれでよしとし
そうでない部分も見ていただければなと思いました。
小学校6年間
SNSで見かけて観ようと思ったが、県内では3館しか上映がなく、いちばん近くでも車で1時間の距離。しかも調べたら朝1の回しかない。厳しい。
それでもやはり観てみたく、小学1年生の子を学校へと送り出してから大急ぎで車に乗り込み、通勤ラッシュの道をはらはらしながら走り、しかも未踏の地なので駐車場入口が分からず周辺道路うろうろしてさらにハラハラし、なんとか時間ぴったりにシアターに入れました。
1年生と6年生ってこんなに違うんだなあ。同じ場所で学んでいるのが不思議なくらい、無駄に走り回り地面に寝転んでごろごろしちゃう1年生は100%子供!って感じだし、先生に敬語で話し会釈をする6年生はもう90%くらいは大人だ。
うちの1年生も、こんなふうに6年生に面倒見てもらいながら、学校に慣れていったんだろう。そして今ごろこんなふうに楽しそうに授業を受けて、給食の配膳や清掃も頑張ってるんだろう…などと思いを馳せつつ観ていました。
あと、高校ですが元教員なので、どうしても先生目線で見てしまった。こんなに違う生き物を教える小学校の先生は大変だな。1年生に対しては親のように大きく包みこみ、6年生に対しては背中を叩いて送り出す。子供子供していた頃を知っているからこそ、卒業式の日は感慨ひとしおなのだろう。
他の学年の先生から◯年生さわがしかったねと言われて、すみませんと謝る感じ、職員室あるあるで笑った。修学旅行の夜、生徒が静かになるまで見守らないといけないので薄暗い中で小声で話す感じも、教員あるある。そのあとも反省会とか明日の打合せとかで遅くなるから、修学旅行の引率は4、5時間しか寝れなくてきつかった…と思い出。
小学校を舞台に、児童たちの成長を映しつつ、先生たちの裏舞台もバランスよく扱われていて、面白かったです。
昭和の学校?
シンバルをうまくたたけない子に大きな声で怒鳴り、委縮させ、泣かせる教師。提出物を期 限を守って提出しない子に、「そんな状況では、提出物の多い中学校ではダメだぞ」と威嚇する教師。皆の前で厳しく叱ることが教育と思っているのかもしれないが、ほめる時は皆の前、叱る時は個別に指導することが基本だと思うのだが。
命令と統制のシーンが多く、60年前の私の小学生の時代とあまり変わらない。公立小学校は世の中の変化から遅れているのだろうか。どうして評価が高いのか疑問。
また、この映画が海外で上映され、こういう上から目線、集団主義的な教育が日本の学校教育だと誤解されてしまうのも怖い。
日本の学校では、皆で掃除をしたり、給食を配膳するなどは素晴らしいと思うし、ワールドカップで日本チームの控室がきれいで賞賛されたことは、日本的教育の成果であり、良い部分だと思う。ただ、もっと児童生徒の自発性を大切にする教育に転換しないといけない。
命令に服従する子をうみだす教育、自主性を阻害する教育から脱しないかぎり、日本の再生は遠いでしょうね。
先生、それはいくら何でも難しくないですか?Teacher, isn't this just a bit too difficult?
子供と対峙する大変さと、
それに伴う喜びと、
凄い仕事だなと改めて思った。
と、同時に、大半の先生方は
おそらく、大学からそのまま学校へ就職されたことを考えると
それ以外の道筋で教師になる方法も
あったほうが良いんじゃないかと
思ってしまった。
それほどまでに大変な仕事だから。
別の仕事を経験して、
そこから教師になる人がいることは
教師にとっても子供たちにとっても
良いことなんじゃ?
と思いながら見ていた。
映画に出てくる先生方は、
本当によくやっていると思うけれど、
引き出しのバリエーションで苦労しているようにも見えた。
後半、新1年生を歓迎するために、
ベートーヴェンの第9の4楽章をみんなで
色んな楽器で弾く試みがあったけれど、
まぁまぁ難しい部分から、最後に向けてをやっていた。
みんな頑張ってついていって、結果上手くいっていたけど、
ずいぶん、チャレンジングなことをするなぁと
感心するとともに
「先生、それはいくら何でも難しくないですか?」
とも思ってしまった。
自分は結婚してないし、
当然、子供もいないので、
小学校の今をこうして垣間見れたのは
貴重な経験だった。
Facing children is both challenging and rewarding.
Once again, I was reminded of how incredible this job is.
At the same time, considering that most teachers likely go straight from university into teaching,
I couldn't help but think that there should be alternative paths to becoming a teacher.
After all, it’s such a demanding profession.
Wouldn't it be beneficial for both teachers and children
if some teachers had prior experience in other fields before stepping into the classroom?
That thought crossed my mind as I observed them.
The teachers in movies seem to do an excellent job,
but they also appear to struggle with the variety of approaches they can take.
Later, to welcome the new first graders,
the students attempted to play the fourth movement of Beethoven’s Ninth Symphony
using various instruments.
They tackled a fairly challenging section leading up to the finale.
Everyone worked hard to keep up, and in the end, they pulled it off.
But I was both impressed by the ambitious challenge
and found myself thinking,
"Teacher, isn't this just a bit too difficult?"
Since I’m not married and, of course, don’t have children,
getting a glimpse into the reality of elementary school today
was a valuable experience for me.
「日本人が作られていく」事を日本人が知る事になるドキュメンタリー
銀座を歩いていたら『小学校〜それは小さな社会〜』が20分後に上映されるのを見つけた。
時間もあったので観てみることに。
「6歳児は世界のどこでも同じようだけれど、12歳になる頃には、日本の子どもは“日本人”になっている。すなわちそれは、小学校が鍵になっているのではないか」との前提の思いがまず面白い。
この作品は世田谷の公立小学校を1年以上かけて撮っている。
1年生の女の子と6年生の男の子を中心に学校生活を丁寧に見せていくドキュメンタリー。この2人がかなりいいキャラクターで2人とも壁にぶつかり乗り越える。この2人を見つけて追えた事がこのドキュメンタリーの成功に繋がっている。
小学校という集団生活の中、給食や掃除などの仕事分担、運動会の全体パフォーマンスや入学式の音楽隊などの集団行動、出来ない事を練習して出来るようになる勤勉さなど「日本人が作られていく」様を当たり前な感じでみせてくれる。
まず日本人が作られていくという感覚が面白い。海外でウケていて、短編にまとめたものは今年度アカデミー賞にノミネートされているらしい。改めて観ていると確かに日本人が作られていく。良くも悪くもだ。
また小学生だけでなくもちろん担任の先生も撮られている。先生の言動も日本人を作ることに寄与している。これも色々と賛否はあるだろう。
未来の日本のためにこの映画を観た多くの大人たちと語り合いたい気分になる映画でした。
#小学校
#それは小さな社会
#映画
子を従順平均に矯正する教員、感動して泣いたって駄目だ。
これが正解と言っているわけではないし、これが全てとも言っていないが、現実の一部であり、映画という形にしたことに意義がある。よく実現できたと思う。
現代の小学校の一面を、ありのままに生に映し出す。
決してこれが正しいと言っているわけでもなく、ある部分は正しく素晴らしいが、その反面問題もある。
現場の教師の皆さんは、本当に真摯に対応されていて尊敬する。
生徒もまた一生懸命。
それを、ナレーションなしで、良くまとめた。
観ながら自然と何度も泣いた。
そして考えさせられる。
良く実現できたと思う。
数知れない許可取り、承認が必要だったかもしれない。
NHKだからできたという面もあると思う。
テレビで十分という声もあるかもしれないが、これを映画と言うパッケージにしたことの意義は大きい。
テレビ・ドキュメンタリー番組では、そうはいかない。
映画として、世界中に流通させることが容易になる。
そのことで、より多くの人々に、伝えられる。
不登校児童が増えるのに納得しました
最近の小学校事情は報道くらいでしか知らない者です。
すごく評判になっているので劇場に向かいました。
これは、世田谷区の小学校だけの雰囲気なのでしょうか。
コロナ下だからでしょうか。まさか全国平均??
自分達の子供の頃とくらべて、あまりに息が詰まるというか、細かくて、
先生も児童も大変だなと思いました。
縄跳びや打楽器が苦手な子が努力して克服するのは感動的ですが、
「できない→くやしい→がんばる→できるようになる」の公式に当てはまらない子にとっては、地獄のような環境ではないでしょうか。
日本で生きる限り、あらゆる組織団体で同調圧力はありますし、
その免疫をつけるのが学校での集団生活なんだなと改めて思いました。
この集団生活になじめず、体調不良を起こす子が、不登校になっていくんだなと、
すとんと納得できました。
高齢化のすすむ日本では、子供達は宝です。
この学校生活についていけない子たちに合った別の道、才能を伸ばして成長させてあげられる道をきちんと用意してこそ「個性」「多様性」を大切にしている国といえるでしょう。
「小学校」を見て、「小学校に行かないで済む方法」の必要性を考えてしまいました。
いずれにせよ、教育についての議論を巻き起こす話題作だという評判どおりの映画でした。
日本人がしっかり見て考えないと!
たくさんの人に観てほしい。
まずは、シネコンでこの地味な作品だと、もしかして貸し切り状態かなと思ってたら、ほぼ満席でびっくり。
観る前からちょっと感動。
新一年生が1年間の成長を経て、次の新入生を迎え入れる様子を丁寧に追った作品だけど。
自分は、縁あって20年以上地元の小学校の入学式・卒業式に出席しているし、ちょいちょい小学校に入るので、ほぼ見慣れた光景だけど、この新1年生の大冒険を知らない(忘れている)大人たちはきっと多いことでしょう。
とにかく「自分はなんでもできる!」という万能感とすべてを父や母に守られていた幼児期をおえて、いきなり『社会』にほうりこまれた6歳の、困惑と挫折が痛いほど伝わってきます。
『競争』なんてもんに直面して、頑張っても一位になれないってことがわかったり、楽器をうまく弾けずに、練習不足だと叱られたり、給食の配膳で失敗してしまったり。
とにかくこの1年は、できるようにならないといけないこと、克服しなければいけないことが次から次にやってくる。
足し算とか漢字とかなんて5%くらいしか占めてないんじゃないかと思うくらい。
逆にいうと、『学校』というものの重要性が浮き彫りになってくる。
さっこん、「通信制高校」なんてもんがもてはやされているけど、人間が集団のなかで形成される能力ってのは、中学生でも高校生でも実は重要なんじゃないか。
その中でしか培われない力ってもんがあるんじゃないか。
なんてことを考えさせてくれる作品でした。
来月も卒業式に呼ばれてるんだけど、6年前に作品中の新1年生と同様、立ったり座ったりで必死だった子たちが、立派な合唱ができるようになり、しっかりとした答辞を言えるようになってるのを見るのはいつも楽しい。
それにしても、「さんぽ」で新一年生が入場し、「旅立ちの日に」で巣立っていくのは全国共通なんですかね?
「日本人の形成」のプロセスがつまびらかにされる
舞台は2021年度の世田谷区立塚戸小学校。新入生の入学前から翌年の入学式までの一年間を追ったドキュメンタリー。主に1年生と6年生に焦点を当てて追いかけていて、6年生は新入生を迎えるところから卒業式まで、1年生は自分たちが入学するところから翌年2年生として新入生を迎えるところまでが描かれている。
ちょうどコロナ禍2年目の年で、マスクやアクリルの仕切り板、そして黙食など、あの時代を象徴するいくつかのアイテムが必然的に含まれることを除けば、おそらく多くの日本人にとっては馴染み深い、誰しもが頭に描くであろう小学校生活が淡々と映し出される。
学習指導と生活指導が並行して行われ、その中で規律や努力、勤勉といった日本社会や日本人を形容するのに頻繁に用いられる資質を6年間で獲得していく様、まさに英語タイトルが示している通り「日本人の形成(The Making of a Japanese)」のプロセスがつまびらかにされている。
まさに日本人の美徳であり、その過程での児童たちや先生方の葛藤や努力の様には胸を打たれ、目頭が熱くなる。おそらく製作者サイドの意図もその日本の良さを世界に知らしめることにあったに違いないと思う。
ただ、一方で、前日に「型を破る」話を観たばかりであるせいか、「子どもたちの主体性を伸ばすために頑張っていきましょう」と職員会議で話していながら、手の挙げ方や靴の揃え方、廊下の歩き方まで、事細かに指導している様を目撃していると、どちらかというと「型にはめる」方向に向かっているのではなかろうかという疑念が自分の中で払拭できなくなっている。社会マナーの指導の意義も理解できるだけに、どの点をどう評価するのか、観客一人ひとりの観点が問われる気がする。
全106件中、41~60件目を表示