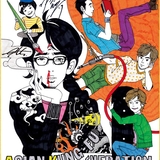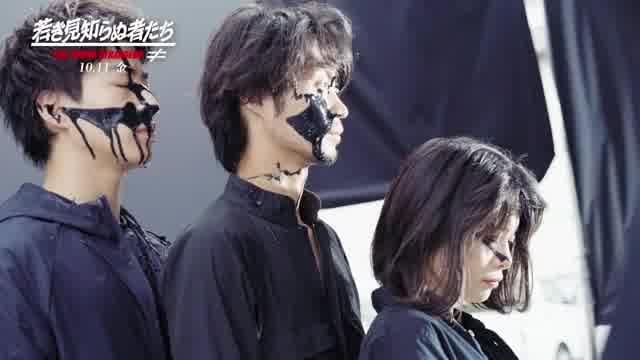若き見知らぬ者たちのレビュー・感想・評価
全95件中、41~60件目を表示
幾つものアンコンシャスバイアス
知り合いの話だが、短期間に三度「職質」を受けた人がいる。
2008年に起きた「秋葉原通り魔事件」をきっかけに休止されていた歩行者天国が、
2011年にテスト開催されたとのタイミングで。
本人の迷彩ズボンにリュックを背負っていた外見も
疑わしかったのかもしれない。
警官側からはけして触れようとはせず、
自らリュックを開けて中を見せるよう(強く)促すところは
本作で描かれている始終と共通。
勿論、やましいことは無いので唯々諾々と従い、
直ぐに解放された由だが、それにしても
「続けて三回かよ!!」と憤慨していた。
ただ、その「職質」が、後々の悲劇を呼び込む契機になることも。
警官だった父親は、ある事件で手柄をたてたものの突然に退職、
カラオケバーを開く。
が、何故か莫大な借金を残し突然自殺。
それを見た母親は正気を失う。
兄の『彰人(磯村勇斗)』は昼には工事現場で働きながら
夜は父が遺したバーを開け、背負った借金を細々と返済する。
弟の『壮平(福山翔大)』はMMAのプロとなり、
階級のチャンピオンを狙えるランキングにいる。
兄弟二人と『彰人』の恋人で看護師の『日向(岸井ゆきの)』で
母『麻美(霧島れいか)』の面倒を見るが、
家の内外での奇矯な行動に身も心も休まる暇はない。
社会情勢を扱った昨今の作品同様、
ここでもやはり幾つかの課題が提示される。
一つは公助に頼らず、自助に閉じてしまう介護の問題。
一旦沈んでしまえば、再び浮かび上がるのは困難で
「親ガチャ」とか「社会格差」で片づけるには
余りにも理不尽な。
または、一たび面倒を起こすと、それが常について回るラベリングの問題。
周囲も色眼鏡で見てしまい、それが命を脅かすのに直結するケースがあるのは
由々しき事態。
或いは公的機関が、時として権威を振りかざすことも俎上に乗る。
直近でも「大川原化工機事件」があったばかりだが。
疑いをかけられた側だけでなく、
かけた側の一部にも心に傷を負う者はおり、
それが『風間』家の悲運につながるのは、
なんともやりきれない連環だ。
終盤の盛り上がりに寄与する迫力満点のMMAの試合シーンは、
『壮平』が我が身に降りかかった不運の鬱憤を晴らす場として機能するかと思っていたら
然にあらず。
あくまでも肉体と肉体の純粋なぶつかり合いとして描かれる。
暴力とは異なるすがさがしさに、
鑑賞者は僅かながらの光明を見ることになる。
壮絶な暗さ…⭐︎
磯村勇人演じる風間彩人の日常を描く。
精神的な病気を患う母、格闘技に没頭する弟、看護師の恋人、親友らしき人。
過去と現在が時々入り乱れて物語が進み、途中と最後あたりに何かの象徴として
頭に銃で撃たれるシーンが入る。
何かと言うことはわかるけど何⁇言われのない暴力?、父親がいなくなるシーンも突然
現れてどうなったと思い、彩人の店が荒らされて その後友人や弟が現場を
見ても完全スルーするのはどうして⁇と自分にはわからないことだらけの映画だった。
ただ、前編通して全く救われない気持ちになる。
母親があれだけ重症の病なら、病院からも何らかのフォロー出来る施設への提案も
あると思うし、自立支援の相談もある。
店を荒らした半グレ三人組には目もくれずに彩人だけを連行する警察もありえない。
社会的にこぼれ落ちた人々、今の日本のある状況を描いているのだろうけど
あまりにも辻褄が合わないことが多すぎて、自分には物語として受けとれなかった。
⭐︎はやはり磯村勇人、母を演じる霧島れいかの「ドライブ・マイ・カー」の真逆の演技、
岸井ゆきの、染谷将太の存在に。
楽しい映画ではないことはわかった上での鑑賞だったけど、あまりに暗い内容で
来週はもう少し明るい映画を見ようと思いながら映画館を出た。
率直に言えることは、エピソードを詰め込みすぎで、何を伝えたいのか主題がぼやけてしまいました。
『佐々木、イン、マイマイン』(20)が評判を集めた内山拓也監督が日本、フランス、韓国、香港合作で手がけた商業長編デビュー作。語り口は辛辣でも、全てを包む温かなまなざしを感じさせます。あらゆる理不尽にまみれても、自分の正義を守り懸命に生きようとする、名もなき人々の魂の叫びをスクリーンに焼きつけました。
●ストーリー
風間彩人(磯村勇斗)は、亡くなった父亮介(豊原功補)の借金を返済し、 血管性認知症を患う母、麻美(霧島れいか)の介護をしながら、 昼は工事現場、夜は両親が開いたカラオケバーで働いています。借金返済に追われて精神的にギリギリの状態でした。恋人の日向(岸井ゆきの)や親友の大和(染谷将太)の支えで、何とか持ちこたえていたのです。
若くして一家を背負った彩人はサッカー選手として将来を有望視されながら、夢をあきらめ、人生を家族にささげてきたのでした。
そして弟の壮平(福山翔大)も兄と同居。父の背を追って始めた総合格闘技の選手となっても、同じく借金返済と介護を担いながら、練習に明け暮れる日々を送っていたのです。そんな息の詰まるような日常のなかでも、恋人である日向との小さな幸せを掴みたいという思いが、彩人のかすかな希望でした。しかし、大和の結婚を祝うつつましくも幸せな宴会が開かれた夜、思いもよらない暴力によって、彼らのささやかな日常がもろくも奪われてしまうのです。
●解説
彩人の苦労がいつか報われてほしいという淡い期待は打ち砕かれ、事態は悪い方へと向かいます。現実世界もまた同じように理不尽で、不条理だからとでも言いたげな展開です。でも不遇続きの彩人を人生の敗者として描いてはいません。とっくに押しつぶされていてもおかしくないのに、彩人はたまに達観した態度で哲学的なセリフを吐くのです。納得できないことには毅然と筋を通してしまうこと。それがあだとなるのですが、強く、気高い人なのです。その存在感は物語から退場する後半に、より際立ちます。
後半には、総合格闘技のタイトル戦に臨む弟・壮平に焦点が移り変わります。長回しで捉えた肉弾戦のシーンはほの暗く、乾いたタッチの前半と打って変わって、目もくらむ明るさ、むせ返る熱気です。
彩人が望んでもかなわなかった若さと感情の発露として、壮平が屈強な肉体をリングで躍動させます。共演シーンこそ多くありませんが、磯村と福山が魂のバトンをつなぐ兄弟役を対照的なアプローチで演じました。弟が兄の人生を内在化したように、兄もまた亡き父親を慕い、面影を追いかけていたのです。心の中にいる絶対的ヒーローの存在、その鮮やかな交代劇は、爆発的なエネルギーが渦巻く内山監督の「佐々木、イン、マイマイン」とも通じます。
日本を含めて四つの国と地域による共同制作。異論を力で封じ込める風潮や、前世代のツケを払わされることへの次世代の怒りが伝わってきます。国や言語を超えて共感を呼びそうなメッセージも声高には訴えません。フラッシュバックか。妄想か。時折、遊び心のある演出が差し挟まれて、後味も意外に軽やかです。
●主演磯村勇斗について
インタビュー映像で、主演の磯村は、介護や家事を日常的に担う「ヤングケアラー」を演じる磯村は「社会の理不尽さなど、日々感じることとリンクすることが多い」と撮影を振り返りました。
磯村はこれまで、知的障害者施設の殺傷事件が題材の「月」、特殊性癖者の孤独を描いた「正欲」など、近年、社会の問題を突く作品で難役に挑んできました。本作で演じる彩人は、若くして家族の呪縛にとらわれ、貧困と母親の介護負担にあえぐ。夢も等身大の幸せもあきらめ、生きながら死人のようです。「親の介護以外に意識を持っていけない。ただ息をすることしかできない。そこは彩人をやるうえで優先したところ」SNS社会で自己表現の場は表向き増えたように見えるが、「何かしたくてもできない。声を上げられないというところは結構、今の時代にマッチしている」。と語ります。
俳優デビューから10年。作品ジャンルや主演、助演を問わない活躍ぶりですが、当初は脚光を浴びる同世代の活躍に焦りを感じていたそうです。「なぜ俺はそこにいないんだろうと思っていた。すごいな、なんか、むかつくな。自然と生まれるハングリー精神みたいなものは絶対なくしてはいけない」と強調します。自身の俳優としての強みを「普通なところ」と言いきります。「白いパレットでありたい。様々な色をのせて、作品ごとにカラーが変わっていく。普通は僕にとってはうれしいこと」
そういう点で本作の彩人が抱える苦悩と希望の複雑な心境を磯村は演じきっており、当たり役になっていたと思います。
●感想
ただ率直に言えることは、母親の介護とか貧困、将来有望だったサッカー選手としての挫折、彩人のまっすぐな正義感、それに弟・壮平の総合格闘技選手としてのサクセスストーリーが絡んで詰め込みすぎで、何を伝えたいのか主題がぼやけてしまいました。
そして時折挿入される登場人物が拳銃で自殺を図るシーン。これも誰が妄想しているのかすらわからなく、唐突に挿入されるので混乱しました。まるで『ジョーカー2』みたいです(^^ゞ
それに加えて、本作での警察への反感が異常なくらいの描かれ方をしているのです。
劇中彩人が遭遇する通行人の若者への職質質問が以上にしつこく、人権無視な対応として描かれています。疑問を感じた彩人が警官に詰め寄ると、問答無用で無関係な彩人まで逮捕されて警察署まで連れて行かれるのです。
それだけではありません。別な日によぱっらいにからまれて大けがを負った彩人に対し、たまたま現場に駆けつけた先日と同じ警察官は、なんと彩人を介抱もせず、病院にも連れて行かず、ただ警察署に連行するだけでした。
警察に対する余りの権力乱用な描かれ方に驚きました。監督は余程警察に恨みを持っているようです。
上映時間 :119分
劇場公開日:2024年10月11日
演者の力では作品の酷さはカバーできない、最大の戦犯は上映館だ😡
自宅介護の実態を全く理解してない脚本、冒頭からその薄っぺらさが瞬時に分かる。万が一分かっていたなら自宅介護者への冒瀆で指摘したらキリがない。ネグレクトでない自宅介護に献身した主人公(と思ってた)は中盤で呆気なく死亡、その顛末の酷さは他の方のコメント通り。そこから荘平が父の記憶とともに突如メインになり長回しの格闘シーン展開には全く付いていけないし、勝ち負けも何か意味があったのか。ラストの2人の警察官の処理は観客の溜飲を下げるサービスのつもりなら火に油でふざけすぎだし、何日経ったのか不明だがひなが母親と食事してる→面倒見てるならムリ→要介護5クラスを看護婦といえどヘルパー等無しでワンオペ出来るわけないので。
磯村、岸井、染谷など中堅ところを集めて演者は良かったと思うが、鶴も掃き溜めでは泳げない見本です。監督、脚本とも若い方はもっと社会勉強してください。何より新宿P館、ふざけるなです。
発想、題材は興味深いのに勿体ない
あまりに共感しづらい
まとまりのない群像劇とでも言おうか。
要するに何だったのか、とにかく分かりにくいという印象しか残らない。観る側に解釈を委ねるというニュアンスなのかどうかすらよく分からないほど、この物語の主軸を定められなかった。つまり本来この作品の主題である「何が彼を殺したのか?」に対する解答を僕は最後まで見つける事が出来なかった。
彩人の死によって途中で主人公が弟へ交代するというアイデア自体は決して悪いとは思わないが、結局それが映画に何をもたらしたのか僕には正直あまり伝わって来なかった。もちろん僕の読解力の責任でもあるが、とは言え弟の背景がほぼ描かれていないので、そもそも感情移入出来るわけがない。なので後半は主人公が交代すると言うよりも主人公不在のまま話が進んだだけなのでは、と言わざるを得ない。だから主人公を交代させた意味は結局何だったの?となるわけだ。
最後の格闘技も、ワンカットで撮るという大胆さで素晴らしいシーンだったとは思う。ただその生々しさや迫力が映画をより「高み」へと導くという役割をまるで果たしてないように感じられた。ワンカットであろうかなかろうが、そのシーンが映画の中で効果的に生かされなければ何の意味もないわけで、もしかしてワンカットで撮る事自体が「目的」になってしまったのではと感じた。この映画のこの場面でこの長回しの格闘技シーンは本当に必要なのか?とさえ思ってしまうほど意味が全く見出せないのだ。だから非常に素晴らしいシーンであると同時にとても残念なシーンであるとも言える。でもこれだって要するに弟の人物像をしっかり描いてないからこういう事になるのではないか。
各登場人物も一人一人を見れば良かったとは思うが、基本的に描写や表現が少な過ぎて個々の人間性や心の動き、それぞれの関係性などが分かりづらく、想像するにしても振れ幅があまり大きいためひたすら戸惑ってしまう。例えば彼女が食べ物を吐くシーンも過食なのか妊娠なのかよく分からない。また母親をどう描きたかったのか、難病や貧困や介護の問題、父親の存在が兄弟に与えた影響、兄弟間の葛藤、友人との絆、それら全ての描写に何らまとまった方向性を見出せず、非常にストレスが溜まる形になったと言わざるを得ない。
そして何より警察官の対応や事件の処理の仕方などリアリティに欠ける表現がさすがに限度を大きく越えていて、それ以降の話がどうにもこうにも入って来ない。この作品に限らず意外にありがちだと思うのだが、世の中の「悪意」というものを表現する際に誇張が過ぎると逆効果というか「そんな事あるかい」とすごく冷めてしまうのだ。デフォルメの全てがいけないとも思わないが、少なくともこの作品においては彩人の死に直結するエピソードだけに、警察官との絡みはリアリティがとてつもなく重要ポイントだったはずだ。なので途中からすっかり気持ちが離れてしまったのは否定出来ない。
ただ唯一、彩人の死後に親友の大和が警察署へ出向いて警察官を問い詰めるシーン。「人なんて曖昧で不確かなものですよ」「だから信じるんですよ」このやり取りは良かった。これがこの映画のハイライトかなと思う。またチャンピオンになった弟がお店のカウンターで茫然と佇むラストカットもとても良かったと思う。ただこれも直前の格闘技シーンがいまいちハマってないから結局あのラストが生きて来ないのだ。本当はもっと圧倒的に良いシーンに出来たはずなのに。
それにしても群像劇がまとまる事なく最後までバラバラだと、結局何がしたかったん?となってしまう。改めて言うが僕の読解力の問題も否定は出来ない。ただ公平に見ても非常に伝わりにくい作品だと言うしかないだろう。基本的に監督は観る側に媚びたりせず、思うように好きなように作れば良いと個人的には思っている。とは言えただの「自己満足」になってしまってもいけないと思うのだ。
ああ無情
2点台は滅多につけないんですが……
認知症の母を抱えて生活が苦しく、夢も諦めてそれでも何とかギリギリ生きている青年に、次々と不運が重なる話。
表現したかったことは分からないでもないですが、観る側は、それで?と思います。
ドラマティックな悲劇というより、生活感のある災難が続きますがリアリティに欠けるから、共感できません。警察に怒られそう。何でも食べてしまうのに、テーブルの上に食べ物や調味料を置きっぱなしにはしないですよ。映像もわざと不快な感じにしてますね。
大変な役を演じた磯村勇斗さんと霧島れいかさんにはお疲れさまでしたと言いたいです。
カラオケの選曲、あれは無いですね。歌ってる場合じゃないところで敢えて歌うなら、私だったらTRAIN-TRAINにするかな。それとも、昔みんなで盛り上がって歌った曲。あの歌よりはリアリティがあると思います。
若い監督が撮ったとは思えない古さ
陰々滅々とした話が延々続く。ツッコミどころだらけ。
不幸ばかりに見舞われる一家が主人公だが、被虐的な演出が過剰では
露悪的でもあり、若い監督が撮ったとは思えない昭和的な古臭さを感じました。
自分を抑えて恋人とその家族に尽くす日向、恋人が死んでもまだまだその家族と家に尽くすんだ、日本の伝統的家族制度の「嫁」ですか。こんなところも古い。
神奈川県警のあれはヒドイ
住民の通報があったなら目撃者だっているだろうし、なんで救急車を呼ばないのか、どこに連れて行こうとしたのか、何がしたかったのか、町中には防犯カメラだってある。検死すれば死因も明らかになるし、それら全部をもみ消せるっていうことですか?
世間では「神奈川県警」といえば〇〇と言われているけど、神奈川県警から苦情来なかったんだろうか
ほぼ動きのないひとつのシーンが長回しで延々続く、それが多用され、視線の先になにがあるのか、次にどうなるのか、なかなか表れなくてフラストレーションが溜まる。そのくせ、肝心なことを明らかにするかしそうな場面は一瞬でぱっと切り替わる。これ、監督的にはスタイリッシュなのでしょうか?
あんな母がいるのになんで公的扶助を受けないのか
母の病気は何なのか、いつからなのか、きっかけはあるのか
アヤトは難病らしいがどんな病状なのか
父親は退職金その他をどうしたのか
父親はなぜ死んだのか
スナック花火の血まみれの床を見て、なぜ誰も何とも思わないのか
などなど、疑問と不可解と不明解ばかりなのに説明がまったく足りていない。
ツッコミどころも満載。
後半、唐突に弟主観の話になり、それまで弟をほとんど掘り下げてないのに唐突すぎて今までのは何だったんだろうと思った。
そして、予想はできたが格闘技の場面を延々と編集なしワンショットで見せられる。
なんとか最後まで見たが苦痛だった。
今後、内山拓也監督の映画をみることはないと思う。
映画ならではの良さ
9:25から観ました。観ようかどうか迷っていましたが、王様のブランチの映画コーナーに、磯村と岸井が出てて、感じが良かったので観ました。レビューの評価が良くないので、あまり期待していなかったのが、良かったのか、映画作品として、良かった!自分の母親の介護などテレビで、描ききれないところが秀逸です。親の介護はとても大変です。特に認知症があるとものすごく大変。私も母親の介護を経験してるので良く分かります。結局私は施設に入れましたが、本作は、磯村が精一杯面倒をみている姿に感動しました。警察の対応は良くないが、ありそうな感じが描かれている。暴力はいけないというメッセージが感じられました。岸井が素晴らしい!こういう彼女がいると救われます。染谷の演技も良い。格闘シーンもgood!やっぱり映画はいいね~観て損しない作品です。
傑作になり損なった凡作?
映画鑑賞中から???だった点を順不同で書いてみた。
①若い方の警官が良心の呵責から告発、或いは最低限の再調査を行うように警察内部での問題化、もしくは遺族に上司の隠蔽のことを教える等の行動はなにもしないまま?
②①がなかったとしても、医師の判断で彩人の飲酒量の検査結果や酒瓶による傷であることは分かるから司法解剖になりませんか?
(あの警官二人はそれをもみ消せるほどの大物ではまったくない!)
その結果、あのカラオケスナックでの調査が本格化するのでは?
③父親が「誤認逮捕で責められたことを苦に自殺」(という理解で合ってる?)という経緯があったことから、彩人の家族にとって警察は悪代官のような存在=滝藤賢一はその象徴のように描かれていたが、この警官が本当の悪者である3人を放ったらかしにしてまで救急車を呼ばない理由がまったく理解できない
④いやいや、この映画のテーマは警察の闇を浮き彫りにすることなんかではなく、もっと深い社会派ヒューマンドラマじゃなかったっけ?
不運な境遇にあっても、心はとっくに絶望でほとんど折れているのに、それでも公助に頼ることをせず(もしくは頼る方法を知らない)、自助努力でなんとかしようと真面目に働き、かろうじて生きている人。そんな人に追い打ちをかけるように襲いかかる不幸。
周囲にはそれを支えようとしてくれる人だっていたのに。日向=岸井ゆきのは彼の子を授かるほど愛していたのに(トイレのシーンはそういうことですよね?)。
これでもかというほど徹底的に報われることのない『若き見知らぬ者たち』。
穴だらけの設定は、それなりに意図的なものだとは思うのですが、ことごとく裏目に出てしまった。
そんなふうに感じました。
苦痛であり不快
前半がとても良かった。 前頭側頭型の若年性認知症の母を諦めた視線で...
舞台挨拶にて鑑賞 テーマ、ストーリー共に重い重い。 途中で帰りたく...
ご都合主義。だから、撮り手の撮る動機の浅さが分かる。
わかりにくいのがもったいない
悲壮感漂う予告から話の結末が気になり、公開2日目に鑑賞してきました。予想どおり観客はまばらでしたが、それも頷ける感じの作品でした。
ストーリーは、病気で自身の行動も制御できない母・麻美と格闘技で頂点を目指す弟・壮平の三人で暮らす青年・風間彩人が、母の世話をしながら昼は工事現場、夜はカラオケバーを経営して生計を立てる一方、母の不始末の謝罪と弁償に奔走する毎日を送っていたある日、バーに現れた理不尽な客とのいざこざから事件に巻き込まれてしまうというもの。
こう書くと事件ドラマに思えるかもしれませんが、そういう類の話ではありません。全方位にわたって救いのない彩人の生活が、序盤から終盤に差しかかる頃までずっと続き、とにかく胸が苦しくなります。こんな生き地獄のような生活の中で、人間らしさをかろうじて失わない彩人の姿が沁みます。理不尽な職質を受ける若者を見過ごせずに警官との間に入ったのは、警官だった亡き父の「あらゆる暴力から自分の範囲を守るんだ」という教え、その父が誤認逮捕を犯してしまったことから狂い始めた人生を思ってのことでしょうか。
また、母への接し方にも胸を締めつけられるものがあります。スーパーの商品を勝手に持ち帰る、近所の畑を荒らす、台所にさまざまな物をぶちまける、しまいには水道を出しっぱなしにして水浸しにするといった奇行を繰り返す母。実の親でも殺意を感じるレベルの壊れ具合を見せる母に対して、怒りをぶつけることなく穏やかになだめる彩人の姿には、優しさを通り越して、心を無にする諦めの境地が見て取れます。途中で描かれる自殺を思わせるシーンは、その表れでしょう。
そこへ追い打ちをかけるような酔っ払い客、さらに理不尽な警察の仕打ちに、はらわたが煮えくり返る思いがします。友人の大和が詰め寄るも、保身を図ってのらりくらりの対応を見せる腐った警官と警察組織に吐き気がします。壮平と仲のよい警官が辞めたのも、そのあたりが理由なのでしょうか。
本来なら、そんな彩人と支え合わなければいけないはずの壮平さえ、彩人との確執もあり試合を優先して自宅を離れます。格闘家の彼も、父の教えを受けてリングに立ったように見えますが、本作における存在意義がイマイチ見出せません。壮平は辛くもベルトを手にしますが、彩人を亡くした今、暴力ではない格闘能力で彼が守ったものは何だったのでしょう。とはいえ、タイトルマッチでのワンカット長回しのファイトは圧巻です。普段は格闘技を見ることがないので余計にそう感じたのかもしれませんが、福山翔大さんの役者魂がビンビン伝わる迫真のファイトが秀逸です。
ただ、全体的には悲壮感が漂うばかりで、本作のテーマがどのあたりにあったのかはよくわかりません。彩人と壮平がそれぞれの信念に基づいて“自分の範囲を守る”ために奮闘する姿を通して、現代の若者が抱える悲しみや怒りを描こうとしたのでしょうか。だとすると、回想シーンから父への尊敬や思慕を感じさせるものが少なすぎたように思います。いずれにせよ、悲惨な末路への切なさと理不尽な暴力への胸糞の悪さが印象的な、苦味の残る作品です。
主演は磯村勇斗さんで、これまでの役とは異なる抑えたトーンが印象的です。脇を固めるのは、岸井ゆきのさん、福山翔大さん、染谷将太さん、霧島れいかさん、滝藤賢一さん、豊原功補さんら。中でも、霧島れいかさんの壊れっぷりが凄まじいです。
「舞台挨拶」
ヤングケアラーの思いを代弁した作品
どんな内容の映画なのか、あまり詳しい情報を持たずに鑑賞しました。ただ主演の磯村勇斗をはじめ、岸井ゆきの、福山翔大、染谷将太、滝藤賢一、豊島功補、霧島れいかなどなど、若手からベテランまで中々の巧者を集めていたことに期待していました。内容的には、チラシの写真で磯村勇斗が頭にピストルをあてていたので、てっきりノワール系なのかと思っていたものの、全く違う内容でした💦チラシで注目すべきは、ピストルよりも磯村勇斗の虚ろな視線の方だったようです。
で、肝心の内容ですが、いわゆる”ヤングケアラー”のお話でした。若くして前頭側頭葉変性症という一種の認知症を患った母親(霧島れいか)の介護をしながら、父親(豊島功補)の残した借金の返済も続ける兄弟(兄・磯村勇斗、弟・福山翔大)という、何ともやり切れないシチュエーションに置かれた主人公の生き様を描いており、未来への光明が全く見えないその救いのなさに、気持ちは自ずと沈まざるを得ませんでした。
ただ注目すべきは、こうしたヤングケアラーに対して公的支援(公助)がないとか、地域社会や周りの人たちの手助け(共助)がないと言った現代社会の重大問題を告発している訳ではなく、また自らの努力(自助)が足りないと言った話を描いている訳でもなかったこと。一般に介護保険の適用は、65歳以上の高齢者に限られますが、認知症については特定疾病に該当し、40歳以上であれば介護保険の給付対象になるようです。従って、本作でもセリフの中で少し触れられていましたが、母親の年齢から考えれば恐らくは介護保険の助けを得られると考えられた訳ですが、磯村勇斗演ずる彩人は適用申請をしようともしていないことが窺われました。
また、母親を定期的に病院に連れて行きながらも、処方された薬を自分で服用している彩人の行動は、中々理解できないものでした。母親が、スーパーの商品を勝手に食べてしまおうが、近所の畑を荒らそうが、水を出しっぱなしにして台所を水浸しにしようが、キレもせずに母親を見守り続ける彩人の心の深奥に、一体何があるのか?これは観た人それぞれが百人百様に感じるものであり、監督の意図も観客毎の解釈に委ねているように感じました。
私的には、ところどころ挿入されるピストルで頭を撃たれる(若しくは自ら撃つ)妄想シーンを観る限り、彩人の心には無力感が満ちており、生きることへの執着が一切感じられませんでした。こうした心理状態こそ、”ヤングケアラー”の特徴的な心情なのかと想像するしかありませんでした。監督が伝えたかったのもそうした立場に置かれた人たちの他人に伝えられぬ思いだったのだろうと解釈が、果たしてどうなのでしょう。ただ質の悪い警官(滝藤賢一)や質の悪い酔っ払いの存在に引っ張られて、ストーリーが一定の方向性を見出しにくくなっていて、”ヤングケアラー”の理解を妨げているような気もしたところに若干首を傾げてしまいました。
あと、総合格闘家を演じた彩人の弟・壮平を演じた福山翔大が、試合のシーンで3ラウンド2分31秒の間、ガチで闘っていたのは評価すべきかなと思います。シナリオの範囲で動いているのは勿論ですが、身体を仕上げて”試合”=”撮影”に臨み、インターバルを挟みながらも9分近く動き続けた福山の役者魂は素晴らしかったです。
そんな訳で、本作の評価は★3とします。
全95件中、41~60件目を表示