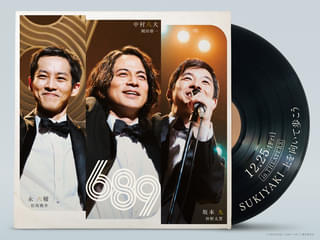コラム:どうなってるの?中国映画市場 - 第78回
2025年11月6日更新

北米と肩を並べるほどの産業規模となった中国映画市場。注目作が公開されるたび、驚天動地の興行収入をたたき出していますが、皆さんはその実態をしっかりと把握しているでしょうか? 中国最大のSNS「微博(ウェイボー)」のフォロワー数270万人を有する映画ジャーナリスト・徐昊辰(じょ・こうしん)さんに、同市場の“リアル”、そしてアジア映画関連の話題を語ってもらいます!
“言葉にならない痛み”を確かに知っている――「ひとつの机、ふたつの制服」製作陣が語る創作の背景

Renaissance Films Limited (C)2024 All Rights Reserved.
昨年の釜山国際映画祭で鑑賞し、心を強く動かされた作品があります。
それが「ひとつの机、ふたつの制服」(日本公開中)。
一見すると淡く切ない青春映画のようですが、その奥には当時の台湾社会――教育格差や階層意識、そして“女の子であること”が抱える抑圧――が、透けて見えます。個人の揺らぎと社会構造が交錯する映画はそう多くありませんが、「ひとつの机、ふたつの制服」はそのひとつに数えることができる希少な1作だと思います。
今回は、90年代の台湾“夜校”という独特の背景をもとに、少女たちの痛みと再生を描いた本作について、ジャン・ジンシェン監督、脚本のシュー・フイファン、ワン・リーウェンの3名にお話をうかがいました。
それぞれの視点から語られる創作の背景には、懐かしさだけでなく、今なお続く問いが息づいていました。
【「ひとつの机、ふたつの制服」概要・あらすじ】
1990年代の台北を舞台に、高校の夜間部と全日制でひとつの机を共有する2人の女子生徒の友情と成長を描いた青春ドラマ。
受験に失敗した小愛(シャオアイ)は、母親の強引な勧めで名門校「第一女子高校」の夜間部に進学する。コンプレックスを抱えながら通う中、全日制と同じ教室と机を使うため、成績優秀な全日制の敏敏(ミンミン)と机に手紙を入れて交流する「机友(きゆう)」となる。夜間部と全日制では制服は同じだが、胸の刺繍の色が違う。小愛は敏敏に制服交換を提案され、ふたりは行動をともにするようになるが、やがて同じ男子校生に恋心を抱いていることに気づく。

Renaissance Films Limited (C)2024 All Rights Reserved.
●書くことは、あの頃の自分を手当てすることだった
シュー・フイファン(脚本) この物語は、私自身の体験が出発点です。若い頃、女子校の夜間補習校に通っていました。当時は受験や進学に追われて、心の整理をする余裕もありませんでした。中年になり、娘が中学生になって会考(旧・聯考/高校卒業試験に相当するもの)を迎える年齢になったことで、あの頃の感情が再びよみがえったんです。
国立大学や大学院に進学しても、心のどこかで“私は本当にここにふさわしいのだろうか”という思いが消えませんでした。
成功しても、自分を完全には肯定できない。その小さな劣等感の根をたどるようにして、この脚本を書きました。言ってみれば、“書くこと”が過去の自分を癒やす行為だったんです。
ジャン・ジンシェン(監督) フイファンさんの脚本を初めて読んだとき、90年代の空気が一気に蘇りました。あの頃の高校生たちは、進路や家庭、そして“親の期待”という見えない鎖の中でもがいていました。
読んでいるうちに、私もリーウェンも涙が出ました。とくに母親と娘の言い争いのシーンは、自分の記憶と重なって胸が痛くなりました。私たちの世代は、あの“言葉にならない痛み”を確かに知っています。

Renaissance Films Limited (C)2024 All Rights Reserved.
●女の子たちの距離感、それが女子校のリアルだった
ワン・リーウェン(脚本) 私は女子校出身なので、脚本を読んだとき“わかる”と思いました。女子同士の関係って、友情とも恋愛とも違う、あの微妙な距離感があるんです。支え合いながら、どこかで張り合っている。その曖昧なバランスこそが、この映画のリアリティだと思います。
ジャン・ジンシェン(監督) フイファンさんの第一稿はすでに完成度が高かったので、私たちがやるべきことは“守りながら広げる”ことでした。原作の核を損なわず、若い観客が入りやすいように恋愛や友情の要素を少しだけ加える。でも軸は“成長の物語”のまま。そこは決して譲りませんでした。
製作前にはいくつかの学校の生徒にも取材を行いました。試験制度は変わっても、プレッシャーは今も変わらない。だから「ひとつの机、ふたつの制服」は、単なるノスタルジーではなく“現在の物語”でもあるんです。

Renaissance Films Limited (C)2024 All Rights Reserved.
●「夜校」という消えゆく制度、母娘を象徴する“依存と信頼”
シュー・フイファン(脚本) 今の台湾では、夜校はほとんど存在しません。私が通っていた頃は、昼に働き夜に通う人と、純粋に夜だけ通う学生が同じ教室にいました。社会的には“日校=優等”“夜校=劣等”という風潮があって、夜間補習校も“健康的ではない進学の抜け道”と批判されました。やがて制度は廃止され、私たちはその“最後の世代”でした。この映画は、あの制度の終わりを見つめた作品でもあります。
ワン・リーウェン(脚本) 姉妹や母娘の関係は、この映画の核にあります。たとえば“互いに刮痧(かっさ/中国伝統の民間療法。水牛の角などの板で皮膚を擦り、経絡の気血の流れを良くして全身の機能向上や症状改善を目指すもの)をする”シーン。最初は母が娘にしてあげるだけでしたが、私自身の経験をもとに“互いにやり合う”形に直しました。父のいない家庭で、母が頼れるのは長女だけ。その手の温度をどうしても残したかった。また、女校での距離の近さも、恋愛ではなく“信頼の言語”として描いています。
シュー・フイファン(客歩) 小愛は特別な“勝者”ではなく、多くの人が共感できる存在です。努力して、失敗して、また努力する。ときに虚栄心もあるけれど、どこか愛おしい。彼女が少し道を誤っても、観客が“守ってあげたい”と思えるように意識して描きました。青春の痛みと成長の矛盾を、彼女にすべて託したんです。
ワン・リーウェン(脚本) フイファンさんが小愛に“卓球”という特技を与えたのが素晴らしいと思います。スポーツの真っ直ぐさが彼女の性格を映し、母親との関係を結ぶモチーフにもなっています。ラケットを握る瞬間だけ、彼女は自由になれる――そんな感覚を描きたかったんです。

Renaissance Films Limited (C)2024 All Rights Reserved.
●90年代を、記憶の質感ごと立ち上げる
ジャン・ジンシェン(監督) 美術や衣装のチームは台湾でもトップクラスでした。ビデオレンタル店、五月天の曲、ニコール・キッドマンのポスター、当時流行したケイシー人形――。時代考証を徹底し、一つひとつの記憶を映像に組み込んでいきました。懐かしさの中に痛みと希望が同居する、あの時代の空気を再構築したかったんです。
ワン・リーウェン(脚本) 制服の色をどうするかはかなり議論しました。最終的に“緑”を選んだのは、台湾ではそれが“優秀”の象徴であり、第一女子高校を想起させる色だからです。色によって人が分類される社会。その違和感をあえて見せたかった。海外の観客には伝わりにくくても、台湾の人なら誰もがその意味を理解できるはずです。
●観客を“現実に戻さない”ために要した“十カ月”
ジャン・ジンシェン(監督) 年代ものの映画で一番怖いのは、観客が途中で“現実に戻ってしまう”ことです。だから編集には十カ月、二十バージョン以上を費やしました。テンポを微調整し、音楽や効果音の呼吸をコントロールして、観客が自然に物語に溶け込むように。観客を“映画の中に留める”ことこそ、最も大切でした。

Renaissance Films Limited (C)2024 All Rights Reserved.
●“いい子”同士の衝突をどう描くか
シュー・フイファン(脚本) この映画の難しさは、二人の少女がどちらも“真面目すぎる”ことでした。彼女たちは不良でもなく、教師に反抗するタイプでもない。だから葛藤はすべて内側で起こる。当初は“静かすぎる”という声もありましたが、ジャン監督とリーウェンさんと一緒に調整し、“静かな張りつめ方”を見つけられたと思います。
ジャン・ジンシェン(監督) 主演のチェン・イェンフェイさんはスマホ世代で、90年代を実際に知らない世代です。それでも彼女たちは、自分たちの“親の青春”を理解するようにして役づくりをしてくれました。歩き方、話し方、家族との距離感――すべてを自分の身体で掴み取ろうとしてくれた。その真摯さが、この映画のリアリティを支えているんです。

Renaissance Films Limited (C)2024 All Rights Reserved.
●日本の観客へメッセージ
ジャン・ジンシェン(監督) 「ひとつの机、ふたつの制服」は、気軽に観られる青春映画です。90年代台湾の高校生たちの物語ですが、日本の皆さんにも共感していただけると思います。伝えたいのはただ一つ――“自分のままでいい”ということです。
シュー・フイファン(脚本) 制服を脱いだあと、あなたは誰ですか?映画を観終えたあと、この問いを自分に投げかけてみてください。
ワン・リーウェン(脚本) 私は高校時代、成績も気持ちもあまり冴えていませんでした。この映画は、頑張っているのに報われない人たちに捧げたいです。どんな場所にいても――“自分であること”がいちばん。