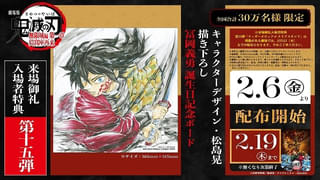コラム:二村ヒトシ 映画と恋とセックスと - 第33回
2025年5月22日更新

作家でAV監督の二村ヒトシさんが、恋愛、セックスを描く映画を読み解くコラムです。今回は19世紀フランスに実在したヒゲを生やした女性をモデルに、コンプレックスを抱えながらもありのままに生きようとする女性を、ステファニー・ディ・ジュースト監督が描いた人間ドラマ「ロザリー」を考察します。
※今回のコラムは本作のネタバレとなる記述があります。
ありのままに生きたいと願い、強烈な性のエネルギーに満ちた主人公 差別と愛の物語「ロザリー」

(C)2024 - TRESOR FILMS - GAUMONT - LAURENT DASSAULT ROND-POINT - ARTEMIS PRODUCTIONS
「差別する」とはどういうことか。「お前(たち)を理解したくない」と宣言することです。
この定義を思いついたのはドイツ映画「大いなる自由」を観たときでした。その映画について本連載で書かせてもらった文章は、ZINE(自主制作本)として出した『AV監督が映画を観て考えたフェミニズムとセックスと差別と』にも収録し、増刷した第二刷の帯の背表紙側にも、この一文を載せました。
「嫌う」のは仕方がないです。人間は生きていれば何かを嫌いになることがある。誰のことも嫌いにならずに生きていくことができれば、それは幸せな人生だろうなと思いますが、そうもいかないでしょう。嫌いだというのは感情ですから。
嫌いなもののことは理解したくないのが「普通」の人情でしょう。でも、何かを嫌
いだという感情や、嫌いなものを嫌いなままでいたいという思いには必ず理由がある。わきあがる感情には、本人だけが気がついていない感情の源(みなもと)があることが多い。
自分がそれ(その人、その人たち)を、なぜ嫌いなのかは考えてみたほうがいい。考えれば、それを嫌うことが「あなた」にとって必要なことなのか、だとしたら、それはなぜ「必要」なのか、それとも「みんなが嫌っているから、なんとなく一緒になって嫌っているだけ」なのか、その判別がつくかもしれない。
それは自分自身を理解することでもあります。
自分の心の底にある、本人だけがわかろうとしてない理由で誰かを嫌っちゃっている人は、まあ「生きていきにくい、かわいそうな人」だと言っていいだろうと僕は思います。もちろん、もっと大変なのは差別されている側の人ですから、「差別する人は生きにくい人なんだから、そっちにも同情すべきだ」と言いたいわけではありません。同情はしませんけど、差別をする人は自身の感情を理解していない哀れな人です。

(C)2024 - TRESOR FILMS - GAUMONT - LAURENT DASSAULT ROND-POINT - ARTEMIS PRODUCTIONS
▼フランス映画「ロザリー」から見る差別をする人の心
僕は今、フランス映画「ロザリー」に登場する悪役たち、村の権力者であるバルスラン(パンジャマン・ビオレ)や、ロザリーの夫の元部下であるひげづらの男ピエール(ギョーム・グイ)、いわゆる犬笛を吹く、差別の扇動者たちのことを言っています。
人間は社会的な動物なので、害がないのにみんながなんとなく嫌っているものをなんとなく嫌ってしまう場合は、もちろんある。でも、たとえ嫌いな相手でも、嫌いなままで、相手と自分のあいだに横たわっているものが何なのか理解してみようとすることはできる。嫌いであっても(自分の身に直接の害がおよんでいないのであれば)やみくもに攻撃はしないで、いったん遠ざかって遠くから観察してみて、相手と、その相手にたいする自分の感情の源を理解しようとしてみることは可能なはずです。
無理に好きになろうとする必要はないです。また、他人というものを完全に理解することは絶対にできません。嫌いだろうと好きだろうと家族であろうと、自分ではない人間のことを「私は理解している」と思うことは、理解したくないと宣言するのと同じくらい傲慢なことで、それもまた一種の差別だろうと思います(被差別者の味方を自称する人が、しばしばそういう差別をします)。
ただ、嫌いな相手でも、完全には理解できない他の人であっても、本当に自分が嫌うべき相手なのか考え、少しでも理解してみようと試みることで、すくなくとも差別者にはならなくてすむ。そして自分のことが理解できるようになる。

(C)2024 - TRESOR FILMS - GAUMONT - LAURENT DASSAULT ROND-POINT - ARTEMIS PRODUCTIONS
▼多くの女性たちとちがうことは「個性」なのか、それとも「異常」なことなのか
主人公ロザリー(ナディア・テレスキウィッツ)は体毛が濃い、剃らないでいると顔にひげが生えてしまう女性です。ホルモンの分泌が他の多くの女性たちとはちがうからですが、そのことは彼女の「個性」なのか、それとも「異常」なことなのか。この映画は今から150年ほど昔が舞台ですが、もし医学が進歩した現代だったら「治療」するべき「病気」なのか。
彼女の父(ギュスタブ・ケルベン)は、娘を愛しています。でも彼が娘のことを見る目は、つねに悲しげです。自分にも責任があると思っているのでしょう。父は娘のひげをずっと剃ってあげていたのでしょう。剃りかたも教えてあげたのでしょう。
ひげが生えてきてしまうという自分の生まれながらの「ありのままの姿」を、悲しがられたり、否定されたり差別されたりするのは恐ろしいことです。
ロザリーが自分を支えるように祈っている小さな十字架にはキリストではなく、聖ウィルゲフォルティスの磔刑像が彫られています。この聖人は14世紀の女性で、望まぬ結婚を父親から強要され(他に好きな男がいたのではなく、一生を信仰に捧げたかったため結婚したくなかったのです)苦しんで神に祈ったところ、ひげが生えてくるという奇跡が起きて、それで先方に嫌われて結婚は破談になったのですが怒った父親に彼女は殺されたのです(なので、DV被害者の守護聖人でもあるそうです)。

(C)2024 - TRESOR FILMS - GAUMONT - LAURENT DASSAULT ROND-POINT - ARTEMIS PRODUCTIONS
▼ロザリーの祈りの真意は……
ロザリーはその十字架に祈ります。つまり、ひげが生えてこなくなるように祈っているのではないのです。夫になる人が私のことを否定しないよう、私が私自身を愛せるよう、そういう心をもてるよう祈っています。この映画には、ロザリーがのびのびとマスターベーションを楽しむシーンがあります。いい映画だと僕は思いました。
ひげや体毛のことを知らずにロザリーと結婚した夫(戦争で大きな傷を負った障害者です。演じるブノア・マジメルは、若いころは「ピアニスト」で、最近では「ポトフ 美食家と料理人」で好演していましたね)に体を見せる前、セックスする前に、彼女は「子どもが絶対に欲しい」と言います。あらゆる子どもが、どんな子どもであっても、ありのままの姿で肯定されるのは素晴らしいことだ。自分は自分が産んだ子どものすべてを、きっと肯定して愛する。そうしたい。
ロザリーは子を産んで、その子を愛することで、自分自身を育て直したくもあったのでしょう。

(C)2024 - TRESOR FILMS - GAUMONT - LAURENT DASSAULT ROND-POINT - ARTEMIS PRODUCTIONS
▼他人を差別することで自分を保とうとする哀れ
ひげづら男のピエールは、ひげ女ロザリーのことが嫌いです。それはピエールが、ロザリーの夫アベルのことを本当は性的な意味で好きだったからなんだろうと僕は推察します。ピエールは嫉妬をするだけで、ロザリーの心や人生を理解しようとはもちろんしません。
村の権力者バルスランはロザリーが嫌いなのではない(自分に逆らう生意気な女のことは嫌いでしょうけど)。彼は本当は、ひげの生えた女とセックスがしたいのです。それはバルスランの魂から起こる衝動なんだろうと僕は思うのですが、彼は「立派な男」ですから、そのことを自分で認めるわけにはいかない。自分の欲望を理解できないということは、つまり彼はロザリーのことだけではなく「自分の欲望」をも差別している。
19世紀のヨーロッパの田舎の厳格な男性優位社会で、美しい人妻に横恋慕することは権力者の男にとっては「あり」でしょうが、ひげ女に興奮している自分を意識することは彼自身のプライドを脅(おびや)かすのでしょう。あくまでも、もの珍しさから好奇の関心を持ったというスタンスでいきたい。他人を差別することで自分を保とうとする。じつに哀れです。
このときバルスランが「すなおになる」には、どうすればよかったのでしょう。ロザリーの前に跪(ひざまず)いて、その美しいひげにちょっとだけ触らせてくれと懇願するべきだったでしょう。もし触らせてもらえたら(まあ無理だったでしょうが)その感触を覚えて帰って家で一人でマスターベーションするべきだったでしょう。しかしそれはこの時代の「立派な男」には、できないことです。立派だということは、くだらないことですね。
ロザリーの人生は苛烈ですが、夫アベルの感情や葛藤も複雑です。彼は最初は「こんな女と結婚できるものか。俺が障害者で借金もあるからといって……」と感じたかもしれません。しかしロザリーのひげと優しさと芯の強い人間性は、アベルの人生をも結果的に変えていきます。アベルはロザリーと暮らすうち、彼女のことを少しずつ「理解」せざるをえなくなるのです。

(C)2024 - TRESOR FILMS - GAUMONT - LAURENT DASSAULT ROND-POINT - ARTEMIS PRODUCTIONS
▼感動的な映画であると同時に、普通ではないエロさで我々を逃さない映画
「ロザリー」は差別と愛の物語だと言えますが、その「差別」は「理解しようとしない差別」であり、その「愛」は「理解という名の愛」です。
ロザリーはアベルと別れ、見世物小屋で差別と歓声を身に受けて気高く暮らす人生を選ぶこともできたでしょう。そのほうが彼女は「自由」だったかもしれないし、そこでまた別の「愛」に出会うストーリーの映画もありえたかもしれません。
しかし、多くの人にとって「理解できないもの」が見世物小屋の外にいることは、その社会の秩序が乱されることであり、バルスランのような人間にとっては恐ろしいことでしょう。それは、いいことだと僕は思います。
この映画は感動的な映画ですが、同時に、前述したロザリーのマスターベーションのシーンも含めて、普通ではないエロさで我々を逃さない映画です。背中や豊かな胸の谷間にもじゃもじゃと毛を生やした美女ナディア・テレスキウィッツは過剰に蠱惑的で、ひげをきれいに整えた彼女は強烈な性のエネルギーに満ちています。ステファニー・ディ・ジュースト監督は感動と奇妙なエロさを両立させる表現を、わざとやってます。

(C)2024 - TRESOR FILMS - GAUMONT - LAURENT DASSAULT ROND-POINT - ARTEMIS PRODUCTIONS
筆者紹介

二村ヒトシ(にむらひとし)。1964年生。痴女・レズビアン・ふたなり・女装美少年といったジェンダーを越境するジャンルで様々な演出の技法を創出、確立したアダルトビデオ監督。
著書『あなたの恋が出てくる映画』 『なぜあなたは「愛してくれない人」を好きになるのか』 共著 『日本人はもうセックスしなくなるのかもしれない』 『欲望会議 性とポリコレの哲学』ほか多数。
Twitter:@nimurahitoshi