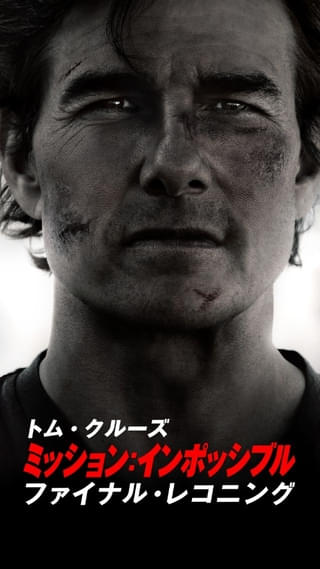コラム:若林ゆり 舞台.com - 第97回
2021年4月15日更新

第97回:古き良き映画館が舞台の新作に、中井貴一が「今だから伝えたい」と込めたメッセージの温かさ!
コメディにシリアス、時代劇からミュージカルまで何でもこなす、当代きっての名優・中井貴一。円熟味を増す彼の活躍は映画やテレビドラマでつとに知られるところだが、舞台でも格別の魅力を発揮していることはご存じだろうか? 中井貴一の舞台には、ハズレがない、という印象がある。特にパルコのプロデュース作品は、2001年の「二人の噺」以来、三谷幸喜の「コンフィダント・絆」や古沢良太脚本の「趣味の部屋」、旧PARCO劇場のクロージングシリーズを飾った「メルシー! おもてなし〜志の輔らくごMIX〜」など、例外なく高クオリティをキープしてきた。そして今、新生PARCO劇場のオープニングシリーズの掉尾を飾るのが、新作「月とシネマ」だ。
舞台となるのは昭和に生まれ、50年以上もの間、映画ファンに愛されてきた地方の映画館ムーン・シネマ。中井の役はその館長の息子で、今ではフリー映画プロデューサーとしてヒット作を生み出している並木憲次だ。長らく絶縁状態だった父が亡くなり、実家に帰ってきた並木は父の遺言状を紐解いて仰天する。そこには映画館を、アート系の女流監督・三城麻衣子(貫地谷しほり)に遺贈すると書いてあったのだ。思いがけないなりゆきで三城とタッグを組み、この映画館を使って映画を製作することになる並木。やがて彼は、父と映画館にまつわる驚愕の事実を知る……。

撮影:若林ゆり
PARCO劇場で中井が主演した多くの作品と同様、本作も中井の「こういう芝居がやりたい」という考えからスタート。脚本・演出のG2と話し合う中で、一番考えたのが「コロナ禍の今、演劇にできることは何か」ということだった。
「コロナで緊急事態宣言が出た時に、僕たちの商売が一番、回復の時期が遅くなるだろうということは予測していたんです。コロナ禍において最も怖いのは、ウイルス自体より人間の心が殺伐とすること。幕を上げる時には自分たちがやりたいことだけをやればいいのではなくて、どうやって心を殺伐とさせない何かを提供できるか。1時間でも2時間でもいいから心が動く何かを作れないか、という思いが自分の中に強くありました。それで僕、G2さんに難しいことを言ったんですよ。『僕は“ハートウォーミング”という言葉はあまり好きではないんです。でも何か温かさを感じられる、体全体が“ほわ~”ってなって、見終わったお客さんが“なんか、よかったねぇ~”と言う、そういうものを作りたい』って。G2さんには『それ、どういう意味でしょう?』って言われたんですけど(笑)。“スコーン”と入ってくるんじゃなくて、“じわ~”っと何かに包まれて劇場を出る、そういうものを作りたかったんです」
そこで登場したのが、昭和の映画館というアイデアだ。
「映画館もコロナ禍で割を食わなきゃならなかった場所でもあるし、それを劇場で演じることができて、しかも昭和のノスタルジーが感じられる作品です。今、僕たちが当たり前に生きてきた昭和が『昭和っていいですね』と言われるんですけど、振り返ってみると、いろんなものが緩い時代だった。緩かったがゆえにダメだったこともあるけれど、その緩さに人が救われていることも実はたくさんあった時代だということが、今になってよくわかってくるんです。僕たちの商売って、その“緩さ”の中に存在する。その“緩さ”みたいなものを、昭和の映画館を描くことで出せないかな、ということで話がまとまりました。G2さんは『僕は映画業界のことはまるで知りません。“映画あるある”じゃなくて“映画ないない”なんです』と言うので、作劇として必要な“あるある”部分は僕が周辺に取材してお伝えしました」

中井が演じるのは、ヒット作には恵まれてもなかなか賞を獲ることはできないプロデューサー。相対するアート系女流監督の三城は「あの人がモデル?」という人物がすぐに浮かぶが、並木役にモデルはいるのだろうか。
「いや、個人的に誰かをモデルにしたということはありません。女流監督にしても、いろんな方の要素が入っているんじゃないかな。長年俳優をやっていると、ある程度プロデューサーの佇まいがわかってくるんです。意外とプロデューサーって“詐欺師タイプ”というかね(笑)。口でいろんなことを運ぶタイプの人が多いので、敢えて難しい資料を読まなくても役作りはできたと思います。映画にはいろいろな考え方があって、作り手にはいろんなタイプの人がいます。たとえば、自分の撮りたいものを撮るために自主映画で全部自分でやって、共感してくれるお客さんが来てくれればいいという人。これが三城監督。一方で『映画はエンタテインメントだ』と考え、どうやったら多くのお客さんが見てくれるかを一生懸命考察して、そこに向かって走る人。これが並木です。この両方とも、決して間違いではない。でも相容れないという、この関係性を出そうとしているんです。一番いいのは、このふたりがうまい具合に重なり合うことなんですけどね。だから誰がモデルと言うよりは、その両極がいるという話なんです」
筆者紹介

若林ゆり(わかばやし・ゆり)。映画ジャーナリスト。タランティーノとはマブダチ。「ブラピ」の通称を発明した張本人でもある。「BRUTUS」「GINZA」「ぴあ」等で執筆中。
Twitter:@qtyuriwaka