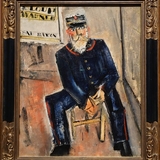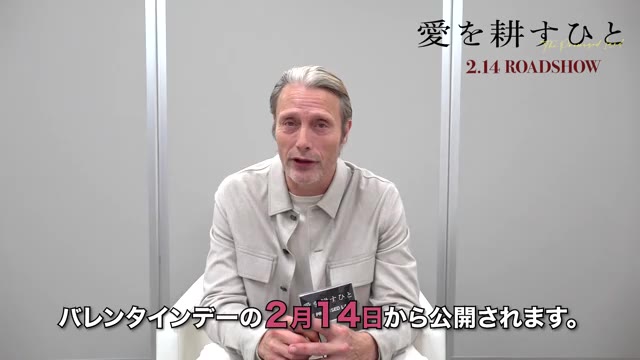愛を耕すひとのレビュー・感想・評価
全109件中、61~80件目を表示
今ひとつ主人公の心境がよく分からないのよ。
重厚な歴史ドラマ。デンマーク語(だよね)であるところが好感持てる。最近は大市場のアメリカを意識してかヨーロッパが舞台であっても全編英語っていう映画が多く違和感を抱くことが多い。ナポレオンが英語喋っている作品もあったよね。
舞台はデンマーク領ユトランド半島。「バベットの晩餐会」と同じ土地です。あれは海っぺりだったけど本作は内陸の荒れ地(ヒース)。時代は「バベット」のちょうど100年前です。
まずこの時代感というか主人公の生活環境の過酷さがいまひとつ表現できていないと思う。かたや仇役のシンケルの暮らしぶりのキンキンさ。デンマーク王国は全盛期はかなり豊かだったと聞くけど片田舎の荘園領主があんなウィーンのど真ん中みたいな生活していたかなあ。
映像は確かに美しいけどどうも土にまみれて大地を耕しているという感じはしない。小綺麗なんです。
最大の問題はルドヴィ・ケーレン大尉の人物表現。この映画の原題は「Bastarden」私生児です。原作にあたっていないのではっきりは言えないがこれは彼が周りからそのように呼ばれ蔑まれていたということでしょう。人格形成に影響がないわけがない。そのような経験は、上昇志向がありながら卑屈であり、時として優しく時として冷酷で暴力的な人間として、すなわち二面性のある複雑な人間を生み出すと思う。冷酷なところはならず者たちに罰を加えるシーンに表れているがその他、基本的にはこの作品はルドヴィ・ケーレンという人物の心の中には分け入っていない。全てマッツ・ミケルセンの重厚な演技で覆い隠されていて単に鈍重な我慢強い人にしか見えず今ひとつ心の陰影が見えてこないのです。演出のせいではもちろんあるのだが、ミケルセンの演技プランにも問題がなかったといえるのか?素晴らしい演技だ、名優だともてはやす声があまりにも多くて、天邪鬼の自分としては疑問を呈してしまうのです。マッツ・ミケルセンの最高演技は007のル・シッフルだと思っているひとなもんで。すいません。
男爵の由来じゃないよ
あんまり話題になっていないけど、マッツがでてるとつい見に行っちゃいます。
マッツはやっぱり、期待を裏切りません。それでも、誰でもわかる主演作があげれない、ライダーズ・オブ・ジャスティス?重賞もとっていないんじゃないかなぁ?
地味なこと以外は減点ができません。
史実を元に脚色していると思うけど、現代人の視点では結末も合格です。
原題はBastardenで英語から考えると「クソ野郎」なので、むしろこういう邦題を付けるとかえって敬遠するひともいるんじゃないかな。
作物の育たない荒れ地を開墾する話し。全く笑わない「クソ野郎」のマッツと作物がちょっとだけ生長するのを眺める作品。封建制を敷いている国であれば、どこでも成立するストーリー。空き地とお屋敷があればお金をかけずに撮影できそう。日本でも頑張ってリメイクしてみて下さい。
本作やイニシェリン島の精霊、燃ゆる女の肖像みたいな寒くて風が強そうな所は、食材のバラエティーがなくて、実にメシマズに見えますね。現代においてもそういったところの食事は単調ですもの。ビタミンなんて単離されてないとは言え、あのような食事をしていれば寿命は短くなるよね。それに比べると、同時期の江戸の町民の食生活は恵まれてるし、文化が発展する余地があるんだなと、見ながら思いました。あと、あの領主はフルーツゼリーがよっぽど好きなんだろうね。ケーキは手を付けてなかったけど。
配信で上がっていても気付かなそうな作品なので見ましょう。
ずっと見ていられる!
凍てつく心を耕したのは?
マッツ・ミケルセンの演技に圧倒された約2時間だった。
「007カジノ・ロワイヤル」や「インディ・ジョーンズと運命のダイヤル」しか映画ではお目にかかってないが、存在感がある俳優とマークしていた。
だからこそ、期待して「愛を耕すひと」(原題「BASTARDEN」の意味である「私生児」とはかけ離れているようであるが映画の結末から納得した)を鑑賞したのだが、期待以上の感動をもらった。
とても嬉しい❗
不毛の大地を独りでも開拓しようとするルドヴィ・ケーレンが、襲い掛かる自然の脅威と地主であるフレデリック・デ・シンケルからの非道な仕打ちに抗いながら、彼のもとから逃げ出した使用人の女性アン・バーバラや家族に見捨てられた少女アンマイ・ムスとの出会いにより、ケーレンの凍てつく心に変化が芽生え、愛するようになっていく。
アンマイ・ムスとの別れと修道院で再会のシーンには涙が溢れた。
演じたメリナ・ハグバーグは初めての映画出演だが難しい役をこなしていた。
フレデリック・デ・シンケルのシモン・ベンネビヤーグの徹底したサイコパスな演技がこの作品をさらに見応えあるものにしている。
結末が予感できたためスコアを「4.5」にしたが、初めてのデンマーク映画、重厚な色彩の映画を観て良い時間を過ごした。
是非とも観るべき一作。
2509
愛憎渦巻く濃密なドラマ
私生児
原題のデンマーク語のBastardenは、英語のbastardのことで、私生児やロクデナシという意味。邦題の「愛を耕すひと」も英題の「the promised land」もなんか違う感じ。原題の「私生児・ロクデナシ」が一番しっくりくる。
主人公のケーレンは貴族の使用人の子供で、25年間、軍で働き大尉の地位に就く。彼は軍を退いた後、貴族の称号を得るために荒地の開墾を始める。つまり、ケーレンは、自分が私生児であることに劣等感を感じていて、それを、爵位を得ることで埋め合わせようとしている。
敵役のシンケルは生まれながらの貴族でありながら、非情なロクデナシで、自分を権威付けるために「デ」シンケルと自分を呼ぶように命じる。そして、ケーレンが王権の下に自分の土地を開墾することを恐れている。
つまり、二人とも敵対していながら、どちらも欠落感や劣等感を抱えているという意味では同じなのだ。
開墾と敵対の過程で、ケーレンはタタール人の子供を引き取り、逃亡した小作人の妻を愛し、貴族のシンケルのロクデナシ振りを知る。苦労して開墾に成功した後に爵位を与えられるが、それを拒否する。ケーレンは、身分や財産以上に重要なことに気付いたのだ。
壮大なデンマークの荒地の撮影が素晴らしい。セットや衣装なども当時の様子を忍ばせる。マッツ・ミケルセンをはじめ役者陣の演技と役作りにも説得力がある。
是非、映画館で味わってほしい重厚な作品。
マッツ・ミケルセンの最高傑作。
「アナザー・ラウンド」も「ライダーズ・オブ・ジャスティス」も面白かったし、「007」シリーズ、「インディ・ジョーンズ 運命のダイヤル」も見事にエンタメを楽しませてくれたが、今作品はマッツ・ミケルセンの代表作となる大傑作だ。ただし、敵役の地主の人物造形は客を呼ぶエンタメ要素としては仕方なかったのかもしれないが、ちょっと安易ではあるが、それでも全体を通しては許せる範囲だ。ここ何年かでもお目にかかれないレベルの名画だと思う。私は勝手に脳内変換をして、舞台を日本の明治初期・屯田兵で北海道の開拓に従事したドラマとして「高倉健&倍賞千恵子」のコンビ、もう一つ「三船敏郎&新珠三千代」のコンビで想像して楽しんだ。きっとこれらも名画になっただろうと勝手に思いを巡らせて興奮している。
こんな世界打ちひしがれるわ、ほんとに。。。 しかし素晴らしき大傑作...
題名の通りの内容でした。
さすが、マッツ・ミケルセン!演技も渋いし圧巻!
映画は異文化を知る絶好の機会と言われている。この愛を耕すひともまさに
その一つ。
デンマークの農地開拓史に関する伝記ドラマで、見ごたえがあった。
何よりケーレン大尉を演じたマッツ・ミケルセンの演技が圧巻で素晴らしかった。
彼のこの作品に対しる熱い思いがスクリーンから物凄く伝わった。
マッツ・ミケルセンはアナザーラウンドに続いて2作目だが、彼の演技は渋い!この
一言に尽きる。
観て良かった作品で大変素晴らしい作品でした。
不憫すぎるマッツ
本日3本だて
痛快アクションのトワイライトウォリアーズからのファイアーブランド&愛を耕す人
ヨーロッパの重くて暗い歴史物の2本連続はきつかった
昔は身分の差が激しく庶民の命がこんなにも軽く扱われた現実を映画で観ると毎回憤りを感じます
ディカプリオのジャンゴで腹が立ちまくった記憶が蘇りました
しかしとことん不憫なマッツが悲しすぎた
実話を元にした小説の映画化らしいので是非原作を読んでどこまでが真実なのかを知りたいところです
ちゃんと歴史に名を残せた人だから小説になったんだろうな、と思いたい
不憫な生まれから恵まれない人生を生き、強い意志をもって貴族に成り上がる
そんな目的を揺るがない鉄の意志でやり遂げる様は本当に見事だった
雪の日も血の雨がふる夜も、たった一人でも負けない強い意志
夢を叶える事を原動力として生き、そのために失ったもの
夢が叶った時に夢は夢でなくなり現実となる
生きる原動力が消え果てた時に残ったものは
手に入れた金と権力がいかに虚しいことだったのか
長い年月をかけて彼が悟った人生に必要なもの
生きる意味
結末はあれで良いんだよ
人生で大事なものはお金じゃない
辛くて酷い事柄をマッツで耐え抜く
マッツ・ミケルセン
映画館で予告編が流れまくってたんですが、クサいシーンの連続で、予告編だけで胸ヤケしてしまい、スルーしようと思ってたけど、諸事情で観た(笑)
低い期待値で観てみると、映画本編はクサいシーンばっかじゃなく、暗すぎず明るすぎず、バランス良く、テンポも良い、とても観やすかった。
デンマーク開拓史の話で、実在した人物をマッツ・ミケルセンが圧巻の演技力で演じてます。
アン・バーバラ役のアマンダ・コリンも綺麗だし演技も良かった。
エレン役の人もいいな♪と思ったら『シック・オブ・マイセルフ』に出てた人!クリスティン・クヤトゥ・ソープじゃありませんか(笑)
見違えた(笑)アホっぽい映画でアホっぽい役を演じてたのに、今作は知的で品のある女性を演じてます。
あっという間の127分。
面白かったし名作だと思う、テレビで流してもいいでしょうね。
僕は、もう1回観ます♪
万人に、オススメです。
人間感情揺さぶる壮大なドラマ。
雰囲気はある映画
ラストシーンの切なさに胸が押し潰されそう
ラストシーンの解釈。僕はケーレン大尉の心の中で生き続けるアン・バーバラを連れて(アン・バーバラの姿は幻であり、ケーレン大尉の心象風景)、彼女の行きたがっていた海の見える街へ移ったと確信し、その切なさに涙が溢れてしまいました。何十年もかけ命も懸けて(時には良心をも棄て)掴みとった爵位、名声、安住の生活、それらのすべてを捨ててアン・バーバラの面影だけを胸に海の見える街へと一人で向かったと思ったのです。しかし、映画鑑賞から一夜明け、彼女の短髪を考えると男爵の地位を得たケーレンの嘆願が通り恩赦(釈放、あるいは奪還)された可能性も否定できないという考えも(だとハッピーエンドですね)。
ケーレンとほぼ同世代にあり、孤独を感じることも多い日々を過ごすおじさんとしてはこれ以上身に堪える映画はなかなかないです。
New York TimesやVulture の受け売りをそのままに「驚くほどに美しく、カタルシスに満ちた、感動的な叙事詩」でした。
邦題ダサいけど
2025年劇場鑑賞51本目。
エンドロール後映像無し。
邦題から感じるのんびり感は全くなく、農業的な困難(自然の厳しさ)と戦う映画かと思ったら国の領地を自分の領地だとゴネて通そうとする貴族との血みどろの戦いでした。原題は私生児という意味らしいです。それはそれで生々しいけど・・・。
国王からの依頼でやっている事業なのに、どうしてあの貴族を訴え出ないのか(こいつが裁判官だとしても本国にそれも含めて訴えればいいのに)ずっとモヤついていましたし、最後も嫌なやつすぎてあれでもまだスカッとしきれなかったです。
最後の最後はどうやってああできたのかいまいち分かりませんでした。史実なのですが、ネットでも全く調べられなかったのでどこまでがフィクションかは分かりませんでした。
色々書きましたが、どうやって困難を解決していくか、というのは面白かったです。
全109件中、61~80件目を表示