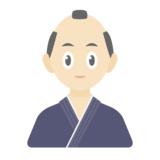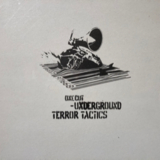オッペンハイマーのレビュー・感想・評価
全766件中、521~540件目を表示
彼らはボタンを押した。多くの人は「優位と破滅は紙一重」と気がつかない。
ある程度は事実関係の知識は持ってたが
その程度のレベルじゃ追いつかなかった。
それでも3時間は長くは感じなかった。
できれば「ネタバレ」を気にせずに
全ての登場人物や内容を押さえておくこと。
それがこの映画を一番楽しめる方法だと思う。
ネタがバレてもカット割までは分かるまい。
全編に渡り監督は問いかける。
手にしてはいけないものの正体を。
権力者は優位に立つことが全てと思い
調査し、策略し、罠を仕掛ける。
「核爆弾」という兵器を作り上げ
名を上げ、金儲けをし、優位に立つが
それが破滅への道と気がつかない。
学者は常に新しいものに挑戦する。
没頭し、探って探って探りまくる。
敵国と競う様にソレを作り上げ
ソレが完成した途端、恐れを感じる
オッペンハイマーの気付きと
アインシュタインの顔が全て。
彼の描いた、とある破滅のシーンは
今ある核を使えば簡単に現実化する。
※
功罪を冷静に観れるか?
科学者の視点で描かれる、研究・発明の苦悩と葛藤。
小さい頃に近所で企画され、親の手を握りしめて見た原爆写真展。そして修学旅行の広島・原爆ドームで改めて実感・体感した悲劇の記憶。幼い時に受けた、あの衝撃的な日本の描写は本作には無い。
だがロスアラモスで行われた『マンハッタン計画(トリニティ実験)』、この実験で起こる事と頭の中にあるイメージが重なる瞬間。まさに息を呑むと言った表現がピッタリ合う。そして数十秒後、思い出したかの様に遅延して襲い掛かってくる現実。
原爆開発の他国間競争、そして時間との戦い。開発している科学者達とは別のベクトルで進んでいく、戦争という誰にも止められない国の暴走。
キリアン・マーフィー演じるオッペンハイマーの乏しい表情は、本人もきっとそうだったと何の疑いもなく受け入れてしまう程のハマり役だった。
本作で広島や長崎への投下描写が無かったのも、オッペンハイマーの視点からすれば納得。それでもほんの一瞬、あの酔っぱらいの嘔吐までの数シーンの描写をオッペンハイマーに絡めて入れてくれたノーラン監督に感謝。人間の想像力を最大限に活用して、あとは個々人に任せてくれた。
そして圧倒的な演技力で本作の主演を奪う程の勢いだったロバート・ダウニー・Jr.演じるストローズ。本作を観るまで知らなかった人物だったが、2つの伏線に見事にやられた。
"赤狩り"や"共産党"の予備知識だけは、鑑賞前に必要かも知れない。
何が良くて、何が悪いのか。何処に所属するとどうなるのか。この時代だからこその歴史背景がわかると、オッペンハイマーが翻弄されてしまった意味もある程度は理解出来ると思う。
(という自分も一回の鑑賞だけでは全く理解しきれませんでした(笑))
日本人の根底にある原爆被害国という意識は一旦横に置いておいて、科学者という1人の人間が戦争に翻弄される人生を擬似体験する3時間。新たな視点で原爆を考えさせられた素晴らしい作品。
ノーラン監督お得意の時間軸、カラーとモノクロで複雑に絡み合うが、絶妙な脚本で混乱一歩手前ギリギリで楽しませてくれた。何度も観たくなる傑作。
見終わったらシワシワ
割と人間ドラマだよと聞いていたがそんなことなかった。ちゃんとプロメテウス的世界を描いていたと思う。映像と主題とが、時間を操作したがるノーランの作家性と(ようやく)うまく一致したのではないか。/キリアン・マーフィもRDJもよかった。RDJに至っては、あとから「あれか!」となる始末。/善悪なんてそう簡単にはわからないこと、未来は予測可能か・コントロール可能か、ということを通して人間というもののダメさと限界を突きつけられ、それは当然こちらに残された宿題になるので、見終わったらシワシワである。
(2024.4.2追記)原爆の惨状を描いてないという批判もあり、そうかもしれないが、それを直接描かなかったのに、原爆なんかにそうそう手を出すもんじゃねえ、と思わせたのがこの映画の凄みではないか。
(2024.4.23追記)原爆の被害の惨状に関する描写についてしつこく考えていて、アジアへの軽視みたいなことも考えたんだけど、それでいうと『バービー』の方がそれを感じたんだよなあ。先のアカデミー賞受賞式でも話題に上がっていた、“そもそも視界に入ってない”みたいな意味で。
うーん、これはさすがに無理があるなぁ。
ノーラン監督の作品はこれまで
なぜか食指が動かず本作が初。
感想を一言でいえば、寅さんの名台詞
「てめぇさしずめインテリだな」
’
わかりにくさは予習を相当したので
クリア。
映画は、天才科学者の光と闇にスポットを当て
時代が変われば世間の評価がガラリと
変わること、核の虚しさ、無意味さ、
「一人を殺せば殺人だが、百万人を殺せば
英雄である」の怖ろしさを描こうと
しているのだと思う。
’
だからゆえ、なるべく社会や政治的背景を
省き、オッペンハイマーに寄せたのも
理解はできる。
後半は、サリエリとモーツァルトを彷彿と
させる対比も有りだろう。
’
けれどことは原子爆弾だ。
政治的駆け引きの中ですべて行われた大惨事、愚行を
天才の内省だけで追いかけるのは、やはり片落ち
だろう。
’
せめてパート1,2と分けてもっと歴史も含め
綿密に描いて欲しかったなぁ。
’
ノーラン監督の目的はただ一つ 単なる一時の娯楽として映画を観に来ただけの大衆に、核兵器使用の恐ろしさについて強制的に自分の頭で考えさせることだったのです
オッペンハイマー
2023年7月米国公開
被爆国の日本では2024年3月公開と8ヶ月遅れたのはご存知の通り
その理由もここのレビューでも渦巻く被爆国としての特別で複雑な感情があるからです
広島長崎への原爆投下を描いていない
その被爆の惨状を描いていない
その後も続く原爆症も描かれていない
これに尽きるかと思います
本作への激烈な反発が日本中で沸騰するかも知れない
もしかしたら日本の上映館や配給会社へも抗議が殺到するかも知れない
下手をすると不測の事態も起きかねない
そう考えだすとなかなか日本公開の決断をするのは勇気がいったはずと思います
結局、アカデミー賞を総ナメするほどの海外での高い評価が後押しになり公開されたのもご存知の通り
日本公開から3ヶ月経ちました
日本での反応は予想通りのものでした
しかし、とても冷静な受け止め方で心配されたような事態は何も起こりませんでした
自分も早々に観に行きました
でもなかなかレビューする気になれませんでした
なにかモヤモヤする
それが言葉に纏まらないのです
結局、皆さんと同じなのかも知れません
先に挙げたことが引っかかっているだと思います
でも違う
実はノーラン監督に見事にはめられているのではないか?
それもこれも全部ノーラン監督の思う壺だったのではないのか?
私達はノーラン監督の計算通りの反応を示していただけではないのか?
やっとそこに思い至りレビューを書く気になりました
ノーラン節というものがあります
それが何かと説明せよとなるとこれは難しい
でも確かにノーラン節というものはあるのです
本作に於いてもあります
例えば時系列を複雑にして構成するというノーラン監督作品の特徴は本作でも踏襲されています
何故、そのようなことを毎作やるのか?
何故、複雑に時系列の操作をやるのか?
何故、誰もがすぐに理解できる平易な時系列の構成にしないのか?
そこに答えがあると思います
時系列が複雑になると私達観客は考えなくてはなりません
そんなに難しい作業ではないのですが
これがこうなってこういうことなのかという頭の回転が常に上映時間の間ずっと続くのです
するとどうなるのか?
普通の時系列であると、上映中の間私達は実はなにも考えていないで観ているのです
単に筋だけを追って、エンドマークがでたら、「あーおもしろかった」か「まあまあだな」とかのただの表面的な感想だけが残るのみなのです
それをノーラン監督は嫌っているのだと思います
強制的にでも私達観客に映画の内容について考えさせようとしているのだと思うのです
複雑な時系列を、観客の頭の中でそれぞれが自分に理解できる形に再構成しなおす作業をさせ続けると、観客は作品のテーマやメッセージについても否応なしに考えざるを得なくなるのです
それが監督の主張するところと同じものになるかも知れませんし、監督の狙い通りのものではなく観客の独自の考えになるかも知れない
いずれにしてもノーラン監督の作品を観て、その作品のテーマについて自分の考えがまとまって行くのです
すると自分の頭で考えたことは自然と人に話たくなるものです
映画館の帰り道のカフェや居酒屋やバーで、あるいはSNSでべらべらと作品について自分はこう考えると語りだすのです
その内容は俳優がどうだったとか、映像が綺麗だったとか、音楽が良かったとかそんなことではなく作品の主張するテーマやメッセージに対して自分はこう思ったというものになっているのです
それこそがノーラン監督の狙いであって、それこそがノーラン節と呼ばれる物の正体なのだと思います
ノーラン監督は本作を原爆をテーマに映画を撮るにあたり、21世紀に於ける核戦争の危機を全世界の観客に通り一辺の核戦争反対の映画を観せることでは不十分だと考えていたと思います
観客それぞれに、原爆について自分の頭で考えさせたかったのだと思うのです
それ故に敢えて広島長崎の原爆投下シーンをみせなかったのだ思います
原爆投下シーンと被爆の惨状
それは普通の監督ならそれを映画のクライマックスにしようとしたはずです
観客もそれを期待して観に来ることでしょう
しかしそれをわざと見せないことで観客自身に想像するように仕向けたのです
原爆が実際に都市に使われたときどうなってしまうのか?
核の炎の下に何十万人の人間が暮らしていたならどんな地獄になったであろうか
観客自らの頭で考えさせようとしたのです
原爆投下は広島長崎だけに起きたことではなく、これから世界のどこの都市にでも起き得ることなのだ、つまり自分の住んでいるところのことなのだと考えさたかったのだと思うのです
だから原爆投下のシーンの代わりに、ドイツ軍のV2号ロケットが米軍の重爆撃機のはるか上空を何発も夜空を高速で通り過ぎて海を越えてロンドンに向かうシーンがあるのだと思います
あのミサイルの弾頭にもしも原爆が仕込まれていたなら?
いやそれは現代では普通のことなのだ
そう観客に考えるようにした思考の補助線のシーンであったと思います
何発もの原爆が自分住むの都市に雨のように降り注ぐのだと想像できるように
いつも通り複雑な時系列でなぜそうなったのかを観客に主体的に考えさせる
さらに原爆投下と被爆の惨状を敢えて見せない
その事で観客をフラストレーションに陥れる
仕方なく観客は自分自身でそれがどんな映像になるのかを想像する他なくなるのです
そうすることで観客は原爆投下について、核兵器の使用について、個々人、人それぞれなりに様々に考えだすのです
そして映画を観終わったあとその各自の考えを友人や家族にベラベラと話だすのです
SNSに書き込むのです
原爆=核兵器の恐ろしさ
その使用がどんなに恐ろしいことなのか
そのような考えが観客の何倍にも広がるだろう
ひいては世界中人々の考えとなることにまで持っていきたい
それがノーラン監督の本作での最大の目的だったのでないでしょうか
ノーラン監督のその目論見は計算通りに成功したのです
観客は自らの頭で考えたかのように口々に、原爆投下の凄まじい被害を描いていない!と言いはじめたのです
被爆の実態から目を背けている!
実はノーラン監督がそう観客に批判を言わせるように仕組んでいたのも知らずに
ノーラン監督の目的はただ一つ
単なる一時の娯楽として映画を観に来ただけの大衆に、核兵器使用の恐ろしさについて強制的に自分の頭で考えさせることだったのです
世界中の観客がまんまとそれにのせられていたと思うのです
その結果がアカデミー賞総ナメということになりました
つまりノーラン監督の目論見は大成功したのです
観客一人一人に自主的に考えさせることに成功したのです
だだひとつ問題は、そんなことをしなくても日本人だけはそれを考えることができるということです
しかしノーラン監督はそれをわかっていたと思います
それでもお気楽に本作を一時の娯楽として観にくるであろう世界の大多数の大衆に考えさせることを優先したのだと思うのです
広島長崎への原爆投下を描いていない
その被爆の惨状を描いていない
その後も続く原爆症も描かれていない
私達がそう思い本作を批判するのは当然なのです
私達日本人は原爆=核兵器を使用することの絶対禁忌をわかっているからです
しかし、米国やそのほかの世界の国々の人々が被爆国の日本と同じわけではないのです
彼らにどれほど重大なことなのか
それを自らの頭で考えて貰うためにあえてこのように撮られていたのです
2020年の前作TENETでは、ノーラン監督は歴史の逆行を阻止しなければならないと、私達観客に考えることを要求しました
そして本作ではノーラン監督は、核戦争の阻止を訴えているのです
ウクライナ戦争で、プーチンは核恫喝を実際に行いました
戦闘機に核爆弾を外部から見えるように搭載して欧州に向けて飛行させたのです
そしてつい最近では、核兵器の使用訓練を実際に行ったのです
そのことを単に非難する映画を撮ったところでそれは反ロシアのプロパガンダ映画だと言われるだけです
世界中の人々が自らの頭で考えた結果、そんなことを絶対に許さないという考えを持つこと
それが本作の目的だったのです
昨年、広島に旅行して、原爆ドームと平和記念資料館にいきました
平和公園の原爆死没者慰霊碑には「安らかに眠って下さい 過ちは繰返しませぬから」と刻まれています
誰が?
それは世界中の人々がそう思わなければ達成できません
本作をみて、何かを考えること
それが過ちを繰り返さないことの努力の一つであることには間違いないと自分は思います
アカデミー賞を総ナメにするのは当然だと思います
原爆開発者の苦悩の軌跡が見事に描かれている!
最初の核爆発の轟音と振動に、肺腑をえぐられるような恐怖感を味わいました。それは水爆の中から生まれてきた山崎監督のゴジラの咆哮と同じように聞くものを揺さぶり、恐怖に落とし入れる感覚に不思議な一致を感じました。アメリカ側から見た第二次世界大戦の終結を急ぐために、降伏を拒む日本軍部の頭を切り替えさせるために原爆を落としたという理屈を聞くと、とても悲しい気がしました。アメリカ人は当時広島、長崎への原爆投下されたばかりの頃、正義の鉄槌を日本に加えたと捉え、熱狂的にオッペンハイマーの実績をたたえていますから、戦争の正義ほど無意味なものはないということが、身に染みてわかります。アメリカは日本とドイツに原爆を落としたかったそうですが、ヒットラーの自殺でドイツでは起きませんでした。そんなふうにして歴史を俯瞰してると、広島と長崎の不幸が軽んじられるような気がしてならないのは私だけでしょうか。人類が犯してはならない原爆の使用は、この映画を見ている限りは、当時のアメリカの大統領の心の中にサタンが居たとしか思えません。むしろオッペンハイマーは、原爆を開発する使命を帯びて、この世に生まれてきただけで、それを忠実に実行したにすぎないと私は思います。この宇宙には善も悪もありません。ただ川の流れのように、歴史はあるがままに進んでいきます。誰もそれを阻止することができないものかもしれません。ただ、3次元の世界では、物理学300年の歴史が核兵器を誕生させたというのが否定できない事実なのです。それを担ったオッペンハイマーは幸せだったのか不幸だったのか。そのことを一人ひとりに考えることを促す名作だと思います。そして付け加えれば、日本の立場から描かれる原爆を描いた映画の上梓を切に望みたい。
もっと分かりやすく、短くはならなかったのか
予備知識を蓄えてから見に行こう
不思議な映画でした。正直にいうと、あんまり響いてこなかったです。
退屈はしなかったし面白くないとは微塵も思わないし、むしろとてもスリリングで長尺も感じることなく、やや前のめりで観られたのですがノーラン映画特有の時間軸の入り乱れ方が正直不要なものに思えました。
演出もあまりにも大仰すぎてオッペンハイマーに感情移入できる映画にはなっておらず、もっと客観的に社会的な出来事と、自分がやるべき仕事と、自分の周辺の人間関係をどういう意図で選び、進んでいったのか、その原動力やその根底にある思考をもっと知りたかったし、理解したかったです。
原爆描写うんぬんとは全く違うポイントで、ここ数作のノーラン映画に気持ちが乗らない自分を感じています。
時系列の操作など、ノーラン的映画手法に満ちていることを理解したうえで鑑賞したい一作
原爆開発の中心人物として著名なロバート・オッペンハイマーの、原爆開発前後の動向を描いた作品です。
しかしクリストファー・ノーラン監督は、もちろん本作を典型的な伝記映画の枠組みにはめ込むようなことはしていません。本作においてノーラン監督は、オッペンハイマーの人生を様々な時点で分断し、つなぎなおしています。時系列が前後し、カラーとモノクロームの映像が錯綜する物語は、たとえオッペンハイマーの経歴を予習していても、把握することは極めて困難でしょう。「オッペンハイマーの伝記映画」あるいは「原爆開発の過程を追ったドキュメンタリー的な作品」を期待してしまうと、確実に混乱してしまうことになります。つまり本作は、まぎれもなくノーラン監督作品、さらにいうなら彼の作品群の現時点での集大成です。
本作が原爆(核兵器)についてどのように認識しているのか、非常に気になるところですが、作中では軍や政府の決定をやや批判的に描いているものの、核兵器の功罪について明確は立ち位置は示しておらず、広島、長崎の被害についても踏み込んだ描写は避けています。
未だ原爆投下について世論が割れている米国社会の現状を踏まえるとやむを得ないとも言えますが、オッペンハイマーが原爆投下の状況を幻視した際の一人の女性の表情、そしてその役を演じているのが誰なのかを踏まえると、ノーラン監督のメッセージは自ずから明らかとなるでしょう。ロスアラモスの「あの瞬間」もまさに圧倒的な迫力ですが、終盤のオッペンハイマーの幻視もまた、よく注意して観てほしい場面です!
集中力が途切れてしまった
これほどまでの質で作品を作り上げたことには称賛、納得
正直、めっちゃ難しかったです。それは中身が難解とかいうよりも、構成があまりにも入り組んでいて、しかもそれが長い・・・前半は我慢がかなり必要でした。表現も過剰に感じるし、劇的演出もかなり感じるので、伝記ものと捉えて鑑賞すると違和感を覚えるかも─。ただ、後半の怒濤の展開で、劇映画としての面白さを存分に堪能できました。ただでさえ質が良いのに、それがまたさらに上をいっているという画質と音響、プラス演者のパフォーンマンスは言うまでもなく─。ロバート・ダウニージュニアがネットニュースになってしまうほどの名演を存分に楽しめたし、キリアンー・マーフィーから脇の面々含めすべての演技もまた画質や音響に負けないくらい強烈でした。
空高く伸びる炎には悲しみしかありませんでしたが、核兵器どうこうとか原爆の父がどうこうとかというか、そういった方向性は意外と抑えられていた印象です。確かに、礼賛や苦悩といったことは描かれていたものに近かったんだろうし、決して手放しでアメリカンパワーを肯定しているわけではありませんでしたけど、核とか原爆への焦点をうまい具合に別の方向へと変えられていたように思います。それが良いかどうかよく分かりませんが、自分はそのおかげでこの作品が見やすくなっていたと感じました。
長いから嫌だなぁと思っていたのですが、意外と一気に見切ったという印象です。
オッペンハイマー核を作った男
いままで核を誰が作ったのか
知りたいとも思わなかった
が…
今回この作品で
核を作る経緯そしてその人物を
知ることが出来た
大いに脚色されていると思うけど。
全体的に公聴会でのやり取りで
回想を交えての会話劇の様
この作品の中で核実験で爆発と数秒間
遅れて爆発の音、爆音が鳴り響いたとき
は痛かったですね
“痛さ“を感じました
その時のアメリカの人たちの
お祭りのような歓喜あふれる
情景が辛かったですね
原爆で皮膚が剥がれていく
様子と人が焼き焦がれ
足に黒い物体がまとわりつく
オッペンハイマーが想像する
核の怖さの表現はよかったと思います
最後にアインシュタインと会話した
言葉が印象的です
作りたくて作った原子核
戦争で兵器として使用され
…産みの親として
思い悩み苦しむ様は計り知れない
吹替えがなく字幕で観ましたが
聴聞会の詳細が分からない
…核を作った男
オッペンハイマーに焦点をあてた作品
観てよかった
吹替えがでたら…もう一度。
と思ってますが
制作者の想いのごく僅かしか受け止められなかった
開発者の責任は?
学術的に有意義な成果が戦争の絶対的な兵器と成る事への開発者の責任はどこまて有るのか?
開発者とその兵器使用の権限者とそれぞれ、大きな責任がある。
アメリカが広島、長崎に使った原爆は世界大戦の早期終結の為に使用で多くの戦死を産まない為に正当化されて居る。
表面的なご都合主義の正当化は良く無いと思う。
2発の原発で亡くなった方々は民間人であり、その数は大きな誤算があったと思う。
オッペンハイマー氏の水爆開発否定の行動は、人間として当たり前の行動であったと思うし、ここで使用を止める事が出来なければ人類を含む多くの生物は死滅し、地球環境が大きく変化し、地球破滅へ進むしか無い事が判明して居る。
人類による地球の破壊は神に許される事であろうか?
人間世界の不条理を見直す事で、これ以上の生物の死滅を避けて欲しいものである。
つくづくこの想いが浮かんで来た。
文句なし!緻密さが際立っていた作品
文句なし!緻密なストーリー構成とこの伝記を映画作品にするノーラン監督の熱意をスクリーンから感じた。
広島、長崎の原爆被害者記述は某国営放送の番組でのノーラン監督インタビューやオッペンハイマー特集でも原爆被害者を描いていないと某国営放送アナウンサーの質問もあったが、これはネタバレになるので詳細は省くが、これは作品のあるシーンで上手く対比している。ここもノーラン監督の緻密さが見事。
この作品のポイントをまとめてみる。
1.観客に問いかける映画
上映が終わった後ふと思ったが、TAR、福田村事件を観た時も感じたが、観客に監督から問いかけられた気がしてならない。
2.俳優の演技は文句なし!
オッペンハイマーで一番評価したいのは出演俳優。キリアン・マーフィーやロバートダウニーJRら出演俳優の演技が素晴らしかった。アカデミー賞で出演男優、助演俳優賞も納得した。
3.1人称で通したのも素晴らしい
もう一つ評価したいのは1人称。ノーラン監督のインタビュー記事を見て知ったが、なるほどと感じた。これも評価したい。
4.時間軸をいじるのは健在
時間軸をいじるのはノーラン監督の十八番だが、今回もさすがと唸らされた。
確かに原爆への言及はあるが、それ以上に戦後アメリカの赤狩り騒動がここまで凄がったのも印象に残った。
アカデミー賞作品賞を含め七部門受賞も゙納得できる。
見事すぎる伝記作品だった。
オッペンハイマーはある程度調べておくといいが、観る当日は色々感情もあると思います。しかし、一旦忘れた方がいい作品です。見事。
政治的に無垢なピエロ的悲喜劇 -- 歴史的知識抜きに理解するのは難しい
Robert Oppenheimerの個人に焦点をあてており、興味深かった。
ただし、個人的な描写で欠けていると思う点は3つあります。
1 自分より才能が劣った人間を見下し軽蔑する横柄な人柄であったこと。
( 弟Frankの証言) ストローズに『卑しい』仕事と発言したことでのみ描いている。
2 第1級の業績を上げられずノーベル賞に届かないため、劣等感を抱えていたこと。 その代わりとして原爆開発に邁進する俗物的野心家の面があまり描かれていない。
3 原爆完成後、『権力中枢に接近し、悦に入っていた』側面が描かれていない。 (A. Pais "Subtle Is the Lord"など周辺の物理学者の証言)
核開発、核戦略、冷戦、赤狩り、国家と科学者、軍産複合体など多くの側面がある。科学者も多様で、ナチスが降伏したので核開発は無用とラスアラモスから去った物理学者Joseph Rotblatがいた。他方京都への原爆投下を強硬に主張するNeumannなどもいた。
最後に、『原爆が戦争の終結を早めた、戦死者を少なくした。』という言説について。
議会の承認なく秘密裏に原爆開発をしていた(副大統領のトルーマンにすら知らせれていなかった)ため、もし原爆を使わなければ何のための膨大な予算執行かと政府の命取りになるだろう。(開発費用は日本の国家予算を上回っていた。)それゆえ、そもそも原爆を使用しない選択肢はなかった。しかし、投下後予想されるアメリカ国民からの道義的責任追及から逃れるための方便こそ、『原爆が戦争の終結を早めた、戦死者を少なくした。』という理由づけであった。後付けの方便が真実のように独り歩きし定着してしまったのである。アメリカ軍部内には、陸軍・海軍の貢献を原爆によって横取りされてたまるかという反対論もあった。
いっぽう、日本政府・軍部は、1945年4月頃から、ソ連を通じて終戦交渉を模索していた。分割占領を主張していたソ連を通じて外交交渉を行うなどインテリジェンスや外交は完全に破綻しており無能であった。天皇制護持にこだわり続け、ぐずぐずの終戦交渉も原爆投下の一因であった。
蛇足ついでに、物理学者が核開発後に核戦略など政治に口をだすと手ひどいしっぺ返しを食らうのは、アメリカに限ったことではない。ソ連の水素爆弾開発の主要人物サハロフしかり。核政策に反対した結果、国内流刑、科学者仲間からの無視と疎外、家族への差別的取り扱い。これらは、『サハロフ自伝(回想録)』に詳しい。
全766件中、521~540件目を表示