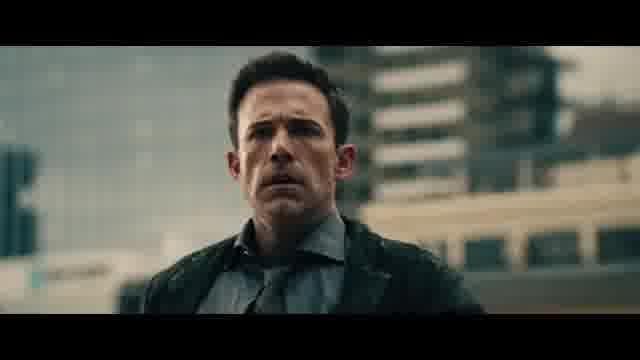「荒唐無稽に見えてその実、ロドリゲスにとって身近な題材とテーマで固められた「私的」な映画。」ドミノ じゃいさんの映画レビュー(感想・評価)
荒唐無稽に見えてその実、ロドリゲスにとって身近な題材とテーマで固められた「私的」な映画。
なんか、出てくる「悪の組織」の格好にすげえ見覚えがあると思ったら……
『東京フレンドパーク』じゃないか!!
どうりで、関口宏って昔からどっかヤバそうな気がしてたんだよ、俺……(笑)。
ロバート・ロドリゲスが、柄にもなくフィンチャーやシャマランやジョーダン・ピールみたいな、どんでん返し系のネタ映画にイッチョ噛みしてきやがったと、最初にこの映画の宣伝を目にしたときにはちょっとびっくりした。
でも、いざ足を運んで実際に観てみたら、最終的にやってることはいつも通りのロバート・ロドリゲスで(もろ、B級ウエスタンのパロディですよね、あのラストって)、大いに安心した次第(笑)。
全体にそこはかとなく漂う拭いがたい「B級感」というか、
シャマランやピールのような緻密さを欠く「いい加減」さというか、
過剰な設定に視聴者がついてこられなくても別にいいやといった調子で話をどんどん進めていってしまう「居直り」ぶりというか、
そういったゆるくて投げ槍な部分もひっくるめて、いつものロバート・ロドリゲスのまんまだったとでも言いますか。
ロバート・ロドリゲスって、『エル・マリアッチ』(92)や『デスペラード』(95)で颯爽とデビューしてきたときから、基本中身はクッソ面白いんだけど、総じて雑なつくりの映画を毎回「ほぼ確信犯的に」作ってきた印象がある。
それを、ジャンル愛で押し切って、「アミーゴ、あんたもこういうおバカなB級映画大好きだろ?? 俺っちも好きで好きでしょうがねえんだ。だから気楽に楽しんでくれよ」という内輪ノリでテキトーに納得させてきたっていう。
要するに、立ち位置としてはクエンティン・タランティーノの弟分で、作ってきた作品もどれも快作揃いなのだが、「愛するトラッシュ・ムーヴィー群」に由来する本質的なゆるさ、バカっぽさ、過剰さ、適当さを、あまりブラッシュアップさせないまま、いままでやってきちゃった感じはどうしてもするんだよね。
そんな人が作った「ネタ映画」なので、「この手の映画が得意な監督たち」が計算ずくで仕掛けてくる周到なやり口と比べると、どこか語り口に雑さがあって、面白いは面白いけど、観ていてどうも腑に落ちない部分が多い点は否めない。
一番の問題は、観客が今までの現状に得心が行く前に、語り手側がどんどんさらなる不可能状況を積み重ねたり、過剰な謎解きを勝手に進めてしまうせいで、語られていること全体に「胡散臭い」イメージが付きまとってしまう点にある。
すなわち、製作サイドからすると「実はこういうことでした!」という真相の設定を明かしているつもりでも、ナラティヴがうまくないせいで、その真相までが嘘くさいというか、おバカなインチキ話のようにしか思えない。
これは、あまりよろしくない状況だ。
『ドミノ』の情報呈示は、性急すぎるんだよね。
こちらが今何が起こっているかを把握する前に、バンバンネタばらしをしてきて、それを観客がなんとか理解しようと努力しているあいだに、さらにそのネタを膨らませたり、ひっくり返したりしてくる。
しかもその内容が、世の中の一般的な感覚でいえばいかにも「トンデモ」で「陰謀論っぽい」「インチキ臭い」話であるために、製作側がマジでこんなバカな話を「真相だ」として話を進めようとしているのか客も半信半疑のうちに、きわめて荒唐無稽なホラ話が途方もない次元にまで広げられてしまう。
要するに、作り手が用意している「虚構」に、観客がアジャストしきれないのだ。
この映画、邦題こそ「ドミノ」とつけられているが、原題は「ヒプノティック(催眠の形容詞形)」だ。
だから、観客は最初からこの話が「催眠」絡みの話であることは理解している。
すなわち、この物語のナラティヴが必ずしも真実とは限らないこと、主観によって現実が歪められている可能性があること、催眠状態でウソがホントにすり替えられるあたりに、本作の「核心のネタ」が秘められているらしいことは、織り込み済みの状態で観劇をスタートしている。
この物語で描かれていることの、どこまでが「リアル」で、どこまでが「ヴァーチャル」なのか。
そこで一番重要となってくるのが「もっともらしさ」だ。
「偽の世界観」を上書きする「真実の世界のルール」が、偽のルールより「もっともらしくなければ」観客は納得してくれない。
『ドミノ』の作り手は、ここの「もっともらしさ」を醸成する手順が荒っぽいのだ。
だからお話の全体が、陰謀論者の唱える「真実」のように、胡散臭く、納得しがたい。
真相を明かされても、「えっ? 実はそうだったの? うわっ、やられた!!」って気分にあんまりならない(笑)。むしろ「ねーよ、そんなアホな話ww」って気分になっちゃう。
あと、この映画に出てくるヴィランって、いかにも『JOJO』に出てきそうな能力者で魅力的なんだけど(手順は違うが、これ岸辺露伴のスタンドに結構近い能力だよね)、せっかく面白いキャラなのに、やっぱり映画内の出し方がてんでダメでもったいない。
タメもないままにいきなり出したうえ、えらく軽い扱いで……いくらでももっとラスボス感を出せたはずなんだが。
いやまあ、ロドリゲスからすれば、こういう「ねーよ、くっだらねー(笑)」って感覚自体がまさにやりたかったことなのかもしれないけど。本質的には「おバカ映画をシネフィルの立場で再生産する」ことこそが彼の本願であって、必ずしも「出来の良いどんでん返し映画」を作ることがモチベーションではなさそうな気もするし……。
でも、おんなじことやるにしても、もうちょっと「バカっぽく」なく作ることはふつうに可能だったとも思えるんで、やはり「もったいない」気分にはなっちゃうんだよなあ。
― ― ―
パンフを観る限り、ロバート・ロドリゲスはヒッチコックの『めまい』に影響を受けたと主張している。映画評論家の尾崎一男氏は、類似作としてブライアン・デ・パルマの『愛のメモリー』(76)と『フューリー』(78)の名前を挙げていて、なーるほどと。
他にも、似た傾向を持つ映画を挙げだしたら、おそらくきりがない。
ヒロインと主人公の関係性と逃避行、敵の正体などは『未来世紀ブラジル』(85)ともまあまあ被る気がするし、子供探しのサスペンスがいつの間にか明後日の方向に肥大して壮大なホラ話へと転じていく構造は、あの怪作『フォーガットン』(04)とも似ているかもしれない。ダニー・ボイルの『トランス』(13)も、観たことのある人は『ドミノ』と関連して必ず思い出しそうなネタを扱った映画だ。
超能力バトルものの古典としては、『メデューサ・タッチ』(78)とか『スキャナーズ』(81)とか。『AKIRA』(88)でも、能力者同士の技の掛け合いを描いた名シーンがあったかと。
あと、あまりいうとネタバレになりそうだけど、本作の基本構造は84年にドリュー・バリモアが主演した某映画を祖型にしたようなところがある。
もちろん、この手のネタ映画としては、「ア」で始まる映画とか、「シャ」で始まる映画とか、さらに遡れば「トゥ」で始まる映画とか、「マ」で始まる映画とか、いろいろ前例となる作品は挙げられるだろう。
自ら●●した○○を知らずに追い求めるという意味では、「エ」で始まるホラー映画や、「メ」で始まる映画あたりも、祖型と言えば言えるかもしれない。
だいたい、この映画でやってることって、昔の中国の武侠小説とか日本の忍法小説とかで、幻術士が水とか火の幻影を見せながら繰り広げていた幻術バトルと変わらないし、ラストのオチにしても、落語の怪談とか昔噺によく出てくる「酒池肉林の宴を繰り広げたが、朝になったらそこは荒れ寺の墓場で、どこからか腹鼓の音がポンポンと……」といったネタとも似たり寄ったりな気がする。いわゆる「王道」の化かし合い映画ではあるんだよな。
(以下、ネタバレに近いことが書かれているので、未見の方はご注意ください。)
というわけで、たしかに本作には、何かしらの影響を及ぼしたかもしれない先行例はたくさんある。そりゃそうだろう。
だが、もしかすると本作のアイディアは、本当にロバート・ロドリゲスのとても身近なところから勝手に湧いてきたのかもしれない。個人的にはそう思っている。
なんでかっていうと、ロバート・ロドリゲスって、故郷近くのテキサス州オースティンに、自前のスタジオを持ってるんだよね。
今回の映画も、そこでほぼ全部撮っているらしい。
もともとは、ロスで2020年に撮るはずだった映画らしいが、コロナウイルスのパンデミックのせいで18か月延びて、オースティンのスタジオで撮ったとのこと。
(今回のセットはすべて『アリータ:バトルエンジェル』(18)のを流用したらしい)
それって、まさにラストの「アレ」じゃないですか。
あの終盤の解明シーンって、ある日、自分の王国であるスタジオで、書き割りの街を前に見ながら「これ自体を使って何かできねーかな」って思ったのが最初だったんじゃないの?
(いや、単にそうだったら、面白いのにな、という程度の話ですがw)
たとえそうじゃなかったとしても(2002年に脚本を書き出した時点ですでに思いついていたアイディアだったとしても)、このラストのネタって、やっぱり自分の映画製作の現場で湧いて来た「生のアイディア」だった気がするんだよね。
仮想現実だ、虚構空間だっていうけど、目の前にあるこの書き割りの街こそが、まさにそれじゃんと。映画作りながら、いつもはウソをホントに見せかけてるこの張りぼての街を、逆に主役みたいにして映画を撮れないもんだろうか?、と。
そう思ったんじゃないだろうか。
そもそも、ロバート・ロドリゲスはこの十年近く、ルーカス・フィルムでVFXメインの映画製作の現場をずっと踏んできている。実際『シン・シティ』(05)は、ほぼグリーンスクリーンの前で撮影されたらしい。すなわち、ありもしない空間で「そのつもりで演技する」ことを役者にオーダーする側に、ロドリゲスはずっと居たわけだ。
要するに、ロドリゲスが日々やっている映画製作の営為そのものが、どっぷりと「仮想現実」の世界に浸かりきったものだった。「本当はそこに誰それが立っている体(てい)でやってください」「ここが拘置所の体でやってください」みたいなのは、それこそ毎日出している、もはや当たり前の指示だったはずだ。
この映画で、ベン・アフレック演じるダニー・ロークが経験する悪夢的な異常体験は、ロドリゲスにとってはむしろ「日常」なのであり、現代に生きる映画人が日々体感している思い切り「身近なネタ」なのだ。
しかも、この映画の本質は「ファミリー・ムーヴィー」だ。
家族の結束と、再生をテーマに掲げる映画。親から子へと受け継がれた特殊な能力をいかに生かして、家族一緒に頑張っていけるかを探っていく映画。
それって、まんま『スパイキッズ』じゃん。
ウエスタンの流儀で、悪漢から家族を守り抜こうとする姿は、いつもテンガロン・ハットを手放さないロバート・ロドリゲス自身の姿ともダブって見える。
そういえば、この作品もまさに4人の子供たちをスタッフ(プロデューサー、作曲家、アニメーターとしてそれぞれ参加している)に迎えて作り上げた映画だった。
目の前にあるセット。書き割り。バミったテープ。指示の殴り書き。
日頃から慣れ親しんでいる「ヴァーチャル空間を脳内で認識する」感覚。
外から人を操り、演技させ、演技者もまたそれを現実であるかのように自ら言い聞かせるような「監督と俳優」という仕事。
才能をもった子供たちをどう育て、どう親が共同作業を構築していくかというテーマ。
『ドミノ』は、一見すると猛烈に荒唐無稽で浮世離れした物語に見える。
しかしその実、映画製作者にとっては(少なくともロドリゲスにとっては)、想像以上に現実と地続きで、「手垢のついた」題材を扱ったつもりの映画なのではないか。
監督にとって、身近で、大切で、喫緊のテーマと素材だけを集めて作り上げた、きわめて私的でインティメットな映画なのではないか。
そう思うわけだ。