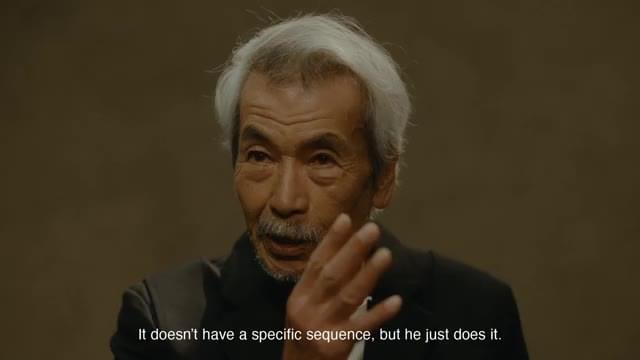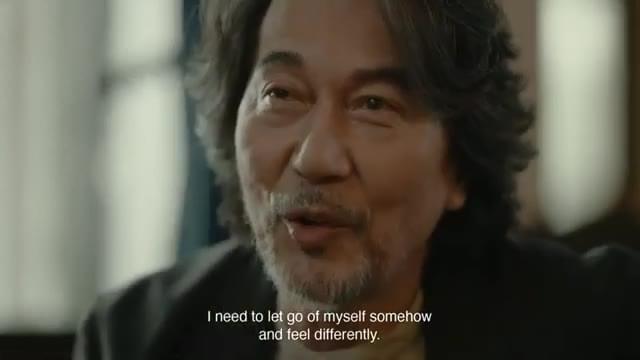PERFECT DAYSのレビュー・感想・評価
全1018件中、221~240件目を表示
アナログおじさんの日々
カセットテープを聴いて
文庫本を読み
フィルムカメラで写真を撮る。
当然ガラケー。
小さなアパートに独り住まい。
キッチリ仕事して
銭湯でひとっ風呂あびて
いつもの店で一杯やる。
そんな日常がつづられていく。
ずっと【お一人様】
だけど
一杯やる飲み屋も
フィルムを現像に出す写真屋も
文庫本買いに行く古本屋も
みんな古い付き合い
気心のしれた人々が沢山いる。
孤独じゃない。
そんな生活が心地いいんでしょうね。
特に説明はないけど伝わってくる。
そう、説明がほぼ無い。
それが良いのかも。
こういう生活にいたる経緯とか
全く出てこない。
若い頃の回想シーンとか
やりたくなりそうだけど
無いのがいい。
なんというか
無くていい、無い方がいい。
つまりは
そこは大事じゃない。
どうでもいいってこと。
ということを見てて感じた。
「今度は今度、今は今」
ってセリフがあった。
そういうことなんだよね⁉
役所とヴェンダースの凄さ
淡々としてる作品を少し寝不足で観に行くのは少し心配でしたが、全然大丈夫でした。
最初はすこし眠いと思いながら観てはいましたが、もう五分もすると役所広司の演技、表情、所作から目が離せませんでした。
昔はこういう映画はヨーロッパとかを舞台に描かれていたのではと思いつつ、東京を舞台に描くのはヴィム・ヴェンダースが日本好きだからか、日本の文化が世界的に認知されたのかとも思って観てました。
この作品も役所広司ありきの作品だと思いました。
その極みなのではないでしょうか。
画もとても美しいというのとは違う、凄みある画でした。
あのアスペクト比もなかなかもって、イカすエモい良い演出でした。
トイレツアーは行ってみたいです。
植物
都会の生活なんだけど
緑がよく出てくる。
同じ日常をこなしながら
小さな楽しみを見つける。
関わる人との距離感を守って
暮らす。
少しづつ
友達の緑を増やして育てる。
普通ってなんだろとか
思う歳になる頃
完璧な日常ってタイトルからくる
この内容は
年月を歩んだ者に
響くのかも。
自分の人生を豊かなものにできるかどうかは本人次第なんだと強く教えら...
退屈と出るか?感銘受けるか?
清掃
変哲もない1日なのに何故このタイトル
主人公が愛でる個人的空間
静かな映画。おんぼろアパートに一人で住む初老男性が主人公。仕事は都内の公衆トイレを巡回掃除すること。趣味は、部屋で植木を育てることだ。ずらりと小さな鉢が並んでいるのは壮観だが、それらはまだ、背が低いので、こういう生活を始めて、まだそんなに日数が経っていないことを思わせる。朝、箒で掃除をする音で目覚め、歯を磨いて植木に水をやり、階段を下りて、仕事に行く。それが終われば、浅草で夕ご飯を食べ、銭湯へ行き、ときには、飲み屋でいっぱい。そして、寝る前に少しの読書……ほとんど他人との交わりがない、個人的空間で過ごす。これが、主人公の一日である。突然、姪が訪ねてきたり、ほんのり好意を寄せている飲み屋の女将が素敵な男性と抱擁しているのを垣間見て動揺したりもするが、それは一過性のことであり、基本的は同じことの繰り返しである。そんな主人公の過去はまったく明かされない。トイレの使い方がわからない外国人女性に英語で教えてやったり、高級車に乗ってやってきた妹との対峙で、かすかに彼の背景を想像するしかない。ある意味、過去を捨てた男なのだろう。捨ててしまったから、逆に失うことを恐れていないのかもしれない。それが証拠に、彼は出かけるときに施錠をした様子がない。盗まれて困るものなどないからなのだろう……と思ったのだが、姪が転がり込んできた際には、「開錠」する描写があるから、やはり鍵はかけたようである。それとも、姪の持ち物は大事であったか。それとも、姪との個人的な空間を他人におかされたくなかったのだろうか。そう思えば、トイレも非常に個人的な空間だが、やはり、施錠する描写はない。主人公は、ふたつの個人的空間を愛しているように思えてならない
ものすごく乱暴なレビューを書きます
ものすごく乱暴なまとめ方をする
今作はキャラ萌え日常系映画だ
「◯◯な趣味をやらせてみた」ではないものの『ゆるキャン△』や『けいおん!』の仲間である
主人公はトイレ清掃員・平山
早朝から仕事に向かい、明るいうちに終えて銭湯で汗を流す
さっぱりしたら行きつけの酒場でレモンサワーを一杯
夜は文庫本を片手に眠くなるまでの時間を過ごす
休日にはプロの技で手際よく部屋の掃除を終えると、汚れた仕事着を持ってコインランドリーへ
合間の時間には趣味で撮ったインスタント写真の現像にも出向く
夕方には少し気になる女将のいる小料理へ
そうして平山の一週間は巡る
インスタには載らない。しかしこれ以上なく丁寧な生活だ
そう、そんな彼を好きになるための映画
演じる役所広司氏はPERFECTだ
ヴェンダース監督の控え目な描き方も心地良い
『オイラは平山。寡黙だけど不思議と周りに慕われるトイレ清掃員さ!』
と語らせるのが0点ならば100点の形で彼の魅力を引き出している
情報を入れて難しく考える必要はない
平山さんに好感を持つか否かだ
静かな映画
後味の良い映画
泣き笑いの人生 腕時計 木洩れ日
多くの方が絶賛しているので、感じたことだけを書こうかと思う。主人公の出勤日のルーティンな生活風景は、何とも見ていて気持ちが良い。玄関の横に鍵やカメラ、財布など並べてあり、それを身に付けて行くのだが、なぜか腕時計だけは持っていかない。不思議だなあと思っていたが、近隣の神社の入口を掃除する箒の音で目を覚まし、決まった所に仕事に行き、淡々と一人で、仕事をするのに腕時計は不要なのだと気づく。ところが休日にはこれまたなぜか腕時計をしっかり着けて、コインランドリーに行き、馴染みの古本屋と写真屋と憧れのママのいるお店で一杯飲む。これまたルーティンな休日の風景。面白い。
すべてがオブラートに包まれたような優しいと言うか、苦味を感じさせない作風は興味深い。そこには公園の公衆トイレの酷く汚損された現実の姿も、主人公が静かな日常を選択せざるえなかった過去の経緯も、また容赦なく入り込んでくる周囲の悪感情も、この映画には描かれない。
主人公が毎日撮り続ける木洩れ日の風景(朝ドラのカムカムエブリバディの中で木洩れ日は日本にしかない表現だと言う場面を思い出した)、その写真をそれまでの忘れたい過去の気持ちや心を浄化するように押入れにしまい込む。
そんな頑なな完璧な日々も毎日は続かない。知らない内に変化が訪れる。パトリシアハイスミスの小説が「不安」を如実に表現していると言うように、最後の笑うとも泣くとも、何とも言えない表情は、私達が日常で抱える「漠然たる不安」をよく表現している。こういう場面を演じる役所広司は、さぞや役者冥利に尽きるだろうなあと感心して観ていた。
悟らせる、と言う演出の極み
静かで美しい、質素なのに贅沢
役所広司氏がカンヌで賞をもらった、くらいの前知識で観ました。
皆さんおっしゃるように、セリフでなく表情と生き様で語ってくる映画。
質素なのに、なんだか羨ましくなる生活。
「風呂無しの木造アパートで、公共トイレの清掃員」と文字にしてしまうと、寧ろ敬遠したくなるような生活なのに。
家具や装飾品はほとんどないのに、晩年はああいう部屋に住みたいと思ってしまったのは、彼が自分の生活に満足していることが伝わってくるから。
自分の仕事を満足できるように工夫してて、心安らぐベンチを見つけてて、心地よい風呂屋があって、いつも元気に明るく話しかけてくれる馴染みの飲食店がある。
なんか人生に必要なものはコレで充分なんじゃないかと思えるほど。
そして、あぁだから「パーフェクトデイズ」なのかと納得する。
アメリカではなく、フランスで賞をもらえたのも納得。
デザイナートイレと役所広司で一本映画作ってみた
渋谷区のデザイナートイレを見てきた妻が、それらをモチーフにした映画を見たい、といいだしたのが鑑賞のきっかけ。役所広司が渋谷のトイレ掃除をする映画がある、というのは知っていたが、映画祭に出品したとか、その内容からして地味な邦画だろうと敬遠していた。とっくに上映期間は終わってるだろうと思っていたら新宿のキノシアター(旧EJアニメシアター)で上映中とのことで鑑賞することに。
ある程度予想していた通り、かなり地味な展開の"邦画"然とした構成。ドイツ人巨匠監督が作成、とのことでさもありなんという日本というか東京の捉え方をしている。
初っ端でスカイツリーを映像に入れることで「場所」と「年代」を意識づけしてスタートするのだが、ほとんどの状況説明が全て「わかる人にはわかる」という不親切設計。玄人映画受けはするだろうが、一般受けは望めない。と思ったが、どうも海外の映画祭出品を前提にしているから、という構造もあるんだろうと思う。絵面がいちいち「東京住んでたらそうはせんだろう」というリアリティの無さがあるからだ。
・浅草周辺から早朝に渋谷区に勤務する軽バンが、なぜか首都高に乗る
・清掃するトイレが全てデザイナートイレ
※そもそもあのデザイナートイレ有りきで、スタートした企画だろうとは思っているが。
・東京は治安がいい、というのを表現したいのか、玄関に鍵を掛けない主人公・デザイナートイレのある公園に浮浪者がいる
・少なくとも20~30年前のカセットテープが車の中に置かれて劣化せずに聞ける。(鉛筆で弛みを締めてる描写は良かった)
・二階に上がる外階段があるのに、内部でメゾネット構造の広いボロアパート・やけに綺麗なアパートの内部、布団と枕、なのにトイレ掃除で汚れてるはずのツナギはいつもピカピカで一週間洗濯せずに部屋に吊り下げ
・四畳半の畳の敷き方が真ん中に半畳ではなく隅に半畳
・スナックのママが石川さゆりで歌が滅茶ウマ
まあ他にも気づかなかったところは数ありそうだけど、
外国人向けに、「東京のエモい風景」をアピールするための絵作りをした結果なんだろう。賛否両論はあると思うが、個人的には悪くない選択だと思う。
ちなみに16~17個ある、デザイナートイレ、2021年ごろにできたものだが隈研吾や、安藤忠雄、佐藤可士和など、一般の人でも名前くらいは聞いたことある有名デザイナーが関わってるとあって、当時かなり話題になった。トイレを見るためにわざわざ寄り道したくらい。いったのは中から鍵をかけるまでは透明な壁が鍵を書けると曇りガラスになるやつ。代々木公園から近い。
主人公の変わらない日常=パーフェクトデイズと彼に関わってくる不確定要素の人物の対比が物語の基本的な構造(というかほぼ全て)になっていて、彼の決まった日常を前半で何週かさせた後に、それをズラす要素(人)を入れることで観客の心を揺さぶりにかかっている。
普通の映画なら、複線ー回収で読者のカタストロフィを満足させる構造にしがちなところを、全てをイベントを単発で、投げっぱなし、回収、連続性なしにすることで、「変わらない」日常を表現している。
とはいえ、主人公が変わらないことを完璧に望んでいるのかと思いきや、そうではない描写が、後半にいくつかでてきたり、主人公の前半生が実は上流階級の全然違う生活だったことを仄めかす演出があったり、で見ている方はどっちなの?と迷わされるところもある。そういった説明や主義主張が全て「見ている人の解釈にお任せします」という投げっぱなし演出になっている。
特にラストの長尺部分は解釈に迷うところで、満足して泣いているのか、逆なのか、どうとでも取れる演出で少しずるいなあとは思う。
ただ、演出、小道具、絵作り、いろんなものが賛否両論とれそうになっていて、他の人と「あれどう思う?」と聞いてみたくなる作り。
その1点だけで「いい映画」と言い切れると思う。
デザイナートイレと役所広司を揃えた時点でのプロデュースの勝利、と言える一品だと思う。
東京の片隅が舞台のお伽噺
毎日の車通勤も、銭湯まで自転車でのんびり向かうのも、ヴェンダースの手にかかるととたんにロードムービになる不思議。
主人公は、詳細は明らかにはされないけれどきっと苦悶の時を経たであろう、どこか影を引きずるトイレ清掃員、という、設定としては少し痛ましさすら感じるほど現実味あるものなのだけど、不思議とお伽噺のような浮遊感をも纏っているように見えます。平山さんの部屋が、夜の東京の路地裏に、紫色にぼんやりと浮かぶ情景。平山さんとニコが自転車で橋を渡る時の会話。公園の木々から落ちる木洩れ陽。光、影、音。
ベルリン・天使の詩の天使のごとく、ヴェンダースの映画には登場人物たちの日常を見つめるあたたかい眼差しのようなものがあり、わたしはこれがヴェンダースを好きな理由でありますが、この作品も例外ではないようです。
異常なまでに寡黙な平山さんの、朝、ドアを開けて空を仰ぐ時の微かな笑み、ニコの突然の登場に戸惑いながら見せる嬉しそうなほほえみ、そしてラスト、止まらぬ涙。
日本の俳優はただのタレントばっかでレベルが低い、と毛嫌いしてましたが、この作品のお陰で思い込みが吹き飛ばされました。
さすが何十年も日本に関心を持ち続けているヴェンダース、ここまで親和性があるとは思いませんでした。ヴェンダースの久々の長編ドラマが日本で撮られるとは、そしてここまでふかく印象に残る一作となったのは、嬉しいことです。
フライヤーなどにキャッチコピーありますが、「こんなふうに生きていけたら」?
選択肢がある中で、ボロアパートに暮らすトイレ清掃員の生活に、誰が好き好んで「こんなふうに生きていけたら」と?裕福な家の出(と、ほのめかされる)の平山さんが一体何にぶち当たり苦悩しこの生活を選びとったか。選ばなければいけなかったのか。観客は知る由もないけれど、流行りのミニマリズム的な感覚で、表層部分のみをすくい取っただけのコピーの浅はかさに驚いた。
首都高がロードムービーになるとは
首都高を走る時の音楽、最高でした。
植物を愛しみ、仕事に出かける時も仕事中も空を見上げて表情がほころぶ。なんて心に平和があるのでしょう。いいなぁ、この空気感。
仕事が終わると銭湯へ一番乗りして、馴染みの居酒屋へ立ち寄り、自転車で隅田川を渡って帰る平日のルーティン。コインランドリーへ行き、古本屋と写真屋に寄り、スナックへ行く休日のルーティン。本を読んで寝落ちする夜とその夢の残像。
幸せな気持ちで毎日を過ごすって、こういうことなんだなー。
そして、女子中学生が夜一人でいても安全な国、自販機が壊されない国、公園のトイレが安全&清潔で使える状態キープの清潔な国、監督者がいなくても誠実に仕事をする国民性という、日本のポジション(ブランド)を余すところなく表現していて、監督の日本愛が伝わってきました。
女性に好意を寄せられがちな平山と、「お金がないと恋ができない」というタカシ。そういうところだぞ、タカシ。借りたお金は返せよー。
三浦友和さんと役所広司さんの影ふみ遊びを見られるとは思ってもいなかった。貴重な名シーンになるのでは。
ラストの役所広司さんの表情は圧巻で、今生きること・やがては誰もがこの世を去ることを考えると私も涙が止まりませんでした。人生という長い湾曲したロードを走行しているんですね、私たちは。
帰り道、電車に乗るより無性に都会の夜を歩きたくなり、日比谷から東京駅まで歩きました。映画の続きを観ているような幸せな時間でした。
全1018件中、221~240件目を表示