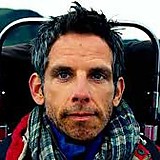夜明けのすべてのレビュー・感想・評価
全503件中、81~100件目を表示
あったけえ会社
普段は穏やかだが、月に一度PMS(月経前症候群)によりイライラがひどい藤沢さん。転職し、同僚がとても理解ある栗田科学で働く。そこに転職してきた無気力な山添君に、強く怒ってしまう。しかし彼はパニック障害だった。
PMSはなんとなく分かるけど、パニック障害は有名人がなったのを聞くだけで、実際は知りませんでした。二人とも、土日休むときつくなるというのも意外、確かに休みに会社へ来ていた。山添君は、ラーメン食べてて発症し電車に乗れなくなってしまうが、自宅にいるときだけ自分らしく全く普通。人それぞれ症状は違うだろうけど、山添君が会社でも普通にふるまえるようになっていくのが良かった。藤沢さんも、前向きになっていくし。栗田科学が、二人に対する理解がなんともあったかくて、スゴイ会社です。栗田社長や山添君の元上司も、自死家族会の会員で二人の良き理解者であったのも良いです。
静かな日常の中で感じること
再鑑賞して
上白石萌音さんの藤沢さん、
最初、顔の表情がぼんやりしていて、
この人こんな顔だったっけ?と驚いた。
重い生理は心身共に辛いのはわかる、が、
人それぞれだから言えないが、
周りのことを忘れての
前の職場や今の山添さんに対しての言動が、
ちょっと理解しにくい。
イライラ最骨頂にはなるのだが、
あんなに周りが見えないものか⁉️
病名も付けられているぐらいだからなのか。
体調悪く早退して
散らかった自宅でどよ〜んと寝るしかできない
というのはよくわかる。
松村北斗さんの山添さん、
パニック障害の怖さ凄い❗️
突然症状が出るというのも手立てはあるのか、
と思う。
前の職場でも先輩や同僚とも上手くいっていたようだが、なぜ転職?
仕事内容からか?
今の職場はいい人しかいない。
子供向けの学習キットに関わる仕事。
しかし最近は元の職場に戻りたがっていたから
仕事内容には関係ないのだ。
会社のいいところというインタビュー、
他の人のほのぼの回答、
山添は自分と絡めて良い職場と言うが、
どうなんだろう、
一見人となりが出ていそうだが、
演出過剰な気もする。
仕事内容の良さも言ってつけたしみたいに
ちょっと、言うだけなら
好感持てたかも。
プラネタリウムの時、
藤沢さん黒スーツ着て顔もキリッとして、
別人のよう、極端過ぎないかと思う。
山添さんも企画のような仕事で
やりがいを感じたのだろうか、
この職場に残ると変化。
母一人子一人なので、
母をそばで見守ろうと
実家近くに転職するのはいいな。
お母さん何の病気かわからないが、
施設入所していて
あんなに仕送りできるのだろうか、と疑問。
のどかな景色が映され
音楽も心穏やかな曲が流れ、
二人持病があっても思いの外
アットホームな職場で、
良かったということだが、
エンドロールの映像で
キャッチボールしたり皆次々と外に出て来て
わざとらしさに興醒めしてしまった。
再鑑賞、
山添さんが、藤沢さんの家にスマホとプラネタリウムの原稿を届けに行く時、寒いこともあり、会社ネーム入ジャンパーを羽織り出かける。
以前の会社の先輩に今の会社に残ることも告げる。
たまたま戻った会社で社長と弟さんの仏前に手を合わせる。
藤沢科学で生きて行こうと決心。
その理由を考えてみると、
あのプラネタリウムへの取り組みが大きかったかなと。
社内の雰囲氣や人間関係良好であっても、仕事に魅力が無いと続けられないと思う。
社長の弟さんの仕事への愛情や勤勉さをテープやノートから知ることにより弟さんの意思を成就させたい、それだけやりがいのある仕事だと認識できたからではないかと思う。
弟さんは、人間死ねば星になんかならない、
消えて無くなるだけ。と言っているが、
弟さんの意思は、こんなにも自分の心を揺さぶるではないか、消えてなどいない、と山添さんは感じたのだろう。
まだまだ未知数だが、子供の心だけでなく大人の心も惹きつけ揺さぶるモノやイベントを企画もしていける可能性も見出したのではないだろうか。現実を見て病気と上手く折り合いながら生きていくことも考えての最良の選択なのだろう。
途方もなく優しい映画
何故か序盤からずっと泣きそうになっていた。PMSがテーマになってる映画って初めて見たかも。
私自身も藤沢さんほどではないが生理前後の感情の起伏が大きくなることはあったため、気持ちはよく理解できた。
松村北斗くんも役柄とすごく合っていた。徐々に生き生きしていって魅力が増していって。
脇を固める役者さんたちも素晴らしかった。
自分の弱さも他人の弱さも認めよう、と言う話なのかな、と。
劇的に変わることはないけど、夜明け前の空と同じで少しずつ明るくなっていくから。
押し付けがましい希望の話は好きじゃない。
でも絶望ばかりしていても仕方ない。
少しだけ、前を向く。そんな気持ちに自然とさせてくれた。
こんな映画が日本にある、それこそが大きな希望。
やさしい映画
人生の大切な映画の一本になった
いろんなことがある今の世の中で、ホッとできるお守りみたいな映画。
特別なことは何も起こらない、ただの日常なんだけどそれがとても愛おしい。
原作も読み、原作のあのシーンやってほしかった!と思うこともあるが、逆に原作に無いプラネタリウムのシーンを追加したことが本当に大きな意味があって素晴らしい改変になっている。
特筆すべきは、主演のふたりが恋仲にならないところ。恋仲になりそうな雰囲気すら漂ってこないところが非常に良い。男女がいたら、そのように見えてきてもおかしくないだろうから、とても難しいと思うが、監督と俳優陣がとても丁寧に繊細に演じられたのだろうと思う。
人生に疲れてしまった人、毎日生きるのがしんどい人、明日が来なければいいのにと思う人、そんな人にも優しく寄り添ってくれる映画。全く押し付けがましくなくて、温かい気持ちになれるはず。
ちょっと手を差しのべるだけでいい
PMSで自分をコントロールできず、急に苛立ってブチギレて
そんな自分に落ち込みつつ、暮らしている藤沢さん。
パニック障害の山添くん。
お互いの病気を知ってから、藤沢さんは心配して山添くんにおせっかい(田舎のおばちゃん的な)。
同僚同士の関係はかわることなく、お互いを理解するようになる。
「3回に1回くらいは、藤沢さんの発作の前に助けることができると思う」と山添くん。
そうだよな。それくらいの距離感で
誰かが困ってたら、手を差しのべたいものだよな。
病気を抱えてこまっている人のことに気づける、
そして説教臭くもない、がんばりすぎない、良い映画だった。
タイトルの意味
パニック障害の山添くんと、重度のPMSの藤沢さん どちらも普段は『...
パニック障害の山添くんと、重度のPMSの藤沢さん
どちらも普段は『普通』なので
なかなか他人からは理解されづらい病気。
山添くんの病気に気づいた藤沢さんが
『お互い無理せず頑張ろう』と声をかけるけれど
山添くんは、お互い病気でもしんどさもそれに伴うものも
全然違う、と否定します。
『病気にもランクがあるってことだね』と藤沢さんは
帰ります。
このシーンにハッとしました。
他人の辛さに対してもっと辛い人はいる、と
謎のマウントをとる人っている、、、
辛さの当事者同士であっても自分の方が辛い、
と周りに寄り添えなくなってしまう。
映画はこの山添くんが少しずつ藤沢さんの辛さにも目を向け、『ひとりでイラついててください』と優しく距離をとりながら心に寄り添います。
会社の上司、元上司もそれぞれ
辛い過去を抱えながらまわりの辛さに目を向けます
そこがわざとらしさもなくうまく描かれているなぁと思いました。
たい焼き買ってるだけで感動する映画NO1
マーベルとかの作品がミックスフライ定食だとしたら、こちらは上質なお茶漬け
ストーリーと呼べるほどの起承転結があるわけでもないので、あらすじだけ見ると「それだけ?」ってなるし、実際それだけだから人にわかりやすい魅力を伝えづらい
とにかく「なんか今、生きづらいかも。昔、生きづらかったかも」と感じる方に見てほしい
感動というと親子の劇的な再会とか、恋人の余命宣告とかそんなイメージだけどそう言った展開は無しで感動させてくる
ただホクト氏が自転車乗ってるだけで泣けてくる
たい焼き買ってるだけで泣けてくる。そんな映画は今まで見たことがなかった
だってアイアンマンがたい焼き買ってても全く感動しないもん
ホクト氏とモネ氏がW主演となったらとりあえず恋愛させるのかなと思ったら、ラブロマンス要素を完全に取り除いてくれていて本当にありがとう
この美男美女に恋愛させないのは至難の技だったと思うありがとう
対恋人や対家族などの特別な感情がなくても人は誰かの支えになれる
実際に二人はお互いのこと気にかけつつも、ある意味どうだっていいというか気を遣っていない
大学で週に一回授業で会う程度の距離感
だってモネ氏なんかポテチの最後のカスを流し込んでたからね。2回も
最後の夜についてのメモがまた良かった
「夜があるから自分の外の世界を想像できる」
人という字は人と人とが支えあって…
素敵な映画
病院の待合で聞くような他人の病気自慢と、馴れ合い感が苦手だった!!
他人の持病に全く興味が無いのて、しんどいです。それでも若い時はお節介にも関わろうとした事があるので、理解できない訳では無いですが、そればかりやられるのも面白くないです。微妙にブスなヒロインが積極的なのと、職場の馴れ合いも気持ち悪いです。病院の待合で、他人の病気自慢を聞いているのが好きな人はあまりいないと思いますが、レビューも何かもう同調圧力が凄くないですか。プラネタリウム云々も何か鼻に付きますし、「そして、バトンは渡された」に続き、この作者の本は私には合わないです。ぶっちゃけ夜明けは来ませんよ。
太陽が向こうから近づいてきていると信じている人のレビュー
新しい映画なのにレトロ感がある映像。
劇中に登場するカレンダーを見ると、まさに今の日本が舞台になっている。
藤沢美紗(上白石萌音)が、親元を離れて自立してから始まる夜明け前の苦しみの時期と、のちの夜明けに至るまでをじっくり丁寧に描いている。
藤沢は、薬を見付けて山添(松村北斗)に渡したり、自転車を譲ったり、髪を切ってあげたりするが、今作に登場する男女は誰一人として月と太陽のごとく一線を越えず、お互いを欲したり交わろうとしない。
性欲が存在しない架空の世界なのだろうか。
整列している星の夜空の見えかたからは、プラネタリウムのように空のほうがゆっくり動いている考え方のほうがしっくりくるし、もし誰かが言うように地球が自転公転していたら、物理の法則によると夜明けの度に定期的に地震のような衝撃があるはずである。
世界の仕組みも人の體の仕組みも、すべてが解き明かされてしまわないように、知識の共有を阻む何かがあることを感じざるを得ない。
夜空のように全てが繋がったまま、徐々に明るい方向へ好転していく。
栗田和夫(光石研)の弟が残した数十年前の記録が、内容はともかく時空を超えて未来の誰か(藤沢たち)に届いたのは素敵なことである。
ずっと穏やかなBGMで、刺激的なことは特に無いまま終わったので拍子抜けしたが、なぜか余韻が抜けない作品。
同情ではなく理解を
PMS(月経前症候群)の女性とパニック障害の男性が生活の中で職場で居場所を探そうとするお話です。僕が、PMSという言葉を知ったのはほんの1~2年前の事なので、男性として知っておきたいと思える物語でした。しかし、『ケイコ目を澄ませて』の三宅唱監督はそれを力こぶの「障害者映画」にはしませんでした。
病や障害を持つ人に安易に「同情」するのではなく「理解」する事でこそ自らをも癒し得ることを語るとても穏やかで優しい物語でした。悪い人は出て来ないのですが、「それもいいじゃないか」と僕はスクリーン前で大きく頷きます。そして、安っぽく恋愛映画にしなかったのがとてもよかったなぁ。映像には独特の間(ま)があり、そこで見せる上白石萌音さんの素の表情の演技が素晴らしかったです。
抑揚のない退屈なドラマ
各々精神疾患(PMS(月経前症候群)・パニック障害)を抱えて、人付き合いが下手でぎこちない日々を送る会社の同僚の二人、上白石萌音扮する藤沢さんと松村北斗扮する山添くんを主役に据え、その窮屈でもどかしい互いの日常を粛々と追った作品です。
カメラは彼らに同情的でもなく、フィックスの長回しを多用し、寄せアップも殆どなく、ゆったりとした緩いテンポで淡々と、まるでドキュメンタリーのように映していきます。しかし彼らが抱える、病気による苦悩や悲哀は描かれないので、鋭く問題提起するわけでもなく、終始メリハリのない滔々とした映像が延々と続きます。ラブロマンスはなく、謎解きミステリー要素もなく、サスペンス性もありません。つまり起承転結のない2時間のドラマが本作といえます。
それでも前半は、藤沢さん視点で映されていきます。そこでは山添くんも藤沢視点で胡散臭い客体の一つとして描かれますが、中盤藤沢さんが山添くんの整髪をする長回しカットから山添視点にカメラが移り、藤沢さんも面倒くさい人として映されつつも、暖かく見つめられていることが感じられます。
そして徐々に二人の視点が重なり合っていきますが、決して恋愛関係には至らない淡泊な関係のままエンディングを迎えます。
斯様に抑揚のない退屈なドラマで、その上、登場人物が悉く善人ばかりなので、事件もなくハラハラドキドキすることもなく、ただただ安心して観ていられたに過ぎないのですが、不思議に飽きることなく観賞できたのは、リアルな生活感を実演した役者たちの演技力によるのでしょう。
ただ、つい近所でもありそうな、あまりにも身近な話であり、夢やロマンといった快感は得られず映画的なスケール感は全くありません。巷間、非常に高評価なのが、率直に言って私にはよく理解できません。
一服の清涼感は得られた気はしますが、非日常空間である映画館で観客に披露する作品とは言い難いと思います。
映像作品としては悪くはありませんが、BSでのドキュメンタリー風ドラマが向いているのではないかと思ったしだいです。
生きづらさを抱えた人へ
事前に原作など読まず見に行きました。
様々な理由で生きづらさを抱えた人たちと
それを理解して見守ってくれる人たち。
一緒に見ていた主人はPMSについて知らなかった、知れてよかったと。
人は色々なバックグラウンドがある。
表面的にはわからないかもしれないけど
それを心に留めておくだけで、
人と関わるときに少しだけ心配りができるようになればいいな。と思わせてくれた映画でした。
悲しい時も嬉しい時も必ず終わる
全503件中、81~100件目を表示