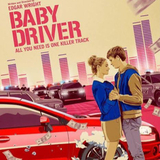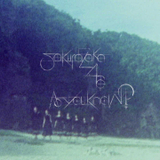君たちはどう生きるかのレビュー・感想・評価
全762件中、621~640件目を表示
宮崎駿監督が少年時代に読んだ本に感動して 現代社会、若者たちに問題提起する作品!
君たちはどう生きるか?
アニメーションの中だと真人の亡くなった
お母さんが遺した本を少年である真人が
発見した場面が、題材となった小説になぞらえた部分だと思いました。
真人が幻の世界に入り込み、亡くなったお母さんに会うことが出来なくても、屋敷のばあやに似た人型の木が御守りの代わりになり
積み木をひとつひとつ重ねるように新しいお母さん夏子や、これから生まれてくる生命、
お父さんと共に生きて欲しいと思えるストーリーでした。
青鷺は、人が亡くなることの悲しさ
ペリカンや、同じものの集まるところは、
今までのジブリ作品と重なるシーン
集大成だと思いました。
君たちはどう生きるか?
自分が世界の中心ではない
自分が世界の1部だと言う視点で世の中を見る
新しい発見をする
問題を解くのに答え自体ではなく
答えを導き出す後押しすること
世の中の生産性、まだまだ解決出来ていないことをこれから生きていく人たちに
自分がその1人となる可能性があることを
示すようなメッセージ性を感じました。
補足、感想が難しいのでまとまらなくて
乱文ですみません。
タイトルなし(ネタバレ)
スタジオジブリ&宮崎駿監督作品
これだけの情報だけで、観に行こうと思えるのが凄いよな。と思いながら、劇場へ足を運んだ。
ひと事で言ってしまえば
「よくわかんなかった」
でも、ふと思う。
今までの作品、自力でわかってた?私?
前宣伝で知るあれやこれや、インタビュー記事、そういういろんなものの助けを借りて、予備知識やら、鑑賞後の補足で、理解していたのかもしれない。
そう考えると、本作が特別わけがわからないわけでもないような、、
それでももちろん謎が残るもやもやはあり。
大伯父の積み石がもたずに訪れるはずの危機とは。
眞人が継がずにどうなったのか。
そもそも大伯父の前にも同じような人がいたのか。
義理の母はなぜあちらにいたのか。
なぜあの時代を舞台したのか。
etcetcetc.....
米津玄師さんの歌を聴きながらのエンドロール
だれがだれの声か、なんで書かないんだろう
そんななか。
これから眞人の母になる未来に向かって帰るひみと、母のいない未来に向かって帰る眞人が、それぞれドアを開けて、互いに別れをつげるあの瞬間、なんとも言えない気持ちになって、印象に残ったシーンだったな。
「銀河鉄道の夜」を見たときの感覚
本日 2回目鑑賞
ストーリー分ったうえなので咀嚼して見れた
やはりスルメ映画
話が分ったうえでも 始終 不安感に包まれた感じで物語は展開
異世界パートは 杉井ギサブロー 監督の「銀河鉄道の夜」(1985年)に通ずるものを感じた
モヤモヤ感、生と死、鳥、等々…
タイトルなし(ネタバレ)
ジブリ流タミフルかと…なんかようわからんままエンディング来た……
前情報なしのワクワク感が味わいたくて公開2日目に来たけど、感想としては「いやこれはある程度頭に入れてからじゃないとわからねーぞ」でした。
すべてを理解する頃には物語も終盤。
2回目を観ることを前提にしているのか…?
他の人も言ってたけど、たしかにジブリ過去作欲張りセットではある。
というか日本のアニメ欲張りセットって感じ。
でもなんというか、目新しさというより何もかもをごった煮にした二番煎じのような気がしてしまいました。
でも美術は綺麗だし、キャラデザは脇役が優勝でした。
ワラワラちゃんと大量のインコちゃんはグッズが欲しくなっちゃったゾ。
グッズ造られないのかな〜
凄いもの見た。
面白いかと言われれば微妙だけど、ともかく物凄い作品だと思った。
ずっと宮崎駿が見ている夢を見せられている気分というか。
作中、水と火がとても対照的に表現されていて、印象的だった。
水は、優しく、幻想的で、でも所詮は嘘で作られた紛い物を。
火は、厳しく、恐ろしいけれど、真実を、
それぞれ象徴していたように思う。
同時に、真実=死でもあることががっつり明言されていて、
とんでもないテーマだなと思った。(全然的外れな意見かもしれないけど。)
一番印象的だったのは、ラスト近くでアオサギが言った、
異世界での出来事を覚えている眞人に対して驚いたあと、
「でもいずれは忘れちまう。だけどそれでいいんだ」的な台詞。
それって、まんま私たち観客に向けた台詞だよね……。
いずれ忘れてもいい。全部理解してくれなくていい。
今だけでも感動してくれれば、
ちょっとだけでも考えてくれれば、それで充分だってことなんだろうか……。
映像は見事だが、物語性が希薄
熱心なジブリファンではないが、事前のプロモーションを一切行わないという話題性のみで鑑賞。
物語の構成は千と千尋に近い感じ。
ただ千尋が異世界で成長して仲間を増やしていくストーリー性やキャラクター同士の絆の描写などが本作では薄いので、あまり感情移入できず。
ストーリーとしては30分くらいのショートムービーくらいの作り込み、という印象。
不思議の国のアリスを読んだ時のような難解さと退屈さを感じた。
映像は隙がないくらいの手の入れようで、そこは見事。
ただ事前情報があれば見に行かなかったかな。
シン・ジブリかな??
※かなり重要な部分のネタバレありです。ご注意ください。
『風立ちぬ』を観て「もう宮崎駿監督は映画を作らないんだろうなぁ」なんて感じていたので新作が観られて本当に嬉しいです。長年に渡り情熱を持ってアニメーション映画を作り続ける姿勢に敬服いたします。
自分は監督の大ファンなんでどんな内容でも星5なんですがそれではレビューの意味がないのでここはあえて・・・。
まず、映像は間違いなく高クオリティ。これに文句をつける観客はほとんどいないと思います。どのシーンも安定的、かつさすがジブリと言える品質で安心して観てられます。
さて、問題はストーリーですよね。
舞台は戦時の日本。でも戦争はバックボーンにあるだけでストーリーには直接関係してきません。
主人公のまひと君(漢字忘れました。小学校高学年から中学生くらい?)は火事で母親を失います。
それから数年後、父親がいつのまにか母親の妹といい仲になり再婚します。
って!おーい!そりゃねえよ!!何十年後ならともかく学生の子供がまだ学生くらいの年月しか経ってないのに再婚?!しかも妻の妹と?!
ここを「そういうこともあるよね、まあ昔の日本だし」でスルーできるか「何この男最低!!!」となるかでこの映画を楽しめるかが分かれると思います。第一の関門。
話が逸れました。
傷心癒えぬまま田舎で継母と暮らすことになったまひと君。最初はどことなく不貞腐れて継母と距離を取っています。無理もない。
そこで母親が生前にまひとくんに遺した本「君たちはどう生きるか」を見つけ、それを読んでまひと君は前を向き始めます。タイトル回収はここで。まさかのキーアイテムでしたか。
その直後に継母が謎の失踪。本を読んでひと皮むけたまひと君は継母を探しに不思議の世界へ飛び込みます。
この不思議の世界の冒険がジブリ感満載。過去のジブリ作品のオマージュかな?関連してる世界なのかな?と思わせるような描写があちこちに散りばめられてます。ここは純粋にとても楽しかったです。
そしていろいろ冒険したクライマックス、ユパ様みたいなイケオジがまひとくんに「この不思議の世界の創造主になってほしい、さもないとこの世界は消える」と迫るのですが、まひと君は「自分には無理です」ときっぱりあっさり断って元の現実世界に戻ります。
ここで私はおおっ?!となりました。
今までのジブリ作品って少年少女に過酷な運命を託すものばかりだったんですよね。そして少年少女はそれを当たり前に受け入れる。ナウシカ、シータ、アシタカ、そうすけetc・・・。
何だか、そういう少年少女に対して「辛いことさせちゃってごめんね」と監督自身が言いたいのかなと、引いては今を生きる子供たちに「いかにももっともらしいことを言う大人や周囲に従わなくていい、自分の考えた道を進みなさい」と言ってるのかな・・・と思いました。
自身の過去作品を否定し完結した「シン・エヴァ」のような要素を感じました。もしかしてこれは「シン・ジブリ」なのか・・・?!
と、まあ完全な勝手な妄想です。これから情報がでてきて全然見当違いになるかもしれませんね!というかほぼなると思います。恥ずかし!
で、これを「面白かったから絶対に観るべき!」と人に自信を持って勧められるかというとちょっと悩むので星3.5です。自分は面白かったけど隣で見ていたどこかの子供は退屈そうにしてましたね・・・。不思議の世界での冒険が始まるまでがちょっと長いのと、テンポが緩いんですよね。あと子供が惹かれるような分かりやすく魅力的なキャラとかメカはいないので。
自分は満足でした!初見では見逃してるものがたくさんありそうなのでもう一回くらい観たいです。
ネタバレがしづらい映画
すごくおもしろかったと思います。
一回しか鑑賞していないので、雑感です。
この映画は、テーマのしっかりした視聴者に親切な冒険ファンタジーと捉えられます。その一方でメタファーが多いので、また別の見方ができるおもしろい作品だと思いました。
宮崎駿のことを知らなくても、知っていても楽しめる作品です。
アオサギが物語のテーマとして重要な役割を持っているので、広告ポスターに選ばれた理由がわかりました。
私小説的な側面のある作品ですが、前情報なしに鑑賞する体験そのものがこの映画をエンタメ化させていると感じました。
まさに集大成
宮崎駿の集大成。
醜いアオサギは宮崎駿自身。自身を嘘つき呼ばわりして自戒しながら、それでも今回も主人公の旅の案内をする。
主人公から見た最初の世界は、周りのばあばたちをトランクに群がる醜い虫のように見つめる、冷え切った世界。最初から人らしく見えるのは、美しい母に似た新しい母親と父のみ。それが旅を通じて、少しずつ周りの多くの人が、自分を守ってくれる優しい人だと気付く。
最初は卑しく表現されていたキリコは、力強い心を持ち、主人公も、幼い頃の母さえも助けてくれた人物だった。
自分にとって卑しいと感じるものをただ排除し、否定する我々現代人だが、自分自身もささやかな悪意を持つ存在であると、主人公の若者は最後に気付く。そして、ささやかな悪意を持つ存在の多くに、自分は守られているのだと徐々に気付く。
汚れなき積み木で楽園を築こうとする神は孤独の象徴であり、汚れなき存在などこの世に存在せず、全ての生き物が罪を背負って、ただ前に進んでいる健気な存在。
仏教感とも異なり、ただ自分の不浄を受け入れて、その中でこそ美しく輝く優しさこそが、おそらく宮崎駿が伝えたかったこと。
最後に主人公が現世に持ち帰った石の欠片は、この作品そのもの。すぐに忘れ去られる存在だが、それでも意味がある。
これは間違いなく、宮崎駿の最高傑作。
期待しただけに、、、
予告や前情報がない状態で、公開日の朝1番で観ました。
始まりは戦時中の話?と思ったけど、そこからは良くわからず、、違う世界に行って色んな人物が出てきて、、、終わってからは結局何なん?ってなりました。。
理解するまでに時間がかかりそうです、色んな方の考察動画を見たいと思います。
主題歌は素晴らしい😊
挑戦かあるいは....
正直言ってストーリーは散文的であり、淡々と物語の進行していく。セリフはさほど大事じゃないと感じた。無声映画として見てもそこまで変わらないであろう。セリフから得られる情報が少ない。つまり説明が限りなく少ない。観客を置き去りにしてる。
僕が大人になったのか、数多くのアニメや漫画に触れたからなのか分からないが、ナウシカやラピュタ、千と千尋のような世界観とは異なり、今作の世界観は全く心惹かれなかった。わくわくしなかった。なんか夢に出てくるような意味不明で現実と架空をごちゃまぜにしたような世界をそのまま描き起こした感じがした。
難解で映画としては駄作だと思えるようだが、観客に理解してほしいだとか楽しんでほしいだとかそういう目的での作品ではないと思う。ある意味、往年の名映画監督らしくはない若さを感じた。個人的にはこれまでの宮崎駿作品とは全く異なる印象を受けた。彼は新たなことに挑戦しようとしてしているのかもしれない。あるいは老いたのか...。
次作も楽しみである。
これは僕の妄想ではあるが、彼は観客を小馬鹿にしたいのかもしれない。
宮崎駿というビッグネームの作品、理解不能で意味不明なストーリー、そして「君たちはどう生きるか」という如何にも意味ありげなタイトル。
映画鑑賞後に悩む観客たちを屈託のない笑顔で嘲笑っているのかもしれない。
ジブリの世界観を堪能
ストーリーなど事前情報がないことに何か意味があるのかというと、特に意味はないのかなと思った。
別の世界に行ってからのジブリ感満載な世界観はやっぱり見ていてワクワクするし楽しめるものだった。
主人公が何をきっかけに大きく成長や意志を持ち出したのかは明確ではなかったが、子どもの成長とはそんなものなのかと思い、ファンタジーの世界でもリアリティを感じた。
寝落ちした
7/15午後に視聴。大きな劇場が満席でしたが、途中席を立つ人がちらほら。ぼくは2回ほど寝落ちしました。
戦時中から戦後にかけての話で、空襲で母を亡くした主人公が、母代わりの叔母を探すうちに不思議な世界に迷い込み…
という展開。
宮崎駿さんぽい魔物がうようよ出現する世界観は好きですが、ストーリーがわけがわからない。主人公以外の脇役の登場理由や動機が説明不足で、唐突に新しい脇役が出てきて主人公と絡んで、また次の脇役との絡みへ。この繰り返しと、なぜ主人公を邪魔するのか理由が不明な魔物との戦いが繰り広げられる。物語になっていないです。
ストーリーが破綻した綺麗な映像を120分近く見続けたら、寝落ちもするし、途中退席もする。
宮崎駿さんじゃなければ、ぼくも退席していた。
間違っても小さな子ども連れでは行かない方がよい。山場もないし、退屈してぐずると思います。
期待していただけに残念。
星1つは、声優陣やスタッフさんへのねぎらいの意味。
私は好きな作品です。
昨日から公開なのをうっかり忘れていて、午前中に定期検診を入れてました。昨日、日テレで宣伝してるのを見て「しまった!唯一映画館で観られる朝イチ上映は?」と調べてみると…
大迫力音響『Dolby Atmos』を最大画面、追加料金なし!の謳い文句が!
なんということでしょう!映像の匠、人は彼をジブリの魔術師と呼ぶ、そんな宮崎駿監督の技を10年ぶりに感じられる土曜の朝。(加藤みどりさん風に)
前置き・枕はこれくらいにして、一応『枕』に韻を踏んでみるとまさにビフォア・アフターではないですが、観る前の気持ちと観終わった後の気持ちがこれほど劇的に変わるとは思ってもみませんでした。
前情報があまりにないことと、急に観ることになったせいで予習不足は否めず、このままでは赤点必至なので、封切り日のまだ少ないレビュー40件くらいを見てからの鑑賞。『宮崎駿も終わりだ』『訳わからん』『駄作』みたいな書込みが多かったせいでハードルをくるぶしくらいに落としての鑑賞。
いえいえ、確かに難解で子供向けではありませんが(他のジブリ作品も大人向けのもの、結構多いですよね!)米津玄師さんのエンディング曲が流れた時には涙が出てきてました。もしかして本当に宮崎監督作品の見納め?という感情だけではないと思いますが、娘、孫まで3世代の情操教育を担ってくれたジブリ作品から宮崎監督が足を洗う(もっといい表現ないものでしょうか?)ことの寂しさをひしひしと感じたことは間違いありません!
正直1回目ではまだまだ消化不良ではありますが、これから何度か観直すごとに理解を深めながら感動も重ねていくことになると思います。
本編に触れるなら『ハウルの動く城』『千と千尋の神隠し』『となりのトトロ』『崖の上のポニョ』『魔女の宅急便』『思い出のマーニー(宮崎監督作品ではありませんが)』他、たくさんのジブリ作品のオマージュ、おばあちゃん軍団は湯婆婆やポニョの施設のお年寄りみたいですし、特に青鷺のおじさんはほぼカルシファーのキャラですよね。
強いて言うなら舞台を日本の戦中・戦後においた理由は今ひとつわかりませんが『風立ちぬ』も同じく宮崎監督の思い入れが大きいのでしょうね。ハウルとソフィのごとく眞人とお母さんのお互いを想う気持ちが痛いほど響いてきましたし、どなたか書かれていましたが積み木の数と宮崎作品の数、宮崎監督が離れたあとの『ぼくたち』はどう生きるか、が深く深く響いてきます。
あとは言うまでもなくジブリ作品特有の美しすぎる映像と久石譲さんの美しい旋律、声優をつとめられた皆さんの素晴らしさに感動です。宮崎駿監督作品をBlu-rayBOX(高かった!)で買って毎週、孫とトトロ鑑賞にいそしむ(ガンバレルーヤのまひるさんのごとくセリフを暗記してしまいそうです!)お年寄りとしては「いいものを観せていただきました!美味しゅうございました。(岸朝子さん?)」が率直な感想です。さあ2回目でもっと深掘りしなきゃ!
DNAを揺さぶる宮﨑駿の脳内プロジェクション
公開初日のレイトショーで鑑賞。上映開始直前まで情報を遮断したかったので、SNSは開かず周囲の会話も耳にしないようイヤホンを装着したまま座席に着いた。ここまでまっさらな状態で向き合う映画体験が昨今あっただろうか。声優のイメージや事前情報による余計な先入観に引っ張られることなく、物語と絵に全ての集中力を注ぐことができた…いや、そんな能動的な状態ではなく、全神経が勝手に持っていかれた。それだけで至福の時間だった。
最初から最後まで宮﨑駿節が全開。彼にしか生み出すことのできない、あの独特の絵の表現、キャラクター造形、ストーリーとが凝縮されていた。(詰め込むだけ詰め込んであった、という方が正直なところかもしれないが…。)「私はいま宮﨑駿の新作を見ているんだ・・・!」という興奮がずっと続いた。と同時に、本当にこの作品をもって引退するんだな、という決意というか哀愁を感じて、エンドロールではホロホロと涙が溢れてきた。米津玄師の主題歌も良かったな…。
監督の自叙伝的なお話しと聞いていたが、まさに監督の思想や悔恨みたいなものを映像化した、監督の脳内をスクリーンにプロジェクションしているような、そんな作品だった。「君たちはどう生きるか」は劇中で主人公が読む本のタイトルだった。母親から主人公へと贈られたその本はどんな内容なのだろうかと、そこにも興味を惹かれた。
「難しかった」とか「よく分からなかった」みたいな感想を抱く人もいると思う。でも私は、難解さや意味不明さがイコールつまらないにはならないと思っているし、分からないからこその面白さが宮﨑駿監督作品の醍醐味ではないかと思うくらいだ。私自身、小学校低学年の頃に「風の谷のナウシカ」を観たのが宮﨑駿作品との出会いだが、あの時の「・・・よく分からないけど、なんかすごい面白かった・・・」(それから何度も繰り返し観た)感覚はもはやDNAに刻まれていると言ってもいい。中年になった今日に、幼少期と同じ感覚を呼び覚まされた、そんな体験だった。日本に生まれ、宮﨑駿が生む作品と共に育ってきた私には、条件反射のように揺さぶられる感情があるのだ。
さて、もう一度劇場で鑑賞したら、どんな感想を持つだろうか。確かめてみたいと思っている。
彼が世界を受け入れる話。
今、世界は揺れている。
未曾有のパンデミック。大国による侵略。金利上昇に伴う銀行危機。
挙げだしたらキリがない。科学技術は進み、数十年、数百年前の世界と比べてみれば、世界は確実に豊かになったと言えるだろう。しかしこれは、人々の人生が良くなったことを意味するのだろうか。
世界は揺れている。
崩れてしまうのかもしれない。それでも彼は、皆がいるこの世界を愛し続けるのだ。
斯様な主張が感じ取れる今作であったが、前作に『風立ちぬ』を撮ったとは思えないほどケレン味溢れる描写が多く、特に序盤の炎に包まれるシーンは、御年82歳にして新たな扉を開けたようだった。
ただ、前述の主張にたどりつくまでのプロセスが十分に描ききれていなかったようにも感じる。なぜ彼は大叔父の提案を拒むほどに世界を愛しているのか。
ナウシカっぽい終わり方だし、ナウシカくらい感情移入しにくい主人公だった。
*追記(2回目)
あれ、あんま面白くない?
ストーリーわかった状態でもう一度見てみると、この映画、思ったよりもとっちらかっている。
「夏子を取り戻しに行く」という目標はあるものの、ワラワラに出会ってみたり、インコに殺されそうになったり、ヒミとご飯を食べたり、本筋と関係ないようなことが多すぎる。
テーマにしても同様で、複数のテーマが同時に語られるので結局何が伝えたい映画なのか掴めない。まず分かりやすいものが「少年が母の元から巣立ち、自立する」という物語。そして「混乱した現在でも、生き続けなければない」というメッセージ。最後に「共存する生と死」という概念。これはワラワラという生命の源が魚を殺さなければ生きていけないことや、そのワラワラを食べるペリカンですら自分たちの命のために行動していることからも分かる。
僕たちは何を見せられたのだろう?
Twitter大喜利以外の事前情報無しに観ました。
素直に考えると、宮﨑駿さんの内なる情景、もしくは自伝的ストーリーと捉えるのが筋なんだろう。そういう意味ではこれまでのナウシカから風立ちぬまでもそうであったはず。
〜〜〜以下ストーリーの感想やら印象やら疑問〜〜〜
今時の流行りや商業ベース狙うなら、主人公は女の子かと思ったら、ストレートに男の子、それも美少年を強調してたのはどう言った意味があるのだろう?
城の大伯父さまと実母、夏子ママと、主人公の真人の血のつながりもかなり強調されていたのは、どういう伏線、もしくはテーマなんだろう?
主人公の真人の出自が地方の地主か名士の裕福な家系であるところから、パラレルワンダーランドに迷い込むところ、全てが終わって最後に東京という現実に戻るところまでが予定調和的だった。
インコの帝国は何かのパロディ(奪い奪われ合う現実の人間社会の?)かもだが、インコの王様は最後何がしたかった?
〜〜〜
何年か何十年後かにまた、この映画の内容と宮﨑さんが伝えたかった事について考えることになるかもしれないが、それまでゆっくり温めてておこう。
作る前に誰も止めないのか?
義理の母といきなり近づきすぎ。
最後になって現実で鳥はなぜ消える?
地下の世界はあの後どうする?なくてよかったのでは?
婆さんのお守りたちはなに?
なぜ鳥?
題名何?
友達作る?なぜそれで納得する?
ハァ?ハァ??ハァ??
とにかく内容についてパヤオとかに指摘するとハラスメント系で誰も何も言えないとか?
一番良かったのは始まる前のIMAXの紹介映像は最高!
初日鑑賞後???が巡った。
何コレどういうこと?
一夜明けてみると、宮﨑監督の集大成というか、ああなんだかすごいモノを見てしまった感に包まれている。
というか大風呂敷を広げてたくさんのモチーフを詰め込んで、敢えて閉じずにリリースされている気が。
見てはならないとか、持ってきてはいけないとかの神話的な部分や、木火水土金、鳥は人の魂を運ぶ存在であること、改めて生と死はとても近いところにあるのではないかと。
そして、下の世界の眞人さんの冒険は、チルチルとミチルの物語を思い出した。
子供の頃から宮﨑監督の映画をなんとなく見続けてきてきたけれど、この作品はきちんと説明されずに不可解な部分が特に多い…
ただそれらが意味するものに、興味惹かれて色々と考えてしまう内容だと思う。
全762件中、621~640件目を表示