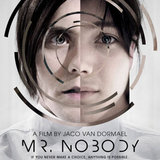君たちはどう生きるかのレビュー・感想・評価
全762件中、261~280件目を表示
1回じゃ理解不能
時間たってるからレビューとか見ればなんとなく物語を心して見れたけど、何も入れないでみると途中から訳がわからなくて世界に入りきれない💦。
声優さんとかは見たからつい探してたら木村拓哉さんは直ぐにわかったけど菅田将暉さんは後半であれっ?って気づいた(笑)。
他もなんとなくわかったけど滝沢カレンさんはわからなかった。
あとシーンの所々で過去のジブリ作品のオマージュシーンっぽいなって見てたらやっぱりそうだったみたい。
なんか名前が出てる所で「ドーラ」とかあったり、ハウルの婆さんの顔した婆さんいるし(笑)、その辺探すのも込みで2、3回見ないとわからないかもなー(笑)。
素晴らしい。君たちはどう生きるか?問われた作品でした。
観ている最中、涙が自然と流れてきて、懐かしさや愛おしさや、魂に触れるような。非常にメッセージ性があり、何回も観たくなる映画でした。
難しいというお声もたくさんあります。その理由もわかります。が、しかし何回も観て
あなたは自分の世界をどう生きる?と常に考える時間をもち、生きたいと思います。
またあの世界のことは忘れてしまうとのことですが
強力なお守りがあるから、覚えている。
わたしたちにとってこの映画こそがお守りになるのかなと思います。
たくさんの方に観ていただき、観た方たちで深く観察を語りたいです。
ジブリファンは楽しめます。推定(妄想)を含んだコメントも書いてみました。
感想としては、「宮崎監督の集大成作品」「日本のアニメ界の大御所集合」が大きな見所!!と思っています。
まずは、「集大成=自分オマージュがすごい!!」。宮崎アニメで育った人間としては、映画館いるにもかかわらず、隣の人に話しかけたくなる衝動を抑えるのにかなりの力がいる映画です。
こんな経験は初めてで、やはり偉大な監督の作品を追い続けるのは、大きな楽しみがあるなと実感しました。
覚えている限りで、
キリコと船での出航=未来少年コナン
大叔父の服=ナウシカの王蟲
異次元世界での壁登り=ラピュタ
亡霊船群=紅の豚
呪われた塔=五月とメイの家
冒頭の火事=火垂るの墓(高畑監督作品ですね)
一緒に観に行った者からは、「ポニョとハウルのシーンがあった」と言っていたので、多量の「オマージュ成分」ふくまれています。
本当に、宮崎監督やジブリ作品が好きな方にはたまらない魅力のある映画です。
ポスターの周りに貼られた作品群はすべてオマージュされているのかなと思っています。
エンドロールで、スタジオカラーやスタジオ地図などの大御所スタジオのクレジットがあり、オマージュに気をとられていたことを自覚され、すぐさま、映画の内容を思い返すという仕掛けもアニメファンに向けて用意されています。
ここからは根拠の全くない完全妄想ですが、
ゼロ戦の風防(キャノピー)は、「無駄に時間をとったシーンであり、滅茶苦茶クオリティーが高い」「他の場面とのバランスをギリギリ崩すことを狙った兵器愛あふれる写実表現」から、根拠はないですが、庵野監督のお仕事だと勝手に確信しています。
細田監督部分は、「急に躍動感が上がって,その後元に戻った」ところを考えて「なつこを探して塔の中に入ってからのシーン」がそうなかなと、消去法的に推定しています。
妄想を含む感想部分ですので、後で情報が出たら、間違っていると笑ってください。
こういう妄想を書いてしまうことも含めて,鑑賞後も楽しんでいます。
こんな映画は、滅多に出会えないと思います。
まだ、他の方の感想を観ていないので、これから観ます。それも楽しみです!!
心躍る映画でした。
ネタバレありますのでご容赦ください。
ジブリの映画では、今まであまり取り上げられなかった母親への恋慕と女性への目覚めを少年を通して描かれていたと思いました。
なんと言っても今までのジブリに無い艶っぽいキャラクターが今回のヒロイン?のポジションに存在感満々で描かれています。
そこにまず心躍る人は多かったかもです。
でも、少年も観客もその性的存在感に気がつかないと言う演出や構成がされている。
だから、わかりにくい。
宮崎さんは、自分の母への想いや性的な表現があからさまにバレる事を恥ずかしく思っていたと思います。だから今まで取り上げてこなかった。
今回そこに挑戦したように思います。
だから、いろいろ心ざわつくのに、心躍るのにそれがどこから来るのか見た人はよくわからない。そこが86才の巨匠の狙いだった。
人間の生きる動機は、ラブとエロなんですね。それが同化しているのが人間です。
でも自我を優先すると必ず軋轢が起きる。想いは叶わない。死別もあれば失恋もある。望まない出会いや邪な欲望も起きる。
それが国レベルになると、発展や成長にもなり、戦争や抑圧にも拡大する。
なんと、個人も人類も罪深い存在である事をジブリ映画は、破壊と再生、喪失と希望を織り交ぜて表現してきました。
でもその根源的な、欲望の中心にある、性的な自我を描く事を避けて来た。
そこを、少年にも気づかれず、観客にも気づかれず、この作品で描いてしまった宮崎駿のエネルギーはどこから来るのだろうかと驚きます。
二人の女性と少年で、恋心から世界の誕生まで描いてしまうのには恐れいりました。
さらに、欲望を昇華して、成長や生産に向かうとはどういう事なのかも、語っています。でもそこをわかりやすくすると、説教じみてしまうので、そこも選択枝で表現されているのでわかりにくい。
見て、よくわからないけど、こころざわついた方は、宮崎駿の術中にハマったと言うところです。
タイトルなし(ネタバレ)
公開から日が経っており、不評なレビューも見かけたが、ハヤオの映画は最後かもしれない、そう思うと見ずにはいられない。映像はやっぱりジブリという感じで新しさはないが、ジブリと言えばこれ、懐かしさもあるが古いと思う。
つまらなくはない。序盤から青サギが現れて、これが何か謎であり、観客の関心を惹きつけ続けるだろう。
主人公マヒトは中学生位?だろうか、少年であるが優秀である。戦争で母を失い、父の田舎の実家?に引っ越しする。母の妹が新しい母であるが心を開けないようだ。新しい母のお腹には子供を授かっている。
田舎と言っても大豪邸。家は大きく部屋は広い。10人位の高齢のお手伝いさんがいる。マヒトや母は美形であるが、お手伝いさんたちはリアリティがなく、お化けみたいな容姿だ。
青サギの中身はおっさん。マヒトの先祖である大伯父からの指示でマヒトをあっちの世界に連れて行こうとする。大伯父は昔神隠しに会っていて行方不明。実際にはあちらの世界の平和を守っている。
マヒトの新しい母、夏子と言ったか?、が山に入っていくのをマヒトは見ていた。その後、夏子が行方不明になり、マヒトは夏子の捜索にお手伝いのキリコと一緒に山に入る。その先でマヒトとキリコは青サギの狙い通りあちらの世界に行ってしまう。
あちらの世界では、キリコは若返っている。インコは人間みたいだ。
宮﨑駿の夢であり神話
宮崎駿の最後の作品かもしれないので行ってきました。自分は決してジブリのファンではないのでジブリ作品は見ていない作品がいくつかありますが、宮崎駿は全ての映画作品と未来少年コナン、風の谷のナウシカ(漫画)、宮崎駿の妄想ノート、泥の虎、などを見てきています。さらに原体験的に6歳くらいに再放送されていたパンダコパンダまで見ています。振り返りますと宮崎駿のファンであったなと思います。
他のレビューを見ていますとジブリ作品ってこういうものなの?という感想が見られます。初めて映画館でジブリ作品を見たのがこの作品なのでしょう。確かに「ラピュタ」「トトロ」「魔女の宅急便」と比べると分からない作品だと思いますが、宮崎駿の過去作を見てきた自分には「こういうのも宮崎さんだね」ということで納得をしています。ミリオタであり、児童文学作者であり、神話好きであり、SF作家でもあるのが宮﨑監督です。今回はかなり神話よりの児童文学的作品だと思います。
ストーリーが分からないというコメントがありますが、物語の主点は少年の成長です。主人公眞人は母の死という受け入れがたい喪失によって心の傷を負っています。彼は疎開先の父の実家の裏山にある塔の下の世界に降りていき、そこで下の世界創造の秘密を握る大叔父と実の母の少女時代であるヒミ、その他アオサギ、傷ついたペリカン、キリコなどに出会い成長します。主人公を導くアオサギは神話でいうところのトリックスターです。アオサギは主人公を異世界に導き成長を促します。少年の成長を中心に据えた異世界冒険譚として捉えますと分かりやすくなります。
また、古典的な物語としてオイディプス王の物語が取り入れられています。母久子を亡くした眞人は母に似ていて優しく妖艶な夏子に惹かれます。眞人が夏子に惹かれているのは後にキリコから「その人のことが好きなのか」と問われて「お父さんの奥さんだから」と答えることで分かります。眞人は自分の夏子への思いを父の後妻さんだからと抑え込んでいるのです。眞人は父と夏子のキスシーンを盗見しますが子どもの彼はどうにもできません。つわりで寝込んでいる夏子の病室に眞人は訪れ傷を優しくなでられ労りの言葉を受けますが、しかしそれは母としての労りであり自分のものにはなりません。その自分のものにならないという思いは憎しみとなりタバコを盗むという行為で代償します。
ここで私は驚きました。主人公が堂々と盗みを働く宮崎作品を初めて見ました。また少年の性欲を隠さず描いています(とても上品にオブラートで包みながら)このような点でこの作品が宮崎監督作品ではなく宮`﨑`監督作品であると理解ができました。有り体に言えば宮崎駿が初めてパンツを脱いで下半身を私たちに見せているのです。
眞人は夏子が塔に向かっているのを見て追いかけます。この時点で母捜しと夏子探しは重なっています。ここで細かい辻褄がおかしくなることで物語が難しくなりますが、しかし眞人の無意識化の次元では母久子と夏子は重なって認識されているので物語上ではあまり問題にはなりません。下の世界で実母の少女時代であるヒミと出会い、夏子が向かった産室までたどり着きますがそこで夏子から拒絶されます。このあたりはイザナギに桃を投げつける黄泉に降るイザナミのようです。黄泉下りと桃による神々の誕生が重なるように生と死がこの世界では両立します。そしてイザナミが姿をイザナギに隠したように、出産の場所は他者に見られてはいけないのです。女ではない母としての夏子を見てしまった眞人は「夏子お母さん」と呼びかけます。ここで父を殺して母を娶るという無意識下の眞人の思いは頓挫します。
眞人の現実の父は善い人ですが現実に生きる企業人でかつ眞人のことを理解していません。塔の向こうの世界も分からず入ることもできません。話はあくまで少年と母たち(キリコ、婆やたちを含む)だけで進みます。少年と母と動物しかいない下の世界にいるもう一人の男性は大叔父です。大叔父は13個の石を3日に一個積むことでこの下の世界を絶妙なバランスで維持しています。一つの解釈ではこの13個の石はジブリの過去作、13×3でジブリが続いた39年、そして大叔父は宮﨑監督、という解釈も成り立ちますが、そこは神話的物語として寓意が開かれています。つまり、解釈はいくらでも可能なのでこれという答えがあるわけではありません。大叔父は自分の血族の中から誰かが下の世界を継ぐことを待ち望んでいました。眞人に善意だけでできたこの石で積み木を続けて世界を維持してくれと頼みます。しかし、善意だけでできた石など嘘だと眞人は傷ついたペリカンとの出会いで知ってます。理想郷を作ろうとした大叔父の善意は多くの人を傷つける偽善的な世界を作りだし、この世界は人を食べる獰猛で扇動されやすいインコの大群に占拠されつつあったのです。大叔父は塔の最上部で下層の苦しみを何も理解しないまま積み木をつみ続けていたのです。眞人は傷を見せて自分が無垢ではないと示します。この傷の意味も多様だと思います、継母に欲情する汚い性欲、友達を作れない傲慢さ、金持ちとして生まれたことの負い目、いろいろあるでしょうが物語的に意味は開かれています。そして眞人は汚さと苦しみのある現実世界に戻りアオサギのように善悪美醜両方を持つ多くの人々と「友達」となることを宣言します。男が一人しかいない理想の美しい世界に閉じこもることを拒絶して美醜が混在する現実に欲望と痛みを持った一人となって戻るのです。異世界冒険譚は主人公が死などによって異世界に降りて、そこで敵と戦うなどの困難を経て元の世界になかった宝を持って戻ることが主要テーマになっています。ここで眞人は、下の世界の王になる、あるいは塔の宝を持って帰るのではなく、「現実で友達を作る」という決意持って現実世界に戻るのです。友情を作るという決意、これが主人公が現実に戻ることに対して宮﨑監督が持って帰って欲しいと思った宝でした。これは現代における神話として監督が少年少女に示す一つの解でした。
物語的に父の代わりである大叔父の願いを拒絶することで王殺しを達成した眞人は下の世界から現実へと戻ります、その現実へと戻る際に実母の少女時代であるヒミと別れます。火に焼かれて死ぬ世界に戻るのかと眞人は母ヒミに問いかけます。この問いに「眞人に出会いたいから戻る」と答えます。父から母を奪い娶るという形での性の解消ではなく、母が父と結ばれることで自分が生まれ、自分が母から強く望まれて生まれるという生殖の営みが示されたことで別の形での性の解消となり宮﨑版オイディプス王物語は終わります。ここで私は奇妙な爽快感を覚えました。大叔父に代わり下の世界の王となることで自己を自己が肯定するのではなく、母からありのままのあなたを愛している、と言われることで他者からの肯定を眞人は得たのです。眞人は母を救えなかったという負い目から解消され、うじうじしていた自分を含めた存在そのものを亡き母から全肯定されました。ここが物語の終結点だと私には思えます。このような聖母的な母かつ少女から全肯定されたいという宮﨑監督の思いを「気持ち悪い」と突き放したいという思いも私にはあります。ですが火事で死ぬことが決まっている世界に戻る母から「あなたに会いたいから」と言われることの感動が上回りました。
正直、この映画は細かいつじつまを追って行くと疲れるだけです。設定や登場人物の動きは主人公が体験する主観のためにあるものでつじつまが合わない部分も多いです。ですが、主人公の主観的な物語はちゃんと追えていますので眞人の主観を中心で見ていけば物語は理解できます。また、最近の漫画やアニメのように主人公が感情を吐露したり、脇役が状況を台詞で詳しく説明もしてくれません。ですので、見ている方に絵や行動から物語を解釈する力が求められます。そういう点で万人向けでありませんし、また近代の小説(物語)というより昔話や神話の方に近く作られているため主人公が内心を吐露することはあまりしません。ですので、最近の物語(小説、漫画、アニメ)に慣れている人は面食らうと思いますが、動きや表情をよく観察し、台詞の裏の思いを推し量っていけばなんとなく感情は想像できて流れを追うことができます。
私個人は最近の映画やドラマにある、オーバーで分かりやすい演技、なぜか状況説明を台詞でしだす登場人物、色分けや容姿でハッキリと分かる敵味方、などに食傷気味でしたので、分かりやすさに全く媚びなかった宮﨑駿に共感しています。また、これだけの作品を作った宮﨑監督に次の作品がないとは思えません。一つ言えるのはこれ作ったら漫画版ナウシカのアニメ化は必要ないなということです。それは、大叔父と眞人、インコ大王、アオサギのラストが漫画版ナウシカまんまだったので。
楽しみ方ガイド(ついでに考察と解説)
IMAXで2回、ノーマルで1回視聴後の感想。
ようやくこの映画の楽しみ方がわかりました。
コレは全12話くらいのシリーズを2時間にまとめた総集編だと思えば非常に楽しめる映画。
(ソレだけの強度と奥行がこの2時間に凝縮されてる)
登場人物の行動が突飛で意味不明、シーンの繋ぎがバラバラ、などと感じるのは、本来描くべき場面をカットして編集しているのだと考えれば納得。
「君たちはどう生きるか」というタイトルはつまり
「君たちはこの映画のカットされたシーンを、どんな風に想像(創造)して今後の人生をどう豊かに生きるか?」という問いかけなのです。
作品のテーマはズバリ「想像力を育もう。他者の心情を慮って友達を作ろう」です。
はっきり言って説明不足も甚だしい映画なので否定的な意見が多い作品ですが、想像力を駆使して自分だけの完全で納得なストーリーを脳内で補完しましょう。
(全12話設定ですと、当然キリコさん以外も全員若い姿で大集合です。例えばメガネの婆さんは「ド近眼のドジっ娘天然美少女」として登場!など)
さぁ、段々楽しくなってきましたね?
さらに言えば、宮崎駿初の本格派ダーク・ファンタジーなのでコレをリアルタイムに視聴出来る我々はラッキー。
「亡くなった奥さんの妹と再婚とか超キモいんですけど~」などの意見も聞きますが、昔はよくあった風習(順延婚)なのでキモくありません。
(私の父方の祖父母がそうでした)
特にあの家系は家柄良さそうですしね。
「アオサギは誰?」「大叔父は誰?」「下の異世界はジブリ?」「墓に眠るのは誰?」「このシーンは過去作のオマージュ?」とか、そんな作品のテーマから外れた穿った見方はYouTubeの考察動画投稿者にでも任せて、宮崎駿ファンはただこの映画体験を純粋に楽しめばよろしいのです。
(そもそも、同じモチーフの使い回しなど宮崎作品ではお馴染みなので「このシーンはあの作品からの引用~」「ジブリ映画の総決算!」とか、
「おま、、、いまさら何言ってんの?」と片腹痛くなります)
そして、筋金入りの駿ガチ勢である私の個人的な意見としては
“(映画)初監督作品の「カリ城」が評価はめちゃ高いのに公開時の興行収益はめちゃ低かった”
の真逆の”現象“を最後の最期に創り出した、監督の壮大な伏線回収(あるいは皮肉を効かせた復讐?これこそ、もうひとつのテーマである“悪意”)に愉快痛快、ゆえに私は拍手喝采。
(ちなみに、初“演出”作品の「未来少年コナン」は日本のテレビアニメ史上至高の大傑作だが、視聴率が低かったので知名度も低かった。これも今の状況とは真逆)
、、、。
さて、ココからは私なりの“穿った”考察的解説になります。
・主人公のモデルは監督のお兄さん?
駿監督なら、自身をモデルにしたキャラクターを美形には設定しないでしょう。
監督本人は最後にチラと出た幼児。
つまり宮崎駿が誕生するまでの物語と言えます。
(そう考えると、ワラワラの飛翔シーンや産屋での眞人とナツコのやり取りも違って見えてくるでしょ?)
・主人公の自傷行為とイニシエーション。
眞人は最初、礼儀正しいが世間知らずの自己中心的な少年として描かれています。
労働奉仕を拒絶してクラスメイトとケンカした挙げ句、腹いせに自傷行為で登校拒否を正当化。
ナツコさんが行方不明になった時も、
近付くことすら禁止されてた謎の塔に接触する口実が出来たとばかりに自作の竹弓矢で敵=アオサギを退治するコトの方を優先。
(この前に母が残した「君たちはどう生きるか」を読んでいますが、ソレはまだ“知識”にすぎない)
その後、下の世界で若キリコさんからの教導=労働を体験し、死と生の循環を目の当たりにするコトで、本で読んだ「人間は社会的動物で、他者との関わり無しには生きていけない」を知識と実践で真に理解します。
ココで眞人はようやく物語の主人公たる「人格」を得るのです。
アオサギと和解しようとしたり、ナツコさんを「ナツコ母さん」と呼ぶようになるのも、このイニシエーションがあったからですね。
(むしろナツコさんの方こそ本心では冷たく自己中な眞人を疎ましく思っていた。当たり前である)
最後に面白注目ポイント。
・お婆さんズが妖怪にしか見えない。
・出てくる鳥がもれなくキモい。
・「風切りの7番」優秀すぎ。
・青鷺と眞人のほのぼのDIY。
・包丁を研ぐインコで爆笑。
・インコ大王、結局何したかった?
・鳥が群れると周辺は糞だらけ、コレめっちゃリアル。
・ナツコさんが異常にエロい。
・ヒミ様の本名は久子?
・最後は結局ハッピーエンド、いつものジブリ映画。
それでは皆さん、この世紀の大傑作を心逝くまで楽しんで、ビッグウェーブに乗り遅れるな!
2回、3回と映画館にゴーだ!!
今までとは違う感動
ジブリ好きの娘が先に見に行った感想があまり良くなかったので、あまり期待はせずに鑑賞しました。
結果本当に良かった!
わたしは大のナウシカファンですが、ナウシカのマンガを現代風にアレンジしたもののように感じました。
ところどころにラピュタや千と千尋、紅の豚などを思い起こさせる要素はあれど、異世界・石・壊す・崩壊・現世界の重要要素はナウシカからそのまま引き継がれていてるように思います。
なぜ石を壊されたのか、なぜその道を進むことを決意したのかは、ナウシカでは6巻かけた結果に対して、映画はたった2時間なので唐突に感じる部分もあります。
ただ、これを書きたかったんだ!(漫画版ナウシカ)と勝手に思い込んでいるナウシカオタクの身としては、映像化されたことに深く深く感動しました。
内容どうのこうのというよりも、ずっとずっとこれを見たかった。石の内部を見たかったし、黒い部分も見たかった。
宮崎駿が言いたかったことは、結局初期作品からずっとブレずに変わっていないのかな、と感じました。
ありがとう!!
きっとみんな忘れているから、ジブリが描くことに意味がある
一言で言えば、「あの頃は良かったなあ」を具現化し、全ての人へ今とこれからを問いてくる映画だと思う。
ほとんどの場面は様々なジブリ作品が内包する薄気味悪さを凝縮させて根底に広げた感じ。それをすべてひっくるめて、ラストと主題歌で浄化してくれる。
主人公が出会うあらゆる「場所」は、前述のように薄気味悪さが常にある。それは多分、社会的なものでもあり個々人が持つものでもある、理不尽さだったり悪意だったり怖さだったり。それらが渦巻く世界で、主人公だけが浮いている、特別である。それは、主人公がもつ、子どもらしさ所以じゃないかと思う。
「子どもらしい」とは、良くも悪くも使われる。純粋無垢を意味することもあれば、それゆえの残酷さを示す場合もある。それでもなお、主人公は「子どもらしく」、等身大で、純粋無垢で、真っすぐである。当初は産みのお母さんへの思いもありナツコさんのことをお母さんだと受け入れられず(この年代なら当たり前だと思う)、他人行儀であり、「お父さんの好きな人」と話していた。一方お父さんに対しても、熱血すぎるところをちょっと疎ましくも思っていて、でも全力で注がれている愛情をちゃんと分かっていて。だからキリコさんに「嫌いでしょ」と言われたようにナツコさんを好ましく思ってなかったとしても、絶対に助けたかったのかなと思う。親を助けたい、役に立ちたいという子どもの時に抱く背伸びした気持ちもあれば、火事の時にお母さんを助けられなかったからかもしれない。どちらにせよ、その一心な想いと子どもらしさを持っていたから、あんな世界でも常に前に進み続けられたんだと思う。
要所要所の主人公の行動に対して、なんでそんなことするの!?って思えた人は大人なんだと思う。好奇心の赴くままに突撃したり、自分で工夫して道具を完成させたり、怖いくらい怖いものしらずだったり、迷惑かけられたのに死にゆく間際の話を聞いて同情したり、その場で出会った人をちゃんと信じられたり。そういった子どもらしさを、多くの人が幼い頃持っていたはず。例えば、ある日隕石が落ちてきたら、この水面の下にもう一つの世界があったなら。もしも魔法が使えたら、突然誰かを助けるヒーローになれたなら。走り回って冒険した場所があったり、秘密基地を作ったり、あの日拾った宝物があって、夢中になれるなにかがあって。こどもの時の世界とか、あのときの自分だけの「ともだち」とか、夢とか希望とか、透き通った心とか。それらはいつか忘れてしまう、思い出の中に消えて行く、そうして大人になっていく。
そういった「あの頃」を忘れてしまった大人に、あの頃の良さをすくい上げて存分に目の前に広げたうえで、「それでは、君たちはどう生きるか」と聞いてくる。私はこれを、子どもだからこその世界を数々描いてきたジブリが、宮崎駿が手がけたことに、計り知れない良さを感じている。
加えて、映画の最後で、主題歌「地球儀」が響かなかった方は、ここで再度歌詞を見ながら聞いてみてほしい。映画の場面や上記の想いが丁寧に切り取られていることに気づけるのではないかと思う。
「罪悪」を扱った妥協のない作品
罪悪に敏感な人と鈍感な人がいます。
あるいは、人生のある時期に罪悪に敏感になることがあります。
この映画では、罪悪に敏感になった人たちが塔の中に迷い込んでいきました。
分かりやすい「殺生」という罪悪から、自己攻撃の罪悪、そして、善を追求する中に潜む巧妙な罪悪(墓と同じ石に象徴される)へと、塔の中では自己反省が深まっていきます。
善い人間、正しい人間であろうとすると、積み木の危ういバランスの中を生きるしかありません。人間はどうしても悪を犯すものだから。そして、自分の悪を隠すために、塔の中に隠れるしかありません。
インコたちは自分が唯一心を開ける相手として塔の主が飼っていたものでしょうか。
それでも最終的には、このインコによって塔は破壊されます。
「正しさ」の王国が実は積み木のようにもろい基盤であったと知るとき、何かが始まるのだと思います。
深くて妥協のないすごい作品でした。
失敗作 宮崎氏の自己満足? 売り方もセコイ
一言でいえば、お金持ちのお坊ちゃまが、マザコン特有のストレスで実社会になじめず
現実逃避の夢の中で、思ってたんとチャウ、カオスな展開に翻弄されてそれも嫌になり
目が覚めた後は普通に過ごせるようになりました。てな話。
作画が凄いとか聞いたのに、画角が液晶テレビサイズになってて、映画館のスクリーンに
合わず、右も左も余白(黒色)になってしまい、結果コンパクトなスクリーンで見せられてしまう。
こんなんなら、前から3列目くらいに座ればヨカッタ。 鬼滅の刃も同じだったねえ。
かと言って、画面が緻密で凄いかという事もなく、期待したせいか、いつ凄い絵が来るのか
待っていたら終わってしまった。多分動きの描写に注力したのかも。記憶に残らなかった。
声優も今一つ。せっかく呼んだ俳優さん達にアフレコして貰ったら雰囲気合わないからって
「チェンジ」と言えない大人の事情? 活舌も声質も不自然で、どう聞いてもボツなテイクばかり。
ジブリ全般もアメリカもそうだけど、声優使わずに俳優呼んで話題作りは結局失敗して終わり。
金持ちのボンボンを主役にしたのもアレだが、馬鹿親父が転校初日に田舎の学校の校庭に
当時は贅沢品の車で乗り付けて見せびらかしたせいで、地元の学生から忌み嫌われるという、
少し考えればわかりそうなタブーを犯すとか、主役サイドに感情移入できないキャラ設定。
まあ現実逃避して夢世界から帰りたくなくなるのもワカランではないが、この脚本は嫌いだ。
あのシーンにはこんな意味が・・とか、このエピソードはあの件の心情の投影だとか、
隠れキャラ探しの楽しみがあるとか解説する連中もいますが、伝わらない人が多すぎたら
それは成功ではなく失敗であり、それをよしとするなら自己満足でしかない。
上辺しか見ることができない奴は見るなと言うなら、内容を極秘にして世間煽って
金払った観客を集めるなんて、詐欺になっちまう。 その罪深さで減点は大きい。
映画としてはつまらない、と言う
宮崎駿監督作品を、映画館で観るのは「紅の豚」以来やも。と言うかテレビやらでもそれ以来まともに見ていない。そんな人からすると宮崎駿作品だからと言ってあまり期待も何もなく観に行ったんですが、端的に言ってつまらなかった。主人公の真人の心の動きは理解しがたいし、役者の演技は一部を除いて拙いと言っていいものだし、結びも結局何しにいったんだか?って感じ。行っても行かなくてもあの世界じゃなくても問題ない。はっきり言って夏子さんが何しに行ったのかわからないからあそこで起きたこと全てが無駄にしか見えない。
なんかこう、あそこはカリ城っぽいとかラピュタっぽいとかの古参へのご褒美はあったけど、そんなもんはどうでもいい単体の映画作品としてつまらない。あと、よっぽど宣伝目的の芸能人声優と言われたのが悔しかったんだな、あそこまで合ってないのに頑なに使ってるのがあれか。
扉からでたとこのシーンでインコの糞まみれになった夏子さんが次のシーンでは糞がなくなってる。あそこまでが幻想と現実の境目を表してる表現かと思えばお父さんは糞まみれ。あれミスじゃね?
君たちはどう生きるか
開始5秒でこの映像で新たな作品が見れることに喜びを感じた。
戦争で母を亡くし、父の再婚相手と共に暮らすことになった真人は青鷺とのやり取りのうちに不思議な世界に迷い込むというあらすじ。
物語の終盤、真人は選択を迫られる。
悪意の積み木を足して(戦争を続けて)世界を安定させる、悪意なき積み木で(戦争を忘れて)新たに世界を作る。
しかし真人が選んだのはそれらを理解した上で自分の世界を生きる事。悪意さえも無かったことにはせず、自らの弱さをも認め進む姿は気高く映る。
なんこれ?
「風立ちぬ」以来10年ぶりの宮崎駿監督最新作。正直「風立ちぬ」自体がだいぶ私に合わなかったため今回もあまり期待はしていなかったが、逆の意味で想像を超えてきた。まじで意味が分からない。
映画冒頭は作画がすごく、宮崎駿気合入ってんなーと少し期待したが、そこからは退屈な日常パートが体感1時間弱続く。意外と普通で拍子抜けだなと思っていたら後半からは怒涛のワニワニパニック。伏線をばらまきつつ整合性の取れないストーリーを展開し、最終的にほとんどの伏線を回収することなくおわり。
ぽけーっとした状態のままシアターを出てしばらくして我に返り、すぐにネットで解説を漁った。あれは宮崎駿の人生で、墓の主は宮崎駿自身で「我を学ぶものは死す」みたいなやつの意味は私を真似てアニメを作るのは失敗するぞって意味だ。13個の積み木は今まで彼が作ってきた作品で誰かに引き継いでほしいけどいない。ジブリ(石の世界?)はここで終わりって意味だ。みたいな解説を見て、なるほどあれは宮崎駿の内面を描いた映画なのか、と自分の中で何となく理解は出来た。でもそんなの映画にして観客に見せちゃいかんでしょ。そういう「このシーンにはストーリーにおける意味とは別にこういう別の意味があって~」みたいなのは元のストーリーがちゃんと成り立っているからこそ成立するのであって、元のストーリーぐちゃぐちゃにして自分の内面を映像にしてペタペタつなぎ合わせていったのを映画と呼んでいいの?なんかこの映画はアートだから感じるんだ!みたいな意見もあるけど、アートなら映画館じゃなくて美術館でやってもらわなきゃ。
映画はジャンルはなんであれその究極の目的は人を楽しませること、つまりエンタメにあるはずだ。私はそう思う。今回の映画を作るにあたって監督はそのことを少しでも考えて作ったのだろうか。なんとなく今回の映画の意味が分かったうえでも、これは監督の自己満足のために作られた映画としか思えない。肯定的な意見を述べている人も、この映画をジブリや宮崎駿監督と切り離して、単純に一つの映画として見せても(絵的に即バレだろうけど)同じ感想を抱くのだろうか。とても気になる。どんなにその映画に含意されている内容、メッセージが素晴らしいと言っても、映画自体が面白くなかったらそれは駄作だろう。少なくとも本作は映画館で大勢の人に見てもらう映画ではない。
期待していなかったと言いつつも、やはりジブリには大好きで思い入れのある作品も多い分、やはり心の底では楽しみにしている気持ちもが自分の中では強く、久しぶりにジブリ映画を映画館で見れた満足感はあった。それだけに私的には本作の出来は非常に残念だった。
良い映画。
宮崎駿というビッグネームにつられて見に行ったが、見に行ったことを後悔させないような良い映画だった。事前情報が全くなかったため、より一層新鮮な気持ちで鑑賞できた。
疎開先で虐められた眞人がキリコやヒミ、大叔父の生き様を肌で感じ、どう生きていくのか。どうしてヒミは火の力を使えるのか、アオサギの正体は何なのか、一体扉の先の世界はなんだったのか。背景が描写されていないものや細かく説明がなされないものが多かった。悪く言ってしまえば不親切で理解しにくく、どういうメッセージがあるのかが伝わりにくい映画だ。
確かに受け手に伝わりやすい映画というのはストーリーがよく分かるし登場人物に感情移入しやすい。こういった親切な映画は不親切な映画と比べ面白いと言われる。これは自然なことであり、今回の映画が面白くない、分からないと言われるのも頷ける。ただ、考える余地を残している映画だからこそ多種多様な解釈の仕方があり、映画にこめられたメッセージの受け取り方も違う。「君たちはどう生きるか」というタイトルにもあるように、どう感じるか、どう考えるかは今を生きる私たちが考えるべきことである。「眞人はこう生きていくのだろう、キリコはこう生きてきた。じゃあ私はどう生きたいのか。」
人生の生きる意味を考えさせる素晴らしい映画だと感じた。
文七元結や紺屋高尾と一緒で…
タイトルに縛られちゃうと、なんだこりゃ?になる。タイトルはたまたまあの時代に流行った本から借りただけ(ぶっちゃけ「われら少国民」でも構わん)
内容は、あるジブリ作品(ネタばれになるから書かない^^)をバックボーンにして、そそこにジブリ作品のあちこちから部品としてはめた宮崎カラー全開の映画だなと思った。MCU総出演のジブリ版かな?予告も流さず、パンフレットも作らず、うまくやったなと。世間は賛否両論だが、自分はプラス評価。これはあれから、あれはそれから、と元ネタを探しながら見るのも一興か。
自分の中の答えを出す為にもう一度観たい
衝撃的だった台詞が、うろ覚えなんだけど火事に遭ってしまったお母さんの別世界キャラの台詞。お前と会えたから火も悪くないよ、みたいな。
ギュッと抱きついた無邪気なあの姿は私の見間違いなのか…帰り道で泣きそうになって堪えたけど、私達はこんな残酷な世界でも結局人を愛して生きている。その救いをもう一度確かめに行きたい。
宮崎駿はこう生きた。からの〜、君たちはどう生きるのか?
表面だけ追ってると、単に叔母さんを助けに行って帰ってくるファンタジー物語。
その奥は、母を失った少年が、叔母を母として受け入れるまでの成長物語。
その裏には、自分の中にある悪意を認め、人間とは純粋ばかりではなく悪があってこそ人間たりうるという人生哲学。
しかしてその実態は、散りばめられた過去作のオマージュを丁寧に追っていくことで、この映画は宮崎駿の人生のオマージュであり創作に対する宮崎駿の意見表明だとわかる。
その上で、自分の次の世代に、どう生き、どう創作をしていくのかを問うているのが本作なのだと、私は理解した。
このように、なかなか良く考えられた構造の映画ではあるが、いかんせん、オマージュを多用して自分の人生を語り、メッセージを伝えるという多層構造は、数年前に弟子の庵野秀明がシン・エヴァンゲリオンでやった手法なわけで。そういう意味で映画の構造に新鮮味は感じられなかった。(まあ、知っていたから理解できたと言う面もあるが)
そもそも、伝えられる宮崎駿の創作論とか人生観に、イマイチ興味が湧かなかったという・・・。
そして何より、表面のストーリーがイマイチ面白くない! ボケーっと見てたら、多分つまらない退屈な映画、星1という評価だったろう。
そんなわけで星3ぐらいにしておきます。
ポニョの別バージョン?
日本では、魂は海からやってきて生まれ、死ぬと鳥となって飛び立ちます。
だから、ポニョが半魚人化したとき、鳥の脚を持つことに妙に納得したのです。
今回も、死後の世界、あるいは生まれてくる前の世界が描かれていますが、そこにはたくさんの鳥がいます。
彼らは死んだばかりの魂?
インコたちは、太平洋戦争で命を落とした兵士の魂でしょうか。
生まれ出る命、「わらわら」は、魚の内臓を食べて飛翔します。
わらわらを食べて、この世に生まれることを邪魔するペリカンたちは、なんのメタファなのか。
ポニョでは、宗介が「以前通ったことのあるトンネル」を抜け、「あの世」と思わしき世界へ到着しました。
今作では「通路」が登場しています。
大叔父が司っていた、今にも崩れそうな「世界」が太平洋戦争に敗北する日本なのだとしたら、大叔父とはいったい何者なのでしょう。
命の循環を、宮崎駿監督は、なんとして語り掛けているのか、一度ではわかりませんでした。
物語のもう一つのテーマは、「母を喪失した少年が、新たな母を得て母子になっていく物語」ではなかろうかと思います。
当時、妻が亡くなると、その妹を妻にすることは珍しくなかったのでしょうが、ナツコには姉への遠慮があり、眞人にも複雑な感情があったはずです。
亡き母とそっくりなナツコへの思慕もあるでしょうし、それでも母とは違うというためらいもあったのではないかと思います。
その葛藤が、「ナツコさんを探しに行く」ことでほどけていく過程が描かれているのかと。
なんにせよ、何度か見返さなくては、いろいろ見逃してることがありそうです。
よくわからないけど、それで良いよね。
周りの評判が良くなかったのと、原作を読んでいたので説教くさい作品かな〜と期待せずに鑑賞してみたらもの凄く良い作品だった。
内容は抽象画のような綺麗な映像とストーリーで受け手によって解釈は人それぞれになるのかなと思います。
自分の感想は良くわからない。
でもエンディングの地球のような青い映像と米津玄師さんのエンディング曲を聞いていたら自然と涙が溢れました。
積み木のように不安定で罪や戦争、死と生が混じり合った世界。
一つ一つのものに意味や理由などの答えがはっきりと存在しなくてもいいのではと思えました。
良くわからなかったけれど、感じるものありました。
また5年、10年経った時に観てみたいと思える映画です。
全762件中、261~280件目を表示