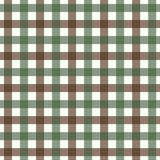君たちはどう生きるかのレビュー・感想・評価
全1334件中、141~160件目を表示
熱量に圧倒される
恥ずかしながらジブリ作品を映画館で初鑑賞。昔は金曜ロードショー頼り、紅の豚より後はテレビですら観ていないものだらけだ。しかし今回は、ジブリらしからぬタイトルとアカデミー賞授賞という話題に押されて映画館で鑑賞した。
スクリーンで観るとやっぱり映画の凄さを感じる。冒頭の火事のシーン。炎の迫力や主人公の必死さはテレビではこれほどには伝わらないだろう。
観ていて気付いたのは、過去の作品群を彷彿とさせる様々なシーン。これまで、こういうシーンは無かった気がする。まるでこれが集大成であるといわんばかり。
母親を亡くした主人公、母の妹が父の再婚相手としていきなり現れる。自分と周囲の時間の流れの違いや、母の面影のある再婚相手への複雑な感情に内心戸惑う主人公。しかし、表情を崩すこと無く姿勢は正しく、所作にも子供っぽさがない。だらしないところを見せて母のせいにされるのを恐れているのか、甘えられる相手がいないのか。
そんな彼が父の愛を試すように、自らの頭を傷つけるシーンは観ていて辛い。本の中に母の筆跡を見つけて泣く姿、ヒミの焼いたパンを美味しそうに頬張る姿には目頭が熱くなった。
世間だけでなく自身の内面すらも理不尽で残酷な面がある。それでも、状況を受け入れて留まる事無く手足を動かして前に進む事で、状況が動き見えてくることがある。小賢しく生きようとせず、そうした泥臭い経験をもっと積めと言われている気がする。
『君たちはどう生きるか』というタイトルは、自分の人生に対する覚悟はあるのかという世間への問いであろう。今の世の中に対して抱えている怒りをエネルギーにしつつ、希望という自分のエゴを作品にする宮崎駿の創作に対する熱量に圧倒された作品だった。
アオサギ、特殊詐欺、フィッシングサギ
久しぶりの映画館鑑賞となりました。映画館は北陸初のIMAXシアターも増え、各スクリーンの扉も新しくなっていた・・・まるで別世界に迷い込んでしまった感覚に陥りましたが、映画そのものも別世界に。所々宮崎駿作品らしいというか、過去作へのセルフオマージュを散りばめられたような映像・演出部分(特に湯バーバ)にほっこり。ちいかわまで登場・・・笑笑
アオサギ、ペリカン、インコという鳥の世界。神隠しに遭った少女といい、生と死の狭間を彷徨う姿が生き方を問うかのような不可思議な感覚にさせてくれた。特に積み木なんてアイテムが考えさせられるのです。
ただ、ストーリーはキリコとヒミが現われた時点で読めてしまうのが残念なところでもあるし、グロテスクさも現実と不思議世界の対比で中途半端になってる気がしました。ドロドロの血とこぼれそうなジャムの色が似通っていたりして・・・
久しぶりの宮崎作品を観ただけで涙を流してしまいましたが、冒頭の火災シーンで輪島の朝市通りを思い出したり、キリコ(能登の祭りの切籠)やヒミ(氷見市)という名前が追い打ちをかけてきました。さらには落ちてきた塔とかで震災を思い出さずにはいられなかった。公開当時に観ていればそんな感情は湧かなかっただろうに・・・
戦争を扱った部分はあったけど、悲惨な被害は敢えて(?)描かず、少年眞人の複雑な感情中心だったと感じた。叔母さんからお母さんへと変化する夏子への想い。火災で死ぬことがわかっていても生きることの意味。もしかして大空襲や原爆被害についても予知していたかのような眞人の表情が気になるところ。なにしろ大伯父の顔がアインシュタインに似ていたし・・・
一生懸命に生きよう
時間が合わなくて見れていなかったのだけれど、アカデミー賞の影響で上映が続いていたので遅ればせながら鑑賞しました。
なるほど、この内容だと評価が分かれるのも納得です。
「誰でも、人生には現世を嫌悪したい時もあり、そういう時に逃げ場を求めたくなる時もある。でも結局は現世で一生懸命に生きていくしかないのだよ」ということ。それが、流されるままに鑑賞した私の感じたことです。でもこの映画から感じることに正解はないように思います。
おそらく、この映画は「絵画」や「ダンス」を見るように感じるままに見てくれと、そういうことを映画全体で表現しているのだと思います。そこには論理とか辻褄のようなものがありません。私は肯定的にとらえましたが否定的な受け取りをする方もいるはずです。ですから、評価も分かれて当然。表現者「宮崎駿」ここにありですね。
集大成?
やはり難しかった...けれど
表情豊かなファンタジーアニメーション映画
ほとんど前情報無しで見に行きました。同名小説は読んでないので関連性のほどはわかりません。
基本的には表情豊かなアニメーションを楽しむ映画だと思いました。正直、物語としての完全さよりも作者が書きたいシーン(アニメーション)を優先して詰め混んだような印象があるので、その辺りで評価が分かれてしまってるのかなと思います。
よくわからない話だったみたいな前評判も見かけましたが、個人的には登場人物の心情が分からないということは少なくともなく、素直に解釈できる物語だったと思います。
一つ一つのシーンやキャラクターをなにかのメタファーだと考え始めると一貫した解釈が得られずに困惑すると思うので、素朴にファンタジー冒険譚として見るのがちょうどよい映画だと思いました。
「君たちはどう生きるか」
宮崎駿ワールドの爆発!
戦時中とは言え
母を亡くして、その母の妹と直ぐに結婚する父親。その妹のお腹に赤ちゃんがいて、困惑する息子に、能天気そう(に見える)父親。そこに反発を感じつつ現実を受け入れる少年。戦時中とは言え、この設定は納得いかない。痛みとしか感じない。
映像は期待していたほど感動的では無かったと思う。人物と背景の質感の違う絵と、屋敷のお手伝いさんたちがなんであんなに大勢いるのかとか、主人公の少年や父親などにくらべて、大きくデフォルメされて千と千尋の湯婆婆の系統のおばあちゃまばかり…そこに何か意味があるのかと思ったけれど、最後までその意味はわからなかった。
そして、なぜ幻想の世界に生きるのが鳥たちだったのかも、よくわからなかった。鳥が平和の象徴だから?それくらいしか思い当たらない。アオサギは良いとしても、インコはあまりにマンガチックでアタマが悪そうで、本物の賢いインコに申し訳ないと思わせるキャラ設定。
大変申し訳ないけれど、アカデミー賞はもっと以前の作品で貰っておくべきだったと思ってしまいました。
ちなみに、お隣のおばさまは寝ていました…分からなくもない…
じいさんのマスターベーション、勘弁してください。
アカデミー賞受賞も納得の映画。但し,、、、。
アニメ作品は私の鑑賞対象にならない。大評判になっているのに、それを観ないのは映画好きな人間の沽券にかかわるので、見ることにしている。アカデミー賞長篇部門賞を獲得したので、観てみた。
自然描写の美しさに驚いた。アメリカのアニメーションは全くと言っていいほど見ていない。映画館の予告編で流れるディズニー系のCGで作られるアニメなど、私に言わせれば、阿呆らしくて見る気持ちにもならない。言葉は悪いが、お子様向けの映画である。
もちろん、アメリカにも大人の鑑賞に耐えるアニメーションの映像作家がいるに違いない。しかし、儲からないから映画配給会社も二の足を踏んでいるのだろう。資本主義社会に生きているので、諦めるしかない。
さて、この作品だ。その自然描写の美しさにうっとりとさせてくれる。細部にわたり宮崎監督の目が入っているに違いない。彼がいなくなったら、日本のアニメ界はどうなってしまうのだろうか。そんなことを私に想像させる。
だか、この作品の背景、世界観、宗教観は独特で一度見ただけでは理解できなかった。私には何回も観ないとわからない作品に感じる。誰かに教えてもらいたいぐらいだ。
映像は素晴らしいが、ちょっと残念な部分も
米アカデミー賞を切っ掛けに鑑賞しました。
前情報を見ていた分恐る恐る観ましたが、特に難しいと感じることはなかったです。至極単純でストレートな物語。ちゃんと台詞やストーリーを追っていれば分かるかと。冒頭の炎の映像が素晴らしく、少年の疾走感や焦り、慄く人の声が緊張感をもたらし、また緑豊かな自然や田舎の町並みが絵画のように美しくて、大きなスクリーンで見れてよかったと思った。芸術作品と海外の観客が言っていたのも頷ける。
物語は、深層心理の世界で少年眞人が次第に感情を見せるようになったり、言葉数が増えてきたりするのがよかったし、中盤の「母さん帰ろう」の辺りは、一緒に気持ちが高ぶってうるっとしてしまった。突然放たれる本音は痛くて辛いけれど、隠されたままじゃなくてよかったとも思った。青サギやワラワラもユーモアがあってジブリの可愛いキャラクターにクスッと笑える。
ただ、すごくすごく残念なのは、一部違和感……というかあまりにも演技が下手な声優さんがいて、そのキャラが出てきてからは途中途中意識が散って物語に集中できなくなってしまった。キャラの口と台詞が合っていないのを観るのは、何十年振りだろうか。いいんだ、あれで……と、ちょっと愕然としてしまった。
私は主に昔のジブリが好きで、さらにアニメ好きでもあり、声優好きでもあります。だから映像、ストーリー、そして声の三つがちゃんとそろって素晴らしい!と納得できないと、なかなかひとにお薦めすることができません。それだけが残念でした。
描写は賞賛、企画はやや不足
日本公開時には、内容がまったくわからずレビューは酷評ばかり。とゆう事で観るに及ばすでした。御多分に洩れず受賞理由を知りたくて観るはこびです。
よく出来てます。内容は好みで別れるところでしょう。宮崎駿監督作品で私の好みは、未来少年コナンや天空の城ラピュタです。なので今作はまあまあ中の上。まさに世界観の話。マトリックスとか。なぜ?を言い出したらキリがないので割愛。描写、表現は、いつも通り宮崎駿ここにありでした。わたしのようなSF好きからすると、プロットに新しさを感じない。展開にうねるようなダイナミックさが無い。などおもに企画、ストーリー的にやや不足でした。描写も慣れちゃったんでしょうね、宮崎駿テクニックに。つねに進化をつづけないと。
全1334件中、141~160件目を表示