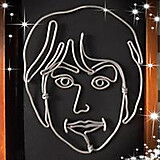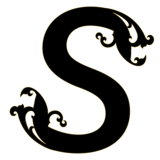君たちはどう生きるかのレビュー・感想・評価
全1336件中、461~480件目を表示
不快感なほど雑
自己満足の世界で万事が雑。地に足がついていない。絵もそんなに綺麗だろうか…自分には絵も雑な印象だ。世の中のアニメのレベルも上がっているから、見る側の目も肥えてきている。作り手として一切の妥協を許さず、試行錯誤して練りに練ったと言う情熱も伝わってこない。最初に決めた通りに、周りも口出しできずに計画通りに製作が進んだに違いない。大企業病に罹ってしまったような映画で、王者のおごりを感じた。周りが見えていない。残念だ。カリオストロの城を初めて見た時の、新鮮で痛快な衝撃を味わえる宮崎映画はもう期待出来ないのか。やはりアレはラッキーパンチで偶然の産物だったのか。
「もしも思いが叶うなら」
偉大なる巨匠ともなると、自分が作りたいもの、求めてるものがその都度かたくなにあると思いますが、
それが果たして見る者が求めてるもの、さらに心に深く残るものであるかは・・・わからん!
君たち・・・よりも、
ナウシカたちはどう生きるか
が、観たいです!!
生きねば。
面白い
60歳以上のカップルにお薦めします。
何と言っていいのか
駿おじいちゃんの昔語り全部盛り
このシーンどこかで...
鑑賞中何度思ったかしれません。
どのシーンもジブリ作品の焼き増しに見えてしまって、尚且つ戦時中の話なので暗い雰囲気。
このシーンはあの映画のあのシーンやなー、とぼんやり考えてたら話がどんどん進んでしまって物語に入り込めない。
勿論どのシーンも表現は素晴らしいんですよ。
しかし、やりたい放題あちこちで広げた風呂敷からポイッと放り出された観客達は、突然のエンドロールで呆気に取られて、米津玄師の声でハッと目が覚めるって感じ。
千と千尋やポニョ辺りから、ストーリーよりアート寄り、アニメーション表現の追求に重きを置いているような気がしていて、それはそれでいいんだろうと思っていたのですが、今作はそれの極めつけ版。
アニメーターさん、デザイナーさんが表現の参考にするって見方はありでしょうが、それでもワクワク感を感じるシーンが少ないのは残念。
過去の話を何度もするお年寄りと相対しているようでだんだん眠くなってしまった。
どこを切り取っても美くはある
しかし壮大な暗喩的昔語り。
答えは見た人の数だけあり
テレビで放映されるのを見たほうが良い
宮崎駿からの「訣別」の傑作
これまで数多くの白眉を通して、長年にわたって「人間の業の深さに嫌悪しながらも、共に生きること」を描いてきた宮崎駿がついに、世界の崩壊を示唆し、「もはや、共に生きることはできないけれど、それでも人間の生活は続くのだから、君たちはどう生きるか、ひとりひとりで考えなさい」と訣別を表現した傑作、と読み取りました。
物語としては、人間の業によって崩壊する世界を暗喩しながら、母を喪った悲しみを形象化していくことの苛烈さをミクロの視点で描きつつ、そうした苛烈さをも内包する命がつながっていくマクロ的な輪廻観を、どこか冷ややかに対置させています。
ナウシカやシータやアシタカが目指したように、世界とそこに生きる人たちが呼応して、共に生きたかった。けど、クシャナやムスカやジコ坊や堀越二郎のような抗いがたい業によって秩序だった世界はほどなく滅んでしまう。せめて、キキやサンや千尋やポニョのように、ひとりひとりがよく考えて、連綿とつながっていく「命の営み」だけはどうか絶やさずに。
そういった根底にあるストーリー(とわたしが勝手に読み取った)以外は宮崎駿の好き放題。普通の作家なら、コンテの段階で配給やプロデューサーに「わけわからん」をはじかれること請け合いだろう。メタファーや実験的表現、あるいは過去作品や古今東西の芸術に対するオマージュがてんこ盛りで、そもそも観客に何らかの解釈することすら許さない、ある種の難解さは、さながらピカソがキュビズムで世界に問いかけたかのよう(知らんけど)。
ちなみに、自身が創造してきた世界をだれかに引き継ぎたかったけど無理だったという、宮崎駿の諦念的な自己投影が、危ういバランスで石を支えている大叔父さんにほのかに込められていると解釈するのは深読みが過ぎるだろうか。
おいてけぼり〜〜
ある程度の覚悟はしていたけど、、
やっぱりよくわからんかった
世界観?ジブリ的ファンタジー?
ジブリ信者ではないが、まぁまぁジブリファンではあるのに、それでも入り込めなかったーー
謎が多すぎて
今までの作品でも不条理はあってもそれを気にせず乗り越えるテーマや魅力があったんだが、、
最初の火事から、絵の素晴らしさは惹きつけられた
ところどころジブリらしさというか、ハッとさせられる絵の美しさ、インパクトもあるんだけも、どうもお話しの中になかなか入れなかった
でも、宮崎駿の最後なのかな、と思うとどうしても映画館で観たかった
多分全てが伝わらなくてもいいと思ってるんだろうね
やりたいことを思う存分できる立場にいることはすごいね
落ち着いてまた観たら何かわかるのかな〜
宮崎駿の終活
様々なアニメの名作を生み出し続け、世界中にその名を轟かすアニメ作家「宮崎駿」。
彼が自らの老いと向き合い、死ぬまでにあと何作作り、残すことが出来るのか…そんな自分の限界と向き合いながら「これが最後」、「これが最後」と本気で自らの作家性と作品に向き合い続けたのがこの10年間ではなかったかと推察します。
近年の宮崎監督は、絵コンテを切りながら、仕上がった絵コンテを基に同時進行でアニメが制作される…そんなスタイルだったように思います。
以前であれば、ある程度の道筋を脳内に描きながら、立てたエンディングに向けてストーリーを無難にまとめ上げる余裕感があったのですが、近年の数作…ハウルやポニョ辺りからは、もう宮崎監督の(悪く言えば)行き当たりばったり的な展開が強く、最後は苦しみながら何とか無難な着地点を見出して結末を見せる…そんな印象を受ける作品が続いていたように感じます。
そして、今作はそんな宮崎監督が今までのアニメ監督として得た名声を後ろ盾に、好き勝手に、自分の想像力を解放して気持ちの赴くままに絵コンテを切り続け、自らもどんな着地点に達するか想像できない状況で自らを試すような形で作品を作り上げて行ったのではないかと、作品を見終わった後に、そんな印象を受けました。
私も個人としては、これまで散々エンターテイメントに徹した面白い作品をこの世に沢山生み出してくれた訳だから、自分の人生の最後を飾る作品くらい、彼の好きなように自由に作りたいものを作らせてあげたらいいじゃない!という気持ちが強かったので、作品の良し悪しがどうだとか、興収が過去作と比較してどうだとか、そういう次元でこの作品を語るのは、宮崎駿に対して失礼極まりないのでは?とさえ思うわけです。
目に飛び込んでくる目紛しい映像から、耳に流れ込んでくる音楽から伝わる感性をありのままに受け止め、その時々の自分の心の変容を楽しむ…そんな風に私はこの映画作品に対して向き合わせて頂きました。
色々な意見が交錯していることも承知していますが案外、この作品がアカデミー賞の長編アニメーション部門でも受賞したら皆、掌を返したようにこの作品を持ち上げだすんだろうな…とそんな状況を想像したりしてほくそ笑んでいます。
宮崎駿監督自身も、この作品については「良くわからない」と語っていたとの事なので、多分誰が見ても「良くわからない」作品なのだと思います。
それを自称評論家風情がしたり顔で、分かった風な語り口で色々な考察を繰り広げている様は、如何にも滑稽で愉快です。
今回、宣伝を一切行わなかったという鈴木プロデューサーの判断も、そうした宮崎駿というアニメ作家に対する敬意の現れ、リスペクトという視点で見れば、妙に納得できる訳です。
夢を見ているようでした
私の個人的な意見ですが、この物語は宮崎駿さんが子どもの頃に抱いていた理想や恐怖を大人になった今、再び思い出しながら物語として綴られたものなのだと感じました。だから、細部にまで深い意味の込められていた従来の作品とは違い、今回は明確な答えが見つからずにそのままストーリーが完成していき、宮崎駿さんご自身もおそらくはよくわかっていないシーンもあったのではないでしょうか。
そのため、多くみられる「意味がわからない」という意見にも納得できました。しかし、意味を求めるってそんなに重要なことなのでしょうか。
圧倒的な映像美、壮大な主人公の冒険、不気味で美しい宮崎駿の作る世界に浸り、大満足です。
私にとっては最も好きな映画作品です。
好みの分かれる作品
おもしろいけど好みが分かれるだろうという印象。
前半は主人公をとりまく現実世界の環境の変化が粛々と描かれ、かなり硬派な内容。
後半は翻ってファンタジーな世界の中で叔母を探すために冒険を繰り広げる。
好みが分かれそうな要素
1 前半がひたすら硬派。おそらく後半につなげるために必要な描写なのだろうが、「千と千尋」や「もののけ姫」のような世界観は一切なく、退屈に感じるかもしれない。
2 後半のファンタジー世界はいわば「なんでもあり」なため、理由の説明もなく不思議な出来事が立て続けに起こる。それ故に説明可能性を重んじる人は好きではなさそう。
個人的には前半は面白いと思わなかったが、後半は楽しめた。
面白かったとは思うけど人におすすめはしないかな?といった感じ。
すごい迷作
単純に目の保養
愛と命の物語
とてもおもしろい。
この世は生きるに値する
情報過多の時代に前情報ゼロの作品。
「観た?どうだった?」という会話を久しぶりにした気がします。
自分の目で観て、耳で聞かないといけないなと強く感じました。
結果、もう一度観たい!
皆さんの感想に共感!
キャラクターの感情のある動きや液体の動き。たくさんの生き物がうごめく様。…などなど。
これこれ!ジブリだー!と何だか昔の作品にスクリーンで再開できた懐かしく嬉しい気持ちが溢れました。
分かりそうで分からない物語だったけど、過去作のように多くを語らず、観た人に委ねるのはこちらが試されている気がする。
実際、過去作も年齢によって受け取るものが毎回違うから不思議。
この作品もきっと、年齢や経験、置かれた立場によって人それぞれ受け取るものが違うのでしょう。
なんだかひとつの時代が終わったのを観た気がします。
そしてエンドロールの豪華な名前やスタジオ名の数々は圧巻!
それを観ると「あとは任せてあるから!」と宮崎さんが言っているようで…。
新しい時代をみせられているようで…。
涙が止まりませんでした。
10年前の引退会見で言っていた、
「子どもたちに、"この世は生きるに値するんだ"と伝えることが自分たちの仕事の根幹」という言葉をこの作品で思い出しました。
いろいろな考察や感想をみるのも楽しい。
過去作のように何度も観なおしたいものと出会うことができ、制作関係者全ての方に感謝です!
作品を観た後だと、ポスターの題名と言葉が胸に刺さります。
今にも動き出しそうで…💦
見守ってる?見られてる?
賛否が分かれるのも理解できるが、宮崎監督が培ったあらゆるアニメ表現を詰め込んだ映像を劇場で観る意義は、十二分すぎるほどある一作
ほとんど事前の情報公開もしないという異例の広告戦略であるにも関わらず、『風立ちぬ』(2013)以来10年ぶりの宮崎駿監督の最新作ということで、公開直前から急激に注目を集めた本作。興行的には好調のようですが、実際鑑賞した人の意見は結構明確に賛否が分かれています。
確かに『風立ちぬ』との連続性を感じさせるような舞台設定の前半はわかりやすい物語性を帯びていたんだけど、中盤以降の、まさに宮崎アニメ的、としか言いようのない異世界との境界線がたち現れた途端、成長譚とファンタジーが入り混じった物語にモードチェンジします。
作品世界や物語の筋を理解するための様々な要素をごろっと提示するものの、それらの関連性や構造についての説明はかなり抑制的であるため、多くの観客が初見では意味がわからなくて混乱する、あるいは煙に巻かれたような気分になるのも、ある意味しかたないかも。
表題にはあまり引っ張られず、宮崎駿監督の最新作、ということを念頭に入れて鑑賞した方が、展開を受け入れられやすいかも知れません。
食べ物描写、水の表現など、宮崎監督のアニメ作品の独自表現がもはや名人芸の域に達していて、それをスクリーンでつぶさに観察できる、というだけでも劇場に足を運ぶ意義は十二分にあります。公開当初は発売してなかったパンフレットもようやく売店に並ぶようになったので、その意味でも今から鑑賞するのがおすすめ。
宮崎駿の哲学書
宮崎駿はアニメーション監督である。
哲学者は文章で語るが、監督はアニメーションで自分の哲学を語る。
そういう映画だと思う。
だから、新海誠監督の映画のようなエンタメを期待して観た人には総すかんなのだろう。
哲学を辞書で引くと「世界や人生の究極の根本原理を客観的、理性的に追求する学問」とある。
そのままではないか。
この作品を宮崎駿の自伝であり、自分の人生、作品を見つめ直したものだ、と評する人が多いが、ある意味その通りだとも言えるし、そうでは無いとも言える。
そもそも、監督は一旦引退したものの、描くべきものが見つかったとして、この映画を作った。
今まで、生と死、なんとか道を切り開いて生きていく事を主題に作品を作って来た監督の(最後に)描くべきものが自伝というのはどう考えてもおかしい。
自作品のオマージュまで次々と挿入するのもありえない。
では何故、見方によってはそのようにも見える映画を創ったのか。
想像ではあるが、戦後、死に物狂いで生き、血眼で働き(たまたま宮崎駿はアニメーション製作を仕事とした)、この生きづらい世の中をなんとか生きてきた自分の生き様をさらけ出そうと思ったのではないか。
一つのケーススタディとして、或いはメタファーとして。
後半の幻想世界の描写は混沌としていて、物語の秩序も欠いている。
ある意味見方次第でどうにでも取れるように作られている。
死の世界なのか、生まれる前の世界なのか、夢なのか現実なのか、その境界は無く、観るものがどのようにも解釈できるようになっている。
人間は大きな矛盾を抱え生きている。
宮崎監督自身も子供は外で遊ぶべきだというのが自論でありながら、映画館や家で観るアニメーション映画を作っている。
また、氏は戦車や戦闘機の機械や造形を好むが、これが人を殺す兵器だという事にも嗜好性の矛盾を感じていたことも有名な話だ。
(風立ちぬ、はその事も主題の一つにしている)
人間は生きているだけで環境破壊をしているし、生きるために戦争をして他者を殺す。
そうした矛盾を抱えながらも生きていかなければならない。
宮崎監督は戦後なんとか歯を食いしばり生きて来た自分をさらけ出しつつ、生きづらい現代に、むしろ絶望的ともいえる今、未来に、
大きな矛盾を抱えながらもなんとか生きていかなければならない、子供達や若者に、
家族や仲間と力を合わせて生き抜いていく責任を問うているのではないか。
米津玄師と宮崎監督が何度もセッションをし、完成させたという主題歌の題名は「地球」ではなく「地球儀」。
人間が作った地球のミニチュアだ。人間が自分でクルクル回せる地球だ。
この主題歌がこの映画の主題を端的に表していると思う。
「君たちはどう生きるか」というタイトルは自分をさらけ出した上で、「こう生きろ」と決めつけるのでは無く「自分で考えろ」、という宮崎駿からの挑戦状と受け取った。
2023.7.22 チネチッタ川崎
全1336件中、461~480件目を表示