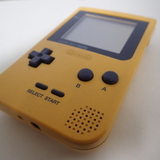君たちはどう生きるかのレビュー・感想・評価
全2100件中、1181~1200件目を表示
挑戦を諦めた3流ジブリ映画
あーこれ過去の○○ぽい。ジブリで見てしまうとは、、、作品がよくわからない。とかじゃなくて。
過去の○○ぽいを意図的にやってるじゃん。ジブリにもとめてるのは、そこじゃないのよ。知らない世界を観たいのよ。
それが終始○○ぽい。ぽいの劣化だらけ。この映画の象徴的絵が見終わった後に浮かんで来なかった。
話はシンプル。世界の均衡は継がれずに壊れた君たちはどうするのー。だけ、お家騒動とかドヤられても困る。
歳を重ねて自分の原風景をそのまま描いてしまうのは仕方ないとして、自分が作り出した作品にまんまのっちゃうは流石にアレ。
挑戦を諦めたこんなジブリは見たくなかった。
-- 追記
過去のジブリアニメを観るたび、私達は宮崎駿の原風景に憧れを強めていた。ので「原風景なんてこの程度」と描いてくれたのはありがたい。
過去に憧れた作品は、宮崎駿"そのもの"ではなく、宮崎駿という"職人"が綿密に作り上げた構造物だったと再認識できた。そして、職人芸に私達は感動をしていたんだなと。
出してしまったからこその終わり。残された私達はどうするん?とまるできかれてるよう。
ただ、出し方のアイディアが、自分の作品のオマージュってなんつうか流石に俗物すぎてやっぱ好きじゃない。日本に蔓延する後ろ向きをもろに受け止めすぎでしょ。。もっと希望を出してほしいわ
ソフト部分のチャレンジを期待していた…
7/14初日に都内で鑑賞、劇場の席は9割ほど埋まっていました。
今ネット上で様々な人達が書いている「意味分からない」「難しい」「エンタメではない」「本当に宮崎駿の作品?」「様々な考察」「言語化出来ないけどスゴイ」「これぞジブリ!」「圧巻のアニメーション!」「宮崎駿の原液」などなどどれもこの作品から人が受け得る感想・感情・印象の1つとして理解できる気がします。でも「クソ映画」「神映画」はどちらも当てはまらない気がします。この映画がクソならもはや表現方法が存在しないほど酷い映画はもっとあるしこの映画が神ならもはや表現方法が存在しないほど素晴らしい映画ももっとあります。
私がこの映画を観て感じたのは「またこれか…」です。
ゲームで言うならオープンワールドで明確なストーリー無し、自分で目的や解釈や楽しみ自体を見出し、その方法も結論もどれが正解・間違いなどなく、自分の中で味わい尽くせる形にできれば良いようなゲームです。私は映画でもこのタイプが大好きです。
でも…ジブリが宮崎駿がまさか今更この方向性で映画を一本作るとは思っていませんでした。。。ジブリなら宮崎駿ならアニメ映画界の次の新たなムーブを起こしてくれると期待してました。既存フォーマットの使い回しではなくまだ誰も経験したことない世界を体験させてくれると期待してました。10年ぶりの満を持しての新作ということもあって勝手にそのような期待を持ってしまっていました。ところが蓋を開けてみたらなんと既に出来上がっているセオリーに沿った小さめにまとまった思ったより優等生な作品でした。
もう古今の国内外の様々な監督の作品でこのジャンルがハマる人にはとことんハマるということは証明されている気がします。日本国内のアニメ映画なら庵野秀明がまさにこれを最大限活用してエヴァを巨大コンテンツまで育てましたし、押井守にとっては最も得意とする手法ではないでしょうか。しかしそれをあえて今、ジブリが宮崎駿がやることだったのか…。
なので「またこれか…」と感じてしまいました。
マーケティングに関しては新しいことへのチャレンジに感動しました。
宣伝無しの戦略です。世の中からの大きな期待がかかっている中、大きなプレッシャーの中、まだ世の中に多くの実績や正しいやり方が用意されていない手法に大きなリスクを抱え果敢にチャレンジしたことと、そしてこれを結果に結び付けたことに本当に感動しました。
この実績は今後の映画業界の形を変える可能性を秘めているとさえ感じます。今後この事例はビジネスの世界でも多くの方が参考にされ口にされることと思います。
マーケティング部分だけではなくコンテンツ・ソフトの部分でもこういった真の大きなチャレンジをしてほしかったものです…だって誰でもない宮崎駿ですよ?!それを期待していました。
最後に。もう多くの方が書かれていることではありますが念のためこの作品の特徴を書いてみます。
・単純明快な最大公約数の客が楽しめるタイプの作品ではない
・小さなお子さんには良くわからない可能性が高いかもしれない
・受動的な体験を期待している方にはちんぷんかんぷんな作品になるかもしれない
次回作も楽しみにしています!
**7/21追記**
書き忘れたので追記します。
私は絵と動きと色とカットと人・人以外を含めた生物の造形などに宮崎駿の魅力をあまり感じませんでした。宮崎駿のユニークなものではなくやはりこれも今世の中に溢れているアニメの一般的なフォーマットに近いものを感じました。
今作ではこれまでの宮崎駿作品と違い宮崎駿は絵コンテに集中し作画は作画監督に委ねたといった書き込みをネットで見かけました。この情報の真偽は分かりませんが適切な情報であるならそれに起因したものかもしれないと思っています。これまではアニメ制作の多くのパートに宮崎駿が監督として介入していたが今回はこの範囲を狭めたのかもしれないと、これは完全に私の妄想ではありますが、感じました。
とは言えアニメーションのクオリティは平均を大きく超えていると感じます。どんな観点であれこのアニメーション部分に何かしらの文句を付けるのは贅沢過ぎる素晴らしい品質であることは付け加えておきたいです。
宮崎駿監督、最高です。
サギとインコの神隠し(中略)
【タイトル】君たちはどう生きるか
【脳内変換】シン 火垂るの坂の となりの崖の上の城の 思い出の姫と サギとインコの神隠し を追うこども
帰りのエレベーターで若い女の子たちが「良かったね〜♪♪♪」と言っているのを聞いて、少なくともこんな陰湿なレビューを書く人間はお呼びでない作品なんだな、と実感した次第です。
というわけで、以下本作がお好きな方には大変不快なレビューとなります事をお断りしておきます🙇♂️
鑑賞後の第一印象は「疲れた…」の一言です。
元々上映時間が長い作品ですが、苦痛に感じるほど長かった…
スタジオジブリ作品らしく、素晴らしいアニメーションと美味しそうな食事シーン、幻想的な風景描写と、ファンなら各シーンで既視感を覚える画が随所に登場し、思わずにやけてしまいます。
ただ、ストーリーまでその辺ごちゃまぜした上に新しい展開を足そうとしたのか、過去作+他監督某作をまぜて煮込んだ上澄みでなく底の方をすくった作品、という印象を持ちました。
上澄みの方+αなら今までにない新しい味だったのかもしれませんが、煮込んだ鍋の底にある◯◯ガラとか香辛料の葉やら実やらを皿に盛り付けたようで、「知ってる味はするし、高そうな材料使ってるけど、この料理何…?」という感じです。
悪い意味で先の見えない展開、わからない人はついてこないでいいと言わんばかりの描写、でもジブリの作画はすごいでしょ?と。
ただ、その辺を気にしなければジブリらしさ満載のジブリファン待望、吾郎監督じゃない駿監督作品のファンタジーです。(ただし作画のみ)
大衆に迎合するようなエンターテイメント作品ではく、宮「﨑」駿 監督のやりたい事を詰め込んだ芸術作品なのでしょう。
ナウシカ、ラピュタの頃の感動をまた味わいたい一心でずっとジブリ作品を追っていましたが、いい加減卒業します。
今まで本当にありがとうございました🥲
ミヤさんアンタすごいよ
初回視聴は新宿に出来た109シネマズプレミアムで観ましたが、隣の大学生ぐらいの子がポップコーンをガリガリ口を開けながら食いやがったから、話が入ってこず最低な映画だと思いました。初心に戻り、日比谷TOHOスクリーン1にて2回目観賞したところ号泣。ポップコーン大学生に「君はどう生きるか」と問いたい。おじさんになった私は、ただ後世に光り輝く若者に次を託したい。星4にしたのは、死ぬまで作品を作って欲しいので満点は付けたくないです。
日本人アニメクリエイターに向けた遺言
通常版とDolby Cinemaの計2回観賞してきました。この作品は日本経済の現状とスタジオジブリの現状をアニメに落とし込んだ内容に感じました。2回観賞して思ったのが、眞人とアオサギの関係が興味深かった。アオサギは鈴木プロデューサーと想定して観ると、眞人と共に行動しているときは過去のジブリで描かれたシーンのオマージュが頻繁に描かれていて答え合わせの気分で最初は楽しめましたが、だんだん退屈に感じられて集中しづらかった。
この既視感を踏まえてポスターのアオサギは、宮崎監督の「創造の領域」に案内するナビゲーター=鈴木敏夫と解釈して本作を観賞すると、不思議な塔の中と外はスタジオジブリのアニメーションの技術がハッキリわかりました。塔の中は過去作の描写がふんだんに使われているのに対し、外の世界は今までにない描写が描かれていました。
空襲に怯える人々は陽炎のようにモヤモヤしていて「恐怖・不安」の心情をわかりやすく伝えていた。個人的にびっくりしたのが「大人の」キスシーンを音だけで表現していて、一歩踏み込んだ演出に関心しました。外の世界は「今現在のジブリ」、塔の中は「今までのジブリ」という考察に至りました。
終盤の積み木のシーンは「日本の経済に組み込まれたスタジオジブリ」という印象でした。いびつに積み上げられた積み木は負債まみれの日本そのもので、現状維持のためにアニメを利用されていることに嫌悪感を抱いているように見えました。
宮崎監督の創造の根源は戦争経験かと思えるあの「どす黒い雲」のような抽象的に描いているシーンがありますが、これは現実で経験したからこそ、13の善の積み木を具現化できたことがモノづくりに対して真摯に取り組めた結果であって、決して金儲けのためにアニメを作っていたわけではないと伝わりました。
不思議の国の真人
この作品をどう見るのか?
戦争時代という冒頭の始まりから、その時代背景とその時代に失ってしまった母親。
なんだか、色んな要素がふんだんに詰め込まれるているパラレルワールド感に頭の中が混乱していた。
主人公の眞人が義母に心開けずにいる中で、その義母が行く不明になってしまう。
その義母を探す為に冒険に出る事になる。
背景などがどこかトトロやラピュタ、ハウルなどを思わせるようなシーンが組み込まれるているなと、思った。
ストーリーとしては、とても難解であります。
この作品は、原作を読んで、それを基にしているという感じよりもその作品からインスパイアされた作品だと思った。
他の人のレビューを参考に考察すると、異世界の世界は、(宮崎駿)の過去の栄光の中の世界である。
ただ、その世界が今にも無くなるのを前にして、残された人達は、どう出来るのか?
その問いかけは、少し傲慢さを伺えるのかもしれない。
自分と同じ事が、それ以上のものが作れるのか?
そんな風に聞こえてしまう。
それは、自分がいなくなってしまうという寂しさからくるものかもしれないです。
そんな要素を踏まえながらもこの作品を自分にとってどう観るのか?
それがこの作品をさらに楽しむ為の課題かもしれない。
全体的に難しい。
けども、最後の何気なく終わるシーンは、好きでした。
巨人なき後、僕たちはどう生きるか
一時代を築いた人がいなくなった後、その意志を継ぐ者たちはどう生きていけば良いのだろうか?
どう生きるか?という内容ではなく、
さあここからどう生きますか?
と問われて終わった内容だった気がする。
ちゃんと一例を示してくれないあたり、やはりという感じ。
真人は君であり、私であるなと。
メッセージを受け取った。
No. 1261
賛否両論あるかもしれないけど、想像力と映像力は文句なし
まったくの事前知識も何もないまま観ました。
リアル寄りなのかファンタジー寄りなのかも分からないまま観るなんて久しぶりで、とても新鮮でした。
物語としてはふわっとした筋はあるものの、時代背景やその他もろもろの要素についての必然性にはあまり説得力がなく、まとまりに欠けているように感じられた。
少年の内面の葛藤とファンタジー要素との絡み合いで、あやふや度が増しているからこそ、人によっては混乱し、消化不良に陥るかもしれない。
でも、私は82歳という老齢の宮﨑駿氏が未だにこれほど自由な想像力を持ち、広さを感じさせる映像美を作り出せることにただただ驚嘆しながら観ていた。
お行儀の良い、まとまった作品ではなく、どこか少年のような粗削りさが目立つ作品だと思うのだが、自分の中の空想の扉が開いていく感覚はとても心地よい。
私は観て良かったです。
ただ、エンディング曲に米津玄師を採用したことにはガッカリ感がある。ちょっと食傷気味である。歌ではなく音楽だけで良かったし、歌にするならばもう少し透明感のある新鮮な歌い手による歌が良かった。
「悪意」と「悪意のない13の石」 追記:タイトルについて
一回目は絵力に圧倒され時を超えた親子の物語に涙しつつもさまざまに疑問もあったので二回目の鑑賞に臨みました。
一回目で一番飲み込みづらかったのが悪意云々の件です。
積み木を差し出されマヒトが「これは木ではなく墓と同じ石で悪意がある」といい、大叔父が長い年月をかけて用意した「悪意のない13の石」を差し出し、マヒトはこめかみの傷を見
せながら「これは自分の悪意の証でその石には触れられない」といったことを言います。
「悪意のない13の石」については宮崎駿の劇場公開作品の数と同一であることは指摘されています。では悪意とは何か。
あちらの世界というのは「上」とは違い、「石」と大叔父の契約によって「創られた」世界です。
積み木として使われる石は無数に存在する中で「悪意のない石」が宮崎駿の作品群であれば、映画やあるいは創作物、「創られた」ものが石ということになるかと思います。
マヒトの「悪意」とは、行為としてはこめかみに自ら傷をつけたことで、「命を弄ぶ」ことと言えます。
他の作品によく見られるような「命を弄ぶ」作品は作らなかったという宮崎駿の自負です。
「悪意のない13の石」でより良い世界を作ってとマヒトに伝えながらも、マヒトには断られ、インコ大王が無茶苦茶にして、世界は崩壊します。
大叔父が宮崎駿であるならば、「命を弄ばなかった」という自負がありながらも、それによって若い人たちに良い影響が与えられるなどということはない、自分の作品が世界を変えるなどということはなかった、そしてそれでいい、というのが宮崎駿のたどり着いた境地なのではないでしょうか。
もう一つあちらの世界について、夏子さんの「あんたなんか大っ嫌い!」というセリフがあって、あちらの世界(宮崎駿の作品)には嘘がないのではないかという点も気になって、青鷺のセリフを確認しましたが、少なくてもあちらの世界に行ってからの彼のセリフには嘘はありませんでした。
命を弄ばず嘘をつかなかったと自分の作品を評価しつつも、最後には自分で突き放し崩壊させ「それでいい」と言えるのは、かっこいいジジイだなと思いました。
追記:「君たちはどう生きるか」について
吉野源三郎著のものは未読ですが、児童書ということでおそらくは子供達に向けて道徳的な教えのある内容だろうと推察します。映画の中では亡くなった母が「大きくなったマヒトさん(君だっけ?)に」と書き添えた本をマヒトが見つけ、これを読みふけ涙する、というように扱われています。この涙の場面から、夏子さん失踪騒動の場面に直結しますが、実はこの時点でマヒトの成長譚としては区切りがついているのではないかと思っています。
この場面以降マヒトは苦労することはあるものの、悩み葛藤することがありません。夏子さんを連れ帰らなくてはいけないという芯がブレることが、全くないのです。つわりで苦しんでいる夏子さんにあんなにそっけない態度をとっていたはずなのに。つまり母親の思いのこもった本を読んでマヒトは変わったのです。
おそらくは夏子さんのような人を悲しませるのは良くないことだいう風に変わったのではないかと思います。だから自分のことを「大っ嫌い」とまでいう夏子さんに精一杯に「お母さん!」と叫ぶことができた、「僕は変わったよ!」と。
だから冒険を通して成長する物語ではなく、成長した少年の冒険、というふうに自分には見えました。
宮崎駿が吉野源三郎著「君たちはどう生きるか」をどう思っているのかは分かりませんが、少なくても映画内ではマヒトを成長させるものとして扱っています。いわゆる良書であり、「悪意のない石」と同義のものではないでしょうか。
映画の「君たちはどう生きるか」というタイトルは、挑戦的な意味合いではなく、宮崎駿自身が作り続け、今後もあらゆるところで生まれ続けるであろう「悪意のない石」に触れて、若い人たちはどんな大人になっていくんだろう、どんな世界になっていくんだろうと、老人が思いを馳せているような意味合いに自分は感じました。
世界を崩壊させたくだりと矛盾しているような気がしますが、創作物の可能性を信じながらも無価値さも感じているという、相反する思いが混在しているのがこの映画、というのが現段階での感想です。
様々な動画経ての感想
様々な動画を見るに、この映画は、宮﨑駿が生まれて初めて「この映画を見る子供」を意識せずに作ることができた映画なのではないかとおもいます。誰よりも褒められたかった老人である宮崎駿が、宮崎駿以上に誰よりも褒められたかった老人が、先に死んだからこそ生まれた奇跡の作品です。もう彼より褒められる必要はないのです。彼は死に宮崎駿は生きているからです。
多分に作り手の思惑に寄り添ってこそ楽しめる作品ではあります。かといって普遍性もちゃんとありますし、若く、日本で最も優秀なアニメーターとのコラボ作品でもあります。そのノイズもふくめ、「アニメーションとは」を何も知らない自分でさえワクワクさせるものがあります。
面白くはない!何回か観てやっとわかるジブリ映画!
風たちぬから10年ぶりの宮崎駿監督のジブリ映画期待して観に行ったんですが、
中盤ぐらいからかな、
う〜ん、
なんかよくわからなくなってきた〜
あ!ダメだな〜ってなってきた😅笑
公開前から、
ネタバレ注意とか言ってたわりには、なんだこれ??みたいな感じ😅笑
正直、もののけ、千と千尋などに比べたら、天と地の差ほどぐらい面白くない😥
多分、何回か家でゆっくり観て、やっと宮崎駿監督が何を言いたかったのかわかる映画になってるんだと思う😅笑
子供には難しいから、レンタルで十分かな🙆笑
これを面白いと評価してる人はかなりヤバい人間🤭笑
むずいって
これは鈴木さん宣伝しようがないわw
宣伝しない!って鈴木さん言ってたけど、宣伝しようがなかったんだねw
これにどんなコピー付けるか?って言ったらタイトルがコピーそのものだしねw
あらすじ書いても訳わかんないだけだし
ジブリ映画としてのタイトルだったら絶対「の」を入れる事にこだわったはずで、その点でも匙を投げたんだろうな
この映画って万人に向けたメッセージなんかでは無くて、ジブリに関わってる、関わってた人へ向けたメッセージなんだろうなと思った
だからある意味内輪ネタしか無いので一般人には意味不明になる
ネタバレはするつもりは無いけど、雰囲気としては後期ジブリ作品のそれを引きずっていて、アリエッティ、マーニー、ぽいのを駿がやったら…的な感じ(^◇^;)
お話が分からん…って言われてるけど、多分これはそれほど重要じゃ無くて、登場させたい人物や物が決まっていて、それを出すための装置に過ぎないんだろうな…と思った
ハウルやポニョあたりからか、やたら年寄りが出るようになったが、今作もまた同じだった
美しいものを描こうというのを拒否して、敢えて醜いものを出し始めた
ミュゼットみたいな七人のババアは正直なところ気持ち悪かったし…
あと群体シーンもしょっちゅう出てきて、苦手な人は苦手だと思う
ポニョの魚はオオ!スゲェ!と思ったのにな
コダマの風船版みたいなのはもうキャラ戦略上のものとしか見れんかった…
涙のシーンはようやく千と千尋から変えて来たのはさすが駿と思ったが、、それほどでも無かった…
アオサギはまあ見るからに鈴木さんなんだろうけど、、カオナシとカルシファーとジコ坊と…みたいな役回りをミックスしたようなので、、これも心地悪かった(まあ実際鈴木さんはそのような人なんだろうけどw)
大体くちばしの中に歯がある表現が気持ち悪くて、あとブヨブヨした部分とか、後年の作品はやはり醜いものを出したがるのがイヤ
音楽は、四度重ねの久石節は薄められてた(ミニマルぽいのは少しあったけど、北野武映画の何か、、あれももういいわて思ったし)
ピアノ主体の演出はゼルダブレワイぽくてwちょっと逃げたかな…とも思った
アオサギのとか
でもそう言うのは酷かもしれない
この作品に曲作れってなったら頭抱えるだろうし
ご老体に鞭打ってよく駿に付き合われたと言うべきなんだろう
さてさて、、
さあ、次は少女が主人公の冒険ファンタジーものを皆待っておりますw
いつまでもいくらでも待っております!
駿さま、どうかお元気で作り続けて下さい!
追記)
2回目観に行ったので追記
今回出てくる女性キャラって、全て駿のお母さんのそれぞれの年代の姿だなと思った
ポニョの時もそうだったけど、今回それを全開にしたんだな、と思った
ポニョの時にトキさんに飛び込むシーンを、駿はボロボロ泣きながら描いてた
ホントは一番抱きつきたい人に、それをためらって、そしてようやく胸に飛び込んだ…風に見えた
でも今回はいろんな人に抱きつくシーンが描かれてて、ポニョの時にあった躊躇みたいなのが無くなった感じがした
母に対する思いが解放されたのかなぁ、、と思った
うーん
もうちょっと、こう‥
なんていうか
10年もの時を経たんだし
感動したかったというか、
やってくれたな、パヤオ。
期待したものが
これ??
ジブリ作品を長きにわたり
観てきた作品たちの中で
こんだけ意味のわからんものが
あっただろうか。
過去の作品で
裏設定を画だけで見せるとか
不親切なものはあったけど
ネットで検索すれば
親切な人が説明してくれてるサイトがあったりします。
誰か
助けて ヽ(´o`;
声を演じた役者はとても豪華で
エンドロールで見て
えっ
という人ばかりです。
なんだかそれすらもったいなくて。
さすが宮崎監督!
これぞジブリ!!
館で観たほうがいいよ!!!
と言いたかったです。
⭐️が1つか5つか
評価が分かれるのが
後に語られる作品になるというのは
よくあるかもしれませんが
どうしても5つには振り切れません。
僕は原作の本とか読まない派です。
原作は同じタイトルだけど
内容は違うらしいです。
ということは宮崎監督の
イマジネーションが全てですよね。
作画的には
ジブリぽさが随所に見られたんですが
いかんせんストーリーが。
一回見ただけじゃわからなさすぎて
しかし2回見ても理解する自信もない。
ただシンプルに
セリフで聞いたことだけ理解しときゃいいのかな。
だったらタイトルが全てということに落ち着くかもしれません。
映画を観る時は
出来るだけ予告は見ないほうがいいです。
良い場面を見せすぎて
本編を観ているときに
あ、CMで見たシーンだ〜
と要らないことを感じてしまうからです。
この作品は予告を一切見せてなかったので
その宣伝方法は賛成だったのですが
もっともっと内容を深く
理解させて欲しかったなと思います。
もちろん感じ方は人それぞれなので
これで十分伝わったという人はいるでしょうけど
僕は初見で納得できるものではなかったです。
悲しさと寂しさ ジブリの集大成 そして終焉
途中から、あ、これは宮﨑駿の自叙伝的な感じ?と思って観ていました。
最後らへんの13個の石のくだりでやっと確信。
スタジオジブリと宮﨑駿の終焉を感じ涙。
スタジオジブリと宮﨑駿は新しい物はもう創らないんだなと受け取りました。
(てか、宮﨑駿監督って言っても他の方に自由にやらせていた感がありました。駿感があんまりなかった。でもアオサギのキモいシルエットは駿(絶対にそう)。)
とてもシンプルなエンドロールにクレジットされた方々をみてさらに涙が溢れました。
(なんか、爺さんの生前葬を関係者で執り行ったみたいな。さしずめ、我々、観客は参列者か、、、。)
米津玄師の曲はさらっとしていて耳に残らない、が、またそれが何も残さない感じで泣ける。
宮﨑駿ありがとう、そして、さようなら。
てか、なんで宮崎から宮﨑に変えたの?
今までのジブリ作品に、影響を受けた王と鳥を混ぜ混ぜ、死ぬ間際の走馬灯のよう(語彙)
話の内容や登場人物に、多くのメタファーがあると感じました。
小2の子供と夏休みにもう一回観る。
過去のジブリ作品をしらない純粋な子供の感想を聞いてみたい。
全2100件中、1181~1200件目を表示