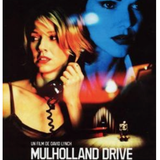君たちはどう生きるかのレビュー・感想・評価
全2100件中、901~920件目を表示
なんこれ?
「風立ちぬ」以来10年ぶりの宮崎駿監督最新作。正直「風立ちぬ」自体がだいぶ私に合わなかったため今回もあまり期待はしていなかったが、逆の意味で想像を超えてきた。まじで意味が分からない。
映画冒頭は作画がすごく、宮崎駿気合入ってんなーと少し期待したが、そこからは退屈な日常パートが体感1時間弱続く。意外と普通で拍子抜けだなと思っていたら後半からは怒涛のワニワニパニック。伏線をばらまきつつ整合性の取れないストーリーを展開し、最終的にほとんどの伏線を回収することなくおわり。
ぽけーっとした状態のままシアターを出てしばらくして我に返り、すぐにネットで解説を漁った。あれは宮崎駿の人生で、墓の主は宮崎駿自身で「我を学ぶものは死す」みたいなやつの意味は私を真似てアニメを作るのは失敗するぞって意味だ。13個の積み木は今まで彼が作ってきた作品で誰かに引き継いでほしいけどいない。ジブリ(石の世界?)はここで終わりって意味だ。みたいな解説を見て、なるほどあれは宮崎駿の内面を描いた映画なのか、と自分の中で何となく理解は出来た。でもそんなの映画にして観客に見せちゃいかんでしょ。そういう「このシーンにはストーリーにおける意味とは別にこういう別の意味があって~」みたいなのは元のストーリーがちゃんと成り立っているからこそ成立するのであって、元のストーリーぐちゃぐちゃにして自分の内面を映像にしてペタペタつなぎ合わせていったのを映画と呼んでいいの?なんかこの映画はアートだから感じるんだ!みたいな意見もあるけど、アートなら映画館じゃなくて美術館でやってもらわなきゃ。
映画はジャンルはなんであれその究極の目的は人を楽しませること、つまりエンタメにあるはずだ。私はそう思う。今回の映画を作るにあたって監督はそのことを少しでも考えて作ったのだろうか。なんとなく今回の映画の意味が分かったうえでも、これは監督の自己満足のために作られた映画としか思えない。肯定的な意見を述べている人も、この映画をジブリや宮崎駿監督と切り離して、単純に一つの映画として見せても(絵的に即バレだろうけど)同じ感想を抱くのだろうか。とても気になる。どんなにその映画に含意されている内容、メッセージが素晴らしいと言っても、映画自体が面白くなかったらそれは駄作だろう。少なくとも本作は映画館で大勢の人に見てもらう映画ではない。
期待していなかったと言いつつも、やはりジブリには大好きで思い入れのある作品も多い分、やはり心の底では楽しみにしている気持ちもが自分の中では強く、久しぶりにジブリ映画を映画館で見れた満足感はあった。それだけに私的には本作の出来は非常に残念だった。
良い映画。
宮崎駿というビッグネームにつられて見に行ったが、見に行ったことを後悔させないような良い映画だった。事前情報が全くなかったため、より一層新鮮な気持ちで鑑賞できた。
疎開先で虐められた眞人がキリコやヒミ、大叔父の生き様を肌で感じ、どう生きていくのか。どうしてヒミは火の力を使えるのか、アオサギの正体は何なのか、一体扉の先の世界はなんだったのか。背景が描写されていないものや細かく説明がなされないものが多かった。悪く言ってしまえば不親切で理解しにくく、どういうメッセージがあるのかが伝わりにくい映画だ。
確かに受け手に伝わりやすい映画というのはストーリーがよく分かるし登場人物に感情移入しやすい。こういった親切な映画は不親切な映画と比べ面白いと言われる。これは自然なことであり、今回の映画が面白くない、分からないと言われるのも頷ける。ただ、考える余地を残している映画だからこそ多種多様な解釈の仕方があり、映画にこめられたメッセージの受け取り方も違う。「君たちはどう生きるか」というタイトルにもあるように、どう感じるか、どう考えるかは今を生きる私たちが考えるべきことである。「眞人はこう生きていくのだろう、キリコはこう生きてきた。じゃあ私はどう生きたいのか。」
人生の生きる意味を考えさせる素晴らしい映画だと感じた。
ちゃんとジブリ世界が堪能できました
前情報無しで、しかもレビュー評価も真っ二つだったのである程度の覚悟を決めて鑑賞。
序盤はどうなることかと思いましたが、進んでいくうちにちゃんとジブリの世界へ。確かに、監督が作品に込めた思いとかメッセージとか色々読解しようとすると難解な映画って評価になっちゃうのかもしれませんが…単純にジブリ新作として観ればしっかりジブリですよ。色々読解しようとしたら、それこそラピュタやナウシカ、ハウルなんかも難解になっちゃうんじゃないかと思ってしまうし、普通に映画観るってスタンスで挑めばちゃんと楽しめる、ちゃんとジブリの良作、そんな感じだと思います。
後半どんどん引き込まれて、ポップコーン食べる手が止まる位にのめり込めました。星5評価で問題無いかなぁと思います。
文七元結や紺屋高尾と一緒で…
タイトルに縛られちゃうと、なんだこりゃ?になる。タイトルはたまたまあの時代に流行った本から借りただけ(ぶっちゃけ「われら少国民」でも構わん)
内容は、あるジブリ作品(ネタばれになるから書かない^^)をバックボーンにして、そそこにジブリ作品のあちこちから部品としてはめた宮崎カラー全開の映画だなと思った。MCU総出演のジブリ版かな?予告も流さず、パンフレットも作らず、うまくやったなと。世間は賛否両論だが、自分はプラス評価。これはあれから、あれはそれから、と元ネタを探しながら見るのも一興か。
どう生きれば良いのでしょ♪ 答えは見つかりませんでした♪ 男の子版...
どう生きれば良いのでしょ♪ 答えは見つかりませんでした♪
男の子版の「千と千尋の神隠し」かなぁ・
ギレルモ・デル・トロ、ティム・バートン、ドゥニ・ビルヌーブあたりが好みそうなテーマに挑戦してみたのかしらん。「風立ちぬ」あたりから、ジブリの独特の筆のタッチというか、キャラクターというか、敷衍してしまっているイメージでは表現しにくい題材に敢えてチャレンジしてるのかしらん宮崎駿氏。
わからないでもないけど、ぶっ飛びすぎてて・・。ストーリーの全体像も無理やりぽいし・・あんま共感できなかった・・。
ピクサーが、あのタッチで深刻なスパイ物、戦争物、ホラー、ぶっ飛んだSFを創ったらちょっとねぇな感じになると思うけど・・ジブリは敢えて難しいモチーフにチャレンジしたかな・・。
特に、ジブこリの熱烈なファンでもないので・・・前宣伝をしなかった事は幸いだったかもね。
鳥の扱いもちょっとで?なんで鳥なのも謎・・・。
たまに近所の川でアオサギを見かける事がありますが・・今度、撮ってアップしてみよっと♪
宮崎さんは、古の日本の、上流階級というか中産階級の生活様式というか佇まいに憧れでもあるのでしょうか?好きですよね・・。お手伝いさんがいて、ちょっとモダンなファッションの女性・・そんな女性が住んでる洋館。
宮崎駿さん、これで最後にしようと思ってるのだろうなぁと感じたのが・・幽霊船の群れが「紅の豚」で天に登る飛行機の、異世界へのトンネルや草原は「千と千尋の神隠しの」、あのポニョポニョした丸いのも「もののけ姫」の木霊・・、虫も「ナウシカ」のオウム・・などなど、ご自分の創り出した世界のオマージュが散りばめられている点。
こだわりと言えば、ベッドにゴロンっとなったときの布団のハネかたやら、ズック(運動靴)を履く時のゴムの部分の内側のめくれかたとか、すんごく細かいところの表現が、相変わらず宮崎駿監督でした。他にも、そういう細かいこだわりに溢れているのでしょうね・・。
そうそう、婚約者で懐妊している彼女に、重いぞって言って荷物持たせないよね・・普通・。
ツギハギだらけの駄作
自分の中の答えを出す為にもう一度観たい
衝撃的だった台詞が、うろ覚えなんだけど火事に遭ってしまったお母さんの別世界キャラの台詞。お前と会えたから火も悪くないよ、みたいな。
ギュッと抱きついた無邪気なあの姿は私の見間違いなのか…帰り道で泣きそうになって堪えたけど、私達はこんな残酷な世界でも結局人を愛して生きている。その救いをもう一度確かめに行きたい。
宮崎駿はこう生きた。からの〜、君たちはどう生きるのか?
表面だけ追ってると、単に叔母さんを助けに行って帰ってくるファンタジー物語。
その奥は、母を失った少年が、叔母を母として受け入れるまでの成長物語。
その裏には、自分の中にある悪意を認め、人間とは純粋ばかりではなく悪があってこそ人間たりうるという人生哲学。
しかしてその実態は、散りばめられた過去作のオマージュを丁寧に追っていくことで、この映画は宮崎駿の人生のオマージュであり創作に対する宮崎駿の意見表明だとわかる。
その上で、自分の次の世代に、どう生き、どう創作をしていくのかを問うているのが本作なのだと、私は理解した。
このように、なかなか良く考えられた構造の映画ではあるが、いかんせん、オマージュを多用して自分の人生を語り、メッセージを伝えるという多層構造は、数年前に弟子の庵野秀明がシン・エヴァンゲリオンでやった手法なわけで。そういう意味で映画の構造に新鮮味は感じられなかった。(まあ、知っていたから理解できたと言う面もあるが)
そもそも、伝えられる宮崎駿の創作論とか人生観に、イマイチ興味が湧かなかったという・・・。
そして何より、表面のストーリーがイマイチ面白くない! ボケーっと見てたら、多分つまらない退屈な映画、星1という評価だったろう。
そんなわけで星3ぐらいにしておきます。
宮崎駿の新作映画を観られる幸運を
いいと思う
ポニョの別バージョン?
日本では、魂は海からやってきて生まれ、死ぬと鳥となって飛び立ちます。
だから、ポニョが半魚人化したとき、鳥の脚を持つことに妙に納得したのです。
今回も、死後の世界、あるいは生まれてくる前の世界が描かれていますが、そこにはたくさんの鳥がいます。
彼らは死んだばかりの魂?
インコたちは、太平洋戦争で命を落とした兵士の魂でしょうか。
生まれ出る命、「わらわら」は、魚の内臓を食べて飛翔します。
わらわらを食べて、この世に生まれることを邪魔するペリカンたちは、なんのメタファなのか。
ポニョでは、宗介が「以前通ったことのあるトンネル」を抜け、「あの世」と思わしき世界へ到着しました。
今作では「通路」が登場しています。
大叔父が司っていた、今にも崩れそうな「世界」が太平洋戦争に敗北する日本なのだとしたら、大叔父とはいったい何者なのでしょう。
命の循環を、宮崎駿監督は、なんとして語り掛けているのか、一度ではわかりませんでした。
物語のもう一つのテーマは、「母を喪失した少年が、新たな母を得て母子になっていく物語」ではなかろうかと思います。
当時、妻が亡くなると、その妹を妻にすることは珍しくなかったのでしょうが、ナツコには姉への遠慮があり、眞人にも複雑な感情があったはずです。
亡き母とそっくりなナツコへの思慕もあるでしょうし、それでも母とは違うというためらいもあったのではないかと思います。
その葛藤が、「ナツコさんを探しに行く」ことでほどけていく過程が描かれているのかと。
なんにせよ、何度か見返さなくては、いろいろ見逃してることがありそうです。
子供たちは、トイレに立つことはあったが、席を後にすることはなかった。
映画館の私の周りには母親に連れられた子供たちが、たくさん座っていた。夏休みに入ったためだろうし、席が出口に近かったことも関係していたのだろう。
映画の内容は、導入部と展開部の二つに分かれていた。導入部は戦争中の現実の世界。展開部は、宮崎駿の空想の世界。導入部は、映画「風立ちぬ」の続編かと思わせた。風立ちぬの時は、半藤一利さんとの対談をまとめた「半藤一利と宮崎駿の腰ぬけ愛国談義」が出たことを思い出す。さぞかし、宮崎さんは半藤さんに、この映画を見せたかっただろう。少し間に合わなかった。宮崎さんが唯一、当時の戦闘機で描けると言っていた「風防」がたくさん出てくる。お父様の思い出。
後半の展開部は、宮崎さんの頭の中の世界。これまでのジブリにでてきた映像が連続する。前半と後半をつないでいるのが、疎開先の敷地のはずれの母方の大叔父が関連する塔。この塔は、外観も書籍に埋もれた内景も映画「薔薇の名前」に出てきた塔を思わせた。後半に入って行くときに、一本の真紅のバラが気になった。
後半は、確かに子供さんたちには、ついて行くのが難しかったかもしれない。でも、私たちの耳に馴染んでいる名優たちの声が聞こえてくる。私にとっては、何よりも、一枚の絵が出発になっているように見えた。宮崎さんが、まだお若い頃、私たちも大変尊敬している堀田善衛さんと司馬遼太郎さんのお二人から、書生として話を聞く形をとった「時代の風音」という本を残している。本当に、ヨーロッパのことを勉強されていたのだ。後半、出てきたドアは、パリ・シャンゼリゼ劇場のそれに似ていた。
空想の世界から戻ったあと、主人公は少年に成長する。私たちが中学に入学する頃に、岩波少年文庫で読んだ吉野源三郎の「君たちはどう生きるか」のコペル君と同じように。
私の席の周りの子供たちは、確かにトイレに立つことはあったが、最後まで席を後にすることはなかった。きっと、この映画のことを大人になってから、思い出すに違いない。宮崎駿は、あの子供たちのためにこそ、この映画を作ったのだ。
傑作である。
--
書店に、長いこと見なかった「時代の風音」(朝日文庫)が並んでいた。増刷されたようで、大変うれしかった。(2023.10.01)
--
この映画が、オスカーの前哨戦の一つであるニューヨーク映画批評家協会賞のアニメ映画賞を受賞した。台湾や韓国での評判も聞こえてくるし、遠からず中国でも受け入れられるだろう。宮崎駿は、少なくとも半分は子供たちのために、この映画を作ったはずだ。私たちが、小学校の後半から中学校にかけて、吉野源三郎の書いた「君たちはどう生きるか」のコぺル君に親しんだように。(2023.12.02)
--
本作は、第81回ゴールデン・グローブ賞のアニメーション作品賞を受賞した。さあ、次は、いよいよアカデミー賞だ!(2024.01.08)
--
この映画が、第96回アカデミー賞の長編アニメーション映画賞にノミネートされたことが伝えられた。我が国でも、より多くの人たちにこの映画を観ていただきたいと思う。前宣伝が一切なかったとか、難しいとかの評判に惑わされることなく、この素晴らしい映画を楽しんでほしい。今からでも、遅くない!(2024.01.23)
--
アカデミー賞の受賞、おめでとうございます!
皆さん、今からでも決して遅くないので、劇場に足を運んで、この映画を見てください!
前評判とか、人が言ったことにとらわれることなく。
詳しい事情がわからない外国で、これだけ評価されたことが、何よりの証拠です。
素晴らしい映画ですから。
(2024.03.11)
よくわからないけど、それで良いよね。
周りの評判が良くなかったのと、原作を読んでいたので説教くさい作品かな〜と期待せずに鑑賞してみたらもの凄く良い作品だった。
内容は抽象画のような綺麗な映像とストーリーで受け手によって解釈は人それぞれになるのかなと思います。
自分の感想は良くわからない。
でもエンディングの地球のような青い映像と米津玄師さんのエンディング曲を聞いていたら自然と涙が溢れました。
積み木のように不安定で罪や戦争、死と生が混じり合った世界。
一つ一つのものに意味や理由などの答えがはっきりと存在しなくてもいいのではと思えました。
良くわからなかったけれど、感じるものありました。
また5年、10年経った時に観てみたいと思える映画です。
星をいくつ、つけるべきか
とりあえず4つ星をつけたけれど。
立て続けに金曜ロードショーで久々にナウシカともののけ姫を見た後に観た最新作。
もう二度と無いと諦めていた最新作。
世界に誇りたくなる背景の美しさ。
ちょっと遠目のアングルになった時の人物のラフさの可愛さ。
癖のある脇役達。
最初の1秒で、「そうきたか!」と腹を括って観始める。
私は、泣かなかった。
泣くほどグッとくるところは無かった。
でも泣いた分だけいい映画な訳ではない。
金曜ロードショーで、ナウシカを見てなかったら、また違ったのかもしれない。
11歳の息子も誘って観に行くか悩んだけど、連れて行かなかった。
連れて行っても良かったかもしれない。
春に観たコナンとは質感もストーリーもまるで違うアニメ映画を、息子ならどう受け止めたか気になるところでもあるが。
私にとっては、面白かったけど、
それはfannyではなくinterestingで、
見終わった後にスカッとする訳ではないけれど、
モヤモヤする訳でもない。
感動して何か教訓を受けた訳でもない。
それでも映画館でこの作品を観れて良かったとは心底思う。
余談だが、エンドロールで流れる「声の出演」を見て、「やっぱりな」が1人、あとは結構驚いた。
宮崎駿監督の集大成
ここまで何も情報が明かされないまま見た映画は初めてかもしれません。
あらすじもキャストも主題歌も、それどころか予告さえないのはびっくり‼️
それが逆な興味をそそられました。
実際何もない方が映画そのものを純粋に楽しめるかもしれません。
とはいえ、初日に話題になったから、キムタクやら菅田くんやら、米津さんやら、、とわかってしまいましたけどね。
でもストーリーは知らないまま見ました。
最初戦時中の話?と思いましたが、そういうわけでもなかった。真人の母が入院する病院が火事になり、亡くなってしまった。
その後地方へ疎開し、父が真人の母の妹ナツコと再婚する。
疎開先では学校に馴染めずいじめに遭ったりする。
そんな中、家の近くにある不思議な建物、そして人の言葉を話す青鷺と出会う。
ナツコが帰ってこないので、森へ探しにいくと、真人と一緒に行ったキリコは建物に取り込まれてしまう。
森の中の穴を抜けていくところはトトロみたいだし、トンネルくぐるところは千と千尋、ラピュタみたいに建物の外にある木の根をつたっていくところとか、海のシーンや魚を捌くところ、トーストにジャム載せるところとかはポニョ、建物の中で出会う男性のシルエットや階段、扉はハウルみたい。
もののけ姫のこだまみたいなワラワラとか、父の働く軍需工場の部品がならべられるところは風立ちぬや紅の豚、鳥はナウシカみたいだし、鳥がしゃべるのは魔女の宅急便みたい。
そんな感じで監督が手がけた12作品の要素が散りばめられていると思いました。
他の方のレビューにありましたが、13の石はその作品数の象徴で、もう自分の世界はこれで終わりだから、次の世代へ君たちが繋いで行ってくださいというメッセージ性もなるほどなあと思いました。
深い作品でした!
もうこれで本当に最後だと思うと寂しいけど、、生きるとは何か、ということをいつも考えさせられました。
ありがとうございました。
>二回目
真人が不思議な世界であったヒミとキリコは、昔母が一年ほど行方不明になったことがあったとあったから、その時のことなのかと思った。
母だけ行方不明になっていたと思うが、キリコも一緒に扉を開けて帰ったということはそういうことなのかな。
たくさんあったおばあちゃんたちの人形の中から、キリコだけ人形を持ち帰ったのは何故だろう?
予感してたのかな?
宮崎作品は瞬きするのも惜しいほど緻密すぎる、、
なんかこの一瞬で何かを見落としてる気がする(笑)
積み木を自分で選びなさいと言って断ったところ、人から与えられたものでその世界に籠るか、それとも自分で自ら切り開いていくか、そういう選択かなと思った。
後継者について
自伝的な作品である。
宮崎駿がどういう人間かは、これまでの作品の中ではバッチリとは語られてこなかったので、少年時代の彼と、年老いた孤独な男である今の自分を多少誇張して登場させて、二人で対話をさせたというかなり内面的な作品と見ました。
そこに若い頃の母親と、プロデューサーである鈴木敏夫と、何人かのスタッフを多分入れ込んでいるのだと読みました。
君たちはどう生きるか
ジブリ好きです。
子ども達が小さい頃。毎年見に行ってました。ジブリ美術館も毎年行ってました。宮崎駿さんこだわりのご飯食べて。子ども達は本を選んで買ってもらうのも楽しみにしていていました。
宮崎駿さんの最後の映画?なら見に行かなくてはと。
少しだけ前評判を見ていて。だから一人で。
実際は、最後は、もうこれでおしまい?と思ったし。声優さんはどの役だったかのテロップもなかったけど。
でも楽しかったなあ。
おばあさんたち。わたしは好きです。
沢山の鳥も。
変身も。
彼の世界。
夏子さんの為に急に何故あそこまで?とは思うけど。
次が。あるなら。又見に行きますよ。
彼の作品で日本のアニメ映画が沢山変わって。子ども達もいろんなことを感じた。
2歳でもののけ姫を毎日食い入るように見ていた息子は心配でしたが。とても優しい男子に育ちましたね。
声優さんを使わない彼の選択をわたしは指示します。わたしは声優さんの癖のある喋り方が好きではなく。それが気になってしまって本編に集中できなくなります。
是枝裕和監督の映画作りと似てる気がします。
全2100件中、901~920件目を表示