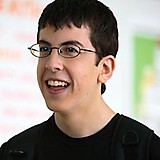君たちはどう生きるかのレビュー・感想・評価
全2098件中、281~300件目を表示
あれから10年
風立ちぬを映画館で鑑賞して以来のジブリ作品。
公開からだいぶたったが、NHKスペシャルで宮崎監督の仕事ぶりに感動したので、観に行きました。
ストーリーはざっくり把握してましたが、戦時中の話からはじまるとは思っていなかった。
アニメーションは相変わらずのジブリテイストで良かった。
疎開先から天界に行くまでの序盤は淡々と進んでいく。
サギ男や老婆などとのコミカルなやり取りに思わずニヤっとした。
あちらの世界に入ってからは、だんだん面白くなりそうな感じがしたが、そこまで盛り上がらずに物語はあっさり終了してしまった。
往年のジブリ作品を期待した人には、物足りない内容だった気もするが、監督の年齢は既に80代と考えれば頑張ったんじゃないでしょうか。
厳しくみれば、全盛期のナウシカ、ラピュタ、もののけ姫のようなワクワクドキドキや感動は無かったのは事実。
作品のテーマは、生と死。
高畑監督へのオマージュでもあり、師匠の高畑監督からアニメーション界を託された宮崎監督がどう生き、生きてきたのか。
作品を通してそれを描いている感じがしました。
大叔父がいる世界は宮崎監督の思い出の世
界。
そこに留まっている事も出来たが、それを断ち切り現実世界で美しい世界を作っていこうと決意する再生の物語。
ゆったりと静かなテイストのハートフル作品。
全米興行では歴代を塗り替えたそうですが、世界での評価はどうなんでしょうか。
エンタメ性よりもアート性が高い作品として評価される気がします。
音楽はジブリ作品の中では平凡でした。
次回作また作るのかは分かりませんが、とにかく完成までこぎつけてくれて、お疲れ様でしたと言いたい。
イメージの濁流
ストーリーが意味不明という意見が多い。正直わたしも訳が分からなかった。でも意外と単純なのかもしれない。戦争中に軍需産業に携わった家庭で何不自由なく育ち、そのことに強い負い目を感じ、しかも母を亡くした少年が精神的に自立して、さらに新しい母親を受け入れていくまでの心の葛藤を映像で具現化しているのだろう。ただし描かれているのは少年の頭の中なのでつじつまが合っていない。そういう事だと思う。
それにしてもアニメーションが物凄い。見ているこちらはまさにイメージの激流をカヌーで川下りしている感じ。あれよあれよと思っているうちに2時間が経ってしまった。退屈している暇などあるはずがない。
西洋絵画に興味のある人はいろいろ気が付くと思う。この辺は印象派とか、ベックリンの「死の島」のような背景だったりルネ・マグリットのシュールレアリスムのようでもあり画面を見ているだけで圧倒される。
思うに自分の境遇に疑問や不安や葛藤のある少年が自分の母親である少女のちからを借りて生まれ変わっていく話なのだと思う。
なのでストーリーを追う事自体意味が無いのかもしれない。画面をみて何を「感じる」かそれこそが大事なのだと思う。
なんだこれは
私小説
うん、よく分からん
肉の入ってないカレー
美術作品だな~って思いました。
なんとなく映画が見たくなって、やっている映画を検索していたら見つけた作品でした。え、宮崎駿作品?!やってるなんて知らなかった~と思って思わず予約。
名作を残してきた宮崎駿さんが、80代になられた今、どんな作品を通して何を伝えたいと思うのだろうかと、そんなことが気になって見に行きました。
正直、今までのように斬新でワクワクするようなストーリーではなくて、見たこともない世界観を味合わせてくれるような作品でもなくて、心温まる感じとも違うくて、「どうだった?」って聞かれても、「おもしろかった~!!」って言うよりは、「うん、よかったよ~。上手く伝えられないけど、見て、感じてきて~!」って伝えるストーリーでした。
でも、あ~どうせこんな話でしょ。と分かり切った薄いストーリーではなくて、音楽や勢いで感動させるものでもなくて、、うまく伝えられないけれど、宮崎駿さんの思いを感じられる映画でした。宮崎駿さんと対話しているようなそんなストーリーでした。
その時、自分の考えていることや、伝えたいことをストーリーに込めて伝えてこられた宮崎さんだからこそ、今のご年齢で今感じていることを伝えて終わりたかったのかなと。
私が感じたストーリーは、、
「周りからみたら変な点や理不尽なこともある世界でも、意思が積み重なってできたその時代は、築いてきた人たちには、壊したくないかけがえのない世界で、自分の大切な家族にも引き継ぎたいぐらいの世界だったりして、、自分もそうやって、与えられた世界の中で、自分なりの考えや意思を持って自分の世界を作って生きてきました。振り返ると、自分の考えと向き合い続けた人生だったな~と。あんなことを考えた日々もあったし、こんなことを考えた日々もあった・・・でも、そんな私も年をとって、私の世界もそろそろ終盤に向かっています。いつの時代も古い時代が壊れてまた新たな時代が来る。人生や世界とは、意思の積み重ねなんだなぁと改めて感じている今日この頃です。あなたの世界はあなたの意思で築かれる。あなたたちはどんな意思を持って、どんな世界を作っていきますか?」
っていうようなことを言われているように私は受け取りました。いや、、正直、1回見ただけでは細かい描写は拾いきれないし、もっといろいろ込めてるとは思うし、、そもそも私の考えとは全然違うことを伝えているのかもしれない、、、
この作品を通して、自分を見れる。自分がみたい、宮崎駿作品をみれる?美術品のような作品だと思いました。いや、実は今までもそうだったのかもしれない。
また、主人公が、塔を出た瞬間におじさんとの記憶が無くなる感じも、なんとなく、親戚が亡くなった際に、その時は、死と向き合って残りの人生について考えるのに、日常生活に戻ると、忘れてしまっている自分と重なりました。
宮崎駿さんが周りの人やファンに向けたメッセージのような映画なのかな?宮崎駿ファンにはすごくじ~ん。と感慨深い映画でした。これで終わって欲しくはないけれど。宮崎さんのなんだか心に染みわたる絵と世界観が大好きです!まだまだ、魅せて欲しい。
そして、この作品を、広告や宣伝なしで放映することを決めた、鈴木プロデューサーもさすがだなぁって思いました。宮崎駿さんのこの作品に、広告や宣伝に振り回されている世の中への問いかけの思いも乗せて、世に放った作品なのかな~なんて思ったりして。これはただの、私の願望。みなさんも、自分がジブリに期待していたもの、求めていた物、ジブリに感じていて欲しいと思う、自分の意思を確認しに、観に行ってみられたらいいと思います。
やっぱり、一番、宮崎さんの考えと向き合って、信じてきた方なんだろな~。名コンビ。
お決まりの映画だった
全米No.1になったので今更見に行きました
ジブリの映画
私達はどう生きるか?どう過ごしてきたか?自分は、貴方は?
やっぱりジブリ好き!
遡れば小学生の頃、友人に誘われあまり興味のなかったアニメ映画だったので、朝早くから新宿まで行くのヤダなーとイヤイヤ行って観た「風の谷のナウシカ」で
あまりにも衝撃的で号泣し、終わった後なかなか席から立ち上がれなかったのが、ジブリとの出会いでした。
小学生ながらにこんな世界があっていいのか…と
イヤイヤ来た事を心苦しく思いました。
それからジブリの映画は、必ず映画館で観てきました。
宮崎さんは、私の父と同世代なのですが
頭の硬い昭和初期の頑固オヤジだったので
同世代でこんな世界を描ける柔らかさと、
世界観、創造性に
今回も驚き、惹き込まれていました。
「君たちはどう生きるか」という問いは
「私はどう生きたいか」という、観た人それぞれの
答えがあるように思います。
きっと私も死ぬまでこの問いを自分に投げかけ続け、
いくつになってもこんなふうに豊かな柔らかさを大切に持っていたいなと感じました。
おじい様の来ていたガウンが、風の谷のばば様と同じような物だったのも嬉しいポイントでした!
今までのジブリ作品にでてきた色んなものが
隠れていたのも楽しかったですね♡
問われた課題はあまりに重い
ジブリファンとしては、久しぶりのジブリ映画を劇場で鑑賞できただけで...
ジブリファンとしては、久しぶりのジブリ映画を劇場で鑑賞できただけで嬉しかった。
でもはじまりの青いトトロが1番感動したかも。
マーニーとアリエッティと風立ちぬをごちゃ混ぜにして、哲学的な難しい雰囲気をプンプン匂わせた感じの映画。
ラストもうすこし主人公の成長が見たかった。
観てよかったけど、ジブリの中でアリかナシかだとナシ。
その後もう一度観る機会があったけど、やっぱり理解しきれなかった。
他人の内省世界。
宮崎監督作品を劇場で鑑賞するのはナウシカ以来二回目。
好きなのは未来少年コナンとナウシカだけで、ジブリだからとかそういう思い入れは全くありません。
で、本作。
宮崎駿氏の内省世界をひたすら見せられます。
何を作っても許される晩年の大御所監督が作りがちな自身を内省する為の映画で、そこに観客の為のエンタメは無いです。宮崎監督も結局そこに落着しました。
他人の内省世界なので、それは当の本人にしか知りえない世界。
それを見せられて分かった気になる人間もいるだろうし、そうでない人間もいるでしょう。
アニメ作品にありがちですが、考察して分かった気になれるファンなら楽しめる映画だと思います。
個人的に苦手だった点。
アオサギというキャラが登場しますが造形が醜くキャラ自体もウザい。主人公をいざなってしまう重要キャラで割と出ずっぱりですが、単にウザいだけなら別にそういう作品なので問題ないです、ただの嫌いなキャラで済みます。
しかしこれに声をあてている菅田将暉の声や演技が悲惨過ぎてウザさに拍車をかけている。自分には終始コレが引っかかってしまい冷めてしまっていた。やっぱり声優はプロにやってほしい。
単純にエンタメとして楽しもうとする向きには合ってはいませんが、いろいろ想像を巡らせながら鑑賞していけば普通に楽しめます。作画や動画、映像全般は相変わらず素晴らしいし。
ご本人はまだやる気らしいですが年齢的におそらく最後になりそうなので、とくにファンというわけでもなくジブリに思い入れが無いにしても、記念に見ておくのもよいと思います。
ファンタジーの醍醐味
ようやく観賞しました。レビューでは賛否あるのは知ってたが、予備知識ナシで臨みました。基本的にファンタジーやおとぎ話的な世界観こそジブリの真骨頂だと思ってますので、違和感なく観賞できました。
ストーリー展開もわかりやすく、序盤の前フリから異世界への旅立ちまで青サギでうまく興味を引き立て誘い繋いでいます。そこからはファンタジーです。次はどうなるの?とワクワクドキドキ感をもたせる展開は見事だと思います。それがファンタジーの醍醐味だと思います。
ストーリーが難解だとか何を言いたいのか分からないとの批判も一定は理解できるけど、そんなに小難しく考えなくても楽しめると思いますよ。どう解釈しようが観た人の自由です。それでいいのです。宮崎駿の脳内は宮崎駿にしか分からないですよ。
「戦争」が根底にあって、それを踏まえて上でこの先君たちはどう生きるのか?争いのない世界を夢想して生きるのか?それとも現実を受け止めて困難のなか生きるのか?戦争経験者である宮崎駿からの問いかけなのかなとぼくは思いました。
想像の世界を脳内で詳細まで構築し、それを映像化して一つの世界観をつくるなんてとんでもない凄さを感じます。宮崎駿の頭のなかどうなってるのか知りたいです(笑)
全2098件中、281~300件目を表示