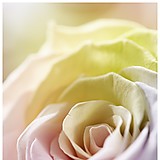ヒトラーのための虐殺会議のレビュー・感想・評価
全120件中、61~80件目を表示
特別処置って言葉が怖い。
悪趣味な映画かな、、と思ったが議事録を元に作られた歴史再現ドラマです。こういう映画をわざわざ作るって、ドイツ偉いとつくづく思う。
大仰な音楽も演出も無いです、エンドロールも只々無音、、、黙祷です。
会議はナチスvs政治家になってますが、どちらもユダヤ人を地球上から殲滅する事は同意の上。問題になるのは処刑に携わる兵士のPTSD、ユダヤ人技術者、一次大戦でドイツの為にたたかった功労者の処遇。
そしてドイツ人とユダヤ人混血問題。
彼らのユダヤ人への憎しみ半端なく、そこら辺がピンと来ないんだけど、ピンと来なくて良かったよ。
LGBT問題もチェチェンみたく、ちょっと国の指導者が違うとあっさりこんな会議がどこかでこっそり開かれてるかもしれないと思うとマジ怖い。
もう会議自体は非常にスムーズで合理的、そして司会者が優秀。僕らの会社の会議もこのくらい無駄なく進むのが理想的。どこ感心してるんじゃ、、、、。
追記:この映画の元になったヴァンセー議定書や参加者の自伝などに詳しい人の話を伺う機会があったのですが、ほんとはもっとビジネスライクに最終解決(ユダヤ人絶滅)に向けて指揮権の移譲が話あわれ、ドイツ兵のPTSDに関する記述はなかったようです。
おぞましい
知ることに意味がある
強烈な違和感
一貫して会議をしているだけです、回想シーンもありません。
登場人物たちは自身の立場において職務をまっとうしようと議論しているだけです。
議題さえ違えば。
立場の違いからくる意見の相違や権益を奪われたくないとする言動から、しばしば議論は荒れますが、彼らのユダヤ人に対する見解は共通しています。
彼らの前提にある思想、価値観がとうてい理解できないために、強烈な違和感があります。
この人たちはいったい何を議論しているんだ?と不快感嫌悪感を感じる前に、脳が理解を拒否しているようでした。
このレビューを書き起こすのにも時間がかかってしまいました。
本作は実際の議事録にもとづく再現だそうで、戦争の醜悪さを伝える新たな切り口として斬新です。
23-017
事実は変えられないとわかっていても。
なんとか結果が変わって欲しいと思いながら観てしまった。
「皆殺しなんて無理無理無理。」っていう意見もあったんだなと思いつつ、しかし、無理の理由が「労働者がいなくなる」だの、「弾丸がもったいない」だの、見事に倫理的観点がないのが怖すぎる。
今まで観てきたナチス映画を脳内で繋ぎ合わせてみるもやはり混乱。「ナチス第3の男」がハイドリヒなんだよね。「ハイドリヒを撃て」っていうのもあったよな。などなどもう一回過去作も改めて見返したくなりました。
戦争の恐ろしさ
ユダヤ人はこの世から消し去らなければならないということを大前提に、総務省やら総督府やら東部担当官やらよく区別ができない様々な立場の高官が、文書でのやり取りでなく美しいバンセー湖畔の建物に一堂に介して話し合おうという会議の一部始終。
1942年の段階ではドイツはまだ優勢だったのか嘘か、フランスの一部より西南と北欧を除いてほぼ全てがドイツの手中にあり、ドイツ国内のみならず全ヨーロッパのユダヤ人を絶滅させる使命を感じている。ただこの時点で彼らのような高官が「ここにはこんなに食べ物があるんだな」と言うくらいだから、庶民は間違いなく貧していただろう。
意見の中には「先の戦争ではドイツ軍として戦ったユダヤ人もいる」などユダヤ人を十把一絡げにしたくないというものもあるが、65才以上や功労者は別の収容所を用意するという結論で良いことになってしまう。
ラストにユダヤ人虐殺の手段の話になり、1人ずつ銃殺では非効率過ぎて不可能という議論になる。そこでガス殺が出てくるのだが、国民性が日本人に似ていると言われるドイツ人が、アウシュヴィッツ強制収容所などの凶行に至った理由が少し分かった。
ドイツ人がズラリと並ぶとワールドカップのドイツ選手と被る。戦争とは友愛や倫理とは切り離されるものなので、生まれた時代が違えば、彼らだって、もちろん私達だって…。
「普通」の会議
残された議事録に基づく完全再現だと思う。
準備段階(配席や食事の準備、列席者への根回し)から、休憩そして裁決に至るまで、90分の会議の一部始終を描いた映画。舞台はただそれのみ。
各組織の管轄争い、利害の絡んだパワーゲームの側面はありながらも、大きな紛糾もなく、会議は紳士的で見事に議事進行されており、そういう意味でも一見「普通の会議」を見ているような気がした。だからこそ、その異常さが際立ち、見ていてゾワゾワ、ドキドキせずにはいられない。
議題は、いかに効率よく(コストをかけずに)1100万のユダヤ人を1人残さず抹殺するか。「大義」(ユダヤ人は不浄で争いの火種で消えるべき存在であるという考え)に基づく「任務」の遂行のために、数字上の計算と共に行われる議論には、規律と組織を重んじるドイツ人の特質も随所に感じられる。休憩中の会話やふとした表情に本音が感じられるようなシーンもあるが、「倫理」を持ち出して異議を唱える参加者もそもそもの大義に異議を唱えてはおらず、各人が自分に与えられた「任務」に徹しようと努めているようだ。
個人的に一番印象に残ったシーンは、終盤のアイヒマンの虐殺計画の説明を横で聞いている議長のハインドリヒが、満足そうな恍惚にも似た表情を浮かべているところだ。アイヒマンの官僚的な有能さ、ハインドリヒの優秀なリーダーとしての人格が、より一層不気味さを際立たせていた。
これは国民のため、子や孫のため、世界平和のため…本当にそうか?結局は、ヒトラーという狂人のためでしかないんじゃないの?
いざ戦時下の渦中にいたら、人間はこんな風になってしまうのだろうか。
少し難しいかも
23-017
ただの会議なんですよね、議題以外は。
ホロコーストを扱った「別角度」作品の一つと言って良いのではないでしょうか?実際の議事録を元に作ったそうです。ですから、映画として云々・・・というよりも、会議が行われたという事実と、その場で話された内容を多くの方に届けるという意味合いで、大変重要な作品だと思います。故にとっても興味深い作品になっていると思います。
その会議の経過を通じて当時のナチスドイツの軍、役人の力関係や個人のパーソナリティをうまく散りばめ、さながら池井戸作品の「企業モノ」みたいな感じ(笑)・・・けど、これってとっても恐ろしい議題について、皆冷静かつ建設的に話し合っているという・・・薄寒い話なんです。
会社の効率的な会議のお手本ですよ、これは。根回し、議事進行、決を取るための周到な準備。素晴らしい。90分で終了した理由がよくわかります。みなさん、優秀!
けど・・・議題は・・・・悪魔のそれです。
方針を誤っている独裁者やカリスマやリーダーが居るってこういうことなのね?って感じです。ロ◯アって北◯鮮って、某巨大国の重要会議ってこーなんだろうなぁ、、、、なんて思っちゃいました。だって、誰一人、このおかしな議題への疑問を持たないんだもん。すごい。
ほんのちょっとでもヒューマニズムや人としての葛藤を期待している自分がいましたが・・・現実ってそんなに甘いもんじゃないってね。
作中ではユダヤ人を表す言葉がまぁひどいです。でも、そういう扱いだったってことだもんなー。会議の中では、たくさんのホロコースト映画で描かれた虐殺までのプロセスが話し合われます(こいつらが決めたのか・・・)。仕事の一つとして話されます。呆気に取られるくらいに命がぞんざいに扱われます。まさにゴミのよう。敗戦後、「ヒトラーの指示に従っただけ」って言って戦犯逃れした人はたくさんいたのでしょうが、この映像を見ると「いやいや、虎の威を借る狐だって犯罪者だぜ」と言いたくなります。ナチスドイツの全責任者を処しても良かったんじゃ?
もっともっと演出をぶち込めば大作になりそうな作品。けど、このフォーカス具合が良作となり得ているのかも?
会議の行い方の見本のような映画。 ただ一つの強烈な違和感を除いて。
第二次世界大戦時にナチスドイツが行ったユダヤ人大量虐殺(以下:ホロコースト)を扱った作品は数多く存在する。しかし、ホロコーストを“スムーズに履行するための会議”は今まで聞いたことがなかった。本作はその会議「ヴァンセー会議」の内容を、残された議事録を基に描いているという。ちなみに、
会議に要した時間は90分という。
なんやと?90分で決めたやと?ホロコーストをスムーズに完遂するために政府高官および各省庁の重役、計15名で会議を開き、1,100万ともいわれるユダヤ人の運命を一刻に満たない時間で決したのか。衝撃である。いったいどんな雰囲気で会議が進んだのか?それを観るために劇場へ脚を運んだ。
映画開始冒頭から会議が始まるのかと思うてたが、そうではない。席の割り振りから始まり、参加者の簡単な説明があり、そして議長:ハインリヒが政策の味方に対し最終確認をする。具体的な数字を出しているとこをみると用意周到さが窺える。90分で決めたとはいえ、入念な準備を行って万全を期して会議を開いたのだろう。また会議始まって冒頭から「ヒムラー(=ヒトラーの側近)よりユダヤ人問題の最終的解決をすみやかに実行すること」というお達しを皆に伝えることで会議の目的を明確にしたことも、皆の意識を一つに向ける効果がありそう。かくして、会議はユダヤ人の数と、それに伴う移送問題と収容所問題に分けられた。
しかし意見は存在する。収容所を持つ管轄の負担はどうか?移送にかかる鉄道の輸送力は?欧州全体に散らばるユダヤ人を集める方法は?これらに関しては議長のハインリヒが書記のアイヒマンらと予め策を講じていたのだろう、軽快に計画を説明していく。これに関しては誰もが納得した。すると今度は役所の人間:シュトゥッカートが意見する。混血の方はどうする?1/2は条件付きでドイツ人として認める。1/4ならドイツ人だ。法律も示している。それをいまさらユダヤ人とするのか?他のドイツ人が混乱し、場合によっては家族を失うドイツ人が出ることに懸念を示す。他方、第一次世界大戦を経験したクリツィンガーは言う。計画的にユダヤ人を“処理”するのは若いドイツ兵だ。それも欧州全体に及ぶと処理の期間は長くなる。成熟していない若者が長期間処理を続けるにあたり精神的な障害を追わないか心配だ、と。ここはハインリヒも用意していた策が通じなかったか、上手く丸め込めなかった。そこで彼は、シュトゥッカートに対しては1対1の話し合いと言う手を使い、相手に配慮しつつ腹の内を吐き出しながら説得した。相手はなんとか納得した。クリツィンガーには、処理はユダヤ人が行い、ドイツ人は精神的に参らないように配慮する案を出した。クリツィンガーは納得する。「これなら人道的です」と。こうして会議は終結する。
ここまで観て、私は会議や議論に関しては素人ではあるも、だからこそ「会議はこうやって進めていくんだな」と思った。味方の確保と根回し、事前の入念な下調べ、具体的な数字把握、周りが納得できるような案の準備。周りに対する配慮。会議の目的の明確化。意見があったときの冷静な対処。議論がかみ合わない相手には1対1であっても懐に飛び込む勇気と決断力。だからこそスピードある意思統一ができるのか。なんか会議の見本を見ているような、ビジネスにも活用できそうなイメージである。こんなコメントを書く自分は途中まで思考が麻痺していたんでしょう。しかし、映画の後半の中頃あたりから、ふと強烈な違和感に気づきます。
だれも“ユダヤ人を根絶やしにする”ことに異論を唱える人はいない。
一瞬ユダヤ人のことを考えて、さすがにまずいのではと思われる節を持つ人がいる。さすがに人道的に・・・かと思いきやよくよく聞けばそれをする“ドイツ人の肉体的・経済的・精神的負担”を危惧する内容なんです。夥しい数のユダヤ人が死ぬことに誰一人罪悪感を持っていない。ここにいる皆の共通認識は、ユダヤ人=害虫、である思想だと感じてしまう。つまり本作で描かれているのは、如何に効率よく、負担が少なく、ユダヤ人を処理するか・・・。
民族を滅ぼす計画を、害虫を駆除するビジネスのように語っていること。
この映画はそこに焦点を当てている。映画を観てて途中麻痺してしまっていたが、これが実際の歴史であったことと思うと静かな恐ろしさを感じます。戦争とゆがんだ認知(=差別)がもたらした結果がホロコーストを加速させた。関係者は対岸の火事を見ているかのように。
そしてふと気づく。現代でも起きている戦争・人種差別・迫害のなかでこうした会議が起きているのではと。ゆがんだ認知を持つ者たちだけの会議が行われていないかと。この映画は、そうした人にならないように、そうした人(政治家)を生み出さないようにと訴えているように思う。過去にそれを起こしてしまったドイツだからこそ描けた作品なんでしょう。今起きていることを過去から学ぶかのような、なにかには気づいてくれと言っているような映画でした。
恐るべき「最終的解決」
第二次世界大戦下、ヨーロッパ各地にいる1100万人ユダヤ人の処遇をどうするか…実際に行われたという90分の会議を描いた作品。
ナチスを描いた戦争映画は数あれど、銃声の一発も響かない、本当に延々と会議の様子だけが描かれた作品など他にあったでしょうか?
沢山の人物が出て覚えきれないし、皆高官だけあって言葉選びも慎重かつ難解。よって、細かな所までは理解できなくもこれ程までに引き込まれるとは見事な作品です。
成程、感心などして良い話では無いですが、ホロコーストもただ我武者羅に行われた訳ではなく、ナチス側の効率や負担、混血の問題についても…。
各重役の裏に見え隠れする思惑が、話を一筋縄には行かせない。内容はともかく、見応えがある。
とにかく、所々少々熱くなる場面はあれど、こんなにも恐ろしいことを淡々と、本当にビジネスの一部とでも言わんばかりに冷静に話し合う姿が恐ろしい。。
沢山の高官が登場しますが、1番恐ろしかったのはアイヒマンかな。他の人物も言っていることはアレですが、まだ感情が垣間見えるものの、アイヒマンは本当に1ミリもテンションを変えず淡々と・・・。
最初は隠語のように語られていた会議も段々と生々しくなっていきましたしね。。
1つの場面が続きつつも飽きさせないつくりに驚かされるとともに、この悲劇の重さに改めて苦しくなった作品だった。
ユダヤ人の最終的解決
恐ろしい。
ユダヤ人が戦争を望んでいる
この人種の除外(だったかな?)に異議はない
射殺するドイツ兵が心配
まずはうちのユダヤ人から処理を
など、え?論点そこなん?と目を見張るワードがてんこ盛り。や、わかってたけども…。
この議題に、各人が自分の仕事を全うしようと、各々の立場で反対意見を言ったり、意見が通らなくても言うべき主張ができたと満足したり、もっとコネを求めてゴマすったり。来年度の予算執行のーとか、コロナ対策としてーみたいな、議題を扱ってるかのような態度。たぶん実際そうやったんやろうな、このように振る舞えることが、人間の醜さなんやろうな…と思いました。
映画ハンナアーレントでの小物感溢れるアイヒマンと、
この映画での有能なアイヒマンの落差に、視野を限定して生きる“凡庸な”人の恐ろしさが、より自分に刺さります。
「凡庸な悪」をきっちりと映像化
ハンナ・アーレントが本作にもキーマンとして登場したアイヒマンを表した言葉「凡庸な悪」。
それが単に彼だけではなく、ナチスにおける重要事項の決定会議の参加者に蔓延していたことをしっかりと映像化した作品。
やや退屈なシーンもあるにはある。ただし、議事録を元に作った、という言葉を信頼すれば、600万人というユダヤ人を死に至らしめた決定が、このような空虚な会議によって決まったことにただただ戦慄する。
あまりにも淡々とした議論に驚く
ユダヤ人虐殺を政策として決定し、虐殺の方法を議論した「ヴァンゼー会議」を描く、一風変わったナチス映画。
基本的に当時のドイツ政府の高官たちが議論する姿しか映らないので単調になるかと思っていたが、なかなか緊迫感のある映像だった。それはやはり1100万人のユダヤ人を根絶しようという大暴挙が、異論をほぼ挟まれることなくあまりにも淡々と議論され決定されていくからだ。若干反論もあった。でもそれはユダヤ人を殺すことへの反論ではなく、自分の仕事が増えないように、もしくは自分が作り上げた法律への解釈が変わることのないようにという憂慮からの反論。唯一の人道的な配慮はドイツ人兵士に向けられたもの。会議の参加者に多少の人道的な戸惑いみたいなものがあるかと思っていた私のわずかな期待をあっさりと崩すものだった。
1つの民族をここまで憎み、根絶したいと考える思考はどこから来るのだろう。個人的にはやはり経済的な格差や不平等感から始まっているのではないかと考えてしまう。それは今もヨーロッパで起こる移民への排斥運動やネオナチの台頭につながっている。80年前の出来事だが、全然終わっていない問題ってことだ。現代のことを考えさせるという意味でもとても意義がある。
また、会議の運営って視点で考えると別の感想も。議長を務めた国家保安本部は自分たちがユダヤ人虐殺を仕切るために、各省庁の合意を取り付けようとしていた。だから根回しが周到だった。ビジネス的な意味では優秀だ。でも、結論ありきの会議は参加者にとってかなりしんどい。自分が会議に参加している感覚になってしまうとなかなかの疲労感が残る映画だ。
最も印象に残った
全120件中、61~80件目を表示