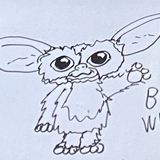ベルサイユのばらのレビュー・感想・評価
全315件中、1~20件目を表示
名作「ベルばら」を2時間弱で駆け抜ける
歴史と少女漫画のロマンチシズムを如何に見せて頂けるかと期待したいところですが、様々なエピソードを手短に紹介する、そんな歴史ドキュメンタリーなダイジェストを印象にもってしまったことは否めません。
ですが、それでもバラは咲くことを止めない。「ベルばら」はやはり「ベルばら」であったと十分に納得できたと思うのですが如何でしょうか。正直、ベルばら原作もヅカの舞台も触れたこと無いので自信を持っていうことが出来ません。フランス革命もマリー・アントワネットのこともよく知らなかったし。
でも、画面に乱舞する美しい薔薇は、これぞ少女漫画なのだな、と思う。上映時間をおしてもドラマ部分を削っても、挿入歌とそれを演出する映像は素晴らしい。踊るモーションは実に華麗。それらの演出は歌劇である宝塚版を意識されているのでしょうか。特にマリーとフェルゼンの逢瀬で、夕焼けに染まった薔薇の浮かぶ水辺の光景には身震いしました。ただ、「恐ろしい子!」で有名な白目ショック顔はクスッときたけど、笑って良かったのでしょうか。
歴史は詳しくないし、本当にこんなにドラマティックであったのか。私には判らないけど、これをきっかけに史実を紐解くのも良いかもしれません。ベルばら原作や宝塚の舞台にも触れてみたい。ああ、そういえば、歌舞伎の俳優祭でベルばらを演じられていましたね。まだニコニコとかに動画残ってるかな。男性が男装の女性を演じるという、よく判らないことになってましたが。
改めて、画面を乱舞する薔薇が実に美しい。少女漫画を余り知らない私ですが、「エロイカ」ぐらいなら読んだことがあって、その外伝「ツェット」の1話で多くの薔薇が描かれていたけど、描くのが難しいので他の先生に頼んだんだったか。描くのも折り紙で折るのも難しい薔薇。最後に誰も居ない「薔薇園」で締めるというのは素晴らしいエンディングでした。映画でも舞台同様に「カーテンコール」で締める作品が好きなのですが、誰も出さずに登場人物を象徴する薔薇でご挨拶というもの意味が深く、実に感慨深いものがあります。何はともあれ、スタッフの薔薇職人様(って、いるのかな?)お疲れ様でした。
でも、あえて要望するならば、エンドロールで傑作OPの「薔薇は美しく散る」を流してほしかった。そしたら一緒に歌いながら劇場を後に出来たのに。私は原作を知らないくせに歌だけは覚えていて、普段から折を見て口ずさんでいますから。
ベルばら初心者の私は今も余韻が抜けない
私が持ち合わせている『ベルサイユのばら』の知識は「男装をした女性がいる」という知識のみ。名作と言われているしこの機会に見てみようかなと、気軽な気持ちで見てみた。
上映が終わり、周りが明るくなった時
何度もこぼしたポップコーンの跡と(映画館の方すみません)何度も涙を拭ったことでの頬の乾燥が、この映画の衝撃と感動と、名作の偉大さを表していた。
原作やアニメを好きな人が見たら評価は違うかも知らないけれど、この令和の時代で初めて『ベルサイユのばら』を見た私には、彼らのそれぞれの生き様や信念に釘付けになった。
映画はディズニーのようなPOPSのミュージカル調だった。しかも深層心理を表しているため、海の中だったり空を飛んだり、花が散ったりの、まるでアニメのOPやEDのイメージ映像。最初は戸惑ったものの、まー『レミゼラブル』だってミュージカルだし、宝塚の『ベルサイユのばら』だって歌うしなと受け入れてからは逆にこの音楽で泣けた。というか曲が全部良い。声優さん達の歌がうますぎる。
ストーリー構成は、あの長いフランス革命を2時間でやろうというのが土台無理な話で、けれど音楽に任せるところで初心者が見ても理解して楽しめる構成になっていた。もしかしたらあのキャラがいないだの、あのシーンが無いだのあるのかもしれないけれど『ベルサイユのばら』の初心者入門総集編としてはとても良い作品なのではなかろうか。なんせ私はこれをきっかけに原作絶対読むってなったので笑
1日経った今でも余韻に浸っている。彼らの強い眼差しが忘れられない。オスカルとアンドレに出逢わせてくれてありがとう。もし映画化されていなかったら、私は彼らを知らないまま人生を終えていたかもしれない。
名作はいつの時代になっても色褪せないから名作なんだと思い知らされた。
オスカルの魅力を余すところなく
旧テレビアニメ版よりも原作に忠実に、オスカルの生きざまを中心に構成する内容で、リメイクした意義のある作品となった。革命の要因となる民衆の困窮などの描写は原作と比べると減っている、尺の都合が大半だろう、しかし、オスカルというキャラクターの哲学、魅力は余すところなく描いてみせたと思う。「人が自由であるのは心のみにあらず、髪の毛、指の先まで自由であるべき」の信念を貫くカッコいいオスカルがアニメで見られたのは感無量だった。沢城みゆきのオスカルが本当にカッコいい。
マリー・アントワネットに関しては、デュバリー夫人やポリニャック夫人、首飾り事件などがカット(ミュージカルパートでダイジェスト的に流れるが)された関係で、ともすれば自分勝手に嫌な人に見えそうなところを、平野綾の気品ある芝居で押しとどめていた。少女時代と大人時代の演じ分けも見事。宝塚みたいに「マリー・アントワネット編」とか「フェルゼン編」みたいに各キャラクターメインのエピソードとか作ってほしい。ベルナール・シャトレとロザリー編もほしい。
無理難題を歌とイメージで突破しようとした製作陣の蛮勇にビビる
原作やアニメシリーズやベルばらファンとして、不満点はわんさかあります。それがもはや今っぽいアニメの絵柄やスタイルについて行けてない老害的な部分もあるとは思うが、にしても、2時間以内に原作をほぼほぼ収めようなんて狂気の沙汰。想像だけど、作り手だってそう思っていたんじゃないか。そして製作陣が出したひとつの答えが、ええい、複雑なストーリーを語ったり、人間の成長譚を丁寧に追う時間はない! 歌だ! ガンガン歌とイメージ映像で進めていけば、キャラクターのエモーションだけは残すことができるんじゃないか? どんな会議があったのかは知らないが、結果的に、インド映画的なミュージカル手法に、LDHっぽい楽曲(個人の印象です)に載せるという狂った映画ができあがった。曲調もまったくフランス風とか考えてなくて低音ズンズン鳴ってるし、歌詞も「I believe in my way 私のデスティニー」とか、英語混じりの日本語でムチャクチャだとは思う。でもまあ、どだいムリを承知で産み落とされた強烈にヘンな映画であり、こんなベルばらがあってもいいような気はしたんですよね。不満点はわんさかあるんだけど、まあアリ。
池田理代子による原作劇画のパワーを再認識
宝塚の舞台はもちろん、TVアニメにもなった人気劇画初の劇場用アニメをこのタイミングで観ると、改めて池田理代子の原作がいかに優れていたかがよく分かる。フランス革命という史実をベースにした男装の麗人、オスカルと、オスカルの従者で幼馴染みのアンドレの悲恋物語は、拘束が強い時代だからこそ価値がある、自由の意味を問いかけて来るのだった。あの『ベルばら』ブームの本質はここにあったのかという驚きと共に。
アニメ映画としての視覚効果については議論が分かれるかも知れない。でも、隙間だらけのスクリーンを埋め尽くし、そしてそれを凌駕する物語の熱さに、思わず込み上げるものがあったことは事実だ。
それにしても、オスカルとアンドレの関係性に潜むジェンダーというテーマが改めて浮き彫りになったこと。そこにも、池田理代子の視野の広さを感じないではいられない。
昔、話題になった劇画のアニメ化という表層だけで判断せず、劇場に足を運ぶこそをお勧めする。
ミュージカルが嫌いという訳ではないが…
ベルばらはとても大好きな作品で、ムビチケを買って初日に観ました。
結論から言うと、期待はずれの内容で、
ミュージカル?MV?の部分、観ていてしんどくなりました。フランス革命の内容はそこそこに悲劇的な二組のカップルのラブストーリーだけを追いかけてます。
このような内容なら無理に映画にする必要は無かったのでは?
唯一、ビジュアルだけはとても良かったです。
この作画でテレビアニメ化していただけたら最高だと思います
映画→原作→映画をやりたくなる映画
オスカルかっこよさ✨✨✨✨👍️
原作やテレビアニメのようには尺的にじっくりは描けないのでどうしても...
べるばらTimlyアクエリアス!!
原作、舞台とも未見でべるばら初めて見るけど期待通り、否それ以上だ!絢爛豪華な王侯貴族の世界と虐げられた民衆の蜂起というフランス革命期のコントラストを人間ドラマの愛憎劇を絡めて昇華した物語は見事だと思った。
原作の出来の素晴らしさは推して知ることができるし、この映画単体をとっても初めてべるばらに触れた私のような者にも分かりやすく尚且つ感動を与えてくれる見事な構成になっていると思う。現代アニメの映像技術で表現された美しいキャラや背景のヴィジュアルは見事。途中の挿入歌の部分はまさにミュージカル風にもっとダンスを取り入れた演出をしてもよかったかも。
このシーンを見て宝塚のミュージカルやその他の舞台演劇も観てみたいとおもった。
それはともかく沢城みゆきさん演じたオスカルは素晴らしく凛としたその姿と内面の鮮烈な美しさを最大限に表現していて、TVアニメとしてリメイクされたらこの人しかキャスティングできないと思った。
そしてスピリチュアルやな観念や占星術から見た世界観やを知る私としては個人的にこれは当にエネルギー的に今の時代を象徴するの映画で、タイムリーベストなタイミングで上映されたものだとおもった。
スピ的な表現で言うと古い時代のエネルギーが淘汰され、新しい2000年紀の始まりと風の時代到来を告げるに相応しいあいが映画だと感じた。
なぜならフランス革命期も丁度今の時代のように古い時代の破壊と再生を司る♇冥王星が♒水瓶座という変革のサインである星座に滞在していた時期に起こったものであるから。フランス革命のスローガンとされる自由・平等・博愛はそのまま水瓶座のテーマそのものでもあり、製作陣やプロデューサーなどに占星術の知識に長けた人がいたのではと思えてならない程にベストなシンクロニシティ(共時性)!これ以上なくタイムリーなタイミングなんだよね。
そう考えると現代のロシア✕ウクライナ戦争が収束に向かいつつある現状など、様々な変革の流れは時代の遷移に伴い天の星々が起こした運命的な出来事と思える。
そして、オスカルというアニメ史に燦然と輝く金星のうような傑出したこのキャラクターは自由、平等、博愛を信じてあらゆる理不尽や偏見、抑圧からの人間の解放のために今尚戦い続ける真のヒーローであり、その姿を見た現代の人々を力強く勇気づけて前に進ませてくれる。約50年ぶりにベルばらが復活した意義がここにあると思う。この不滅の名作を生み出してくれた原作者池田先生に心から感謝しています。ありがとうございます。🙏
そしてこの映画を観て素晴らしい感動を得られた幸せに素直に感謝したい。製作スタッフ・キャスト一同にとても感謝しています。ありがとう!!✕3☺観てよかった!!ブラヴォ!ブラヴォ!!Bravo!!😄😆
これぞ少女マンガの王道
これよこの目の描きは当時流行りました
が、?
しかし、池田先生は違いますのよね
多分ベルサイユのバラは
ちょっと大人向けでして
当時なかよし、りぼんの読者さんにも
懐かしいと思っていただける
今作のベルサイユのバラだったのではないかと思います
革命の戦闘中、ゆうゆう歩く主要人物が真っ正面から狙撃されるのはギャグですか?
ファンの母、未履修の自分とで観に行きました
感想は「長いミュージカルPV」「オスカル見たい人むけの映画」って感じです。
ただし作画と絵の良さは文句なし。言いたいことは以下です。
・ハブいちゃだめなシーンをハブいている。そのせいでラストに感情移入できない
・ミュージカルが何度もCMのように挟まり蛇足
・↑これらの理由でストーリーが薄い。
・ファンではない自分には、オスカルの顔のよさしか伝わらなかった
ただしラストシーン。革命が勃発する中で主要人物が撃たれるシーンがあるんですが
ゆうゆうと騎乗してお散歩してる主要人物が狙撃されるシーン。
いやいや戦闘中だろ!?兵士は何してんだよ!?戦闘中に悠々と横切るように歩くな!撃たれたいのか!兵士は防御姿勢だのカバーを取れよなんっで棒立ちでパンパン撃ってんだよ緊迫感なさすぎだろ!?
しかも狙撃が陰からじゃなく両軍うちあってる真正面からパーン!ギャグか!!?
………母はオスカル推しではなく「オスカル出すぎじゃない?」とばかり言っていました
最後ですが、作画がいいことは認めます。構成が惜しいですよこれは
中途半端なダイジェスト版
原作は読んでません。 原作を読んだ嫁の影響で見に行きました。 原作...
予備知識なしで観ても楽しかった
フランス革命を題材にした漫画を原作とするアニメ映画化作品。原作漫画は1979年から1980年にかけて一度アニメ化されており、この漫画がアニメ化されるのは45年ぶりで、さらに劇場アニメ化されるのは初である。18世紀のフランスを舞台にフランス国王妃マリー・アントワネットと女性で軍人のオスカル・フランソワ・ド・ジャルジェのドラマチックな生涯を描く。
点数:4.0。お勧めします。華麗かつ緊張感のある雰囲気のアニメ映画。貴族社会と軍隊社会の張りつめた雰囲気が視聴者の背筋を伸ばしてくれる。女性で軍人のオスカル准将は自分は一体何者かという自己同一性に悩むが最後に答えを見つける。オスカル准将のこのような人生は同様に自己同一性に悩む視聴者に生きるヒントを与えてくれる。
※フランス革命とは: フランス革命とは、1789年から1799年にかけてフランスで起こった、絶対王政を倒し、封建制度を廃止した市民革命です。啓蒙思想の影響を受け、自由、平等、博愛をスローガンに、国民議会による立憲君主制、共和制への移行、そしてナポレオンによるクーデターによる終結まで、激動の時代でした。(AI回答より)
※自己同一性とは: 自己同一性(じこどういつせい、アイデンティティ)とは、自分が何者であるかを認識し、自分自身を他者や社会の中で一貫して理解する感覚のことです。簡単に言えば、「自分が自分である」という意識です。(AI回答より)
有名な少女漫画が原作という以外は予備知識がなかったのだが私はこのアニメの華麗かつ緊張感のある雰囲気が楽しかった。特にバスティーユ監獄襲撃作戦でのオスカル准将の戦死の場面はドラマチックで迫力があった。オスカル准将は以前は自分が何者か悩んでいたが答えを見つけてから戦死したのでこの場面がすごく印象に残った。自分が自分であるという意識は人生で何かアクシデントがあった場合に必要になってくるのではないだろうか。順調に人生を送っているときは深く考えなくともよいがある日、引っ越ししたり、仕事を変えたり、生活環境が変化した場合になぜ私は生きているんだろうと悩むことがあるかもしれない。その時に自分が自分であるという意識を持っていると強いと思った。ましてや家柄により女性であることを禁止されて育ったオスカル准将の様な人物は自分が自分であるという意識はいつも必要であったに違いない。いわば本作はオスカル准将が自分の人生の名刺を作成する物語である。
テレビアニメ「機動戦士ガンダム 水星の魔女」(2022年-2023年)も自己同一性に悩む主人公の女性が答えを見つける物語である。地球から遠い田舎の星である水星育ちの少女スレッタ・マーキュリーは巨大ロボット兵器「モビルスーツ」のパイロットになるため軍人を育てる教育機関アスティカシア高等専門学園に転校してくる。そこで彼女は宇宙を支配する大企業ベネリット・グループの総裁の一人娘ミオリネ・レンブランと運命的な出会いをする。大企業の御曹司や美男子の男子生徒たちに言い寄られながらもスレッタ・マーキュリーは学園生活を送るのだが、彼女は自分が何者か自信がなくなっていく。そんなある日、事件が起こりスレッタ・マーキュリーとミオリネ・レンブランの運命は大きく動き出す。スレッタ・マーキュリーにはお母さんがいるが実は本当の母親ではない。そしてスレッタ・マーキュリー自身も普通の人ではなく誰かのコピー人間であると判明する。スレッタ・マーキュリーは自分が何者か悩むが親友のミオリネ・レンブランなどの仲間たちのおかげでその答えを見つける。最初は自分に自信がもてなかったスレッタ・マーキュリーは最後は自分を確立する。
オスカル准将は女性でも男性でもない育ちによって悩んでいた。これは現代日本人の悩みでもあると思った。現代日本は男女平等を推し進めているにも関わらず矛盾も多い。男性はどうあるべきか。女性はどうあるべきか。などという指針があいまいな現代社会では私は男性か女性かと考えるのではなく私は何者かと一人一人が考えなくてはいけなくなっている。つまり男性か女性かなどという問題はどうでもいいのだ。この映画の最後、愛する人や愛する国が見つかったのだからオスカル准将は自分が女性か男性かなどどうでもいいと思ったにちがいない。オスカル准将は悩むことをやめ、ふっきれたのだ。白か黒かつけないでよいこともあるというこの考え方は素晴らしいと思った。なので人生勝ちか負けの2択だとは思わないようにしようと私は思った。
視聴:液晶テレビ(有料配信NETFLIX) 初視聴日:2025年6月10日(約2か月前) 視聴回数:1(早送りあり) 視聴人員:1(一人で見た)
2025年6月10日に書いた昔のレビュー:
自分の心も美しくなった気がする美しい映像
主人公オスカルのシーンが大げさなくらい美しく描かれていてすごい。ベルサイユ宮殿に咲くバラの花のように美しいオスカルが戦いのなかバラの花のように美しく散っていくさまを見たとき自分にも美しい涙が出ているような気分になりました。カンフー香港映画を見た後自分が強くなった気分になるみたいにこの映画を見ると自分も美しくなった気がしてくる不思議な映画です。フランス革命が舞台なので西部劇みたいな銃撃戦のシーンも楽しめます。
2025/08/13 追記1:
主人公の自己同一性の確立をテーマとする映画は多い。自分が何者であるかわかるという事は大きな精神的成長を意味するので視聴者はカタルシス(すっきり感)を得やすい。なので主人公が成長する成長物語は同時に主人公の自己同一性の確立の物語であるとも言える。アメリカの実写映画「ジョーカー」(2019年)は社会弱者の主人公アーサー・フレックが社会から理不尽な虐待を受けた末に堪忍袋の緒が切れ無慈悲な狂人ジョーカーに変身し悪のカリスマ(アイドル)になる話だ。映画のラストで無慈悲な狂人ジョーカーとなった主人公アーサー・フレックは自己同一性を確立しそれを観た視聴者は大きなカタルシス(すっきり感)を感じたのでこの映画は大ヒットした。ところがその続編映画「ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ」(2024年)ではあろうことか主人公アーサー・フレックは確立したはずの自己同一性を放棄して無慈悲な狂人ジョーカーであることをやめてしまう。視聴者は主人公が成長せず退行するこの映画からカタルシスを得られず映画は全くヒットしなかった。自己同一性の確立は主人公の成長を意味する。NHK朝ドラと呼ばれる作品シリーズの中で大ヒットしたテレビドラマ「おしん」(1983)を例にとる。このドラマは雪国の貧しい村で生まれた主人公の少女おしんがいろいろな苦労の末に田倉商店を興して会社を成長させる話である。初めは何者でもなかった少女のおしんがスーパーマーケットの社長になるのでこれはおしんの自己同一性の確立の物語である。これらは「自分はいったい何者か?」と問いかけ「私は~である。」と答える構造の物語である。複雑な階層社会である現代人類の社会はじつに数多くの役割があり、「自分はいったい何者か」がわかりにくい。答えはひとりひとり異なるのである。地球に住む人類80億人が一人一人異なったアイデンティティ(自己同一性)を確立するのが理想であるがそれは難しい。全ての人はそれぞれ条件が異なっているからだ。だから人類は人生のなかでアイデンティティ(自己同一性)の確立に悩むのであろう。
追記2:
この映画の登場人物は華やかで自信ありげに振る舞うがそれはこの映画が創作物だからである。実際の貴族や軍人は常にこうではなかったと思う。映画では立派な部分しか見せない。人間が生きるという事は泥臭いものが大半である。だからこそこのきらびやかな映画には価値がある。この映画は美しさとは何かというテーマももっている。美しさとは本来は瞬間のものなのに、永遠に美しく見せようとする貴族社会の美しさは民衆の苦労の犠牲の上に成り立っている。本来の自然の美しさは一瞬である。本作のタイトル「ベルサイユのばら」の薔薇は自然の美しさを、ベルサイユは貴族が所有するベルサイユ宮殿の民衆の犠牲の上に成り立っている人工的な美しさをそれぞれ意味している。薔薇の自然の美しさははかないがベルサイユ宮殿の人工的な美しさは民衆の犠牲が必要だが長く続けることができる。同様にオスカル准将は自然の美しさを、マリー・アントワネット妃は人工的な美しさを作品中で象徴していたと思う。オスカル准将はフランス革命で貴族を裏切り民衆の味方をするが、これはオスカル准将はたとえ長く生きられないといえ、はかない自然の美を選んだという事だろう。貴族社会の人工的な美しさは莫大な費用がかかるので誰かの犠牲の上になりたっており、持続可能社会(SDGs)の理念からも大きくそれている。オスカル准将は自然の美しさが人工的な美しさに勝つことを知っていたのだと思う。美しさは人類にとってとても価値があるが。それは誰かや地球の犠牲の上に成り立ってはならないし、持続可能でなくてはならない。オスカル准将はその理念を示し自然の美しさの素晴らしさを世に示しながら戦死を遂げたのであった。不謹慎だが私にはオスカル准将の死のさまはとても美しく感じた。この戦死の場面は人間の生ははかなく寿命があるからこそ美しいといわんとしている様であった。この作品でオスカル准将は自然の美は貴族の美より何よりも美しいと言いたかったのかもしれない。
追記3:
本作は劇場映画ということもありベッドシーンがありますがベッドシーンの名作映画は数多い。アメリカのアクション映画「ターミーネーター」(1984年)ではハンバーグレストランでアルバイトしている女子大生サラ・コナー(リンダ・ハミルトン)が未来からやってきた姿は人間そっくりの無敵の暗殺ロボット「ターミネーター」T800(アーノルド・シュワルツェネッガー)に訳もわからず命を狙われる。そのとき同様に未来からやってきた若い男の兵士カイル・リース軍曹(マイケル・ビーン)が無敵の暗殺ロボットT800を一時的に撃退し二人は一緒に無敵の暗殺ロボットT800から逃げる。無敵の暗殺ロボットT800からの追撃もかわし二人で逃げるうち二人の間には愛が芽生えそこでベッドシーンが入る。このベッドシーンは重要な意味があり、この時にできた息子が大きくなって未来の無敵の暗殺ロボットたちの親玉を倒すことになっている。
フランス・イギリス合作の恋愛映画「愛人/ラマン」(1992年)は1929年のフランス領インドシナ(現在のベトナム)が舞台であり裕福な華僑の中国人青年(レオン・カーフェイ)と貧しいベトナム人とフランス人の混血の少女(ジェーン・マーチ)のベッドシーンがある。裕福な華僑の中国人青年は少女が好きだが、貧しい少女のほうはこの関係をビジネスと割り切っている。この映画のベッドシーンは愛情とは違う意味をもっている。
ジブリのアニメ映画「もののけ姫」(1997年)でもベッドシーンがいちおう存在する。不慮の事故で「人類の破壊の呪い」を受けてしまい村に迷惑をかけないよう村を出て行った少年アシタカは放浪の旅の末に戦争で両親を殺され犬の神に育てられた「人類の破壊の呪いの被害者」少女サンと出会う。少女サンは人間を恨み「人類の破壊の呪い」の象徴である危険な鉄砲工場のタタラ場に殴り込みをかける。タタラ場の工場長エボシの策略によりサンはピンチになるがアシタカはサンを助け負傷してしまう。サンはアシタカを自分のほら穴の住みかに連れて行きケガの治療をする。ケガが治ったころ二人はそのほら穴で関係を結ぶ。行為中のベッドシーンはないが、サンとアシタカが一緒に寝ていて朝目覚める場面だけが存在する。この場面により視聴者にベッドシーンを想像させている。
フランス映画「デリカテッセン」(1991年)のベッドシーンも良かった。近未来のフランス・パリ、一階が精肉屋のアパートに住む個性的な住人たちの物語。この映画のベッドシーンは音だけだが印象的だ。ベッドシーンは監督の性格や嗜好が反映する映画において注目の要素である。
コミックを愛する所以か…不完全燃焼感が否めない
TVアニメのときよりちょっと大人向けかも
絵柄は少女漫画っぽいのだけれど
愛と葛藤がとても伝わってきてちょっと大人向けになってるのかなと思った
もしくは子供の頃に見た時は、それがわからなかっただけかも
漫画とTVアニメと両方知ってる自分としては
その中間的な雰囲気
アンドレがオスカルに毒ワインを飲まそうと血迷ったシーンは
初見の人はあれが毒ワインってわかるのかなーとか思いつつ
漫画ではオスカルは毒と気付きつつ、アンドレが飲まそうと思うのなら、と
あおろうとするのよね。あのシーンに引っ張られて、しんみりする
名前忘れちゃったけど、
漫画ではオスカルのお世話をしてくれる市民の女の子も
子供をかばうシーンでチラッと出てた
贅沢三昧、マリーアントワネットにも
孤独がゆえに、という同情的側面も
これは大作よね
何年経っても古びない名作
池田理代子先生すごいわ
オスカルかっこいいと思っていた子どもの頃と違って
人間としての生き方や愛を感じるようになった
ベルサイユのばらって、マリーアントワネットとオスカルのことだったのね
もう一度言うけど
池田理代子先生すごいわー
軍隊とは・・・
映画は、7月13、14日の戦闘描写にかなりの尺をとっている。
国王方の軍隊、衛兵隊と民衆、双方とも容赦なく相手を殺戮する。血しぶきをあげて倒れる兵士、民衆。国王方の兵士もまた、その髪の毛1本1本まで自由な存在であるはずだし、衛兵隊の兵士同様に、軍備品を売却して家族の生活費を賄う社会の最底辺層の出身かもしれない。だが、戦場では倒すべき「敵」としてしか存在できない。スクリーンを見ながら、軍隊とはつきつめていけば人殺しのプロ集団であることをあらためて認識させられた。実戦は初めてとは思えないオスカルの見事な指揮官ぶりに、オスカルは士官学校で、味方の損害は最小限に抑えながら相手方を殲滅するという現場の指揮官あるいは参謀本部の司令官として求められる能力を教え込まれたのだろうな、と考えたりした。だから、オスカルが撃たれて断末魔の苦しみのなかで、自らの信念を貫いて生きた人生を振り返る場面を見ても、「あれだけ殺したのだから仕方ないのかな」というある意味突き放したような感想しかもてなかった。そこから振り返ると、「生涯を剣に砲弾に捧げて軍神マルスの子として生きる」というオスカルの決断も何かざわざわするというか、後味の悪さが残ったのである。
全315件中、1~20件目を表示