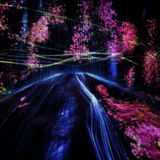コーダ あいのうたのレビュー・感想・評価
全563件中、141~160件目を表示
本音でぶつかる事
素晴らしい出会い❗
昨日、ライブラリーに素晴らしい作品が加わった。 「coda」
スクリーンで観てから8ヶ月・・自室で再び魅せられました。
台詞の「粋」な処、音楽の楽しさ、素敵なカット(構図)、キャスティング❗️多種の問題も織り込みながら展開して行く話が・・素晴らしい、
「粋」な、映画とはこれだろう。
人は何て素敵な創造力を、持っているのだろう この作品に出会えたことに感謝しかない❗
この様な作品に出会ってしまうから「映画」は、辞められない。
ヴィラロボス先生が素敵過ぎです‼️
聾唖の方々は全て手話トークですが、お父さんだけが「一言」声にします・・・お聴き逃し無く。
国により違う手話ですが、もう一つのコミュニケーション言語として身近に在りたいモノです。
素晴らしい感動作!
いやぁ~、これは素晴らしい映画、感動した!
これまで無かったようなオリジナリティあふれるドラマも心に残る。
この映画については、キネ旬などでも概要は読んでいたし、アカデミー賞でも話題になっていたので、「ろう者家族に囲まれた1人のろう者でない娘のドラマ」ということだけが事前情報だったが、実際に作品を観てみると「想像の遥か上をいく展開」に驚かされて感動も…。
やはり、この映画がここまでの作品となったのは、ルビーを演じた主演女優エミリア・ジョーンズの存在が欠かせない。
ルビーが、「家族のための仕事」と「自分の将来のための大学受験」の狭間で苦悩する姿が見事!
手話付き歌唱シーンは、感動の涙あふれる名場面。
この映画は必見映画であることは間違いない。
聞くチカラ
あたたかい
家族って。親ガチャって。
家族
娘から家族が自立する話。
テーマ自体はありふれた旅立ちの話。だが良くできてる。
家族の中で唯一耳の聴こえる子が一番若年で、その娘が家族と世間の唯一の窓口となっている。
娘以外の家族は世間とは閉鎖された世界で生きており、耳が聴こえないがゆえに世間の目も気にならない。が、その世間の目を唯一耳の聴こえる思春期の娘が一身に受ける。
それ故、娘が一番しっかりしており、傷付きながらも家族を世間から守って生きている。
娘が合唱部に入ったと聞いて、反抗期と思う自己中心的な母親。無神経な父親。自立しようともがく兄。
これは娘の自立と言うよりも、家族が娘からの自立の話。
リメイクらしいけど、脚本が出来た段階で成功は娘役のキャスティングいかんに掛かっていたと思う。
その中エミリアジョーンズですわ。
めちゃめちゃ良かった。そりゃ感動しますよ。
とても良い作品でした。
他のキャスティングも良かった。兄役も良かったし、V先生も無神経な父親も良かった。
久しぶりに心洗われました。
青春の光と影…そして,愛
本年度のアカデミー作品賞を受賞した作品。近場の映画館では公開していなかったので、遅れて鑑賞。聴覚に障害のある家族の中で、唯一人、耳が聞こえる少女の心の葛藤と成長を描いたヒューマン・ドラマ。
最近のアカデミー賞は、人種やジェンダー問題等、個性の尊重を取りあげた作品が受賞する傾向にある。今回は、耳の聞こえない障がいのある人達が生きていく息苦しさを、背景に描いている。しかし、主人公の家族は、聾唖であることを障がいと感じながらも、決して卑屈にならずに逞しく生き抜く、人としての強さと明るさを感じられるように描いている。そして、それを支えているのが、ゆるぎない家族愛なのだと思う。
漁師である聾唖の家族の為に、幼い時から通訳となって漁師の手伝いをしてきたルビー。学校では、変わり者の家族ということで、仲間外れにされながらも、新学期に合唱部に所属する。その担当教師が、ルビーの歌の才能を見出し、音楽大学進学を勧める。一方で、ルビーの通訳を頼りにしている家族は、進学に反対し、家族を守ることを願う。好きな歌を続けるのか、家族の為に歌を諦めるのか、その葛藤の中に、淡い恋心も織り込みながら、ルビーの青春物語を描いていく。
それほど、サプライズのあるストーリーでもないし、よくあるヒューマン・ドラマだが、本作の素晴らしさを増幅したのは、やはり手話による演出構成であると思う。主人公家族となる、父役のトロイ・コッツァー、母役のマーリー・マトリン、そして兄役のダニエル・デュラントは、実際に、聴覚に障害を持ちながら、聾唖俳優として活躍している。だからこそ、本作の演技が、決して台本を読むだけの演技ではなく、彼らの心の内から訴えるような、喜怒哀楽が現れているのだと思う。
手話を知らない自分でも、その手話や表情からその想いが伝わり、音声としての言葉を発しなくても、ヒシヒシと感じるものがあった。特に、最後の『青春の光と影』を歌うルビーが、家族の前で、手話をつけて歌い出すところは、それまでのストーリーと相まって、心に熱いモノが溢れてきた。
海外では、こうした障がいのある人々が、エンターテイメントの世界でも、堂々と活躍できる場もあり、それを認める風土ができている。日本も、『24時間テレビ』の時にだけ盛り上がるのではなく、常にこうした人達が、明るく生きられ、互いを認めあえる社会を、築いていかなければいけないと感じた。
マイルズのギターに合わせ、ルビーの部屋でデュエットの声合わせするするシーンが最高
違っているけど、みんな同じ
今、注目のヤングケアラーと、そのろうあ家族の自立物語。
どうしても越えられない壁がある。
本作の場合、「聞こえる」主人公と「聞こえない」その家族という壁だ。
だからこそ理解できない、ゆえに信じきれない可能性をどう理解しあい、
相手を、自身を信じて、しがみついていた手を離し、互いに自立してゆくのか。
過程が見どころだった。
でなければやがては共倒れになる未来が待っているのだから
このあぶなっかしい駆け引きには、やきもきとハラハラのし通し。
(ああ、家族の犠牲になっちゃダメだとか。気を遣わないからって子供ばかりに頼らず、外の人にも頼ってとか。どちらも気持ちは分かるだけに!)
社会からの疎外は感じているものの、そこは日本とちがう海外気質?
鬱めくどころか、外へ外へと向かう主人公家族の自己主張力と、
駆使したサバイバル精神がとにかく痛快だ。
だからこそ導かれた大団円のような気もしたなら
「自立とは多くの人に少しづつ頼ること」である
という全ての人へ向けられた言葉がぴったりのラストには、
もしかするとこの作品は「ろうあ」という要素がなくても
成立する物語では? と閃いた。
いやつまり、ありふれたただの家族の物語をあえて「ろうあ」で再現したところに、
「私たちはちょっと違っているけど、みんな同じなんだ」
なんて多様性への共感、容認を
じつに軽やかに示す作品だったのでは、と感じている。
ろう者の世界を知れる作品
実際のろう者の役者を起用している作品で、普段では知ることのできないろう者の世界を知れるのは映画体験の楽しみだと思う。さらにここで出てくるろう者は性に奔放で強者として生きていて、暗く描かれているのが良いと思った。自分の体験として、ろう者と仕事をした時に初めて知ったのだが、映像に付けられる手話はなぜテロップにしないんだろうという質問にろう者はそもそも文字が読めない人も多い事を初めて知った。「あ」という文字を「あ」と発音する概念がないから形として覚えるしかなく、先天的に聞こえない人は特殊な教育を受けないと文字を読むことができない。聞いたらすぐに腑に落ちる事なので、自分の質問の浅はかさが恥ずかしくなった。手話に関しても世界共通ではないので、情報を得る事のハードルの高さは凄まじいものがあると思う。 映画の話に戻ると、基本は家族愛の話として気持ちよく見れるのだが、最後まで音楽とろう者の距離は近づかないまま、娘を評価する先生を通したところで納得する部分に関しては音楽をテーマにするならろう者と音楽についてもう少し深掘りをして欲しいところもあった。日本では落合陽一が耳で聴かない音楽会という新しい試みをしているし、音楽というテーマじゃなくてももう少し他者の世界観を深く知るという事があるともっとよかったのかなという印象もあったが、父役のトロイ・コッツァーはアカデミー助演男優賞を受賞していて、手話を交えた役者の演技は素晴らしかったし、知らない世界を知れる体験だった。
「コーダ」と「あいのうた」を分けて観るのがポイント
他の家族が皆聴覚障害で、1人だけ耳が聞こえる主人公の気持ちをはかることはできない。
ただひとつ言えること。この状況を前向きに進ませるには、家族がひとつにならざるをえない。
「心温まる」とか安易に美辞麗句を並び立ててはいけない。
家族が寄り添うことで、彼らは必死に前向きに生きているのだから。
外野からとやかく言う必要はまったくない。
主人公の彼女も言っている。
「家族ぬきで行動したことがないんです」と
だから、「コーダ」の部分は各々観る者が、自分の心と向き合えばいい話だと思う。
「あいのうた」の部分で一番印象的なのは、主人公の音楽教師。バークレー音楽院出のメキシコ系。
とにかく教え方が個性的で、たとえが絶妙。
極めつきは、デビット・ボーイがボブ・ディランを「砂と糊みたいな声」と評した逸話。
それを得意げに言う教師と、そのたとえがあまりにも的を得ているので、思わず笑みがこぼれる。
大切なことだから面白く
リメイク元の「エール!」も良かったけど、こっちも良かった。
やっぱりいろんな感情を発露させる歌のくだりは素晴らしいし、
ろう者の家族がルビーの才能に(ようやく)気づくってくだりは鳥肌モノ。
今も思い出すだけで涙が出そうになるくらい感動した。
リメイクにあたっての改変もすごく効果的だったと思うし、
こちらの方がエンタメ性の部分で上かもしれない。
ただどちらの作品でも訴えていたのは、
親として、自分が理解できない子どもの表現を評価できるかってとこだと思う。
人は自分が見ているものだけが全てだと思いがち。
その枠から飛び出して、本当の意味での理解者に。
大切なことだから面白く伝えるっていう、
個人的に映画の本質だと思う部分で非常に良くできた作品だったと思う。
Power Of Music
全563件中、141~160件目を表示