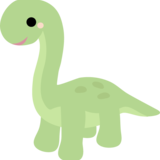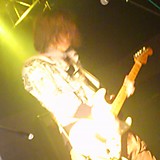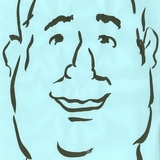コーダ あいのうたのレビュー・感想・評価
全563件中、41~60件目を表示
単なる苦境を克服して誕生する歌手のサクセスストーリーではない
🔳押し付けないハンデある人たちの心情
聴覚障害というハンデを持ちながら強く生きる家族に対し世間は必ずしも優しくない。それでも明るく、時には社会の不条理にそれぞれの形で立ち向かう家族の姿が自然と見ている人の心を引き込んでいく。
🔳第一クライマックスの静寂がどんなメッセージをも超越
衝撃的な表現力だった。どんな観客も主人公の美しい歌声を聴きたくなるだろう。ましてやその歌声それが家族なら。そんな家族の気持ちを表現するための表現は主人公の最高の歌を期待していたものに実に容赦無い。ここで見るものの誰もが主人公に家族側が背負ってきたハンデの凄まじさを知ることになる。単に歌手のサクセスストーリーを描きたかったのではないという監督の信念を感じさせられた。
🔳トレードオフされているヤングケアラー問題
聴覚障害の家族の元に生まれた主人公はヤングケアラーにあてはまる。この主人公は自分の歌に希望を見出すことが出来た。現実にはそうした境遇にない人が少なくないであろう。声もあげられず、与えられた境遇に甘んじながら生きている子供たちがいることに思いを馳せるとこの作品を手放しで賞賛しづらいものがある。
🔳聴覚障害者にとって手話の歌とは
さらに聴覚障害がある人に手話で歌を共有する価値を過大に評価していないだろうか。音の振動のリズムと手話が調和して伝わる感覚やその他にも視覚で音楽を表現する試みはあるだろう。それで聴覚障害者も一緒に感動を共有しているかどうかは聴覚保持者は確信を持てないはずだ。それでもそうした試みの価値は評価されて良いが、真に感動を共有できる手段を追求しないと単なる思い込みで終わってしまう。
手話は、世界に溢れる言語のひとつ
手話は、世界に溢れる言語のひとつ。
優しくて美しい、
コミュニケーションのひとつなのだと気づくはず。
素晴らしかった。
ただ、素晴らしかった。
後半ずっと泣いてました。
「コーダ」とは、
「Children of Deaf Adults」の略で
耳が聴こえない親を持つ聴こえる子どものことを言うそう。
両親と兄、家族の中で1人だけ耳が聞こえる歌が好きな女の子。
これは、彼女の困難と葛藤、そして生き様を通して描かれる、家族の愛と成長の物語。
ろう者視点とコーダ視点、健聴者視点それぞれの世界がリアルに描かれていて、『マイノリティとどう向き合うべきか』を突きつけられる。
セリフの一つ一つ、手話の一つ一つが突き刺さった。
歌が好き。
なぜわかってくれようとしないのか。
逃げたい。苦しい。理解したい。助けたい。
愛してる。
それぞれが、それぞれの環境や境遇の中で自分の人生を生きている。
それを知り、考えること。
大切だと思わせてくれる素敵な作品でした。
是非とも映画館で
それぞれの"音"を楽しんでほしい。
☆☆☆☆ 配給会社、タイトル狙いすぎ(u_u) まあ、それは置いと...
☆☆☆☆
配給会社、タイトル狙いすぎ(u_u)
まあ、それは置いといて…
とても良かったなあ〜(´ω`)
ここまでウェルメイドに徹して作られていると、好感が持てる。
但し、少しばかり毒っ気のある作品が好みな人にはオススメしませんが、、、
実は鑑賞後直ぐにネット繋がりの映画仲間に「超オススメ!」と伝えたところ。
「リメイクですよね!」との返事。
「?」あらら本当だ!ここ数年は、鑑賞前には予告編以上の情報を観ずに鑑賞する事が多いので。
(原作本がある日本映画はまた別として)
この作品がフランス映画『エール』のリメイクだった事を知らずに鑑賞していた。
慌てて、当時の自分のレビューを見ると…
あらららら、、、日付と劇場名だけ💧
確かに鑑賞中には既視感強めに感じていたのは事実。でも直ぐに『エール』の事を思い出せなかったのだから、それ程には自分には刺さらなかったのだろう(。-_-。)
前半からかなりの下ネタを繰り出しては観客を笑わせて行く。
でもその下ネタが、決して観ている観客に眉をひそめさせる下ネタではなく。寧ろ微笑ましい下ネタなので、観客側に嫌な思いを抱かせない。
真面目な場面が続いた後には、そんなクスクスとさせてくれる場面がある為に、どんどんと引き込まれて行った。
とかく聾唖者を扱うだけに、深刻な内容になりやすいところでの笑いの場面でもあり。私の様な健常者でも、聾唖者の人の気持ちに寄り添えているのでは?との思いにさせて貰える。
(但し、その思いが果たして聾唖者の方達から観て、どの様に映ったのか?は完全には分からない。当たり前の事なのだけれども…)
と、ここまで書いたところでやっと元ネタでもある『エール』のストーリー展開を思い出して来た。
ほぼ元ネタ通りのストーリー展開だったのではないだろうか。(ちょっと記憶が怪しいですけど)
おそらくは、最後のオーディション場面で涙腺崩壊する人が多いのではないでしょうか?
実際問題、私もこの場面で遂に涙腺崩壊を起こしたのです。
でも、そこに至る前の場面にこそ私の心に刺さった場面がありました。
それこそが、ルビーの歌声を(心で)初めて〝 聴いて 〟周りの人達の喜びの表情から感じた《家族》の想いでした。
特別に凄い演出であったり、映像に凝っていたりするわけではないのですが。的確に観ている観客の心の隙間に入り込んで来る爽やかな風の匂いを感じたのでした。
あの黒澤明が生前に言った言葉をちょっとだけ思い出した。
「作品にはそれを作った人の性格がでるんだよ!」
(正確ではないけれど、それに近い意味で)
この作品を監督したのは女性で、まだ作品数はこれで2本目らしいですね。
その演出であり作風から、心優しい人なのでは?との思いをさせてくれて、早くも次回作品が楽しみになっています。
ところで、多分元ネタの『エール!』には無かったと思えるのが、若い2人が池の上にある大きな岩から飛び込む場面。
スティーブ・テシックの自伝的脚本でピーター・イェーツが監督した青春映画の傑作『ヤング・ゼネレーション』
アメリカ映画界では名作との認識が浸透しているだけに。岩や崖から池や湖に飛び込む映画が有ると『ヤング・ゼネレーション』?と、ついつい思ってしまう。80年代映画大好きおっさんであります(^^;;
「◯◯になるな!」
兄貴かっこいいぞ!
2022年 1月21日 TOHOシネマズ日比谷/スクリーン9
ここで見る星は海で眺める星ほどキラめいてないな
前半 笑える 、後半 泣ける
泣かされると分かっていても泣く
いろんな愛を綺麗な歌声にのせて
素直にやさしい気持ち・・・
ろう者の家族をとりあげた難しいテーマ。恋愛や進学、家業の漁師の存続など色々な出来事が主人公の心を揺れ動かすんだけど、全編を通して美しい音楽と歌声が効果的に連鎖されていてぶれない。最後まで時間を忘れて観続けられる作品でした。
まだまだ数少ない女性の映画監督。正しい観方ではないかもしれないけれどその感性の違いを期待を込めて意識して観るようにしています。この作品ではボーイフレンドとのからみが乙女チックでこっぱずかしかったり、下ネタ多過ぎちゃう?とか最後は絵にかいたようなハッピーエンドが気にならないでもないけれど、観終わってみれば何故か素直にとっても優しい気持ちになっていました。女性監督さんにさらなる期待です。
2014年のフランス映画である『エール!』の英語版リメイク。聴覚...
2014年のフランス映画である『エール!』の英語版リメイク。聴覚障害を持つ家庭で育つ、聴覚が保持された子供の成長を描くヒューマンドラマ。
『 CODA(Cildren of Deaf Adults) 』とは、聴覚障害のある親をもつが、自身は聴覚に障害のない人を指す言葉。CODAは幼少期から親の通訳や代理交渉等を行うことが多く、年齢にそぐわぬ過度の負担がかかり、成長への影響が心配されている。また『ヤングケアラー(young carer)』とは、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子供を指す。
本作の主人公はCODAであり、ヤングケアラーでもある。
タイトルがCODAであることから、この問題を映画の主題にしようとしているのだろうが、主人公に特殊才能(歌が上手い)を付与してしまったことで、CODAやヤングケアラーの闇部分が飛んでしまい、過酷環境から脱出する少女の単なる感動映画にすり替わってしまっているように感じてしまった。
なお、父親役のコッツァーは現実世界においても聴覚障害者である。フランス版「エール!」で手話がデタラメだと批評されていたので、本作では修正したのであろう。
良い映画。安心してみられるラスト。
面白さがよくわからなかった
聾唖の家族の中で生きる一人の健常者の女の子が歌の才能を見出されて……という話
とはいえ、家族たちが自分たちの理解できない分野に挑戦しようとする主人公と衝突するような展開を期待していると肩透かしを喰らいます あくまで家族や周囲の反応は良識的で、ひどいいじめやバトル展開になったりはしなくてよくいえばリアル、悪くいえば盛り上がりにかけるなあという感じです
映像や演技、主演女優の歌が美しく素晴らしかったのですが、結局何も残らなかった感じがして残念です
今までで最高のキスシーンだった
デビッド・ボウイ、ジョニ・ミッチェル、マーヴィン・ゲイ、アイズレー、クラッシュなどなどセンス良い曲が歌詞に合わせた場面で使われていて、それが作品のポイントになっている。
そして細かいところでは、ボブ・ディランの声を引き合いに出したり、高校生にレッツ・ゲット・イット・オンを合唱させたり、キング・クリムゾンのTシャツやKOOKSというバンドのポスターにまで意味があって、ディテールに凝っている。
ミニマムに絞った挿入曲や、こういう音楽ネタを駆使するあたりは、クレジットで大々的に音楽プロデューサーを掲載しているところから想像できたが、さすがだ。
音楽と聴覚障害という相反するテーマをうまく融合させている。
シンプルな演出で、家族全員の演技も良い。
途中で入る90秒ぐらいのサイレントの間では、自分も含めて皆さん明らかに泣き声が漏れないよう我慢するのに必死で、映画館で観ている意味というか価値というか、分かち合える時間と空間だったと思う。
私はオッサンで、かなり泣いたが、隣のオッサンもオバサンも、後ろのオネーさんたちも、自分以上に泣いてた。
20220128 豊洲ユナイテッドシネマ
涙なしには見られない、美しい愛に満ちあふれた映画
映画館で友人と鑑賞しました。
音のある世界からない世界へと移った瞬間、今までは客観的に映画を観ているだけだったのがすべて自分ごとになり、映画の中に入り込んだような気持ちになりました。
耳が聞こえない家族の中で唯一聞こえる主人公の想いが痛いほど伝わって、涙が溢れてきました。同時に、耳が聞こえない家族の想いも伝わります。お互い愛し合っているのにすれ違い、理解しようとしているけれども理解できない、などもどかしい気持ちでいっぱいでした。
最後の音楽大学の入学試験で家族の前で披露した歌は本当に忘れられません。
歌とは想いをのせるもので、音として聞こえなくても家族に想いが通ったと思うと、今でも思い出すだけで感動して涙が溢れ出てしまいます。
ぜひこれは多くの人に見てもらいたい映画です。傑作です。
エール!の方がいい。
全563件中、41~60件目を表示